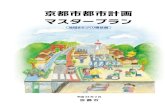AREAS News · 今後も、地域に残されている豊かな里山の環境や地域資...
Transcript of AREAS News · 今後も、地域に残されている豊かな里山の環境や地域資...
AREAS News2015年1月30日号
No.14
2015年が始まりました。本年もよろしくお願いいたします。
さて、旧年も押し迫った12月28日、大町市では、故郷大町市に関心を持つ若者100人が集い、市の将来像について話し合う「信濃大町youthサミット」が開かれました。マチサラ(※まちごと全部の意味)実行委員会の主催により、大町市の
若手職員も積極的にサポートし、みんなの意見を熱心に吸い上げていました。大町市で活躍中の5人のトークに加えて、16のテーマで行われたワールドカフェでは、「大町市を全力で楽しむ!(by地元の若者)」 「リアルに空き家に移り住むには?(by移住者)」 「自らの思いを実現するために、仕事をどうつくれば?(by Uターン希望者)」など、熱く盛り上がりました。
地域戦略センターと大町市の定住促進に関する共同研究も2年目に突入します。今年も信大×若者×大町市で頑張りたいと思います。 (助手李素婷)
Contents■主催イベント「人口変化から信州の未来を考える」■共催・関連イベントエチオピア政府関係者視察、鬼無里WS、伊那谷アグリ、林業を考える会、お金セミナー
■地域志向教育研究支援事業■他大学の動き■その他学内・地域の動き ほか
■主催イベント
地域戦略センター主催による「地域課題学習セミナー」として、12月18日(木)、長野市の工学部SASTecを会場に、野村證券株式会社 金融公共公益法人部 主任エコノミスト 和田理都子先生による講演会を開催しました。今回の講演では、信州の全市町村の人口分析に加え、産業やコミュニティ力などから導き出した「都市力」をご報告いただき、信州の未来について考えました。講演のポイントは、私達の社会が人口増加を前提としてきたことをあらためて実感する点にありました。和田先生は講演の中で、人口増加曲線をボールの放物線に例えて表現されました。今まではボールを上に投げて上昇していた時期でしたが、現在はその上昇が止まり、降下に向かうタイミングであるということです。従って、私達は重力加速度がついて手遅れになってしまう前に、加速を和らげたり、軟着陸するための空気抵抗や浮力をどう作っていくかを考えることが重要だということでした。すなわち、「都市力」分析から読み取れるような地域の独自性や独自の課題を認識して地域経営戦略を構築することが必要であるということです。また、今回の講演では人口変化と都市力が数量的に定義されたことも重要な点でした。数値指標の定義は分析視点によって決定されるので一義的な妥当性や信頼性は議論できませんが、数量化は、「共通言語」「可視化」「比較」を可能にするため、多くの人が議論に参加できるというメ
リットがあります。もちろん、数値を読み解くためにはデータの取得条件やある程度の統計基礎知識が必要になることもあります。これを「リサーチ・リテラシー」と呼びますが、
大学の得意とする分野の一つです。地域の戦略を考える上で、我々はこうした「知」を伝えていくことも重要であると感じました。 (准教授 林靖人)
エチオピアの水灌漑省やエネルギー省などの政府関係者ら12名が、低炭素で低排出なクリーンエネルギーの自国への技術移転を目的とした研修を12月16日(火)〜18日(木)の3日間、北信・東信地域で行いました。これは、国連工業開発機関(UNIDO)と海外人材育成協会(HIDA)が主催し、長野県が後援した事業で、当センターはこれに共催し全体のコーディネートを行いました。一日目は、長野県庁で阿部知事への表敬訪問が実現し、「長野県のエネルギー政策と事例紹介」と題した県環境エネルギー課による講演も聴講しました。二日目は、本学工学部にて、飯尾准教授による「小水力発電ラボ視察」と、当センター副センター長でもある天野教授による「ソルガムが拓く地域自立型循環システム」と題した講演を聴講。その後、木島平村馬曲温泉へ移動し、築150年の古民家にて里山の郷土料理で昼食を取った後、村をあげて取り組む「小水力発電事業」について学びを深めました。三日目は、佐久市の「メガソーラー発電所」と「太陽光利用施設」を視察しました。非電化地域を郊外に多く有するエチオピアでは、特に小規模な再生エネルギーの技術導入と現地でのコミュニティの形成過程が参考になったようで、コスト面などに関するステークホルダーとの調整ほか多岐に渡る質問が飛び交っていました。国や文化は違えど、現在直面している地域課題はさほど変わらないということに気づかされました。
(研究員 新雄太)
「人口変化から信州の未来を考える」
地域戦略センター(AREAS)ニュース 2015年1月30日号 No.14 発行・編集地域戦略センター email: [email protected] HP: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/
野村證券 和田理都子氏
■共催・関連イベント低炭素・低排出クリーンエネルギー技術移転[LCET]プログラム-エチオピア政府関係者啓発研修-
エチオピア政府視察団、阿部知事を囲んで
かんがい
12月2日(火)、伊那市役所多目的ホールにて、第8回シンポジウム「中山間地域の景観と観光」(主催:伊那谷アグリイノベーション推進機構、日墺協会長野)が開催され、元オーストリア農林環境省のイエルク・ホイマーダー氏が、オーストリア・チロル州の山岳景観保全を核とした農村開発について講演されました。ホイマーダー氏は、オーストリアの山岳地域における農林畜産業の営みが長い年月をかけて創り出してきた景観を保全し維持することが、歴史的にみても文化的にみても重要であることを主張し、観光業による地域経済の振興と景観保全を並行していくことが有効であることを述べられました。続いて、農林水産省関東農政局の小林厚司氏が、日本における都市農村交流が、若者の農山漁村への回帰志向とともに高まっていることを紹介し、観光業の施策の多様な展開について講演されました。 (研究員 福島万紀)
地域戦略センター(AREAS)ニュース No.14
地域戦略センター(AREAS)ニュース 2015年1月30日号 No.14 発行・編集地域戦略センター email: [email protected] HP: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/
長野市鬼無里「里地里山の活性化と共生した低炭素な地域づくりに関するワークショップ」
伊那谷の林業を考える研究会-シカを活用する取り組み-
「中山間地域の景観と観光」伊那谷アグリイノベーション推進機構
第8回シンポジウム
「地域活動のためのお金セミナー」
上智大学中島恵理氏の講演
イエルク・ホイマーダー氏による講演
様々なシカの活用
NPO法人まめってぇ鬼無里が主体となって展開している中山間地域における新しい低炭素・自然共生型のライフスタイルのあり方に関するシナリオを大学や研究機関他と協働してデザインする活動。その一つとして、昨年秋頃から本学農学部の斎藤助教の指導のもと、農学部学生とともに鬼無里に入り森林量等の調査を行ってきました。これら
今年度の成果発表を12月23日(祝・火)に前夜座談会として行い、翌24日(水)には本学工学部キャンパスSASTecにおいてワークショップを行いました。今後も、地域に残されている豊かな里山の環境や地域資源を古民家再生やバイオマスエネルギー利用の観点から捉え直していく活動が続きます。 (研究員 新雄太)
12月16日(火)、信州大学農学部にて、「伊那谷の林業を考える研究会」が開催され、伊那谷の林業関係者や行政関係者など、約100名が参加しました。研究会では、諏訪地域の「すわしかプロジェクト」、泰阜村の「けもかわproject」などの地域ぐるみの活動や、シカ肉や皮のみならず、角、骨、爪、油など様々なもので創作活動を行う伊那市高遠在住のアーティストの活動について紹介されました。また、「長野県のジビエ生産施設と流通」に関する卒業論文に
取り組む農学部森林科学科4年生の河野卓朗さんが研究内容を紹介し、活発な質疑応答が行われました。
(研究員 福島万紀)
1月11日(日)、塩尻えんぱーくにて、「地域活動のためのお金セミナー」の第1回が行われました。この講座は、信州大学が進める社会人向け地域リーダー養成講座「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」のオプション講座として、信州ファンドレイジングチームを主催とし、NPO法人 長野サマライズセンターの小笠原恵美子さん、同じく わおんの山田勇さんを講師として、3回に渡って実施していただくものです。25名の受講生のうち15名が地域プロゼミ受講生であり、オプションとしてうまく講座連携できたようです。第1回は「ファンドレイジングってなに?」と題して、お金を集める方法のあれこれを学びました。後半行われたワークショップでは、受講生から具体的で斬新な資金集めのアイデアが提示され、普段から課題意識をもって取り組んでいることが垣間見られました。第2回「挑戦してみてわかったクラウドファンディング」は
1/25(日)、第3回「助成金申請書の書き方」は2/1(日)に、同じくえんぱーくにて開催されます。 (CDN 田村守康)
にち おう
やす おか
受講生による発表
■他大学の動き
地域戦略センター(AREAS)ニュース No.14
地域戦略センター(AREAS)ニュース 2015年1月30日号 No.14 発行・編集地域戦略センター email: [email protected] HP: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/
12月9日(火)・10日(水)の両日、本学教育学部キャンパスにおいて、シンガポール国立教育研究所のチー・キット・ルーイ教授をお招きし、「未来型教育の体験授業ワークショップ」が開催されました。地域からも大学からも学びの意欲の高い参加者が集まり、ともに学ぶ「開かれた大学」となりました。このワークショップは、教育学部助教の林寛平先生が企画されたもので、ルーイ教授による基調講演「ICTが授業と学習をどう変えるのか」、反転授業とジグソー法の体験授業、「10年後の学校」を考えるワークショップが組み合わされた密度の濃い2日間でした。当日の模様は、信州大学比較教育学研究室HPにも掲載されています。ワークショップで作成した動画も閲覧できますので、ぜひご覧ください。(研究員 白神晃子)
「未来型教育の体験授業ワークショップ」
東北公益文科大学主催「地域課題解決全国フォーラム in 庄内」
教材を体験してみる
グループで「10年後の学校」を考える
本学のCOC事業の参考となる手法を知得するとともに、他大学の事業推進者とのネットワークを形成することを目的に、12月20日(土)~21(日)、山形県酒田市・鶴岡市で開催された東北
公益文科大学主催の「地域課題解決全国フォーラムin庄内」に参加してきました。全29件中、公益大の学生発表11件を含む地域志向人材育成に関する事例、地域課題解決につながる実践活動事例等の「実践・研究報告会」や、地域住民との意見交換の場としての「地(知)の拠点円卓会議」、「食と健康の庄内~地域連携とソーシャルデザイン~」をテーマに、「食」を通じて健康や医療、地産地消など、さまざまな視点で地域おこし、地域貢献に取り組む熱量ある地域リーダーによる「パネルディスカッション」など、興味深いプログラムが続きました。参加者は地域住民を中心に両日とも約300人。特に円卓会議では、公益大が取り組む6つの課題解決アクションプログラムについて、担当教員がショートプレゼンを行い、そのテーマに賛同する地域住民(一般市民やNPO職員など)がその場で興味を持ったテーマごとに別れて意見交換し、アイデアを出し合い、次のミーティングの設定まで行うというチーム形成を行いました。意識の高い市民が自発的にこの会議に参集し、積極的に教員とともに課題を議論・意見交換する光景は圧巻。チーム形成、協働の緒の付け方として、そのやり方が大変面白く参考になりました。東北公益文科大学は、2001年に設立された公益学部1学部の学生700人弱、教員40名弱の小規模な私立大学です。COC事業を牽引する鎌田剛庄内オフィス長/准教授によると「軌道に乗せられそうな感触」との発言で、30数名という教員が何らかの形でCOC事業の推進に関わっているとのことでした。公設民営、地域に望まれて設立されたという経緯もあり、庄内地域(酒田市・鶴岡市中心に人口30万人の地域)の地域住民や自治体と大学教職員をあげて、総力で地域課題解決、ならびにCOC事業に取り組もうとしていることが感じ取れる2日間でした。
(CDN 田村守康)
円卓会議でのショートプレゼン
■地域志向教育研究支援事業
「漆喰塗り親子ワークショップ」
子どもたちの膝は真っ白
猪瀬先生の解説と学生のデモンストレーション
11月30日(日)、本学教育学部キャンパスに、須坂市の小学生と親が集まり、信州の地域資源である蔵の仕上げ材に用いられる漆喰を使ったワークショップが開催されました。このワークショップは、彫刻制作を専門にする猪瀬先生と、建築を専門にする山岸先生のコラボレーションで実現しました。美術・家庭科の両コースの学生たちも積極的に関わり、学生の学びにもつながったイベントでした。参加者は1人1枚のパ
ネルに漆喰を塗って左官体験をした後、凹凸を利用して自由に表現を楽しみました。完成した作品は、蔵をモチーフにした壁面に組み立てられ、須坂アートパークイルミネーションフォレスト2014の会場でライトアップ展示されました。
親も子も、取材に伺った研究員も夢中になって漆喰を使った作品作りを堪能しました。 (研究員 白神晃子)
し っ く い
次号予告| 地域戦略プロフェッショナル・ゼミの報告| 地域志向教育研究支援事業の紹介| 主催・ 共催・参加イベントの紹介
■近日開催イベントのご案内
地域戦略センター(AREAS)ニュース No.14
地域戦略センター(AREAS)ニュース 2015年1月30日号 No.14 発行・編集地域戦略センター email: [email protected] HP: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/
地域の防災・減災機能の強化を考える-信州大学地域連携フォーラム-
■その他学内・地域の動き
高等教育コンソーシアム信州は、12月9日(火)、信州大学松本キャンパスをメイン会場として、2014年度インターンシップ成果報告会を開催し、諏訪東京理科大学、清泉女学院大学、長野大学、松本大学、信州大学の学生が、各々のインターンシップの経験を報告しました。報告内容を聞いていると、実習内容や期間、受入担当者の関わり等、体験の質に大きなばらつきがあり、中には会社説明会の参加報告のような内容も含まれていました。インターンシップの多様性を感じましたが、大学の教育機会として紹介するのであれば、中身を検証する必要がありそうです。
(研究員 松浦俊介)
学生による発表
「松本市地域づくり市民活動研究集会」12月13日(土)、浅間温泉文化センターにて開催された松本市地域づくり市民活動研究集会に参加してきました。松本市は平成26年度、35箇所の地域づくりセンターを設置し、市民の自発的な地域
づくり活動を基盤にした松本市づくり・市政運営を目指しています。うまくいっている事例から伺える活動の背景には、具体的で個人的な困りごとが動機と して存在しており、
結果として地域=顔の見える人のつながりが形成されているように思いました。できることを楽しみながら、仲間を増やしつつ続けていく。それを10年間続けた先に、暮らして気持ちのよい地域ができていくのだと思います。頭では分かっていたこととはいえ、自身の活動のスタンスにあらためてカンフル剤となりました。 (CDN 田村守康)
■公募・助成金情報
パネルディスカッション
会場いっぱいのパネル展示
日時:2015年 2月22日(日)9:45~17:05(受付9:00~)
場所:ホテルメルパルク長野1Fイベントホール
【入場無料】
<プログラム第Ⅰ部>地域防災への科学技術の役割について考えよう
<プログラム第Ⅱ部>危機管理として何ができるかを考えよう
信州大学の研究成果を一挙公開!
日時:2015年 3月3日(火)11:00-17:00
3月4日(水)10:30-16:00
場所:松本市浅間温泉文化センター
【入場無料】
<出展ゾーン>●材料・ナノテク・新素材●省・新エネルギー●災害対策●情報通信・宇宙航空●環境・食品・農業●医療・健康・福祉
●ライフサイエンス●文理融合・人文社会学●地域連携●土木建築●部局等紹介
第2回信州大学見本市~知の森総合展2015~
◆公益財団法人三島海雲記念財団研究助成[公募締切] 2015年2月28日[研究分野] 人文社会科学系、農学生物系[応募資格] 個人研究者、共同研究者/機関[助成額・期間等] 1年間、個人1件100万円、
共同研究200~500万円[HP] http://www.mishima-kaiun.or.jp
◆一般財団法人全日本冠婚葬祭互助協会社会貢献基金助成[公募締切] 2015年2月28日[研究分野] 人文社会学系、その他[応募資格] 団体等[助成額・期間等] 1件100万円~200万[HP] http://zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html
2015年1月現在の主な公募・助成金情報をご紹介します。詳しくは各担当機関の最新情報をご確認ください。
「2014年度インターンシップ成果報告会」
いつ起きるかわからない自然災害。信州大学と一緒に地域の防災を考えよう!