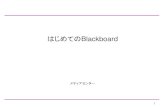Title エマソンの『英国人の特性』 : 愛国者エマソソの一面 英 …...エマソンの『英国人の特性』エマソソの『英国人の特性』-愛国者エマソソの一面-小畠啓邦
はじめに - CAPE · り体操指導士と理学療法士の国家資格を取得。身体...
Transcript of はじめに - CAPE · り体操指導士と理学療法士の国家資格を取得。身体...


1 2
1986年デンマークへ留学。1989年以降、ドイツに渡り体操指導士と理学療法士の国家資格を取得。身体障害児のための養護学校での勤務を経て、2001年に帰国。現在では全国各地で講習を行いポジショニングの普及のために活躍。
伊藤 亮子さん理学療法士フェルデンクライス・プラクティショナー
医療・介護の現場で欠かせないポジショニング。普段何気なく行っているポジショニングも実は複雑な支援技術の1つです。一度はその手技を理解したつもりが、療養者の状態や症状、さらに体型によってフィットせずに思うようにいかずに悩んだ経験はないでしょうか?
適切なポジショニングを行うには、介護する側とされる側、そしてそれらを取り巻く環境をまず理解することが重要です。そしてその基本的な概念や原理と理論を上手く使って個別対応をすることが、ポジショニングの質を高めます。
本書では、適切なポジショニングを実践で行うために必要な基本的知識と手技が分かり易く解説されています。また、医療・介護の現場で悩まれているポジショニング関連のポイントも各章に含まれています。
皆さまが医療・介護現場で悩まれているポジショニング、体位変換の解決策の一助になれば幸いです。
アセスメントの流れ写真を撮る身体部位の位置関係重さの確認方法重さのかかり方仰臥位(下肢ポジショニング)スネーククッションを使用した下肢ポジショニングRF5を使用した上半身ポジショニング下肢伸展拘縮のポジショニング側臥位ポジショニングスネーククッションを使用した側臥位ポジショニングスモールチェンジ半腹臥位まとめ製品紹介
P3P4P5P7P11P13P17P20P21P23P27P31P33P37P38
は じ め に
Contents

実践の効果を導き出すために
アセスメントの流れ
日常的に御本人がどのような姿勢で過ごしているのか、どのようなサポートをされているかを把握します。
拘縮や褥瘡発生部位など気になる部分だけではなく身体全体を撮る
POINT!
ポジショニングピローの導入/使い方の変更の前に①姿勢(身体の部位同士の位置関係/重さのかかり方)②目的(すでに起きている問題/これから起こりうる問題)③要因を十分に把握することから始めましょう。
写真を撮る
実践しているポジショニングが適切かどうかを判断する一つの手段として、導入時からの経過を写真で比較できるようにしましょう。その時々の状態がわかる写真はポジショニングに関わる支援者間の共通理解を促す手段にもなります。
身体の部位の位置関係を把握しやすい姿勢
経過を知るために写真を撮る(計4枚)
1身体の部位同士の位置関係 3この状態でどのような問題が 起きるのか?(問題把握)
2身体とマットレスとの関係 重さのかかり方の確認
今の状態 足下に立って 真横から
仰臥位 足下に立ってピローなどを何も使用しない状態で(※本人に無理のない範囲)
※個人情報の取り扱いについては各自で責任を持ち、写真を撮影する前に御本人/御家族の了承を得ましょう。※姿勢を立体的に理解するために、足下、真横からと少なくとも2方向から撮影するようにします。
・鼻先・耳・肩先端・腰骨 (上前腸骨棘)・手 (手のひら・ 手の甲)・膝・爪先
真横から
目で見て気になることは?
マットレスは適切ですか?
ほかの部位との関係性
◎立ち位置や目線を変えてみる
◎より重さがかかっているのはどの部位か?◎それぞれの部位(例:骨盤)の重さのかかり方は?
◎骨盤が沈み込んでいないか?◎押し付けている場所はないか?
ほかの部分は?
□頭の側から□ベッドサイドに立って、 目線を下げる
【位置】左/真中/右【広さ】
◎既に起きていることは何か?◎このままの状態が続くとどうなるか? (予防から予測へ)
身体面/生活面
4なぜ、そうなっているのか? (要因)
◎今、姿勢を変えたときに起きたこと?その場で解決する
◎継続的に起きたことの結果?□福祉用具□介助の仕方□そのほかの環境要因
◎(1日のなかで)24時間姿勢管理下の□とっている姿勢のバリエーション□それぞれの姿勢を保つ時間
・骨盤と両足・胸部と両腕・背骨でつながっている 頭・胸部・骨盤
(例:ベッド・壁・テレビなどの配置)
訪室した時の姿勢
使用しているピローなども負担のない範囲で出来るだけ外す。
真横から撮ることで部位の前後の関係性が見やすくなる。どの部位が沈み込んでいるか、どの部位が押し上げられているか、などを確認。
仰臥位
3 4
アセスメントポジショニングコンパクトガイド【実技編】

姿勢を把握しましょう
身体は頭、胸郭、骨盤、両腕、両脚の7つの部位に分けることができます。この部位同士の位置関係が変わると姿勢は変化します。
両脚が左側に傾き始めるとやがて骨盤は左側に捻れ始め、更に胸郭にも影響していく。(重力の影響により、傾き始めると戻しにくくなる)
左右の関係性
捻じれ(それぞれの部位の正面はどこか)
背骨で繋がっている頭、胸郭、骨盤は前後、左右に位置関係を変えたり、それぞれが捻じれたりしながら、バランスを保とうとします。(身体を支える面の上で重力の影響を受けながらバランスを保とうとします。)
気になる部位だけでなくその隣の部位がどうなっているか確認していくことで早めに捻じれや傾きに気付き、対応できるようになります。
→左右の同じポイント、同じ側の隣のポイント、1つのポイントとマットレスとの距離などポイント同士を結び、長さや傾く方向から部位同士の位置関係(捻じれや傾き)やマットレスとの関係性を把握していきます。
●鼻先●耳●肩先端●腰骨(上前腸骨棘)
●手(手のひら・手の甲)●膝●爪先前後の関係性
枕の高さにより頭(額/顎)と胸郭の位置関係が変化する
POINT!
POINT!
●脚の重さは骨盤の位置に影響します。
●腕の重さは胸郭の位置に影響します。
●身体の部位同士の位置関係を把握しやすい頭側に立って見ます。
●いつもより目線を下げて真横から見ます。
目印になるポイント
5 6
アセスメント~身体の部位同士の位置関係を把握する~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】


頭の重さを確認する手を入れる時と抜く時に、もう片方の手を頭に添えて、頭が転がらないようにします。
POINT!
⑥胸郭の重さのかかり方を確認します。頭側の手を肩から肩甲骨(自分の立っている側)の下へ、足側の手を脇(腕と身体の間)から肩甲骨に向かって入れます。
⑦最初に入れた頭側の手を抜きます。
⑧肩甲骨からウエストに向かって胸郭の重さ(背骨より手前側)を確認します。
⑨頭の重さを確認します。
手は開いた状態で身体の下を滑らせながら重さを確認します。腕だけを使わず自分自身も移動しながら確認するようにしましょう。力が入り過ぎると握ってしまい、移動せずに確認しようとすると持ち上げてしまいます。
POINT!
④骨盤から大腿部、ふくらはぎ、踵と足の重さを確認していきます。重さがかかり過ぎて手を動かせない時には頭側の手を補助的に入れると動きやすくなります。(重さの確認は片手で:補助的に入れた手は抜き忘れないように)
⑤腕の重さを腕のつけ根から肘、手と確認します。
※実際にはグローブをして確認します。
移動
逆側も同じ手順で確認して、左右の違いを確認
アセスメント~重さの確認~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
9 10

重さのかかり方
骨盤は沈み込んでいませんか
マットレスの上で身体を伸ばせる場合は頭、胸郭(肩甲骨、またはその少し下)、骨盤(仙骨部)、ふくらはぎ、または踵に重さがかかりますが、身体の部位同士の位置関係が変化し身体の形が変わってくると重さのかかり方は変化します。
目的を明確にする
身体の部位同士の位置関係と重さのかかり方を確認したら、その状態ですでに起きている問題、今後、起こりうる問題を把握しましょう。
1日をどの姿勢でどのぐらいの時間を過ごしているかを把握します。重力がかかることで今、起きている問題の悪化が予測できるマイナスな姿勢、重力が改善する方向に働くプラスな姿勢、プラスでもマイナスでもない姿勢を把握し、24時間での姿勢管理を考えます。(参照:コンパクトガイドVol.2 P13)
問題に対してのマイナス要因を把握する
介助方法、福祉用具(マットレス・ピローなど)
マットレスは適切ですか
まず初めに一番大きな支持基底面であるマットレスを確認します。「ポジショニング=ピローを入れること」のように考えられがちですが、マットレスの種類によっては、部分的に沈み込み過ぎることで圧が集中したり、屈曲傾向を強めてしまうことがあります。ピローの使い方を考える前に適切なマットレスかどうかの確認が重要となります。
脚の屈曲拘縮やギャッチアップ機能を使う場合は骨盤に他の部位の重さがかかり、沈み込みを起こしやすくなります。
押し付けている場所はないですか筋緊張の変化によっても重さのかかり方は変化します。
接触面積を増やすことと重さの配分の両方を考えることが重要です。POINT!
福祉用具の選択と使用方法だけでなく、介助の仕方が姿勢に大きく影響していることがあります。御本人の状態に対して、介助方法、速さ、力のかけ方などが不適切な場合、姿勢を変えるたびに筋緊張を高めてしまったり、重さを十分に移動しきれずに傾きやねじれを生じさせてしまうこともあります。それが続くことで変形は固定化され、二次的な問題を起こしやすくなります。
POINT! 介助の影響
違和感・痛み褥瘡(皮膚)拘縮(関節・筋肉)筋緊張呼吸嚥下骨粗鬆症(骨)など
【身体面】姿勢保持着替え排泄ケア移動・移乗情報収集・コミュニケーションなど
【生活面】
●姿勢を変えた時のサポート
とっている姿勢のバリエーション(重力の影響)、時間、介助する方向の偏り●一日の中での姿勢の変え方
ベッド、入り口、テレビなどの配置●その他の要因
マットレスが部分的に沈み込み身体が丸まっている
適切にある程度、身体を沈み込ませることで接触面積を増やせている
固いマットレスだと身体が沈まない分、浮いてしまうところができて、接している部分に圧が集中する
11 12
アセスメント~重さのかかり方~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】

ピローをセットする時のポイント RM1を使用
仰臥位は身体とマットレスの接地面が広い安定した姿勢です。しかし、拘縮のある方やマットレスに身体を押し付けている方の場合は拘縮や押し付けを助長しないように立体的にピローを使ったサポートが必要となります。脚部の屈曲や押し付けは仰臥位で身体を大きく支える部位の一つである骨盤のねじれを引き起こす要因となります。脚部の屈曲が進むほど、重力の影響により脚部は左右に倒れやすく、骨盤のねじれに繋がりやすくなります。早い段階でポジショニングを導入していくことで足を伸ばしていく方向に重力を働かせることが可能となり、そのためのサポートも提供しやすくなります。
力の入らない人の脚は、重力により落ちようとしています。上から握ったり、膝裏に手を差し込むと部分的に負担をかけることになり、介助者の負担にも繋がります。
POINT!
ピローの両サイドを引き、張りを持たせながら筒状に巻いていく。表面がカーブを描くように。
POINT!
①RM1を巻き込み、筒状にする。
②巻き込んだピローの端が下側か外側になるようにするとよりしっかりと脚をサポートできます。それでもピローが脚(特に大転子部)から離れてしまう場合は巻き込みを少なくし、径を細くします。
②膝の外側をサポートします。介助者自身も体重移動をしながら、御本人の脚の重さを骨盤に移動させるように曲げていきます。
③脚が立てられる場合は一度、脚を立て、足底で脚を支えるようにします。ピローの操作をする際に、脚の重さが介助者の負担にならないようにしましょう。
ピローを準備します
下肢を曲げていきます
①力を膝下の骨格(脛骨、腓骨)に伝えていくように、踵の手前(内くるぶし、外くるぶしの延長線上)から押していきます。
仰臥位~下肢屈曲拘縮のポジショニング~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
13 14

ピローの長さが足りず、サポートが不十分な場合は、RM3などで補助するか、スネークミニ、またはスネークを使用します(参照:コンパクトガイドVol.2 P18)
POINT!ピローが脚(特に大転子部)から離れてしまう場合は巻き込みを少なくし、径を細くします。
POINT!
①膝下を胸郭方向に押す、または脚部の下に介助者の前腕(頭側の腕)をくぐらせ、踵の手前から膝方向に押すようにしながら脚をマットレスから離します。
②足下側の手でピローをセットします。
③大転子から大腿骨の外側と脛骨の内側をサポートし、ピローの上で脚が小さく内側にも外側にも転がれるような支持面を提供します。
④ピローに足をのせて、張りを持たせながらピローの両端を持ち、ピローと足を一緒に小さく内側、外側へと転がします。小さな動きによってピローの中身が身体に馴染むと、しっかりとしたサポート面が提供できます。それと同時に余分な力が抜けやすくなることで、身体の重さをピローに預けやすくなります。
ピローに足をのせていきます
大腿部の重さをピローに預けたまま、足首を持って位置を変えようとすると膝に不必要な捻じれが生じ、負担となります。脚を寄せたり開いたりする時は、膝下だけを動かすのではなく、脚全体を一度、ピローから離して、乗せ直すようにしましょう。
POINT!
仰臥位~下肢屈曲拘縮のポジショニング~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
15 16

全てのことを一つの姿勢で解決しようとせずに、仰臥位で足底のサポートをしない場合は寝返りなどの時に足首を使えるように介助したり、座位で足底に荷重しながら足首を曲げる機会を提供しましょう。
POINT!
①均等に2つ折りして分けます。
②中身が移動し過ぎないようにゴムなどで止めたり、クッション自体をねじります。
③中央を足元側にして片足ずつピローをセットしていきます。
④大転子から大腿部の外側、膝下を通して、脛骨の内側をサポートします。
・膝が曲がっている場合はサポートをした方が安定します。・膝が伸びている状態で足首を直角に曲げてしまうと、ふくらはぎの筋肉が伸ばされたままになります。
ポジショニングをしていると介助者の立っている側に足を引き寄せてしまう傾向があります。横から見ても気付きにくいので、最後に必ず足元から全体を確認しましょう。
POINT!
微調整は持ち手を持ってピローを振りながら内容物を均等にします。ピローの表面を叩いて均してしまうと平らで硬くなり、身体にフィットしづらくなります。
POINT!
スネーククッションを使用した下肢ポジショニング
足底サポート
仰臥位~下肢屈曲拘縮のポジショニング~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
17 18

RM1を二つ折りにしてから軽く振り、厚みを変えます。前腕を置く場所を提供することで、手をお腹の上に置くよりも肘を伸ばしやすくします。手を身体の横に置くことが難しい方の場合はブーメランを使用します。
POINT!
柔らかいピローは身体の形に合わせて形状が変化しやすく、身体との接地面積を増やすことができますが、時間の経過とともに沈み込んでいく傾向があります。頭や肩甲骨周辺など、重さがかかっていく部分がより沈んでいくため、ベースになるピロー(RF5)の下に支えるためのピローを入れることでバランスをとりやすくします。必要に応じて肩甲骨から上腕にかけてRM3を使用するとより安定します。
POINT!
大きなピローで下肢全体に接地面を提供していても、ピローの素材や形状によっては時間が経過すると沈み込みが生じ、姿勢のくずれに繋がることがあります。
POINT!
圧の集中しやすい踵を挙上するために足首にのみピローを入れると、足首を圧迫させてしまうことがあります。横から見た大転子、膝、踵の位置関係を変化させ、膝を伸ばし過ぎてしまったり、臀部が重たくなり過ぎたりすることもあります。
POINT!
内容物が同じクッションでも形状によってサポートに変化が起きる
頭、胸郭をサポート RF5を使用
前腕をサポート RM1/ブーメランを使用RM1:スリットによって内容物の移動が最小限に留まります。RM2:時間の経過とともに身体の重さによって内容物が移動し、沈み込みやすいです。
①RF5を振って、内容物を片側に寄せて厚みを変えます。
②厚い方を頭側、薄い方を骨盤側にして胸郭の下まで敷き込みます。RF5の下に頭をサポートするためのRF3をセットしておきます。
ピローの厚みを変えてより立体的にサポートします。
仰臥位~下肢屈曲拘縮のポジショニング~
仰臥位~円背、腕の屈曲拘縮のポジショニング~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
19 20

筋緊張が変化し、少しでも力が抜きやすくなってきたら、膝下でピローを折り返して膝が少し曲がるようにします。折り返す時間、元に戻す時間を作り、膝と股関節の小さな動きから筋緊張の変化を促します。
POINT!
摩擦係数の低いグローブの中にピローを入れ、滑らせながらセットします。皮膚を引っ張ることなく、位置を微調整することができます。
POINT!
踵の部分を折り返すとピローと脚の接地面積を増やし、より立体的にサポートできます。
POINT!
下肢伸展拘縮のポジショニング RM1を使用
①摩擦係数の低いスライディングシートなどでピローを包み、ピローと足、ピローとマットレスの間が滑るようにします。
②両端のスリットに左右の踵をのせていくようにシートごとピローを滑らせます。
③そのままピローをシートで滑らせながら、脚をのせていきます。
④脚の間にある中心のスリットの辺りを持ち、ピローを引き上げていくことで、ピローがより立体的に脚に触れるようにします。
⑤膝を少し曲げた時には大腿部にもサポートが必要となります。
上から見た図
横から見た図
ピロー配置図
ピローを使い、足と支持面との接地面積を増やすことで圧を分散させると同時に、足を認識しやすくします。マットレスへの押し付けが強い場合、ピローの入れ方を工夫し、御本人と介助者相互の負担を軽減しましょう。
仰臥位~下肢伸展拘縮のポジショニング~
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
21 22

フラップ部を身体の下に敷き込み、ピローのずれによって生じる姿勢のくずれを軽減します。
POINT!
上側の腕を身体の前から横に持っていき、上側の肩がピロー(RM2)に寄りかかれるようにします。肘が肩より後ろに下がり過ぎる場合は、肘の下にピロー(RM3)を置くと高さを提供できます。(最終的に上側の腕の位置を確認するまでの仮置きとします)
POINT!
側臥位になった時に下側の肩が詰まったような状態になりやすいので、耳と肩を結んだ線の左右差や重さのかかり方を確認しましょう。肩甲骨の下に手を入れ、肘の方向に引いて肩の詰まりを解消します。(参照:コンパクトガイドVol.2 P22)
POINT!
側臥位になった時に上側になる下肢が頭・胸郭・骨盤の下か、やや前方にくるようにします。あらかじめ、②でピローは骨盤の下に用意しておきましょう。
POINT!
足底(踵の前)から膝に向かって押しながら、股関節を曲げるか、膝を開くようにしてみましょう。
POINT!
RM1,2,3,4、RF1,3を使用して
①胸郭と骨盤を支えるピロー(RM2)を用意します。形が御本人の身体に合っているか、長さが十分にあるか確認しましょう。
②上側の下肢を支えるピローを用意します。(RF1の上にRM1を二つ折りにして重ねます)
③胸郭、骨盤の順にピローに重さを預けていきます。
④RM1のスリットの上に、下肢(主に下腿部~踵まで)がしっかりとのるようにします。ピローの位置を動かし下肢が安定する位置を見つけましょう。
⑤下側になる部位の重さのかかり方を確認します。(肩の下→(一度、 手を入れ直して)脇の下から胸郭→骨盤→大腿部外側→膝→下腿部→外くるぶし)手が入らないぐらい重さのかかっている部分には無理に手を入れずに、必ず、何かを変えなくてはいけない部分と認識しておきます。
仰臥位で身体の傾きやねじれの状態を確認してから横向きになります。
下側の肩の位置
ピローを用意する位置
骨盤の下にピローが置けない場合
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
側臥位
23 24

大転子部より膝が下がっている場合、下肢は内側に入りやすく、下肢の重さで骨盤は引っ張られていきます。
POINT!肩と肩を結んだ線と腰骨と腰骨を結んだ線で胸郭と骨盤の間のねじれを確認します。上の肩と腰骨、下の肩と腰骨を結んだ線で左右の傾きを確認できます。膝の方から大腿部の外側を支えるようにしながら、骨盤横の一番、重さのかかっているところに手を入れ、上側の腰骨を押しながら、膝方向に引くことでねじれを解消します。(参照:コンパクトガイドVol.2 P22)
POINT!
重さのかかっている部分に手が入らない場合はグローブを使用します。引く時に滑ってしまうので、重さのかかっている部分の下ではなく、骨盤の後ろ側まで骨盤を包み込むように手を入れるようにします。(手は平らではなく、柔らかくカーブさせます)
POINT!
腕を支持面から離す時も介助者の前腕で広く支えるようにします。重力により、落ちようとする腕を上から掴むことで部分的な負担がかからないようにしましょう。
POINT!
⑥下側の膝が浮いていたり、足が開き過ぎている場合はRM3またはRF3でサポートします。
⑦RM3を仮置きしていた上側の腕の位置関係を確認します。肩‐肘‐手首‐指先 それぞれの位置関係で重さがどちら側にかかっていくのかは変化します。腕全体をサポートし、腕の重さが腹部にかかりすぎないようにするためにはRM4を使います。
⑧最後に身体全体の状態を見直しましょう。 身体の部位の位置関係:頭、胸郭、骨盤の正面はそれぞれどちらを向いていますか。 重さのかかり方:下側の重さのかかり方の配分は⑤で確認した時よりも偏りが少なくなっていますか。
肩と骨盤の位置関係
介助グローブを使う場合
上側の下肢の位置関係
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
側臥位
25 26

⑤寝返りをうっていくためにクッション側の下肢を立てます。立てた足で踏み込み、骨盤にかかっている重さを片側から反対側に移動させながら側臥位になっていきます。
④ピローに頭をのせます。側臥位になる時に頭がクッションの上で転がっていくための長さが必要です。ピローは頭に対して真横ではなく少し斜めに入れます。
①取っ手を持ち、クッションの内容物が均等になるように振ります。
②身体の位置をベッドの中心よりもクッションを入れる側に移動します。身体のすぐそばにピローを置きます。
③上側になる上肢を胸郭の上にしっかりのせます。
⑨高さなどを微調整しながら、頭をのせ直します。
⑥下側になる下肢は曲げた方が支持基底面が広がり、側臥位はより安定します。
⑦身体をしっかりと支えるためにはクッションに張りが必要です。クッションに張りを持たせる時に頭まで引っ張っていかないように、首の下辺りを頭側の手で押さえ、足側の手でクッションを引きながら、身体に沿わせるようにします。胸郭から骨盤へゆっくりとクッションに重さを預けていきます。
⑧下肢をのせていく時もクッションがたわみ過ぎないようにします。
スネークを使った側臥位のポジショニングでは、頭から胸郭、骨盤、上側の下肢までを一つのクッションでサポートします。
身体の形に合わせやすい→背中の丸みが強くなった方少しずつ姿勢を変化させることができる→夜間や筋緊張の高い方の体位変換身体の部位から部位へと動きを連動させることができる→寝返りの動きをサポート
POINT! スネークを使うと…
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
側臥位~スネーククッション~
27 28

⑬耳と肩の位置関係、肩と骨盤の位置関係はどうなっていますか。肩と骨盤の位置関係はどうなっていますか。必要に応じて、肩を肘方向へ、骨盤を膝方向に引き、その時起きた問題はその場で解消します。(P24参照)
⑩クッションの厚みがほぼ均等になるため、膝が伸びきってしまわないようにRF3をクッションの下から入れて高さを提供します。大腿部の外側から下腿部の内側方向へ斜めに入れます。
⑪スネーククッションを使わない側臥位のポジショニングと同じように進めていきます。上側の肘は肩に対して下がり過ぎていませんか。(RM3/仮置き)
⑫下になる側にはどのように重さがかかっていますか。
⑯上側の腕(肩・肘・手)の位置関係を確認し、必要に応じて、RM4を使用します。最後に全体の位置関係と重さのかかり方を確認しましょう。
⑭下側の上肢はサポートがあれば、伸ばすことができるでしょうか。(RM3使用)
⑮下側の膝が浮いていたり、股関節が外側へ開き過ぎているようであれば、サポートが必要です。(RM3使用)
スネーククッションが身体に触れていても、クッションがマットレスから離れていると支えとして十分に機能していないことがあります。特に重さのかかる骨盤を支えている部分などが浮いているようであれば、スネーククッションの下にRM3、またはRF3を足して支持性を高めます。
POINT!
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
側臥位~スネーククッション~
29 30

④次に関われるタイミングで肩、骨盤、下肢の下とRM5を抜いていきます。
⑤最初の側臥位の状態に戻ります。この後、仰臥位になったり、RM5をもう一度、入れてから、この姿勢に戻り、その後、仰臥位になるなど、小さな変化で姿勢のバリエーションを増やすことができます。
①肩の位置でスネーククッションを身体の方に押しながら重さのかかる場所を移動し、RM5を入れていきます。
②骨盤、下肢の下にも同様にRM5を入れていきます。膝の高さを提供するRF3は一度、はずし、RM5の下から入れ直します。
③頭以外、肩の位置からスネーククッションの下にRM5を入れて、より深い側臥位になります。
⑦何度か、⑥を繰り返します。上側の下肢の大転子部が踵よりも下がってきたら、踵をクッションから下ろします。反対側の足も徐々に内側に寄せてくるのを忘れないようにしましょう。
⑧下肢の部分のクッションを抜いていく際にグローブを使用し、持ち上げずにグローブの下でクッションを滑らせながら抜いていくことができます。
⑨スネーククッションを抜いて、仰臥位になります。頭の部分は側臥位の時よりも低めにします。
⑥スネーククッションそのものを少しずつ引きながら、さらに小さく徐々に姿勢を変えていくことができます。
身体の下でクッションが大きく動かないように、身体に近い位置でクッション表面を片手で摘むようにしながら、身体の方向に引き上げ、布に張りを作ります。その部分のクッションの下側に手を入れ、布の部分を持って、少しずつゆっくりと引き出すようにします。肩、骨盤で同じように引き、上側の足の高さも少しずつ変わっていくようにします。
POINT!
仰臥位に戻っても、それまで下になっていた側にまだ重さがかたよっているので、一度反対側に寝返りをしてかたよりを解消します。寝返りが難しい場合はグローブを使い、下になっていた側に手を入れてかたよりを軽減します。
POINT!
※頭の下には入れません。
少しずつクッションを引いていくことで重さのかかる場所を移動させていきます。夜間の体位変換、筋緊張の高い方、痛みのある方にも受け入れやすく、介助者にとって、ピローを入れていくことが難しい場合もピローを引くことであれば協力が得られるなど、御本人、介助者、双方に負担の少ないポジショニング方法です。
POINT! スモールチェンジ
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
側臥位~スモールチェンジ~
31 32

①寝返りをうっていくスペースが必要なので、最初にベッドの端に移動します。身体の横に、均等に振ったスネーククッションを用意します。
②少し斜めにしたクッションに頭をのせたら、身体の上にクッションをのせます。
③上側になる腕でクッションを抱えるようにします。
④上側になる下肢をクッションにのせます。
⑤これで寝返り準備完了です。
⑥クッションを膝下の辺りで持ち、大腿部の延長線方向に引いていくと骨盤に動きが伝わっていきます。骨盤がついてこない場合は骨盤の動きをサポートします。
腕の重さで肩がマットレスの方に下がってきてしまうようであれば、肩の下にRF3を入れると手がクッションに届きやすくなります。足の重さで骨盤がマットレスから離れづらい場合も、骨盤の片側の下にRF3を入れて高さを提供します。膝下辺りのクッションを引きながら寝返りをうつ方向へ回していくと、骨盤の片側が持ち上がり、ピローを入れやすくなります。このように、肩や骨盤の下にあらかじめ、ピローを入れておくと、半腹臥位になる時だけでなく、身体の大きい方の寝返りの介助をする時も手が届きやすく、また、少ない力で介助することができます。
POINT!
半腹臥位では日常的に寄りかかることの多い背部にかかっている重さを移動することができ、重力との関係性の違いから、力の抜きやすさや動きやすさが大きく変化します。無理なく体重移動の可能な範囲から始めていきましょう。
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
半腹臥位
33 34

⑦クッションのサポートで下肢から骨盤、胸郭と動きを連動させていきます。骨盤の動きが大きくなっても胸郭の動きがついてこない場合は、胸郭の動きを助けます。
⑧上側の腕が安定しない場合はピロー(RF3)で腕を置きやすい場所を提供します。
⑨下側の肩に重さがかかりすぎていないか後ろ側から確認します。 ①胸郭と骨盤の後ろに寄りかかるためのピロー
(RM2)を用意しておきます。②御本人が少ない力で後ろに寄りかかったり、前方に戻ったりしやすい骨盤と下肢の位置関係を、上側の足の高さをピローで変えながら探します。③仰臥位からの寝返りが十分にできず、姿勢を変えられない方でも、重力のかかり方と身体の部位の位置関係の違うこの姿勢では同じぐらいの力でも大きく動くことができ、姿勢を変えやすくなります。
POINT!
下側の足首が不安定であれば、RM3でサポートします。
POINT!
前後に移動する①
③
②
②
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
半腹臥位
35 36

ポジショニングとは
バランスをとろうとする力、動こうとする力をプラスに活かせる環境作りとして、姿勢(身体の部位同士の位置関係・支持面(福祉用具)と重力の影響)を理解し、すでに起きている問題、これから起こりうる問題(予測から予防へ)とそれに対してのマイナス要因を明確化していくことから始めます。部分的・一時的な問題解決だけではなく、より多面的で継続的なサポートとなるよう、連携(協力/役割分担)しながら、御本人の状況と受け入れに寄り添えるよう、確実に続けられるペースを見つけていくことが重要です。
その時の姿勢とサポート状況1日の姿勢・介護力の確認問題(身体面/生活面)とマイナス要因の明確化
把握
発赤、痛み、姿勢の崩れ(位置関係)、重さのかかり方、筋緊張を確認しながら小さなことから始めて確実に
導入
状況の変化を再評価・検討し、継続、あるいはやり方を変えて実行する再度、見直し→判断→実践を繰り返す
見直し
様子を見ながら、時間や変えていく範囲を徐々に広げていく
経過 観察
御本人や介助者へポジショニングの目的を説明説明
ポジショニング導入の流れ
RF15,000円(税抜)
RF35,500円(税抜)
RF513,000円(税抜)
RM114,500円(税抜)
スネーククッション25,000円(税抜)
サポタイトブーメラン13,000円(税抜)
サポタイト三角枕9,800円(税抜)
RM214,500円(税抜)
RM32,700円(税抜)
RM47,500円(税抜)
RM515,000円(税抜)
スネークミニクッション16,000円(税抜)
サポタイト標準枕5,600円(税抜)
サポタイト側臥位セット21,000円(税抜)
製品紹介
ポジショニングコンパクトガイド【実技編】
まとめ
37 38