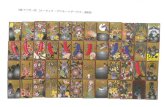工 備 整 設 施 理 管 1 -1 3 - Sapporo · 工 備 整 設 施 理 管 1 -1 3. 標 準 図 札幌市造園工事 札幌市建設局みどりの推進部 特 記 仕 様 縮
北大植物園ガイド資料 - CANPAN FIELDS北大植物園について 1 地 形...
Transcript of 北大植物園ガイド資料 - CANPAN FIELDS北大植物園について 1 地 形...

北大植物園ガイド資料
NPO 法人北海道市民環境ネットワーク主催北大植物園観察会資料(北海道林業技士会西川事務局長作成)

北大植物園について
1 地 形
札幌市は、豊平川(支笏湖の西側にある小漁岳が源流)の扇状地(に発達した街である。札幌市の中心の北大植物園、札
幌市役所、札幌駅があるあたりが、扇状地の先端となっている。この辺りから氾濫原となり、石狩平野につながる。明治時代には
護岸が進んでいなかったので、度々水害に見舞われた。しかし、川筋からはなれたところは、水のはけがよく、伏流水が豊富で、
居住しやすく、果樹栽培を含む畑作に優れた土地として利用された。
湧き水は、この北大植物園の
ほか、北海道庁、北海道知事
公館、北海道大学構内の池に
点在している。なお、札幌市のサ
ッポロは、豊平川のアイヌ名がサ
ッポロペッで(サッ=乾いた、ポ
ロ=大きな、ペッ=川)であった
ので、そこから命名されたとされ
る。なお、サツ(乾いた)の意は、
扇状地を流れる川の特徴とし
て、分水して水量が少なかった
り、渇水期に極端に水が減り、川底の石がごろごろ見えるからだといわれている(アイヌ語地名研究家の山田秀三(1899
年~1992 年)。ポロは札幌周辺に川の中で、一番大きいので「サッポロペッ」になったとされる。
2 北大植物園の歴史
ア 札幌市の歴史
明治維新後の 1869 年(明治 2 年)、アイヌの土地だった札幌近郊は、開拓使(現在の「省」)直轄の地となった。主席
判官の島義勇は、石狩本府(役所)を現在の南一条通りに置き、ここから南北、東西に分かれる整然とした現在の札幌の
街造りを計画した先人として名を残している。1871 年(明治 4 年)5 月に札幌開拓使庁ができ、1875 年(明治 8 年)に屯
田兵が入植して、本格的に北海道の開拓が進んで行った。明治 18 年に北海道庁が新設され、札幌市は北海道の首都
となる。
イ 北大植物園設置当時の状況
開拓使は鬱蒼とした原生林の広がる道庁の西側を牧羊場と定め、明治 15 年その中に博物場を建てた。札幌農学校の
教頭クラークは、開拓使に対し、植物学の教育・研究には植物園の設置が必要であると進言していたこともあり、明治 17 年、
博物場及びその付属地 15,000 余坪(4.5ha)が植物園用地として札幌農学校に移管された。明治 19 年(1866)に開園と
なったが、これは日本で初めて近代的植物園として造られたもので、日本で 2 番目に古い植物園である。
初代植物園長は、設計を担当した宮部金吾であるが、天然の風致を生かし、水系(湧水)・起伏やハルニレなどの巨樹を
そのままとした。宮部金吾は、明治 17 年から日高、道東沿岸、千島、エトロフへ植物採取に出かけ、園内に植栽した。又、
北海道の荒廃した森林の復旧造林のための樹種として外国樹種〔注1〕の育苗、販売も行なっていた。

(注1〕 北海道の森林は、明治以前からの和人の移住に伴う乱伐や山火事によって荒廃していた。政府(開拓使)は、明治当初
から荒廃地の復旧造林の必要性を痛感していた。植栽する苗木については、当時、郷土樹種であるトドマツ、エゾマツなどの養
苗技術が確立されていなかったため、明治4年、東京の青山、麻布に「開拓使官園」を設置して、外国から家畜や農作物とともに
樹木の種子を移入し、苗木の育成・試験を行い、育成した苗木を北海道に移入して植林する方策を講じた。北海道における開
拓官園は、明治 6年、札幌市北 6条(後、札幌農学校所属地となる)に設置され、その後開拓官園(札幌勧業試験場と名を変え
る)は、規模を拡大し、明治 9年、札幌農学校付属地、明治 13年(1880)には、札幌神社外苑に円山養樹園を設置し、東京の開拓
使官園から移入した外国樹種等の養苗を育て、国有林に造林され、民間に払い下げられた。
3.植物園の樹種構成
面積 13.30haの園内には、約 4,000 種の植物が育成、保存されている。特徴的なのは、開園当時のハルニレ、イタヤカ
エデ、ハンノキ、ミズナラ、ドロノキなどを主体とした広葉樹林が残されていることであり、石狩低地帯の原植生の面影を示す
貴重なものとなっている。その他、郷土樹種以外のユリノキ、サイカチ等国内産、アカナラ、メタセコイア等外国産樹種が育
成されている。
植物園の中心をなすのはハルニレの林で、本数も最も多い。大きなもので樹齢 150 年~200 年と推定されている。従って、
開園当時の樹齢は逆算すると樹齢 30 年~80 年の小中径木であったことになる。
ハルニレ(春楡) ニレ科
北大植物園のシンボリックな樹木
◆和名由来:春に花をつけるニレ。ニレとは皮をはぐとヌルヌル
していることから。ヌル→ヌレ、ニレになったものといわれている。
名:エルム(英名)、アカダモ。北大は、構内にハルニレが多く
生育していたことから、エルムの学園と言われてきた。◆分布:
日本各地。適湿かやや湿った肥沃な土地に生育する。◆花
期等:4 月。花色は赤紫。花序は穂状。花は葉の展開に先
立って枝先に咲く。◆葉:互生。葉はやや厚くてざらつき、縁
は重鋸歯。裏面葉脈には毛が多く、葉の形は左右非対称
<神話を生む美しい巨木>
1 北欧の神話によると天地を創造した首神(オーディン)が
ニレの木に魂を与え、エンプラと名づけ、人類最初の女性
とした。以後、神は遠慮してこの木には雷を落とさないという
伝説を生んだ。
2 ユーカラに語り伝えられるニレは女神である。ハルニレ姫は
天上の神々が見とれるほど美しかった。ついに雷神が足を
滑らせハルニレ姫のうえに落ちてしまう。姫は身ごもり、男の
子アイヌラックルを産んだ。アイヌラックルは神のもとで成長
し人間界に帰り、悪魔から人間を守った。従ってハルニレ
は、神様の位では最高の「火の神」として敬われた。

サワグルミ クルミ科
◆和名由来:沢に生育するクルミの意。◆分布・生態:日本
固有種。北海道南部、本州、九州、四国。湿地に富む峡谷
に生育する。◆花期等:5月。淡黄緑。花序は尾状。葉は互
生で肥厚した葉柄のある奇状羽状複葉。◆果実はひし形の
翼をもつ。材は軽くて割れにくく、建築、家具材として利用され
る。公園樹や並木に用いられる。
オニグルミ(鬼胡桃) クルミ科
◆和名由来等:オニは、表面がなめらかなヒメグルミに対して
凸凹があり、ゴツゴツしていることから。クルミの語源は①呉の
国から伝えられたためクレミ(呉実)の転。②黒実の転。◆しわ
の多い果実は人間の脳に似ていることから中性ヨーロッパでは
すりつぶしたクルミの実に草を混ぜて精神病薬にしたという。
◆分布・生態:日本各地の山野の渓流沿いに見られる。◆
花期等:5~6月。◆葉は互生で大型の羽状複葉。◆古く
から食用にされ、 縄文時代の遺跡から出土しているクルミの
実は、殆どオニグルミである。
キタコブシ(北拳) モクレン科
◆和名由来:北方に生えるこぶし。こぶしはつぼみが
人のこぶしに似ていることから。◆分布・生態:北海
道、中部以北。適度に湿った日当たりの良い場所。
◆花期等:4 月。帯紅色。花序は頂生。
◆葉:互生。◆材は柔らかく、マッチ軸、床柱に利用される。
樹皮は灰色。◆アイヌの人々はこの木をふだん「いい香りを出
す木(オマウクシニ)」と呼んでいた。伝染病が流行しているとき
には病魔も香りに惹かれてやってくるおそれがあると考え、「放
屁(オナラ)をする木(オプケニ)」とわざと名前を変えて呼んだ
そうである。ふだんはこの木の皮や枝を煎じてお茶のように盛ん
に飲んだという。(北方植物園より)。