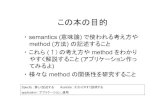総合的な学習の時間 - Kanagawa Prefecture · 2017-05-15 · 有しながらまとめ...
Transcript of 総合的な学習の時間 - Kanagawa Prefecture · 2017-05-15 · 有しながらまとめ...

- 139 -
総合的な学習の時間
1 研究テーマとねらい
(1)研究のテーマ
アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた指導方法の研究~社会への接続としての「総合的な学
習の時間」の意義~
(2)研究のねらい
「探究のプロセスの充実」を意識した授業改善となることをねらいとし、「地域学習」「グルー
プ・エッセイ」等をテーマにした単元で、アクティブ・ラーニングの視点を踏まえ、対話的な学
び、主体的な学び、深い学びの三つの学びの視点を踏まえた実践を行う。
2 実践事例
【実践事例1】
(1)単元の指導計画及び重点を置いた授業展開例
①単元名:地域研究~城山について知ろう~(学年:第1学年)
②単元のねらい(身に付けさせたい力):
・身近な場所について様々な視点から調べ学習を行うことによって、探究活動に対する主体的、協働
的な態度を育む。また、地域の姿を再確認し、地域との関わり方など自らの実生活に関連付けて考
える力を育む。
③単元の評価規準
協働する力 課題設定力 情報収集能力 自己表現力
積極的に協働作業に
参加し、他者の意見
を尊重しながら課題
に取り組んでいる。
必要に応じて、的確
な課題を設定してい
る。
情報にアクセスし
ながら、その情報
中の必要な情報を
取捨選択し、活用
している。
調べたことや学んだ
こと、自分自身の考
えを、分かりやすく
表現している。
④単元の指導計画 a:協働する力 b:課題設定力 c:情報収集能力 d:自己表現力
時・次 学習内容 学習活動 評価の観点
評価規準 評価の方法 a b c d
1
(本時)
城山につい
て知る
・4分野(古文
書、歴史、自然、
産業)に分かれ、
それぞれ資料を用
いてワークシート
を作成する。
○ ◎ c.資料から必要な
情報を読み取り、
活用しながら課題
に取り組んでい
る。
観察
ワークシート
2
事前学習
・登山のマナーや
注意事項、チェッ
クポイントなどを
確認する。
◎ b.実際の散策を想
定し、留意点など
を考えている。
観察
3
城山散策
・城山に登る。
・チェックポイン
トをまわり、記録
○ ◎ c.事前に調べた内
容を他者と情報交
換しながら、それ
観察

- 140 -
を取る。 らを活用して活動
している。
4
協議
・4分野のグルー
プで調べたことを
クラス内の班で共
有しながらまとめ
のワークシートを
作成する。
○ ○ ◎ d.調べたこと、学
んだこと、自分の
考えをわかりやす
く他者へ伝えてい
る。
観察
ワークシート
(※ ◎単元の総括の資料とする観点、 ○単元の総括の資料としない観点)
⑤授業案
学習活動(指導上の留意点を含む) 評価の観点
(評価方法)
●活動の見通しを持つ。(単元のねらいと以降4時間の流れ、本時のねらいと活
動内容を説明する。)
●担当する分野に関する資料を用い、ワークシートを協力して作成する。
(古文書読解、歴史、自然、産業の4分野にあらかじめ振り分けておく。協力
して作成できるように配慮する。資料の活用方法を助言する。)
●班ごとに調べた内容をまとめ、発表する。意見や関連する具体的な体験を交え
て話す。単元の4時間目に他の班員に説明することについて整理を行う。
(生徒の様子を観察し、必要に応じて助言を与える。)
a(観察)
c(ワークシー
ト)
研究実施校:神奈川県立城山高等学校(全日制)
実 施 日:平成28年9月26日(月)
授業担当者:三津谷 真季 教諭
(2)アクティブ・ラーニングの視点に基づく授業の解説
本単元では、「探究のプロセスの充実」を主眼とした。単元の最初に、調べ学習からまとめ学習までの
流れを説明し、見通しを持たせることで、生徒が自らで計画を立てて学習することができた。また、情報
の受け手を設定することにより、調べたことを分かりやすくまとめようという意欲が向上した。【主体的
な学び】また、生徒と教師との対話だけでなく、地元出身の生徒が、他の生徒に知識を披露する場面も見
られるなど、生徒同士の対話も活発化し、思考が広がったり、深まったりした。【対話的な学び】城山散
策では、事前に得た知識と、直接目で見て、触れるという体験を結び付けることができた。散策後のまと
めの学習では、調べ学習で得た知識を生徒同士の学び合いによって共有した上で、4分野の共通項を考え
させた。この活動ではそれぞれの分野における具体的な知識から普遍的な言葉を発見させるという帰納法
的な思考が必要となる。少し難しかったようだが、根拠を持って共通項を発見できた者もいた。また、地
域における今後の課題を発見し、その解決法を考えることができた。【深い学び】
(3)成果と課題
(成果)資料準備やワークシート作成を分担して行い、特定の教師だけに負担が偏らないようにした。ま
た、各教科の教師が関わることで、教科横断的な授業を行うことができた。生徒は身近な地域を様々な視
点から再認識し、概ね達成感を持つことができた。「楽しかった」、「意外と知らない事が多く、驚い
た」、「班での作業で意見を出すことができた」などの感想からそのことが分かる。
(課題)調べ学習の段階でタイムキープや役割分担が不十分であったために、ワークシートが完成しない
者もいた。ワークシートの内容を精選したり、調べ学習のルールや手法を指導したりする必要がある。ま
とめの学習では、共通項を発表する際に、他の班の意見に流され、全く同じ言葉が複数出るという結果に
なった。他の班の発表に流されないような工夫が必要である。また、担当者や学年が変わっても同じ単元
を実施し、一定の効果を得るためには、総合的な学習の時間に対する教師間の相互理解が求められる。成
果を学校全体に周知し、資料等の引き継ぎや連絡を綿密に行っていきたい。

- 141 -
【実践事例2】
(1)単元の指導計画及び重点を置いた授業展開例
①単元名:グループ・エッセイ ~他者と協力し、小論文を完成させよう~(学年:第3学年)
②単元のねらい(身に付けさせたい力)
・小論文の『型』を理解し、他者の視点や助言を受容しながら小論文を完成させる力。
・グループワーク(協働学習)による相互評価を通じて、小論文作成の手法を深める。
③単元の評価規準
課題設定の力 協働する力 表現する力 分析する力
テーマに関心を持ち、
小論文の作成や、相互
評価に意欲的に取り組
もうとしている。
他者の意見や質問を理
解し、根拠や具体例を
示しながら自分の考え
を述べている。
小論文作成上の課題を
理解し、執筆や評価の
際に意識して実践して
いる。
相互評価に際して、
具体的に根拠を示し
ながら分析・評価し
ている。
④単元の指導計画 a:課題設定の力 b:協働する力 c:表現する力 d:分析する力
時・次 学習内容 学習活動 評価の観点
評価規準 評価の方法 a b c d
1
「型」を意
識して構想
を練る。
〇テーマ決定→骨組作成
・個人作業→グループワー
ク。
・根拠や具体例、想定反論
等を考え、論を掘り下げ
る。
○ c.小論文
の「型」
を理解し
ている。
ワークシート
振り返りシー
ト
2
グループワーク
で内容の充
実を図りな
がら作成す
る。
〇グループワークの成果を
踏まえて小論文を完成させ
る。
○ b.互いに
高め合お
うとして
いる。
振り返りシー
ト
3
(本時) 振り返り
〇相互評価
・協議の上、評価を集約
し、学習活動を振り返る。
○ d.成果を
踏まえ、
評価項目
や基準を
提案でき
る。
答案評価シー
ト
自己評価表
⑤授業案
学習活動(指導上の留意点を含む) 評価の観点
(評価方法)
●活動の見通しを持つ。(5分)(『答案評価シート』を配付し、本時の目標と
活動内容を説明する。その際、提出された小論文の個人名は伏せる。)
●それまでの学習内容を踏まえて評価の観点(小項目)について話し合う。
(10分)(各自の『答案評価シート』に評価の基準とともに記入させる。)
●1人に1枚ずつ配付された他者の小論文を、1枚につき2~3分を目途
に、次々に読み、評価コメントの書き込みをし、評価結果を表にメモす
る。(12分)(他の生徒との重なり、矛盾などがあっても気にせず書き込ま
せる。)
d (答案評価シ
ート)

- 142 -
●グループ評価を班の『答案評価シート』に集約し順位をつける。(13分)
(協議に際しては、傾聴の態度と根拠を示した説明を求める。評価の違いがあ
った場合、違いをしっかり受け止めてまとめさせる。)
●答案評価シートの《自己評価表》等の記入を通じて、本時の学習を振り返
り、小論文学習で得た知識・理解を深める。(10分)
d(自己評価表)
研究実施校:神奈川県立小田原高等学校(全日制)
実 施 日:平成28年9月30日(金)
授業担当者: 吉野 久美 教諭
(2)アクティブ・ラーニングの視点に基づく授業の解説
本単元では、小論文作成から相互評価までの学習のプロセスにおいて、言語活動を適切に位置付け、他
者と協働して学習テーマを掘り下げることにより、一人ひとりの学習を深めることを目ざした。小論文を
書くことが苦手な生徒のために、小論文作成の手順をワークシートで機能的に分解して分かりやすくする
とともに、その段階ごとにグループワークを行うことで、悩みや問題を共有しながら最後まで書き上げる
モチベーションを維持する学習活動とすることができた。【主体的な学び】構想を説明する活動を取り入
れ、班員に質問や助言をもらうことで、よりよい表現を意識し、内容を深めることができた。相互評価に
おいても、評価する立場と評価される立場を同時に体験することにより、客観的かつ広い視野でものを見
ることができるようになった。振り返りシートにおいても、次回作品に向けての意欲や、指針、他者との
交流を通じて得られた気付きを挙げた生徒が多く見られた。【対話的な学び】また、各時間の目標を明示
したことにより、学習のプロセスで強く意識した項目(課題)が、相互評価の項目を考える活動でも生か
された。本事例は単元の3時間目で、「定義を入れよう~『…とは』を効果的に用いよう~」という、よ
り高度な要素を取り入れたが、目標として意識することで作品のレベルが高まり、評価活動の基準を考え
る過程でも再度認識されることとなった。表現者としての視点と、評価者の視点の双方からその効果を考
え、意識的に実践したことが、他者の評価を通じて客観的に再現され、深い学びへと自然と導かれること
となった。【深い学び】
(3)成果と課題
(成果)問題解決において、多くの生徒に主体的に関わろうとする姿勢が見られた。相互評価では、個人
の仕事が不十分であっても、全体として協調して進めることで、まとまった成果や相互補完の効果が得ら
れた。主体的な個人の学びだけでは得られない成果が、対話的な学びによってもたらされることを、今後
も生徒にしっかりと伝えられるようにしていきたい。
(課題)年間指導計画の中に複数回位置付けることにより、継続的な成果を収めていくことが必要であ
る。今回は、少人数で行ったために、まとまった評価結果を発表してクラス全体で共有する活動は行わな
かったが、全体で共有することにより、更に自分たちの協働学習を相対化(客観化)して深めることがで
きるため、次の機会には、クラス規模の生徒数を対象として実践したい。また、英語による論文やサマリ
ーの作成においても、この手法は応用できそうだという指摘があった。他の教科・科目でも幅広く応用す
ることができるように、さらに研究していく必要がある。
(まとめ)小論文作成の過程を探究の過程に見立てれば、課題のテーマ設定や、研究手法の検討、中間報
告等においても、個人ワークとグループワークを交互に使用しながら深める手法は効果があると思われ
る。また、相互評価をグループワークで行う手法は、「探究」活動を、客観的な視点で互いに評価し合う
ことにより【深い学び】へと導いてくれるのではないか。今後、「生徒同士の相互評価」も更に意味を持
つこととなると思う。「グループ・エッセイ」の手法を、いろいろな場面で工夫して活用していきたい。

- 143 -
【実践事例3】
(1)単元の指導計画及び重点を置いた授業展開例
①単元名:地域学習(学年:第3学年)
②単元のねらい(身に付けさせたい力):課題解決力、コミュニケーション能力、価値観の形成
③単元の評価規準
課題設定の力 協調性 思考する力 発表の能力
自分が暮らす(通学し
ている)町の身近な課
題を考えることができ
る。
グループでの話合いを
通じて、課題を共有す
ることができる。
課題についての町の
現状や、解決するた
めの方策を導き出す
ことができる。
話合いで導き出した
「課題の解決方法と
課題が解決した地域
の姿」を他者へ分か
りやすく紹介するこ
とができる。
④単元の指導計画 a:課題設定の力 b:協調性 c:思考する力 d:発表の能力
時・次 学習内容・学習活動 評価の観点
評価規準 評価の方法 a b c d
1
(本時)
課題の設定・解決
①地域の課題を考える。
②藤沢―大船間に新設予定の
新駅について、概要を知
る。
③駅の新設によってどのよう
な課題が解決されるかを考
える。
○ c.課題について、
街の現状や解決す
るための方策を駅
の 新 設 と 関 連 付
け、導き出すこと
ができる。
記述の分析
行動の観察
発表のための
成果物
2
(本時)
発表
各グループごとに、どのよう
な課題が駅の新設によって解
決されるのかを発表する。
○ d.話合いで導き出
した「課題の解決
方法と課題が解決
した地域の姿」を
他者へ分かりやす
く紹介することが
できる。
発表内容
ワークシート
⑤授業案
学習活動(指導上の留意点を含む) 評価の観点
(評価方法)
<5校時>
●個人活動・・・「駅の利点・欠点」、「地域の課題と思うこと」について付
せんにできるだけ多く書き出す。
●グループ活動・・・ワークシートに付せんを貼り、整理する。次に、大判の
地図に新駅の予定地をマークする。最後に、新駅を設置することで、どのよ
うな課題が解決されるのかをグループで考え、発表用のワークシートにまと
める。(教師はグループ内の様子をチェックし、必要に応じて助言を与え
る。)
観察
ワークシート

- 144 -
<6校時>
●特派員タイム・・・グループの1人が別のグループへ行き説明を受ける。
この時、迎え入れるグループは発表の練習を行い、派遣されるメンバーは他の
グループの考えを参考にする。
●発表・・・グループごとに順番に発表する。発表を聞く他の生徒は、気付い
たことや感想をメモする。
研究実施校:神奈川県立深沢高等学校(全日制)
実施日:平成28年11月10日(木)
授業担当者:笠原 志郎 教諭
(2)アクティブ・ラーニングの視点に基づく授業の評価と分析
本単元では地域の課題を新駅開設と結び付けることによって、地域社会に関心を持ち、社会のあるべ
き姿について主体的に考える【主体的な学び】とともに、それらを模索し他者と共有する中で、他者と
の協調を図りながら【対話的な学び】、自らの価値観やものの見方や考え方の形成をすることを目ざし
た。
新駅の概要と大判の地図、そして藤沢市、鎌倉市が抱える代表的な課題を書いたプリントのみの少な
い資料から情報を整理・分析することにより、生徒たちは話し合いながら両市が抱える課題を考え、設
定した。例えば、地図を観察することで「周辺地域の商業施設の不足」、「子育て環境の不足」という
課題が、また、生徒が普段から感じている「周辺地域の渋滞」、「ムクドリの騒々しさ」、「観光客に
よる治安の低下」等の課題が考え出された。
新駅に近い土地に住む生徒や、市外から通う生徒がグループ内に混在し、多様な意見交換がなされる
ことにより、講義形式の授業では得られない情報や考え方の共有が図られ、地域社会への関わりやその
中での自分の在り方を深め、広げることができた。
異なる意見をまとめて発表する内容を決定する過程では、話合いで導き出した「課題の解決方法と課
題が解決した地域の姿」を他者へ分かりやすく紹介することにより、【深い学び】の過程を実現すること
ができた。
(3)成果と課題
(成果)授業後のアンケートでは、「考えたことのない地域の課題を考えることができた」、「自分の
考え付かなかったことを他のグループの発表で気付くことができた」などの回答があり、授業の様子を
合わせて考えると、生徒の考える力を伸ばし、他者と協調し自己の考えを形成する場としての授業の実
践という意味では一定の成果があったと考えられる。
(課題)生徒自らが、市役所の訪問や、新聞や書籍を使った調査を行うことができれば、より実際的で
より多い情報を取り扱うことができたかもしれない。年度が始まる前に綿密な計画を立て、授業時数を
確保する必要がある。また、生徒が最初の二つの個人活動(「駅の利点・欠点」、「地域の課題と思う
ことについて」を付せんに書く)に、それぞれの関連性をうまく見出だせなかったことは反省点である。
短い時間設定の単元では、より情報量や方向性を絞ることに注意するべきであった。

- 145 -
特 別 活 動
1 研究のテーマとねらい
(1)研究のテーマ
特別活動におけるアクティブ・ラーニングの視点を踏まえた指導方法の研究
(2)研究のねらい
特別活動の中の一つである「ホームルーム活動」の目標は、「望ましい人間関係を形成し、集団の一
員としてホームルームや学校におけるよりよい生活づくりに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、
実践的な態度や健全な生活態度を育てる。」となっているが、このことに向けて有効な指導方法の研究
を、テーマに即して行う。
2 実践事例
【事例1】
実施学年:2学年
題材名:「下校中に大地震が起こったら…最も安全な避難経路を考えよう」
(1)ねらい
・防災意識を高め、不測の事態に遭遇しても対処できる力を身に付ける。
・グループによる協議を通じて、お互いの意見をすり合わせ調整する力を育む。
・論理的に状況の分析を行い、適切な解決策を導き出す力を養う。
(2)活動の流れ
学習課題:大地震が下校途中に起こった時、どのような方法で安全に避難を行うか。
「下校して 10 分後、震度7の地震が発生しました。公共交通機関はすべてストップ
しています。この状況下でどのような経路や施設を利用すれば、安全に避難できるで
しょうか。」
(ア)活動1「学習課題を理解し、学習活動の見通しを持つ」
前時の LHRで決定した4つの帰宅方面のグループに分かれ、学習課題を理解する。
(イ)活動2「危険箇所を白地図に書き込む」
各グループに1台ずつ与えられたタブレットで、横浜市がウェブ上で提供する防災地図
「わいわい防災マップ」を参照する。担当地域の白地図に危険箇所を書き込む。
(ウ)活動3「避難に役立ちそうな拠点を白地図に書き込む」
避難に役立つ拠点を選び出し、担当地域の白地図に書き込む。
(エ)活動4「情報を基に安全な避難経路を考え、発表する」
各グループで白地図に記入された情報を基に望ましい避難経路を考え、そう考えた理由やその
工夫について、グループの代表者が発表する。
(オ)活動5「学習内容を振り返る」
本時の学習活動を通して考えたことをまとめる。
(3)展開例(50分)
学習活動 指導上の留意点
(活動1)
・震度7の地震が発生した場合、どのよう
な被害が起こるかを考える。
・本時の課題を捉え、課題解決へ向けた学
習活動の手順を理解する。
○熊本地震で被害を受けた道路や建物の写真を黒板
に掲示することにより、震度7の地震が起きると学
校周辺の道路や建物がどのような状況になるかに
ついて具体的なイメージを持たせる。
○学習活動の趣旨を説明することにより見通しを持
たせる。また、ワークシートを配付して説明するこ
とにより、学習活動の手順を把握させる。
○登下校の方面が同じ生徒でグループを形成するこ
とにより、実際の避難状況に近い場面を設定する。

- 146 -
(活動2)
・災害危険箇所を選び出す。
・タブレットを見ながら、避難に適さない
道路、土砂災害警戒区域を、指定された
マーカーで白地図に書き込む。
○土砂災害警戒区域のチェックボックスをオンにさ
せる。
○縮尺は1/10000 もしくは1/20000 であることを
確認させる。
○机間指導を行い、タブレットの操作を含めた質問に
対応する。
(活動3)
・タブレットを見ながら、避難に役立つ箇
所を選び出す。
・公園、公衆トイレ、一時滞在施設のチェ
ックボックスをオンにする。
・コンビニエンスストアや病院の位置を確
認する。
・それぞれの場所の指定されたシールを白
地図に貼り付ける。
○応急対応マップに表示を切り替えさせる。
○机間指導を行い、機器の操作を含めた質問に対応す
る。
○グーグルマップに切り替えさせる。
○避難経路を考え始めた直後に、グループのメンバー
の一人が骨折していることが判明したという条件
を付け加えることにより、生徒の考えを広げる。
(活動4)
・(活動2)と(活動3)を通じて、最も
安全性の高い地域防災拠点を選定し、そ
こまでの経路を緑のマーカーで白地図
上に書き込む。
・各グループで決定した避難経路につい
て、その経路を考えた理由や避難時の工
夫した点をホワイトボードシートにま
とめる。
・白地図とホワイトボードシートを黒板に
貼り、各方面から1班ずつ発表する。
(活動5)
・各班の発表を聞いた後、授業の振り返り
をワークシートで行う。
○これまでのグループ協議を生かして、一つの結論を
導き出させる。
○発表時間3分を厳守させる。
○グループの発表について、講評を行う。
○本時の学習活動を通して考えたことを、自分の言葉
でまとめさせる。
研究実施校 : 神奈川県立荏田高等学校(全日制)
実 施 日 : 平成 28年 11月 24日(木)
授業担当者 : 石丸 あゆみ 教諭
(4)成果と課題
クラスにおける災害図上訓練(DIG)は初めての試みであったが、学校付近という身近な地域に
隠れた危険箇所が意外と多いことに生徒自身が気付くことができ、状況に応じた避難経路を適切に
選ぶことができていた。また、グループによる学習活動を通じて、互いにコミュニケーションを取
りながら課題解決に努めていたことから、概ねねらいを達成することができたと考えられる。
例)【生徒の発表より】「(避難場所まで)最短で幅の広い道路を選んだ」、「(防災)拠点に早く着
いた方が安全だし、けがをした時にすぐ手当できる。あと、物が落ちてくる心配がない。」
例)【生徒の感想より】「このあたりは家などが密集しており、それらが倒壊したら、ほとんど逃
げ道がなくなることが分かった。」、「自宅の辺りに、土砂崩れの危険のある所がたくさんあっ
て危険な所が多いと感じた。」、「思ったより逃げられる場所が少なくて、危ないなと思った。」、
「(避難場所に行くまでの道のりに)トイレや病院が少ない。」
一方で、授業を進める上での課題も見つかった。タブレットに不具合が生じ、生徒はスマートフ
ォンを使いながら手分けして地図を検索するなど臨機応変に対応していたが、このような事態を想
定し、紙の防災マップを準備しておくのも有効である。今回のようなアクティブ・ラーニングの視
点を踏まえて計画した学習活動をより効果的に行うには、前もって具体的な手順や時間配分を生徒
の実態に応じて綿密に考えるとともに、学習活動の進行についての指示をクラス全体に的確に伝え
ることの重要性を確認することができた。

- 147 -
○授業の様子
タブレットやスマートフォンで防災地図を検索 得られた情報を白地図に書き込む様子
避難経路を考えた理由や工夫した点などを 発表で用いた白地図
まとめたホワイトボードシート
○ワークシート(抜粋)
■ 本時の流れ
① 「わいわい防災マップ」を開くと、画面左側に凡例が表示されるので、凡例の中から【避難に適さない
道路:幅4m、土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊】のみチェックボックスをオンにする。タブレッ
トの表示を見て、自分たちの白地図にマーカーで書き込もう。※縮尺は1/20000 もしくは1/
10000で見る。
タブレット操作
【地震タイプの切替】⇒【南海トラフ巨大地震】⇒【表示地図の切替】⇒【災害危険マップ】⇒【防災関連】
避難に適さない道路:幅4m (画面では赤で表示) ⇒ 蛍光ピンク色
土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊(画面では水色の網掛けで表示) ⇒ 蛍光ブルー色
② 避難する時に役立つと思われる個所【公園、公衆トイレ、地域防災拠点】のみチェックボックスをオン
にする。また、【コンビニ、病院】をグーグルマップで検索する。それらを白地図上にシールやマーカ
ーで書き込もう。
11/24 6校時LHR
下校中に大地震が起こったら … 最も安全な避難経路を考えよう!

- 148 -
タブレット操作
【表示地図の切替】⇒【応急対応マップ】⇒【防災関連】
地域防災拠点 ⇒ 蛍光オレンジ色のマーカー
公園 ⇒ 緑色のシール
公衆トイレ ⇒ 青色のシール
コンビニ ⇒ 黄色のシール
病院 ⇒ 赤色のシール
③ 与えられた地図の中で、☆印のついた地点から一番安全性の高い地域防災拠点を選ぼう!また、そこへ
行くまでの避難経路を蛍光グリーン色のマーカーで書き込もう。
④ 発表に備えて、避難経路を考える上で工夫した点・理由などをホワイトボードシートに箇条書きにする。
※書く要素は、1.工夫した点 2.その理由 3.課題を通じて感じたこと
⑤ リーダーは、白地図とホワイトボードシートを黒板に掲示し、1グループ3分で発表する。
⑥ 発表を聞いて最も参考になると思ったグループを、理由とともに挙げよう。
■本時のアンケート
今回の授業について、当てはまるものに、○をつけてください。
① 積極的に意見を言ったり、話合いに参加したりできましたか。
できた だいたいできた あまりできなかった
② 自分で考えたり、理解を深めたりすることができましたか。
できた だいたいできた あまりできなかった
③ 他の生徒の意見や考えを聞いて、自分の考えが広がりましたか。
そう思う だいたいそう思う あまり思わない
感想
グループ【 】 番号【 】 氏名【 】
1.工夫した点
2.その理由
3.課題を通じて感じたこと
・グループ
・理由

- 149 -
【事例2】
実施学年:3学年
題材名:「校内探検による防災学習」
(1)ねらい
・校内の、地震が発生した場合の危険箇所や地震への対策について調査する活動を通じて、防災に関
する意識を高め、身の安全を確保する方法を考えさせる。
・他者と協力して物事を成し遂げる力を育む。
・物理の授業との関係を示し、双方の学習内容を立体的に捉えさせる。
(2)活動の流れ
学習課題:震度7の地震が発生した場合の校内の危険な箇所や地震対策について調査し、地震か
ら身を守る手段を考える。
(ア)活動1「演示実験を見る」
落下物や転倒物の危険性について具体的なイメージを持つ。
(イ)活動2「学習課題を理解し、学習活動の見通しを持つ」
校内の調査や発表等について、流れや内容を理解する。
(ウ)活動3「5名グループを形成して校内を探検、調査する」
タブレットで撮影しながら、危険箇所や地震への対策について調査する。
(エ)活動4「グループごとに調査内容をまとめ、発表する」
A4用紙にまとめ、教材提示装置を使って発表する。
(オ)活動5「学習内容を振り返る」
本時の学習活動を通して考えたことをまとめる。
(3)展開例(50分)
学習活動 指導上の留意点
(活動1)
・「物体の落下実験」、「構造物の転倒」について
の演示実験を見る。(代表の生徒は、落下物が
1kgであることを確認する。)
演示実験
① 質量 1.0kgの球を 2.5mの高さから
プラスチック板に落下させる。
② 構造物をベニヤ板の上に置き、ベニヤ
板を横に振動させ構造物を転倒させる。
○本時のねらいを示すことにより、学習活
動の見通しを持たせる。
○物理の授業で学習した、物体が落下した
時の力積(衝撃)と、物体が転倒するメ
カニズムに関連付けて説明や演示実験
を行うことにより、落下物や転倒物の危
険性について具体的なイメージを持たせ
る。
(活動2)
・活動の手順、発表内容や撮影のポイントにつ
いて確認する。
発表内容
① 写真の説明
② その写真を取り上げた理由
③ 対策(もしも写真の場所で地震が起き
たらどうするか。予防できることは
何か。)
○発表内容(①~③)を事前に伝えること
により、発表を意識しながら撮影できる
ようにする。
発問
震度7の地震が起きたとき、校内にはどのような危険があるだろうか。また、
被害を少なくするためにできることは何だろうか。

- 150 -
研究実施校 : 神奈川県立伊志田高等学校(全日制)
実 施 日 : 平成 28年 11月 14日(月)
授業担当者 : 虻川 純平 教諭
(参考文献)
総務省消防庁 防災 48より P34「8.学校を探検してみよう」
http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/main/bunrui.html
(4)成果と課題
今回は、3年理系クラスでの実施であったため、生徒は事前に「物体が落下したときの力積(衝
撃)及び物体が転倒するメカニズム」を学んでいる。このことにより、地震発生時の落下物や転倒
物の危険性を物理の視点で考えさせることができた。また、物理で学んだことを防災教育に取り入
れることで、教科横断的な視点から深い学びへとつなげることができた。
校内の調査では、グループごとに興味を持って危険箇所の撮影に取り組んでいた。日頃から活用
している教室や施設を、落下や転倒の危険性という視点を持って観察することにより、生徒は「昔
に作られた学校のためか、老朽化している場所が多かった。」、「トレーニング室などにはバーベルな
どがあり、落下の仕方によっては命の危険がある」ことに気付くことができた。また、「皆で話し合
うことにより、防災の意識を高めることができた。」、「こういう防災訓練は今までやったことがなか
った。皆で話をし、写真を撮ることが楽しかった。」など、活動を通じて防災の意識を高めることが
できた。発表においては、写真データを交えながら活動内容を分かりやすく伝えることができたグ
ループもあった。これらのことから、今回の学習活動は、主体的・対話的で深い学びの実現に有効
であったと考えられる。
一方、「パソコンの操作が難しかった。」という感想もあるように、タブレット端末の操作に手間
取っている生徒が見られた。スマートフォンの普及等の理由で ICT機器の操作に慣れているのでは
ないかと考えていたが、キーボード、ファイル操作に関しては苦手と感じる生徒が多かった。今回
の授業だけでなく ICT機器を活用する場合には、十分な事前指導と不具合への対応策を考えておく
ことが大切である。
(活動3)
・グループごとに、校内の指定されたルートを
回り、危険な箇所や地震対策が施されている
箇所をタブレットで撮影する。(図書室、3年
8組教室、化学教室、情報機器室、昇降口、
トレーニング室、自転車置き場、校庭仮設ト
イレ付近。)
○教室に戻る時間を明確にし、厳守させる。
(活動4)
・グループで話し合い、A4用紙に発表事項を
まとめる。
・グループの代表者が教材提示装置でA4用紙、
撮影データを投影し、2分以内で発表する。
○発表資料は簡潔に作成するよう促すこと
により、時間内に資料を作成できるよう
にする。
(活動5)
・学習内容を振り返る。
○本時の学習活動を通して考えたことを、
自分の言葉でまとめさせる。

- 151 -
生 徒 指 導
1 研究のテーマとねらい
(1)研究のテーマ
「SNSトラブルへの理解と学校の関わり方」
(2)研究のねらい
ICT 機器のうち 2015 年末の普及状況を見ると、携帯電話及び PHS の世帯普及率は 95.8%、その内、ス
マートフォンの普及率は 72.0%に上る(総務省「平成 28 年度版情報通信白書」より)。高校生は、音楽
を聴く、ゲームをする、学習のツールといった利用目的の他、コミュニケーションツールとしてスマー
トフォンを使っている。
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、人と人とをつなぐ、コミュニケーションの一手
段としてこの 10 年間で急速に社会的に認知されてきた。この媒体は不特定多数の人間とのコミュニケー
ションを可能にすることが特徴である。また、本委員会のアンケート調査の結果からも高校生は友人と
の交際や限られたネットワーク内での交際においても SNS を利用しているのが現状である。子どものコ
ミュニケーション能力の発達不足や ICT 機器への過度の依存という問題はあるとしても、最近の高校生
が日常生活を送る上で SNS の利用は必要不可欠になっている。しかし、SNS の利用の広がりの裏で、トラ
ブルに巻き込まれている高校生がいる。そのトラブルは、友人間をはじめとした身近な人間関係のトラ
ブルに留まらず、社会的な問題、ときに犯罪に関わるものもあり、我々教職員は具体的な対応策を検討
していかなければならない。
SNS トラブルが広がる中でも、多くの保護者は子どもの安全確認や連絡手段としての利便性のために、
スマートフォンを持たせている。学校は生徒の ICT 活用能力等を高めるために情報教育を推進している
が、急速に拡大する SNSトラブルに対しては、学校が十分な対応を行っていく必要がある。
「急速に発展する SNS と生徒の関わり、教職員と生徒の関わり及び教職員と SNS の関わりを整理し、
どのような指導を行えば、生徒を取り巻く SNS に起因する問題の解決を促し充実した生活を送ることが
できるか」、「SNS の適切な使い方を知り、それを活用することで将来の進路希望実現に資する」という
目的で本研究テーマを設定した。
2 SNSに関する基礎知識
ここでは、主要な SNSの特徴や長所、短所などがひと目で把握できるよう、簡潔にまとめた。
(1)LINE(ライン)
特徴:韓国の IT企業の子会社 LINEが運営している SNS。スタンプ等を用いてコミュニケーションを取
ることができる。アジア圏を中心として利用者が増加しているが、日本でも 2010年代初頭にス
マートフォンが普及してから、爆発的に流行している。
長所:メッセージのやり取りをチャットのように行うことができる。ネット回線を用いて、無料で通話
をすることができる。更にグループ機能を使えば、複数人と同時に連絡を取ることもできる。
短所:情報に対して「返信しなければ」等、心理的影響があるため、アカウントを維持することの負担
が大きく、「既読無視」等のトラブルを招きやすい。また、個人情報を登録する必要がある。
(2)Twitter(ツイッター)
特徴:アメリカの企業 Twitter,Inc.が運営している SNS。登録しているメンバー同士で「ツイート」と
呼ばれる短文を共有することが特徴。
長所:情報収集や友人とのやり取りなど、汎用性の高い使い方ができる。また、情報発信しなくても使
えるので、継続して使用することに対する負担が非常に軽い。
短所:批判的書き込みが急増し、閲覧・管理機能が損なわれる状態を「炎上」という。不特定多数の人
間がツイートを見る可能性があり、使い方次第では「炎上」や個人情報漏洩の危険性がある。

- 152 -
(3)Facebook(フェイスブック)
特徴:アメリカの企業 Facebook,Inc.が運営している SNS。元々は学生間の交流を促進するために開発
されたが、それが全世界に広がった。実名登録を原則としているのが大きな特徴。
長所:実名登録が原則のため、特定の人物の検索が比較的容易である。「グループ」や「イベント」な
どといった機能も充実している。
短所:不特定多数の人間が投稿を見る可能性があり、使い方次第では「炎上」や個人情報漏洩の危険性
がある。
(4)Instagram(インスタグラム)
特徴:アメリカの企業 Facebook,Inc.が開発した SNS。Facebookを利用して、ユーザー間で写真の共有
を行うことを目的としている。
長所:写真の投稿が簡単にできる。
短所:写真を共有することを目的としているため、メッセージのやり取りには向いていない。個人情報
漏洩の危険性がある。
(5)Google+(グーグルプラス)
特徴:アメリカの多国籍企業である Googleが運営している SNS。実名登録を原則としているのが大き
な特徴である。
長所:Facebookと Twitterの利点を合わせるようにして開発されている。
短所:不特定多数の人間が投稿を見る可能性があり、使い方次第では「炎上」や個人情報漏洩の危険性
がある。
3 SNSに関するアンケート結果
本委員会では、まず生徒が SNS をどのように利用しているのかを具体的に調査する必要があると判断
し、無作為に抽出した県内の高等学校の生徒による独自のアンケート調査を行った。以下がその結果で
ある。(回答者数:796名)
97%
78%
32%
11% 8% 3% 3%
Q1:主要なSNSの利用率
LINE Twitter Instagram Google+ Facebook その他 利用していない
91%
66%
42%
19%
12% 7%
2%
1 2 3 4 5 6 7
Q2:SNSの利用目的
1.家族、友人との連絡、情報共有
2.情報収集
3.交友関係を広げるため
4.みんなが利用しているから
5.情報発信
6.日記代わりとして
7.その他
14%
86%
Q3:SNSのトラブル
経験の有無
ある
ない

- 153 -
今回の調査では、高校生のほとんどが LINE、
Twitter を利用していることが分かる。そのため、
トラブルの多くはこの二つの SNSから生まれてい
るものと推測することができる。特に SNSを「交
友関係を広げるため」に利用している生徒に対し
ては、保護者の目の及ばないところで犯罪に巻き
込まれる可能性も否定できないため、より一層の
注意が必要であろう。
また、Q4の結果を見ると、「トラブルを先生
に相談をしている生徒」が 11%に留まっている。更に、「相談していない」が 29%となっている。
Q4と Q7に「カウンセラーのような専門の人に相談した」という選択肢があったが、どちらも0%であ
った。
このことから学校で SNS によるトラブルを早期発見し、対応するためには、相談体制の強化を図るこ
とと、生徒との日々のコミュニケーションを緊密に取ることが重要であると考える。
(注)Q1の主な SNS の利用率において「Google+」(グーグルプラス)を 11%の生徒が回答しているが、
「Google」を使って検索することと勘違いをしている生徒が少なからずいると思われる。
16%
42% 11%
2%
29%
Q4 : トラブルの相談相手
家族に相談した
友達に相談した
先生に相談した
ネット上のサービスなど
で相談した 相談していない
61% 12%
27%
Q5 : SNSトラブルを解決
することはできたか
解決した
解決しなかった
分からない
32%
68%
Q6 : 友人のSNSトラブルを見
たことがあるか
トラブルを見た
ことがある
見たことはない
6%
19% 7%
1%
67%
Q7 : 友達のトラブルを誰か
に相談したか
家族に相談した
友達に相談した
先生に相談した
ネット上のサービスな
どで相談した 相談していない
40%
6%
54%
Q8 : 友達のトラブルは解決
できたか
解決した
解決しなかった
分からない

- 154 -
4 事例検討
代表的な SNSトラブルの事例について検討を加えた。いじめ、犯罪、なりすまし、不適切な投稿に分類
し、気付き、対応及び指導上困難な点についてまとめ、考察を加えた。
【番号:1】【事例:いじめ】
キーワード ・LINE ・中傷
気付き
・休みがちになった生徒Aの家庭に担任が連絡した際、事実と異なるAの行動や
中傷が LINEに書き込まれ、書き込んだ生徒に「事実と異なる」と抗議すると、内
容がエスカレートしていき、学校に行きづらくなっていたことが分かった。
対 応
・Aに書き込まれた LINEの内容を資料(証拠)として提出してもらった。
・加害生徒Bに対し、印刷した資料を提示し、目的、経緯などの確認を行った。
Bは、悪意があったことを認めた。Bの保護者に事案の概要説明を行ったが、
口頭による説明では「たいしたことではない」との認識であったが、資料を見
せたところ認識が変わった。
・管理職による説諭等を行った。担任、生徒支援グループが、B及び保護者との
面会の場を設定し、A及び保護者に対して本件について謝罪や再度書き込まな
いことを確約させた。
指導上の困難な点
(注意点)
・LINEの内容は、生徒から情報提供がないと確認が難しい。
・特に絵や写真が LINEの内容に含まれると、口頭で説明するのは難しく、内容の
雰囲気が伝えにくい。
考 察
・LINEの内容を印刷やスクリーンショット等で保存しておきたい。軽く考えてい
た加害生徒の保護者も、実物を見ることにより、被害生徒の気持ちを理解しや
すくなる。
・情報提供してくれた生徒への配慮が必要である。
【番号:2】【事例:JKビジネス】
キーワード ・Twitter ・JKビジネス ・DM(ダイレクトメッセージ)
気付き
・女子生徒Cの友人である女子生徒Dが「Cが JK撮影会に参加をしている。Cの
ことが心配だ」と話した。
・Cに確認するとCが JK撮影会をしていることを認めた。
対 応
・性犯罪に巻き込まれる可能性があること等を注意したが、Cは JK撮影会が好き
で、やめる気はないと言った。
・Cの保護者に JK撮影会のことを伝えた。家族の説得でCは JK撮影会をやめた。
指導上の困難な点
(注意点)
・JK撮影会の被写体として働く場合、保護者の同意が必要ない場合が多い。撮影
会社に登録するか、SNS上で撮影者を募り、DM(ダイレクトメッセージ)で直接
撮影者と連絡を取ることもある。そのため保護者が把握しづらい。
・利害関係が一致しているため被害者意識がない。芸能界を目ざし、JKビジネス
にはまっていく生徒もいる。
・虚偽の生年月日を登録して働くこともある。
・JKビジネス自体を規制する法はなく、取締りが難しい。
考 察
・学校は、保護者に対して子どもの行動・持ち物などの変化に気を配るよう注意喚
起していく必要がある。
・背景には家庭の無関心、貧困、虐待が潜んでいる場合もある。この 20年ほどで
SNSが発達したことにより、身近な人とのコミュニケーションが希薄になってき
ている。その中で自己承認欲求を身近な人ではなく、他者に求める傾向が強くな
り、「かわいい」、「きれい」と言われることで自己承認欲求を満たしているよ
うに感じられる。

- 155 -
【番号:3】【事例:SNS経由でワンクリック詐欺・アカウント乗っ取り】
キーワード ・SNSで送られてきた URL ・SNSアカウント乗っ取り
・ワンクリック詐欺 ・高額請求
気付き
・生徒Eが担任に相談した。SNS で生徒Fから送られてきたアダルトサイトの URL
をクリックしたところ高額な料金を請求された。Eが請求元に電話連絡をすると
「所定の額を入金しないと、学校に電話をする」と言われたが、額が大きく自分
では払えない。アダルトサイトなので親に相談できないという。
対 応
・それはワンクリック詐欺であり、そのような電話又はメールが来たら無視するよ
うにとEに伝えた。また、Fに事実確認をしたところ、そのような URLを送った
覚えはなく、Fの SNSのアカウントが乗っ取られていたことと、他の生徒にも同
様の URLが送られているということが分かった。そのような URLをクリックしな
いようにと全生徒にも呼びかけた。
指導上の困難な点
(注意点)
・周りに相談する人がおらず、不安と焦りから、生徒自らが連絡してしまい、トラ
ブルに巻き込まれる可能性が高くなる。
・有害サイトを見たという事実を周りに知られたくないという気持ちと、周りの大
人に迷惑をかけたくないという気持ちから、被害生徒は一人で解決しようと抱え
込んでしまう。
・信頼している人からのメッセージだと、悪質な詐欺メッセージだと疑わずに URL
をクリックしてしまう傾向がある。
考 察
・一人で抱え込まないように、信頼関係を築くことが大切である。学校は「困った
ときには親や先生に必ず相談すること」を繰り返し発信していく必要がある。
・「誤作動で登録の方はサポートセンターにお電話下さい」というメールや「払わ
ない場合は、弁護士発行請求書、債務回収業者への委託、少額訴訟をする」など
という警告は、個人情報を収集するためである。
・アカウントを乗っ取られないためにパスワードをこまめに変える必要がある。
・Eによると情報の授業で教職員から、「SNS トラブルで困ったことがあったら大
人に相談するように、と何度も言われたのを思い出した。」という。
【番号:4】【事例:SNS上でのなりすまし】
キーワード ・Twitter ・なりすまし
気付き
・生徒Gの Twitterの IDによく似た IDを使い、Gのふりをしてツイートしている
者がいるという連絡をGから受けた。
・Gはまず警察に相談し、その後教職員へ相談をしてきた。
対 応
・ツイートの内容には実際に起きたことを茶化している記述もあり、加害者は身近
にいる生徒の可能性が高い。
・G及び保護者が警察に相談したが、Gに危険が及ぶ内容ではなく、さらに名誉毀
損に当たる内容もなく、学校で実際に起きたことがツイートされていることか
ら、まず学校に相談してみるようにアドバイスがあった。
・Twitter本社へ該当ページを閉鎖する手続きの支援を行った。
・全校集会で SNSの使用に関する話を行った。
指導上の困難な点
(注意点)
・加害者の特定が難しい。
・Twitterのページ閉鎖依頼方法が複雑で難しい。
・抑止の方法が限られる。
考 察
・些細なことでも生徒から情報提供を受けられる信頼関係の構築が必要である。
・SNSでも現実世界でも守るべきルールやマナーは同じであることを理解させる。
・ネット上へ流失した内容を削除するのは大変困難であることを理解させる。

- 156 -
【番号:5】【事例:Twitterへの喫煙・飲酒画像の投稿】
キーワード ・Twitter ・投稿 ・飲酒 ・喫煙
気付き ・外部から学校に、本校の生徒と思われる Twitter上に飲酒及び喫煙している写
真が掲載されていると連絡があった。
対 応
・アカウントを教えてもらい、学校が前後の画像などから確認したところ、男子
生徒Hであることが分かった。
・Hに確認したところ、Hが認めたため、特別指導を実施した。
・投稿を削除させた。
指導上の困難な点
(注意点)
・外部からの情報提供に頼ることが多い。
・アカウントを教えてもらい、実際の投稿を見て、前後の画像などから生徒を特
定しないと対応できない難しさがある。
考 察 ・投稿がきっかけになり、「拡散」、「炎上」につながっていく可能性もある。
【番号:6】【事例:不適切な投稿】
キーワード ・Twitter ・投稿 ・拡散 ・炎上
気付き
・外部から学校に対し、「校内の映像が出回っている」と指摘を受けた。
・ある生徒Iが校内の様子を動画に撮り、不用意に投稿したことがきっかけであ
った。
対 応
・Iに投稿を削除させた。
・全生徒にこれ以上ツイートしないように指導した。
・教職員が気付いたときには、すでに他者により拡散されていた。
指導上の困難な点
(注意点)
・アップした動画、画像、ツイートなどが他者によりネット上に拡散されると完
全に削除する方法はない。
考 察 ・SNSに投稿することの危険性を発信し続け、理解させるしかない。
・投稿がきっかけになり、「拡散」「炎上」につながっていく可能性もある。
5 対応についてのまとめ
SNS による問題行動・トラブルは、教職員が不適切な画像や書込み等について確認できた時には投稿内
容が拡散していたり、トラブルがより深刻な状況になっていたりすることもある。
不適切な投稿をした生徒には削除をさせるが、内容によっては運営会社に削除を要請することも必要
になる。学校外での人間関係でトラブルになっている場合、学校や教職員だけで対応することには限界
があり、警察等の関係機関との連携が不可欠になる。
特にアダルトサイトに起因してのワンクリック詐欺や架空請求に対しては、生徒は保護者に知られた
くないという思いから「自分で解決しなければ」となり、誰にも相談せず深刻な状況に陥る危険性があ
る。学校は日ごろから、生徒に対して詐欺の形態、対処法を周知していくとともに、「困ったときには
相談すること」を徹底する必要がある。また、消費生活センターなど公的な外部機関、相談機関の紹介
も必要である。
SNS トラブルについて教職員に相談した生徒には、精神面の支援や安心して学校生活を過ごせるように、
十分な配慮と丁寧かつ慎重な対応を継続的に行うことが大切である。教職員は日常より生徒との信頼関
係を築き、生徒が相談しやすい人間関係を構築することも重要である。
SNS は新しいコミュニケーションの媒体として今後も発展、進化していくことが予想される。生徒ばか
りでなく教職員も SNS の特性を理解し、使用を規制するばかりでなく、意図せずトラブルに巻き込まれ
ることのないように上手に使用する方法を伝えることも重要となる。

- 157 -
6 SNSトラブルの背景と未然防止のための方策
これらの事例検討を通して SNS トラブルの背景には直接的コミュニケーション不足とネットリテラシ
ーの不足があることに気付いた。それらを踏まえ、本委員会では SNS トラブルを未然に防止するための
方策について検討した。
(1) SNSトラブルの背景
ア 直接的コミュニケーションの不足
SNS 上の人間関係トラブルの一因に、言語運用能力の未発達を挙げることができる。理解力や表現力が
不十分な状態で相手の顔が見えない SNS で会話をすることは、誤解を生む表現や勝手な解釈を招きやす
く、それが人間関係トラブルにつながるのではないかと考えられる。
また、JK ビジネスなどの SNS を介したトラブルは、生徒の過度な自己承認欲求が誘発しているとも言
えるのではないか。SNS は「いいね!」という言葉に代表される他者からの好感的な反応が人々の気持ち
を満たしてくれる。コミュニケーション不足により家庭や社会から孤立している子どもは、自己承認欲
求を SNS 上の他者に求めやすく、それが JK ビジネスなどのトラブルにつながる可能性があるのではない
かと考えられる。
これらの現象の背景には、社会全体の直接的コミュニケーション不足があると考えられる。言語運用
能力や自己承認欲求というものは、家庭や、学校、地域社会における直接的コミュニケーションの中で
育まれるものである。しかし、便利さと速さを追い求めた結果、直接的コミュニケーションの機会が減
少し、子どもたちはそれらを十分に身に付けることができずにいると考えられる。
イ インターネットリテラシーの不足
インターネットリテラシーの不足も SNS トラブルに関係していると考えられる。インターネットリテ
ラシーとはインターネットを利用して必要な情報を取り出したり、その情報の信憑性を判断したり、ま
た、インターネット絡みのトラブルに巻き込まれないよう自衛できる能力などのことである。SNS は匿名
利用であったり、相手の顔が見えなかったりということから判断力が鈍り、迷惑行為ともとれる投稿を
信じたり、他者の写真や情報を無断で安易に投稿したりしてしまうのではないだろうか。また、ワンク
リック詐欺やアカウント乗っ取りなどの事例からセキュリティ意識が不十分であることもうかがえる。
ネットリテラシーという言葉が世の中に認知されて久しいが、未だ SNS トラブルが起き続けていること
を考えると、知識が行動につながっていないということが言えるのではないかと思われる。
(2) SNSトラブルの未然防止に向けた方策
ア 直接的コミュニケーションをとることのできる場を増やす
生徒の言語運用能力や自己承認欲求を満たすためには、授業や学校行事の中で多くの人と直接的コミュ
ニケーションを取る機会を増やすことが有効であると考える。学校外から様々な世代、様々な国籍の人
を招いて交流したり、授業で自己表現活動を取り入れて仲間から承認、評価される場を設けたりするこ
とは、生徒の成長に有益であるとともに、SNS トラブルの未然防止につながると考える。そのためには、
日ごろより家庭、学校、学校外の機関や近隣住民が連携して、組織的に子どもの成長を見守ることが必
要である。
イ ネットリテラシー教育
SNS をはじめとするインターネットの正しい利用方法だけでなく、SNS の使い方を間違えれば、誰でも
SNS トラブルの被害者にも加害者にもなり得るということを、事例をもって分かりやすく生徒に伝えてい

- 158 -
く必要がある。また、生徒を SNS トラブルから守るためには、教職員や保護者も積極的にネットリテラ
シーの知識を身に付けるべきである。実際、生徒の方が大人よりも SNS を使う頻度が高く、知識も豊富
である。平成 27 年に行われた神奈川県教育委員会主催「高校生による SNS 講座」のように、大人が生徒
から SNS について教わったり、ともに正しい SNS の利用方法について考えたりする場もネットリテラシ
ーの浸透のためには有効であると考える。
SNS トラブルは他の問題行動より気付きにくい側面がある。更に気付いたときには深刻化していること
もある。教職員は授業だけでなく集会等の機会の度に SNS の危険性を訴えていくことが必要ではないだ
ろうか。
ウ 教職員が生徒、保護者と信頼関係を築き、アンテナを高く保つ
SNS トラブルは表面化しにくいため、教職員が気付くまでに時間がかかることがある。早期にトラブル
を発見するためには生徒とのコミュニケーション、そして生徒との信頼関係の構築が重要となってくる。
日頃から、生徒とコミュニケーションを取っていれば、生徒の気持ちや些細な変化にも気付くことがで
きるだろうし、トラブルに巻き込まれたときに自ら相談してくるだろう。また、生徒と教職員の間に信
頼関係があれば、SNS トラブルに巻き込まれた生徒がいるということを他の生徒が教職員に情報提供し、
早期発見につながることもあると考える。当然、保護者との信頼関係も必要となってくる。保護者と学
校の間に信頼関係があれば、「生徒のために」という共通した目的に向かって保護者と協働することも
可能になる。
そして問題を解決するためには、学校全体で問題を認識し、警察や通信会社、諸専門機関と連携し、
組織的に対応することが必要となってくる。また、変化し続ける情報化社会と生徒を取り巻く環境に対
応すべく、教職員はアンテナを高く保ち、SNS に関して、また諸専門機関との連携について知識を深める
ことも重要であると考える。
7 終わりに
本委員会が行ったアンケート調査において SNS トラブルの相談相手に「先生」と回答した生徒が少な
いことから、問題が表面化しづらいこと、また、事例検討より表面化したときには問題解決が難しい複
雑な状況になっている可能性もあることが分かった。そのため、学校が SNS トラブルを早期発見に尽力
することが重要であるとともに、教職員も SNS に関する知識を持ち、学校全体で対応するべき問題であ
ることを認識しなければならない。SNS の危険性を繰り返し発信するなどトラブルの未然防止のための啓
発活動が重要である。
生徒指導及び生徒支援で最も重要なのは「気付き」、「対応」、「未然防止」である。生徒は SNS を
通して、書込みに対する過敏な反応やいじめといった生徒の学校生活を脅かす行為、更に詐欺・JK ビジ
ネスといった犯罪に巻き込まれる可能性と常に隣り合わせである。生徒の変化に「気付く」ためには普
段からの生徒とのコミュニケーションも大事である。“教職員”といっても担任、教科担当、養護教諭
等様々な立場がある。立場により生徒とのコミュニケーションの取り方は異なるがそれぞれのアプロー
チで生徒との信頼関係を日頃から築いておくことが気付きへの第一歩となる。そして問題が発生した際
の「対応」では、問題の背景にある家庭環境の変化や地域社会とのつながりなど社会的要因も考慮しな
ければならない。また、問題を「未然に防ぐ」ための教育や指導及び啓発活動も忘れてはならない重要
な事項である。SNS は今後も発展・進化していくことが予想される。SNS と上手に付き合うための知識を
身に付けさせなければならない。
生徒指導及び生徒支援に必要なことは、生徒と教職員の信頼関係である。そのためには生徒の些細な
変化に気付くことができるアンテナを日頃から高く保つことが必要である。生徒指導及び生徒支援は気
付きから始まる。気付きがあるから支援に進むことができるのである。しかし残念ながら生徒の変化に
気付けないこともある。それでも保護者、関係機関と連携し学校全体で行動することで、気付く可能性
は高くなるはずである。生徒指導及び生徒支援に関わる問題はその時々において事例が異なり、事例に
応じた対応をその都度考え行動しているのが実情であるが、SNS で考えられる問題の事例を挙げ対応例の
研究も行った。この研究成果を生徒に合った指導を考えるための参考資料として活用していただきたい。

- 159 -
人 権 教 育
1 研究のテーマとねらい
(1)研究のテーマ
参加型学習教材「人権学習ワークシート集」の作成に向けた授業展開例の考案とその実践を通し、授
業やホームルーム活動等での活用を目ざした教材の開発。
(2)研究のねらい
一人ひとりの児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、「自分の
大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具
体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにする
ことが、人権教育の目標である。
教育課程研究会研究推進委員会では、生徒が「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」が
できるようになり、それが具体的な態度や行動に現れるような指導、すなわち、「人権感覚を十分に身
に付けるための指導」の充実を図ることをねらいとし、教師が教育活動の様々な場面において、積極的
な人権教育の展開を可能とするための資料集及び手引きの作成を目ざした。
2 実践事例
(1)授業展開例
① 科目名:「コミュニケーション英語Ⅰ」(学年:1年)
② ねらい
障害者の人権問題では、障害者が社会との緊密なつながりを持つことが大きな目標だと考えられる。
そのため、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」
が施行されるなど、法的な改善は進んではいるが、目標達成のためには、私たち一人ひとりが障害に対す
る先入観にとらわれることなく、相手の状況や場面、心情に応じた配慮や支援について考える力を養い、
より具体的なサポートをすることが大切である。ここではマーティン・ピストリウスさんが自身の動か
ない体に閉じ込められたまま13年間過ごしていた中で、一人のセラピストが彼を注意深く見ていること
によって、他の誰も気付くことができなかった「彼に意識がある」ことに気付き、それが社会復帰の第
一歩となったことを理解し、他者を思いやり、具体的な支援を行おうとする意欲と態度を育みたい。
世の中には様々な障害がある人がいることを学び、目に見える状況だけに気を配るのではなく、その
人たちが目に見えない部分で困っていることに気付き、具体的な支援ができる意欲と態度を持てるよう
にする。
「コミュニケーション英語Ⅰ」の「英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を
育成するとともに、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする基礎的な能力を養う。」とい
う目標に則り、マーティン・ピストリウスさんが装置を通じて発する英語を聞き、相手の話に耳を傾け、
その意見を尊重するというコミュニケーションの大切さを学ぶ機会としたい。
(2)ワークシート
ワークシート:「障害者の人権について」(教育課程研究会研究推進委員会作成)
動画:「誰も知らなかったこと-私の心はどの様にしてこの世に復活したのか?」マーティン・ピス
トリウス(TEDウェブサイト)

- 160 -
(3)授業実践例
学習活動 指導上の留意点
1 ワーク1 (10分)
①から③のキーワードから障害の種類を考
える。
2 ワーク2 (5分)
ピストリウスさんの言葉から彼にどのよ
うな障害があり、どのような支援を必要と
しているかを考える。
3 ワーク3 (25分)
ピストリウスさんのプレゼンテーション
の映像を見て、問いに答えながら、彼と周
りの人々の状況や関わり方を知り、彼の社
会復帰の過程を考え、グループで話し合
う。
4 ワーク4 (10分)
障害のある人たちが、障害のない人と同じ
ように社会とつながるために、自分たちには
どのようなことができるかをグループで話し
合い、意見をまとめる。
○ 様々な障害について知り、具体的にどのようなこ
とで困っているのかを学ぶ。障害に付けられてい
る名前は自分たちと区別をするものではなく、支
援のヒントとなるものであることを強調する。
○ 生徒や家族に当事者がいる可能性も踏まえ、授業
を展開する。
○ ワーク1の考え方を基本に文章からピストリウス
さんがどのような状態にあるかを考えることを通
して、障害者それぞれの困難を理解し、支援の方
法に気付くよう促す。
○ 映像の中には難しい表現も含まれるため、教師は
ピストリウスさんがどのように意識を取り戻した
かなど、具体的に映像を見る上での着眼点を示し
て、生徒が内容を理解しやすいように配慮する。
○ 障害者が、社会とのつながりを持つにはどうした
らいいかを考えるよう促す。この時グループ同士
で意見を交換させるなどして、自分たちの考えだ
けでなく他者の考えも取り入れ、生徒が広い視野
を持てるよう配慮する。
研究実施校:神奈川県立金井高等学校(全日制)
実 施 日 :平成28年11月15日(火)
授業担当者 : 河野 武二 教諭
(4)生徒による授業アンケートの集計結果
①質問項目
1.授業のねらい(この時間に何を身に付けなければならないか)を理解し、見通しを持って授業を受
けることができましたか。
2.授業の中で積極的に意見を言ったり、話合いに参加することができましたか。
3.授業の中で、自分で考えたり理解を深めたりすることができましたか。
4.授業の中で他の生徒の意見や考えを聞いて、自分の考えが広がったと思いますか。
5.授業のねらい(この時間に何を身に付けなければならないか)が達成できましたか。
6.授業の最後に振り返りを行い、次の授業に向けての課題が分かりましたか。
①できた
②だいたい
できた
③あまりで
きなかった
①できた
②だいたい
できた
③あまりで
きなかった
質問項目1 質問項目2

- 161 -
②生徒のコメント ※抜粋 ※生徒の記述のとおりに記載
質問項目1
・障害者に対する接し方を改めて考えることができた授業だった。
・障害のある人への考えを深めることができた。
・障害者の人たちへの偏見などをなくして普通に接したいと思った。
・偏見や先入観を持って人と接することは相手にとってとても悲しいことだと分かった。
・はじめはどんな授業をするのか分からなかったが、授業を進めていく中で、障害者の人の気持ちや、そ
れに対する自分の行動をどうするべきかなどを考えることができた。
・障害者と障害のない人々とで分け隔てなく暮らしていくことも大切だなと感じた。
質問項目2
・班になって意見交換に取り組むことができた。
・考える時間や班の中でも言える時間があったのでよかった。
・グループでは意見が言いやすくてよかった。
・班での話合いで積極的に意見を言い、他の人の意見をしっかり聞くことができた。
質問項目3
・普段では考えないことを自分で考えられてよかった。
・自分の意見に対して友達が意見を言ってくれたので、深く考えることができた。
・自分の考えを見つめ直し、更に発展させることができた。
・身近に障害のある人はいないが、障害のある人がいたら助けてあげようと思った。
質問項目4
・クラス皆の考えを聞いていろんな考えがあることが分かった。
・生徒一人ひとりが違った意見を持っていてとても参考になった。
・他の人の意見を取り入れながら考えることができた。
・友達の意見を聞いて自分とは違う考えだったので、考え方が広がった。
質問項目5
・障害のある人とない人が一緒に暮らせる社会の作り方を理解できた。
①そう思う
②だいたいそ
う思う
③あまりそう
思わない
①できた
②だいたい
できた
③あまりで
きなかった
①分かった
②だいたい分
かった
③あまり分か
らなかった
①分かった
②だいたい分
かった
③あまり分か
らなかった
質問項目3 質問項目4
質問項目5
質問項目6

- 162 -
・障害のある人に対する気持ちも変わったし、気を付けていきたいと思った。
・障害者の方への接し方や、彼らにできることが何かを考えることができた。
質問項目6
・人と人とのつながりの大切さやコミュニケーションの大切さが分かった。
・障害のある人にどう接するべきか、また、これからどのように変えていけばよいかが自分に問われるよ
うな授業でした。
・これから障害者の人と接する機会があったら普通に接したいと思う。
・自分じゃ想像もできない困ったことがあるかもしれないので、よく観察するようにする。
・次の障害者の授業をするときは障害者の人の声をもっと多く聞きたい。
・次の授業もしっかり受けて色々な考えを身に付けたい。
・自分の考えをまとめることができたら、それを人に伝えられるようにしたい。
<授業の様子>
(5)成果と課題
学校においては、教科等指導、生徒指導、学級経営など、その活動の全体を通じて、人権尊重の精神に立
った学校づくりを進めて行かなければならないという視点で、研究授業を実施した。学校教育においては
「生きる力」を育む教育活動が進められている。「生きる力」は、変化の激しい社会において、他者と協調
しつつ、自律的に社会生活を送るために必要な実践的な力であり、これらは、人権教育を通じて育まれる他
者との共感やコミュニケーションに係る力、具体的な人権問題に直面し、それを解決しようとする行動力な
どとも大きく関わりを持つものといえる。人権教育については、このような「生きる力」を育む教育活動の
基盤として、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間や教科外活動等のそれぞれの特質を踏まえつ
つ、教育活動全体を通じてこれを推進することが大切である。
研究授業後の生徒対象の授業アンケートの集計結果やコメントから、授業のねらいについて、生徒はしっ
かり理解し、見通しを持って授業を受けることができたとある。また、アクティブ・ラーニングの視点に基
づく授業という観点においては、アンケートの質問項目3、4において非常によい結果となっており、グル
ープ内で積極的に意見交換し、他の生徒の意見を聞くことにより、自分の意見を深めることができた。また、
生徒が人と人とのつながりの大切さやコミュニケーションの大切さ、障害者にこれからどう接するべきかを
考える好機になったと実感している。
今年度と来年度の2年間で「人権学習ワークシート集Ⅶ」の作成に向けて、研究を継続し、各人権課題の
ワークシートと指導方法の解説について、その見直しと効果的な活用方法の一層の検討を進めるとともに各
学校における人権教育の充実を目ざし、今後もこれらの授業実践の普及に努めていきたい。

- 163 -
障害者の人権について
ワーク1
①から③はそれぞれ障害がある人にとって問題となりうるものです。どのようなことが問題となるのかを考え
ながら、それぞれ障害の種類を書きましょう。
① ハイブリッドカー
② カラフルな服装
③ 自分の写真
ワーク2
こんな映画を見たことはないだろうか?ある日目覚めると幽霊(ゴースト)になっているのだけれど、自分が
死んだことが分からない。ぼくもそんなふうだった。みんなぼくがいないかのようにふるまっているけど、なぜ
なのかが分からない。「ぼくを見て」と必死で頼み、訴え、叫び、金切り声を上げようとするが、誰も気づいて
もらえない。ぼくの心は使いものにならない身体に閉じ込められて、腕も足も思い通りにならず、声も出せない。
「意識が戻ったよ!」と伝えるサインも音も出すことができない。ぼくは誰の目にも映らない、幽霊少年(ゴー
スト・ボーイ)なのだ。
「ゴースト・ボーイ」 マーティン・ピストリウス著 /ミーガン・ロイド・デイヴィス著 / 長澤あかね訳
PHP研究所 ( 2015年 )より
ピストリウスさんにはどのような障害があり、どのような支援を必要としていると思いますか。
ワーク3
映像を観て、1から5の問いに答えましょう。
1 周囲の家族や、医師、ケアハウスのスタッフはなぜピストリウスさんが意識を取り戻したことに気が付かな
かったのでしょう。
2 その結果、ピストリウスさんはどのような辛い思いをしましたか。
3 ピストリウスさんは駐車場での体験によってどのように思うようになりましたか。
4 ピストリウスさんが意識を取り戻していることに最初に気付いた人は誰でしたか。
5 その人はなぜ気付くことができたのでしょうか。
ワーク4
今日学んだことから、障害のある人たちが、障害のない人と同じように社会とつながるために、私たちは何が
できると思いますか。

- 164 -
【解説】
ワーク1について
世の中には様々な障害があることを知り、理解する。また、それぞれの障害に私たちが気付きづらいその
障害特有の必要があることを学習するための機会とする。またそれぞれの障害に付けられている名前は自分
たちと区別をするための名前ではなく、その名前からどのようにその人たちと接し、支援ができるかを考え
るためのヒントであることを伝えたい。
①視覚障害 健常者にとって、ハイブリットカーの静かさは素晴らしい機能の一つだが、聴覚で周囲の情報
を得ることが多い視覚障害者にとっては、その静かさが、近くに車がいることを知る上で、困難となる要
因にもなりうる。
②聴覚障害 手話により他者とコミュニケーションを取ることが多い聴覚障害者にとって、カラフルであっ
たり、柄の多い服は手話を読み取る上で、相手の手話の位置と服が重なってしまい、相手の手元が見にく
くなったり、目がちらついてしまうなど、長時間集中して手話を読み取ることが困難になることがある。
③パーソナリティ障害 心の奥にある「自信のなさ」への強い反動から、逆に傲慢な態度を取ったり、優越
感が強く、自分の価値を過大評価して、他人への共感が欠如することがある障害である。逆に失敗や批判
に対してとても敏感で、自己評価を満たせないと、怒りを覚えたり、ひどく落ち込むことがある。その結
果、クレーマーになってしまうなど、社会でトラブルを起こしてしまうこともある。
その他の例
・発達障害 必要な情報であるはずの掲示物も、情報が多すぎると発達障害の人には授業への集中を妨げる
ものとなりうる。
・ディスレクシア(識字障害) ディスレクシアとは文字が逆さまに見えてしまったり、文字と音を一致さ
せることが難しく、文字の認識が困難な障害であり、健常者が文字を覚える速度の10倍かかってしまうこ
ともある。ディスレクシアをカミングアウトしている有名人も多く、トム・クルーズは台本をスタッフが
読んでいるものを録音し、セリフを覚えたと語っている。
ワーク2について
南アフリカ出身のマーティン・ピストリウスさんは12歳のとき、感染症にかかり、身体が動かなくなり、
次第に意識も失い14歳のときには昏睡状態になり、両親は医師からは「死ぬまでそっとしておくように」と
告げられる。しかしそれから2年後の16歳のときに意識を回復し始めるが、依然、身体はほとんど動かせな
い状態で意識が戻ったことを周囲の誰にも気付かれずに数年間過ごした。その間スタッフから肉体的、性的
暴力を受け、介護に疲れた母親から「あなたなんて、死ねばいいのに」と言われ、辛く孤独な時を過ごす。
そんな中、一人のセラピストはピストリウスさんの目を見て、色々な言葉をかけ続けていたところ、周囲か
らは単なる痙攣だと言われていた動作が、言葉に対する反応なのではないかと気付きはじめ、両親にリハビ
リを受けさせることを強く勧める。リハビリのおかげで、ピストリウスさんは昔から得意であったパソコン
を使って人工音声を通じてコミュニケーションを取ることができるパソコンソフトを開発する。そして大学
で学位を得て、結婚もしている。
ワーク2ではピストリウスさんの文章から生徒たちがピストリウスさんがどういった問題を抱えていたの
かを気付くことができる目を養いたい。
ワーク3について
実際にピストリウスさんが自身のソフトを使ってこれまでの体験を語っている様子を生徒に見てもらい、
ピストリウスさんが意識を取り戻していることに気付いたきっかけを考える。セラピストがピストリウスさ
んに対して健常者と話すように話しかけ、注意深く観察し、ピストリウスさんのかすかな動きの違いを見つ
けることができたという事実から、生徒たちも障害者の障害名や目に見える障害にだけ気を配るのでなく、
本当に必要としているものに気付くには注意深い観察とわけ隔てのない接し方が大事であるということを理
解してほしい。
ワーク4について
それぞれのワークで学んだ、障害には様々なものがあり、目に見えるものだけでなく「目に見えづらい
困難」があるということ、また相手をよく知り、注意深く観察し、本当の必要に「気付く」ということや、
気づいた上で、彼らにどのように社会との「つながり」、ともに助け合いながら生活することができるか
を具体的に考えてほしい。

- 165 -
環 境
1.研究のテーマとねらい
(1)研究のテーマ
「持続可能な社会の実現を目ざしたこれからの環境教育~高等学校における環境教育に関する取
組の研究~」
(2)研究のねらい
平成 21年に告示された学習指導要領の改訂で、各教科等で環境教育に関わる内容が増えたこと
を受け、各学校で環境教育の充実を図ることがより一層重要となってきている。
このことを受け、教育課程研究会研究推進委員会環境部門(以下「環境部門」)では、高等学校
の各教科・科目等で実践している環境教育について、アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた
授業改善のための研究を行った。
2.研究で取り組んできた内容
「環境部門」では、高等学校における環境教育を展開するに当たり、平成 24年度から学校の教育活動
全体を視野に入れた環境教育プログラムの構築について研究を重ねてきた。平成 26年度に作成した環境
教育プログラムに関する全体計画及び年間指導計画のモデルプランを基に平成 27年度は、より実践的に
環境教育を展開するために、環境に関する共通テーマ(単元)における教科間の相違を調べた。
平成 28年度は、県立高等学校等で、環境教育をどのような教科や行事等で実施しているかを調査し、
理科(生物基礎)の授業内で取り組む授業実践について計画し、実施した。
3.平成 28年度県立高校等における環境教育の実施予定について
表1は、平成 28 年度の県立高校における環境教育に関わる内容を実施する予定の教科・科目等を調
査し、まとめたものである。すべての学校で理科、公民科、家庭科を中心に、様々な教科・科目等の中
で環境教育に関わる内容を実施する予定であることを確認することができた。
表1

- 166 -
4.環境教育に係る実践事例-研究授業-
(1)単元の指導計画及び重点を置いた授業展開例
①科目名:理科・生物基礎
②単元名:生物多様性と生態系
③単元のねらい(身に付けさせたい力):
生態系がどのようなものであるかの確認を通して、生態系における物質やエネルギーの循環に
ついて理解する。また、生態系が微妙なバランスによって保たれていることを理解し、生態系の
保全の重要性を認識する。
④単元の評価規準
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解
・生態系の成り立ち
について興味・関心
を持ち、主体的・協
働的に探究しよう
としている。
・光に関して植物の生存戦略は様々であり、それが植生の遷移に関連があることについて考えている。 ・生態系をとりまく諸現象において人間活動との関連性や生態系との関連性について考察している。 ・生態系にグループ内で話し合った内容や自分の考えをまとめ、相手に伝えることができる。
・生態系の保全に関
する事物・現象につ
いて、調べた記録や
結果をまとめ、事象
を科学的に探究す
る技能を身に付け
ている。
・生態系に関する
基本的な概念や
仕組みについて
理解し、知識を身
に付けている。
⑤単元の指導計画(全 10時間) a 関心・意欲・態度 b 思考・判断・表現 c 観察・実験の技能 d 知識・理解
学習内容 学習活動 評価の観点
評価規準 評価方法 a b c d
1 植生と生態系
・生態系を構成する要素及び、森林の階層構造について理解する。
○ ○
・生態系の成り立ちについて興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・生態系に関する基本的な概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 筆 記 テスト (後日)
2 植生の遷移
・陽樹と陰樹の特徴を理解する。
○ ○
・光に関する植物の生存戦略が様々であることについて考えている。(b) ・植生の遷移に関する基本的な概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 ワ ー クシート 小 テ スト
3 植生の遷移
・一次遷移(乾性遷移、湿性遷移)や二次遷移について理解するとともに、極相種は気候により変化することを理解する。
○ ○
・陽樹と陰樹が植生の遷移に関連していることに気付く。(b) ・植生の遷移に関する基本的な概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 筆 記 テスト (後日)
4 地球上の植生分布
・陸上のバイオームにどのようなものがあるか理解する。
○ ○
・陸上のバイオームについて興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・陸上のバイオームに関する基本的な概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 筆 記 テスト (後日)
5 陸上のバイオーム
・世界のバイオームにどのようなものがあるか理解する。
○ ○ ○
・世界のバイオームについて興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・世界のバイオームについて資料収集などを行い、それらをまとめ、科学的に探究する技能を身に付けている。(c) ・世界のバイオームについての概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 筆 記 テスト (後日)

- 167 -
6 陸上のバイオーム
・日本のバイオームの水平分布や垂直分布について理解する。 ・暖かさの指数について理解する。
○ ○ ○
・日本のバイオームについて興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・日本のバイオームについて 資料収集などを行い、それらをまとめ、科学的に探究する技能を身に付けている。(c) ・日本のバイオームについての概念や仕組みについて理解し、知識を身に付けている。(d)
観察 筆 記 テスト (後日)
7 生態系のバランスと保全
・生態系をかく乱する要因の1つとして、「地球温暖化」について話し合う。 ・グループの話合いの内容をまとめ、ワールド・カフェ方式で他班と共有する。
○ ○ ○
・地球温暖化について興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・地球温暖化のデメリットと人間活動の関連性について考察している。(b) ・地球温暖化について、資料収集などを行い、それらをまとめ、科学的に探究する技能を身に付けている。(c)
観察 成果物 (ホワイト ボ ード) 発表
8 生態系のバランスと保全
・生態系の保全に関する事象として「干潟」「里山」「熱帯多雨林」「外来生物」について調べるとともにグループ内で話し合う。
○ ○ ○
・生態系の保全について興味関心を持ち、意欲的に活動に取り組んでいる。(a) ・生態系をとりまく諸現象について、メリットや失われたときのデメリットなどについて調べたことから、考察でしている。(b) ・生態系の保全について資料収集などを行い、それらをまとめ、科学的に探究する技能を身に付けている。(c)
観察 ワ ー クシート
9 生態系のバランスと保全
・前時で調べた内容をもとに、生態系の保全に関する事象について話し合い、それぞれの意見をまとめる。 ・まとめた内容を発表し、クラスで共有する。
○ ○ ○
・生態系の保全に関して自分の考えを述べている。(a) ・生態系をとりまく諸現象について調べた内容を基に、人間活動の中でバランスを取ることの難しさについて考察している。(b) ・生態系の保全について資料収集などを行い、科学的に探究し、それらをまとめ、整理して伝えることができる。(c)
観察 成果物 (ホワイト ボ ード) 発表
10 まとめ
・これまでの学習内容を振り返り、生態系を保全するためにどのようにすればよいのか自分の意見をまとめる。
○ ○
・生態系の保全について学習したことをまとめ、科学的に探究し、自分なりの考えを持つことができる。(b)(c)
観察 ワ ー クシート
※「生態系でのエネルギーの流れ」及び「生態系での物質の循環」については学習済み。

- 168 -
⑥本時のねらい
・ 前時までに調べた内容をもとに、生態系の保全に関する事象について話し合い、それぞれの
意見をまとめ、発表することにより、クラス全体で共有する。
⑦学習の展開
学習活動と内容 指導内容・指導上の留意点 評価規準 評価方法
導入(5分)
○前時までの内容の復習と本時の確認をする。(5分) ・生態系は人間活動の様々な影響を受けつつも、微妙なバランス関係によって大きな変化もなく保たれている。前時までに調べてまとめた「生態系の保全に関連する事がら」について再認識するとともに、本時の目標を確認する。 ・ホワイトボード等を受け取り、準備をする。 ・本時の活動の注意事項を確認する。
・各グループのテーマについて、グループ外の人にも簡潔に分かりやすくまとめて教えることが今回の目標であることを伝える。 ・ホワイトボード等を配付する。 各グループごとに役割分担を行い、全員で協力して話合いを進めるよう指示する。『司会進行役』『書記』『発表役』 ・発表は前に出てホワイトボードを使って行う。 ・発表の持ち時間は 1グループ1~2分とする。 ・作業の時間が短いので、時間の配分に注意させる。 ・ホワイトボードには色を使い分け、見た人が分かりやすいようにまとめるよう伝える。
展開(35分)
○各グループのテーマに沿って、各自で調べてきたことを基に、ホワイトボードにまとめる。(15分) 【テーマと課題】 テーマ1 『干潟』 テーマ2 『里山』 テーマ3 『熱帯多雨林』
テーマ4 『外来生物』 ○各グループでまとめた内容について発表し、クラスで共有する。(20分)
・発表の持ち時間は 1グループ1~2分とする。 ・残り時間の管理に留意する。
・生態系の保全に関して自分の考えを述べている。(a) ・生態系をとりまく諸現象について調べた内容を基に、人間活動の中でバランスを取ることの難しさについて考察している。(b) ・生態系の保全について資料収集などを行い、科学的に探究し、それらをまとめ、整理して伝えることができる。
観察 成果物 発表
まとめ(5分)
○本時のまとめ ○次時の確認をする。
○生徒の発表を受けて、次のことについて再確認する。 ・どのテーマにおいても生態系は人間活動の影響を受けつつもバランスを保ちながら存在していること。 ・人間活動が一定の範囲内であればバランスが保たれるが、行き過ぎると生態系が大きく変化してしまうこと。 ・今の生態系を保っていくためには、人間の努力も必要であるということ。
ワークシート
研究実施校:神奈川県立大和高等学校
実 施 日 : 平成 28年 11月 24日(木)
授業担当者:舩田 弘子 教諭

- 169 -
ホワイトボードにまとめている様子
まとめの例
発表の様子
⑧授業の様子
⑨生徒アンケートの結果
ア 質問項目と結果
質問項目 回答番号
1 2 3
1 授業のねらい(この時間に何を身に付けなければならないか)を理解し、見通しをもっ
て授業を受けることができましたか。 34 82 2
2 授業の中で積極的に意見を言ったり、話合いに参加したりすることができましたか。 60 50 8
3 授業の中で、自分で考えたり理解を深めたりすることができましたか。 62 53 3
4 授業の中で他の生徒の意見や考えを聞いて、自分の考えが広がったと思いますか。 69 47 2
5 授業のねらい(この時間に何を身に付けなければならないか)が達成できましたか。 37 75 6
6 授業の最後に振り返りを行い、次の授業に向けての課題が分かりましたか。 32 70 16
※回答番号(1:できた 2:だいたいできた 3:あまりできなかった)
イ :生徒アンケート結果

- 170 -
⑩教員アンケート結果
公開研究授業 振り返り 回答数:9
質問項目
1 学校の課題を踏まえ、授業研究テーマに基づく授業づくりが行われていましたか。
2 単元の指導計画を踏まえ、単元で身に付けさせたい力や本時のねらいは明確でしたか。
3 生徒が主体的に取り組み、自分の考えを広げたり深めたりできる授業でしたか。
4 アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた指導方法が効果的に取り入れられた授業でしたか。
5 本日の公開研究授業(協議を含む)に参加して、組織的な授業改善推進に向けたヒントを得
ることができましたか。
質問 コメント(抜粋)
1 ・情報を取り出し、考えて表現する力を重視する授業だった。
2 ・意見をまとめ、発表する力を身に付ける明確な目標があった。
・他の班の意見や調べたことについて共有、評価するという点は不明確だった。
3 ・各々の役割分担が明確で、発表までの流れがとてもスムーズだった。
・調べた結果のみを伝えるのではなく、調べた結果についての考えが欲しい。
4 ・ほとんど教師に質問せずに生徒たちだけでできていたので難易度はちょうどよかった。
・自分たちで考えて相手に伝えるという活動など、全体を通して能動的に学習に取り組んでいた。
5 ・授業を作っていくためにたくさん話し合うことができてよかった。
・他校の様子を確認することでグループ学習が効果的であることを再認識できた。
5.成果と課題
今回の授業は、身近な自然環境や生態系が微妙なつり合いによって成り立っていること、生物多様性
の保全には生態系のバランスを保つことが重要であることなどについて、生物学の視点から考える単元
「生物の多様性と生態系」の終盤に当たる部分である。
単元全体を通して、アクティブ・ラーニングの視点を意識した授業づくりを「環境部門」の委員で協
議し、準備してきた。
公開授業の前に生徒は、世界と日本のバイオームについて話し合いを行いながら白地図にまとめたほ
か、「地球温暖化」についてワールドカフェ方式で自分たちの知識や文献の情報をまとめ、科学的に分析
し、理解したことを他の生徒に伝えるという活動を行ってきた。自分たちで計画を立て、情報を調べ分
析し、他の生徒とやり取りをする中で、情報を整理し、自分の思考が深まり広がったという生徒の声が
あった。また、教師側からの一方的な知識の伝達ではなく、生徒それぞれが考え協力し合う活動により、
生徒の学習に対する意欲を醸成することができた。
「平成 28年度県立高校等における環境教育の実施予定について」の調査結果からも明らかになったよ
うに、環境分野は人間活動と自然環境との関わりについて扱うため、他の理科科目や地歴公民科・家庭
科など、他教科・科目等と連携し、広く多様な視点から横断的に環境を考える活動を行うことで、より
深い学習活動を目ざすことができる分野であることを認識することができた。
環境教育は、様々な教科・科目等を含めた学校教育全体の中で実践していく必要があり、今後、各教
科・科目等を通して環境教育の充実を図るとともに、アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた授業改
善に取り組んでいくことが大切であると考える。