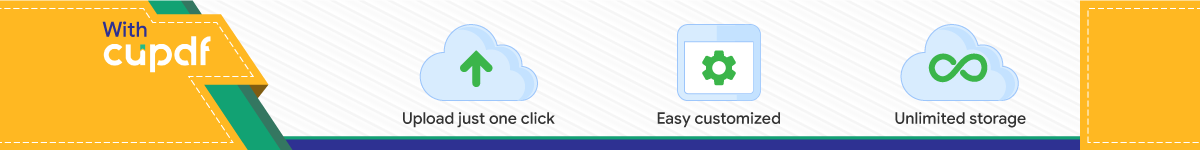

(1)朝日 21 関西スクエア 2010.4
毎月1回10日発行
―ロボットに関心を持ったきっかけは。幼稚園か小学校低学年のころ、手塚治虫の漫画「鉄腕アトム」を読んだのが原点。物を作るのが好きで、その究極形がロボットだと思っていた。ロボットをやろうと京都大学に入り直し、卒業研究にヒューマノイド(人間型)ロボット「ネオン」を作った。卒業と同時に学内入居ベンチャー企業の「ロボ・ガレージ」を起こした。―どのように作っていくのですか。設計図はない。興味あるテーマから「こんなことをさせたい」「こんな物があれば面白い」と、技術のアイデアや作りたい気持ちが高まった物を、1、2年かけて作る。大津市の自宅で作ってきたが、東京大先端科学技術研究センターに移していく。「こんなロボットがほしい」という個人的な欲求からスタートしているが、他人にも「こんなのがほしかった」と共感してもらえる物を作りたい。
―小柄で瞳が大きいデザインに、人間らしい動作が魅力です。意識して作っている。大型だと一人前の働きを期待する
し、あるいは邪魔にもなる。身長40センチくらいがいい。大きな瞳は、使う人とのコミュニケーションに大事だから。だから人間型にこだわっている。動作は目的と関係のない動きもすると人間らしく見えるし、格好いい。
―これからのロボット像は。人と家電や機械製品との間を通訳のようにつなぐ人間型ロボット。説明書を片手にリモコンを操作しなくてすむ。日常のコミュニケーションを通じて利用者の好みやライフスタイルをつかんで、黙っていても好きなスポーツ番組を録画しておいてくれるような、気が利く執事ロボットが「一家に1台」の時代が来る。人間型ロボットは機械としての難しさ、複雑さに加えて、使う人間の感じ方やコミュニケーション能力など奥が深い。たとえば掃除ロボットは勝手に走る掃除機であり、既存製品の延長だ。他方、人間型ロボットは人間と機械の関係が大きく変わりうる全く新しい存在。このロボットが掃除ロボットに指示を出す。生活にも産業にもこれまでにないインパクトをもたらす。
―将来の夢は何ですか。人間型ロボットが機械製品をまとめる「ロボットリビン
グ」のショールームが5年後くらいにはできあがり、新しもの好きの人たちが買い始める。10~15年後には一般家庭に普及しているだろう。ロボットは最初は数千万円して当たり前。安いと、できることが少ないおもちゃになってしまうし、中国でも製造できる。値段に見合う高い価値をいかに持たせられるか。「こんな物があったら面白い」とゼロから全く新しい物を創造するのが、先進国のできることだ。その時々に自分の理想のロボットを発表して「一家に1台」に向けた一翼を担い、その時代を体験したい。
―関西を拠点にする良さとは。物作りのネットワークがある。私が作った部品を複製して
くれる会社が京都に、ロボットの頭脳(コンピューターの基盤)を扱うベンチャー企業が大阪にある。阪大、京大、立命館大、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などでロボット研究が盛んだ。総合的に恵まれている東京に比べて、関西はロボット開発に特化して優位に立つ。大学に知が集積しているし、自治体もロボット開発を後押ししている。
たかはし・ともたか 株式会社ロボ・ガレージ代表取締役、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授、大阪電気通信大と福山大の客員教授。1998年、立命館大産業社会学部卒業。2003年、京都大工学部を卒業し、ロボ・ガレージを創業。ロボットの設計、デザイン、製作をこなす。04~08年、ロボカップ世界大会のサッカー競技に関西のチームで参加し、5連覇。09年秋には、素早く走り、ジャンプできる「ロピッド」=写真=を発表した。
第2回関西スクエア賞に高橋智隆さん
「一家に1台」 人間型ロボットの未来を追い求めて2009年度の「朝日21関西スクエア賞」に、独創的な人間型ロボットの研究・開発で活躍するロボットクリエーターの高橋智隆さん(35)=大津市=が決まりました。関西の若い才能をたたえるこの賞は今回が2回目。ユニークなデザインの下に先端の技術や仕掛けが詰まったロボットを次々発表している高橋さんが、ロボットの未来を語りました。� (小西良昭)
朝日新聞大阪本社 1879年(明治12年)創刊
2010.4
123No.

(2)朝日 21 関西スクエア 2010.4
国内の交通遺児、自殺遺児へ学費支援する、「あしなが育英会」の「あしながさん」の一人として、不況による母子家庭の年収が激減し、全国平均で134万円との厳しい現実に目を向けざるを得ない。公立高校の学費が年24万円、私立高校は46万円。家計を圧迫する学費の滞納で高校中退を余儀なくされ、進学を断念する子どもが増加している。高校中退では働きたくても仕事はなく、次代を担う青少年が未来への夢や希望を失えば、国の未来は暗雲が漂う。高校無償化法案で、朝鮮学校を除外との記事に驚く。拉致問題担当相や大阪府知事が、「国交がなく、拉致問題の国とつきあっていられない」と、朝鮮学校を対象から外すとの報道である。「目には目を」の制裁論理で拉致問題が解決できるのだろうか。国交がなくても、拉致問題があろうとも、子どもたちに罪はない。数年前、チマ・チョゴリで通学する生徒たちに投石した事件がよみがえる。「NPO法人・北朝鮮難民救援基金」は脱北難民の支援に取り組むNGOで、会員になって10年余になる。スタッフは中朝国境で危険に身を挺しつつも、人道上や人権問題か
ら放置できないとの救援活動を高く評価する。今年は日韓併合100年であり、日本は植民地政策では創氏改名、強制連行など、民族弾圧や文化侵害の圧政を強いてきた。朝鮮学校の子どもたちの親世代の多くは、戦中は公民として国策事業に駆り立てられ、戦後は一転、外国人として日本に住み続けた朝鮮・韓国籍の人々である。朝鮮学校への差別感や疎外感を助長する政策は歴史認識を欠くものであり、鳩山政権の唱える、「多文化共生社会」や「東アジア共同体」とは対極にある。日本はいま、グローバル経済での外国人労働者雇用が進み、国際結婚も多く、定住外国人は増加の一途をたどる。多民族国家への意識改革と共に、異文化理解や交流は学校現場、地域社会ばかりでなく、国際社会日本の国益になるはずである。国内で学ぶ外国籍の子らへの平等な教育支援は、今後の日本社会貢献への人材育成になるにちがいない。� (くろだ・むつこ)
私が学生だった時、大学の卒業旅行先に選ばれたのはチェジュ島でした。本土と離れているということで、独特な文化を育んできたチェジュ島への旅に、期待は膨らみました。現地のガイドに連れられ、何カ所かの観光地を巡ったあと、私たちは教室ひとつほどのテントの中に案内されました。そこで始まったのは、地元の人によるお土産販売。しかしその説明の大半は、いかに本土の人たちが地元経済を牛耳っているか、に対する憤慨でした。チェジュ島の人口の1割が虐殺された4・3事件(1948年)について詳しく知ったのもそのあとのことでした。本土から離れた島には、時として国の矛盾が押し込まれます。沖縄も例外ではないようです。米軍基地は朝鮮半島の情勢も絡む複雑な問題ですが、今ふりかかった火の粉をどう消すかという刹
せ つ な
那的な処理をしようと、政府が考えているように思えて仕方がありません。臭いものにはふた。まさか沖縄がゴミ箱?
高校無償化での朝鮮学校の除外を憂う黒田 睦子 日本居住福祉学会理事
関西スクエアのホームページを一新しました朝日21関西スクエアのホームページを一新しました。これまでどおり、会報とバックナンバーはPDFでもご覧いただけます。新たに、「関西スクエア賞」の記事を載せています。月1回の会報に間に合わない「お知らせ」も、必要に応じて載せていきます。インターネットの検索で「関西スクエア」と入力していただければ、すぐ見つかります。ぜひご覧ください。
ホームページアドレス http://www.asahi.com/kansaisq/

(3)朝日 21 関西スクエア 2010.4
「戦争と医の倫理」の検証を ―奈良・山本病院事件の本質―来春の第28回日本医学会総会(東京)へ向けて
山口 研一郎 現代医療を考える会代表、医師
診療報酬不正受給に端を発した奈良県・山本病院事件(医師の山本前理事長は2010年1月13日詐欺罪で実刑判決を受け、控訴中)は、2月に入り、良性の肝腫
しゅよう
瘍を「肝臓がん」として摘出術を行い患者を死亡させた「業務上過失致死事件」に発展している。病院経営のための不要な検査・治療・手術の実施、患者への虚偽病名の告知、経験のないスタッフによる手術の断行、輸血の準備を怠るなどの不十分な態勢、大量出血後の手術の放棄など、様々な問題点が指摘されている。確かに同事件には、一般の臨床場面では考えられない特殊な状況が存在している。関係した医師らの責任が問われるのは当然のことであろう。一方、2月6日付の朝日新聞は、岡山県の女性(73)が県内の公立病院において「病気腎移植」の目的で腎臓を摘出された事実を報じている。「腎臓がん」との病名で手術が行われたが、既に手術前に良性との判断がなされていた。山本病院事件と似通っているが、「透析患者に移植するための摘出」として、担当医は免罪されたのであろうか。奈良や岡山の「事件」の本質は何か。そこに横たわるのは
「生活保護患者」や高齢患者といった「弱い立場の人」の人権の軽視であり、人の身体をモノとしかみない考え方である。かつて戦時中に生じた「医学犯罪」においては、人をモノ
として扱う考え方が徹底して貫かれ、中国人をはじめとする多くの民衆が、幾多の「医学実験」の犠牲となった。今日の医療界は過去の「犯罪」を十分に反省できたのであろうか。医療倫理に関する医学教育は徹底されているのであろうか。私共は2007年4月、第27回日本医学会総会(大阪)と期を一にして、「戦争と医学」と題するパネル展、シンポジウムを開催した。その一環として、全国の大学医学部(医科大学)に対し「医の倫理」に関するアンケートを行ったところ、「七三一部隊」などの細菌戦部隊について教えられていたのは1割に満たなかった(詳しくは、本会報2009年7月号の5ページ参照)。日本医師会は戦争中の医学犯罪について、その事実を正式に認めていない。そのことが、全国の大学への医学教育に関する調査結果にあらわれていると言えよう。その結果日常診療においても、患者を対象に十分なインフォームド・コンセント(IC)もないまま実験的な医療が行なわれることが多い。今回の山本病院を氷山の一角とする患者の人権・人命を無視した「医療行為」は、いまだ医学界にはびこる旧弊として受け止める必要がある。
現在の臨床分野においては、「予防医療」の名の下に手術を含む様々な治療が公然となされている(山本病院で行われたカテーテル手術も狭心症や心筋梗塞の「予防」を名目とした)。また、本年7月より施行される「臓器移植法」により「脳死=人の死」と定められ、乳児や幼児に至るまですべての人々が臓器摘出の対象になるなど、ますます医師に人々の身体や命に関する多大な権限が認められようとしている。そこで不可欠なのは厳しい医療倫理である。それがなければ、人の体にメスを入れることは、医師の行為といえども殺人や傷害以外の何ものでもない。このたびの山本病院事件を、個人の特異な行為としてのみ扱うことはできない。現在の医療界・医学教育のあり方が今のままでは、現在厚労省で進められている、日常診療において医療事故が発生した際に開かれる“医療事故調査委員会”の設置も絵に描いた餅に過ぎない。ましてや、「医療崩壊」を防ぐ手立てとして期待される今春よりの医学部定員の増加も、医師の数が増えるのみで新たな矛盾を生じかねない。私共は現在、全国の医師団体の一つである全国保険医団体連合会を中心に、2011年4月の第28回医学会総会(東京)へ向けて、「戦争と医の倫理」のシンポジウム・パネル展の開催を総会事務局へ要請している。かつてドイツ(ベルリン)医師会は、1980年のベルリン保健大会を契機にナチスの「医学犯罪」について徹底した克服の作業を行い、ついに1988年全国医師会議において『人間の価値』の刊行とシンポジウムを開催した(クリスチャン・プロス/ゲッツ・アリ編、林功三訳『人間の価値-1918年から1945年までのドイツの医学』風行社、1993年参照)。日本医師会においても同様な歴史の掘り起こしが不可欠である。既に医学犯罪に関与した医師の多くはこの世の人ではなく、大学の研究室や各地の研究所に散在していた標本や資料も廃棄されつつある。このまま時が経てば、過去の事実が幻になってしまう可能性が高い。それをくい止めるための掘り起こし作業の一環として、現在防衛省への七三一部隊などに関する資料公開の要請も始めている。日本の医学界が、過去の医療(学)の過ちを探り、真に反省し、未来に向かう姿勢を示さない限り、第二、第三の山本病院事件は生じる可能性が高い。総会事務局は以上のような要請について、現段階では否定的な姿勢を崩していない。実現にはマスメディアを含めた様々な世論の応援が必要である。関西スクエア会員の方々のご理解・ご助言をぜひよろし
くお願いします。� (やまぐち・けんいちろう)

(4)朝日 21 関西スクエア 2010.4
遠くで思うこと優しさを生む国「ラオス」メディアプロデューサーの藤本裕子さんから
私にとってインドシナ半島の国々の中でいまだ足を踏み入れていない国が唯一「ラオス」であった。そこで乾期で一番すごしよい季節といわれる今年1月下旬に訪れた。ラオスは周りを5つの国(タイ・ミャンマー・中国・ベトナム・カンボジア)に囲まれ、海を持たない内陸高地の国である。ほぼ日本の本州の面積の中に60ほどの民族合わせて560万人が住む社会主義国である、それでいて仏教国という何とも不思議な存在に魅力を感じ、どうしてもこの目で見、肌で感じたかったのである。稲作を一家の労働とし、蒸したもち米が主食で千木のある草ぶきの家に住むという、まるで弥生時代をほうふつとさせる山岳部少数民族の生活、日本のルーツの一つだという人もいる、そんな中に他を思いやる心がどのように生まれてくるのだろうか?今でも寺院に子供を託す家庭も多いそうだ、特に古都ルアンパバーンには20余の僧院があり合わせて200人を超す僧侶が修行に励んでいる。毎朝6時勤行を終えた修行僧たちが街の人の喜捨をうけるべく僧衣をまとって一列に並んで歩く、托
たくはつ
鉢は修行の一つである。待ち受ける信者たちはひざまずいて合掌し一握りの飯を鉢に入れる。ヒタヒタと素足の足音と街の音が
聞こえるのみで読経の声は無い。僧の年齢の幅は広くそれぞれが尊敬され、みな表情が優しくひととき和やかな空気と蒸したて「おこわ」の香ばしいにおいがただよう。中に空の段ボールを前にひざまずく子供の姿を見かけた。これは托鉢を受けた僧侶から逆にご飯をもらうための箱であった。まわりが明るくなった頃、箱には数人分の朝食がたまっていた、施しを抱えて子供たちは足早に帰って行った。この国は南北に長くほとんどが高地・丘陵・山地でメコン川は国内総延長1600㎞にわたって流れている古来その恵みは計り知れない。ほぼ中央から北のベトナムとの国境地帯は丘陵で、ジャール平原と呼ばれている。その名は最初に発掘したのがフランスの考古学者だったことにもよるだろう。何とそこには石で作った大小様々な壺が無数に散らばっているのである。大きい物は2メートルを越え小さいのは50㎝程まで形もさまざまで3カ所に分かれて1000個ほどもあるという。壺の中からは人骨と銅や鉄器ガラス玉などが見つかったことから石棺であったと言う説が有力だ。
ここには紀元前5世紀ごろから長期にわたっての遺跡があり、日本も調査発掘に協力し、そのう
ちにユネスコの世界遺産に登録されると聞いた。
ところがこの場所はベトナム戦争当時、ホーチミンルートの真っただ中であった。南北の補給路を断とうとしたアメリカ軍は集中的にねらい撃ちしその爆弾によるクレーターがいくつも見られ中でも爆発と共に手足が吹き飛ぶという悪名高い「クラスター爆弾」が所かまわず撃ち込まれた。現在その不発弾を処理した印に、紅白に色づけされたコンクリートの目印を埋めているが、その数と壺の数とどちらが多いのか?�1975年までの戦争で、ここだけで7500㌧もの爆弾が落とされたという。ラオス全体ではその頃の人口300万と同じ300万㌧の爆弾を浴びたという、1人1㌧という途方もない数字も負の遺産として登録して欲しいものである。「ベトナム人は稲を植える人、カンボジア人はそれを眺める人、ラオス人はその音を聞いている人」。これはかつて統治していたフランス人の言葉だそうだが、言い得て妙と思う。「ここは自給自足でいけるんです」「私は将来コーヒーのおいしい喫茶店を開いてみたいです」。日本語堪能なガイドのセノンさんが言った。「でもバイクや自動車も欲しいでしょ?」「お金は要りません、また仏様にお願いします」。そういって手を合わせた。村の子供達も、貧しい服装はしていても十分な栄養と家族に守られ豊かな表情がその心の様を物語り、手を出して観光客におねだりする風景は見られなかった。
帰国時ベトナムのハノイに立ち寄った。車の騒がしさと物売りの激しい攻勢にタジタジとなる、歩くスピードが2倍になる、そして大阪へ・・・今でもあのゆったり感が懐かしい。
古都ルアンパバーンでの托鉢
ジャール高原に散在する石製の壺
村の子どもたち

(5)朝日 21 関西スクエア 2010.4
ものがたり観光シンポジウム「フジヤマから瀬戸内へ」を開催します。佛教大学教授の高田公理さんから
ものがたり観光シンポジウム「フジヤマから瀬戸内へ」を4月17日(土)午後1時半から、大阪市住之江区のWTCホールで開催します。近代以前に「瀬戸内海」は「存在しなかった」ようです。播磨灘や燧
ひうち
灘など、せまい海域の寄せ集めに過ぎなかったからです。それが近代に「ひとつながりの内海の多島海=瀬戸内海」として「発見」されるのです(西田正憲『瀬戸内海の発見』中公新書、1999年)。そこを1860年に訪れたドイツの地理学者フェルディナンド・フォン・リヒトホーフェンは、その著『支那旅行日記(上巻)』(慶応書房、1943年)に、こう記しています。「広い区域にわたる優美な景色で、これ以上のものは世界の何処にもないであろう。将来この地方は、世界で最も魅力のある場所の一つとして高い評判をかち得、たくさんの人々を引き寄せることであろう。……かくも長い間保たれて来たこの状態が今後も長く続かんことを私は祈る」この本が出た直後の戦後、瀬戸内海は、臨海工業地帯とその生産物の物流の動脈として酷使されてきました。他方、「工業化」とは無縁な、東日本に位置する「フジヤマ」はアメリカ占領下で、いよいよ「ゲイシャ」と並ぶ日本観光の主役になっていったのです。そして21世紀、日本は高度経済成長の果てに、年間3000万人に及ぶ訪問者を迎える国をめざしています。そこでは、近代初期に「発見」された西日本の「瀬戸内海」をいま一度「再発見」する必要があるのではないでしょうか。再発見されるべき要素は少なくありません。内海の多島海の美しい風景、隣り合う島ごとに異なる暮らしと文化、そこに芽生え伝えられてきた珍しくて美味な食べ物、人々のもてなし……。今日、そんな海を往来する船の多くが、貨物輸送の夜行便であるのは「もったいない」と思います。かといって、欧米型のクルージングをめざすというのも、どうかと思います。そこで思い出すべきは、かつてここを訪れた中国人の言葉でしょう。いわく、「日本にもずいぶん広い川がありますね」(JLPT「日本語能力試験問題」より)。瀬戸内海には、川遊びに使われた屋形船のような船が似合うのではないでしょうか。刻々と変わる多島海の風景を愛で、島々に上陸しては、それぞれに異なる風物と人情と美味を楽しみな
がら瀬戸内海を旅するわけです。それは、四国八十八カ所「遍路の旅」を、海上で実現する試み
のようでもありえましょう。同時に、瀬戸内海の島々の人々が、自らの暮らしを支える地域を創成しようとする営みをも励ますにちがいありません。このシンポジウムは、そんな新しい旅と観光をめぐる「ものがたり」を、みずから「紡ぎ出す」ことをめざします。それを瀬戸内海をめぐる船旅の出発拠点の至近距離に位置するWTCホールで実現しようというのです。皆さんのご来場を、心からお待ちし、歓迎いたします。
記念講演:「瀬戸内を旅すれば」神崎宣武(旅の文化研究所所長)
基調講演:「観光を核にしたニッポンの地域再生」西田正憲(奈良県立大学教授)
問題提起:加藤晃規(本学会副会長/関西学院大学副学長)
パネルディスカッション:「瀬戸内は幻か」コーディネーター:高田公理(本学会副会長・佛教大学
教授)パネリスト:白幡洋三郎(本学会会長・国際日本文化研
究センター教授)熊谷真菜(本学会理事・日本コナモン協会会長、食文化研究家)大黒伊勢夫(国土交通省海事局次長)
提言:「瀬戸内のススメ」:白幡洋三郎
シンポジウムは参加無料(ただし船内見学時の昼食は各自負担)。参加資格は観光学習に興味のあるおおむね高校生以上の方とします。参加希望者は必ず住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望プログラム[A班/B班/C班]を明記のうえ、往復はがきでお申し込みください(参加証を返送いたしますので返信用はがきにも自宅住所の記入を)。参加希望プログラム[A班/B班/C班]については、チラシをご覧のうえ、申込時にいずれかを必ず明記。申込先は〒530・0047大阪市北区西天満6-5-17 デジタルエイトビルS棟5F ものがたり観光行動学会[4/17シンポジウム]係へ。参加者1人ごとに1枚の参加証が必要。先着400人で締め切ります。問い合わせは、ものがたり観光行動学会(電話06・6311・3325)へ。
短大での「地域文化論」講義が開講上方文化評論家の福井栄一さんから
(1) 大阪夕陽丘学園短期大学における、「地域文化論」の講義が始まりました。自分の年齢の半分以下の若者たちを相手に、上方文化を講ずるのは、じつに刺激的で楽しいものです。地域の歴史文化を正面からとらまえるため
の講座が、上方のほかの大学・短大でも、もっと開講されてほしいものです。(2) 5月11日(火)午後1時から、神戸市立婦人会館(神戸市中央区橘通3丁目・電話078・351・0861)において、『アジサイ談議』と題した講演を行います。

(6)朝日 21 関西スクエア 2010.4
2009年度企画運営委員の1年を振り返って 朝日21関西スクエアの2009年度企画運営委員は、この3月で1年間の任期を終えました。今期は現場へ出かけての懇談会を3度も開催し、それぞれに好評でした。退任される5人の委員のみなさんに、1年間の活動を振り返ってもらい、ご感想や朝日新聞社、関西スクエアへの注文などを寄稿していただきました。なお、10年度の新しい委員は別掲の通りです。
「モノ」から「コト」への大切さ大西 正
まさ と も
曹さん(関西大学社会学部教授)
この1年間、関西スクエアの企画運営委員の一人として、不況にあえぐ中小企業を
取材してまいりました。そうした中、特にモノづくりに励む中小企業を見ていると、私が従前から主張してまいりました脱モノづくりの必要性をさらに痛感しました。モノづくりにおいて大切なことは、逆説的ですが、つくろうとするモノそのものに囚
とら
われないこと。それよりも自らが持てる力は何かを問う姿勢が重要なのです。すなわち、どんなモノをつくるかではなく、どんなコトをするかがモノづくりにおいても大切になってきたということです。いまだに、中小企業の多くはモノづくりの呪縛に囚われ、新しい展望を開けず
に苦しんでいます。中小企業の経営者には、今一度、わが社の持つ技術がどんな「コト」に使えるのか、どんな「コト」が可能か、広い視野で再考することが何よりも大事だと思い知らされました。こうした思いをきちんと持つ中小企業が、この未曾有の大不況の流れの中を巧みに泳ぎ続けているのを見るにつけ、その考えは強まるばかりです。こうした点を踏まえて、異なった分野の委員のみなさまと議論を深めることが出来たことは望外の幸せでした。今後は、こうした考えをさらに深め、さらに広めて中小企業や地域の発展のために助力していきたいと思っております。
書き手と読み手の論争を加藤 誠さん(伊藤忠商事株式会社 相談役・大阪商工会議所 副会頭)
1年間、他委員様や朝日新聞社の方 と々の交流を通じ、大変勉強をさせていただき感
謝しています。フットワークの軽い皆様と、琵琶湖の沖島、東大阪の企業、そして京都の国際マンガミュージアムを訪問し、記者の基本である「現場主義」の重要性を痛感しました。佐藤先生に「輿論」と「世論」の違いを教わりました。「輿論」は、人々が自分の頭でじっくりと考え、責任をもって議論をたたかわせた過程から見出される、理性にのっとった多数意見であるのに対し、「世論」は、世間に何となく広まっている好悪の感情ということです。新聞には報道の自由があり、大衆には知る権利があります。そしてこの二者の信頼関係が「輿論」と「世論」を決定付けるのだと思います。
新聞は事実を報道せねばなりませんが、記者のフィルターを通して、事実には色がつきます。しかし、私は事実に色がつくことを必ずしも悪いとは思いません。なぜなら、時代を切り取る問題意識をもたない記事には面白みがありませんし、意見・主張がなければ議論をたたかわせることも出来ないからです。私は、新聞の中でも、とりわけ社説を好んで読みます。そこには、その新聞の主体性と問題意識が存在し、私は自分の意見をたたかわせて楽しんでいます。私は、書き手と読み手が論争することで、新聞の質の向上を図るべきだと思います。読み手が参加できるコラムを作り、紙上での論争を掲載してみてはいかがでしょうか。
浅田 稔さん 安田 雪さん中村 順子さん更さ ら や
家 悠介さん大塚 善ぜんしょう
章さん
10年度企画運営委員のご紹介 2010年度の朝日21関西スクエア企画運営委員を、次の5人のみなさんにお願いしました。委員のみなさんとは定期的に懇談会を開催し、朝日新聞社や関西スクエアへのご助言や提言をお願いしています。任期は4月から1年間です。(五十音順)
大阪大学大学院工学研究科教授。人の知能や心理的発達のメカニズムをロボットを使って研究。研究の促進・啓発のためロボットのサッカー大会「ロボカップ」を提唱。56歳。
ピアニスト。関西ジャズ協会長。プロ56年目。大阪・上町台地をテーマに連作を発表する傍ら、若手育成にも力を入れる。アルバム「Be Ambitious」など。76歳。
「ヤシノミ洗剤」などを製造するサラヤ社長。原料のパーム油の生産地・東南アジアの野生動物保護や環境保全にも取り組む。大阪商工会議所中堅・中小企業委員長。58歳。
NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸理事長。阪神大震災被災地の助け合い組織をへて、環境、福祉、地域づくりなどの市民活動を支援するNPOを設立。63歳。
関西大学社会学部教授。専門は人や企業、組織のつながりを扱う社会ネットワーク分析。著書に「実践ネットワーク分析」
「働きたいのに…高校生就職難の社会構造」など。47歳。

(7)朝日 21 関西スクエア 2010.4
「人間」の重要性佐藤 卓己さん(京都大学大学院准教授)
あっと言う間の楽しい一年でした。京都洛中に住んでいると、「関西」在住とはいっ
ても新幹線で通過する以外に滋賀県や大阪府に行くことは稀です。関西スクエアでの琵琶湖の沖島訪問や東大阪市の工場見学は私にとって貴重な経験でした。こうした「現場」を記者のみなさんと歩くことで、メディア社会における「人間」の重要性を改めて痛感しました。私は関西スクエア幹事の前にも二年間、紙面審議会委員として朝日新聞社と接点を持っていましたが、この三年間ほど新聞を取り巻く環境が激変した時代はないように思います。現在、私自身も新聞記事は仕事の合間にGoogleニュースでチェックすることが多くなりました。朝刊はとも
かく、夕刊はほとんど読みません(そもそも普通のサラリーマンには読む時間がないと思います)。新聞「紙」が生活必需品でない時代は予想外に早く来るのではないでしょうか。しかし、新聞紙newspaperが消えても良質な新聞newsの需要は不変です。良質な「新聞」を生み出すのが生身の新聞記者であることも変わらないはずです。ニュー・メディアへの対応で右往左往するのは教育現場も同じですが、結局は人間こそが問題なのだと思います。その意味では、関西スクエアもその一例ですが、人間のつながり、つまり社会関係資本social�capitalの増幅装置としての役割こそ、新聞社にますます期待されているのではないでしょうか。
不思議な集まりチョン・インキョンさん(風刺マンガ家、京都精華大学非常勤講師)
「これはひょっとして場違いなのでは?」。最初の会合でそう思いました。30人近い新
聞社の方々に見つめられ、何だか重々しい雰囲気でした。しかもほとんどの出席者が部長クラス以上と紹介されたら、少しは肩がすくみます。しかし会合を重ねるにつれ、幅広い意見交換ができたと思います。それはおそらく新聞社の中ではなく、企画運営委員の活動現場で、多くの会合が開かれたことに負う所が多かったのではないでしょうか。中でも初めて鮒ずしを食べた琵琶湖の沖島での会合は記憶に残ります。もちろんメーンテーマは鮒ずしではなく、沖島の環境問題への取り組みでした。実は韓国にも海の魚をご飯粒や炊いた粟と一緒に、1週間くらい発酵させたものが
あって、ソウルに帰った時食べ比べてみました。正直なところ、思いっきり腐らせた素朴な鮒ずしの方がよかったです。「関西スクエア」は不思議な集まりだと思います。何か縛りがあるわけでもなく、何となくお互いに緩く繋がっている感じがします。いずれにせよ関西という地域に、様々な意見を発信する、新聞社主宰のこのような集合体があるということは、ひとつの驚きです。東京を中心としたところで起きる物事をじっくり吟味し、あるいは斜めに観察するには、ここ関西が最適な場所ではないかと個人的には思っています。そのアドバンテージを生かし、関西スクエアがこれからどう展開していくのか、楽しみにしています。
現場とメディアをつないで 動き始めた琵琶湖・沖島藤井 絢子さん(NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表)
企画運営委員の1年間は、これまでにないネットワークの広がりの中でのおつきあ
い、という委員名利につきるものでした。現場とメディアをつなげるため、人・地域・くらしをまるごと伝える場として琵琶湖の沖島を選びました。淡水湖に人々が暮らす、世界でも稀
まれ
なこの島は、歴史を今に伝え凜りん
として生き続けてきています。しかし、高齢化・人口減少・生なりわい
業の漁業の厳しさの中、このままでは存続が危うい。未来可能性を真剣に探りはじめているところでした。具体的な島再生の設計「沖島21世紀夢プラン」をいよいよカタチにしたいと、漁師と地元企業(株)日吉の試行錯誤の日々が続いていました。スクエア企画運営委員と朝日新聞大阪本社の皆さまの来島が一気に背中を押すきっかけとなった
のです。具体的な事業の一つ「外来種をペットのおやつに」は〝おさかなまるごと〟の商標で6月からの販売にメドが立ちました。包装を飾るのはチョン・インキョン委員の師匠ヨシトミヤスオ作。二つ目の事業は林道整備。近江八幡市と滋賀県の協力を前提に、加藤誠委員の後押しで、伊藤忠商事(株)と計画策定が進められています。林道を遊歩道として役立てることや、林道整備後のマツタケ山としての再生事業や松枯れ対策、里山整備など、「孫に戻って来てもらう島にしたい」との漁師のことばに力が入ってきました。これからも折にふれ、琵琶湖からのリポートをお伝えしたいと思います。

(8)朝日 21 関西スクエア 2010.4
こんな話 草餅漫画家の河村立司さんから
桜の花びらも、突然舞い降りる雪にギョッ。温暖な瀬戸内も、たびたび四月の雪を見た。竹やぶも、こ
らえきれず、ぐにゃーっと曲がり雪のトンネルをつくってくれたりした。丹波の女流俳人捨女の〈雪の朝二の字二の字のげたのあと〉は小5で習ったが、大雪がくれば、素足に高げたをしばりつけて登校した。二の字ならぬ乱れ字で、よく遅刻したが、先生も顔に湯気を立てながら遅刻して教室に入って来た。あれこれ思い出せば、早春の細雪もグリコのおまけのよ
うで、それなりに遊び相手になってくれた。いよいよ春らんまん。道の駅のように、かならず立ち寄る辻のお堂の仏さんのお顔も、すっかり春の顔。床にカバンを放り投げ、女の先生のオルガンで習った〈春の小川〉などゴチャゴチャ歌っていると、上級生のお姉さんたちもどやどややってくる。腰がヘの字に曲がった堂守のおばあさんも、よっこらしょ
とやってきて、作りたての草餅を仏さんに供えた。上級生のお姉さんは、それを手伝った。「あんたら大きくなったのお」。
みんな顔なじみで、呼び名も知っているから、おばあさんはうれしそうだ。「1時間ほどしたらの、仏さんをよう拝んでか
ら、お下がりを、みんなでいただきんしゃい」と言ってくれた。うまそうな草餅。5、6個はある。お ばあさんは気を利かせてくれている。私 た ちの腹時計は 、超 スピ ードで回転した。
セミナー「デジタル環境下における文学と図書館」報告夙川学院短期大学准教授の湯浅俊彦さんから
1月24日(日)、追手門学院大阪城スクエアにおいて開催された日本ペンクラブ・追手門学院共催セミナー「デジタル環境下における文学と図書館」は104人の参加者を集め、盛況のうちに終了しました。最初に、作家で日本ペンクラブ常務理事の吉岡忍氏による講演「文学にとって図書館とはなにか」がありました。吉岡氏は『古事記』を例に挙げ、江戸期になって本居宣長が研究しようとしたとき、原本がなく、結局各地に散在した写本を訪ね歩くしかなかった。宣長は図書館というものの必要性を最初に感じた人だったにちがいない。写本には異同があるが、これは聖書も同様で、写筆した人の読解力や想像力によって変形していく。これはこれで、人間と想像力の関係を考える面白いテーマとなり得るかもしれない、と語りました。続いて、国立国会図書館関西館の中井万知子館長による講演「国立国会図書館の資料デジタル化はなにを変えるか―図書館・文学・書物」がありました。中井氏は、近代的図書館が出版文化の発展とともに形成され、権力者の図書館から市民の図書館へ変わっていったことを明らかにされました。図書館は書物が読者に手渡し続けられる場であり、知識の社会的基盤として存在している。同じものが刊行される「出版物」を主な所蔵物とする図書館は、どこにでも作られやすい、無料で気軽に利用しやすい、目録や分類など標準化が進みやすい、という特徴をもつことになったのです。ところがコンピューターの発達により目録データベース化
が進展し、総合目録や図書館間相互貸借などの仕組みが実際のものとなりました。そして、インターネットの普及によって知識流通が変化し、紙からデジタルへ、電子情報のはんらんという状況の中で、図書館でも資料を探すための目録などの「二次情報」から資料そのものである「一次情報」がデジタル化され、提供されるように変わってきています。中井氏は今日の状況を次のように位置づけられました。「図書館による所蔵資料のデジタル化という一次情報の発信は、〈いつでもどこでも誰でも〉利用できる〈電子図書館〉を実現するチャンスでもあるが、お金と制度など課題は多い。かえって電子的にしか公表されないボーンデジタル情報が図書館を素通りすると、知識基盤の位置づけが地盤沈下するとの危機感もある。特に納本制度を持つ国立図書館にとっては深刻な問題である」。その上で現在、国立国会図書館が取り組んでいる「近代デジタルライブラリー」などの電子図書館サービスや、2009年から始まった所蔵資料の大規模デジタル化について詳しく説明されました。セミナーではその後、篠原健氏(追手門学院大学・経営学研究科長、総合情報教育センター長)、中西秀彦氏(中西印刷株式会社専務取締役、日本ペンクラブ言論表現委員、大谷大学非常勤講師)を加えて、私の司会でパネルディスカッションを行い、デジタル環境下における文学と図書館の関係について熱い討論を展開しました。当日の資料と報告は下記のHPにて公開していますので、ご参考になれば幸いです。●追手門学院付属図書館「デジタル環境下における文学と図書館」http://www.oullib.otemon.ac.jp/event/20100124seminar.html●日本ペンクラブ「デジタル環境下における文学と図書館」http://www.japanpen.or.jp/about/cat81/post_218.html

(9)朝日 21 関西スクエア 2010.4
冬季オリンピックに思う関西学院大学非常勤講師の熱田親憙さんから
まず、三つの感想が浮かぶ。①金メダルこそなかったが、入賞者を含めると、よくぞ日本は頑張ったという印象が残る②国際的交流にはスポーツが一番であることを確認③今回もまた、日本全国民が国意識を持つのはオリンピックのときだけだという印象を確認。この中で一番気になるのが③である。日頃は国際化、グローバル化の名のもとに日本という国意識は薄く、W杯を超えてオリンピックのときだけ全国民が挙げて「日本がんばれ!」と一丸になる。この時以外は国を忘れて、自己中心の生活に追われているのである。こんなことで、将来いや21世紀に日本は生き残れるのかと心配になるのである。平和ぼけからもう目ざめなければと思う。例えば、バレンチノのバッグが欲しい、バーバリーのコー
トが欲しいと思えば、インターネットで注文できる今日であるが、もし、食べるお米が欲しい、小麦が欲しいといって注文しても、衣料・装身具のようにエアメールで配達してくれますか。穀物やエネルギーはすべて国家間の取引であり、民間個々の取引は許されないのである。国家を動かしているのは人間であり、いくら自由経済、自由貿易を建前にしても、自国に食糧飢饉が起きて食糧不足になってきたら、食糧を輸出してもらえるだろうか。保護貿易もありうることを覚悟して、自国をいかに守るべきか、日本国全体をどう導く
べきかを真剣に考え、その準備をしなければならない時がきていると思ったが、考えすぎだろ
うか。次に印象に残ったのは①である。アスリートが世界レベルの技術に達するために、選手が常に思う存分練習が出来るよう、国を挙げて支援をしている国が多いことがありありと分かった。それに対し、日本は企業などのスポンサーにまかせきりで、後は個人の努力を期待するという貧弱な練習環境である。従って種目によっては選手層が薄いところもある。このような選手生活のスタートラインが違う中で、他国の選手と互角に競ったのであるから、「よくぞやった!」とほめてあげたい気持ちである。スポーツがビジネス化する中で、アマチュア精神に撤するオリンピックは感動的である。その感動の舞台づくりのために国、国民がそろって支援し、その成果として栄誉の国旗と国の英雄が生まれるのである。オリンピックは世界に国力や存在感を示すよいチャンスでもある。グローバル化が進めば進むほどその必要性が高くなるので、日本はオリンピックに取り組む戦略の見直しが必要であろう。最後は②の印象である。開会式と閉会式、スタンドで応援する人々の国を超えた拍手を見ると、感動シーンを共有しながら交流できるのは、やはりアマチュアスポーツのオリンピックが一番だと思う。
「入浜権宣言35周年記念シンポジウム」で運動の経過と成果を確認元・入浜権運動推進全国連絡会議代表の髙﨑裕士さんから
朝日21関西スクエア会報を通して予告していました「入浜権宣言35周年記念シンポジウムinたかさご」が2月21、22日、兵庫県高砂市のふれあいの郷
お お し こ
生石研修センターで開かれました。集会には予想を上回る約80人の学者、弁護士、住民運動家らが集まり、なかには20年ぶり、30年ぶりに再会した人たちもいて、さながら入浜権運動の同窓会のようでした。集会のうち講演会では早川和男・神戸大学名誉教授が
「居住環境としての海浜と入浜権運動の意義」と題して講演、「生活空間としての海岸の多様な価値を主張する入浜権運動は環境を守る運動の先駆的意義を持つ」と強調しました。岡田真美子・兵庫県立大学教授は「入浜権運動の今日的意味―環境宗教学の立場から」と題して講演、「入浜権の説く環境倫理思想は海浜の価値を生産という観点でのみ見るところから精神的なものに高めた」と評価しました。さらに松本文雄・元高砂緑地問題研究会代表と稲澤義隆・高砂町少年団代表世話人が、それぞれ具体的な海浜の保護、利用の具体例を報告しました。松本さんは主とし
て高砂市を相手に、海浜の環境問題を追及、稲澤さんは兵庫県を相手にして交渉を続け、青少年にヨットなどを通して海と親しむことを教えてきた活動の経過を話しました。記念集会と並行してネット上で開催されている「入浜権宣言35周年記念インターネット・シンポジウム」には約20人の人々が論文や随想、メッセージなどを寄稿、その中で髙﨑裕士と上記の岡田真美子教授は昨年10月に出された広島地裁の「鞆の浦訴訟判決」についても、入浜権運動の立場からこれを高く評価する発言をしています。参加者の中からはその判決や、さらに沖縄県の読
よみたんそん
谷村の活動、沖縄県議会の「海浜自由使用条例」制定、学問の分野でのコモンズに対する関心の高まり等々、入浜権運動がもたらした成果であるとの発言が相次ぎました。この後、夜、参加者は交流会で親交を深め、22日には高砂海岸を視察、入浜権運動の成果と言える「県立高砂海浜公園」や「あらい浜風公園」などを見てまわりました。こうして、大きな高まりを得た参加者たちは運動の継続と再会を誓い合って別れました。なお、「インターネット・シンポジウム」は半永久的に存続させ、人々の投稿を掲載、閲覧に供していくことが確認されています。http://homepage3.nifty.com/eternal-life/irihamakenundou.htm

(10)朝日 21 関西スクエア 2010.4
花の万博20周年!4月から多彩なイベントフリーアナウンサー&元咲くやこの花館コンパニオンの坂口智美さんから
1990年、大阪・鶴見緑地で開催された「国際花と緑の博覧会」は、東洋で初めての大国際園芸博覧会でした。皆さんには、どんな思い出がありますか?�私は、大阪市出展「咲くやこの花館」のコンパニオン=写真左下=でした。熱帯から極地までの8つのゾーンに約2600種、1万5000株の植物が植栽・展示された大温室です。私たちの仕事は、エントランスでのアナウンス、手話、館内での植物の説明、観客の誘導、VIP接遇など。(ホストパビリオンでしたので、国賓級のお客様も必
ずお越しになりました)「いらしゃいませ」「ありがとうございました」を何万回言ったでしょうか。しかし、183日間の開催期間は、辛いことなど一つもなく、400万人以上のお客様を動員し、あっという間に過ぎました。花と緑に囲まれて、笑顔で過ごした幸せな毎日でした。花の万博会場には、たくさんのパビリオン、国際庭園、ステージなどがあり、訪れた方々には、それぞれの場所で様々な思い出があると思います。この博覧会以降、街の花屋さんでは、切り花よりも鉢植えが売れ筋となりました。植物を観賞するだけでなく、育てる楽しみを人々に目ざめさせた博覧会でもありました。今、会場は市民が集う公園になっていますが、今年は20周年記念で、様々なイベントが開かれます。主なものをご紹介しますので、是非お出かけください。
(財)国際花と緑の博覧会記念協会主催のイベント(TEL06・6915・4513)1)花の万博の日本画展�(有料)4/14(水)~26(月)大丸心斎橋イベントホール花の万博当時「花と緑・日本画美術館」で展示されていた、現代日本画家50人の50作品をそのまま展示。「花の万博20周年メモリアル展示&写真展」(無料)も併設。当時の会場風景の写真や会場模型、コンパニオンのユニホーム、記念の品々、パビリオン花博写真美術館の作品など。
2)花・緑フェスタ 4/29(木・祝)~5/5(水・祝)①フラワーカーペット・・・5/2まで中央通り 33万本のチューリップの花びらを使用し、600人の市民が参加して巨大花絵(11面11種類)を制作。②花の万博20周年メモリアル展示&写真展・・・陳列館ホール③水の館ホール展示・・・水の館ホール 45団体が参加する都市緑化技術やフラワーアレンジメントの展示・ステージ・園芸体験も。
④スポットガーデン・・・くすのき通 造園関係 団体による「花のある生活の庭」。
⑤スタンプラリー・・・5/22(土)23(日) 花博記念公園鶴見緑地内
3)自然と人間との共生~花の万博からの20年~・・・4/5(月)~4/16(金)朝日新聞大阪本社1Fアサコムホール(土日休) 花博当時のなつかしい写真や、「等身大昆虫写真」コーナーなど、20年間の協会事業が紹介される展示です。ほかに、記念式典(4/30)、花・緑フォーラム(5/16)、等も開催され、共催催事としてFM802ロックライブ(6/13、有料)があります。また、花の万博のマスコットキャラクター「花ずきんちゃん」=写真右=も20年ぶりにお色直しして復活します。どこかで会えるといいですね。
咲くやこの花館 (要入館料) (TEL06・6912・0055)花の万博当時のまま残っているパビリオン。1)20周年特別展示~昔・今・未来 花のある生活~4/1(木)~5/9(日)2F展示室太古から現代までの植物とのかかわりと花のある生活を体感できる展示。植物はもちろん、古い園芸カタログや書物、ユニバーサルな園芸器材の展示の他、近代の風景体験として「十三の渡しの茶屋」の再現、鉢物振り売りの実演もあります。また、花の万博から現在までの「咲くやこの花館」の歴代コンパニオンのユニホームの展示も。タイムトンネルを抜けて、植物との関係を探ってみてください。
2)植物の進化と恐竜展 4/29(木・祝)~5/5(水・祝)フラワーホール長さ5.4mの恐竜ロボット、恐竜の化石、植物の化石や進化の紹介
3)カービングフェスタ 4/24(土)~5/9(日)ソープカービング作品展示に加え、ソープ・フルーツ・アイス、それぞれのカービングコンテストも。
4)熱帯フルーツ展 4/27(火)~5/9(日)珍しいトロピカルフルーツの展示、バナナの重さ当て
クイズなど。
鶴見緑地展望塔 (TEL06・4301・7285 大阪市総合コールセンター)花の万博当時、「いのちの塔」の名称だった会場のシンボルタワー。今年の3月で休館しましたが、この万博20周年を記念して、無料開放されることになりました。期間は、4/29(木・祝)~5/5(水・祝)、10:00~17:00。生命の大樹をイメージしてデザインされた塔の展望室(高さ約60m)から、花博記念公園鶴見緑地はじめ、360度のパノラマ風景をお楽しみください。

(11)朝日 21 関西スクエア 2010.4
活動報告
奈良県桜井市の纒まきむく
向遺跡で昨年秋、大型建物跡が発掘されたのを受けて、シンポジウム「卑弥呼はどこに? 邪馬台国と纒向遺跡」(協力・桜井市、奈良県立橿原考古学研究所)を3月20日、大阪市中央区のエル・シアターで開きました。古代史最大の謎・邪馬台国をめぐるテーマとあって、満員の800人が聴き入りました。発掘調査を担当する桜井市教委の橋本輝彦主査は報告で、「見つかった4棟の建物跡が規則正しく並び、中軸線は東西の同一線上にあり、南北もそろっている。弥生時代に全くない建物群が古墳時代初頭に纒向遺跡で出現した意味は大きい」と述べました。続いて菅谷文則・橿原考古学研究所長が講演。「土器研究からは、箸墓古墳の被葬者は卑弥呼の次代の人。纒向遺跡に卑弥呼の宮殿があったと考えるかどうかは、日本書紀との整合性を検討する必要がある」と指摘しました。後半は、菅谷氏と千田稔・奈良県立図書情報館長、和田萃あつむ
・京都教育大名誉教授、武田佐知子・大阪大教授、玉城一枝・奈良芸術短大非常勤講師が、天野幸弘記者の進行で討論。「邪馬台国を記した魏志倭人伝をどこまで信用できるか」「発掘調査で王宮の所在地を探ることが大切」「保
存と研究、活用・公開の4本柱を考えて調査すべきだ」などの意見がでました。邪馬台国論争の決め手は、中国皇帝からの勅書を収めた箱にある封
ふうでい
泥(粘土の封印)が見つかれば、そこが卑弥呼の都といえるとの見方が示されました。
司会の坂口智美さんも、武田教授が監修した卑弥呼の衣装(大阪府立弥生文化博物館蔵)を披露し、討論を盛り上げました=写真。ロビーでは奈良県三輪素
そうめん
麵工業協同組合や地元のスタッフがにゅう麺を来場者に振る舞い、好評でした。(詳しくは3月25日の朝刊に掲載しました)
激論「卑弥呼はどこに?」/邪馬台国と纒向遺跡シンポに800人
朝日・大学パートナーズシンポジウム「書物の現在-21世紀に出版文化は可能か」(大阪芸術大学、朝日新聞社大阪本社共催)が3月21日、大阪市北区の大阪国際会議場で開かれ約350人が耳を傾けました。最初に小説家の角田光代さんが「本とわたし」のテーマで、デビュー当時の担当編集者だった大槻慎二さん(現朝日新聞出版)と対談。「海燕」新人賞授賞式の後、文壇バーで年上の作家や編集者から「あれは読んだか」「あれはどうだ」と次々に尋ねられたが、何ひとつ読んでいない。よくそれで作家を目指したな、と言われて非常に落ち込んだ。しかし、それもあって、その後は(好き嫌いで選べない)書評の依頼は断らないことにしていると話しました。一番好きな作家は28歳で出会った開高健。「輝ける闇」はそれまで味わったことのない言葉の濃密さにあふれていた、と振り返りました。大阪芸術大学の籔亨、田中敏雄の両教授と出口逸平准教授が書物や出版にかかわる研究報告をした後、パネル討論に移りました。大阪芸術大学の長谷川郁夫教授をコーディネーターに、岩波書店社長の山口昭男さん▽作家で
法政大学教授の中沢けいさん▽装丁家で東京造形大学教授の長尾信さん▽岡山県立大学准教授の瀧本雅志さん▽大阪芸術大学教授の山縣熙さん▽大槻さんの6人のパネリストが、それぞれの専門的な立場からの視点も交え、書物の将来について意見を交わしました。急速に進む電子書籍化の動きについて、「挑発もこめて」長谷川さんが「言霊という言葉があるが、電子ブックの中では、人間のそうした精神の働きといったものは奪われるのではないか」と投げかけると、電子メディアをどう見るかについて活発な討論が繰り広げられました。編集者としての立場から山口さんは「一冊でも多く『百年後に残る本を』という気持ちで努めたい」と語りました。(詳しくは3月28日付朝刊に掲載しました)
本に未来はあるか/大阪芸術大学とシンポジウム
奈良県明日香村のキトラ古墳壁画が5月15日~6月13日の間、同村の奈良文化財研究所飛鳥資料館で特別公開されます。今年は初公開の「朱
す ざ く
雀」をはじめ、「青龍」「白虎」「玄武」の四神図が一堂に見られます。これを記念したシンポジウムを次の通り計画しています。詳しくは朝日新聞
紙上で発表します。【日時】5月8日(土)午後1時~5時【場所】エル・シアター(大阪市中央区北浜東3)【テーマ】朱雀翔
と
ぶ キトラ四神図の世界(仮)
キトラ古墳四神壁画シンポ、5月8日に大阪で

事務局から
(12)朝日 21 関西スクエア 2010.4
先日、不注意から足をねんざした。転勤で住むマンションは会社まで徒歩25分ほど。普段はダイエットを兼ねて歩いているが、とても無理そうなので、会社から臨時の許可をとって2週間ほど自転車通勤することにした。安い自転車を買って通い始めると、道が平らなので足への負担はほとんどなく、少々寒いことを除けば極めて快適である。通勤時間も10分程度へと大幅に短縮された。なるほど、大阪の街に学生や主婦だけでなく、通勤や仕事に自転車を使う人が多い理由が分かる。2006年の統計をみると、都道府県別の自転車保有率
(人口/保有台数)で、大阪府は1.2とトップ。1.2人に1台の割合で自転車がある。他の大都市では東京、京都が1.5、神奈川、愛知、兵庫が1.7、全国平均は1.8だ。保有台数は東京の879万台に対して、大阪は723万台。狭い大阪の自転車密度の高さが分かる。「全国に誇る自転車王国」と言いたいが、マナーへの評価は極めてよろしくない。「全国最悪」と嘆く大阪人もいる。青信号を渡る歩行者はおかまいなしに、直角方向から猛スピードで寸前をすり抜ける。人込みや地下道でも、まず自転車を押し歩きしない。接触しても知らん顔……。不快かつ危険な体験を並べればきりがない。自転車マナーの低下は全国的な傾向だ。ただ、他都市で暴走自転車が主に中高生など若者の問題なのに対して、大阪に特徴的なのは、サラリーマンや主婦らしき人など
「大人」が非常に目立つことではないか?放置自転車もすさまじい。内閣府の調査では、2007年の大阪市の放置自転車は5万371台で全国(全国の市と3大都市圏の町村)の15%強を占め、市町村別で文句なしトップ。大阪より人口の多い横浜市は2万4707台、東京23区全体でも7万184台だ。放置の多い駅の全国ワースト15には、大阪駅など大阪市内5駅が顔を出す。大阪中心部では駅周辺だけでなく、主要なビルの周りのあらゆる場所が「駐輪場」と化している。新しいビルの公開空地も自転車の山で通りにくいか、公開空地から閉め出された自転車が歩道を埋めているか、どちらかだ。どうやら「みんな止めてるや~ん」は、CMの駐車違反おばちゃんだけの話ではないようだ。あちこちに設けられた「駐輪禁止」のロープや障害物が、さらに通行を妨げ、景観や都市の機能性をも大きく損なっている。「一定規模のビルや商店街には必要な広さの駐輪場を強制的に設けさせる」「市の中心部を自転車進入禁止にする」「辻々に指導員を立たせて、ルールを守らない自転車を徹底的に交通指導する」……。そこまでは無理かと思いつつ、怒りにまかせて妄想が広がる。そんなことで最近、自転車に乗るのがあまり楽しくない。� (すずき・なおや)
▽「大学との知の連携」をめざした「朝日・大学パートナーズシンポジウム(APS)」が、3月21日開催の「書物の現在―21世紀に出版文化は可
能か」(大阪芸術大学と共催)をもって休止しました。05年度に始まり、計39件を開催、聴講者は延べ1万5千人を超えました。原則半期3校に絞ってきましたが、毎期、多くの大学から応募があり、毎回、多数の皆さんにお越しいただいたのがありがたかったです。私が担当したのは最後の1年間でしたが、大学の方々はもちろん、講師、パネリストにお招きした様々な分野の人たちと接し、新鮮な刺激を受けることができました。出演を引き受けて下さった方々に、改めてお礼を申し上げます。APSの休止とともに私も事務局を離れましたが、大学との窓口役を引き続き兼ねます。今後ともよろしくお願い致します。� (冨永)▽NHK大河ドラマの影響もあって、全国的に「龍馬ブーム」だそうです。龍馬のふるさと高知は私の初任地。10年ほど昔のことを思い出します。とにかく「あつい」ところでした。太陽が焼けるように照りつけるうえに、人柄も熱い。男も女もお酒が大好きで、大皿にあらゆるごちそうを盛った「皿
さ わ ち
鉢」は、一度座ったらとことん飲むぞという気合の表れなのです。雄大な太平洋に面しているからなのか、よそ者を気さくに受け入れる土地柄でもあります。当時の知事、高知市長とも県外出身なのに人気は抜群でした。初鰹の季節を迎えた今
が、訪れるには一番いい頃なのですが、一つご注意を。地元の人に「お酒は飲める?」と聞かれ、「ええ、少々」なんて答えると、とんでもないことになります。「ほう、2升も飲めるんか」となり、足腰が立たなくなってしまいます。� (深松)▽時間があればデパートの最上階から地下まで見て回るのが楽しみです。普段立ち寄らない階で掘り出し物を見つける喜びは格別です。新聞は情報のデパート。他紙も合わせて、スクエア会員さんの記事発見やお気に入りコーナー、見覚えのある記者の名前、お得情報等、目に入ってくるスピードがだんだん速くなりました。じっくり読み込まれてこそ価値があると思います。僭
せんえつ
越ながら、新聞もデパートみたいに統合せず、それぞれの特性を生かし、人々の生活に潤いをもたらす存在であり続けて欲しいです。� (中林)
「自転車」鈴木 直哉 (経済エディター)
朝日21関西スクエア 会報 No.123●スタッフ小西良昭、浅野稔、永島学、深松真司、相江智也、橋本正人、園真規子
●事務局〒530-8211�大阪市北区中之島3-2-4�朝日新聞大阪本社内TEL�06-6231-0131(内線5048) FAX�06-6443-4431E-mail��[email protected](PDF会報の希望はこちらへ)URL��http://www.asahi.com/kansaisq/
Top Related