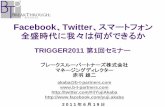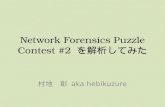S「†一丁下「H - Sophia University ·...
Transcript of S「†一丁下「H - Sophia University ·...

ソフィアサイテック
くnpHdaggerÅ竿誓興会会報
S「dagger一丁下「H
軸憂鞄血
C O- N T 【 N T S 手紙写暮 右上アセチルコリンレセプタとGFP蛍光蛋白の融合体
中全材料中の結晶粒界の写とEPSDによる結晶方位マップ
左下艦i昇温点l分析隷1
1 特集 エネルギーおよび環境と材料技術
10 研究テーマ一覧
14 ただいま研究中
18 研究プロジ工クト
22 掲示板
企業セミナー奨学金の授与報告松本賞
2009年度博士学位論文一覧
2009年度科学研究費補助金採択一覧 受託研究 学外共同研究
2009年度理工学部理工学研究科就職企業一覧
ちょっと拝見
卒業生紹介
9 0 1 2 3
2 3 3 3 3
振興会法人会員
振興会個人会員
編集後記
ト ト
ス ス
ーノ ノ
daggeractor$仇劇旭YO叫mndaggerrom taki咽叩cent紺Shii鵡逼繍触加血喝y Firstistackof01OU叫叩Iltatanearly 叩bl叩lⅦ仰OnJinfin如anintore釦 in sdoncoaldlれさ廿l誠薩廿檜Iackof
WOmOn tOadlOrS tO引汀YS rOb mod01s
Thirdis tho d椚iGUl吋in balanci叩the domalⅦboI叫lⅦU帽h廿檜帽SOa代納Iab With porsonalorIamilylidagger0Fourlhisa lahr細け醐かcentU托u帽鵬tmys00m u叫bwnon
叫血rsquo$叩喝Wnbmr叩柑nOnin
New什喝ramtOS岬叩代Gl血曲伽叩鋤ntW耶l即R紺C鵬帽
InMay2009SophiaUniversityreceivedathree-yeargrant(2009- 2011)fromtheMinistryofEducationCultureSportsScienceand Techno10gy(MEXT)aspartoftheMinistryrsquosprogramldquosupporting ActivitiesforFemaIeResearchersrdquoinscienceandtechnoIogyThe MEXTprogramlaunchedin2006istryJngtOincreasethenunberof WOmenPurSUlngCareerSinscienceandtechno10gyTheprogramhas fundedawide-rangeOfprogramsatJapaneseuniversitiesandreseardl institutesdesignedtoencourageyoungwomenin highschooIsand Universities to take aninterestin careersin what arereferred to as
ldquoSTEMrdquofjeIds(scienceteChno10gyengjneeringandmathematic$) andtoprovidecareersuppo「tforwomenresearchers
AtSophia-aSatalmostalluniversitiesinJapanandoverseas--1he PerCentage Ofwomenfaculty membersin STEM fieldsisslgnificantly
10Werthaninthesocialsciencesand humanitiesln2009womenmade
UP22ofthepermanentSophiafacultybutonly5intheFacu町Of ScienceandTechnoIogyWhile55ofourundergraduatestudentsare WOmenjn science and techno10gy Only19arewomenatthe graduatelevelwhilewomen make up41ofthe totalnumberof graduatestudentsinscienceandtechno10gyOnly14arewomenAs Japan strugglestoconfrontabroad rangeofproblemsbroughtonby thedeclining numberofchildrenitcan no10ngera什Ordtoignorethe POtentialcontributions to science and techno10gy Of half ofits POPulation
IndesignlngaPrOgramtOenCOUrageWOmeninSTEMfieIdsWeneed toconsiderwhysofewwomenchoosethesecareerpathsUntilvery recentlymanypeopleassumedthatmenhadamuchstrongernatura[ aptitudeforSTEM subjectsManyreaders mayremembertheheated debatesin2005whenthethenpresidentofHarvard UniversityLarry SummersSuggeStedthatitwasatleastpossiblethatthesmalInumber Ofwomenin STEM was the result of naturaldifferencesininterdquoectual
aptitude between men andwomenWhenlsawthe Summersrsquo Statementitbroughtbackmemoriesofmyowngraduatestudentdays atthe University of CaliforniaBerke[eyWhenlentered the PhD PrOgramin historytherewere morethan70permanentfaculty members-andnotonewomanOnIyaftertheUnitedStatesCongress PaSSedabirdquoin1972(knowasTitlelX)banninggenderdiscrimination inanyinstitutionreceivlngUSgovernmentfundsdidtheUniversityof Californjabegintomakeaconcertedefforttohirewomeninthesocial SCiencesandhumanities
1fdifferencesinaptitudedonotexplainthesmaHnumberofwomenin STEMfieldsthenwhatdoesAcademicinstitutionsandorganizations inmanycountrieswhichhavesetupprogramstoencouragewomenin SCience andtechno10gyhave reached ageneralconsensusonthe
学術交漬担当副学長
リンダグローブ
sdence and technology
draYSOntheLJniversitysg10blnetYOrkofparlneruniversitiesto establi$rla$yStemOf910baJmentorsforourwomenscholarsThe din細OairnistoproduceldquogLobalレCOmPetentrdquoscholarswhowiJlbe abkbteachardpLJblishinfore短nlanguage$andgivepresentationsat irTtena60naJconferencesWewantourwomenscholarstogoonestep
fur廿檜rrnaSteringtheskiMsthatwillaI10WthemtoseNeaSOrganizersof
intemationalconferencesandresearchprojectsTheprogramalsowirdquo fundpos摘OnSforresearchassistanceforwomenfacultymemberswith $rnallchildrenWillestablishaldquocommunityrdquoofwomenstudentsand researchersformutualsupportandwillundertakevariouseducational
activitiesforstudentsfacultyand prospectivestudentsAprogram
Officehasbeenopenedtocoordinateactivitiesandahomepagewas recentIylaunchedtoprovideaspaceforexchan9eOfinformation 【vwerpsophiaacjpProjectswrsupporu]
Aworkinggroupincruding14facultymembersbothmenandwomen
is organizlng the Sophia programWe have also received strong
SuPPOrtfrom one ofourgraduatesDrArigaSanaea mOlecular bio10gistwhowasthefirstwomento beappointedtoaprofessorial POSitioninthe FacultyofAgricultureatHokkaido UniversityDrAriga received herBSand MSfromSophiaUniversityin1980and1982 andisnownotonlyaJeadingscholarinherfieldbutalsooneofJapanrsquos leadersinthepromotionofwomeninscienceandtechnoIogy
WhiletheMEXT-fundedprogramfocusesonsuppor(ingthecareers OfwomeninSTEMfieldsWereaIizethatmenfacemanyofthesame
ChalLenges aswomenin finding an acceptablebalance between researchworkandpersonalJifeManyyoungermalemembersofthe facu[ty have partnerswhoworkandthey a[sosharethejoysand burdensofraising children andcaringforano義dergenerationlnthe
yearsaheadthenewly-eStab[ishedardquo-Sophiaorganizationtosupporta gender-eqUalworkplace[男女共同参画推進本部]willbestrivingtofind
WayStO makeiteasierforardquomembersofthe Sophiacommunityto balancetheirworklivesincludingteaching and researchandtheir
PerSOnallives
ヾすぎーhellip
ロゴの中央のsumはギリシャ文字のSSOPHIAつまり上智大学のSであ り数学の総加記号でもあります上下の6とTはそれぞれscience (科学)のsとteChnoIogy(妓術)のtのギリシャ文字ですこれら3つの 文字は科学と技術とが融合しつつある現代の状況を示しまた上智 大学のもとに両者を結集させたいという願いを表したものです
呈ネル 奄 切掛壊術 一億炭素社会に向けて-
機能創造理工学科教授 高井 健一
こし汚に コlsquoコざ汗十手rsquoモ
国連での鳩山ステートメント「温室効果ガス
中期削減目標25」は経済界をはじめさまざ
まな立場から賛否両論がでており温暖化対策
をめぐる活発な議論のきっかけとなっている
子供や孫たちが大人になった時の地球を考え
て私たちは何をすべきかとよく問われるが
各家庭や企業における省エネ努力だけでは到底
追いつかない社会システム全体がドラスティ
ックに変革する必要があるしかしエネルギ
ーや環境の問題を解決するための技術開発には
長い年月を必要とし現在の高校生や大学生が
社会の中核として活躍する20~30年後に花を咲
かせるには今からプランニングし解決に向
けた技術のブレークスルーを重ねていかないと
間に合わない
本特集では身近な自動車を例に取り上げ前
半では低炭素脱炭素社会に向けた今後のエネ
ルギー戦略自動車戦略について概説し後半
では普段直接関連があるとは考えにくい「材
料技術」からの低炭素脱炭素社会に向けた貢
献について焦点を絞り現在進行中の国家プロ
ジェクトの研究も含めて紹介する
現在人類は「化石燃料の枯渇」と「地球温
暖化」という2つの危機に直面している世界
で消費されるエネルギーの85を化石燃料から
得ており今後発展途上国のエネルギー増大
が予想される中大きな問題を抱えている1
例えば
①化石燃料から発生するCO2増大による地球温
暖化
②早晩訪れる化石燃料の枯渇(石油は残り約50年)
3政情が不安定な中東諸国に偏在
④イヒ石燃料は持続可能なエネルギー資源でない
などがある化石燃料を燃やして発生する
CO2を再生できれば困らないが我々は植物の
ようにCO2を再生できず増加させる一方であ
るこのエントロピー増大を抑制できる代替エ
ネルギー開発が急務である
ミ撃想琉ユニprimethere4こミミ卓二ミDagger-
上記丑~①の問題点に対し日本政府が2006
年に発表した「新国家エネルギー戦略」では
2030年までにエネルギー効率を30改善石油
依存度を規準の80まで低減を提案また
2007年の「美しい星50(Coolearth50)」では
図1水と水素の循環による再生可能な水素エネルギー社会を目指して
として注目されているが米国では原油輸入
の中東からの脱却による安全保障上のメリット
をより重視する傾向がある
理想とするエネルギー社会を措くと図1のよ
うになる自然エネルギーである太陽風力
水力等から発電し水を電気分解して水素を製
造するその水素を用いて燃料電池内で大気中
の酸素と反応させると排出は水だけで電力と
熱を生み出すまた排出した水から水素を製
造helliphellip と再生可能であり排出物を全く出さな
いすなわち水素製造時も水素利用時もクリー
ンであるゼロエミッションのサイクルが完成す
る一方化石燃料を燃やして発生するCO2
NOxSOxは再生不可能でありそのまま増え
続けてしまうただし現在自然エネルギー
で水素を製造するインフラが整っていないた
め即利用可能な水素の供給として製鉄所の
コークス炉で発生する副生水素ガスなどを当面
利用する研究が進められておりこれだけでも
約500万台の燃料電池車を補える試算である
2050年までにCO2半減を提案しているこれら
の目標達成に向け効率の向上と脱石油の観点
から「21」の革新技術が掲げられ自動車分野
ではプラグインハイブリッド電気自動車
燃料電池車が選定された合わせて水素製造
輸送貯蔵技術も掲げられ水素社会実現が大
きな柱と位置づけられている2ノ
石油エネルギーに替わり永遠に枯渇しない
クリーンなエネルギーとして太陽風力水
力バイオマスなどの自然エネルギー促進が望
まれているただし自然エネルギーは化石燃
料と異なり大量貯蔵できない問題を抱えてい
るしかしこれらの自然エネルギーから「水
素」を作っておけば大量貯蔵大量輸送が可
能なため必要なときに必要な場所で燃料とし
て使用し再び電力を得ることができる しか
も水素は輸入に頼らず国内資源で生産できる
エネルギーでありエネルギーセキュリティー
面からも望ましい燃料である水素社会を目指
す理由として日本では環境問題解決の切り札
今後の環境対応自動牽竃速習 エンジン燃焼改善 摩擦嶺失低減 伝達効率向上
現在地球上のCO2排出量の約20を運輸部
門が占めるがその大半が自動車からのものだ
と言われている3)東京で生活しているとこ
空気抵抗低減 ころがり抵抗低減
れ以上車は必要ないのではと感じてしまうが
世界人口約60億人で自動車が約8億台とすると
車の恩恵を受けている人はたった12である
発展途上国を中心に2030年には16億台まで増
加すると試算4)されており今のままだとCO2
排出の増加は避けられない
自動車に要求される基本機能として「環境」
と「安全」がある特に最近は環境技術で優
位に立つことが自動車産業で生き残る唯一の
道と言われている自動車メーカー各社が自
動車走行時におけるCO2排出低減のために取り
組んでいる技術を図2に示す
燃費向上方法としてエンジンやトランスミ
ッション等の単体効率向上および軽量化や空
気抵抗低減に関する走行抵抗低減を試みてい
るこれらの中で軽量化の効果は非常に大きい
自動車を10軽量化できれば5~10の燃費向
上につながり世界全体でみたら莫大なCO2排
出低減に貢献できるEUでは販売される新車
のCO2排出量を規制する法案を審議中であり
」天然ガス車
図2 自動車走行時のC02排出低減化技術
一
2012年の達成期限にCO2排出削減ペースが遅れ
ると制裁金なども課せられ様々な面で軽量化
は待ったなしの状況にある
一方新動力としてエコカーと呼ばれるハ
イブリッド車プラグインハイブリッド車
電気自動車燃料電池車などの開発が急がれて
いるあるテレビ番組でスーパーカーと環境
に優しい車のどちらに将来乗りたいかを小学生
に選ばせたところ全貞環境に優しい車を選
んでいたことが印象深かった「排気ガスを出
す自動車なんて古い」という時代もすぐそこま
で来ているようだ表1に自動車のタイプ別
のCO2排出燃料補給時間燃料補給インフラ
の比較を示す6)現在ハイブリッド車の普及
が目覚しいが次に来る車としてプラグイ
表1自動車のタイプ別C02排出燃料補給時間インフラの比較
ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

C O- N T 【 N T S 手紙写暮 右上アセチルコリンレセプタとGFP蛍光蛋白の融合体
中全材料中の結晶粒界の写とEPSDによる結晶方位マップ
左下艦i昇温点l分析隷1
1 特集 エネルギーおよび環境と材料技術
10 研究テーマ一覧
14 ただいま研究中
18 研究プロジ工クト
22 掲示板
企業セミナー奨学金の授与報告松本賞
2009年度博士学位論文一覧
2009年度科学研究費補助金採択一覧 受託研究 学外共同研究
2009年度理工学部理工学研究科就職企業一覧
ちょっと拝見
卒業生紹介
9 0 1 2 3
2 3 3 3 3
振興会法人会員
振興会個人会員
編集後記
ト ト
ス ス
ーノ ノ
daggeractor$仇劇旭YO叫mndaggerrom taki咽叩cent紺Shii鵡逼繍触加血喝y Firstistackof01OU叫叩Iltatanearly 叩bl叩lⅦ仰OnJinfin如anintore釦 in sdoncoaldlれさ廿l誠薩廿檜Iackof
WOmOn tOadlOrS tO引汀YS rOb mod01s
Thirdis tho d椚iGUl吋in balanci叩the domalⅦboI叫lⅦU帽h廿檜帽SOa代納Iab With porsonalorIamilylidagger0Fourlhisa lahr細け醐かcentU托u帽鵬tmys00m u叫bwnon
叫血rsquo$叩喝Wnbmr叩柑nOnin
New什喝ramtOS岬叩代Gl血曲伽叩鋤ntW耶l即R紺C鵬帽
InMay2009SophiaUniversityreceivedathree-yeargrant(2009- 2011)fromtheMinistryofEducationCultureSportsScienceand Techno10gy(MEXT)aspartoftheMinistryrsquosprogramldquosupporting ActivitiesforFemaIeResearchersrdquoinscienceandtechnoIogyThe MEXTprogramlaunchedin2006istryJngtOincreasethenunberof WOmenPurSUlngCareerSinscienceandtechno10gyTheprogramhas fundedawide-rangeOfprogramsatJapaneseuniversitiesandreseardl institutesdesignedtoencourageyoungwomenin highschooIsand Universities to take aninterestin careersin what arereferred to as
ldquoSTEMrdquofjeIds(scienceteChno10gyengjneeringandmathematic$) andtoprovidecareersuppo「tforwomenresearchers
AtSophia-aSatalmostalluniversitiesinJapanandoverseas--1he PerCentage Ofwomenfaculty membersin STEM fieldsisslgnificantly
10Werthaninthesocialsciencesand humanitiesln2009womenmade
UP22ofthepermanentSophiafacultybutonly5intheFacu町Of ScienceandTechnoIogyWhile55ofourundergraduatestudentsare WOmenjn science and techno10gy Only19arewomenatthe graduatelevelwhilewomen make up41ofthe totalnumberof graduatestudentsinscienceandtechno10gyOnly14arewomenAs Japan strugglestoconfrontabroad rangeofproblemsbroughtonby thedeclining numberofchildrenitcan no10ngera什Ordtoignorethe POtentialcontributions to science and techno10gy Of half ofits POPulation
IndesignlngaPrOgramtOenCOUrageWOmeninSTEMfieIdsWeneed toconsiderwhysofewwomenchoosethesecareerpathsUntilvery recentlymanypeopleassumedthatmenhadamuchstrongernatura[ aptitudeforSTEM subjectsManyreaders mayremembertheheated debatesin2005whenthethenpresidentofHarvard UniversityLarry SummersSuggeStedthatitwasatleastpossiblethatthesmalInumber Ofwomenin STEM was the result of naturaldifferencesininterdquoectual
aptitude between men andwomenWhenlsawthe Summersrsquo Statementitbroughtbackmemoriesofmyowngraduatestudentdays atthe University of CaliforniaBerke[eyWhenlentered the PhD PrOgramin historytherewere morethan70permanentfaculty members-andnotonewomanOnIyaftertheUnitedStatesCongress PaSSedabirdquoin1972(knowasTitlelX)banninggenderdiscrimination inanyinstitutionreceivlngUSgovernmentfundsdidtheUniversityof Californjabegintomakeaconcertedefforttohirewomeninthesocial SCiencesandhumanities
1fdifferencesinaptitudedonotexplainthesmaHnumberofwomenin STEMfieldsthenwhatdoesAcademicinstitutionsandorganizations inmanycountrieswhichhavesetupprogramstoencouragewomenin SCience andtechno10gyhave reached ageneralconsensusonthe
学術交漬担当副学長
リンダグローブ
sdence and technology
draYSOntheLJniversitysg10blnetYOrkofparlneruniversitiesto establi$rla$yStemOf910baJmentorsforourwomenscholarsThe din細OairnistoproduceldquogLobalレCOmPetentrdquoscholarswhowiJlbe abkbteachardpLJblishinfore短nlanguage$andgivepresentationsat irTtena60naJconferencesWewantourwomenscholarstogoonestep
fur廿檜rrnaSteringtheskiMsthatwillaI10WthemtoseNeaSOrganizersof
intemationalconferencesandresearchprojectsTheprogramalsowirdquo fundpos摘OnSforresearchassistanceforwomenfacultymemberswith $rnallchildrenWillestablishaldquocommunityrdquoofwomenstudentsand researchersformutualsupportandwillundertakevariouseducational
activitiesforstudentsfacultyand prospectivestudentsAprogram
Officehasbeenopenedtocoordinateactivitiesandahomepagewas recentIylaunchedtoprovideaspaceforexchan9eOfinformation 【vwerpsophiaacjpProjectswrsupporu]
Aworkinggroupincruding14facultymembersbothmenandwomen
is organizlng the Sophia programWe have also received strong
SuPPOrtfrom one ofourgraduatesDrArigaSanaea mOlecular bio10gistwhowasthefirstwomento beappointedtoaprofessorial POSitioninthe FacultyofAgricultureatHokkaido UniversityDrAriga received herBSand MSfromSophiaUniversityin1980and1982 andisnownotonlyaJeadingscholarinherfieldbutalsooneofJapanrsquos leadersinthepromotionofwomeninscienceandtechnoIogy
WhiletheMEXT-fundedprogramfocusesonsuppor(ingthecareers OfwomeninSTEMfieldsWereaIizethatmenfacemanyofthesame
ChalLenges aswomenin finding an acceptablebalance between researchworkandpersonalJifeManyyoungermalemembersofthe facu[ty have partnerswhoworkandthey a[sosharethejoysand burdensofraising children andcaringforano義dergenerationlnthe
yearsaheadthenewly-eStab[ishedardquo-Sophiaorganizationtosupporta gender-eqUalworkplace[男女共同参画推進本部]willbestrivingtofind
WayStO makeiteasierforardquomembersofthe Sophiacommunityto balancetheirworklivesincludingteaching and researchandtheir
PerSOnallives
ヾすぎーhellip
ロゴの中央のsumはギリシャ文字のSSOPHIAつまり上智大学のSであ り数学の総加記号でもあります上下の6とTはそれぞれscience (科学)のsとteChnoIogy(妓術)のtのギリシャ文字ですこれら3つの 文字は科学と技術とが融合しつつある現代の状況を示しまた上智 大学のもとに両者を結集させたいという願いを表したものです
呈ネル 奄 切掛壊術 一億炭素社会に向けて-
機能創造理工学科教授 高井 健一
こし汚に コlsquoコざ汗十手rsquoモ
国連での鳩山ステートメント「温室効果ガス
中期削減目標25」は経済界をはじめさまざ
まな立場から賛否両論がでており温暖化対策
をめぐる活発な議論のきっかけとなっている
子供や孫たちが大人になった時の地球を考え
て私たちは何をすべきかとよく問われるが
各家庭や企業における省エネ努力だけでは到底
追いつかない社会システム全体がドラスティ
ックに変革する必要があるしかしエネルギ
ーや環境の問題を解決するための技術開発には
長い年月を必要とし現在の高校生や大学生が
社会の中核として活躍する20~30年後に花を咲
かせるには今からプランニングし解決に向
けた技術のブレークスルーを重ねていかないと
間に合わない
本特集では身近な自動車を例に取り上げ前
半では低炭素脱炭素社会に向けた今後のエネ
ルギー戦略自動車戦略について概説し後半
では普段直接関連があるとは考えにくい「材
料技術」からの低炭素脱炭素社会に向けた貢
献について焦点を絞り現在進行中の国家プロ
ジェクトの研究も含めて紹介する
現在人類は「化石燃料の枯渇」と「地球温
暖化」という2つの危機に直面している世界
で消費されるエネルギーの85を化石燃料から
得ており今後発展途上国のエネルギー増大
が予想される中大きな問題を抱えている1
例えば
①化石燃料から発生するCO2増大による地球温
暖化
②早晩訪れる化石燃料の枯渇(石油は残り約50年)
3政情が不安定な中東諸国に偏在
④イヒ石燃料は持続可能なエネルギー資源でない
などがある化石燃料を燃やして発生する
CO2を再生できれば困らないが我々は植物の
ようにCO2を再生できず増加させる一方であ
るこのエントロピー増大を抑制できる代替エ
ネルギー開発が急務である
ミ撃想琉ユニprimethere4こミミ卓二ミDagger-
上記丑~①の問題点に対し日本政府が2006
年に発表した「新国家エネルギー戦略」では
2030年までにエネルギー効率を30改善石油
依存度を規準の80まで低減を提案また
2007年の「美しい星50(Coolearth50)」では
図1水と水素の循環による再生可能な水素エネルギー社会を目指して
として注目されているが米国では原油輸入
の中東からの脱却による安全保障上のメリット
をより重視する傾向がある
理想とするエネルギー社会を措くと図1のよ
うになる自然エネルギーである太陽風力
水力等から発電し水を電気分解して水素を製
造するその水素を用いて燃料電池内で大気中
の酸素と反応させると排出は水だけで電力と
熱を生み出すまた排出した水から水素を製
造helliphellip と再生可能であり排出物を全く出さな
いすなわち水素製造時も水素利用時もクリー
ンであるゼロエミッションのサイクルが完成す
る一方化石燃料を燃やして発生するCO2
NOxSOxは再生不可能でありそのまま増え
続けてしまうただし現在自然エネルギー
で水素を製造するインフラが整っていないた
め即利用可能な水素の供給として製鉄所の
コークス炉で発生する副生水素ガスなどを当面
利用する研究が進められておりこれだけでも
約500万台の燃料電池車を補える試算である
2050年までにCO2半減を提案しているこれら
の目標達成に向け効率の向上と脱石油の観点
から「21」の革新技術が掲げられ自動車分野
ではプラグインハイブリッド電気自動車
燃料電池車が選定された合わせて水素製造
輸送貯蔵技術も掲げられ水素社会実現が大
きな柱と位置づけられている2ノ
石油エネルギーに替わり永遠に枯渇しない
クリーンなエネルギーとして太陽風力水
力バイオマスなどの自然エネルギー促進が望
まれているただし自然エネルギーは化石燃
料と異なり大量貯蔵できない問題を抱えてい
るしかしこれらの自然エネルギーから「水
素」を作っておけば大量貯蔵大量輸送が可
能なため必要なときに必要な場所で燃料とし
て使用し再び電力を得ることができる しか
も水素は輸入に頼らず国内資源で生産できる
エネルギーでありエネルギーセキュリティー
面からも望ましい燃料である水素社会を目指
す理由として日本では環境問題解決の切り札
今後の環境対応自動牽竃速習 エンジン燃焼改善 摩擦嶺失低減 伝達効率向上
現在地球上のCO2排出量の約20を運輸部
門が占めるがその大半が自動車からのものだ
と言われている3)東京で生活しているとこ
空気抵抗低減 ころがり抵抗低減
れ以上車は必要ないのではと感じてしまうが
世界人口約60億人で自動車が約8億台とすると
車の恩恵を受けている人はたった12である
発展途上国を中心に2030年には16億台まで増
加すると試算4)されており今のままだとCO2
排出の増加は避けられない
自動車に要求される基本機能として「環境」
と「安全」がある特に最近は環境技術で優
位に立つことが自動車産業で生き残る唯一の
道と言われている自動車メーカー各社が自
動車走行時におけるCO2排出低減のために取り
組んでいる技術を図2に示す
燃費向上方法としてエンジンやトランスミ
ッション等の単体効率向上および軽量化や空
気抵抗低減に関する走行抵抗低減を試みてい
るこれらの中で軽量化の効果は非常に大きい
自動車を10軽量化できれば5~10の燃費向
上につながり世界全体でみたら莫大なCO2排
出低減に貢献できるEUでは販売される新車
のCO2排出量を規制する法案を審議中であり
」天然ガス車
図2 自動車走行時のC02排出低減化技術
一
2012年の達成期限にCO2排出削減ペースが遅れ
ると制裁金なども課せられ様々な面で軽量化
は待ったなしの状況にある
一方新動力としてエコカーと呼ばれるハ
イブリッド車プラグインハイブリッド車
電気自動車燃料電池車などの開発が急がれて
いるあるテレビ番組でスーパーカーと環境
に優しい車のどちらに将来乗りたいかを小学生
に選ばせたところ全貞環境に優しい車を選
んでいたことが印象深かった「排気ガスを出
す自動車なんて古い」という時代もすぐそこま
で来ているようだ表1に自動車のタイプ別
のCO2排出燃料補給時間燃料補給インフラ
の比較を示す6)現在ハイブリッド車の普及
が目覚しいが次に来る車としてプラグイ
表1自動車のタイプ別C02排出燃料補給時間インフラの比較
ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

呈ネル 奄 切掛壊術 一億炭素社会に向けて-
機能創造理工学科教授 高井 健一
こし汚に コlsquoコざ汗十手rsquoモ
国連での鳩山ステートメント「温室効果ガス
中期削減目標25」は経済界をはじめさまざ
まな立場から賛否両論がでており温暖化対策
をめぐる活発な議論のきっかけとなっている
子供や孫たちが大人になった時の地球を考え
て私たちは何をすべきかとよく問われるが
各家庭や企業における省エネ努力だけでは到底
追いつかない社会システム全体がドラスティ
ックに変革する必要があるしかしエネルギ
ーや環境の問題を解決するための技術開発には
長い年月を必要とし現在の高校生や大学生が
社会の中核として活躍する20~30年後に花を咲
かせるには今からプランニングし解決に向
けた技術のブレークスルーを重ねていかないと
間に合わない
本特集では身近な自動車を例に取り上げ前
半では低炭素脱炭素社会に向けた今後のエネ
ルギー戦略自動車戦略について概説し後半
では普段直接関連があるとは考えにくい「材
料技術」からの低炭素脱炭素社会に向けた貢
献について焦点を絞り現在進行中の国家プロ
ジェクトの研究も含めて紹介する
現在人類は「化石燃料の枯渇」と「地球温
暖化」という2つの危機に直面している世界
で消費されるエネルギーの85を化石燃料から
得ており今後発展途上国のエネルギー増大
が予想される中大きな問題を抱えている1
例えば
①化石燃料から発生するCO2増大による地球温
暖化
②早晩訪れる化石燃料の枯渇(石油は残り約50年)
3政情が不安定な中東諸国に偏在
④イヒ石燃料は持続可能なエネルギー資源でない
などがある化石燃料を燃やして発生する
CO2を再生できれば困らないが我々は植物の
ようにCO2を再生できず増加させる一方であ
るこのエントロピー増大を抑制できる代替エ
ネルギー開発が急務である
ミ撃想琉ユニprimethere4こミミ卓二ミDagger-
上記丑~①の問題点に対し日本政府が2006
年に発表した「新国家エネルギー戦略」では
2030年までにエネルギー効率を30改善石油
依存度を規準の80まで低減を提案また
2007年の「美しい星50(Coolearth50)」では
図1水と水素の循環による再生可能な水素エネルギー社会を目指して
として注目されているが米国では原油輸入
の中東からの脱却による安全保障上のメリット
をより重視する傾向がある
理想とするエネルギー社会を措くと図1のよ
うになる自然エネルギーである太陽風力
水力等から発電し水を電気分解して水素を製
造するその水素を用いて燃料電池内で大気中
の酸素と反応させると排出は水だけで電力と
熱を生み出すまた排出した水から水素を製
造helliphellip と再生可能であり排出物を全く出さな
いすなわち水素製造時も水素利用時もクリー
ンであるゼロエミッションのサイクルが完成す
る一方化石燃料を燃やして発生するCO2
NOxSOxは再生不可能でありそのまま増え
続けてしまうただし現在自然エネルギー
で水素を製造するインフラが整っていないた
め即利用可能な水素の供給として製鉄所の
コークス炉で発生する副生水素ガスなどを当面
利用する研究が進められておりこれだけでも
約500万台の燃料電池車を補える試算である
2050年までにCO2半減を提案しているこれら
の目標達成に向け効率の向上と脱石油の観点
から「21」の革新技術が掲げられ自動車分野
ではプラグインハイブリッド電気自動車
燃料電池車が選定された合わせて水素製造
輸送貯蔵技術も掲げられ水素社会実現が大
きな柱と位置づけられている2ノ
石油エネルギーに替わり永遠に枯渇しない
クリーンなエネルギーとして太陽風力水
力バイオマスなどの自然エネルギー促進が望
まれているただし自然エネルギーは化石燃
料と異なり大量貯蔵できない問題を抱えてい
るしかしこれらの自然エネルギーから「水
素」を作っておけば大量貯蔵大量輸送が可
能なため必要なときに必要な場所で燃料とし
て使用し再び電力を得ることができる しか
も水素は輸入に頼らず国内資源で生産できる
エネルギーでありエネルギーセキュリティー
面からも望ましい燃料である水素社会を目指
す理由として日本では環境問題解決の切り札
今後の環境対応自動牽竃速習 エンジン燃焼改善 摩擦嶺失低減 伝達効率向上
現在地球上のCO2排出量の約20を運輸部
門が占めるがその大半が自動車からのものだ
と言われている3)東京で生活しているとこ
空気抵抗低減 ころがり抵抗低減
れ以上車は必要ないのではと感じてしまうが
世界人口約60億人で自動車が約8億台とすると
車の恩恵を受けている人はたった12である
発展途上国を中心に2030年には16億台まで増
加すると試算4)されており今のままだとCO2
排出の増加は避けられない
自動車に要求される基本機能として「環境」
と「安全」がある特に最近は環境技術で優
位に立つことが自動車産業で生き残る唯一の
道と言われている自動車メーカー各社が自
動車走行時におけるCO2排出低減のために取り
組んでいる技術を図2に示す
燃費向上方法としてエンジンやトランスミ
ッション等の単体効率向上および軽量化や空
気抵抗低減に関する走行抵抗低減を試みてい
るこれらの中で軽量化の効果は非常に大きい
自動車を10軽量化できれば5~10の燃費向
上につながり世界全体でみたら莫大なCO2排
出低減に貢献できるEUでは販売される新車
のCO2排出量を規制する法案を審議中であり
」天然ガス車
図2 自動車走行時のC02排出低減化技術
一
2012年の達成期限にCO2排出削減ペースが遅れ
ると制裁金なども課せられ様々な面で軽量化
は待ったなしの状況にある
一方新動力としてエコカーと呼ばれるハ
イブリッド車プラグインハイブリッド車
電気自動車燃料電池車などの開発が急がれて
いるあるテレビ番組でスーパーカーと環境
に優しい車のどちらに将来乗りたいかを小学生
に選ばせたところ全貞環境に優しい車を選
んでいたことが印象深かった「排気ガスを出
す自動車なんて古い」という時代もすぐそこま
で来ているようだ表1に自動車のタイプ別
のCO2排出燃料補給時間燃料補給インフラ
の比較を示す6)現在ハイブリッド車の普及
が目覚しいが次に来る車としてプラグイ
表1自動車のタイプ別C02排出燃料補給時間インフラの比較
ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

図1水と水素の循環による再生可能な水素エネルギー社会を目指して
として注目されているが米国では原油輸入
の中東からの脱却による安全保障上のメリット
をより重視する傾向がある
理想とするエネルギー社会を措くと図1のよ
うになる自然エネルギーである太陽風力
水力等から発電し水を電気分解して水素を製
造するその水素を用いて燃料電池内で大気中
の酸素と反応させると排出は水だけで電力と
熱を生み出すまた排出した水から水素を製
造helliphellip と再生可能であり排出物を全く出さな
いすなわち水素製造時も水素利用時もクリー
ンであるゼロエミッションのサイクルが完成す
る一方化石燃料を燃やして発生するCO2
NOxSOxは再生不可能でありそのまま増え
続けてしまうただし現在自然エネルギー
で水素を製造するインフラが整っていないた
め即利用可能な水素の供給として製鉄所の
コークス炉で発生する副生水素ガスなどを当面
利用する研究が進められておりこれだけでも
約500万台の燃料電池車を補える試算である
2050年までにCO2半減を提案しているこれら
の目標達成に向け効率の向上と脱石油の観点
から「21」の革新技術が掲げられ自動車分野
ではプラグインハイブリッド電気自動車
燃料電池車が選定された合わせて水素製造
輸送貯蔵技術も掲げられ水素社会実現が大
きな柱と位置づけられている2ノ
石油エネルギーに替わり永遠に枯渇しない
クリーンなエネルギーとして太陽風力水
力バイオマスなどの自然エネルギー促進が望
まれているただし自然エネルギーは化石燃
料と異なり大量貯蔵できない問題を抱えてい
るしかしこれらの自然エネルギーから「水
素」を作っておけば大量貯蔵大量輸送が可
能なため必要なときに必要な場所で燃料とし
て使用し再び電力を得ることができる しか
も水素は輸入に頼らず国内資源で生産できる
エネルギーでありエネルギーセキュリティー
面からも望ましい燃料である水素社会を目指
す理由として日本では環境問題解決の切り札
今後の環境対応自動牽竃速習 エンジン燃焼改善 摩擦嶺失低減 伝達効率向上
現在地球上のCO2排出量の約20を運輸部
門が占めるがその大半が自動車からのものだ
と言われている3)東京で生活しているとこ
空気抵抗低減 ころがり抵抗低減
れ以上車は必要ないのではと感じてしまうが
世界人口約60億人で自動車が約8億台とすると
車の恩恵を受けている人はたった12である
発展途上国を中心に2030年には16億台まで増
加すると試算4)されており今のままだとCO2
排出の増加は避けられない
自動車に要求される基本機能として「環境」
と「安全」がある特に最近は環境技術で優
位に立つことが自動車産業で生き残る唯一の
道と言われている自動車メーカー各社が自
動車走行時におけるCO2排出低減のために取り
組んでいる技術を図2に示す
燃費向上方法としてエンジンやトランスミ
ッション等の単体効率向上および軽量化や空
気抵抗低減に関する走行抵抗低減を試みてい
るこれらの中で軽量化の効果は非常に大きい
自動車を10軽量化できれば5~10の燃費向
上につながり世界全体でみたら莫大なCO2排
出低減に貢献できるEUでは販売される新車
のCO2排出量を規制する法案を審議中であり
」天然ガス車
図2 自動車走行時のC02排出低減化技術
一
2012年の達成期限にCO2排出削減ペースが遅れ
ると制裁金なども課せられ様々な面で軽量化
は待ったなしの状況にある
一方新動力としてエコカーと呼ばれるハ
イブリッド車プラグインハイブリッド車
電気自動車燃料電池車などの開発が急がれて
いるあるテレビ番組でスーパーカーと環境
に優しい車のどちらに将来乗りたいかを小学生
に選ばせたところ全貞環境に優しい車を選
んでいたことが印象深かった「排気ガスを出
す自動車なんて古い」という時代もすぐそこま
で来ているようだ表1に自動車のタイプ別
のCO2排出燃料補給時間燃料補給インフラ
の比較を示す6)現在ハイブリッド車の普及
が目覚しいが次に来る車としてプラグイ
表1自動車のタイプ別C02排出燃料補給時間インフラの比較
ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

今後の環境対応自動牽竃速習 エンジン燃焼改善 摩擦嶺失低減 伝達効率向上
現在地球上のCO2排出量の約20を運輸部
門が占めるがその大半が自動車からのものだ
と言われている3)東京で生活しているとこ
空気抵抗低減 ころがり抵抗低減
れ以上車は必要ないのではと感じてしまうが
世界人口約60億人で自動車が約8億台とすると
車の恩恵を受けている人はたった12である
発展途上国を中心に2030年には16億台まで増
加すると試算4)されており今のままだとCO2
排出の増加は避けられない
自動車に要求される基本機能として「環境」
と「安全」がある特に最近は環境技術で優
位に立つことが自動車産業で生き残る唯一の
道と言われている自動車メーカー各社が自
動車走行時におけるCO2排出低減のために取り
組んでいる技術を図2に示す
燃費向上方法としてエンジンやトランスミ
ッション等の単体効率向上および軽量化や空
気抵抗低減に関する走行抵抗低減を試みてい
るこれらの中で軽量化の効果は非常に大きい
自動車を10軽量化できれば5~10の燃費向
上につながり世界全体でみたら莫大なCO2排
出低減に貢献できるEUでは販売される新車
のCO2排出量を規制する法案を審議中であり
」天然ガス車
図2 自動車走行時のC02排出低減化技術
一
2012年の達成期限にCO2排出削減ペースが遅れ
ると制裁金なども課せられ様々な面で軽量化
は待ったなしの状況にある
一方新動力としてエコカーと呼ばれるハ
イブリッド車プラグインハイブリッド車
電気自動車燃料電池車などの開発が急がれて
いるあるテレビ番組でスーパーカーと環境
に優しい車のどちらに将来乗りたいかを小学生
に選ばせたところ全貞環境に優しい車を選
んでいたことが印象深かった「排気ガスを出
す自動車なんて古い」という時代もすぐそこま
で来ているようだ表1に自動車のタイプ別
のCO2排出燃料補給時間燃料補給インフラ
の比較を示す6)現在ハイブリッド車の普及
が目覚しいが次に来る車としてプラグイ
表1自動車のタイプ別C02排出燃料補給時間インフラの比較
ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

ンハイブリッド車電気自動車燃料電池車
の順と言われているただし自動車メーカー
は短距離では電気自動車長距離では燃料電
池車のように利用シーンでこれらの車のすみ分
けが起こると予想している経済産業省では
2030年までに日本の総保有台数の40(新車販
売台数の約7割)を燃料電池車や電気自動車な
どの次世代自動車に置き換える目標を掲げてい
る
以下図2の中から低炭素社会に向けた
「軽量化」の取り組みおよび脱炭素社会に向
けた「燃料電池車」の取り組みについて解説す
る
排ガス低減だけでなく「走る曲がる止ま
る」の基本作能に対しても好影響を与える次
世代日動車の普及には時間がかかるのでそれ
までガソリン車ハイブリッド車の燃費向上が
低炭素社会に向けた重要な課題であるそこで
安価で資源の豊富な鉄鋼材料の高強度化への期
待は非常に大きい- しかし鉄鋼材料を高強度
化すると長期間使用中に錆に伴うカソード反
応で水素がけ科内に拡散侵入することによ
り突然破壊する水素脆性の危険性が危倶され
る こ)閏毯を解決しないと自動車へのさらな
る高強度鋼の適朋美牒は難しい
脱炭素社会に向けた切り札「燃料電池牽』
低責務故意臆穐贈魔感動感慨層腰靴
衣1でprimeJthere4たように燃料電池車は走行中に
COJをうミく排出せず2章で示した①~④の課
題を解決てきる切i)札である水素エネルギー
什会primeメミ現に仙ナた日本政府のプランを図3に示
す2020年頃までは政府が水素エネルギー社
会構築をprimeトprimeクアップしその後は民間の力で
普及させるシナリオであるただし水素は室
温で矢作のため固体や液体の化石燃料に比べ
「かさばる燃料_ であるすなわち水素をい
かにコンパクトにいかに軽く輸送貯蔵でき
4章で述べたように燃費向上すなわち
CO2排出低減に対して軽量化の効果は非常に大
きいただし1990年代以降大型車の増加
エアバック等の衝突安全性向上対策カーナビ
等の装備類の増加のため車両重量は増加傾向
にあったそこで安全性を損なわずに軽量化
するため自動車の原材料構成比のうち73を
占める鉄鋼材料の高強度化が急ピッチで進めら
れている7ノなお軽量化の利点は燃費向上
2020年 2030年
拗潜函紺挿
テ一泊淵
図3 日本の水素エネルギー社会実現プラン(資源エネルギー庁資料より)
るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

るシが水透エネルギー社会実現の一つのキー
テクノロジーである当面高圧水素タンクに
よる庄縮水素中心であるが将来的には材料中
に水素を吸蔵させる水素貯蔵材料に置き換えて
いく計画である
燃料電池の原理発見は約200年前にさかのぼ
りその後1968年からアポロ計画で採用され宇
宙で成功を収め次に宇宙から地上に降りて現
在に至っている2000年のシドニーオリンピッ
クの女子マラソンで優勝した高橋尚子選手を先
導した車も排気ガスゼロの燃料電池車である
燃料電池車の特長を以下に記すごP10
①cO2排出なし
②環境有害物質(NOxSOx等)排出なし
③理論発電効率が約83と高い
④多様な燃料から製造した水素を利用可能
(水の電気分解天然ガスエタノール等)
亘騒音振動なし
⑥短時間での水素充填可能
⑦ガソリン車と遜色ない航続距離
燃料電池には内燃機関におけるピストンの
往復運動のような動く部品がなく基本的に動
いているのは水素と酸素だけなので摩擦抵抗
が無くエネルギー効率が高い図4に水素によ
る発電と水素製造反応およびリース販売され
ている燃料電池自動車実験稼働中の水素ステ
ーションの一例を示す走行するときは右への
反応であり水素は大気中の酸素と反応し電気
エネルギーを得てモーターを回して走り水蒸
気のみ排出する究極のクリーンエネルギーであ
る一方自然エネルギー等から得た電気を使
って水素を製造するときは左への反応(水の電
気分解)となる自動車メーカーによって改良
が重ねられトヨタのFCHV-advでは1回の
水素充填700気圧で走行できる航続距離は約
830kmホンダのFCXクラ1)ティでは350気圧
充填で620kmと性能ではガソリン単に見劣りし
ないまた表1で示したように水素充填時
間も数分と短時間でありガソリンと同等であ
るただし燃料電池車の開発担当者によると
「現在の燃料電池車はFlカーのようなものであ
り性能的には十分可能なことが実証されたが
一般の人でも購入できる価格でしかも誰でも扱
え十分な長期耐久性を保証するまで作りこむ
にはまだ時間が必要である」と述べており
いくつかの課題に対し技術的なブレークスルー
が必要であるその中の一つがやはり水素と
接する構成材料の水素脆性克服である
発雷
水素+酸素 電気(熟)+水
作吉井Cいpartdyノ 〔ホシタ声Cズクラリティノ
図4 燃料電池内での発電および水素製造反応と燃料電池車水素ステーションの一例
(トヨタホンダHPより)
雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

雉まDaggerdaggerヤーIニーチニてl-「daggerト-oline∵き浮環
燃料電池車はガソ リン車に匹敵する性能を有
するが電気自動車とは異なり水素ステーショ
ンを全国に新たに建設する必要があるため普
及させるには水素インフラの整備ユユ)が鍵を振っ
ている現在ホンダが実験稼動を進めている
太陽電池式水素ステーション12Jでは太陽光発
電から水の電気分解で水素を製造して車に充填
するというまさに図1で示したような水と水
素による完全循環を達成しているその先は
水素供給を各家庭で行うホームエネルギーステ
ーションを想定し各家庭で製造した水素を貯
蔵しておき燃料電池単に供給あるいは家庭
用燃料電池で発電および温水を家庭に供給す
ることを目指しているすなわちこれは各家
庭に小さな発電所を作ることを意味する
現在最新鋭の大型火力発電システムは電力
の他に発生する熱の大部分を海や大気中へ捨て
ているためエネルギー効率は40~45と小さ
く送電ロスを考慮するとさらに小さくなって
しまう9)一方各家庭に設置される天然ガス
改質型の小型燃料電池は電力だけでなく熟も利
用でき送電ロスもないため電気と熱を合わ
せると75~80と非常に高いエネルギー効率を
達成する当面は既存のインフラ設備である
ガスパイプラインを利用して各家庭で天然ガ
スを改質して水素を製造し発電する計画であ
る1)既に2009年2月から福岡水素タウンプロジ
ェクトにおいて150戸で実証試験が開始してい
る
図5 水素脆性に影響を及ぼす主要3因子
いて員の側面も有している水素は最も小さな
原olinerであるため金属中の原子の隙間を自由に
動きl=Iる 力のかかった状態で使用されること
の多い韓織構造材料は水素の影響を受けて
ある句ミり週後二primeトさな力で突然破壊する「水
素阻作_ が危惧される すなわち図5に示す
ようにけ科こ二応力が負荷された状態で水素が
佳人した甥r二起こる
自動車の oline環境_ と 安全を両立するため
に国際的に高強度綱の適用拡大を急いでいる
が高強堅鋼ほど水素脆性が起こりやすいとい
う間毯を抱えている雨などの水(H20)によ
って鉄鋼材料が錆びる際カソード反応で水素
原子が拡散侵入するためである13)
また燃料電池車の燃料となる水素は室温で
気体であるため体積当たりのエネルギー密度
がガソリンの13(XM程度しかないそこでガ
ソリン車並みの航続距離を確保するには高圧
水素タンクの水素庄を35~70MPa近くまで圧
縮する必要がある= またガソリンスタンドに
代わる水素ステーションでは車載搭載以上の
水素庄を必要とするしかし水素を高圧にす
ると水素分子が金属表面で解離し水素原子
として金属内に拡散侵入してしまう図6に
示すように水素利用社会に必要なインフラの
大部分は水素と讃する可能性があり水素と接
する全ての金属材料において水素脆性が懸念さ
れる
olineす童草間苺点とは
水素はクリーンエネルギーとして脚光を浴び
ているが一方水素エネルギー社会構築にお
J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

J燃蝉署恕卓 デてペンチー
園6 水素利用社会に必要なインフラと課題
(2)水素局部変形助長説
水素が原子間の結合力を低下させるのでな
く転位(結晶中の線欠陥)の運動を促進し
局所的に変形が容易になる説
(3)水素助長ひずみ誘起空孔説
水素が変形に伴って生成した原子空孔を安定
化し延性的な破壊の進行を容易にする説
現在進行中の国家プロジェクトにおいても
「back to the basic」を掲げ一度基礎に立
ち戻って原子レベルから水素脆性メカニズムを
見直し応用研究へ展開する研究体制で進めら
れているこれまで水素が直接金属材科の
力学特性へ影響を及ぼしていると考えられてい
なぜ水素で金属宿料恕鷲娩毛な養母
この数年燃費向上および水素エネルギー社
会構築に向けた機運の高まりから水素脆性克
服に向けた研究は世界中で実施されているが
まだ統一したメカニズム解明に至っていない14)
その原因の一つとして水素は原子番号が一番
小さく金属中へ容易に侵入し著しく速く拡散す
るため破壊直後に材料中から放出してしまい
現行犯で捕らえ実証することが困難なことお
よび水素のような軽元素を検出できる分析装置
も限られることなどが挙げられるもし水
素脆性の本質を解明できれば水素脆性克服に
向けた材料設計指針へ反映で
き安全で環境性能に優れた
高強度金属材科の創製が可能
となる
これまでに擢唱された主な
水素脆性メカニズムを図7に
示す概説すると以下のよう
になる
(1)格子脆化説
水素が格子間に存在する
と隣接金属原子相互の結合
エネルギーを低下させる説 図7 これまで提唱されている主な水素脆性メカニズムの模式図
7
水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

水素を徐々に放出させ分離することに成功し
た現行のTDSでは室温から加熱するため
弱い結合のトラップサイト中の水素を分離でき
なかったが低温TDSを用いることで各種
格子欠陥にトラップされた水素を分離可能とな
った-6ノさらに鉄原子100万個に水素原子1個
という微量水素の定量も可能である今後のプ
ロジェクトにおいて金属内に侵入した水素は
金属中のどこにどのくらいの量どのくらい
の強さでトラップされているかさらには応力
下での水素の挙動1丁の実験的解明を目指す計画
である
たが著者らのグループにより水素は応力負
荷された際に材料中の格子欠陥(主に原子空
孔クラスター)形成を促進する役割でありそ
の形成促進された格子欠陥が水素脆性の直接的
な因子であるという新しい実験事実も得られつ
つあるユ5ノ
ふ-there4二Daggerdaggerニーthere4デーこ oline-ミニりつ
現在のように高度に発達した科学技術におい
て新しい機能を持った材料を開発するには従
来のような錬金術的な手法では難しくナノ
さらには原子レベルから解析し積み上げてい
くことが近道であると言われている囲7で示
したように水素が格子間転位原子空孔等
どこにトラップされているかを解明できる技術
開発の要望を受け国家プロジェクトの中で試作
した低温TDS(ThermalDesorpdonSpectrometer)
の外観を図8に示す各トラップサイトと水素の
結合力の遠いを利用し-200の低温から加熱
することで弱い結合のサイトにトラップされた 図8 金属材料中の水素トラップサイト同定のために試
作した低温TDS装置の概観
図9 純鉄中の各種格子欠陥にトラヅプされた水素のピーク分離の模式図(a)現行TDS
(b)低温TDS
界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

界中の研究者が競いしかも進行中の国家プロ
ジェクトでは物理化学機械電気材料hellip
などの異なる分野の研究者が同じ目標に向かっ
て協力しながら遂行しておりこのような研究
テーマも数少ない本学理工学部は「複合知」
を駆使し「人間と環境の支援を担う人材育成」
を使命としているエネルギー環境問題が深
刻化するころ社会の中核として活躍する現在の
高校生大学生若手研究者の皆さんにはま
ずはそれぞれ人と違った分野の専門を徹底的に
掘り下げその分野の第一人者を目指して欲し
いその後は各専門を軸として少しずつ異なっ
た専門家と協力し環境エネルギー問題をはじ
め何らかの形で世界に貢献できる研究者技術
者として飛躍することを期待するまたこの
ような人材を育成できれば幸いである
世界から尊敬さ覿愚国巻層魔鶴橋
もし日本が安価な燃料電池自動車の実用
化に成功したら世界をリードできるインテ
ルのチップが世界中のパソコンに使われるのと
同じように日本企業が作ったモーターが世界
中の自動車に使われるだろう」(元多摩大学長
中谷巌氏)と述べている日本がどんなに経済
大国となったとしても世界から尊敬されること
は少ないがもしエネルギーおよび環境問題
に貢献する製品を開発普及させたらきっと
世界中から感謝され尊敬される国となるだろう
本特集で取り上げた課題はほんの一部である
が技術的コスト的に実現するのは容易でな
いしかし科学技術に携わる身としては簡
単に解決する課題では挑戦する意味がない世
参考文献
1)国土交通省国土交通政策研究所ldquo水素エネルギー社会におけるインフラ及び都市住宅に関する研究rdquo国土
交通政策研究第59号(2005)
2)山本修榊田明宏松田和人柏木芳治江口徹福本紀ldquo燃料電池車用水素系部品開発からの水素脆化研
究への期待rdquo水素脆化研究の基盤構築フォーラム研究会シンポジウムp1(2009)
3)日本鉄鋼協会編ldquo自動車はここまで軽量化できるrsquorsquoふえらむVOl6p930(2001)
4)鈴木正実ldquo未来の自動車と鉄への期待rdquoふえらむVOl10p716(2005)
5)梶川義明ldquo環境負荷低減に向けての自動車材料技術rdquoまてりあVOl39p25(2000)
6)噺日本自動車研究所ホームページ(httpwwwjariorjp)グラフィックTheAsahiShimbunより一部抜
粋
7)杉山香里ldquo軽量化と衝突安全性の両立に貢献する鉄鋼材料技術rdquoふえらむVOl11p766(2006)
8)杉山香里ldquo水素ステーションが身近になる日rsquorsquoふえらむVOl9p692(2004)
9)石井弘毅燃料電池がわかる本オーム社出版局(2001)
10)LLeveen著宝月幸彦訳水素日刊工業新聞社(2004)
11)山地憲治水素エネルギー社会エネルギー資源学会(2008)
12)為乗浩司ldquo自動車を取り巻く環境変化とFCVのエネルギーマネージメントrdquo平成20年度電気学会産業応用部
門大会講演集p127(2008)
13)松山晋作遅れ破壊日刊工業新聞社(1989)
11)南雲道彦水素脆性の基礎内田老鶴圃(2008)
15)KTakaiHShodaHSuzukiand MNagumoldquoLattice defects dominatinghydrogen degradation ofmetalsrdquo
一1ctaMaterialiaVOl56p5158(2008)
16 高井健一鈴木啓史ldquo各種組織因子を含んだ水素の存在状態解析に関する実験的研究rsquorsquo鉄鋼材料の革新的高
強度高機能化基盤研究開発プロジェクト 第1回シンポジウム講演予稿集p93(2009)
1T primet田裕樹鈴木啓史高井健一萩原行人ldquo弾性塑性変形過程における純鉄およびIncone1625の水素放出
挙動【鉄と鋼VOl95p573(2009)
上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

上智大学理工学
研究テーマー 物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
上智大学学部学生数10538名 上智大学大学院学生数1062名
理工学部学生数 理工学研究科学生数 前期 後期 合計 理工学部教月数 教授 准教授 講師 助救 助手 合計
1 4 0 35 機械工学科 電気電子工学科
数学科
物理学科
化学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科
情報理工学科
機械工学専攻 0 1 1 物質生命理工学科 17 13
電気電子工学専攻 0 4 4
3 4 2 2 9 4 7 0 0 9 0 1 2 5 6 7
2 1 1 1 2 2 2 2
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
機能創造理工学科 23 9 1
1 3
理工学専攻 359 21 380 情報理工学科 17 12 5 1 0 35 計 計 362名 30名 392名 計 57名 34名 7名 8名 1名107名
(2009年10月1日現在)
敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

敷 授板谷清司
敦 授大井隆夫
教 授梶谷正次
教 授幸田清一郎
教 授小駒益弘
教 授スコットハウエル
教 授南部伸孝
教 授早下陸士
教 授増山芳郎
教 授陸川政弘
教 授長尾宏隆
准教授遠藤明
准教授木川田喜一
准教授久世信彦
准教授鈴木教之
准教授高橋和夫
准教授竹岡裕子
准教授内田寛
講 師杉山徹
助 教臼杵皇展
助 教田中邦翁
助 教橋本剛
助 教藤田正博
セラミックス原料粉体の合成と性質
同位体効果の解明とその理工学への応用
含硫黄金属錯体の合成反応性機能性
界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
プラズマを用いた高機能表面の作製
化学英語科学英語
化学反応の理論的解明と機能分子設計
超分子形成に基づく新しい分離分析法の開発
均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成
機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム
金属舘体の合成と配位子反応を利用した物質変換
機能性金属錯体の合成および電気化学特性
化学的手法による火山活動モニタリング
気体電子線回折マイクロ波分光法計算化学による分子構造解析
有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
機能性高分子材料の創製と電気光学特性評価
有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜推積プロセスの開発
光反応を利用した含硫黄金属錯体の合成と機能評価
天然物化学生物活性天然有機化合物の化学的研究
プラズマによる薄膜堆積表面改質及びプラズマ診断
金属錯休または電気化学を用いた新しい分離分析法の開発
イオニクス材料の合成と機能評価
教 授 東善郎
教 授高柳便暢
教 授田中大
准教授岡田邦宏
准教授星野正光
放射光科学原子分子物理学
原子およびイオンの多電子励起に関する研究
電子分光による原子分子物理学の研究
イオントラップによる原子原子核の分光学的研究および低温イオンー分子反応の研究
電子陽電子多価イオン放射光を用いた原子分子物理学の実験的研究
教 授田宮徹
教 授林謙介
教 授安増茂樹
准教授神澤信行
准教授小林健一郎
准教授千葉篇彦
准教授牧野修
准教授斉藤玉緒
ヘビ毒遺伝子の構造と発現機構の解明
神経細胞の形態形成と機能分化
膵化酵素の発生進化学
運動タンパク質の細胞生物学
環境適応の生物学
脳の機能と行動発現
微生物を用いた遺伝生化学
細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
11
研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

研究テーマ一覧 助教以上
環境融和型水圧宅区動システム
工作機械の高度化およびその高精度高能率評価法
Hinfin制御系の設計および実プラントヘの応用
繊維強化複合材料構造の損傷および破壊
機械系構造物の運動振動解析
水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
機能性流体および流体解析
高度輸送システム探査システムのダイナミクスと制御
計算固体力学
先進鋼鉄材料の性能評価
多変数制御系および適応制御系の設計理論
高精密マイクロ加工プロセスとその複合化環境負荷低減化技術
粘弾性体の力学特性とその応用
内燃機関における熟伝達の研究
確率システムの解析と制御システムヘの応用
高度医療技術を支える生体機能材料の構築
水素環境下での金属材料の強度と破壊
教 授池尾茂
教 授清水伸二
教 授申鉄龍
教 授未益博志
教 授曽我部潔
教 授高井健一
教 授築地徹浩
教 授嘩道佳明
教 授長嶋利夫
教 授萩原行人
教 授武藤康彦
准教授坂本治久
准教授佐藤美津
准教授鈴木隆
准教授笹川徹史
准教授久森紀之
助 教鈴木啓史
半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
ナノ構造デバイスを用いた光集積回路
超伝導及び関連技術のエネルギー応用磁気浮上と搬送システム
ナノ量子効果半導体の創造と素子応用
新半導体材料の創成とデバイス応用
電気機器応用システムの高効率制御法
電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
教 授岸野克巳
教 授下村和彦
教 授高尾智明
准教授菊池昭彦
准教授野村一郎
准教授宮武昌史
助 教中村一也
字音論宇宙物理学
光物性非線形光学
低温における量子輸送現象の理論的研究
強相関電子系における電子物性
低次元強相関物質のNMRとFLSR
薄膜の成長遷移金属酸化物光触媒表面科学
原子核物理学に関する理論的研究
低次元系及び半導体ナノ構造の物性
凝縮系物理学に関する理論的研究
量子スピン系強相関系の多重極限環境下の光物性
強光子場と原子分子の相互作用応用光学
超高速非線形分光
教 授伊藤直紀
教 授江馬一弘
教 授大槻東巳
教 授桑原英樹
教 授後藤貴行
教 授坂間弘
教 授清水清孝
教 授関根智幸
教 授高柳和雄
准教授黒江晴彦
講 師水谷由宏
助 教稗田英之
1ワ
ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

ResepartrChgro岬$ 研究テーマ一覧
教 授荒井隆行
教 授川中彰
教 授熊倉鴻之助
教 授笹川展幸
教 授田中昌司
教 揮田中衛
准教授田村恭久
准教授山中高夫
講 師藤井麻美子
音声コミュニケーション(音声科学聴覚科学)音声の福祉工学障害者支援音声信号処理音響学音響教育音響音声学
視覚情報処理画像映像の符号化3次元画像モデル生成コンピュータグラフィックス視覚パターン情報の認識
シナプス伝達特に神経伝達物質放出機構の神経化学神経生理学的研究
神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
脳と心の情朝学システム脳科学精神疾患の脳科学モデル人間と動物モデル学習記憶認朴行動に関する実験データの統計解析モデルグ
情報タイナミックスセルラーニューラルネット画像処理〉」Sl網膜の情報処理回路解析機械学習データマイニング
教育工学eラーニング技術
知覚情郭処理知的センシンクシステムパターン認識匂いセンシングシステム
医用光工学医用電子工学
教 授服部武
教 授和保孝夫
准教授炭親鳥
講 師工藤輝彦
移動通信方式高速パケット通信方式位置積出無線」ANスペクトル拡散通信方式ワイヤレスインターネットセンサーネットワーク
超高速低消費電力集積回路アナログデジタル信号変換技術多情論理回路ナノ構造電子デバイス
生体医工学(超音波電磁波計測治療)医用超音波生体情報学計測システム工学省エネ可視化情報学環境計測
光ネットワーク光交換非線形光学光ファイバ工学
教 授伊藤潔
教 授藤井進
教 授伊呂原隆
准教授高岡詠子
准教授夫人郁子
准教授ゴンサルベス タデウ
准教授川端亮
助 教宮本裕一郎
ドメイン分析モデリング情報システム工学ソフトウェア工学システム評価技術
生産システム工学システムシミュレーション
生産物流システムの最適化
データベー ス工学ウェブアプリケーション
情新メディアコミュニケーション学コンパーサルデザインバイアフリーGISITS
知識工学シミュレーション工学
ソフトウエア生産技術協調工学
組合せ最適化離散アリゴリズム数理計画オペレーションズリサーチ
教 授大内忠
教 授加藤昌美
教 授権田健一
教 授田原秀敏
教 授辻元
教 授中島倭樹
准教授石田政司
准教授角皆宏
准教授都築正男
准教授横山和夫
准教授渋谷智治
講 師後藤聡史
講 師五味靖
講 師平田均
複素領域における偏微分方程式
複素多様体の幾何学的構造
代数群と有限群の表現代数的組み合わせ論
特異点をもつ偏微分方程式の研究
複素多様体論
量子群量子展開環
4次元多様体論ゲージ理論
整数論構成的ガロア理論
保型形式と整数論
組合せ位相幾何学
符号理論情朝数理
作用素環論
代数群Hecke環の表現論
非線形偏微分方程式数理物理
11
ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

ただいま御恩中 上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します
物質生命理工学科
南部 伸孝 「スーパーコンピュータを用いた分子科学」
斉藤 玉緒 「細胞の言葉に耳を傾けたい」
情報理工学科
石田 政司 「4次元多様体論-4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-」
川端 亮 「ソフトウエアの仕様を記述したダイアグラムの再利用」
スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

スーパーコンピュータを用いた
分子科学 亀も
環化学
があり九州大学から春に赴任した南部と申し
ます= 書門は理論化学計算化学になります特に
この号楕が配布される頃には次世代スーパーコンピ
ニータ事業の政治的決着がついているものと思われ
ますが久しぶりに「スーパーコンビュータ」(略し
てスパコン)という言葉が世の中を賑やかしていま
す私の寺門はこのスパコンを用いた分子科学と
なりますではどのように計算をするか高校生の
方も興味を持たれることでしょうから簡単に述べま
す端的には物理化学定数のみを与えて1子現象
を記述するためのシュレーティンガ一方程式をコン
ピュータ上で解き予想される観測値を理論的に求
めます但し原子や分子の動きに対し近似を導入
すれば我々の世界の運動(例えば電車の運動)
と変わらない形で求めることができますその一方
厳密に解ければ様々な実験を行わずとも物質を作
り出すことができるはずです夢のような話ですが
その夢を追い続けてかれこれ20年以上になります
また日本は歴史的にこの分野において世界的にも
先駆けており福井謙一先生がノーベル賞を受賞さ
れます「数学ができる子は化学をやりなさい」と
高校の先生が言っていました今は多分生物がそ
れになっているような感じがいたします
スーパーコンピュータ
さて話題のスパコンですが恐らく10年も経て
ば我々の身の回りに現れますなぜなら今宮さま
が使用されているPCの性能は10年前のスパコンの
性能に近いものだったからです「世界一」ばかりが
問われているようですが10年先の研究が10年後の
豊かさをもたらす軌こなっていますもう少し議論
し削減するべきところはすべきと考えます
成層圏における同位体濃縮現象
前置きがながくなりましたが昨今地球温暖化が
叫ばれていることから環境に関する私の成果の一つ
を簡単にご紹介いたします大気において窒素分子
に次いで存在量が多い窒化物が一酸化二窒素(N20)
ですご存知のように窒素分子は極端に不活性な気
体ですがN20はそれに比べるとやや不安定な分子で
あり生物地球化学的な窒素循環の中で中心的な役
割を果たしていますまた京都議定書の中で取り
上げられた温室効果ガスの一つであり成層圏にお
けるその酸化反応が触媒となりオゾン層破壊の主な
要因となっていますさらに大気中の濃度が産業
化以前のレベルより約17も増加しているのが現
状ですところがこの分子の全地球上の総排出量
見積もりが大変困難なため結果として大気におけ
教授 南部 伸孝
る同位体分析を行い総量試算を強いられています
そしてその観測は数々の野外実験によりなされて
いますその中で重要な同位体種として14N14N160
(略して446)456糾6556447448が上げら
れます主な発生源である土壌及び海洋中のバクテ
リアが対流圏の空気に比べて重い窒素や酸素の同位
体含んだN20を消費させ軽いN20を生成しています
一方拡散王が不明ではありましたが大気におけ
る消滅メカニズムは大変明解であります90が成
層圏の紫外線窓領域における光分解であり残り
10が酸素原子との反応ですさらに東京工業大
学の吉田尚弘教授らの野外観測により同位体濃縮現
象が観測されその現象を筆者らは量子論に基づく
厳密計算を行い原因を定t的解明することに世界
で初めて成功しましたこの結果から大気循環シミ
ュレーションにおいてもN20分子に関する定量的な見
積もりが可能となりました現在は硫黄のサイクル
を調べています
細胞の言葉に
耳を傾けたい
細胸性粘菌とは
研究対象として細胞性粘菌と言う生物を使ってい
ます細胞性粘菌は土壌にいる微生物で多細胞体制
を形成する最も始原的な生物ですその生活史の中
に単細胞と多細胞の両方の時期を持ち更に形態
形成の最終段階である子実体が柄と胞子のわずか2種
類の細胞からなると言う特徴を持っています2000
年には米NIHにより有用モデル生物の一つとして選
ばれまた2004年には国際共同プロジェクトとして
全ゲノムの読解が終了しました
和脂分化ノギターン形成機構の解明
どのように生物の形ができてくるのかつまり細
胞分化パターン形成は多細胞体制を最もよく特徴
づける過程でその機構の解明は基礎生物学の重要
な課題の1つですこの間題を分子のレベルで解明す
る事を目指しています細胞性粘菌は発生の最終
段階である子実体が柄と胞子のわずか2種類の細胞か
らなるので分化パターン形成の研究に適したモデ
ル生物です
細胞性粘菌では形作りの分子(分化誘導分子)と
ノて植物等の二次代謝産物であるポリケタイドと呼
Jれる分子が中心的役割を果たしていますその中
てもDIF-1と呼ばれるポリケタイドは柄細胞をつくる
のに重要な役割を果たすと考えられてきましたDIF-
1の発見からほぼ30年が経ちますがこの分子が生体
内でどのような働きをしているの力りこついてはは
っきりとした結論が出ていませんでした昨年この
間蓮をDIF-1の生合成経路に欠損をもつ変異体を使っ
て解明しました
新規ポリケタイド合成酵素の解析
細胞性粘菌の全ゲノム情報を調べてみると40個
ものポリケタイドまたは脂肪酸合成酵素の遺伝子を
見つけることが出来ましたこれらは細胞性粘菌の
コーディング領域の約2を占めていますつまり細
胞性粘菌はコーディング領域の多くの部分を二次代
謝産物の生合成に関わる遺伝子のために使っている
ようでいろいろな化合物の合成に関して大きなポ
テンシャルをもっていると考えられます
これらの生合成連絡の解析の手始めとして柄細
胞分化誘導分子DIF-1の合成を司る酵素としてハイブ
リッド型ポリケタイド合成酵素(PKS)のldquoSteeLyrdquo
を同定しましたこの酵素は原生生物で最初に同定
されたPKSであると同時にⅠ型PKSとⅢ型PKSとい
う異なる合成システムが融合すると言う珍しい構造
を持つものでした
現在このSteely酵素についてこのような特異な
准教授 斉藤 玉緒
構造を持つ酵素は他の粘菌の仲間にも存在するのだ
ろうかまた異なった2つの酵素がどのように協調
して働いているのだろうかと言う観点から研究を
進めています
移動体の運動にかかる力の解析
細胞の集団の運動がどのようにして協調のとれた
ものになっているのかと言う問題は多細胞生物
の形態形成の過程を知る上で一つの大きなポイント
になると考えていますDIF-1の生合成を司るポリケ
タイド合成酵素Stee岬欠損樵では運動にも大きな欠
損が生じ体が途中で切れてしまいますこのよう
な欠損がどうして起きるのか細胞の運動の組織化
に関するシグナル伝達の側面と運動の力学的な側面
の両方から解析したいと考えています
細胞は常に自然環境や自分のまわりにいる細胞と
コミュニケーションをとっていますつまり細胞
にはそれぞれの「言葉」(化学物質)があるのです
この細胞が発する言葉に耳を傾けることによって
生命や自然環境を理解したいと考えています
低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

低次元量子スピン系の物性
永久磁石は強磁性体で自発磁化を持ち磁場を発
生します自発磁化は電子の重要な属性であるスピ
ンが起源です物質中のスピンは互いに圭子力学的
効果によって相互作用しスピンが規則的に整列す
るときに物質は磁性体と呼ばれ同じ方向に揃った
場合は強磁性になり互いに反対方向に揃ったとき
反強磁性になりますこのような磁性を示す物質は
銅(Cu)やバナジウム(or)などの遷移金属原子等
の同期律表の中で限られた原子イオンだけですま
た私達の住んでいるのは三次元の世界ですが磁
性体の中には格子をつくるイオンのスピンがある
方向にだけ強く相互作用した擬一次元磁性体があり
ますそうした擬一次元反強磁性体では1子効果
が願在化するため通常の三次元反強磁性体と遣う
特異な相転移や磁性を示すことが分かってきまし
た私達の研究室ではこの次元性をキーワードに
低次元量子スピン系の物性を低温強磁場高圧
下でレーザー光を便用した光の非弾性散乱である
ラマン散乱等で研究してきました
擬一次元系ではもともと秩序状態が揺らぎのため
不安定でスピンと格子が強く相互作用した系では
低温で自ら格子変形を起こしスピン対をつくり非
磁性なスピン一重項状態になるスピンバイエルス
転移を起こしますこの基底状態とスピン三重項励
起状態との間にスピンギャップが現われます
我々はラマン散乱の手法を用いてこの励起状態であ
る素励起を観測し擬一次元反強磁性体CuGe03で
のスピンバイエルス転移を研究し不純物や圧力
磁場効果を解明しましたまたスピン梯子構造を
持つNaV205ではV4+とV5一イオンの電荷秩序によ
るスピン一重項基底状態の形成の機構を強磁場や
高圧下のラマン散乱の研究で解明しました
これらの相転移は低次元性のために現われたもの
で磁場や圧力の外場を印加すると低次元性を強め
たり弱めたりできますまた相互作用している
10supe2~10supe3個cm〇のスピンや電子が協力して一つの新
しい基底状態をつくる多体効果による物理現象で
す=
更に低次元系ではありませんがスピン一重項
基底状態を作るスピンダイマ一物質TICuCl3では
磁場を印加するとスピン三重項励起のマグノン粒子
がボーズアインシュタイン凝縮(BEC)を起こし
反強磁性相転移を起こすことが分かって来ました
私達はラマン散乱でこのBEC相の励起状態である素
励起を始めて観測し詳細に研究しました
反強磁性体ではスピンが反平行に揃いますしか
し正三角形を作る構造では二つのスピンは互い
に反平行になることが出来ますが三つ目のスピン
教授 関根 智幸(左)
准教授 黒江 晴彦(右)
はどちらか一方のスピンに対して平行に並んでしま
いフラストレーションがたまった状態になります
このフラストレーションは四面体構造でも現れま
す最近私達はこのフラストレーションを持つ量
子スピン系に興味をもち四面体スピン構造を持つ
擬一次元反強磁性体Cu3M0209を精力的に研究して
いますこの系ではフラストレーションと一次元圭
子揺らぎが競合し新しい磁気秩序相や誘電特性の
異常などマルチフェロイックな物性が期待できま
す
その他緑色半導体レーザー等の応用や擬一次元
系の物性が期待できる柱状ナノ構造を持つ半導体
ナノコラム結晶の物性に興味を持ちプロジェクト
の共同研究も進めています低温高圧強磁場の
多重極限下や顕微鏡下の光物性の装置開発なども行
っています新しい秩序相や素励起を見つけようと
研究室のメンバーと楽しく研究しています
安心して使える材料の研究
材料とその重要な特性である破壊特性について研
究しています学部の講義で云えばいずれも片仮名
の科目名となっているマテリアルサイエンスとフラ
クチャメカニックスを害区億して問題解決に当たって
います材料についてよく言われるのは「使われて
こそ材料」ということです材料はある条件がそろ
うと壊れる破壊することがありますそこでど
のような環境条件あるいは力学的な状態で破壊を起
こさずに使えるかを見極め必要な機能を発揮させ
ることが目的となります逆に必要な機能を発揮
させるにはどのような偉い方をしなければならない
かを示すことにもなります研究内容は民間企業
学協会と連携して進めているものがほとんどすべて
となっています経済産業省や文部科学省の国家プ
ロジェクトとなっている研究テーマにも取り組んで
います
最近政府は25の炭酸ガス削減を目標に掲げま
した地球環境問題省資源省エエネルギーリ
サイクル性持続ネ土会安全安心社会の実現も頻
術研究開発において重要な課題となりますその
ための大きな柱となるのが構造物部材部品の軽
王化ですそれを可能にするのは使っている材料を
高強度化することになりますところが材料は-
般的に高強度になると延性や根性(破壊特性)
は低下しますこれを強度延性バランス強度
執性バランスといい避けられないことですそれ
に打ち勝って高強度化にするにはブレークスルーと
なる技術開発が必要となり破壊に対する評価技術
も格段と発展させて破壊を予知できるようにするこ
とが安心安全につながります
破壊も多様で延性破壊脆性破壊疲労破壊
(金属疲労という言葉は新聞紙上をにぎわせました)
が代表的ですが高強度の材料で無視できないもの
に水素の遅れ破壊があります有名なのがボルトの
遅れ破壊ですボルト締結後しばらくはなんら問
題はないのですが場合によっては数ヶ月あるいは
数年たって突然破壊することがあるのでこのように
名付けられました侮っている間に雨水などで錆び
が起こりそれにともなって水素が発生してボルト
鋼材中に侵入しボルトのねじ底に集まって破壊を
引き起こすことが原因です遅れ破壊をはじめとす
る水素による破壊メカニズムや影響因子の解明水
素に対する材料の抵抗力の簡易評価技術などに取り
組んでいますボルトの遅れ破壊の評価はボルト
の締結状態を再現した長時間を要する試験が主流で
非常に手間のかかる方法でしたそこで通常の機械
教授 萩原 行人
試験速度により数分で評価ができる方法(CSRT
ConventionalStrainRateTest法)を提案し高い評価
を得ています高井健一教授鈴木啓史助教久森
妃之助教とともに材料科学グループに属しています
が当グループは水素にかかわる研究において国内
でも有力な拠点となっています
省資源リサイクル性を確保した21世紀の鉄鋼材
料として結晶粒径をこれまでの110以下にした超微
細粗鋼が注目されていますこの技術は高強度と高
延性を両立させるものですしかし超微細粗鋼に
も弱点がありセバレーションという栃原方向のは
く離割れが起こりやすくなることです通常はその
方向に力がかかることはあまりありませんが力学
的にセバレーションの発生条件を解明して安全安
心な偉い方を示す研究も行っています
これらの研究に学生は新鮮なアイデアを出して取
り組んでいますそして毎年学会の講演大会で積
極的に発表し活躍しています
1ん
4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

4次元多様体論 -4次元微分ポアンカレ予想とその周辺-
宇宙から地球を見ると丸く見えますが自分のま
わりの狭い範囲だけを見ると平らに見えます即ち
大域的に見ると丸く曲がっていますが局所的に見
ると平面です平面は2つの実数の組全体の集合と
考えることができますがこのような集合は2次元
ユークリッド空間とよばれます局所的に2次元ユ
ークリッド空間と同じであるような集合を数学では
2次元多様体とよびます地球の形を理想化した数
学的対象である2次元球面即ち3次元空間内の原
点からの距離が1であるような点全体の集合は2次
元多様体の最も典型的な例ですさらに一般にcap
個の実数の組全体の集合を考えることによりcap次
元ユークリッド空間の概念を導入することができま
す局所的にcap次元ユークリッド空間と同じである
ような集合をcap次元多様体とよびますこれは2次元
多様体の高次元版です同様に3次元球面4次元
球面5次元球面など2次元球面の高次元化が考えら
れます多様体の概念が世に出たのは1854年に
ドイツのゲッチンゲン大学で行われたリーマンによ
る講演が最初だったといわれています
一方ポアンカレは1895年の論文とその後約10
年の間に書かれた5つの補稿の中で現在代数的
トポロジーとよばれる数学の1つの分野の大網を確
立しました1904年に書かれた第5の補稿の中で
現在ポアンカレ予想とよばれる予想を提出しまし
たそれは3次元球面に代数的トポロジーの意味で
近い3次元多様体そのようなものを3次元ホモトピ
ー球面とよびますがそれは3次元球面に連続的に
変形できるであろうというものです正確には
「3次元ホモトピー球面は3次元球面に位相同型であ
る」という予想ですポアンカレ予想は100年もの
長きに渡って数学者を悩ませ続けてきましたNHK
の番組として特集が組まれるなと広く関心を集めま
したがポアンカレ予想は2003年にべレルマンに
よって解決されました彼はリッチフローとよばれ
る多様体の変形を言己述する微分方程式をエントロピ
ーなどの統計力学からのアイデアを便って解析する
ことにより予想を解決しました因みにこの業績
によりペレルマンは2006年の国際数学者会議で
フィールズ賞(数学のノーベル賞)を受賞するはず
だったのですが辞退したことでも話題になりました
さて数学者はポアンカレ予想が解決される以前
に予想を高次元化した一般化されたポアンカレ予
想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球面に位相同型で
ある」を定式化しそれを解決しようとしていました
これは次元によって解決方法が著しく異なりしか
も最初に5次元以上の場合が1961年が解決され続
いて1982年に4次元の場合が解決され最後に3次
元の場合が2003年に解決されるという興味深い歴
史を持っていますさらに位相同型より強い条件で
准教授 石田 政司
ある微分同相という概念があり微分ポアンカレ予
想とよばれる予想「cap次元ホモトピー球面はcap次元球
面に微分同相である」も定式化されていました驚
くべきことに5次元以上では予想に対し反例が存
在することが1956年に判明しており球面に位相
同型であるが微分同相でないホモトピー球面はエキ
ゾチック球面とよばれ5次元以上ではエキゾチッ
ク球面が存在することが知られています一方3
次元エキゾチック球面は存在しないことが知られて
いるのですが4次元エキゾチック球面の存在非
存在問題即ち4次元微分ポアンカレ予想は未だ
解決されていませんこのような大きな研究の流れ
の中私は4次元微分ポアンカレ予想周辺を含む4
次元多様体論の様々な問題にリッチフローやゲー
ジ理論と呼ばれる物理学から影響を受けた理論を応
用し解決することに強い関心をもって研究を進めて
きましたこれまでの研究成果から4次元微分ポ
アンカレ予想が否定的に解決される日もそう遠くな
いのではないかと夢想しています
ソフトウェアの仕様を
記述したタイアグラムの再利用
現在多くの分野でコンピュータが使われていま
すそしてそのコンピュータに仕事をさせるため
のソフトウェアが動いていますソフトウエアの開
発は分析設計実装テストの段階を経て行わ
れますこの仕事は人の経験や勘に頼るところが
多い仕事ですこの仕事をできる限り効率的に行
うためにコンピュータを便って支揺する研究を行
っています効率化する方法の1つとして再利用が
ありますできあがったプログラムの再利用もあり
ますが分析設計段階の仕様書の再利用を対象と
しています
コンピュータを使って仕事を行わせるために仕
事の内容を記述したプログラムを作成しますがこ
のとき対象となる分野あるいは業務について
行わせたい仕事の流れ手順を明らかにし整理す
るという分析を行いますこれは仕様書と呼ばれ
る文書表ダイアグラム(図)などで表されます
私の研究ではこの中で特に仕様ダイアグラムの
再利用に着目していますソフトウェアの仕様を記
述するために様々な種類のダイアグラムがありま
す人装置もの情報の静的な関係を表すダイ
アグラムこれらの時間の流れに沿った動的な関係
を表すダイアグラムなど様々な観点から描かれま
すどのような作業または処理があるのかその
作業を誰が行っているのかその作業に必要な情報
やデータは何であるかその作業の結果何が出て
くるのか作業者にはどのような種類の人がいるの
かどの作業者がどのように連携して仕事を行うの
かということが表されています
これらのダイアグラムは全く何もない状態から
記述するのではなく過去の開発で蓄積されたダイ
アグラムの中から近いものを使うことで分析作
業を効率化できます同じ分野のシステムなら少
しの変更で再利用できますが異なる分野のシステ
ムであっても業務内容を見ると同じような作業
を行っているものがあります例えば鉄道ホテ
ルコンサートという全く異なる分野で使われてい
るシステムがありますが予約という観点で見ると
列車の座席の予約ホテルの部屋の予約コンサー
トの座席の予約など分野が違うので異なる用言吾が
使われていますが同種の作業があります作業が似
ていればこれについて記述したダイアグラムにも
似た部分が出てくると考えられます
似たダイアグラムを探すのはダイアグラムに書
かれている言葉が同じでもその意味する概念や対象
が分野や使われる状況によって異なるので人の経
准教授 川端 亮
験による部分が多くあります多くの経験を持つ開
発熟練者は直感的にこのように異なる用語が同
じ意味を指すものだと認識できますこれをコンピ
ュータで支援するためにはダイアグラムに描かれ
た形やつながりの意味と用語問の概念間の関係を明
らかにし整理することや人がダイアグラムを探す
ときにどのように探しているかという手順を明ら
かにしソフトウェアとして実現していく必要があ
りますこれは分野の知識や開発者が暗弄式白勺に
持つ開発の知識経験を蓄積再利用することです
この知識や経験を明らかにしどのようにコンピュ
ータを使って蓄積し再利用するかといところに
難しさとおもしろさがあります知識を再利用でき
る仕組みをシステムとして実現することはソフト
ウェアの開発だけでなく多くの分野で人の生み
出した素晴らしい知識や経験を継承していくことに
つながると考えています
事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

事
モバイルユビキタスのバリアフリーユニバーサルデザイン
情報メディアコミュニケーション研究室(夫人研)は筆者の2008年4月の着任によっ
て誕生した歴史のない研究室ですモバイルエビキタス技術のバリアフリーデザイ
ン(=障害をお持ちの方の困難を個別に解決する方法)とユニバーサルデザイン(=
障害をお持ちの方も含めて全ての人が使用できるように解決する方法)をキーワード
に新しい支援方法を提案したり障害者の生活調査や分析認知特性の解明などを
行っていますバリアフリーユニバーサルデザインの研究は着任前の情報通信研
究機構時代から一貫したテーマですが「障害をお持ちの方から意見を頂戴する」こと
で一般人を対象にニーズやシーズを考えた場合には見えないモバイルユビキタス
技術の本質が見える面白さがあります指導する学生にも積極的に障害をお持ちの方
と交流させているのですが指導教官には全く見せない心遣いを障害をお持ちの方
相手だとごく自然に出来るほど成長する学生もいてうれしいような少々複雑な気分
です
研究室の講座名に掲げ大学院の授業名にも使用している情報メディアコミュニケ
ーション学ですが 情報通信に関連した文理融合領域で学問として未確立で定義が
あいまいですあいまいであるが故になんでもありでこれから情報通侶分野で何が
起こっても当分メシの食いはぐれがなさそうだという理由で使っていますという
のはかなり本気の冗談ですが若さゆえに面白いものだけに飛びついてきただけのこ
れまでの自分を反省してこれからは情報メディア通信の本質に迫るような研究
を行いたいと考えています
前置きが長くなってしまいました本稿では失人研の現在のミッションを中心に
将来のビジョンについても紹介します
放送と通信の融合により木特定多数に同じ情報を同時に送るブロードキャスト型
から様々な情報を個別に送るコンテンツ配信型へと放送サービスの転換が起こる
18
と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

と言われています将来のコンテンツ配信型放送サービスが配信するコンテンツは
メタデータの利用において文字副音声多言語対応に留まらず触覚嗅覚情報を
用いた高度なマルチメディア性およびインタラクティブ性を有することでしょうこ
のような技術動向において忘れてはならないのが障害者への配慮です本研究は視覚
障害者にも放送コンテンツ中の物体の形状や空間配置などの図形情報を提供する技
術を提案することを目的としています具体的には放送コンテンツのメタデータを
用いてPCや情報家電への普及が見込まれるタッチパネルを制御し視覚障害者が触覚
と音声を通して画面を触りながら図形認識し晴眼者とともに地図や歴史的建造物の
平面図図形パズルなどをインタラクティブに楽しむことを可能とするための基礎技
術を開発します図に基礎技術のイメージを示します
法の延長線上でもユニバーサル
放送コンテンツのメタデータをサ ブウィンドウ上で実行 視覚障害者の情報補助の目的
国1製作するシステムの分類とインタフェース技術コンテンツ技術の開発トピック
移動は人間の自由と尊厳に関る最も重要な行動です草いすは自立移動困難な人々
の最良の補助器具ですが幸いす通行を阻む歩行空間上の各種バリアが車いす利用の
困難さを生じさせています本研究は辛いすユーザの視点から歩行空間をセンシン
グし歩道の通りやすさ通り難さを客観的に可視化する技術をローコストで実現す
ることを目的としています車いすユーザの視点から歩行空間をセンシングする方法
として電動手動牽いすの双方ともに改造することなくマジックテープ等で簡単に
取付可能な小型センサを開発しセンサ間の無線通信によってデータを集約するセン
サネットワーク技術を応用していますまた辛いすユーザが感じている歩道の通り
やすさ一通り難さを客観的に可視化する方法として統計的推論による状態推定結果を
1(1
google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

google mapを背景地図として表示検索可能な技術を開発しています地図上に可視
化された歩道の通りやすさ通り難さは車いすユーザだけでなくお年寄や乳幼児
ベビー カー利用者視覚障害者病人や怪我人等広く市民の移動の質の向上に役立
ちますそして可視化結果の利用によって行政住民双方に益する効率的なバリア
フリー歩道整備事業が可能となることを目指します図2は秋葉原での実験の様子です
図2(左)歩道を幸いすで走行する被験者(右)センサを被験者の幸いすに取り付けた様子
歩行者と自動車との衝突に関連する痛ましい事故事件が後を絶ちません歩行者
と卓とが通信し合い互いに衝突を避けることが出来るそんな未来が通信機器のエ
ビキタス化によって訪れようとしています本研究では遮蔽物のある交差点でか
つ多数の歩行者が存在するという難しい条件下でも安全かつローコストで動作する歩
車間通信の最適な方式を探っています本研究は服部研究室パナソニックとの共
同研究によって実施しています
近年バリアフリー移動支援のための視覚障害者の経路誘導案内を対象にRFIDタ
グ赤外線FM波通信などを用いた歩行者ITSの実用化を目指す公的取り組みがさか
んに行われています支援の実用化には視覚障害の種類受障時期外出頻度歩
行方法年齢といった個人特性から視覚障害者を分類整理しガイド情報提示タ
イミング等に関する望ましい支援内容と個人特性との関係解明の重要性が指摘されて
いますが現状では未解明ですそこで夫人研では白杖を利用する重度視覚障害者
に照準を当て個人特性のうち自杖の使用方法など視覚障害者の実際の歩行を分析し
て得られる歩行特性に着目し調査を通して経路誘導案内の望ましい支援内容と歩
行特性の関係を明かにすることを目指しています図3は2号館1Fで行った調査実験の写
真です
20
図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

図3歩行特性分析のための実験経路を歩く被験者の様子
夫人研究室の2009年度の研究プロジェクトを紹介しました今後はこれらの研究プ
ロジェクトの継続発展を目指すとともに情報メディア通信のなかでこれまで
手薄だった通信の研究にも取り組む所存ですまた筆者は本校着任前に情報通信研
究機構でインターネットの次の通信網「新世代ネットワーク」(英語だとPostIP
FutureInternetなど)を研究する部署に所属していましたが着任後は学会等の解説
記事の執筆程度で研究を行ってきませんでした新世代ネットワークは授業で取り
上げるたびに学生の目がきらきら輝くインパクトのある面白い研究トピックです
私も最新事例を調べて解説するだけでわくわくします手を広げすぎるのは少々怖い
のですが新世代ネットワークの研究にも着手できたらなと考えています
田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

田日田
理工学振興会では理工系大学院1年次生と学部3年次生を対象とした10回目の企業研究セミナーを2009年9月30日(水曜日)に開催しました実施に
あたり本会の法人会員9社のご協力を賜りました今回は講演会形式とブース形式の個別説明会を同時に開催し多数の学生が熱心に拝聴していま
した
開催日2009年9月30日(水曜日)1100~
個別説明会 9号舘352室354室356室357室
〈企業名〉
1100~1400 KYBシャープ東芝三機工業
講演会 9号館353室
〈企業名〉
ニコン
富士通
大日本印刷
東芝
三機工業
KY酎菊
1105~1135
1135~1205
1205~1235
1235~1305
1305~1335
1335~1405
電気電子工学専攻 網野加苗 博士(エ学) ThejrlnteractionswiththeLinguistic-Phon0loglCallnformatjon
電気電子工学専攻 木下慶介 博士(工学) AStudyonSpeechDereverberationandltsAppIications
機械工学専攻 西沢良史 博士(工学) 低周速比型の水平軸小型風車の最適ブレード形状およびヨーイング角速度に関する研究
化学専攻 小川真紀子 博士(理学) ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究
電気電子工学専攻 関口寛人 ResearchonGaN-basednanocoIumnsandnanocolumnlight-emitting
博士(工学) diodesgrownbyrf-Plasma-aSSistedmolecular-beamepitaxy
電気電子工学専攻 VadiveluRamesh ResearchonStrainRela3(ationEffectinTop-DownGaNBasedNano-Structures
博士(工学) FabricatedBylcpDryEtching
理工学専攻情朝学領域 朝生雅人 博士(工学) セルラーシステムにおける高精度位置積出手法の研究
電気電子工学専攻 渡遼修至 博士(工学) 頂点構造化を用いたポリゴンメッシュのデータ圧縮に関する研究
物理学専攻 鯨岡真美子 博士(理学) 集団童子ドットにおける励起子ダイナミクスとラビ振動
22
理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

理工学振興会奨学金(上智大学第3種奨学金)奨学生氏名
理工学娠興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です 2010年度在籍者および2010年度入学者のうち次の学生に給付することが決まりました
博士課程前期1年次生 博士課程前期2年次生 博士課程後期1年次生
機械工学領域 佐藤章史 機械工学領域 種市直紀 応用化学領域 大津あずさ
土信田知樹
電気電子工学領域 佐藤江里子
寺園遺書
中村恭子 電気電子工学領域 木下 萌
博士課程後期2年次生
域 猪瀬裕太
博士課程後期3年次生
物理学領 辻
秦
大
林
之史也樹里
智裕龍美朱
島 原
長南架線
山口一陽
兼坂信之
藤井友理
萩原健太
光武 慧
金子真菜
櫻木 圭 千葉亜矢子
応用化学領域
化学領域
応用化学領域
化学領域
数学領域
物理学領域
生物科学領域
情報学領域
近藤篤史 杉山奈未
佐野香織 増田斐那子
機械工学領域
応用化学領域
生物科学領域
情報学領域 三溝真梨子 物理学領域
森山事実
菅沼拓也 情報学領域 品川知則
成田隆明
蒔 量東 江副航希
内海祥一
奨学金証明書授与式の様子
この賞は化学科の故松本圭一部名誉教授のご遺族からのご寄付で上智大学理工学部より大学院に進学した学生(応用化学領域化学領域生物化学領
域の生物化学研究グループ)の中から最も優秀な学生に授与されるものです2009年度は下記の者に賞状と賞金15万円が授与されました
応用化学領域 塚越清夏 富田実留 若林大陽 生物科学領域
2009年度ティヤールドシャルダン奨学金受賞者氏名
標記奨学金(懸賞論文)は右記の学生に授与されました
この奨学金はティヤールを敬愛し彼の理想に共鳴したベルギーの篤
志家のご厚意により生命科学研究所の故北原隆名誉教授を通して上智
大学理工学部に恵与されたものです
宮本 尚 長谷川雄大 野辺地あかね 山田はるか 坂田奈々絵 中村恭子
金賞(30万円) 地球環境学専攻 BO895497 銀賞(20万円) 理工学専攻(機械工学領域)BO878320
銅賞(10万円) 地域研究専攻 BO967754
銅賞(10万円) 理工学専攻(化学領域) BO978833
北環隆メモリアル賞(5万円)神学専攻 BO991906 北原隆メモリアル賞 理工学専攻(機械工学領域)BO978020
(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

(単位千円)
教 授後藤 貴行 個数揺動自由度を持つスピンダイマー系の構築と制御
基盤研究(A) 教 授岸野 克巳 新材料による緑色半導体レーザの基盤技術の開拓 12500
基盤研究(B) 教 授高井 健一 最新分析技術を駆使した材料中の水素一転値ダイナミックス積出と脆化メカニズム解明 3400
准教授田村 恭久 協調学習の情報抽出とグループを超えた再利用の研究
准教授ご菊池 昭彦 窒化物半導体ナノウォール結晶のヘテロ構造制御と光電子デバイス応用技術の開発
准教授都築 正男 グリーン関数による相対跡公式の研究
教 授大槻 東巳 圭子ネットワークモデルの示す普遍的性質
教 授中島 俊樹 アファイン幾何結晶の構成と結晶基底の表現論
教 授加藤 昌英 正則写像の拡弓長性と複素多様体の構造
教 授田原 秀敏 複素領域での非線型偏微分方程式の特異点の研究
教 授林 謙介 神経細胞の形態形成における微小管アンカーの役割
教 授熊倉鴻之助 開口分泌の素過程特に顆粒供給の時空的制御樹割こ関する研究
教 授ScottHowell 化学英語論文における複合名詞の研究
准教授石田 政司 ゲージ理論的手法によるアインシュタイン計量及びリッチフローの研究
教 授藤井 進 ユビキタス環境下におけるサステイナブル生産システムの構成と運用に関する研究
准教授坂本 治久 砥粒切れ刃密度のインプロセス計測に基づくスキルフリー鏡面研削加工法 900
教 授高尾 智明 低温で膨張する次世代高熱伝導プラスチックによる伝導冷却超伝導コイルの高性能化
教 授下村 和彦 光増幅再生機能を有する波長制御型光分岐挿入多重ノードに関する研究
教 授篠田 健一 有限群の表現指標和およびその応用
教 授辻 元 一般化されたケーラーアインシュタイン計量の研究
特別契約教授伊藤 直紀 高密度天体における量子輸送現象の研究
教 授後藤 貴行 絶対零度の臨界温度を持つボスクラス相への臨界現象のNMRFLSRによる研究
教 授長嶋 利夫 拡弓長有限要素法(times-FEM)による疲労き裂進展シミュレーションの実用化
教 授和保 孝夫 1nAsナノワイヤを用いた超高速アナログデジタル集積回路
教 授安増 茂樹 酵素と基質の分子共進化の研究一硬骨魚の脚化の機構をモデルとして 1600
准教授斉藤 玉緒 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの構造と機能に関する研究
准教授鈴木 教之 合金属小環状アルキン化合物を基盤とする新規な機能性分子の構築
挑戦的萌芽研究 准教授木川田喜一 ウラン同位体比を指標とした風送塵の起源を同定する新規手法の検証
教 授江馬 一弘 ランダム媒質中の光の局在現象と光学特性の解明
教 授早下 隆士 分子識別機能を有する色素プローブデンドリマー複合体の開発
准教授岡田 邦宏 クーロン結晶を用いた極低エネルギー極性分子-イオン衝突反応の研究 若手研究(A)
24
凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

凸版印刷株式会社 命理工学科 炭化水素系電解質膜の研究開発 1000000 2010331
独立行政臥新エネルギー産業榊総合開発機構芸毒苧酢髭命理工学科 107略750 2010320 燃料電池先端科学研究事業
ミツミ電機株式会社 工学科 1000000 2010531 AD回路高性能化の研究
理工学部情報理工学科 三菱電機株式会社 光偏波制御方式の研究 500000 2010315
理工学部機能創造理工学科 教授う也尾 茂
建設機械の省エネシステムの検討 日立建機株式会社 2010331 1050000
理工学部機能創 教授未益博志 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 987000 2010226 カットアウトを有する航空機構造の力学的特性に関する委託研究
理工学部物質生命理工学科 教授陸川政弘 三菱化学株式会社 ポリカーボネート樹脂の機能化 2010331 6000000
理工学部機能創造理工学科 教授清水伸二 株式会社いすゞ中央研究所 ボルト締結部を含むエンジン構造体の振動低減技術の開発 2010331 1050000
造 理工学雨
学型道理工学科
住友電気工業株式会社
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 合研究所
フェムトセル用送信電力制御チャネル割当方法に関する研究
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発
複合材料タンクの口元部の構造様式検討
高強度鋼の遅れ破壊に及ぼす支配因子の解明
1050000
1000000
2010331
2010331
2010326
635000 2010225
equiv哩工学部機能創造理工学科 教授申 鉄龍 トヨタ自動車株式会社第2パワートレーン先行開発部 2010且30 次世代エンジン制御技術の研究 12000000
理工学部機能創造理工学科 教授高尾智明 独立行政法人科学技術摂興機構 3000000 2010331 変動電磁力に対する超伝導界磁コイルのロバスト設計法の確立 造理工学科
理工学科 造 理工学科
観測計算を融合した階層連結地震津波災害予測システム
次世代情報通信システムのためのナノワイヤCOMOS異種技術集榔ヒの研究
水素貯蔵材料先端基盤研究俳金属系水素貯蔵材料の基礎研究
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人科学技術摂興機構
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構
2010331
2010331
2010320
2080000
9900000
9775500
二哩工学部物質生命理工学科 独立行政法人科学技術振興機構 万能ヒドロゲル化学センサアレイ開発のための調査研究 14040000 2010331
理工学部物質生命理工学科 教授南部伸孝 国立大学法人東京工業大学 2010319 理論計算によるアイソトボマー分別係数の決定 1310000
抑
楕
EJID研削を用いた高能率高精度表面処理による人工関節摺動面加工
SoC設計における施策に替わるシミュレーション評価システムの構築
355740 2010310
500000 20101031
つE
臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

臼田臼
2009年度 2005年度-2009年度
男 女 男 女 男 女 5年間の総計
日立製作所 16 6 16 3 78 14 92
NTTデータ 10 2 10 47 9 56
トヨタ自動車 10 4 39 O 39
)リコー 6 6 34 4 38
日本電気 14 3 31 6 37
キヤノン 4 2 24 10 34
本田技研工業 6 5 1 28 2 30
ソニー 4 2 1 23 6 29
東芝 3 2 3 13 10 23
日産自動車 4 19 4 23
野村総合研究所 2 18 2 20
日本ユニシス 1 2 4 4 13 7 20
ブリヂストン 2 6 15 3 18
日本アイピーエム 2 12 3 15
富士ゼロックス 3 1 3 1 13 2 15
NTTドコモ 2 1 3 1 10 3 13
東日本電信電話 2 2 9 4 13
東日本旅客鉄道謄射 4 2 1 12 1 13
大日本印刷 4 10 2 12
オリンパス 2 1 1 8 3 11
大和総研ホールディングス 2 0 11
凸版印刷 3 1 10 1 11
日本ヒューレットパッカード 2 2 10
NTTコミュニケーションズ 1 8 2 10
東京電力 9 1 10
富士通 4 9 1 10
東海旅客鉄道 4 3 9 0 9
アクセンチュア麻) 2 7 1 8
ヤマハ発動機 4 8 0 8
三菱電機 1 1 8 0 8
KDD相対 5 2 7
ソフトバンクモバイル 2 5 2 7
パナソニック 4 7 0 7
マツダ 7 0 7
デンソー 2 6 7
三菱重工勢 2 6 1 7
富士フイルム 5 2 7
ヤフー 6 0 6
旭化成 6 0 6
損害保険ジャパン 5 1 6
電通国際情報サービス 5 1 6
全日本空輸 1 6 0 6
東京海上日動火災保険 2 4 2 6
NTTソフトウェア 4 1 5
アクセンチュアテクノロジーリリューションズ 2 5 0 5
ソニーエリクソンモバイルコミュニケーシ]ンズ l 5 0 5
フューチャーアーキテクト( 3 1 4 5
鹿島建設 1 1 4 0 4
1 4 0 4
東京都(教員) 3 1 4
26
2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

2010年3月1日現在
身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

身長塵
ソフトウエア興業 1 0 1
ソフトバンクB酎菊 1 0 1
2010年3月1日現在
28
藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

藤森工業株式会社 高城昌之
Reportsof[heEnterprlSeS TheMembero[SophlaScl-Tech
藤森工業株式会社は1914年(大正3年)の創業以来「包む価
値の創造を通じて快適な社会の実現に貢献します」という企業
理念のもと塗る貼るといったコア技術を駆使して素材を組み
合わせることで単一素材ではなし得ない様々な機能を付与した
製品を開発しお客様はもちろん社会全体の発展に貢献する
「新たな価値(=包む価値)」を創造してきました
当社では「常に未来と時代の最先端を追求する」「素材に機能
という命を与えて新たな価値を創造する」企業であり続けたいと
いう願いを込めてldquoZACROSrdquoというハウスネームを制定して
いますこれはZ(究極未知)とギリシャ語のACRO(頂
点先端)を組み合わせたものであり当社の技術基盤である
「積層」をモチーフにした大地(緑)と空(青)の色をもつロ
ゴマークとともにお客様やユーザーの皆様に親しまれています
創業以来国内初のポリエチレンラミネ一夕ーを導入するなど
常に時代のニーズを先取りした技術開発に努めて現在では産学
連携も積極的に取り入れて上智大学では理工学部の新技術を利
用した素材表面の機能化についての共同研究を行っています
日々の生活シーンで さりげなく皆さんの手に触れられていま
すシャンプーや洗剤の詰め替え用パウチレトルトカレー等の食
品用パウチ錠剤軍頁粒等の医薬品用包装材料の他に医療現場
で扱われる薬液や流動食用の機能性ソフトバッグから半導体精
密機器用クリーンパックやインクジェットプリンタ用インク袋等
の電子OA用包装材料にカロえ機能材料と呼んでいる偏光板プ
ロテクトフイルム製造工程用キャリアフイルムといった先端分
野で求められる高機能フイルム製品にいたる幅広い分野での事業
展開を行っています
環境問題がクローズアップされている今当社の吉吉め替えパウ
チ【フローパックRシリーズ】は従来の成型容器に比べ廃棄時
の体積はわずか5樹脂の使用量も四分の一に減らしただけで
なく詰め替え時の「使い易さ」も付力l]した現代のニーズにマッ
チした製品ですまた設備作り込みにおいてもorOC(揮発
性有機化合物)処理設備の導入溶剤使用量の削減溶剤を使用
しない製造方法の研究などorOC削減対策に積極的に取り組ん
でいます群馬県の昭和事業所では従来の燃料である重油
LPG(液化石油ガス)に替えてLNG(液化天然ガス)を採用
して二酸化炭素の排出量を大幅に抑制する取り組みを実施してい
ます
こうした様々な製品がお客様の元に届くまでの品質管理を行っ
ているのが私の所属する品質保証課です
当社の品質管理の特徴としましては医薬品医療用包装材料
の生産には名弓長と横浜のGMP(GoodManufacturing Practice)
工場をIT関連向けには業界最高レベルのハイクリーン環境を整
備した沼田と昭和の事業所をというように特色ある生産拠点か
ら製品に対して最適な環境設備を選択し生産工程での作りこ
みから市場要求に合わせた管理体制を構築しています当社は
1995年より各事業所において品質マネジメントシステムの国
際規格であるIS09001の認証を順次取得して2008年1月には言忍
証登銀の統合及び対象部門を拡大してHACCPやGMPなど各業
界で求められる品質管理基準にも準拠した生産体制を整備しまし
たさらに環境マネジメントシステムの国際規格である
IS0140012004を全生産拠点にて取得して「環境保全」の観
点からもお客様の信頼に応える生産品質管理体制の構築に注力
しています
社員一人一人がハード面での規則を遵守するのはもちろんのこ
と新しい物事に挑戦する高い意吉戟を持って日々一丸となって品
質の維持向上に取り組んで業界の最先端を目指していますそ
うした中で私も今後自分の業務の領域と活動の場を広げて多
くのお客様のニーズに応えてより洗練された品質「安心安全」
をお届けできるよう尽力していきたいと考えています
高城昌之
2007年上智大学 理工学部 化学科卒
横浜事業所 品質保証課
活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

活躍中の卒業生
株式会社ナビタイムジャパン取締役副社長
菊池 新 (1994年3月 理工学研究科電気電子工学専攻修了)
私は現在(棟)ナビタイムジャパン
のCTO(最高技術責任者)も兼ねて
おり時刻表経路探索エンジンや組
み込みアプリケーションのプログラ
ミングを行っています私がプログ
ラミングやシステム開発に興味を持
ったのは大学時代でした
学部時代大学院時代ともに加藤
誠巳研究室で時刻表を考慮した経
路探索システムの研究を行いまし
た私は決して鉄道オタクではない
のですがアルゴリズムを考えたり
アプリケーションを作成したりする
ことが好きで寝食を忘れて研究に
愚挙ふrdquoを毒八ハ蒙深兼するシステムを貞
操ご学部マルチメディア発したが島路線の平均所
ラボ(析藤椎巳敷設)の大要勝間だ宣ダイヤ
学堅舗池新さんが修士 呈されていなかった
萱研究として靡発した 毒さんは昨年10月の時
市阪のパソコンを使えば熱 裂を利用杓1靂間かけ
董
崩の中から塁
は以前首都 テ
ム開発
の全時副ヂタをパソコン
に人力その他のJRヰや
私鉄も平喜時蘭デー
タを入力した
探果プログラムは碧
時刻以降に出尭する飛行
攣列申の零すペてを頗
零する方法を採用した
最も早く自的地に到着す
る方法が複数見つかっ允淵
合はで義庸避熱線
するケ一義恕忍嘗巌
諺密告慧講義壌聖霊
肇帯濱掟てオペ沈溺り讃n羞覇E
の恢横漢嚢せ竃よ
襲の環
うエ発した
姦爪象ぐ学級啓時間も
荊暦の暫など
没頭していました
当時は時刻表データが電子化されておらず時刻表から
手打ちでデータを作成しました日本全国を対象とした為
データ作成には2カ月近くかかり大変でしたがなんとか
システムを完成させることができました情幸艮処理学会で論
文を発表し毎日新聞にも取り上げていただきひとつのシ
ステムを作成する楽しさをこのとき初めて感じ充実した学
生生活を送ることができました
また学部時代研究室内にWindows21130のSDKがあ
りましたので多くのサンプルアプリも作成しました新し
い開発キットやパソコンワークステーションを使い試す
ことができましたこの時代はWhdows30が日本発売直
後だったのですが主流はMS-DOSでありメモリの制限や
処理速度が遅いという問題がありアプリの作成には大変苦労
しましたそのような機会を与えていただいた加藤教授には
大変感謝をしております
大西(現ナビタイムジャパン代表取締役社長)との出
会いも研究室でした大西は私が学部4年生の時の博士課
程2年生で幸歩行者を対象とした大規模ネットワークの
経路探索の研究をしておりました私が研究していた時亥り表
経路探索とは同じ経路探索でもアルゴリズムが異なるのです
がこの2つの経路探索から現在のナビタイムジャパンの
ビジネスの根幹となる車電車飛行機徒歩など様々
な交通手段を考慮したルートを検索する「トータルナビ」を
開発することができました大西とはプライベートでもテ
ニスやバーベキュー海外旅行と
研究以外でも多くの時間を共に過
ごしました
こうしてみると大学大学院
時代での経験が現在の私に大きな
影響を与えてくれましたまた
その経験をビジネスに生かすこと
ができ本当に幸せ者だと思って
います
その後私は2000年3月にナビ
タイムジャパンの設立とともに現
職となりましたインターネット
の商用化やimodeEZWeb等のモ
バイルインターネットの発達により弊社のケ一夕イナビゲ
ーションサービスの月額有料会員数は400万人(2009年7月)
を超えるまでになりました引き続きユーザの利便性向上に
応えると共に『ナビゲーションエンジンで世界のデファク
トスタンダードを目指す』というビジョンの下社員一丸と
なって開発およびサービス提供を行っていきたいと思ってい
ます
設立当初の社員数は5名でしたが現在は350名程になり
私の役目も設立当初とはだいぶ変わり多岐にわたって参り
ましたが今後もできる限り開発現場で社員とともにプログ
ラミングを行っていきたいと思います
30
ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

ー攣 誓 王rdquo挙
株式会社 アサヒファシリティズ
アルケア株式会社
磐田電工株式会社
カシオ計算機株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社
シャープシステムプロダクト株式会社
新日本製毒戟株式会社
ダイタン株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社 竹中工務店
電気化学工業株式会社
東京製繊株式会社
東京電力株式会社
株式会社 東芝
東洋通信株式会社
東レ株式会社
株式会社 ニコン
日本電気株式会社
日本光電工業株式会社
パナソニック電工株式会社
株式会社 日立国際電気サービス
株式会社 フジクラ
富士写真フイルム株式会社
富士通株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット
株式会社 みずほ銀行
株式会社 三井住友銀行
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明電舎
株式会社ムラキ
雪印乳業株式会社
森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

森正雄
森本光生
矢入郁子
山口達郎
山中高夫
湯本正友
余話信一
横沼健雄
吉田正武
吉田文彦
吉田泰昌
陸川政弘
笠耐
RDeiters
若井由太郎
和田秀男
和保孝夫
(50音順)
野口敏
信川好子
野村一郎
野村卓也
萩原行人
波多野弘
服部武
早下陸士
林龍行
原利典
平田均
福島敏彦
富士隆
藤井麻美子
藤生崇則
藤江優子
藤田千佳子
藤田正博
測野寿子
星義之
星野正光
堀内四郎
升岡秀治
増山芳郎
松島民夫
松永大輔
松原寺
松山定彦
三反崎規夫
宮尾雅文
宮武昌史
武藤康彦
村原雄二
高橋浩爾
高橋祀司
竹内懐夫
竹岡裕子
竹下浩二
武野仲勝
武村永一
田中邦翁
田中昌司
田中秀数
谷口肇
田野倉敦
田野倉淑子
田宮徹
田村恭久
千葉誠
築地徹浩
辻元
土屋隆英
嘩道佳明
常盤正之
富田清和
友田晴彦
長尾宏隆
長嶋利夫
中野求
中村一也
中村賢蔵
中山淑
南部伸孝
西尾光平
西堀俊幸
新田雄一
酒臭武志
坂田公夫
酒本勝之
坂本治久
佐々木節子
佐藤弦
佐藤正雄
篠崎隆
篠田健一
渋谷智治
清水清孝
清水都夫
清水伸二
清水文子
下村和彦
庄野克房
白砂洋志夫
申鉄龍
新宅童弘
末益博志
杉田成久
杉山徹
杉山美紀
鈴木京二
鈴木誠道
鈴木隆
鈴木啓史
炭親鳥
関根智幸
曽我部潔
高井健一
高尾智明
高橋和夫
岡部眞幸
岡村秀勇
小澤忠彦
恩田正雄
笠嶋友美
梶谷正次
力l]藤誠巳
金井寛
金子和
賀脊隆太郎
川中彰
川端亮
河村彰
神澤信行
木川田喜一
菊池昭彦
木村拓生
久世信彦
工藤輝彦
熊倉鴻之助
公文哲
栗栖安彦
桑原英樹
甲田三重
幸田清一郎
小駒益弘
後藤貴行
小林健一郎
小満茂雄
権田善夫
権平泰進
貢藤玉緒
斎藤直人
相澤寺
青木清
青木義一
秋山武夫
浅賀良雄
荒井隆行
井奥洪二
井口順弘
池内温子
池尾茂
石井進
石川和根
石川徳治
井田明夫
板谷清司
伊藤和彦
伸藤潔
伸藤直紀
猪俣忠昭
猪俣芳栄
伸呂原隆
牛山泉
臼杵豊展
内田寛
内山康一
榎本郁雄
FHoweJl
江馬一弘
遠藤明
大井隆夫
大槻東巳
岡田勲
緒方直哉
32
理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

理工学振興会の発展と
活動の活性化に
ご協力をお願いいたします
会 員 募 集 中
の運営や活動は会員の皆様のご支援とご協力に支えられてい
ます現在理工学振興会奨学金を受ける大学院生は年間35人ですが年々大学院への進学
率が高まる中一人でも多くの学生に奨学金を給付し優秀な人材を21世紀の社会に送り出
したいと考えていますまた上智大学理工学部リエゾンオフィス(SLO)も産学連携のため
の活動をしていますこれからも会員の皆様との相互コミュニケーションを緊密にしていきたい
と念じております
当理工学振興会には3つの制度があります
年会費一口100000円(何ロでも結構です)
年会費一口10000円(何口でも結構です)
寄付をしてくださった個人または企業が当該年度会員になる制度です
会員になられますと本誌(サイテック)や各種行事のご案内をお送りいたしますまた法
人会貞企業に所属の方は上智大学全学共通科目「ビジュアリゼー ション(科学技術における
応用)」へ無料で出席することができます
振興会に興味をお持ちの方はご一報いただければ詳しい資料をお送りいたしますまだ
振興会の会員になられていない企業個人をご紹介いただければ幸いです詳しくは事務局へ
お問い合せください
振興会についてのご意見ご提案ご希望などありましたらご遠慮なく事務局までお知らせ
くださいますようお願いいたします
上智大学理工学振興会事務局102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内
TEL O3-3238-3300 FAX O3-3238-3500
ホームページhttpwwwmesophiaacjpscitech
上智大学理工学摂興会会報21号をお届けいたします新理工学部は3年目を迎え 第一期生の学生諸君はいよいよ自らが選ぶ専門分野の科目へと進みます12年次 で学んだ幅広い知識と己の学問的興味を背景により深い知の探求へと積極的に 踏み出していただきたいと思います
今号の特集は前匡=こ引き続き環境問題を取り上げ機能創造理工学科の高井健一 教授に「エネルギーおよび環境と材料技術」の臨で寄稿していただきましたこれか らの持続的発展と低炭素社会の達成に向けて高い期待を集める水素社会の構築 そこに欠くことのできない材料技術の課題と将来展望に関する多くの話題に触れて いただけたかと思います
さて世は就職氷河期と言われる中2011年魔の採用に向けての就職活動が始ま っています景気後退は底を打ったという声はあるもののメディアではなかなか将 来に対する明るい話題は聞こえてきません学生諸君の就職活動に対しての危機感 は相当なもので今後12年での本格的な景気回復は当てにできないとの認識が支 配しているように感じます我が理工学振興会においても法人会真の退会が続き 景気の先行きに対する不透明感を感じないわけにはいきませんしかしながらこ のようなときにこそ科学技術の大いなる発展が求められるはずでありましょう新た な革新的技術が新しい産業を生み出すことはもちろんのことひとつひとつの小さ な技術的改善が国内産業の競争力を高めてくれるはずです「技術立国日本」の明 るい未来をより確かなものとするために理工学振興会は会員の皆様のお力添えの もと上智大学の理工学部理工学研究科における研究教育活動を支援し未来 に活かされる研究の大いなる発展に期待するとともに我が国そして世界の将来 を担う人材の育成を大いに後押ししていきたいと思います大学と企業との連携が 研究においても人材育成においても今後ますます重要なものとなるでしょう是非 とも会貞の皆様の
一層のお力漂えを期待する次第であります (木川田喜一)
上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバートディ一夕ーズ(理工学振興会名誉会長上智大学名誉教授)
篠臓隆(理工学振興会会長)
早下陸士(理工学振興会副会長理工学部長物質生命理工学科教授)
江馬一弘(理工学振興会副会長理工学専攻主任機能創造理工学科教授)
岡村秀勇(上智大学名誉教授)
板脊清司(SJO長物質生命理工学科教授)
木川田幸一(物質生命理工学科准教授)
小林健一郎(物質生命理工学科准教授)
桑原英樹(機能創造理工学科教授)
鈴木隆(機能創造理工学科准教授)
服部武(情報理工学科教授)
辻元(情報理工学科教授)
曽我部潔(機能創造理工学科教Dagger受)
山中喜代子(事務局)
編集 大日本印刷株式会社
制作 株式会社クラフト
印刷 大日本印刷株式会社
軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社

軸憂鞄d
SOPHIASCl-TECH(ソフィアサイテック)
第21号2010年4月発行
発行上智大学理工学振興会
102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学理工学部長室内 ふl03-3238-3300
印刷大日本印刷株式会社