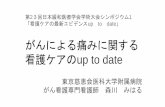この20年の科学、 その偉大なる発展を振り返る Part 1— 物理 ...月本佳代美 この20年の科学、 その偉大なる発展を振り返るPart 1—物理科学分野
PowerPoint プレゼンテーション ·...
Transcript of PowerPoint プレゼンテーション ·...

『新たな価値創造へのゲームチェンジ 』
中期経営計画
2017(平成29)~2019(平成31)年度
2017年 6月3日

はじめに
点的な「自然保護」からつながりのある「里山保全」と「生物多様性の保全」へ
当協会は、大きな変革期を迎えている。当協会設立(1989(平成元)年)当初は、大阪府
自然環境保全条例(1973年公布)に基づき、自然環境保全地域として指定された本来の自
然林に近い状態で残された社寺林の保護や鎮守の森の整備のほか、国の天然記念物に
指定された和泉葛城山のブナ林の保護を目的とした事業など、自然を保護する観点から
の取組みが主であった。
1992(平成4)年には、同条例に基づき、能勢町の三草山が、初めての大阪府緑地環境
保全地域に指定され、当協会が、貴重なヒロオビミドリシジミを始めとするゼフィルスの生息
環境を守るために、地上権を設定して立木を買取り、二次的な自然環境の保全のための
取組みが始まった。同時期に、「生物多様性の保全」の考え方が登場し、当協会でも、1997
(平成9)年から、多様な生物がみられる湿地(能勢町の地黄湿地、信太山の惣ケ池湿地)
保全の取組みが始まった。
わが国では、2002(平成14)年に策定された生物多様性国家戦略を受け、2008(平成20)
年には、生物多様性基本法が制定され、生物多様性地域戦略について、地方公共団体の
策定が努力義務とされ、府内で、生物多様性地域戦略の策定が進みつつある。
当協会では、里山の保全活動にも注力している。2013(平成25)年には、林野庁の「森
林・山村多面的機能発揮対策交付金事業」(以下「さともり事業」という。)を導入し、“さとも
り地域協議会”を立ち上げ、府内の里山保全のための取組みを促進しているところである。
また、「緑の募金」についても、2017年のテーマが“「植える」緑化から「つかう」 緑化へ”と、
森林資源の活用に重点がシフトしたことから、里山においても、森林資源の利用や森林そ
のものを使うことで、森林の多面的な機能の高度発揮や生物多様性保全が求められている。
自然を「保護」することは、「単に囲い込み、手をつけずに自然に任せておけばできる。」
ものではない。特に多様な生物が生息・生育し、生物の多様性保全上重要な里山の保全
では、「適切なかかわり」が大切である。
このような社会背景のもと、当協会でも「自然保護」から、社会的、文化的な価値を含めて、
「生物多様性の保全」、「里山の保全」に、今後、取組みの重点を移していくものとする。
また、生態系サービスを考えると、局所的な保全ではなく、里地里山一帯の生態系を意
識した保全や、山~里~川~海までの流域としてのつながりを配慮した保全が求められる。
しかし、このような取り組みは、当協会や当協会に関わりのある団体だけでできるものでは
ない。府内のできるだけ多くの人に参画してもらえる仕組みづくりが必要である。
当協会を取り巻く厳しい経営環境の中、協会自身が大きく考え方とやり方を変え、より多く
の人の理解と協力を得て、府民総ぐるみで、次の世代に緑豊かで快適な環境を引き継い
でいけることをめざして、本中期経営計画を作成する。
2

Ⅰ 当協会について
1 基本理念
「“みどり”の未来を 私たちの手で」をキャッチフレーズに、府民運動を推進して、人と
自然が豊かに関わり合える社会を次世代の人々に引き継いでいく。
大阪に住み続けたくなる快適なみどりづくりを先導・触発する団体となる。
2 設置目的
■キャッチフレーズ : 「“みどり”の未来を 私たちの手で」
■定款による設置目的:
①府民の参画や協働による自然環境の保全運動及び緑化運動を推進し、
②みどり豊かで快適な環境づくりに寄与すること
3 事業目的とその手段
生物多様性と生態系サービスは、食料や医薬品などの生物資源のみならず、人間が生
存していく上で不可欠な生存基盤として重要なものである。更に、感性、安らぎ、教育、
文化、芸能等、人々の精神や活動にも大きな影響を与えている。
平野部の市街地にみどりが少なく、市街地を取り囲むように二次的な自然が残された大
阪府において、府民運動を推進して、そこに住み続ける人々に、生物多様性と生態系
サービスがより高度に機能発揮される環境づくりに寄与することを事業目的とする。
そのため、健康で安全、そして豊かな生活を支える基盤となる多様な生物が存在する
環境やみどりの大切さ、協会の取組みに参画することの「喜び・楽しさ・満足感」を府民の
皆様に伝え、「共感・共鳴」を醸成することで参画意識を高める。そして、山から海までの
府内各地において、自然環境保全や緑化の運動が進むよう取組みを行う。更には、社会
経済状況の変化により希薄になった人の生活と自然との関わりを取り戻す仕組みづくりを
めざすことにより、事業目的を実現を図る。
4 協会の位置づけ
①府や市町村が出資する公益財団法人(1989(平成元)年 設立、
2012(平成24)年 公益財団法人認可)
②「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づく
大阪府緑化推進委員会に指定 (府内唯一の緑の募金事務局)
③林野庁の「さともり事業」における地域協議会事務局
(府内唯一の大阪さともり地域協議会事務局)
3

Ⅱ 中期経営計画の策定に当たって
1 計画策定の趣旨
1989(平成元)年の設立以来、当協会は大阪府内の能勢町三草山・地黄湿地、和泉
葛城山ブナ林などで「府民の参画や協働による自然環境の保全運動及び緑化運動を
推進し、みどり豊かで快適な環境づくりに寄与」することをめざして活動を継続し、地域
からの信頼を獲得してきた。しかし近年、様々な要因によりその活動活力が低下するに
至った。
そこで、次年度に設立30周年をむかえるに当たり、これまでの実績の集約と並行して
「従来の枠組みを変換し、新たな価値創造に向けた変革を起こす(=ゲームチェンジ)こ
とで当協会を再活性化する」ための指針として本計画を策定する。
2 計画期間
2017(平成29)年度 〜 2019(平成31)年度
3 当協会の課題
1)フラッグシップ事業がない
誰もが知るような事業がないため、協会の存在感がぼやけている。
2)ステークホルダーから見て「ミッション・必要性」「成果」が不明
3)協会自体の知名度の低さ
効果的なターゲット選定、ターゲットに応じたPR手法の検討不足
4)収入不足
遺贈以外の収入(府補助金、会費、寄附)が軒並み減少。
5)CS(顧客満足)意識やサービス精神の欠如
会員やボランティアの自主性に頼りすぎて、活動参画者へ、「喜び」や「満足感」、
さらには「達成感」が与えられていない
6)現在活躍されているボランティアの高齢化
7)核となる人材の不足(期間雇用ゆえ常勤の中心人材が育たない)
※ はP6ロードマップ中の重点項目に対応している
4
あ<ゲームチェンジとは?>
「従来からのパラダイム(枠組み)を変換させ,人々の行動様式や社会の制度を一から変えてしまうような
技術的変革や社会的変革」のこと。
使用例)・2016年11月18日 日経新聞電子版
「従来の金融経済環境が全く変わる『ゲームチェンジ』につながる可能性がある」。
全国銀行協会の国部毅会長(三井住友銀行頭取)
・2016年11月11日 日刊工業新聞
「日本は「理論研究」でAI開発のゲームチェンジを起こせるか」

4 当協会の存在意義の再定義
・新ミッション :
・ターゲット : 人 =「若者」、「子ども&シニア層」(孫と祖父母)
自然 =「地域の自然」(里地里山、森~里~川~海:山から海まで)
5 計画策定の方針
特に当協会が関わる事業地が集中し、そこで築き上げてきたもの(ひと・実
績・地域の信頼等)、全国有数の里地里山の豊かな生態系、菊炭や銀寄を中心と
した多様な資源がある「能勢」をモデル地域に選定。このエリアでのフラッグシップ
事業を中心に、「選択と集中」の視点のもと、「当協会の課題」を解決するための重点項
目を設定し、実践する。
それと同時に、その他の取組みもあわせて実践していくことで、ゲームチェンジを協会
全体に拡げ、協会の元気回復を図る。
【全体的な取り組み方針】
原点回帰で、府民のみなさまに共感してもらえる組織になり、大阪府の重要なパート
ナーになる。
3年間で、会員の倍増をめざし、組織として、自立に向けた取り組みを行う。
“ひとづくり”、“人との関係性づくり”に重点を置く。
府域全体での生物多様性の保全、里山の保全が進むよう取り組む。
当協会が直接事業を行っている箇所については、引き続き重点的に保全と再生に
努める。
「緑の募金」事業について、市街地の緑化と併せて里山の保全に向けて積極的に取
り組む。
5
「大阪みどりの自然遺産」とは・・・ 大阪府域に残されてきたかけがえのないみどりやその文化、それに関わるひと、
そしてそれらを支え続けてこられた方々の想いのこと。
「ひとをつなぐ」とは・・・ 各地のひとをつなぎ、次代へとひとをつなぐこと。
「みどりをつなぐ」とは・・・ 各地のみどりをつなぎ、山から海までみどりをつなぎ、次代へとみどりをつなぐこと。
大阪みどりの自然遺産
ひとをつなぎ
みどりをつなぐ

Ⅲ事業計画
ロードマップ(2017(平成29)年度〜2019(平成31)年度)
6
KPI (重要業務評価指標)
重点項目
その他
・自然環境保全・さともり事業
・みどりの募金関連事業
・御堂筋アメニティ事業
・メディア向け発信
(TV、新聞、雑誌での記事掲
載を促す取組み)
・遺贈・相続寄付用リーフレット作成
・みどりの交流会:年1回以上開催
・情報発信:年100回以上
・みどりの交流会:年2回以上開催
・情報発信:年150回以上
・みどりの交流会:年4回以上開催
・情報発信:年200回以上
1年目 2017(平成29)年度 2年目 2018(平成30)年度 3年目 2019(平成31)年度
フラッグシップ事業
「能勢」をモデルとした、新たな取組みによるターゲットチェンジ *環境省「地域循環共生圏構築検討業務」も活用
ネットワークチェンジ
ファンドチェンジ
CRM(顧客関係管理)チェンジ(継続的コミュニケーション手法の転換)
マネジメント体制チェンジ
本格実施
・会員管理システムの構築
・協会の取組みの見える化
・トラスト感謝祭の開催
・顧客情報の分析と活用試行
・新コミュニケーション手法の試行
・動画コンテンツ配信
(定点カメラ、イベント)
・顧客情報の活用による会員満足度の高いサービスの提供と会員拡大
・webコンテンツの拡充
長期ビジョン策定開始
30周年記念イベント これまでの 実績の集約
・さともり事業実施団体、みどりすと、他の自然環境保全団体等との新たなネットワークづくり
・「生物多様性保全地域連携支援センター」の設立に向けた府との連携
・ネットワーク内での情報の共有化
・産・官・学・民による「みどりのプラットフォーム」の構築
・マネジメントの中核となる人材の確保と組織体制の見直し
・インターン他外部人材との協働 ・持続可能な体制の確立
検討・発信 ・能勢4事業地の徹底した見 える化によるフラッグシップ化 ・4事業地周辺の里地里山の 一体的な保全方策の検討 ・SNS等による情報発信
試行・検証 ・子供向け森林環境ESDの試行 ・若年層・シニア層向イベントの実施 ・一事業地での里地里山の一体的な保全の試行 ・活動拠点化に向けた検討・試行 ・地元運輸関連企業との連携強化
・活動への若年層・シニア層の参加拡大 ・里地里山の一体的な保全策の取組拡大 ・地域と活動のコーディネイト ・地元との接点強化 ・能勢周辺のネットワーク構築
・ファンドレイジング ・会員拡大対策の強化
・既存資料のアーカイブ化
・遺贈・相続寄付対策の本格実施

1 当協会の財産が豊富で多様な資源がある「能勢」をモデルとした、ターゲット
チェンジに向けた新たな取組み ※フラッグシップ事業
1)既存事業地の目標と取り組みの徹底した見える化によるフラッグシップ化
三草山ゼフィルスの森、地黄湿地を中心に、能勢町内の4か所の当協会が関わってい
る事業地の目指すところと、“みどりすと”や学校、企業と協働して実施している取り組み
を徹底的に“見える化”・情報発信することで、フラッグシップ事業化していく。
目標例:三草山:10種類のゼフィルスとタガメをよぶ。
地黄湿地:ハッチョウトンボをよぶ。
2)能勢の魅力の情報発信
アオバズク、ゼフィルス、ギフチョウ、キマダラルリツバメ、タガメ、カブトムシ、カタクリ、サ
ギソウ、トキソウなど、能勢に生息・生育する興味深い動植物や生物多様性の豊かさ、菊
炭や銀寄など、能勢の多様な資源について、ターゲットに向け積極的に情報発信する。
3)ターゲットに向けたイベントの企画・実施等
若年層に「喜び」「共感・共鳴」「達成感」などを提供できる、「里山カフェ&セミナー」(サ
イエンスカフェの里山版)や、農家の縁側で若者とのコミュニケーションを図る「縁側カ
フェ」、「体験系イベント」を積極的に企画・実施する。参加者からのSNSやYouTubeへの
投稿を促し、広く社会に共感・共鳴を拡げていく。
また、「孫&祖父母(子どもとシニア層)」の嗜好に合う自然体験、クラフト、ハイキングな
どのイベントも積極的に企画し、次代層の育成と資産に余裕のあるシニア層へのアプ
ローチを進める。さらに、持続可能な開発に向けた森林環境教育(ESD)による出前授業
や教員講習の実施も検討する。将来的には、海外からの旅行客を意識したイベントも検
討する。
4)能勢での里地里山の一体的な保全
生態系サービスという視点から考えると、希少生物の生息・生育する箇所のみの局所的
な保全だけではなく、その周辺の農地等も含めた、里地里山の一体的な生態系の保全
や、山から川を経て海まで、流域としてのつながりをもつ保全が求められる。
フラグシップ事業においては、4事業地を”核“に、その周辺も含めた保全方策を検討し、
可能な箇所から、一体的な保全の拡大をめざす。この取組みを進めるためには、他の活
動団体や地元の協力が不可欠である。
そのため、能勢町と吹田市のフレンドシップ協定を基に取り組まれている環境省の公
募事業「地域循環共生圏構築活動」(事務局:大阪自然史センター)へ積極的に参画し、
都市域のターゲットに里山の魅力を伝えるとともに、里山での新たな資源循環の取組み
を模索する。地元の方々とのコミュニケーションを深化させ、接点強化に努める。
今後、地元も含めた能勢における生物多様性保全に向けたプラットホームの構築をめ
ざすとともに、活動の拠点化についても、検討・試行する。
7

2 ネットワークチェンジ
生物多様性の保全活動は、各地で進展しているが、まだまだ個々に展開されて例が多い。
各主体間の連携・協働を促進し、横断的な取組みを進めることや取組みを継続していくための
仕組み作りが課題となっている。そのため、下記の取組みを展開し、フラッグシップ事業化する。
1)さともり事業実施団体・みどりすと・自然環境保全団体等との新たなネットワークづくり
当協会が、府内唯一の「さともり地域協議会」事務局となり、その協議会には、平成25年
度以降、毎年60余りの活動団体が参画している優位性を活かし、さともり事業実施団体
活動者、登録ボランティア「みどりすと」、さらには他の自然環境保全活動団体を、当協会
がコーディネーターとして能動的につなぎ、幅ひろく連携・協働が進むよう、ネットワーク
の構築を進める。
また、当協会と連携し、土地所有者と協定を結んでいるような保全地を含む里山保全
団体との間で、より緊密な生物多様性保全の関係を構築する。
2)「生物多様性地域連携支援センター」の設置に向けての取り組み
生物多様性地域連携促進法に基づき、府内でその設置が求められている「生物多様
性地域連携支援センター」の設置に向け、大阪府や関係市町村と連携を図る。当協会と
しては、啓発やネットワークを活かした団体間のマッチング、プラットホームの場の設定等
を支援していく。
8
5)地元運輸関連企業との連携強化
各種イベント等の際に、能勢エリアに根付いた企業である、能勢電鉄、北大阪急行、阪
急バス等との連携を図る。ハイキング等で都市住民を能勢に呼んでもらい、能勢の多様
な資源や独自の里山文化など、地域の魅力を連携して発信してもらうことで、里山保全
運動につなげる。
「千里中央駅構内看板設置」など、互いにメリットのある取組みを実施する。
6)これまでの活動実績・結果の整理と公開
(地元の方やボランティアを巻き込んだ報告会/地元と都市部で実施)
協会設立以来、能勢エリアで行ってきた様々な取組みの内容・成果を収集・整理し、ま
とまったアーカイブとして保管し、今後の業務に活用する。
30周年記念イベント等で、地元や大阪市等の都市部で報告会を実施し、これまでのサ
ポートに感謝の意を表すとともに、協会のPRにつなげる。
7)ファンドレイジング(クラウドファンディング)
クラウドファンディングによる資金調達を行うに当たり、フラッグシップ事業である能勢で
の具体的な取組内容を、社会に対しての訴求ポイントとする。

3 ファンドチェンジ
1)ファンドの造成
既存の二つのファンド(「ブナ林の森ファンド」、「三草山ゼフィルスの森ファンド」)につ
いて、近年実績が低迷していることから、広く、取組みへの関心を誘うとともに事業の財源
の確保を図るため、必要な対策とその費用を明確に示し、ホームページや寄附型ファン
ドのサイト等を活用しファンドレイジングを行う。
また、上記以外の取組みについての財源確保のためのファンドの創設も併せて図って
いく。あらゆる機会を活用し、積極的に募金の呼びかけを行う。
ふるさと納税制度の活用についても検討を行う。
2)遺贈・相続寄付対策の実施
近年、遺産の一部を市民公益活動団体に寄付をする「遺贈」や「相続寄付」への関心
が高まっており、当協会でも実績があることから、「人生の集大成としての寄付を、府内の
自然環境の保全や緑化の促進」に活用させていただけるよう、ホームページの作成や遺
贈・相続寄付用リーフレットの作成、関係機関への働きかけ、相談窓口の開設等、積極的
に対策を実施する。
3)会員拡大対策の強化
会員の拡大は、当協会の経営基盤の安定を図り、協会の取組に対する理解と協力や
支援を得るために、非常に重要である。この3年間で、会員の倍増を目指す。
当協会のこれまでのストックや取組内容について、わかりやすく且つ興味を引くかたち
で、様々な媒体を活用し、積極的に見える化を行う。あらゆる機会を通じ、会員の勧誘を
行う。法人会員の獲得に重点を置く。会員へのサービスについても、再検討を行う。
会員、寄付金者、緑の募金者、イベント参加者など、データ管理を行い、会員の拡大に
つなげていく。
9
3)産・官・学・民による“みどりのプラットホーム”の構築
山から海までの生物多様性の保全を進めるため、府内全域において、自発的・自立的
に個々の活動が進む支援体制づくりや、府内の活動団体と産・官・学・民がこれまで以上
に連携が進められる場の構築をめざす。
この場では、各自然環境保全・里山保全・緑化団体の活動についての情報の共有化、
保全活動団体間の連携、企業や異業種団体との交流が行われることにより、府内の活動
の更なる活性化や、すそ野の拡大をめざす。
とりわけ、異業種交流を積極的に進め、健康づくり、高齢者・障がい者対策、こども対策、
地域力の向上、教育や福祉の向上など、社会的課題の解決に向けて活動されている多
様な団体や企業等にも参加を呼び掛ける。それらの方々に“みどり”に関心を持っていた
だくとともに、交流や連携を図る中で、“みどり”を通じての社会的課題の解決方法を一緒
に検討し、事業地・相手・協会・参加者・地域の5方良しにつながる取組みを模索する。

5 マネジメント体制チェンジ
1)協会の活動の核になる人材の確保と育成
今、当協会に求められているのは、自立的に存続させることである。そのためには、協
会の強みを活かしながら、今のニーズに合った取組みと、必要資金の確保、それらを組
織の中核として、積極的に行っていく職員の確保と育成が必要である。
現在の雇用形態、組織体制を見直し、協会の長期的な展望に立った考え方や継続的
な取組みができる人材の確保とその育成が求められている。
10
4 CRM(顧客関係管理)チェンジ(コミュニケーション手法の転換)
1)会員管理システムの構築と活用
カスタマーサービスを充実し、会員の拡大を図るため、会員管理システムの構築を
図る。過去の顧客情報を整理するとともに、分析を行い、会員拡大につなげる。また、
会員に対しても、満足度の高いサービスの提供が行えるよう努める。
2)アナログからデジタルへの転換
新たな取組みを進め、会員、募金、寄付金の拡大を図るためには、その取組内容
を広く社会に知っていただき、継続的に共鳴・共感を獲得し続ける必要がある。その
ために、新しいターゲット(若年層&子どもとシニア世代)に親和性が高い情報発信
手法への転換が望まれる。
若年層については、情報収集の主要媒体はインターネットが中心であり、モバイル
端末対応(スマホ、タブレット)の利用率が高い。また、子どもとシニア世代を繋ぐ若い
親世代も同様の傾向が見られる。そこで、インターネットに重点をおいた情報発信に
円滑に転換していくため、当協会webサイトのモバイル端末対応(スマホ、タブレット)
を検討し、SNSによる双方向コミュニケーションにも着手する。
情報発信には、インターネットに精通したクリエィターを積極的に活用し、府民のみ
なさんに感謝の意を伝えつつ、共感を得るストーリづくり・見せ方を工夫する。
3)事業説明会の開催等、ステークホルダーとのコミュニケーションの充実
会員をはじめとする、当協会のステークホルダーに対し、現在の取組状況を十分に
知っていただき、共感・共鳴をもっていただけるよう、ホームページや“みどりのトラス
ト”、メールマガジンなどを通じて、取組みや課題の徹底した見える化を進める。
また、トラスト感謝祭も拡充を行い、会員や寄付者、様々な協力者に対する感謝の
意を伝えるとともに、積極的に事業説明会(事業報告会)の場としても活用する。
4)新コミュニケーション手法の試行
即時かつ双方向で動画・画像・文章情報のやり取りができるインターネットの特性を
いかした新しいコミュニケーション手法の試行として、イベントの動画ライブ配信や事
業地に設置した定点カメラからの動画ライブ配信に取り組む。配信データを集積し、
当協会webサイトのwebコンテンツとしての利用も検討していく。

2)新たな取組みのための推進体制の整備から持続可能な体制の確立へ
経営強化を図るため、総務・経理業務推進体制を整備と、寄付金拡大、会員拡大を図
るための体制整備を行う。また、定期的な経理状況の確認、決算期の業務支援、その他
必要に応じて指導助言を得るため、コンサルティング会社を活用する。
生物多様性保全及び里山保全の推進と“みどりのプラットホーム”づくりのため、公1部
門を充実する。
協会本部と現地の間で、より多様なコミュニケーションを図るため、三事業地の保全活
動の企画、みどりすとや様々な活動団体との連絡調整を行うボランティアスタッフ、及び、
IT化推進のため、職員のITスキル向上を図るとともにITに精通したボランティアスタッフを
募集する。
併せてインターン等外部人材との協働を通じた人材確保も検討する。
6 個別事業等の推進方針
1)法的指定根拠をもつ保全地の活動
法的指定根拠をもつ和泉葛城山ブナ林(岸和田・貝塚市)並びに三草山ゼフィルスの
森及び地黄湿地(能勢町)の三保全地は、当協会にとって、独自性のある最も重要な保
全対象である。引き続き重点的に府と地域と協働して回復と再生に取り組む。
そのため、現状と今後の対策について、大阪府と情報の共有化を図るとともに、府と当
協会の役割分担を明確にする。この三保全地については、平成27年度から三か年計画と
して自然の回復に取り組み、平成29年度が最終年となることから、後継対策については、
大阪府と協議の上、計画を作成する。その際、ブナ林については、コアゾーンの取り扱い
について、植生調査に基づくブナの実生苗の活用を踏まえた計画とする。ゼフィルスの森
については、鹿の食害対策に加え、ナラ枯れの脅威と全体事業規模が大きいことから、
選択と集中により、投資効果の高いものから計画的に行うこととする。地黄湿地について
は、当該三か年事業により保全活動の基盤が整えられることから、当面、ボランティアの
主導による通常管理とモニタリングを行うことを基本とする。
また、保全活動を担う「みどりすと」の拡大、育成、スキルアップを図るため、上記三保全
地をフィールドとした人材育成講座「森人塾」を継続実施する。
2)自然環境保全地域の保全活動
府の自然環境保全条例に基づく、自然環境保全地域であり、現状と今後の対策につい
て、大阪府と情報の共有化を図り、適切な措置を講じる。
3)土地所有者との協定締結保全地等における保全活動
各地域での取組みの自立化を促す。
11

4)さともり事業
当事業のねらいは、社会経済状況の変化により、人の手が入らなくなった里山林に、地
域や団体を巻込みながら、人々が関わりを取り戻すような仕組みを新たに作ることにより、
二次的な自然の多様な機能を取り戻すことにある。
国のさともり事業の制度に基づき、府内の里山保全活動が円滑に展開されるよう、行政
の協力を得ながら進める。その際、ネットワークを上手に活用し、自立化を促すとともに、
放置森林対策として活用する。事業の趣旨に即する仕組みづくりについても模索してい
く。
5)みどりの募金関連事業<公2事業>
①緑の募金事業
近年、緑の募金を取り巻く環境は厳しさを増し、募金額が減少している。
今後は、府や市町村との連携の強化はもとより、企業による寄付金付き商品の販売
の提案や、団体による募金活動、道の駅への募金箱設置の依頼、ホームページの充実、
インターネットの活用、 これまでの募金方法とは異なる新たな集金システムの検討など、
新たな展開を図る。
②みどりづくりの輪支援事業
持続可能な社会の構築のための森林環境教育や里山整備の促進への取組みを実施
する。
③森林と木の香り支援事業
次の世代に、かけがえのないみどりを引き継ぐため、小学校への出前事業や教員への
講習などを通じ、子どもたちに木の素晴らしさを伝える取組みを進める。
④里山保全・利用事業
里山保全活動団体のニーズ等を把握し、効果的な里山保全・利用事業を検討する。
6)御堂筋アメニティ事業
大阪のシンボル「御堂筋」が、一層“美しく、魅力的な通り”となるよう、年2回(従来、年1
回)春と秋にフラワーポットに植栽をする。フラワーポットは、選択と集中により効果的な配
置とする。また、協力企業が減少していることから、周辺企業の協力をこれまで以上に得
れるよう努める。
7)メディア対策(TV、新聞、雑誌での記事掲載を促す取組み)
TVに関しては、報道番組、関西ローカル番組等へイベント内容を事前に告知し、取材
の可能性を探る。地上波準キー局はもとより、U局やケーブルテレビ局にも積極的に情報
発信を継続する。新聞やアウトドア専門誌(「BE-PAL」等)にもイベント毎に資料を送付し、
取材・記事化を促す。また、大阪府の広報部署の協力をあおぎ、メディアのキーマンとの
ネットワークづくりに努める。
12

Ⅳ 収支計画
1 協会の収支の長期的展望
8年後に赤字ゼロを目指す。
2 今後三か年の収支目標
1)今後の収支に関わる課題
三大事業地について、2017(平成29)年度までは、三か年の各箇所ごとの保全再生計
画に基づき、事業実施するため、まとまった資金が必要となる。野生鹿対策や森林病害
虫対策、地球温暖化によるブナ林の樹勢回復など、環境変動対策については、民間か
らの寄付金で賄えるものではなく、行政による基盤整備的な事業が必要と考える。2018
(平成30)年度以降の計画については、大阪府と協議をして定めるものとするが、当面必
要な資金で、不足分については、三草山ゼフィルスの森ファンドやブナ林ファンドを取り
崩して対応する。
また、生物多様性保全など新たな課題への対応や、当協会の元気回復ためのPR強化
をはじめとする取り組みのための資金が必要となる。その分については、2016年に遺贈を
受けた資金を活用し対応する。
法人会計部門について、基本財産の利子だけでは対応ができない。これまでは、2014
年に遺贈を受けた資金の一部を、一般正味財産として活用して対応してきたが、それも
2017年度には、不足が生じる。公1事業、公2事業、法人会計について、従事時間で按分
をし、法人会計部門の負担を減少させることで対応を図る。
2)経営改善の方向と対応策
不要な支出の削減と収入拡大の両面から経営改善を図る。
今後、事業の見直しを行うとともに、府と当協会との役割分担を明確にし、府の更なる支
援を求めるなど、経営改善に努める。
新たなファンド等により、事業資金を確保していく。
法人会計部門の不足分についても、ファンドを活用して対応する。
3)三か年の収支計画
別紙のとおり
Ⅴ 進行管理
1 年度ごとの進行管理
本計画を基に、毎年度の事業活動について、上記3カ年の収支計画と照らし合わせ、計画の
進捗状況を確認する。随時必要な見直しを行うものとする。
2 30周年記念事業
2018(平成30)年度に創設30周年記念事業をおこなう。
これに向け、当協会のこれまでの実績の集約をおこなう。
また、30周年を機に、長期ビジョンの策定を進める。
13

事業計画案
単位:万円
収入 内容 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020 2021 2022 2023
基本財産運用益 391 350 350 350 350 350 350 350 350 350
特定資産運用益 30 38 2 11 10 10 10 10 10 10
会費収入 363 339 320 350 400 450 500 500 510 510
補助金等 1,636 1,580 1,679 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
国庫補助金(さともり運営費) 649 633 580 550 550 550 550 550 550 550
受取負担金 92 93 40 60 80 80 80 80 80 80
トラスト寄付金 207 201 200 300 450 600 800 1,000 1,200 1,500
緑の募金 2,112 2,029 1,950 2,100 2,300 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900
トラストファンドからの振替 0 1,300 1,100 2,150 1,200 1,200 900 700 450 150
遺贈からの引き当て 0 0 0 500 500
雑収益 6 17 9 1
収益事業 0 0 0 50 100 200 200 200 200
経常収益計 5,486 6,580 6,230 7,872 7,390 7,340 7,490 7,590 7,650 7,750
支出
場所 内容 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020 2021 2022 2023
(委託料、請負費、必要資材購入費等事業に要する経費)
三草山 通常管理 事業費 190 248 200 160 235 260 230 200 200 200
調査 事業費 37 0 52 20 50 50 50 40 40 40
更新・再生 事業費 314 252 300 0 0 0 0 0 0
その他 事業費 144 141 251 145 145 145 145 140 140 140
事業費計 371 703 755 625 430 455 425 380 380 380
地黄湿地 通常管理 事業費 77 43 42 30 55 55 55 80 80 80
調査 事業費 20 60 30
再生 事業費 153 118 200 0 0 0 0 0 0
その他 事業費 12 24 33 40 25 25 25 15 15 15
事業費計 89 220 193 290 80 80 140 95 125 95
和泉葛城山ブナ林
通常管理 事業費 129 129 60 60 158 158 153 130 130 130
調査 事業費 64 96 22 110 50 80 0 40 0 60
増殖地環境改善 事業費 197 200 200 0 0 0 0 0 0
その他 事業費 169 104 109 121 140 140 140 180 180 180
事業費計 362 526 391 491 348 378 293 350 310 370
三大事業地事業費計 822 1,449 1,339 1,406 858 913 858 825 815 845
自然環境保全区域 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
その他事業費計 459 429 610 862 650 650 650 650 650 650
事業費計 1,412 2,009 2,080 2,399 1,639 1,694 1,639 1,606 1,596 1,626
事業費
緑の募金 交付金 661 596 534 617 700 750 750 800 840 880
助成事業 442 360 147 200 140 170 260 400 440 480
緑の少年団連盟
100 100 80 90 100 100 100 100 100 100
普及啓発 242 91 124 100 80 100 100 100 100 100
募金活動・資材 430 360 420 410 380 380 390 400 420 440
小計 1,875 1,507 1,305 1,417 1,400 1,500 1,600 1,800 1,900 2,000
収益事業 0 0 0 40 80 160 160 160 160
管理費 人件費 3,265 2,934 2,376 3,134 3,100 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
使用料・賃借料 900 913 781 661 600 600 600 600 600 600
委託費 130 234 264 93 90 90 90 90 90 90
その他管理費 300 300 485 490 465 442 420 400 380 360
管理費計 4,595 4,381 3,906 4,378 4,255 4,032 4,010 3,990 3,970 3,950
支出計 7,882 7,897 7,291 8,194 7,334 7,306 7,409 7,556 7,626 7,736
収入 - 支出 ▲ 2,396 ▲ 1,317 ▲ 1,061 ▲ 322 56 34 81 34 24 14
実質基本財産年度末残額 24,340 27,113 27,113 27,113
トラストファンド年度末残額 10,387 9,162 8,142 6,072 4,972 3,872 3,072 2,472 2,122 2,072

参考 (財務状況データの推移)
H22 H23 H24 H25 H26 H27
一般正味財産 10,619 21,193 8,134 5,914 19,380 9,138
指定正味財産 354,790 345,100 333,789 313,645 347,272 362,743
280300320340360380
(1) 正味財産
・H25年1月に遺贈による寄附の申し出があり、その収入を見込んで支出したH25年
度経費について、寄附金の入金が遅れたことから指定正味財産(ブナ・ゼフィルスの森基金)から取り崩して補填。H26年度に入金(57,180千円)があった後、戻入れ。
H22 H23 H24 H25 H26 H27
管理費 38,30 13,18 7,727 10,65 13,24 14,85
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
(2) 管理費
・H23年度以降は、公益法人会計基準により事業実施に係る人件費は事業費に計上されるため、管理 費は減少。 ・H24年度から暫増。
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
H元 H3 H5 H7 H9 H11H13H15H17H19H21H23H25H27
(3) 大阪府補助金
・H22年度より、事業費の1/2補助、H25年度30%カット。 ・H24年度府職員引揚げ
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
H元
H3
H5
H7
H9
H1
1
H1
3
H1
5
H1
7
H1
9
H2
1
H2
3
H2
5
H2
7
(4) 会費
・H5年度(5,337千円)をピークに暫減。 ・H25年度「御堂筋アメニティ事業」を継承により増加したもので、増加分
は御堂筋アメニティ事業に充当。
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
H元 H3 H5 H7 H9 H11H13H15H17H19H21H23H25H27
(5)みどりの募金寄附額
・H23年度以降、20,000千円~25,000千円で推移。
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
H4
H6
H8
H1
0
H1
2
H1
4
H1
6
H1
8
H2
0
H2
2
H2
4
H2
6
(6)ブナの森・ゼフィルスの森基金
合計残額
・H22年度までは暫増であったが、H23年度以降減少傾向。 ・H25年度に約2000万を取り崩して一般正味財産に振替え。
H26年度の増要素は、寄附により戻入れたもの。((1)正味財産に同じ)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26
(7) ブナの森トラスト基金寄附額
・H6年度(14,885千円)をピークに暫減、過去10年は600千円~800千円程度で推移。
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
H4 H6 H8 H10H12H14H16H18H20H22H24H26
(8) ゼフィルスの森トラスト基金寄附額
・H6年度(8,435千円)をピークに暫減、過去10年は100千円~200千円程度で推移。

<参考>
★ SWOT分析(内外からの視点による現状分析)
1)機会(外部環境におけるビジネスの機会) ・地球温暖化防止意識の高まり ⇒ 木材や木質エネルギーの重要性が浸透
・生物多様性保全について
大阪市が多様性保全地域戦略を策定中。 ⇒ 各主体間の連携・協働を促進し、取組を継続していく
ための仕組み作りが課題となっており、生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携支援センターの
設置も求められている。
・多種多様な自然環境保全等の活動グループの発生 ⇒ 協会が活動を支援
・来年度からのさともり事業の実施に当たっては、府の出先事務所や市町村の協力が期待される。
⇒ 活動団体へのアンケート調査により、支援のニーズを把握
・さともり事業の地域協議会の事務局であることから、事業実施団体間のネットワーク化がしやすい状況
・他団体との連携の機運の高まり ・SNSの普及で、情報の受発信がしやすくなった
・遺贈の動きが出てきている ・団塊の世代の労働力が期待される
・ファンドレイジングの普及により、必要な資金の調達が容易になる
・今年度から府で4年間、森林環境税を導入(~31年度) ⇒ 府民の森林への関心が向上。
・環境省公募事業(能勢町と吹田市の交流事業)の採択(H28~30)
⇒トラストの活動、能勢町の資源を知ってもらう良い機会
・環境ESDがH32年頃から、小学校でカリキュラム化
2)脅威(外部環境におけるビジネスリスク) ・震災、消費税アップ、経済の低迷により、自然環境保全事業や緑化への寄付が集まりにくい
・ゼロ金利政策により、利子に頼った事業ができない
・地球温暖化、カシノナガキクイムシによる被害、湿地の陸地化等により3事業地の環境が悪化
・里山の資源循環システムが無くなり、放置森林が増加
・さともり事業はH29年度制度改正。新規優先。地方自治体の負担がないと優先採択がされない
3)協会の強み(同業他者に比べて優位な部分) ・能勢エリアでの豊富な財産(地域の信頼感、ひと、情報、技術、実績等)
・府の出資法人として、高い信用度 ・大阪府唯一の緑の募金の執行機関
・大阪府唯一のさともり事業の事務局 ・府域全体で活動
・(公社)国土緑化推進機構からの支援が得られやすい
・設立28年間の歴史と実績・独自のノウハウ・ひととのつながり
・協会を支援してくれる団体・企業の存在 ・独自のボランティア、みどりすとを抱えている
・各団体とのコミュニケーションがとりやすい
・事務所が、グリーンエコプラザ内に所在し、環境保全に高い意識を持つ団体との交流が容易
4)協会の弱み(同業他者に比べて劣っている部分) ・収入(会費、募金額、寄付金額)の減少
⇒ とりわけ、府の補助金に依存している体質から抜け出せていない
・ブナ林と三草山以外の活動資金の受け皿がない。
・協会の認知度が低い ⇒ 協会全体としてPRしようという意識・体制に課題あり
・協会の組織体制が脆弱 ・活動ボランティアの高齢化
・活動の核になる人材が育っていない
・活動に対する明確なビジョン、戦略などが見えない
・大阪市内の企業へのアプローチができていない
・これまでの調査結果がアーカイブ化されていない

Ⅱ 現状と課題 1 協会の状況 1)役職員数の推移 2)補助金等の推移 3)会員数の推移 4)みどりの募金の推移 5)資産・負債の推移 6)収支状況
強み
機会
◆ 機会と協会の強みを生み出す
戦略は何か?
・生物多様性保全についての、他団体と
の差別化や協働の取組の検討
・さともり活動(里山)および市街地の緑化
グループを核としたみどりのプラットホー
ムの構築
・生物多様性人材バンクの創設
・協会の強みを活かした収益事業の創設
の検討(人材育成、出前研修、技術指
導、クラフト開催、指定管理等)
・協会のこれまでの蓄積を整理し、アピー
ルする。それを活用し新たな価値の創出
を図る
・協会への信用を背景とした遺贈対策を
強化し、それを里山の保全につなげる
脅威
弱み
◆ 協会の強みを保持したまま、脅
威を回避する戦略は何か?
・グリーンエコプラザ内の活動団体への緑
の募金や自然環境保全への協力要請さ
らには、エイジレスセンターとの連携(高
齢者・福祉対策との連携)
・府・市町村・企業との連携を強化し、放置
森林のさともり活動グループによる再生
を推進
・協会のPRの強化と併せたクラウドファン
ディングによる3事業地の再生
・CSR活動企業による支援を拡大
◆ 弱みを解消して、機会を活かす
戦略は何か?
・SNSの活用等による協会のPR強化。そ
れによる事業収入と会員拡大
・3大事業地の聖地化(行ってみたいと思
わせるような写真・動画を使用したPR、
映画やドラマのロケーションサービスへの
アプローチ等)
◆ 弱みを最小化し、脅威を回避す
る戦略は何か?
・トラスト協会の明快な活動ビジョンづくり
により、組織目標を統一し、協会全体とし
て動く
・協会事務所での活動ボランティア・スタッ
フの募集
・みどりの募金事業の里山保全事業への
活用拡大
・三草山、ブナ林以外の活動に対する寄
付金の受け皿の創設










![Honda GROM/MSX125 2013-2020 AIpro APH4 · 2020. 7. 13. · Honda GROM/MSX125 2013-2020 ・..付属の結線コネクターでAIproの [黒/緑]線をECU コネクタ内の「黄/緑」](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/611ed0bc8b6bbd172e267461/honda-grommsx125-2013-2020-aipro-aph4-2020-7-13-honda-grommsx125-2013-2020.jpg)