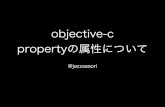6.Qsys コンポーネントの作成...Editor に重点を置いて、 Qsys コンポーネントの構造を説明しています。この Component Editor はコンポーネントについてQsys
和敬 - Akitaずしも正しい使い方がされていない場合があるこ...
Transcript of 和敬 - Akitaずしも正しい使い方がされていない場合があるこ...

豊かな心をもち、たくましく生きる雄中生
秋田市立雄和中学校学校だより 第10号平成26年12月25日和 敬 心穏やかにして、
相手を敬う
冬休みを迎えるにあたって
校長 加賀谷 亨
保護者の皆様には、日頃から子どもたちのために、本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。早いもので、明日から冬休みを迎えます。今日25日(木)は大掃除の後、給食を挟んで
「 」、「 」3年生を励ます会 部活動報告会&賞状伝達そして、全校集会を行いました。全校集では、加藤千穂さん(1B 、種村凜々)
子さん(2A 、藤原惇二郎君(3A)が、冬休)みの抱負を発表しました。3人のやる気に満ちた話に続き、生徒の皆さん
に、次のように語りかけました。
「総合的な学習の時間の発表会」の最後を飾った、伊藤代介さんの言葉は大変印象的でした。皆さんも、心に残っていることがあると思います。伊藤さんのお話の中に、皆さんへのメッセージとして、こんなフレーズがあったことを覚えているでしょうか。「仕事ができるとかできないとかの前に、
大切なのは、あいさつと言葉遣い」今日は、この「あいさつ」について、皆さ
んに考えてもらおうと思います。といっても、伊藤さんのお話を伺うまでも
なく、皆さん自身、あいさつの大切さは十分にわかっていますよね。では、改めて考えてみてください。どうし
て、あいさつは大切なのでしょうか。こんな話を聞いたことがあります。ある経営コンサルタントの方のお話です。そのコンサルタントの方が、ある会社に教
えたノウハウが成功したのに、別の会社にそのノウハウを持っていったら、うまくいかないということがあるんだそうです。別の会社でも十分に使えると、自信があったにもかかわらず、です。長い時間をかけて、あるとき、その理由に
気が付きました。それは、不思議なことに、「社員同士が、気持ちのいいあいさつができない会社に、どんなノウハウを持っていっても、うまくいかない」ということでした。そこで、次に、あいさつとは何か、あいさ
つの目的は何かという、もっと根本的なことを考えてみることにしました。そして彼は、一つの結論に達します。それは 「あいさつとは、相手の存在を認、
め、相手に対して心を開くこと」でした。とすれば 「会社の中であいさつができな、
いというのは、一人一人が同じ会社の仲間に心を開いていない」ということになります。相手に心を開いていない人というのは、ど
んな話をしても 「そんなんでうまくいくの、かよ」とか「大変な仕事でやりたくないよ」という気持ちで聞いてしまいます。心を開いて話を聞くことができれば 「な、
るほどな、ちょっとやってみようか」と思うことができるわけです。一人一人がそんな風に思える会社であれ
ば、コンサルタントの方の示したノウハウが
生きてくるんですね。さて、この「会社」を「学校」に置き換え
たらどうでしょう。生徒同士、生徒と先生が、お互いを認め合
い、心を開いて、気持ちよくあいさつができる学校の未来は、たぶん、明るいですよね。もう一度おさらいです。「あいさつとは、相手の存在を認め、相手
に対して心を開くこと」では、ここで年末年始の宿題です。相手を認め、心を開いたあいさつとは、具
体的にどんなあいさつなのでしょうか。そのポイントは4つあります。
、「 」 。一つ目は 大きな声で わかりますよね二つ目は 「相手の目を見て」これもわか、
りますね。、 、 。では あと二つは どんなことでしょうか
言葉としては簡単なものですから、思いつくのは、そう難しくはないと思いますよ。冬休み明けの集会で、お話したいと思いま
すので、一人一人、考えてみてください。、 、 、 、さしあたって まずは 今日 帰るときに
友達に、先生方に 「相手を認め、心を開い、たあいさつ」をしてみましょう。そして、新しい年を迎えた朝には、皆さんの家族に、そんなあいさつをしてみてください。
後期生徒会では、「雄中連敬宣言」のスローガンのもと、“当たり前のことを当たり前にできる”ことを目指して、自主的な委員会活動に取り組んでいます 専門委員会の活動目標にも 元。 「気なあいさつが飛び交う… 「あいさつから始ま」る…」といった言葉がちりばめられています。
、 、明日からの冬休みは 自分なりの計画のもとに有意義に過ごすことはもちろんですが、雄中生全員が、今年の自分から、ちょっとだけ成長した自分になって、新しい年を迎えられることを願っています。
相手を認め心を開いたあいさつの
ポイント
大きな声で
相手の目を
見て??
大会等の結果から
〇白百合カップバスケットボール大会第3位 バスケットボール部優秀選手賞 安藤千遥さん
※全県優勝による表彰〇秋田市中学校体育連盟表彰栄光賞 バスケットボール部
〇秋田市バスケットボール協会表彰優秀選手賞 田辺夏菜さん
〃 那須仁世さん〇税についての中学生の作文
優秀作品賞 山内 優君〇中央地区アンサンブルコンテスト
木管6重奏 銀賞 吹奏楽部金打8重奏 銅賞 〃

国際教養大学の学生さんによるサポート授業を実施しました
12月2日(火)の午、 、後 2年生の各クラスで
国際教養大学の学生さんによるサポート授業を実施しました。雄和地区を含め市内の
小学校では、同大学の外国からの留学生を招いて、異文化に対する理解を深めたり一緒に外国語活動を行うなどの取組を行っていますが、本校では、日本人の二人の学生さん(赤間建哉さん、濱田太郎さん)をお呼びし、大学生活の様子や英語の学習の仕方、外国や外国人に対する見方などについて、お話を伺いました。様々な刺激を受けた2年生の感想から、いくつ
か紹介します。〇お二人とも最初は、英語が得意ではなかったと聞いて、とても驚きました。私も苦手なのですが、努力すればできるようになることを信じて、頑張りたいと思いました。
〇歴史や文化、習慣が異なっていても、お互いを理解しようとする気持ちが大切なのだということを教えてもらいました。
“Mutual Under〇お互いに受け入れようとする(相互理解)や、決してあきらめstanding”
、ない といった言葉にふれ“ ”Never give up勉強心に火をつけられ、やる気が出ました。
薬育の授業から
12月11日(木 、学校薬剤師の佐藤拓哉先)生を講師に、薬の正しい知識と使い方を学ぶ「薬育」の授業が、3年生を対象に行われました。
佐藤先生からは、薬を服用した際の血中濃度の変化について説明していただいたり、実際の薬を用いた実験を見せていただいたりしながら 「な、ぜ薬は正しく使わなければならないか」を、わか
りやすく教えていただきました。【授業後の感想から】
僕は今まで水ではなく、お茶やジュースなどで薬を飲んでいたけど、それはあまり良くないということが、一番印象に残りました。これからは、薬の使い方や回数などをしっ
かりと理解して安全に使いたいと思います。そのために、薬のパッケージなどにある注意事項をしっかりと読んでいきたいです。
身近な薬についてはあまり良く考えたことがなかったので、今日聞いた話はとても勉強になりました。特に、目薬の差し方を学べたのが良かった
です。家族の人にも教えてあげたいです。
薬は私たちにとって大変身近なものですが、必
ずしも正しい使い方がされていない場合があることに気づかされました。薬による健康被害や薬物乱用を防ぎ、生涯にわ
たって自己の健康管理を適切に行っていくことの大切さを学ぶ機会となりました。
母校訪問を行いました
11月の小学校6年生の体験入学に続き、12月18日(木 、今度は本校の1年生がそれぞれ)
「 」 。の出身小学校を訪ねる 母校訪問 を行いました各小学校での活動の様子を紹介します。
川添小学校
◇1~5年生の教室で、算数の授業のお手伝いをしました。
◇総合的な学習の時間で学習したことの発表や、中学校での授業の進め方、部活動などについて説明し、質疑応答を行いました。
種平小学校
◇クイズ形式で授業や部活、動について説明したほか
吹奏楽部員により楽器の演奏も披露しました。
◇総合的な学習の時間で学習したことの発表や算数のプリント丸付けのお手伝いをしました。
◇最後に、種平小産のトウモロコシで作ったポップコーンを食べながら、座談会を行いました。
戸米川小学校
◇地主重子先生(本校学校評議員)を講師に俳句会を開きました。
◇総合的な学習の時間で学習したことの発表や、中学校生活の説明などを行いました。
◇最後に、座談会を行いました。
大正寺小学校
◇授業や部活動、生徒会活動などの説明と、入学に当たっての6年生へのアドバイスをしました。
◇総合的な学習の時間で学習したことを発表した、 、 。後 最後に 児童室でみんなで遊びました
懐かしい校舎に足を踏み入れ、お世話になった先生方やかわいい後輩たちと再会し、楽しい時間を過ごすことができました。また、事前の準備にしっかり取り組んだことで立派な発表や説明ができ、自分に自信がもてました。中学生としての自分の成長を実感した一日でした。

「総合的な学習の時間発表会」を開催しました
校長 加賀谷 亨
12月6日(土 、学年・学級PTAに合わせ)て、初めての試みとなる「総合的な学習の時間」の発表会を開催しました。職場訪問や職業体験、修学旅行などの体験的な
学習を中心に、自分自身の将来やこれからの生き方について、全校生徒一人一人が、感じたり考えたりしたことを、自分なりの言葉で伝える学習でした。
当日は三部構成で 「発、表会1」では、全校生徒が八つのグループに分かれ、それぞれの会場で全員が発表しました。「発表会2」では、体育
館を会場に、各学年の代表が個人やグループで発表を行いました。保護者や地域の皆様に
は、朝早くから発表会の様子をご覧いただきまして、ありがとうございました。生徒にとっても、教職
員にとっても、よい刺激と温かな励ましをいただいたと考えております。「発表会2」の終了後、講評として、次のよう
に語りかけました。
どの発表にも、一人一人の考えがしっかりと表れていました。職場訪問や職場体験を通して、働くことの
イメージが大きく変わったことや、自分自身の今を見つめ直そうとしていること、また、これまでの学習をもとにした現時点での人生設計など、各学年ならではの考え方を感じ取ることができました。次に、発表の仕方がすばらしかったです。プレゼンテーションソフトを駆使したスラ
イドなどを効果的に活用しながら、聴き手を意識し、声の大きさはもちろん、スピードや
、 、表情 マイクの使い方などが工夫されていて自分の思いや考えを伝えたいという気持ちがよく表れた発表でした。三つ目に、ふるさと雄和への思いがあふれ
る発表を聞いて、うれしくなりました。少子化、高齢化の波は、県都秋田市にも例
外なく押し寄せてきています。皆さんの大好、 、きなふるさと雄和の将来像も もしかしたら
明るいことばかりではないかも知れません。皆さんには、遠く離れて生活していても、
いつも雄和を思い、雄和の地に暮らしながら日本や世界を思う、そんな人になってほしい
と願っているのですが、ふるさとの未来に、何らかの形で関わっていくぞ、そんな気持ちがにじみ出ている発表を聞くことができて、とてもうれしくなったのでした。
そして最後は、種沢ファームの伊藤代介さんを講師に迎えての講演会を行いました。伊藤さんは、地域の農業を担う若き営農家で、
JA新あきたの広報誌「いぶき (H26.10月号)」の巻頭で紹介されていたのを拝見し、半ば強引に講師をお引き受けいただきました伊藤さんからは、農業を志したきっかけ、仕事
の苦労ややりがい、将来の目標などに加え、中学時代の思い出(本校の卒業生)や雄中生へのメッセージなどをお話いただきました。今も印象に残る内容をいくつか紹介します。
( ) 、〇植物 農作物 は子どもと同じように世話をしないと育たない。
〇農作物の生産や販売をとおして、新たな人間関係が生まれることがうれしい。
〇後継者不足が叫ばれる中、農業のイメージを変えたい。
〇農業について、他の地域で学んだことを生かして、地元を守りたい。
〇何を生産するにしても、消費者の口に入ることなど、売れた後のことをイメージして働くことが大切だと考えている。
〇地元(雄和)のよさは、みんながお互いのことを知っていて、心配してくれること。
〇日本の食糧自給を支えているとの気概が、農業者のこだわり。
、 、〇仕事ができる できないの前に大切なのはあいさつと言葉遣い。
〇高校に進めば、今まで経験したことのない大きな集団となる。あまり虚勢を張って自分を大きく見せない方がよい。
雄中生の皆さんは、地域とともに歩んでおられる先輩のお話に真剣に耳を傾けるとともに、たくさんの質問を浴びせ、有意義な時間を共有しました。
全ての活動をとおして、改めてふるさとへの誇りや愛着を深めるきっかけとなったのではないか、そんな手応えを感じ取ることができました。ご来校くださった皆様や、体験活動の際にお世
話になった皆様に、改めて感謝いたします。

冬休みにオススメ!私のとっておきの一冊
明日から冬休み、年末年始は何かと気ぜわしいものですが、そんなときこそ、じっくり読書を楽しむのはいかがでしょうか。夏休みに続き、先生方から、とっておきの作品
を紹介してもらいました。図書委員会からのおすすめの一冊と合わせて、参考にしてください。
事務センター 橋本敏一先生
著者の東田直樹さんは、自閉症により音声で会話ができないため、文字盤を指さしながら意思を伝える「文字盤ポインティング」やパソコンを利用してコミュニケーションをとっています。自閉症の人たちがどんなことを思い、どのように考えているかを多くに人に理解してもらいたい、
、「 」そんな願いから生まれたのが 跳びはねる思考です。東田さんは、人生にとって重要な学びは二つあ
ると言います。一つは「勉強して、考える力を身に付けること」もう一つは「自分の幸せに気づくこと」東田さんの言葉に触れて、新たな発見をしてく
ださい。
事務センター 工藤芳子先生
みなさんにぜひ読んでほしいのは 「私は赤ちゃん (岩、 」波新書)です。著者の松田道雄さんは小児
科医です。診察室で赤ちゃんと接する毎日の中で、親や大人たちから不当な扱いを受けている赤ちゃんが少なくないことを感じてこの本を書きました。この本には、赤ちゃんの目
線から、家庭や社会がどうあってほしいかが、わかりやすく書かれています。私の長女は、予定日よりも早く生まれました。
夜泣きは何度もするし、抱っこをしていないと泣くし、げっぷは出ないし…、このままで本当に赤ちゃんが育つのかと不安だらけの生活でした。
、 。そんなとき 母がこの本をすすめてくれました読んでみると 「赤ちゃんは夜に泣くもの 「お母、 」さんに触れているのが大好きなこと 「人間は一」人一人、別あつらえ であるこ(一人一人違っていること)
と」など、私の育児への不安を和らげてくれることがたくさん書いてありました。皆さんもいつか子どもをもつかも知れません。
そのときに思い出してほしいので、今のうちにぜひ一度読んでみてください。
学級生活支援サポーター 工藤由紀子先生
出光興産の創業者、出光左三さ ぞう
をモデルとした小説「海賊とよばれた男 (百田尚樹)を紹介」します。明治18年、福岡で生まれた
左三は、25歳のときに石油販売の会社を作ります。当時の日本には、200台程度しかなかった石油で走る自動車が、今後は爆発的に増えると予測し、い
ずれ軍艦も石油で動く時代が来ると考えたからです。その際、秋田の八橋油田、道川油田、豊川油田も視察したそうです。そして、第一次大戦中には海外にも進出し、会
社を大きくしていきました。しかし、第二次大戦で日本が敗れ、国中が焼け
野原になったとき、左三は全ての仕事もあらゆる財産も失いました。それでも彼は 「社員こそが財産」という信念、
のもと、一人の社員もリストラすることなく、幾、 。多の困難を乗り越えて 会社を再生していきます
「人は何のために働くのか 「働くとはどうい」うことか」そんなことを考えながら、寝る間も惜しんで読みふけってしまいました。みなさんにも、ぜひ読んでもらいたいです。
学級生活支援サポーター 鈴木ルミ子先生
54年ぶりに再会した少年時代の親友、マックスとジム。マックスはビジネスで成功
し、ジムは財産も仕事も失って人生に行き詰まっていました。運がないと嘆くジムにマックスは、自分を成功に導いた「魅惑の森」の物語を語り始めます。幸運をもたらす魔法のクロー
バーを探しに「魅惑の森」へ旅立った二人の騎士。黒騎士ノットは、自分からは何もせずにクローバーが手に入るのを待ち続け、白騎士シドは、こつこつと苦労を重ねてクローバーを手に入れます。幸運とは何か、どうすれば手に入れることがで
きるのか。幸運は訪れるのを待つのではなく、自らの手で
つくり出すものだと、この本は教えてくれます。夢や希望をもち、志を掲げて頑張っている皆さ
んへおすすめの一冊、それが「 (アレGood Luck」ックス・ロビラ、フェルナンド・トリアス・デ・ベス)です。有意義な冬休みをお過ごしください。