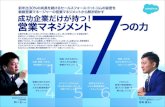データマイニングと機械学習 - Kyoto U...2013/06/04 · pjは 入力パターンpに対する出力ユニットjにおける誤差(希望出力t pjと 実際の出力o
Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力...
Transcript of Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力...
![Page 1: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/1.jpg)
単なるテキストの鑑賞ではなく
「生きるために必要な」読解力
OECD(経済協力開発機構)が国際的に実施する「生徒の
学習到達度調査」|通称PISA(ピザ)は、2003年に第2
回が行われました。この調査に参加したのは41の国・地域の
約27万人の15歳児です。日本では全国の高等学校等の1年
生、約4700人が参加しました。
読解力調査の日本の平均得点は、参加した国・地域の中で
14位(498点)。第1回調査(00年)の8位(522点)から大
きく低下しています(図表1)。この24点の低下幅は、参加し
た国・地域の中で最大でした。
出題形式別に分析してみると、日本の高校生がどんな問題
を最も不得意としているのか、よく分かります。
OECD平均と比較して、日本の高校生の「無答率」が著し
く高いのが「自由記述問題」です(図表2)。自由記述問題の
無答率は、OECD平均より8.1ポイントも高くなっています。
逆に多肢選択問題では、日本の無答率はOECD平均より低
いのです。
ちなみに00年の第1回調査でも、やはり日本の無答率は
OECD平均より8ポイント高かった。00年と03年で比較す
ると、無答率が5ポイント以上上昇した問題の67%が、やは
り自由記述問題でした(図表3)。
こうしてみると、PISAにおいて日本の高校生の読解力が
低水準の理由の一つは、自由記述問題の無答率の高さにある
ことは間違いありません。
そこで、まず押さえておかなければならないのは、PISAで
試される読解力とはどんな能力か、ということです。
PISAでは、「読解力」を次のように定義しています。
「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、
効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、
利用し、熟考する能力」
注目すべきなのは、「効果的に社会に参加するために」の部
分。言い換えれば「生きるために」必要な読解力です。
これは、従来の日本の国語教育でいう「読解力」とは、ず
いぶん違います。日本の国語での読解力とは、あくまでも
「テキストの内容を理解する能力」。テキストに書いてあるこ
とをよく理解しているかどうかだけなら、多肢選択問題によ
って評価できます。だから、この形式の問題に慣れている日
本の高校生は、PISAでも無答率が低いのでしょう。
ところが、PISAでいう読解力は、内容を理解した上で、
「利用し、熟考」して「効果的に社会に参加」し「自らの目標
を達成」できる能力です。そのために必要なのは、自分の意
見を述べること。したがってPISAでは、読み解いたことに2
Interview「生きる力」につながるPISA型の読解力──根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換──●
有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]
ISAの読解力調査で日本の高校生の無答率が高いのは、
資料を基にして自分の意見を述べる自由記述問題だ。
この事実はどんな課題を示唆しているのか。
PISA型の「効果的に社会に参加するための」読解力を養うには、
日本の国語教育に何が足りないのだろうか。
PISAの分析に基づいて授業改革を提案する
有元秀文先生に話をうかがった。
Pありもと ひでふみ●
国立教育政策研究所教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官。
早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。
東京都立新宿高等学校教諭、
文化庁文化部国語課国語調査官、国立教育研究所
教科教育研究部主任研究官を経て現職。
主な著書に『「国際的な読解力」を育てるための
「相互交流のコミュニケーション」の授業改革』
(溪水社)、『読書へのアニマシオン入門』
(学習研究社)などがある。
![Page 2: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/2.jpg)
3
NO
.06
2
00
6
特集 読解力(reading literacy)、日本の教育の何が問われているのか
図表[1] 読解力得点の国際比較(PISA2003)
543534
528 525 522515 514 513
507500 499 498 494
450
400
550
500
0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.0
600(点)� (%)�
日本�
OECD
フィンランド�
23.7
15.6
自由記述�
14.713.9
短答�
9.18.3
求答�
4.5
多肢選択�
韓 国�
カナダ�
オーストラリア�
ニュージーランド�
アイルランド�
スウェーデン�
オランダ�
ベルギー�
ノルウェー�
スイス�日 本�
OECD平均�
2.7
薬物を与えられたクモ 熟考・評価 自由記述 ��求職 解釈 短答 ��メガネ技師 熟考・評価 自由記述 ��薬物を与えられたクモ 解釈 自由記述 ��南極点 情報の取り出し 短答 ��薬物を与えられたクモ 解釈 自由記述 ��ワイシャツ 解釈 求答 ��電話 情報の取り出し 求答 ��電話 情報の取り出し 短答 ��メガネ技師 情報の取り出し 短答 ��南極点 解釈 多肢選択 ��ワイシャツ 解釈 自由記述 ��南極点 解釈 多肢選択 ��求職 熟考・評価 自由記述 ��南極点 解釈 多肢選択
6.7
6.6
6.1
5.9
5.6
5.4
2.9
2.7
2.4
2.1
2.0
2.0
1.9
1.7
1.5
問 題� 読解のプロセス� 出題形式�2000~2003の�無答率上昇ポイント�
図表[2]出題形式別無答率(PISA2003)
読解力得点:PISA調査の平均得点が500点になるようにし、さらにOECD加盟国の全生徒の約3分の2が、400点から600点の間に入るように(標準偏差が100になるように)計算したものである。OECD非加盟国であるリヒテンシュタイン(5位)と香港(10位)を除く。
自由記述…自分の考えや理由などを答える記述式問題短答………さまざまな解答が考えられる短い記述式問題求答………解答が一つしかない短い記述式問題多肢選択…複数の解答候補が用意された選択肢問題
図表[3] 無答率の上昇ポイント
![Page 3: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/3.jpg)
ついて自分なりの意見を表現することが重視されます。日本
の高校生は自分の意見を問われる自由記述問題に慣れていな
いため、どう答えてよいか皆目見当がつかず、無答率が高く
なると思われます。日本の国語教育でも自由記述問題はあり
ますが、生徒に意見を問うことは、あまりありません。
このように読解力についての考え方が大きく違うため、
PISAの出題には日本の国語の出題には見られない特徴が多
く見受けられます。それは次のように整理できます。
(1)現実の社会で直面する、生きるために必要不可欠な実際
的な課題が対象になる。
(2)通常の文章は6割で、残りの4割は実用的な図表・地図
などが占める。
(3)国語の枠を超えて、理科や社会科に関する幅広い話題が
含まれる。
(4)自由記述問題が4割を占める。
(5)読んだことについて「自分の意見を表現する」ことが求
められる。
(6)テキストについて評価や批判が求められる。
(7)意見を書くときには「テキストに書かれたことを根拠に
する」ことが求められる。テキストに書かれていない根
拠を挙げると正答にならない。
このうち(1)から(4)までは題材の選び方や形式に関す
ることですから、今すぐにでも日本の国語教育に取り入れよ
うと思えばできることです。PISAというと、とかくこの部分
だけに目が行きがちですが、むしろ本質的な課題として注目
すべきなのは(5)から(7)までの特徴です。
とりわけ日本の国語教育で馴染みがないことは(6)のテ
キストの評価や批判|つまりクリティカル・リーディング
(批判的読解)でしょう。クリティカル・シンキング(批判的
思考力)の基礎をこれによって養うわけです。具体的にいう
と、例えば物語文を読ませて「主人公の取った行動について
どう思いますか?」と問いかける。あるいは、意見文を読ま
せて「この意見について賛成ですか、反対ですか?」と聞く。
登場人物の気持ちに寄り添って鑑賞させたり、筆者の主張を
正しく理解させることだけに主眼を置く従来の日本の国語教
育では、こうした学習が欠けがちだったのです。
日本の高校生が際立って答えられない
「自分の意見を述べる」自由記述問題
PISAの読解問題は次の3種に大別されます。
(1)情報の取り出し:内容を正確に理解した上で、テキスト
の中から「情報」を取り出す。
(2)解釈:内容を正確に理解した上で、テキストを根拠にし
て推論し、自分独自の「解釈」を述べる。
(3)熟考・評価:内容を正確に理解した上で、自分の知識や
経験や考え方と結びつけて熟考・評価したり、テキスト
を根拠にして自分独自の意見を述べる。
では、実際の問題例で確かめてみましょう。2人の高校生
から学校の壁の落書きについて賛否両論のeメールが送られ
てきた、という設定の問題です(図表4)。課題文を一読して
分かる通り、落書き擁護派のソフィアの文章は明快な三段論
法の手法をとっています。すなわち、①店の看板やポスター
は広告というコミュニケーションの手段として許されている。
②落書きもコミュニケーションの手段の一つ。③だから落書
きも許されてよい。
この課題文について問2は、ソフィアが広告を引き合いに
出した理由を問います。「解釈」の問題です。正答基準は「広
告と落書きの共通点を挙げて落書きを擁護するため」であると
「推論」ができていること。このプロセスが「解釈」にほかな
りません。問2に対する日本の無答率は29%で、フィンラン
ドやOECD平均の約3倍、アメリカの約7倍です。
続いて問3は、2通の手紙のどちらに賛成するか。「熟考・
評価」の問題です。設問には、本文中の根拠を必ず使って自
分独自の意見を述べること、という趣旨の条件が付いていま
す。正答基準は次の通りです。「片方または両方の手紙の内容
に触れながら意見を述べている。手紙の筆者の主張全般や意
見の詳細を説明していてもよい。手紙の筆者の意見に対して
説得力のある解釈をしていること。課題文の内容を言い換え
て説明しているのはよいが、何も変更や追加をせずに課題文
全部または大部分を引用するのは不可」。日本の無答率は
15%で、フィンランドやアメリカの5倍でした。
次の問4も「熟考・評価」の問題ですが、こちらは課題文
の評価の方に重点が置かれています。どちらの手紙の内容に4
Interview「生きる力」につながる P I S A 型の読解力
![Page 4: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/4.jpg)
5
NO
.06
2
00
6
特集 読解力(reading literacy)、日本の教育の何が問われているのか
図表[4] 読解力の問題例「落書きに関する問題」
左の2通の手紙は、落書きについての手紙で、インターネ
ットから送られてきたものです。落書きとは、壁など所かま
わずに書かれる違法な絵や文章です。この手紙を読んで、問1
~4に答えてください。
落書きに関する問1
この二つの手紙のそれぞれに共通する目的は、次のうちどれで
すか。
A 落書きとは何かを説明する。
B 落書きについて意見を述べる。
C 落書きの人気を説明する。
D 落書きを取り除くのにどれほどお金がかかるかを人びと
に語る。
落書きに関する問2
ソフィアが広告を引き合いに出している理由は何ですか。
落書きに関する問3
あなたは、この2通の手紙のどちらに賛成しますか。片方
あるいは両方の手紙の内容にふれながら、自分なりの言葉を
使ってあなたの答えを説明してください。
落書きに関する問4
手紙に何が書かれているか、内容について考えてみましょう。
手紙がどのような書き方で書かれているか、スタイルにつ
いて考えてみましょう。
どちらの手紙に賛成するかは別として、あなたの意見では、
どちらの手紙がよい手紙だと思いますか。片方あるいは両方
の手紙の書き方にふれながら、あなたの答えを説明してくだ
さい。
落書き
学校の壁の落書きに頭に来ています。壁から落書きを消し
て塗り直すのは、今度が4度目だからです。創造力という点で
は見上げたものだけれど、社会に余分な損失を負担させない
で、自分を表現する方法を探すべきです。
禁じられている場所に落書きをするという、若い人たちの
評価を落とすようなことを、なぜするのでしょう。プロの芸術
家は、通りに絵をつるしたりなんかしないで、正式な場所に
展示して、金銭的援助を求め、名声を獲得するのではないで
しょうか。
わたしの考えでは、建物やフェンス、公園のベンチは、そ
れ自体がすでに芸術作品です。落書きでそうした建築物を台
なしにするというのは、ほんとに悲しいことです。それだけ
ではなくて、落書きという手段は、オゾン層を破壊します。
そうした「芸術作品」は、そのたび消されてしまうのに、こ
の犯罪的な芸術家達はなぜ落書きをして困らせるのか、本当
に私は理解できません。
ヘルガ
十人十色。人の好みなんてさまざまです。世の中はコミュ
ニケーションと広告であふれています。企業のロゴ、お店の
看板、通りに面した大きくて目ざわりなポスター。こういう
のは許されるでしょうか。そう、大抵は許されます。では、落
書きは許されますか。許せるという人もいれば、許せないと
いう人もいます。
落書きのための代金はだれが払うのでしょう。だれが最後
に広告の代金を払うのでしょう。その通り、消費者です。
看板を立てた人は、あなたに許可を求めましたか。求めて
はいません。それでは、落書きをする人は許可を求めなけれ
ばいけませんか。これは単に、コミュニケーションの問題では
ないでしょうか。あなた自身の名前も、非行グループの名前
も、通りで見かける大きな制作物も、一種のコミュニケーシ
ョンではないかしら。
数年前に店で見かけた、しま模様やチェックの柄の洋服は
どうでしょう。それにスキーウェアも。そうした洋服の模様や
色は、花模様が描かれたコンクリートの壁をそっくりそのま
ま真似たものです。そうした模様や色は受け入れられ、高く
評価されているのに、それと同じスタイルの落書きが不愉快
とみなされているなんて、笑ってしまいます。
芸術多難の時代です。
ソフィア
国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能~OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2000年調査国際結果報告書~』(ぎょうせい)より
![Page 5: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/5.jpg)
賛成するかは別にして、どちらの手紙の方が、より書き方と
して効果的か、自分の意見を述べる問題です。「批判的な読
み」が要求されているわけです。意見は必ず「なぜならば」
という根拠とセットになっていなければならず、その根拠は
課題文中になければなりません。それが正答基準です。日本
の無答率は27%で、フィンランドの3倍でした。アメリカは
誤答率が51%と高いのですが、一方で無答率は6%と非常に
低い。こうした設問に対する日本の無答率の高さは、文章表
現の効果を評価・批判したり、本文を根拠にして独自の意見
を述べる教育が不十分なことを示唆しています。
アメリカやフィンランドの無答率が低いのは授業のスタイ
ルと関係があるのではないでしょうか。00年のPISAで「国
語の授業で先生が生徒に自分の意見を述べさせる割合」の調
査をしました(図表5)。「毎回の授業で意見を述べさせる」の
は、日本よりフィンランドが約8ポイント、アメリカは約10
ポイント高く、「まったくない」のはフィンランドは日本の半
分以下でした。生徒の主観による回答なので、もちろん一般
論として断言はできませんが、このデータを見る限りでは、
日本ではアメリカやフィンランドに比べて授業中に自分の意
見をいう機会が少ないといえそうです。
読解力を養うプロジェクト学習と
「読書へのアニマシオン」メソッド
読解力の平均得点で00年も03年も1位だったフィンラン
ドでは、どのような授業が行われているのでしょうか。
最大の特徴は、科目を問わず導入されている「プロジェク
ト学習」です。例えば環境問題といった一つの大きなテーマ
について多様な情報を集め、それに基づいて自分の意見をレ
ポートにまとめ、発表して、議論をする。ディスカッション
の場では、資料に基づいて相互批判が展開されます。
日頃こうした授業をしているので、フィンランドの子ども
たちは、読んだ資料の中から根拠を挙げて意見を述べたり評
価をしたりするPISA型の読解力テストで良い結果を出せた
のでしょう。
日本でも「総合的な学習の時間」でプロジェクト学習は導
入されています。しかし、欠けていることがある。それは文
字資料の読み込みとディスカッションです。日本のプロジェ
クト学習では、大体において、調べたことを模造紙に書いて
発表して終わり。調べる時に必ず文字資料を使わなければい
けない、ということもありません。神社へ行って聞いてきま
した、おじいちゃんに聞いてきました、というだけ。もちろ
ん、人物に取材して情報を得ることも大切ですが、それだけ
に頼るのではなく、本、雑誌、新聞、インターネットなど、
あらゆる媒体から必要な文字情報を収集する能力を養うこと
もプロジェクト学習の重要な目的の一つです。出典を明記し
た資料に基づいて自分の意見を発表し、相互批判を通じて、
どうしたらその課題を解決できるか皆で議論する。こうした
一連のプロセスがプロジェクト学習では大切なのです。
もう一つ、フィンランドの子どもたちの読解力が高い理由
として推測されるのが、本をよく読むこと。00年の調査結果
では、毎日1時間以上読書する生徒は、日本が11.7%だった
のに対し、フィンランドは22.3%(図表6)。読書時間と読解
力の関係を見ると、フィンランドではよく読書する生徒ほど
読解力の得点が高いことが分かります(図表7)。
日本では子どもより先に大人が本を読まない。親や先生が
本を面白がって読んでいる姿を子どもに見せないで、どうし
て子どもが本を読むでしょうか。しかし、すでに本を読む習
慣を失ってしまった大人が読書を日常の習慣に組み込むのは
時計を逆回しするようなことで、たいへん難しい。
そこで私が推奨したいのは、1970年代にスペインで開発さ
れた「読書へのアニマシオン」というメソッドです。「アニマ
シオン」とは英語でいえば「アニメーション」のことで、「魂
に元気を吹き込む」という意味。つまり、読書する子どもの
魂に元気を吹き込むための方法論です。モンセラット・サル
トが中心になって築き上げたこのメソッドでは、読書を押し
つけるのではなく、本を読みたいと思う潜在的な意欲を引き
出します。そのために取り入れるのが、ゲームや遊び。
例えば最も簡単なゲームは、低学年の子どもたちに先生が
絵本を1度読んであげて、2度目は「先生が読み間違えたら
教えてね」といってわざと読み間違える。「カラスがカーと鳴
きました」というところを「カラスがチューと鳴きました」
などと読み間違えると、子どもたちは喜んで「あ、違うよ!」
と口々に叫びます。間違いを発見するには集中して聞いてい
ないと分からないし、知らず知らずのうちにクリティカル・
リーディングの訓練にもなっているわけです。また、幼児向
けには、絵本の登場人物がケーキを持っていたり、リボンを
結んでいたり、スカートをはいていたりするのを見せた後、6
Interview「生きる力」につながる P I S A 型の読解力
![Page 6: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/6.jpg)
7
NO
.06
2
00
6
特集 読解力(reading literacy)、日本の教育の何が問われているのか
30.6
10.1
40.7
7.2
39.0
4.0
日本�
アメリカ�
フィンランド�
0 10 20 30 40 50(%)�
毎回の授業である� まったくない�
60
50
40
30
20
10
00 0~ 30分� 30分~ 1時間� 1時間~ 2時間� 2時間~�
(%)�
600
580
560
540
520
500
480
460
0 0~ 30分� 30分~ 1時間� 1時間~ 2時間� 2時間~�
(点)�
514
3.5
55.0
29.126.3
18.2
4.1
22.4
17.815.4
8.2
日 本�
フィンランド�
530
542568
577584
498
539 537 541
日 本�
フィンランド�
図表[5] 自分の意見を述べさせる割合(PISA2000)
図表[6] 毎日趣味で読書する生徒の比率(PISA2000)
図表[7] 読書時間と読解力得点の関係(PISA2000)
![Page 7: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/7.jpg)
ケーキの絵を示して「このケーキは誰の持ちもの?」と聞く
ゲームもよく行われます。さらには、高校生を対象にしたディ
ベートに近いゲームもあります。例えば、ある物語を読んで
から、何人かの生徒が登場人物にふんし、残りの生徒が登場
人物の取った行動の理由や、その是非などについて質問する。
その登場人物にふんした生徒はテキストを根拠にして自分の
考えや意見を述べます。そして反論があれば批判に答える。
こうしてディベートの訓練にもなるわけです。
このように本を材料にしてゲームや遊びをすると、子ども
たちはたいへん盛り上がります。そうやって次第に本の世界
へ近付けていくのがこのメソッドの目的です。モンセラッ
ト・サルトは90通り近くもこうしたゲームを考案して、スペ
イン語圏を中心に普及させています。マニュアルが明快なの
で、教師にとって取り組みやすい方法です。
「読んだことを基に自分の意見をいう」
授業へ転換するための具体的な対策
PISA型の読解力は、個人が自律的に社会に参画していく
ために必要不可欠な能力です。これからの子どもたちが身に
付けておくべき大切な能力の一つといえるでしょう。
では、こうした読解力を育てるには、現状の国語の授業を
どのように変えていけばよいのでしょうか。私は、概ね次の
ような改革が必要だと考えています。
(1)「教科書教材の精読」から「多様な文字資料の活用」へ
教科書に載っている「名作」だけを微に入り細に入り追究
するのではなく、本・雑誌・新聞・インターネットなどから
収集した多様な文字情報を教材として活用するべきです。
(2)「教師主導の一斉授業」から「子ども主導の協同学習」へ
一方的に先生が喋り、ときに質問を差し挟むというスタイ
ルを捨て去り、授業は子どもたちが自主的に意見をいうこと
によって初めて成り立つ、と考えなければなりません。
(3)「教師と子どもの一問一答」から「子ども同士の討論」へ
かといって、教師が次々に子どもを指名して答えさせる一
問一答式のスタイルもよくありません。子ども同士が討論し
て協同的に課題を解決する学習法をとるべきです。
(4)「憶測による心情や内容の理解」から
「推論による表現意図の解釈」へ
登場人物の心情や内容の理解に重点を置いた読解の授業か
ら、テキストに書かれていることを根拠にして「なぜそう書
いたのか」を推論して解釈する学習への転換が必要です。
(5)「教材の無批判な受容」から「教材の評価と批判」へ
教材を無批判に受け入れて感動させる授業ではなく、文章
表現を吟味し、具体的な根拠を挙げて、文章が効果的かどう
かを評価・批判する学習に変えなければなりません。
(6)「体験と感想を基にした表現」から「読解を根拠にした表現」へ
自分の体験や感想だけを基にした表現や意見発表から、テ
キストに書かれていることと自分の体験や考えを結びつけた
独自の意見発表をする学習に転換すべきです。
教科書に載っている『走れメロス』や『ごんぎつね』のよ
うな「名作」を教材にしても、(4)(5)(6)のようなクリティカ
ル・リーディングは可能です。例えば、「メロスはなぜこうい
う行動を取ったのか?」「ごんはこの時どんな気持ちだったの
だろう?」といった質問の代わりに、「この時メロスの取った
行動についてどう思う?」「この話がこのように終わることに
ついてどう思う?」といった質問を投げ掛ければよいのです。
子どもたちに自分の意見をいわせることが大切。恐らく授業
中には後者のような質問を投げ掛ける先生もいらっしゃるは
ずです。ところが、試験になると前者のような質問に戻って
しまう。答えがいくつも出る「意見」は評価できないと考え
るからでしょう。しかし、評価の基準は「テキストを根拠に
すること」ですから、意見そのものの正否を問う必要はない
のです。したがって、どんな意見であっても、テキストに基
づいた根拠とセットになっていれば、それは正解。だから評
価はできるのです。
批判的な思考力を養うには
子どもたちに本音で議論させる
日本の国語教育にいま最も求められているのは、テキスト
に基づき自分の意見を述べる授業を通じて批判的思考力を養
うことです。そのためには、ただひたすらテキストに寄り添8
Interview「生きる力」につながる P I S A 型の読解力
![Page 8: Interview...Interview 「生きる力」につながる PISA型の読解力 根拠を基に自分の意見を表現する授業への転換 有元秀文[国立教育政策研究所総括研究官]](https://reader034.fdocuments.in/reader034/viewer/2022043001/5f7b615fe208d7446d2db926/html5/thumbnails/8.jpg)
って、登場人物の心情の推移を追いかけるだけでは、うまく
いきません。こうした「鑑賞」を重視する従来型の立場から
すると、テキストに書かれていることを批判的な観点から読
み解く、などという発想はとんでもないものかも知れません。
教科書の「名作」には国語力のみならず道徳的な見地からも
学ばなければならないことが盛り込まれているのだ、と。
私も国語教育で道徳的なことを扱うのは、とてもよいこと
だと思っています。ただ間違ってはいけないのは、道徳は押
しつけて教えるものではない、ということ。道徳の押しつけ
に終始すると、「思いやりが大事」という授業が終わったとた
ん、休み時間にいじめが始まってしまったりする。押しつけ
では、道徳心は子どもたちの心にまったく染み込みません。
押しつけるのではなく、子どもたちに議論させればよいの
です。それこそが批判的思考力を養うことにつながります。
例えば、『泣いた赤鬼』という話があります。独りぼっちの
赤鬼は人間と友達になりたいが、なかなか人間から信用して
もらえない。そこで青鬼は赤鬼のために一計を案じる。「僕が
人間の村で大暴れをするから、君はそこへ出てきて僕を懲ら
しめろ。そうすれば君が優しい鬼だということが人間にも分
かるだろう」と。計画は成功し赤鬼は人間から慕われるが、
逆に青鬼は自ら村を去り、赤鬼は青鬼の友情に涙する。
これは尊い自己犠牲の話として扱われることが多いのです
が、そう思わない子どもだっているでしょう。「青鬼の取った
行動についてどう思いますか」と聞いてみればよいのです。
赤鬼のために青鬼は不幸になって、赤鬼は幸せになる。こん
な不幸な話はないのであって、「青鬼の取った行動はおかし
い」という意見だって十分あり得ます。これを素晴らしい話
として押しつけると本音は出てきません。本音で議論させれ
ば国語も道徳も区別なく、批判的な思考力を養えるのです。
とはいえ、こうした授業がなかなかやりにくいのは、評価
や批判を避けたがるタテ社会で事なかれ主義の、日本的な文
化風土に起因する問題でもあります。一朝一夕には実現しな
いでしょう。しかしいうまでもなく、グローバル化した社会
において、こうした批判的思考力の養成は不可欠です。
そのためには、教師の「子どもの話をよく聞く姿勢」が問
われます。子どもたちの積極的な発言を引き出すために、子
どもたちのどんな発言も温かく受け入れ、具体的に褒めてあ
げなければなりません。自由に自分の意見を言い合える教室
の雰囲気づくりが重要になるのです。 9
NO
.06
2
00
6
特集 読解力(reading literacy)、日本の教育の何が問われているのか
『「国際的な読解力」を育てるための「相互交流のコミュニケーション」の授業改革』有元秀文著/溪水社/2006年
『子どもが必ず本好きになる16の方法・実践アニマシオン』有元秀文著/合同出版/2006年
Reference