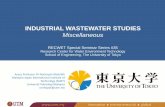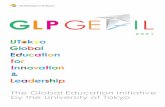東京学芸大学 環境報告書 2017...東京学芸大学 国立大学法人 re-inspect to...
Transcript of 東京学芸大学 環境報告書 2017...東京学芸大学 国立大学法人 re-inspect to...
-
東 京 学 芸 大 学
国立大学法人
re-inspect to re-build再 検 証 か ら 再 構 築 へ
環 境 報 告 書
2 0 1 7
〒184-8501東京都小金井市貫井北町 4-1-1Tel.042-329-7111www.u-gakugei.ac.jp
-
■ 目 次
Top Message 01環境配慮の取り組み 02環境改善企画部門の「これまで」と「これから」 03学芸の森推進部門の「これまで」と「これから」 04環境調査評価部門「これまで」と「これから」 05環境学習推進部門の「これまで」と「これから」 06環境創造地域連携部門の「これまで」と「これから」 07-08成美荘 09万葉池 10環境パフォーマンス 11-13サクラの「これまで」と「これから」 14-15忘れられた椿園の今とこれから 16機構長より 17
■ 編 集 方 針
本報告書は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」にもとづき、本学が取り組んでいる環境整備・保全に関する方針・活動を皆様にご理解いただくと共に、「学芸の森」及び自然を共に守り・育て・継承していくための資料・教材として多くの方々に活用していただけることを目指しています。
学芸の森環境機構
■ 参考としたガイドライン 環境省「環境報告ガイドライン(2012 年版)」
■ 報告書の対象範囲 小金井キャンパス、ならびにその他地区(各附属学校)
■ 報告書の対象期間・発行 対象期間 平成 28年 4月(2016年 4月) ~平成 29年 3月(2017年 3月) 発行 平成29年9月(次回:平成30年9月発行予定)
■ 環境報告書は東京学芸大学のホームページで公表しています。
http://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/01/
■ 環 境 憲 章
基本理念 「教育への情熱・知の創造」をモットーに「有為の教育者」の育成を目指す東京学芸大学は、地球環境問題が焦眉の課題となっていることを深く認識し、継続的な人類の発展に寄与するために、地球環境の保全と充実に向けた教育活動を積極的に展開する。 また、緑豊かな自然を保持する本学は、建学以来育んできた「学芸の森」をかけがえのない教育研究環境として守り発展させ、周辺地域の自然環境との調和に努めつつ、多彩な環境パートナーシップを構築する。
基本方針1 本学のあらゆる活動から生ずる環境負荷を認識し、環境汚染の防止、エネルギー使用量・廃棄物排出量の削減、資源リサイクル量の向上をはかり、園児・児童・生徒・学生・教職員などの心身の健康を図ると共に、環境への自覚を高める。
2 地球環境や地域環境を保全・改善するための研究活動及び環境教育・環境学習活動を推進し、公開講座等を通じて環境問題の啓発、普及に務め、循環型社会の担い手となる優れた人材の育成に努める。
3 大学及び附属学校・園の自然環境の保全・充実に努め、「学芸の森」の学術的・教育的価値を更に高めると共に、地域社会と連携し、園児・児童・生徒・学生・教職員・地域住民等の多様で主体的な環境活動を推進する。
4 「学芸の森環境機構」を中心とする環境マネジメントを構築し、武蔵野の風土と文化を生かした自然環境を形成し、学生も参加した定期的な環境監査等を実施する。
5 環境に関する法規、条例、協定及び学内規定を遵守する。
東 京 学 芸 大 学
環 境 報 告 書 2 0 1 7
東京学芸大学 環境報告書 2017 01
環境への配慮が謳われて久しいとはいえ、地球という環境では温暖化が徐々に進行し続けていることは広く報道されているところです。世界中の各地平均気温が増加傾向をたどっていることに加え、北極や南極の氷が溶けているということや極端な短時間集中豪雨に代表される異常気象、海流異変等地球環境の持続性への黄信号が赤信号になりかねない状況を前にして国際的な取り組みや条約発効の重要性が声高に叫ばれている今日、本学における多くの取り組みが着実に学生、教職員に根付き、常に環境への配慮を行動規範の最上位においての認識とその実践こそが「地球を救う」ことに繋がるのだと思います。 そういう意味でも、広義として環境教育はとても重要なことと考えます。机上の、授業における教室内での学びに限定されるものではありませんし、教科に限定されるものでもありません。学びのいろいろな場面に環境問題は顔を出します。いろいろな教科で、分野で環境問題を少し掘ってみるだけで受け手である児童や生徒、学生の中に何かが届くのではないかという思いを強く抱いております。 3.11の震災および原発の事故から6年が過ぎましたが、当時の節電・節水への意識は今もそのままかと言えば、自身も含め多くの方は否と答えざるを得ないのではないでしょうか。電力事情が好転した背後には火力発電にともなうCO2排出量増加等見えにくいものがあります。ソーラーパネルによる自家発電も一時ほどの注目は集めておりません。温かい便座を否定するものではありません。暑さに対して我慢をもって抗すべし等とは微塵も考えませんが、雨水の利用のことを考えたり、小金井地区の地下水利用への影響を考えたり、建設的な視野から将来の環境を考える取り組みが出てきてもいいように思います。 2020年のオリンピック・パラリンピック成功に向けての取り組みの中に環境志向の取り組みが芽生えることを願っています。
国立大学法人 東京学芸大学 学長
TOP MESSAGE
-
0% 50% 100%%
%0%
!100%50%
!0% 100%50%
60
82
98
予測電力(kw)目標電力 =電力使用率(%)
80%未満
80%~98%未満
98%以上
■電力使用率にもとづく色表示について ■電力使用率の算出方法
電力使用率は、計測器からの予測電力値を目標電力で割ったもので算出しています。
電力使用率に応じて表示(色表示)を変えています。
小金井地区:現在の電力使用率
電力使用率の表示について
80%以上になると表示されます
98%以上になると事務室、研究室等の空調・照明停止の要請をする場合があります。
%
本部棟3階電話交換機室
エネルギーデータ集計パソコン
画像データFTP転送 予測電力値
エネルギー計測器 東京電力メーターより
パルス信号取り出し
受変電室内
データ→グラフ→画像に自動変換
モニターシステム概要
エネルギー計測器 東京電力メーターよりパルス信号取り出し
re-inspect to re-build 201702
2015年の夏より、教職員・学生がパソコンを利用する場合最初に表示されるポータルサイト「学芸ポータル」に小金井地区の電力使用状況をリアルタイムで表記する「電力使用率の見える化」の取り組みを行っています。受変電室内に計測器を設け、電力使用量データをパソコンで集計し、30分ごとの契約電力使用量との割合を表示する仕組みです。また、電力使用率に合わせでグラフの表示色を変えることで、現在の電力使用状況がさらにわかりやすく視覚化され、許容量オーバーへの危機感を持ちやすくなっています。 この取り組みを行ってから 98%以上になると自主的にエアコンの温度を上げ下げしたり、いらない電気を消したりする人が増え、個人の省エネ意識を高める効果が出ています。
教育系大学に属する我々は、一人一人に気付かせる環境改善の取り組みを行っています。財務施設部施設課
夏と冬に 1度ずつ、小金井地区とその他附属学校地区で、地球温暖化対策推進委員及び大学職員による「省エネパトロール」を行っています。居室等における適切なエネルギー管理実施の状況を把握するともに、省エネの観点から適正使用についてアドバイスを行うことにより更なる省エネ推進を図ることが目的です。対象居室は事務室や研究室等で、調査は抜き打ちで行われます。 調査員は「省エネパトロール点検表」(図 1)を使い、照明の消灯状況・空調の設定温度の確認・コンセント使用機器類のチェック等をし、アドバイスを行います。また、調査後は点検結果を集計し公表することで、更なる省エネ意識を高めることに役立てています。(図 2)
環境配慮の取り組み
■ 「 電 力 使 用 率 の 見 え る 化 」
■ 「 省 エ ネ パ ト ロ ー ル 」
[ポータルトップ画面の電力使用率の表示について]
電力使用率の表示について
学芸ポータルトップページ
モニターシステム概要
図 1
図 2
省エネパトロール点検表○:良好 ×:指摘あり -:該当なし
判定 コメント設定温度( )は空調未使用
室温 判定 コメント 判定 コメント 判定 コメント
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
本部棟(4F)
22
23
24
25
室名
照明関係 空調関係 コンセント使用機器類
№
図書館
小金井地区
調査日
部分的な消灯・間引き(支障の無い範囲)
設定温度・測定温度(冬季20℃)(概ね20℃未満の場合及び空調を使用していない場合「○」)
空調負荷の増加防止:(空調使用時)扉・窓は閉めてあるか
足元暖房等の私物の電化製品の使用地
区
本部棟(1F)
本部棟(2F)
本部棟(3F)
建物別
冬季の省エネパトロールの点検結果について
Ⅰ.省エネパトロールの目的
居室等における適切なエネルギー管理実施の状況を把握するとともに、省エネの観点から適正使
用についてアドバイスを行うことにより更なる省エネ推進を図ることを目的とする。
Ⅱ.点検実施期間・点検者
・平成29年2月1日(水)~平成29年3月14日(火)
点検者 (地球温暖化対策推進員及び施設課職員)
Ⅲ.調査対象
対象居室:116室(事務室や研究室等)を抜き打ちで調査
(参考:夏季のパトロールは、小金井地区のみ 80室)
Ⅳ.点検について
1.照明関係
(1)点検内容
業務に支障の無い範囲で照明の間引き・部分的な消灯を実施しているか確認を行った。
(2)点検結果の判定
照明の間引き・部分的な消灯を実施していたのは72室(62.1%)であった。部屋のレイ
アウトや用途上、間引きや部分的な消灯ができない38室(32.8%)は「該当なし」と判定
した。指摘のある居室は6室(5.1%)、非常に良好な結果となった。
2.空調関係
(1)設定温度・測定温度
①点検内容
・設定温度
各室の空調用コントローラーの設定温度を調査した。
・測定温度
温度計測器を用いて、各居室内で2ヶ所計測を行った。測定場所はエアコンの風が直接当
たらず、作業環境に近い机の上などで行った。
・判定
コントローラーの設定温度が20℃(冬季)に対し、-1℃以内または20℃より高く設
定している場合は「良好」と判定。
設定温度によらず、備え付けの温度計で室温管理している居室については、その温度計の
数値で判定(20℃±1℃で「良好」)し、空調を控えている場合は、省エネ上の観点から
「良好」と判定した。
726
38
0 10 20 30 40 50 60 70 80
○:良 好
×:指摘あり
―:該当なし
東京学芸大学 環境報告書 2017 03
環境改善企画部門では、2016年度には 2回にわたり、学内の環境で危険のありそうな場所を部門員や施設課担当者等の関係者たち複数名で見て回り、ハザードマップを作成しました。1回目に危険性が指摘された場所は、2回目には大幅に改善されていました。2017年度にも、同様に 2回にわたりハザードマップの作成を行うとともに、万葉池に堆積した汚泥のかい掘りなども、スキルを持った環境教育の学生たちの協力を得て、行う予定です。
環境改善企画部門長 杉森 伸吉教育心理学講座 教授
毎年、定例化してきた学内のハザードマップづくりは、軌道にのり、2年目を迎えました。報告後には施設課や総務課などの方々の努力でどんどん良い方向に改善が進むのが楽しみで、今年もその成果と必ず毎年出てくる課題をも探しに、夏の時間を利用して、ハザードマップ探訪を行いました。
今年は、東側の東門から、先ず、植物以外の問題点とされていたハンドボールコート脇の伐採した枝の放置の状態をチェックしてみました。2月にはかなり減っていた枝が、うず高く積まれ、時期によって、こんなにも増えてしまうのか、とこの場所を一時保管場所とする習慣は変わらないのがわかります。どれだけ廃棄されるのかを注意深く見いていく必要がありそうです。次はグラウンドの前の人工芝ロールの放置ですが、これも他に移動で
環境改善企画部門の「これまで」と「これから」
■ ハ ザ ー ド マ ッ プ 探 訪
きる場所もなく、かといって今すぐ利用する計画も進まないのか、かなりのボリュームで見慣れた風景になってしまっているという感じです。備品の放置は幾分片付けてきれいに並べられている程度には改善されていました。
植栽については、園芸剪定講習の効果があがった東門からのケヤキ通りの両サイドやケヤキ広場の西側の自然科学 1号館の東側花壇は、きれいなまま管理されていたようです。 特にきれいに植栽が刈られていたのは、飯島記念会館の北側の一角がかなり整備され、鬱蒼とした笹はキレイに刈り取られていました。今後の課題は、万葉池の周辺などでしょう。
機構員 高坂 憲二郎
グラウンド前 飯島同窓会館
ハンドボールコート脇
-
re-inspect to re-build 201704
本部門では、学生、教職員、そして地元住民の皆さんの大学内の植物への知識、関心を深め、東京学芸大学が有する豊かな自然、すなわち「学芸の森」を維持し、さらには発展させることを目指した活動を行っています。2015年から「学芸の森講習会」と銘打った学生、教職員、地元住民を対象とした参加型の講習会を年 4回のペースで行い、主に正門前サクラ並木の整備や花壇への植栽などを行ってきました。本年度から活動範囲をプレイパークにも広げ、すでに 2回の講習会を行っています。また、昨年からは 4月初旬に主に地元住民を対象とした学内のサクラを活用した部門主催の公開講座「お花見学入門」も実施しています。 今後もこうした講習会、公開講座を通じて「学芸の森」を推進していきたいと考えています。
本年度の活動報告〈公開講座「お花見学入門」〉 2017年 4月 2日(土)9:00~ 12:00に学芸の森推進部門員が講師となり、地域の方を対象に、学内のサクラを用いて、花の観察と種の同定の方法について説明する公開講座を行いました。なお、部門員(岩元、高坂)に加えて樹木医の新井孝二朗氏を講師として招へいしました。 地元小金井市から 10名の参加者があり、アンケート結果も大変好評でした。また、アンケートとは別に公開講座の内容が良かったとの参加者からのメールもありました。
〈第1回学芸の森講習会「正門前花壇の整備および正門前サクラ並木の状況について」〉
2017年 6月 21日(水)14:30~ 16:00に外部講師として樹木医の新井孝二朗氏を招へいし、本年度第 1回の学芸の森推進部門講習会を実施しました。参加者は、機構員 2名(岩元、高坂)、学生 4名、地元住民 2名(公開講座に参加された方)の計 8名でした。 今回は、講師の新井氏の指導を受けながら、参加者が実際に正門横花壇の除草と植物の剪定、枯れた植栽の除去、および新しい植物(サフィニア、ペチュニア)の植え込み作業を行いました(写真 1)。サフィニア、ペチュニアは暑さに強く、また挿し芽で増やすことの出来る植物であることから、秋には再度植栽整備の講習会を行い、サフィニア、ペチュニア両植物を挿し芽にして参加者に配付することを予定しています。
学芸の森推進部門の「これまで」と「これから」
植栽終了後は、サクラ並木の病害虫対策をテーマにした新井氏による講義が行われ、正門前のサクラ並木が危機的な状況であることを解説してもらいました。また、ここ数年で植樹されたヤマザクラ(小金井ザクラ)については移植の必要があるものがあり、サクラの植え替えに適切な今年の 11 ー 12月に移植の講習会を行うことを決定しました。
〈第2回学芸の森講習会「こうさくのもり」〉
2017年 7月 12日(水)15時~ 16時 30分にNPO法人小金井こども遊パークとの連携事業として、大学構内の「いけとおがわプレーパーク」において第 2回講習会「こうさくのもり」を開催しました。本講習会では、学生が主体的に企画・運営を担い、「学芸の森」の豊かな自然環境を活用した遊び(プレーパークの旗づくり、垂れ幕づくり、シャボン玉遊び等)を通して、子どもと学生が交流を行いました。 当日の参加者数は約 85名(子ども:約 40名、保護者:約 20名、学生:21名、教員:2名、NPO法人スタッフ:2名)で、参加した子どもたちの弾けるような笑顔が印象的でした(写真 2-4)。
学芸の森推進部門長 岩元 明敏広域自然科学講座 准教授
学芸の森推進部門員 柴田 彩千子生活科学講座 准教授
写真 4:第 2 回講習会の様子 垂れ幕づくりの様子です。布に泥水で手形や足型を押したり、枝で絵を描いたり、葉っぱのステンシルなどを押したりなどしました。
写真 2:第 2 回講習会の様子 猛暑のなか、打ち水をして涼んでからイベントをスタートしました。
写真 3 :第 2 回講習会の様子 シャボン玉液をつくりの様子です。モールやハンガー、ストロー等を組み合わせてシャボン玉遊びを行いました。
写真 1:第1回講習会の様子 講師と参加者が協力して、正門横花壇の除草と新しい植物の植え込みをしています。
東京学芸大学 環境報告書 2017 05
現在の環境機構においては、環境調査評価部門は「環境報告書」づくりを担う部門として位置づいております。 これまでの企画内容は以下の通りとなります。
■ 2007;テーマなし/学芸の森プロジェクト(1:構内各所において、四季折々に多様な植物の多様な状態が見られる自然環境の設備 2:植栽のテーマゾーン設定と設備 3:水辺環境の整備 4:自然環境の教育的利用)/「多摩川エコモーション」
■ 2008;テーマなし/学芸の森プロジェクト/「多摩川エコモーション」
■ 2009;学芸の森から始まる「いのち」のつながり/学芸の森プロジェクト(生命の動きの美しさを見守る)/多摩川エコモーション/多彩な環境活動
■ 2010;100年先の笑顔のために。“学芸の森 ”から、未来を育む。/学芸の森プロジェクト(自然に学び、自由な発想を育む)/ USRの多様性(豊かな森で、一人ひとりの創造性を育む・自然の中に入り、これからの環境を考える)/地域へ、世界へ拡がる環境活動
■ 2011;ここから始まる。次代へつながる。いのちを育む、学芸の森。/学芸の森プロジェクト(自然から学び、創造力を育む)/多彩な USR(環境を築き、次代につなぐ)/社会へ拡がる環境活動(連携から生まれる環境活動)
■ 2012;もう、はじまっているよ。学芸の森で生まれた「次へのつながり」。/学芸の森プロジェクト(多様性を守り、育んでいく)/多彩な USR(“つながり”から発展する環境活動・自然から学び、創造力を育てる)
■ 2013;“遊び ”から学ぶ。“学び ”で遊ぶ。発想がひろがる学芸の森。/学芸の森での活動(“遊び ”と “学び ”で多彩な発想を育む)/多彩な USR(地域とともに発展する環境活動)
■ 2014;学芸の森はワンダーランド/出口学長と行く!学芸大探検隊/木を知ろう!「樹木が教える自然の見方」/タイムスリップ!「ウッドデッキのある風景」
■ 2015;“コ・クリエーション ”学芸の森からはじめよう!/学芸の森環境機構座談会
■ 2016;“re-creation” /振り返ろう、学芸の森環境機構の活動
環境調査評価部門「これまで」と「これから」
そして今号は「再検証から再構築へ」となりました。 以上を受けまして、「これから」として、環境調査評価部門としましてはその名の通り、環境調査を手掛け、それを評価しながら、環境報告書に反映してゆくこととなります。 一般論としまして、「環境負荷の認識・測定」の視点から本学の場合の「課題となる影響の把握」を行い、その中から「重要な課題の特定」を行うことによって本学の「方針・経営目標の設定」に基づき、「事業戦略・計画の立案」をし、「PDCAサイクルにて対応」を進めることとなりましょう。 本学の場合、一般企業とは異なるもののさまざまな環境負荷を生じさせる点では同様であり、その削減に向けた努力を推し進め、環境配慮経営をしなければならないことは言うまでもありません。その重要事項は以下の 5点が挙げられます。
(1)経営責任者のリーダーシップ (2)環境と経営の戦略的統合 (3)ステークホルダーへの対応 (4)バリューチェーンマネジメントとトレードオフ回避 (5)持続可能な資源・エネルギー利用 ※出典:環境報告ガイドライン(2012年版)
表紙裏面の本学の環境憲章を要約しましょう。 1:環境負荷低減と環境意識の向上 2:循環型社会の担い手となる人材の育成 3:学内の自然環境保全・充実 4:環境マネジメント体制の構築・運用 5:環境保護に関わる法令等の遵守
以上を踏まえまして、本部門の位置づけが他の 4部門の評価をも含む包含的なものであることから、これまでの並列的な 5部門構造から脱し、4+ 1部門的な構造へと「再構築」される必要があることが分かります。 本機構員が 2年任期制の半減上陸(各学系からの 2名体制で 2名の任期が 1年ずつずれる仕組み)の見直しも「再構築」の対象となることを前提に部門活動を展開してゆきたいと考えます。
学芸の森環境機構長 渡辺 雅之健康・スポーツ科学講座 教授
-
re-inspect to re-build 201706
環境学習推進部門と銘打って組織に位置付けられたのは 2010年度からとなります。そこでは、「環境+教育」ワーキンググループと環境科カリキュラム研究会が共同で多彩な方々をお招きして研修会を開催し、「環境+教育」戦略について検討しています。そして、2012年には、他の部門と連携しながら、教職員や学生の環境意識を高めるための講演会や研修会を企画、実施し、その後もずっと引き継がれております。環境学習はとても広範囲で奥が深い学びです。どこかに焦点を当てたとしても優に 1年ぐらいはかかるトピックであり、また、テーマとなりましょう。 さて、「これから」のこととなりますと、学芸の森環境機構が 5部門体制を取り、各部門ごとの活動の色合いを鮮明する段階となってきていますので、環境学習プログラムを構築していかねばなりません。 1)キャンパスクリーンデーへの協働;2010年から始まりました全学挙げてのクリーンデーに一昨年度から除草も加えられました。そのための道具を揃え、使い方を指導し、多くの手でキャンパスを居心地良く、美しくする活動となっています。大学主導の行事ですが、残念ながら学生諸君の参加が少なく、加えて教員の参加も限られた一部の者になっている現状の改善が急務です。
環境学習推進部門の「これまで」と「これから」
2)環境学習としてどこに焦点化してゆくか;環境学習としていきなり大きなアドバルーンを上げる講演会ではなく、まずテーマ設定をして、その学習の道筋を見据えた上での講演会なり、研修会を行います。いわば環境学習のための準備を始めるという意味となります。テーマということでは「自然農法」実践者との交流から水や雑草等広い学びを通じて環境学習を展開することを案として持っています。 3)グリーンアドベンチャー活用方法;学内の要所要所にはグリーンアドベンチャーなる標識が自然と目に入ります。パネルに書かれたヒントをたよりにその樹木を目の前にして、樹木名を当てる仕掛けです。これの今後の活用方法を探ります。 4)セミナー企画;本学の学生にとって学芸の森は「教育の森」として極めて優れた価値を有しています。が、その宝の山に気付かかない、あるいは気付けないのか、交流会などを通してふれ合える機会をもってはどうか、などと考えています。その第一歩に S棟南駐輪場内の草地の花壇化を考えております。こんなセミナーを通じて何を植えるか、その後のお世話はどうするかなど身近なところからオーナーシップを醸成してゆきたいものです。
学芸の森環境機構長 渡辺 雅之健康・スポーツ科学講座 教授
キャンパスクリーンデイ
東京学芸大学 環境報告書 2017 07
昨年度までの大きな課題であった「学芸の森ボランティア」組織の再構築について、部門構成員に加えて、大学キャンパス内の特に若草研究室、農園やプレイパークにて定期的な活動を実施しており、かつ将来的に学芸の森ボランティア登録候補有力団体(杜 En、NPO小金井遊パーク、NPOこがねい市民発電、ハケのぼちぼちハウス)の方々と急ピッチで協議を重ね、学芸の森ボランディアの規約案や植栽管理用具の共同利用について合意形成をいたしました。まずは学芸の森環境機構構成員の方々をはじめ、一人でも多くの方々にボランティア登
環境創造地域連携部門の「これまで」と「これから」
録をしていただき、地域の人々と大学との連携・協働体制を強化しつつ、環境保全を考え学芸の森を豊かにしていきたいと考えています。 また、今は日常的には使用されていない若草研究室の有効な使い方についてもいろいろと検討しています。今後は、学芸の森ボランティア会員が有機的に活用することができるスペースとし、各々の活動がより活発かつ効率的なものとなるとともに、相互のスムーズな連携ができるためのルールづくりも整備していきたいと考えています。
活動開始は早春、春蒔きの種蒔きや柿、枇杷、小梅や周辺の桜等の傷んだ枝を剪定を します。 5月になると若草研究室の周辺は草の成長が活発化。通路等の草は自然植生との共存を考慮し、抜いて除草せず丈抑えで対応。この丈抑えは毎月定例の作物等の手入れと併せ、草の力が衰える初冬まで行いました。
年の〆はゲストも交えての餅つき大会。田んぼで作った餅米 12kgを庭で収穫した大豆のきな粉や里芋の芋煮、他収穫作物と楽しながら自然農法を実施しました。
任意登録機構員 小澤 要
環境創造地域連携部門長 森山 進一郎芸術・スポーツ科学講座 准教授
■ 杜 E n の 食 べ ら れ る 庭 造 り / 若 草 ガ ー デ ン
2016/12/25 餅つき大会
庭からの贈り物 排水改善
若草ガーデンランチ
ヤーコン収穫
丸葉藍の種まき
-
re-inspect to re-build 201708
第 1章 総則
第 1条 本会は、学芸の森ボランティアの会(以下、「本会」という)と称す。第 2条 本会は、環境創造地域連携部門におき、本会に事務局をおく。
第 2章 目的および事業
第 3条 本会の目的は、東京学芸大学の学芸の森環境機構(以下、「機構」という)の策定する学内の植栽に関する教育的利用や緑化推進、自然環境の整備・保全に関する方針・計画の遂行に必要な支援を長期かつ継続的に行うこととする。また、これらの活動を通して、機構が行う地域連携による自然環境保全、教育を支援し、環境問題解決への取り組みを推進していく。第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。一 卒業生や教職員OB・教職員・学生・地域住民の植栽の教育利用と緑化推進、環境整備保全のための作業活動二 教職員や学生が企画し、実行する環境改善諸活動への支援三 地球温暖化等環境悪化ならびにその対策等に関する学習、および環境改善に関する計画の策定と実施四 その他目的達成に必要な諸活動2 前項は第 3章で規定するところの「会員」以外の卒業生や教職員OB・教職員・学生・地域住民が事業活動に参加することを妨げるものではない。
第 3章 会員
第 5条 本会の会員は次の 4種とする。一 学校個人会員 東京学芸大学、およびその附属学校の教職員OB・卒業生・その家族・教職員で、本会の目的に賛同して入会した者二 学校団体会員 東京学芸大学、およびその附属学校の同窓会、卒業生で組織しているクラス会、同期生会、ゼミおよび部活動の会、地方支部等の団体で、本会の目的に賛同して入会した団体三 地域支援会員 卒業生以外で、入会時に東京学芸大学および各附属地区の近隣に居住し、本会の目的に賛同して入会した者四 学生会員 東京学芸大学学部、大学院研究科等に在籍している者で、本会の目的に賛同して入会した者2 学生会員は、卒業(修了)後、個人会員へ移行することができる。第 6条 会員は、登録時に必要事項を機構に提出し、登録に伴い機構より発行されるボランティア会員証を特別な事由がない限り、ボランティア活動を行う際には携帯しなければならない。登録期間は、1年以内とし、希望する会員は毎年 4月、機構に登録の更新を書式(更新届)により提出しなければならない。登録更新期限より半年以上、更新届の提出がない場合は、会員登録を休会扱いとする。第 7条 退会を希望する会員は予め事務局に退会届を提出するとともに、ボランティア会員証を返却しなければならない。
第 4章 役員および事務局
第 8条 本会に、以下の役員および事務局長と事務員をおく。事務局は事務局長と事務員により構成され、事務局長
の指示により、本会の日常業務などボランティア活動運営、および会員の管理を担う。一 役員 機構の環境創造地域連携部門会議において担当機構員、および任意機構員、本会会員から選出する(10名以内)。二 会長 役員より機構において選出される三 副会長 本会の会員より会長の任命によって選出される四 事務局長 機構において選出される五 事務員 事務局長が本会会員より若干名(5名以内)選出し、任命する第 9条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合、会長の職務を代行する。3 事務局長は、会長、副会長の指示に従い、会務を処理する。第 10条 事務局長の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。2 事務局長に欠員を生じた場合、補欠の事務局長の任期は、前任者の残任期間とする。3 事務局長は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行う。第 11条 本会に顧問若干名をおくことができる。
第 5章 会議
第 12条 会議は、機構環境創造地域連携部門担当機構員、任意機構員、事務局長および役員による幹事会とし、次の事項を議決する。一 ボランティア活動計画の決定および事務局よりの活動報告の承認二 ボランティア活動予算の決定および収支決算の承認三 その他本会の運営に関する重要な事項第 13条 幹事会は、必要に応じて会長が招集して開催する。第 14条 会議の議事は、この規約に別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。第 15条 役員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。2 前項の代理人は役員でなければならない。
第 6章 会計
第 16条 本会の活動経費は、主に機構の経費を充てる。それ以外に活動の必要に応じて、会員やボランティア活動参加者などから参加費や経費等を徴収したり、寄付を受けることができ、その費用も経費に充てることができる。第 17条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。
第 7章 規約の改正
第 18条 この規約を改正しようとするときは、機構会議において、その出席者の過半数の同意を得なければならない。
付 則
第 1条 この規約施行についての細則は、会議の議を経て別に定める。第 2条 この規約は平成 29年○月○日から実施する。
■ 学 芸 の 森 ボ ラ ン テ ィ ア の 会 規 約 試 案
東京学芸大学 環境報告書 2017 09
東京学芸大学では、東久留米にある成美荘の建物周辺の雑木林(本学所有地、以下「成美地区緑地帯」という。)の整備を地元の「東久留米自然ふれあいボランティア」という 40名程度の市民ボランティアに依頼して進めています。 本年度は、2月から 8月まで草刈りや竹、笹の伐採、遊歩道の為の垣根づくりなどを進めてきました。 このボランティア団体は、東久留米市内にある東京都指定の緑地保全地域、野火止用水歴史環境保全地域、森
※附属学校在学者数()内の数字は海外帰国児童・生徒
小金井地区 敷地面積 306,894㎡東京学芸大学在学者数 教育学部 4771名 大学院 831名 特別専攻科 31名 附属幼稚園小金井園舎 在学者数 150名附属小金井小学校 在学者数 629名附属小金井中学校 在学者数 478名
附属世田谷小学校 敷地面積 28,393㎡ 在学者数 623名附属世田谷中学校 敷地面積 20,307㎡ 在学者数 478名附属高等学校 敷地面積 53,239㎡ 在学者数 1011(41)名
敷地面積 60,719㎡附属大泉小学校 在学者数 570(38)名 附属国際中等教育学校 在学者数 720(305)名大泉寮
敷地面積 18,728㎡附属幼稚園竹早園舎 在学者数 60名附属竹早小学校 在学者数 425名附属竹早中学校 在学者数 478名
敷地面積 24,230㎡附属特別支援学校 在学者数 72名東久留米国際学生宿舎
成美荘周辺雑木林の整備に地元東久留米のボランティアが活躍
の広場(前沢、南町、柳窪ケヤキ)、南沢樹林地、向山樹林地、竹林公園などの自然環境を保全する活動などをされている団体です。今回は、こうした市民連携の自然環境保全活動を広く知っていただくために、今年度の活動風景を同団体の代表の豊福氏と広報担当の下村氏にお願いし、実際の 8月の活動模様の写真を提供いただきました。 東久留米の市民との連携による成美地区緑地帯の環境整備は、順調に進んでおり、さらなるこの地域の活用が期待されています。
成 美 荘機構員 高坂 憲二郎
遊歩道の垣根づくりをするボランティア 竹垣づくりに使う竹を採集 遊歩道の雑草取りは定期的に
学 長
学芸の森環境機構
環境調査評価部門
環境改善企画部門
学芸の森推進部門
環境学習推進部門
環境創造地域連携部門
■ 東 京 学 芸 大 学 の 概 要 (H 28.5.1現在) ■ 学芸の森環境機構 組織図
-
re-inspect to re-build 201710
武蔵国分寺に足を延ばすとそこには万葉植物園がある。一つ一つの植物には万葉歌の札が掛かっている。門外漢にはその札札が垂れさがる様で食傷気味でもある。万葉人になって出直せと言われるのか。だが、知った一歌でいい、一つ知れば見る目ががらりと変わる。風情が急に身体にそよぎ始める。今という時空間から万葉集が編まれた奈良時代へと一気に飛び越えるのだ。想像の世界で家持になれる空間に酔える。 こういう教養が不可欠であろう。目先の理工優先では人は育たない。こんな空間を再生すべきではないか。ただし、札札に囲まれるのはいかがなものか。ガイド資料を手にすればよいのではないだろうか。
(環境子)
万 葉 池
万葉池知ってますか、の問いに答えられる学生はかなり少ないと思われます。教職員も入れ替わりに伴い、知る人は減るばかりではないでしょうか。知っている人でも最近はほとんど足を踏み入れてはいないようです。思わず足を踏み入れると書きましたが、実際に今行ってみますとそんな感じがよく分かるかと思います。万葉池周辺の植物も時の経過とともに成長します。上にも、下にも。そして、枯死することも。昔の姿を見ますと確実に手が入っていることが分かります。高木もそれほど高くなく、付ける枝もほどほど、なのに今は高木が大きく、高くなって、張った枝とその葉が空を塞ぐぐらいとなっています。これでは陽光は下までは届きません。鬱蒼とした茂みになった感がどうしても人を入りにくくさせているのかもしれません。夏場の蚊の襲撃には降参です。 池の水にも注目しましょう。かつては「池」でした。まぎれもなく池なのです。今は落ち葉や泥が堆
積し、ヘドロ化したような、過剰な栄養状態の汚泥が池を支配しています。泡もぶくぶく、と。ガスの発生でしょうか。 さてこれからの万葉池と周辺の一帯をどのように進めていきましょうか。万葉池周辺の植栽をまず考えるべきなのでしょうか。高木への対処と万葉池というそもそもの命名に由来する万葉の植物群の復活、そして、池の再生も必須ですよね。どれも短兵急にはいきません。今後の方向性を定め、対策を考えましょう。 万葉池創設者の田代良一氏は本学の造園計画の主たる方で、1971年ごろに万葉池はその名にふさわしい場となったようです。教員(本学および附属小金井中)から施設課専門職員に転じてまで「万葉池」完成に情熱を燃やされたことを知りますと益々今のままでは苦々しい思いを抱くのは一人ではないことでしょう。
「'84 東京学芸大学卒業アルバム」(昭和 59年 3月発行)より
学芸の森環境機構長 渡辺 雅之健康・スポーツ科学講座 教授
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
188,260
372,427
170,730
321,072
172,077
375,179
163,470
333,592
145,506
306,363 335,389
181,880
その他
28,692
53,491
16,768
27,262
43,75041,576
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
4,1504,200
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
3,300
2,630
1,418
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1,944
6,088
2,015
6,471
2,022
6,180
2,044
6,353
2,058
6,096 6,281
2,118
その他
11東京学芸大学 環境報告書 2017
電気・ガス・水道などの地球環境に影響する使用量および支出額のデータを比較表にして、学内へ定期的に通知し、その増減状況の共通理解を得ることにより、省エネの意識向上を図っています。以下に環境パフォーマンスの取り組みデータを示します。
環 境 パ フ ォ ー マ ン ス
CO₂ 排出量の削減対策として、重油ボイラから高効率のガス・電気式の空調設備へと切り換えを進めています。重油焚暖房ボイラを廃止した結果、重油の使用量がなくなりました。
機器の更新にあわせ高効率の機器の導入を推進しています。ボイラ廃止のため増えています。
本学では、冷暖房期間の電力ピークカットのため空調設備の一部にガスを利用した空調設備を導入しています。空調設備の改修に合せ老朽化した空調設備を高効率の空調設備に更新していますがボイラ廃止のため増えています。
※小金井地区とする。(芸術・スポーツ科学系研究棟30kW、) 総合教育科学系研究棟 3 号館 5kW、附属小金井中学校 20kW)※ 2012 年 6 月以降、芸スポ 4 号館停止(故障による) → 2014 年 11 月修理完了※ 2013 年 6 月以降、総合教育科学系研究棟 3 号館停止(故障による) → 2014 年 3 月修理完了
重 油
電 気
総エネルギー投入量(ℓ)
総エネルギー投入量(MWh)
総エネルギー投入量(Nm3)
(kwh /年)
ガ ス
太陽光発電量
■ 事 業 活 動 に 関 わ る エ ネ ル ギ ー ・ 資 源 の 全 体 量
-
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1,156
3,124
1,229
3,390
1,195
3,320
1,185
3,255
1,378
3,742 3,877
1,487
その他
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
48,630
74,684
40,200
78,393
45,577
78,067
43,860
73,306
48,855
59,560 60,778
43,593
その他
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
11,962,000
9,242,000
11,487,500
6,189,0008,934,500
8,250,750 9,513,000
8,681,500
10,734,000
7,994,500
11,074,500
8,101,000
その他
re-inspect to re-build 201712
本学の小金井地区では井戸水を使用しています。トイレ等の改修にあわせ、節水型トイレや自動水栓を導入し節水を図っています。
使用量の節約を図るため、下記の項目に取り組んでいます。❶ 両面利用の徹底❷ IT 活用の推進❸ 紙媒体から Web サイトへの利用の推進
電力会社が変わり係数が増えたことにより、排出量が増えました。
水
水使用料
紙
水資源投入量(㎥)
総物質投入量(枚) 温室効果ガス(t /二酸化炭素換算)CO2
環 境 パ フ ォ ー マ ン ス
INPUT電 気 8,399,000kWhガ ス 517,269N㎥重 油 0ℓ 水 104,371㎥紙など資源 19,175,500 枚
OUTPUT温室ガス
(CO2 換算) 5,364t
一般廃棄 393,664kg排 水 104,371㎥
環境保全効果
環境パフォーマンス指数 前年比
エネルギー使用量(GJ) 1.05
水資源使用料(㎥) 0.96
温室効果ガス排出量(t-CO2) 1.05
クロロホルム ジクロロメタン トルエン ノルマルーヘキサン
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
0.29
0.100.99
0.59
45.350.09.59
0.99
60.8482.42108.29
273.90 644.16 8.59
123.33
3.09
414.52
2.50
173.081.52
108.67
0.90
235.96
0.58
201.57
1.08
320.726.88
42.34
4.18
4.14
168.89
3.48
93.05
4.76
195.15258.18
173.00190.00128.9546.990.99
209.11
1.49
144.290
255.997
153.749
267.485 262.893
195.065
245.250
128.130
299.429
133.490130.771 129.118 125.190 127.580
161.889
133.035 133.613
234.655
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2011年※ 2012年※ 2013年※ 2014年※ 2015年※ 2016年※
廃棄物等総排出量 廃棄物最終処分量
その他
13東京学芸大学 環境報告書 2017
「東京学芸大学毒物および劇物取扱規定」に従い、教育・研究で使われる化学物質は適正な管理・使用を行っています。PRTR 法の報告対象となる使用量に達するものはありませんが、年間使用量の多い上位4つの化学物質についての数値を記載します。
ゴミの分別、ペーパーレス化の推進および返納物品活用バンクなどにより、廃棄物の減量に努めました。
※その他地区は集計していないためデータ無し。
化学物質
廃棄物
化学物質排出量・移動量(㎏)
廃棄物等総排出量・廃棄物最終処分量(㎏)
環 境 パ フ ォ ー マ ン ス
2016年度 PRTR 対象物質の集計結果について本学の対象取扱量は、右図⑥⑦の要件を満たさなかったため、排出量・移動量について報告は行いません、。しかし、PRTR方は環境に負荷をかける恐れのある化学物質の動向を把握することが目的であるため、今後も薬品庫などの管理に十分留意し、報告を行う基礎を確立する必要があります。本学の集計結果の内訳は HPに掲載してありますのでご確認ください。
http://www.u-gakugei.ac.jp/~yuugaisi
-
26
10m
5m
10m
5m
10m
5m
10m
5m
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 14 13 12 10 8 7 6 4 3 1 2 111215(伐採)
9(伐採)
5(伐採)
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 14 13 12 10 8 7 6 4 3 2 111215(伐採)
被圧(樹木に日照を奪われる状態)のため移植
(移植)9
(伐採)5移植
歩道側に偏芯しているので、緑地帯中央部(東側)へ移植(南北方向はそのまま)
被圧(樹木に日照を奪われる状態)されている状況であり、様子見
10m
5m
10m
5m
10m
5m
10m
5m
4849 47(伐採)
46 455 44 43 42 41 40 4 39 38 373 35 3328 32 31 302936(伐採)
34(伐採)
4849 46 45 44 43 42 41 40 4 39 38 37 35 3328 32 31 3029
被圧(樹木に日照を奪われる状態)のため移植
5(移植)
3(移植)
re-inspect to re-build 201714
サクラの「これまで」と「これから」東京学芸大学には、数多くのサクラが構内にあります。開花時期に開催する「お花見の会」は、教職員・学生にとどまらず地域の方々も訪れる恒例行事です。しかし、近年ではこのサクラに老化現状がおこりはじめています。安全で親しみのもてるサクラ並木を維持するにはどうすべきか―サクラの「これまで」と「これから」を考えます。
正門サクラ並木の「これまで」と「これから」正門サクラ並木は移植や伐採等を行い新たな並木道へ生まれ変わります。
西側
東側
現況立面図
現況立面図
計画立面図
計画立面図
東京学芸大学サクラ並木について 本学にある桜は、古いものは昭和 17年ごろに植えられており、樹齢にすると約 70年以上に達しています。当時は砂利道に植えられている状況でしたが、徐々に環境が整備されていき、現在はアスファルト舗装の並木道になっています。 種としてはヤマザクラやカスミザクラ、ソメイヨシノが多くありますが、オオシマザクラ等も植えられており、様々な種を鑑賞することが出来ます。
老朽化するサクラ 土壌や環境条件で異なりますが、ソメイヨシノの寿命は一般的に 60~ 70年程度といわれています。ヤマザクラなど年数は経ていても土壌改良や環境状況が良好であればソメイヨシノほどの老化現象は起きない種類もありますが、構内のサクラの樹齢を考えると弱ってきていてもおかしくありません。また、舗装路などの整備のために根の切断や盛土などが行われたため衰退傾向にあり自然倒木が起こることもあります。
現在のサクラの状態を把握する サクラの現在の状況を把握するため、樹木医の方に依頼し桜の状態を診断しています。調査結果はあまり芳しくなく、早急な保全計画が必要です。
サクラ並木を守るための取り組み 現在の環境を活かしつつ、教職員・学生・地域住民が親しみのもてる安全で快適な環境の実現に向け、東京学芸大学では以下の取り組みを計画しています。①倒木の危険性が高いサクラは伐採する② 根を残したまま新たなサクラを植えると生育に影響が出るため、できるだけ抜根する③景観を守るため、サクラを補植する④ 回復の見込みのあるサクラについては、樹勢回復措置(土壌改良等)をとり保全する
安全かつ美しいサクラ並木を守るため、東京学芸大学では今後も様々な対策を行い、適切に維持管理していきたいと考えています。
◀学芸大学正門 連雀通り▶
入学式シーズンには、数多くの桜が新入生を迎えます。
東京学芸大学 環境報告書 2017 15
散策してみよう
サ ク ラ 並木正門通り M A P
▲学芸大学正門
▼連雀通り
ヤマザクラ日本の桜の中で最も代表的な種類で、古くから詩や歌に詠まれ親しまれています。展葉と同時に、白色・淡紅白色の花がきます。
ソメイヨシノ明治初期に東京・染井(豊島区巣鴨付近)の植木屋が品種改良した園芸品種です。公園や街路樹などに最も植えられています。
オオシマザクラ伊豆諸島と伊豆半島南部に自生するサクラです。花は白く優雅で美しく咲きます。葉は桜餅を包む皮として利用されています。
カスミザクラ北海道から四国に分布し、見た目はヤマザクラに似ています。花は白色で、花や葉の部位が有毛である場合が多いです。見ることが難しい種です。
オオヤマザクラ本州中部以北に自生し、花や葉などは全体的にヤマザクラよりも大柄です。バラ色の花が咲きます。
小金井桜徳川吉宗の時代に吉野などからヤマザクラを取り寄せ、農民たちが植樹したサクラです。ヤマザクラ特有の気品と優美さがあります。
-
re-inspect to re-build 201716
忘れられた椿園の今とこれから
環境教育研究センターの東隣り、道路沿いの一角に寒くなると素敵な花の咲く場所があるのを知ったのは、数年前でした。手入れが行き届いたというよりは、下草を刈る程度で山肌に自然に生えた椿のように数十本の椿がひっそりと咲くこの場所は、なんともいえない魅力がありました。最初の疑問は、「一体誰がつくったのだろう」でした。様々な品種の椿は、当然、なんとなく植えた筈もなく、誰かが想いを込めて作ったとしか、思えませんでした。
その後、以前から機構員だった数名の先生に伺うと鷲山学長の時代に元ボタン園だった所に椿園を華道の大家であり、親交のあった安達瞳子さんの勧めで作ったものらしいことだけが解りました。 なるほど、初代安達瞳子さんが椿に思いを寄せられていたことは、「椿しらべ」の著書などでも知っていたことから、なんとなく合点がいったものの、どうやったら再生して、楽しめる場所にできるかと考えてはみたものの、
そのまま 1年ほどが過ぎてしまい、今年の夏に再度訪問すると見事な椿の果実が実っていました。 本来の椿の剪定は、花後の 3月から 4月頃に込み合った枝を剪定するか、新しい花芽がついて、果実も終わった 9月下旬から 11月頃に花芽を避けて、軽く剪定するのが基本です。 見てみるとかなり枝も込み合って絡み、剪定はされていないようです。当然、果実をとって、新しく栽培する人もいないのかもしれません。茶ドクガは発生していないようです。ここはなんとか機構会議や市民ボランティアと協力して、管理を進められないものかと思案中です。 夏後の果実の収穫と植え付け、秋の剪定をなんとか実施して、冬には、どんな品種があるのかを見てもらえるようにしたいものです。2013年あたりは、まったく鬱蒼と雑草も生い茂り、手付かずの状態のようでした。この一角に想いをかけた方々の気持ちを受けて、なんとか新たな「庭」ができたらと考えています。
枝もかなり込み合ってきた夏の椿
8月には既に花芽のついた枝も見られるように
機構員 高坂 憲二郎
お問い合わせ財務施設部 施設課T E L 042-329-7160FAX 042-329-7168MAIL [email protected]本報告書に関するご意見、ご感想、ご助言などをお待ちしております。これまで発行した環境報告書は東京学芸大学のウェブサイトからご覧いただけます。
www.u-gakugei.ac.jp/jounhou/01/
東京学芸大学 環境報告書 2017発 行:学芸の森環境機構編集・印刷:有限会社サンプロセス
環境配慮促進法(記載事項等に関する告示)準拠状況番号 記載必須項目 掲載ページ
1 事業活動に係る環境配慮の方針等 表 2
2 主要な事業内容、対象となる事業年度等 表 2・09
3 事業活動に係る環境配慮の計画 表 2・01・05・06
4 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等 09
5 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等 02・04・11・12・13
6 製品等に係る環境配慮の情報 ―
7 その他 ―
第三者意見「東京学芸大学環境報告書 2017」によせて
小金井市は、国分寺崖線(はけ)や野川、玉川上水などの緑や水、広大な小金井公園などの恵まれた自然環境の中で、文教住宅都市として発展を続けています。 また、雨水浸透施設等の設置率が世界的にも高水準にあるなど、市民と協働して良好で快適な環境が持続できる社会の実現を目指しています。 本「環境報告書」を拝読し、「電力使用率の見える化」「省エネパトロール」などの環境配慮の取組、学芸の森環境機構の各部門における様々な取組、成美荘におけるボランティアと協働しての周辺雑木林整備の取組、サクラ並木を守るための取組など、貴大学の幅広い環境保全活動に深い敬意と謝意を表します。さらに、本市では、2022年度に多数の生産緑地が制度上の営農期間満了となることに向けて、緑地保全のための取組も急務となっており、貴大学発の環境活動が、環境保全意識の高揚とともに、2020年のオリンピック・パラリンピック成功に向けての取組の中に環境志向の取組が芽生えることに寄与し、次世代の学生、また地域住民に受け継がれることを期待しております。
小金井市環境部長 柿﨑 健一
東京学芸大学 環境報告書 2017 17
機 構 長より 環境報告書は「学芸の森環境機構」の報告書ではないのである。大学としての環境報告書なのである。本環境報告書の作成に関わり、環境省の「環境報告ガイドライン(2012年版)」による「環境報告書」の意味と意義、そして義務を理解できたのである。関わる前は植物に関わることに(大学構内の樹木や花壇の草花に恋し、雑草との闘いというようなイメージ)偏していたと思う。その上で環境報告書の主体となる「学芸の森環境機構」が新しく「環境報告書」としてここにお届けする次第である。東京学芸大学の小金井キャンパスに留まらず、各附属(世田谷、大泉、竹早、東久留米)全体を視野に置きつつ、環境に関わる様々な諸要因を知る、何をすべきか考える、何が出来るかを考える、具体的な行動をする、その結果を評価する、等のことでその継続性こそが機構の評価規準となればと願う。
学芸の森環境機構 機構長/芸術・スポーツ科学系教授 渡辺 雅之