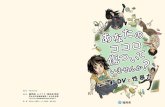BILINGUAL...はずなんですよ。大事なのは感動する こと。だから僕はお笑いも音楽も、興 味のないものでも、できるだけいいと ころを探すようにしています。
目次w3e.kanazawa-it.ac.jp/jinzai/mono/10monos.pdfTPSを実践してきた多くの人は「TPSは教えるものでも、教えられるものではない」と公然と言い放っているし、...
Transcript of 目次w3e.kanazawa-it.ac.jp/jinzai/mono/10monos.pdfTPSを実践してきた多くの人は「TPSは教えるものでも、教えられるものではない」と公然と言い放っているし、...

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
0
目次
1.講座の開始に当たって
1.1 講座の目的 ---------- 1
1.2 講座の構成 ---------- 2
1.3 本年度講座テーマ ---------- 4
1.4 テーマ解決のための考え方と予備知識 ---------- 5
1.5 講座日程計画 ---------- 13
1.6 成績評価、伝達事項 ---------- 14
1.7 後に ---------- 15
2.リードタイム講義
2.1 リードタイムの意味と重要性 ---------- 16
2.2 リードタイムと付加価値時間 ---------- 20
2.3 リードタイムとキャッシュフロー ----------- 24
2.4 リードタイム短縮のための方策の分類 ---------- 25
2.5 部署別リードタイム短縮の着眼 ----------- 26
3.製造現場における改善手法
3.1 ものと情報の流れ図 ---------- 43
3.2 製品ファミリーの分析 ---------- 61
3.3 ライン改善に良く使われる手法 ---------- 65
3.4 連合作業分析 ---------- 71
3.5 工程分析 ---------- 80
4.テーマ実習の進め方 ---------- 96
5.ケーススタディの進め方 ----------106
6.横展テーマの進め方 ----------118
7.自己点検文作成要領 ---------- 122

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
1
1.講座の開始に当たって
金沢工業大学情報経営学科
池田 寛
1.講座の目的
この講座(物つくり知識創造学)は、
単に知識としてのリードタイムを理解するのではなく、「JIT」や「見える化」のものの考え方を用いて、
生産現場やサプライチェーンの問題解決を行う実践力(即ち問題を発見して解決する力)をつけることを目的に
しています。
「JIT」や「見える化」を含むトヨタ生産方式はトヨタを中心としてマネジメントの実践哲学として推し進められてき
ましたが、いまや一企業の範囲にとどまらず、先にはリーン生産方式として紹介され、世界中のものづくりの
バイブルとして使用され、多くの企業での成功例がマスコミにより公表されています。
それは成長期の大量生産を前提とした、「作れば売れる時代」のものの考え方ではなく、
むしろ現代成熟期の買い手市場少量多種生産世界において、更にコアコンピタンスとして有効に機能する考え
方であることが理解されてきたことに他なりません。
ここ北陸では車ほどの集約型組み立て産業は少なく、受注生産型の個別生産品目を中心とした少量多種の
機械産業が中心で、JITに対する認識は無いとはいえないまでも、きわめて甘い世界と言えます。
今まであまり応用されていないこれら中小の個別生産を中心としたものづくりの世界に、この考え方を導入し、
改善を推進することによって、数の上で大半を占める中小企業の競争力を高めることが、日本の将来のものづく
りにとって極めて重要と考えられます。
しかしながら、TPSの研究者や、トヨタの強さを自分達の組織体に植え付けようとしてきた企業人達は、その内
容の理解とは裏腹に、その定着の悪さを嘆いています。
TPSを実践してきた多くの人は「TPSは教えるものでも、教えられるものではない」と公然と言い放っているし、
研究しにきた調査団には「あれはDNAだ」と言わせ、
その実践力を移植するのは不可能に近いことを暗に述べさせています。
JITはもともと難しい手法を含んでいるわけでもなく、物の流れについて、リードタイムと在庫の考え方を示して
おり、きわめて当たり前な、いわば平易な考え方で、巷には星の数ほどのTPSに関する本が発行されているし、
本やテキストを読めば、「なるほど、なるほど、分かった。」と簡単に思えるに違いありません。
しかし残念ながら、実践しないことには、実際には何もわかっていないし、TPSの考え方を用いて、
問題解決を行う能力がついたわけでもないのです。
この講座では、次ページに示すプロセスで、受講者の皆さんに
「TPSの知識を自らの体の中に創造し、現場を改善する実践力を、
自分はもとより、自らの職場に作り出していただきたい」

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
2
と考えています。
2.講座の構成
本講座の構成は下図のようになっています。大きく 4 つのプロセスに分かれています。
①講師による講義
近年の安定成長期における
リードタイムの
ⅰ)概念
ⅱ)領域と観点の変遷
ⅲ)重要性
ⅳ)個別受注型産業と型式量産型
産業の違い
ⅶ)リードタイム短縮の重要性
を少しお話しをし、
主に
ⅷ)リードタイム短縮の方策
等を講義します。
企業の規模や、産業の種類に関係なく、リードタイムが企業成長のキーワードになっていることを理解してください。
リードタイムに関する知識の習得が目的です。
②ケースによる疑似体験演習
受講者の皆さんには、長いものから、短いものまで、リードタイムに関するケース(ビジネス物語小説風のもの)を
2,3編読んでもらいます。
そして自分が主人公ならどうするか、どのような思考プロセスで意思決定するか、ケースの中心に身をおいて考えて
ください。
第一ステップでは、そのケース文の中で、重要な言動や行動をチェックし、なぜそれが重要なのかを考え、
次のステップで、講師より与えられた課題に対し、答えます。
個人で考えてきた後、別途設定された班別討議を経て、受講者によるプレゼンテーションを行います。
班別討議や他の班のプレゼンにより、他の人の考えを聞き、新たな「気づき」も期待しています。
生のケースで考えることにより、講義の内容を概念ではなく、具体的に理解し、異なった場で応用できるまでの思考
及び行動プロセスを理解する知恵の創造が、目的です。
後に簡単に講師より解説を行います。
横展問題
改善提案
本講座の構成
教師による
講義
自己ケース作文による
自己点検ケースによる
疑似体験演習
実企業における
問題解決実習
知識習得
知識理解知恵定着
知恵創造プレゼン、討議
自学自習
調査、検討、計画立案

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
3
③実際の問題解決実習
次のステップは、習得した知恵を実際に使用して、問題解決を実践するプロセスです。
会場会社で準備したテーマ実習と、受講者自らの組織体で、自らが課外で推進する横展テーマに分かれます。
*テーマ実習
グループに分かれ、会場会社にて設定された実際の問題を解決する実習を行います。
ヒアリングによる現状調査から始まり、目標の設定、改善案、改善計画の策定、根回し、オーソライズを行い、
更に本来なら実際に計画立案した改善を行い、その結果までフォローすべきですが、講座の都合上、
改善提案発表会をプロジェクト発足会と模して行い、プログラム終了とします。
*横展テーマ
異なった場でも応用できる目的で、横展テーマの課外実践実習を行います。
受講者はリードタイムに関する自社、あるいは自らが遭遇している問題に対し、
会場会社で行っているメインテーマの検討過程を応用して、自らが中心となって、問題解決を推進していきます。
受講者はまず上司と相談し、横展テーマにどのような問題をテーマとして進めるか、決定します。
横展テーマ登録を行い、計画立案に基づき、行動し、第10週に自分のやってきたことをプレゼンします。
講座期間中は、その進行状況の報告や、勧め方に対する質疑、アドバイス等を講師による個人面談の形で実施し、
異なった場でも応用可能な能力を醸成していきます。
講座の期間の関係で、改善実施まで進めないと考えられますが、講座終了後に実践の進行に伴い、新たな質疑
があれば、メール等の手段で継続的に行います。
講座終了後、改善完了後に結果報告を所属組織体にて、自主的に行ないます。
自らの力で、 後の改善実施後のフォローと改善の評価までやり遂げてください。
なお、自らの改善職場を持たない学生諸君は、社会人の受講者とペアを組み、社会人のテーマを共同で解決し
ていきます。
④工場見学実習
(本年の講座では、時間の関係で含まれておりません。受講者同士で連絡を取り合って、独自に進めてください)
過去の本講座で、会場会社以外の他工場の見学の希望が多くあり、今回講座に組み込んでいます。
受講者の所属する企業体の生産現場を見学し、問題点の発見と解決案の提案を行ないます。
(別途見学工場選定)
工場見学は、事前に問題意識を確立し、テーマとする視点を定めておかないと、何気なく通り過ぎるだけとなって
しまいます。
いくつかのテーマを持って、問題発見能力のトレーニングを様々な異なった観点から行なってみましょう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
4
⑤自己ケース文 A,B の作成
後のステップは、この実習の成果を知的財産として残す過程です。
皆さんの成果は、 終の発表会で良いプレゼンをすることではなく、強い改善マインドが体内に醸成され、
それを自分の職場に持ち込むことです。
そのための財産として、皆さんの今回の経験を文章で記述する必要があります。
後に全てを思い出してまとめて書こうとするとなかなか出来ないものです。
専用ノートを作り、一日A4 1 ページ以上の日記をつけましょう。それを整理しながら、結果だけでなく、
どのようなプロセスでどのように意思決定したのかを物語風に書いて見ましょう。
テーマ実習用 B と横展実習用 A に分けて書いて行った方が良いと思います。
横展実習用 Aでは、自分が取り上げた横展実習テーマを進めていく過程での有為曲折や意思決定、プロジェクトを
進める過程での気付いたことや、重要と感じたことなど、物語風に、ケーススタディにあるケースを作るつもりで記述
していきます。
テーマ実習用 B については、実習中に印象に残った他のメンバーの意見、行動、なるほどと思ったこと等、
自分に新しい気付きを生んだ情景を記録しましょう。
書かれた物を毎週講師とともに確認し、更なる気付きを書き加えていきます。
あなた自身が、職場に帰って、何か困った時、あるいは後輩に『気付き』を与える時、読み直せば発表資料のppt
からは得られない効果があります。
3. 2010 年実習テーマの概要
(1)今回の実習テーマと前回までの違い
昨年までこの講座を同じ企業体の先輩が数多く受講されています。
今回実習テーマを大きく変更していますので、その変更点を以下に示しておきます。
前回までは個別受注型組立型産業を取り上げ、
「リードタイム短縮を営業の引き合いから 終出荷検査まで仕事の対象広く取り、インタビューを中心として
仕事の仕組みの改善を提案する」取り組みをテーマとしてきました。
今回は、型式別生産を基本とし、型式別大量生産の自動車や電器とまでは行かないけれども、
若干の顧客オプションを含む型式別中種中量生産の製品を提供する企業体の生産工程に焦点を当てて、
自らがその工程の調査、分析を行ない、改善を実践する過程の中で、その改善の考え方、改善の手法を学んで
いきたいと考えています。
前回まではインタビューにより、当事者よりヒアリングした情報に基づく改善、
今回は自分自身で、現場を調査、分析して行なう改善 この違いです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
5
このような生産工程では、機械加工を中心とする 終製品の部品を加工製作する工程、
およびそれらの部品や購入部品を製品として 終組付けする工程に大別されます。
無論、部品加工製作工程では、その前工程に原材料を提供する工程が存在する場合や、
表面処理や熱処理等の後工程が存在する場合があったり、で、種々様々です。
(2)講座の狙いと目標
テーマで取り上げられた具体的な問題を改善することにより、改善の進め方、考え方や手法を習得し、
同時に自らの所属する組織体の問題を解決することにより、自らの生産工程改善の力と改善マインドの醸成を
狙っています。
受講者の目標は講座終了後、自らの力で、JITに基づきテーマの改善と自分が取り上げた自社の横展問題を
解決する、もしくは解決方法の提案を行なうことです。これは前回と同一です。
(3)目標達成の評価方法
テーマの発表内容
横展テーマの進行状況
(4)テーマの概略
工程改善の対象となる工程のカテゴリーにより、その改善のための内容が大きく変わってきます。
ここでは期間を分け、2つの問題に取り組みます。
(ⅰ)機械加工を中心とし、若干の組付けを含む創生加工工程
(ⅱ) 終の製品を組み上げる組立工程(主に人による)
4.テーマ解決のための考え方と予備知識
では、まず、この改善はどのような考え方に基づいて進めるべきなのか、少し考えて見ましょう。
一般の「4S」や「見える化」といったものではなく、
「生産システムはどうあるべきか」といった少し硬いところを考えて見ましょう。
(1)JITとは
JIT は自働化とともに TPS の二本柱として広く世に知られ、
「JITとは必要なものを、必要な時に必要なだけ(量)作ること」と定義されていますが、
物を安定的に供給するものづくり組織体にとって、これを否定したり、反論することは極めてまれで、
(たとえば 100 円ショップのダイソーは異なった考え方で経営されています。)
一般的に、ものづくりの公理と考えて良いと思います。
ところで、この定義の中で、「誰が」必要とするかを考えて見ましょう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
6
製品にとって見れば、一般的に、その製品を用いて何か付加価値を生み出したい人、もしくは組織体を「お客さん」
と定義しています。
ここで考えなければならないのは、お客さんはその製品が欲しいのではなく、その製品の機能を手に入れたいの
です。
企業体であれば、その製品の機能を用いて何か利潤を生む仕事をしたいのです。
ここで言いたいことは、その製品、もしくは部品の形がどうであれ、顧客には関係ないということです。
設計された部品の形状が美しいとか、作るのに難しいとかは一切考慮の範疇には無く、
(美術品とか工芸品と呼ばれる類の製品は必ずしもこう言いきれませんが、)
出来上がった製品の機能が、顧客の要望した機能に合致していれば、顧客は満足してくれます。
同様に、どのようにして作るかはお客さんにはまったく関心が無いのです。
製品の形状、および作り方は自分たちの裁量権の中にあることを忘れてはいけません。
次に製品ではなく、部品を製作し、次工程に送る工程を同様に考えた時、誰がお客さんなのでしょうか。
お客さんは製品を使う人なのでしょうか。
終工程、もしくは次工程に部品を供給する各工程は「お客さん」は誰と定義すべきなのでしょうか。
それを考えないと、サプライチェーンのさまざまなポジションにいる人が、自分の立場に置き換えて、JITの考え方
を踏襲して改善を進めることが出来ません。
結論を先に明示すると、それが内製であれ、外注部品であれ、「後工程はお客さん」と考えることが重要です。
となると、後工程が必要なものだけを必要な時に、自工程はどうやって作るか ということになってきます。
一番良いのは
後工程が必要なものを、必要な順番で、後工程が使用する直前に、一個づつ作ることになります。
現実的には、わずかな安全在庫(0 が理想的だが、工程の信頼性による)を持ち、作る、ことにほかなりません。
それを後工程は自分が作る直前に持って来て、もって来た時、初めて前工程にそのもののお金を払う。
一般的なお客さんを考えた時、お金の無い人は、必要なものを、必要な直前に購入し、僅かしか無い金を支払う、
ごく当たり前のことではないかと思います。
これが当然のことと考えるならば、皆さんの職場の各工程はよほどの大金持ちだと思いませんか。
一週間後の夕飯の素材を買ってきて、冷蔵庫の中で腐らせているわけですから。
会社にはある一定のお金しかないわけですから、それぞれの職場がそのように裕福だとすれば、それ以外の所
にはお金がないことになります。当然、働いている人には僅かしか回す余裕はなくなります。
工場の中は物に姿を変えた金貨であふれていますが、働く人には回ってきません。
組織体外の人に商品となって手渡され、代金となって回収されて始めて、そこに働く人に給料として支払うことが

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
7
出来るようになることを忘れてはいけません。
それだけではなく、運転資金が工場の中に溜まって、倒産の憂き目に会うことさえありうるのです。
(2)JIT に立ちふさがる壁
理屈は良いと分かっていても、JIT 生産を行なうためには克服しなければならない課題がいくつかあり、
その課題解決の困難さに勝てずに大量生産型の生産方式を続けている組織体が多いのも事実です。
では、どのような障壁が存在しているのでしょうか。
(ⅰ)不安と保険
お客さんに対して、ぎりぎりまで物を作らないのですから、人間であれば、特に責任感の強い人は、万が一予期
せぬ出来事があって、(機械が壊れたとか、作業者が予期せぬほど休んでしまったとか、素材が前工程から入荷し
なかったとか、)さまざまなリスクに対する不安感が、生じます。
予期せぬアクシデントに対して、早めに作って貯めておけば、後工程の「お客さん」に対し、迷惑がかからないと
責任感の強い管理者は考えるのが普通です。
しかしここに落とし穴が待っています。
保険は高額かけているほうが安心できますし、お金のある人のみがかけられるのです。
極端な言い方をすると、お金に余裕のある人しか掛けられないのです。
言い換えれば、自分の職場に余裕のあるということは、いつ起こるかわからないリスクのために、
無駄なリソーセスを費やしていることなのです。
改善する方向は、保険をより高額掛けることではなく、その不安要素を取り除く努力をすべきです。
とはいえ、一気に保険を解約するのではなく、その不安要素に対して自分の実力は現在どの程度かを評価し、
不安要素を取り除く努力をしていくことが重要で、徐々に保険の金額を減らしていくことが必要です。
(ⅱ)製品の種類とJIT
しかしながら、このような内部的要因だけでなく、外部要因として、更なる大きな問題が立ちふさがります。
製品の種類、それに伴う部品の増加です。
高度成長期には、ターコイズブルー(色の名前)のセリカ(車の名前)がひとつの型式で 2万台の需要がありましたが、
安定成長期の現在、嗜好の多様化により 100 以上の車型で 2,300 の需要で、平均 1 車型 1 台といった状況も
まれではありません。
今回のテーマ実習で取り上げられている織機の例でも、型式は設定されているものの、顧客オプションを含めると
製品の種類は驚くような数字になると思います。
これらの製品を構成する部品は、製品の種類により同一のものを使用できるもの、あるいは異なった形状のもの
が必要になったりします。
ほぼ同一だが、一部分だけ異なるもの(たとえば穴が一個余分にあいているもの)の場合もあります。
いわゆる「似て非なるもの」です。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
8
これが品番数を増加させ、いつ使うか分からない作る可能性のある部品を生み出します。
更には、その部品の原材料が異なったり、次工程へ渡る前に他の部品には無い表面処理が必要だったりします。
また、同一の機能を有する部品でも、製品の大きさや、形状の違いにより、同一の工程で加工できなかったり、
出来たとしても加工時間や組み付け時間が大幅に異なる場合など、製品の中で同じ機能を持つ部品でも形状や
加工工程が異なるものを、用いる必要が生じます。
競争の激化と顧客の多様化、 適化のために製品の種類は増加する一方で、設計は顧客の要求にこたえること
が第一優先で、種類をどんどん増やし、生産方法の理解不足のために、作りにくい設計をします。
一度顧客からクレームがつくと、設計者は自分の責任回避のため加工公差は一段と厳しくなり、
一度厳しくなった公差は製品形状や機能が大きく変化するまで、容易には元に戻りません。
あたかも一度事故のあった交差点は、周囲の状況が異なり、見通しが良くなったとしても、その標識がはずされる
ことが無いのに良く似ています。
次工程に同期化して作ることが、製造のリードタイム短縮につながることは分かっていても、種類が多いために
同一の工程で生産できない場合があります。
ものの形状や加工方法が異なると、加工工程、加工機械、加工時間が変化してきます。
中には段取り替えが必要なものもあったり、ロット生産を余儀なくされる場合もあります。
さまざまな理由により後工程への同期化が困難なものとなってきます。
多くの場合、これらの困難に負け、ロット生産をはじめとして工程間中間在庫を持つ誘惑に負けてしまいます。
そしてそれはやむをえないもの、この製品では仕方の無いこととして容認してしまっている組織体が多いのが実情
です。
あくまで後工程に同期化して、一個流しにこだわり、生産システムを変化させていくことが、生産のリードタイムを
短縮し、中間在庫を減少させ、結果としてコスト削減にもつながることを肝に銘じるべきです。
(ⅲ)コストは後からついてくる
もうひとつの問題は、一個づつ作るのはコストが高くなるのでは?という懸念です。
企業の競争力は Q(クオリティ)C(コスト)D(デリバリィ)により決定する。と従来より言われています。
これら 3 要素の一翼 C が悪化すると、回り近所が認識する中で、いわば反逆行為を行なうことになり、村八分になり
かねない行為を行なうことになりはしないかという懸念です。
現在の製品原価の計算は主に原材料費、稼動費と償却費からなっており、原材料費が同じだとすると、時間当たり
何個作るかでコストが決まってしまいます。
ですから同じリソーセスで、早く作る能力のあるほうが「コスト競争力がある」という結論になってしまいます。
しかし、それは本当でしょうか。
作れば売れるという高度成長期には、必ずそのうちに売れるのですから、「在庫も財産のうち」と考えても良いかも
知れません。
あるいは、販売業で「うちではこんなに数多くの品揃えでお客様を待っています」と、アピールするのは販促費として

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
9
必要かもしれませんが、工場内に中間工程品や、原材料が山のように積まれているのは、必要なものを探す手間が
増えるだけで、なんの足しにもなりません。
結局、同じリソーセスで、早く作れることは、安定成長期の今は、ポテンシャルは持っているかもしれませんが、
コスト競争力があるとはいえない時代になりました。
逆に、余分なものを作っているため、お客様の本当にほしいものが早く届かず、デリバリーの観点から言うと
マイナスになりかねません。
必要なものだけを、必要 小限のリソーセスを用いて作る場合と、
必要あるかも知れないものを作るのに十分のリソーセスをもって作るのと、どちらがコストが高いのかは
考えるまでもありません
(ⅳ)段取り替えと誤組み付け
種類が増えるということは、加工であればプログラムやツールを変えたり、収納する容器を変えたり、原材料を変
えたり、さまざまな段取り替えが発生するのが普通です。
段取り替えは一般にはシステムを停止し、行なわれるので、微視的に見ると稼働率の低下を招きます。
1 回あたりの段取り替え時間が同じであれば、一個流しで頻繁に段取り替えをすればそれだけシステムは停止し、
コストが増大する危険が潜んでいます。
そのため、一回にまとめて作るとコストが下がるので、大ロットで作ったほうが良いという結論に至ってしまい、
「大ロットで作るという何の努力も付帯することなくコストが下がる」ことになってしまいます。
何の努力もせず、コストが下がる、本当でしょうか、そんなことがありうるのでしょうか。
車を走らせる時の燃費を考えてみてください。
滑らかに一定速度で走ったほうが、頻繁に止まったり、発進するよりもはるかに燃費が良くなる(エネルギーが少なく
てすむ)ことを忘れてはなりません。
ここでは、段取り回数を少なくするのではなく、1 回あたりの段取り時間を短縮する努力をして、段取り替えの回数を
増やす、言い換えればロットサイズを小さくする努力をすべきなのです。
組立であれば、組み付ける部品が小刻みに変化するので、誤った部品を組み付けないように、作業指示情報を
製品一台一台、タイミングよく担当者に伝える必要が生じます。
それに基づき、数多くの部品群の中から、その製品に適合した部品を取り出し、組み付けるのは大変だ。
同じ部品を連続で組み付けるほうが間違いにくい、ロットで流すほうが、誤欠品が起こりにくいと考えるのですが、
別の考え方も出来ます。毎回組み付けるものが変化するほうが、しばらく連続で同じものが流れ、突然違うものを
必要とするよりも注意力が向上し、間違いを起こしにくくなるともいえます。
作業工数的にも、平準化を考慮し、的確に作られた生産順序は少ない工数で組み付け可能にします。
更に進んだ部品の供給システムが必要になってきます。
(ⅴ)需要の変化と生産システム
後の大きな悩みは「需要変動に対してどう考えるか」であろうと思います。
新製品発売当初は、生産計画とは比較にならないほど爆発的に売れるが、わずかの期間後には製品が陳腐化し、
急速に減衰して、閑古鳥という製品が珍しくありません。
特に安定成長期に入っては、デザイン重視の製品やファッション性の高い製品ほど、この減衰率も高く、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
10
「今、望ましくないオペレイションを行なっているのは生産計画が悪い」という言い訳になって帰ってきます。
需要の変動に迅速に対応できるフレキシビリティが必要となってきます。
言い換えれば、
人も設備もすばやく現在の需要に合わせた能力に、迅速に変える意欲と力を持たなければなりません。
遅れれば遅れるほど、重要なリソーセスの無駄遣いを続けることになります。
TPSでは、設備的には、後追い設備、寄せ止め、人的には多能工化、非カタログエンジニア(技術者は手を汚し
て何ぼ)、などいくつかのキーワードにしたがって、常に変化に対応して、改善を求められます。
この需要変動に迅速に対応する分野は、常に需要は変動しているので、改善活動は、常に、永久に、続くことに
なります。ここでは変化に対応するまでのスピードが問題となります。
需要予測は一応考慮するが、当たらない可能性が高いこと、を考慮して、生産システムを考えることが重要です。
つまり、事前に、必要な時には、わずかの期間で、わずかのコストで能力が増強できるよう、
たとえばロボットの取り付けベースのねじを定盤上に取り付けておくとか、工程分割の具体的な姿を事前に考慮して
おく等、後からやると膨大な工事やコストのかかる増産対応を、事前に 小限のコストで、 初の計画段階で考慮し
ておいたり(後追い設備)、複数のラインで生産していた製品を一方のラインを停止して、一方に固めて流す
「寄せ止め」を短期間で行なえる配慮をする、等の減産対応を事前に検討します。
レイアウト変更が簡単に行なえるように移動できる基礎の無い設備形態を目指すなど、大きな変動が発生しても
変動に迅速に対応できるシステムを考えることが必要です。
そのような迅速な対応が出来るためには、その組織体で、その需要状況に合わせて、設備を自在に改造できる
計画能力のある技術者となることが必要ですし、実際に改造するテクニシャンを養成する必要があります。
機械を買うだけのカタログエンジニアでは、結局設備供給メーカーに依頼することになり、迅速な対応など望む
べくもありません。
更に、加工や組み付けの担当者が自分の現在担当している工程、機械しか扱えないとしたらどうでしょう。
いかに工程の組み換えや、作業配分を変えて、需要に生産能力をあわせるシステムを計画しても、作業訓練をして、
実行できるまで時間が経過し、すでに市場が変化しているかもしれません。
普段からローテーションを行なったり、計画的に作業習熟訓練をしていなければ、迅速に工程変更など絵に描いた
もちとなってしまいます。
一般的には、需要が増大している時は、「忙しい、忙しい」とは言って、生産計画に追いつかなくても、仕事が無
い時に比べれば、まだ贅沢な悩みであるといわざるを得ません。
その時には残業であるとか、事務職の現場応援、企業間応援シンジケート、期間工(今後法規制の方向)等による
人的リソーセスの増加による対応が考えられます。
しかしながら、生産量が減った時、設備の都合や、各人の仕事の引き当てが困難なために、以前の早いタクトで
ものを作っている事が多いものです。
本来なら、その需要量にあわせた人間で物を作り、生み出した人員で、更なる付加価値を生み出す仕事に着手
したり、日ごろ手のついていない大規模な改善に着手する絶好のチャンスなのですが、それをみすみす逃していま

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
11
せんか。
そのうちに、需要は回復するのだから、一時すれば元に戻るのに、こまめに仕事を変えるのは無駄な努力だ、と
思っていませんか。
不況の時代に、そのリソーセスを有効に使う組織体とそうでない組織体とは、大きな差がうまれることは言うまでもあ
りません。
(3)向かうべき生産システムの姿
以上、JIT 生産を妨げる要素について説明しましたが、致命的に避けられないものではありません。
お客様の本当にほしいものだけを、それを作るための 小のリソーセスで作ることに対する阻害要因について
いくつか考慮してきましたが、それに対してあきらめるのではなく、その阻害要素をあらゆる努力をして突き進もうと
する姿勢が、コストを下げることになると思いませんか。
コストを下げようとするあまり、大ロットで生産し、工程間在庫を増加させる方向に進むのではなく、
一個流しで、お客さんの要求する順序に生産する、そして工場内では 終のお客さんだけでなく、後工程をお客さ
んと考える、そしてそれに対して出現する阻害要因を一歩一歩つぶしていく、
この連鎖が競争力のある生産システムを作り出すことを、しっかりと理解してください。
(4)どの程度を具体的目標とするのか。
目標は常に高めに設定して、チャレンジすることを忘れてはなりません。
「ちょっと努力すれば、出来そうだ」という目標ではなく、「とんでもない、そんな目標なんて」という目標を
設定しましょう。
少し前の話になりますが、自動車の外板部品は 800 トンクラスの大型プレスをタンデムに 5 台ほど並べたラインで
加工されており、その段取り時間は 100 分くらいかかっていました。「3 桁かかっていた」といえます。
その時、指導に来ていた先生から与えられた目標は「シングル」でした。
今でこそゴルフが盛んになって、シングルの意味が分かりますが、当時は、目標の「シングル」の意味がほとんど
のプレス従事者には分からず、シングルの意味を知った時、大半の人間は「そんな馬鹿な、何かの間違いだろう」と
言っていましたが、先生から「シングルとは一桁のことであり、前の製品が加工完了してから、9 分以下で次の製品
の良品が連続的に流れてくる状態がシングル段取りである」と話された時は、集まっていた面々は「そんな無茶な」
と思う反面、「よし、やったるぞ」という意欲にあふれたものとなりました。
夢のような目標が、皆のチャレンジ魂を燃え上がらせ、絶え間ない改善意欲を生み永続的な改善行動を生んだ
と考えています。
その結果、ロットサイズは大きく減り、工場の広大なスペースを占めるプレス品収納ストアも、種類が 20倍にも増え
ているにもかかわらず、工場建屋を拡張することなく操業されています。
皆さんの目標も、予備調査で出来そうだという目標ではなく、普通では考えられない 1/2 とか 1/3 といった、
チャレンジする目標を立てましょう。
(5)実行の手順
一般的な改善の手順を下記に示しましたが、現状の姿をしっかりと調査し、自分の描いたあるべき姿を整理し、
その乖離を埋めるための方法を具体的に考え、実行することです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
12
そのやり方は自らが自信を持って行なうことであり、手順も自分が決めればよいのです。
改善計画を作成するまでの手順は以下のとおりです。
1.自工程のおかれた立場を整理する。 前後工程との関係を明確にする。
2.ものと情報の流れ図ものと情報の流れ図ノートを完成し、流れ図を仕上げる。
3.自工程の現状の生産状況、生産指示情報を整理する
4.自工程の作る製品、部品を分析するし、カテゴライズする (PQ分析)
5.後工程の分析を行い、必要なタクト、生産能力を求める。自工程の必要能力、あるべき姿をまとめる。
6. 自工程の各工程のサイクルタイム測定を行い、ピッチダイヤグラムを描いてみる。
(6’.工程ごとのタイムスタディを行い、工作図をつくる。)
7.自工程の工程内在庫、前後工程とのつなぎの在庫数、在庫の形態(収容状況)を調査記録する。
8.自工程の必要能力、工程間在庫、工程内在庫あるべき姿をまとめる。
9.ネック工程に関する調査を行なう。
8-1.ネック工程はどこか
8-2.ネック工程の仕事を余裕工程へ配賦できないか
8-3.ネック工程のシーケンスを改善できないか、オーバーラップする方法は無いか
8-4.ネック工程の加工を分割できないか 等
10.現状とのあるべき姿と比較し、現状の問題と改善すべき点を整理する。
・ ロット生産のロットを小さく出来ないか(一個流しが出来ないか、近づけないか)
・ 工程間在庫は減らせないか
・ 運ぶ単位を減らせないか
・ 流れ化できないか
・ ちょっとした工夫で、待ち時間を減らせないか
11. 改善計画を立てる

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
13
5.講座日程計画表
講座は16回、48 時間で、下記のスケジュールとなっています。
現時点では後学期(10 月から)火曜日午後を考えています。
時刻 13:00~13:45 14:00~14:45 15:00~15:45 16:00~16:45 17:00~17:45
回 1 2 3 4 510 月5 日 講座の意義、内容 CSの進め方 必要データの配布等1012 グループ討議 発表 グループ討議 発表 解説1019 グループ討議 発表 グループ討議 発表 解説1026 グループ討議 発表 解説112 グループ討議 発表 解説11 横展テーマ発表会9 グループ議論 発表 解説1116 質疑11 会社・製品概要説明30 課題説明 127121412211111181262128 フィードバック 成果物整理作成
工大 2ケーススタディ(C1S1、2)
3工大
ものづくり知識創造学統合特論 スケジュール
場所 日付
工大 1 ガイダンス講義
講義
工大 4
5
6
工大
工大
7工大
16自己点検
津田
14
15津田
津田
工大
12
テーマ発表会 卒業式
13
ラインバランス 改善演習
講義その他の改善手法(工作図等)
11
10
8 クランク工程説明(現場)
横展発表会
津田
ケーススタディ(C2S1)
津田
津田
9津田
津田
生産指示方法の説明
ものと情報の流れ図
ケーススタディ(C1R)
ラインバランス
講義
C2R
ものと情報の流れ図 演習
C3R
発表資料見直し中間発表
改善計画案の作成、予想効果算出 提案書まとめ、発表資料作成
ネック工程シーケンス図、連合作業分析表 作成
改善項目・目標の作成発表、見直し
ネック工程等詳細調査、分析
フローチャート作成
ネック工程等詳細調査、分析
サイクルタイム、要素作業、仕掛量調査
調査まとめ(ラインバランス表、サイクル線図)
サイクルタイム、要素作業、仕掛量調査
ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図 作成

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
14
6-1.成績評価
受講生の今後の研鑽のために、成績を評価します。
数値評価内容は下記の通りですが、加えて講師よりのコメントを追記します。
レポート 議論参加度*
班 個人 個人 個人
講義
ケーススタディ 15 5 5
テーマ実習 30 5
横展実習 30
自己点検文 10
計 45 30 15 10
プレゼン
成績評価 内訳
*議論参加度については自主採点
6-2.その他 伝達事項
受講者の皆さんの様々なアウトプットは出来るだけデータとして持ってください。班内の検討結果の情報共有や、
学習の整理にも効率的です。
そのため、ラップトップのパソコンと USB 等のメディア、および専用ノートを毎週持参してください。
毎回の講座に持参するもの
・パソコン
・ファイルホルダー(A4用)
・USB
・講座専用ノート

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
15
7. 後に、
この講座を受けるにあたって、どうしても受講者にお願いしたいことをお話します。
この講座は名前の通り、受講者の皆さんに講師より知識を移植する講座ではありません。
自らが行い、自らが実践することにより、自分の中に知恵を創造する講座です。
そのためには、自学自習が極めて重要で、講座外での予習、準備が十分でないと、十分な成果が得られない
だけでなく、チーム活動ですので、チームの他のメンバーにも迷惑を掛けることにもなりかねません。
今から脅かすのも変ですが、講座の事前、事後学習を十分実施して、講義に参加してください。
そして、チーム活動では、班内で、役割分担を明確に設定し、リーダーシップ、メンバーシップを十分に発揮し、
討議に積極的に参加する事によって、
皆さんの得た知識が創造性豊かな実践力に変わることを期待しています。
職場の上司の方へ
受講生は、この講座受講直後は、改善の意欲の芽が勢い良く伸びていると思います。
しかしながら、今後、大樹に育ち、果実を得ることが出来るか、もしくは栄養不良であえなく枯れてしまうかどうかは、
上司の行動と職場の風土にかかっています。
言い換えれば、組織体に今育ちつつある改善の芽が風土が定着できるかどうかは、上司の方の一挙手一投足に
かかっています。
上司の方の今まで以上の、ご理解と行動を期待しています。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
16
2.リードタイム講義
1.リードタイムの意味と重要性
リードタイムとは「必要性が生じてから、その目的が達せられるまでの期間」と定義付けられますが
一般的に生産リードタイムとか、調達リードタイムといったように、
○○リードタイムと前に何かその行為が付かないと意味を成しません。
リードタイム短縮が重要視されるようになって来たのは、トヨタの業績が脚光を浴びるようになり、
トヨタ生産方式のJIT(ジャストインタイム)がもてはやされるようになってからと思います。
JITでは当初生産リードタイムを取り上げ、その短縮のための活動が、その考え方とともに進展し、
リーン生産方式と名づけられ、日本だけでなく、世界各地で取り上げられていきました。
高度成長から安定成長に移行して、買い手市場になってからは、
SCM(サプライチェーンマネジメント)の重要なアイテムとして、
オーダーデリバリーのリードタイム短縮が企業の競争力の根源として研究され、短縮のための活動が活発となって
います。
更に、嗜好の多様化や、嗜好の変化に迅速な追従が不可欠となり、開発のリードタイムが、企業の成長を支配す
るようになって来ました。
これらのリードタイム短縮は、リードタイムが生産性等のような個別の部署の活動で達せられるものでは無く、
企業全体の調和の取れた活動を必要とし、
その指標が重要視されるのは、需要の変動に対する適応力やリスク耐性等、企業全体の底力を表わし、
将来の成長をも示唆する指標であるからに外なりません。
見込み生産の量産組立型の産業と、個別受注の、少量生産型の産業とでは
リードタイムの短縮では基本的な考え方は同じでも、その取り組みの方法が異なってきます。
例えば、
量産型の型式見込み生産では、「顧客の欲しいものを迅速に届ける」と言う意味では同じですが、
開発のリードタイムと、オーダーデリバリーのリードタイムに大別され、それぞれを改善する取り組み方法も
異なります。
デルのオーダーデリバリーリードタイム短縮のビジネスモデルは、デルのシェアの拡大と共に一世を風靡しました。
一方、個別生産の場合は、受注されたものが、全く同一の仕様のものというのは皆無に近く、いわば、毎回異なった
商品を開発し、お客様に届けると言った開発、オーダーデリバリーが渾然一体となったリードタイムとなっています。
ものづくりを主体とする企業において

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
17
リードタイム短縮は顧客に対する満足度を高める、そして、コストを削減する、即ち作る、売る両者に寄与することを
まず理解してください。
一般に、ものづくりを行う企業は売る所と作る所で利潤を生んでいますから、他の構成員は、それら「売る」「作る」
行為がし易くなるように働かなければ、企業の業績は上がりません。
顧客は特殊な事情が無い限り、買うと意思決定してから、早急にその機能(物ではありません)を獲得して、
その機能を使いたいと考えます。
企業であれば、その得られたものを使用して、何か利潤を生む行為を行いたいと考えています。
ですから、受注してから納入されるまでの時間が競合者と比較して短いのは、売りやすいポテンシャルを持っている
ことになります。
一方、作る側で言えば、
作り始めて、完成するまで、半分の時間で出来ることは、その期間2倍の人数がいることと同義ではありません。
一般的にはトータルの工数として、より少なくて済むと言われています。
一言で言えば原価を大幅に低減する効果を持っています。
第二は
リードタイムの短縮は一部署の努力や行動、あるいは一部の人のそれでは、さしたる実績を上げることは出来ない
ことを理解すべきです。
リードタイム短縮は、先日世界陸上が大阪でありましたが、400m リレーに似ています。
第一走者は営業で、以下設計、調達、製造と繋ぎますが、いかに各走者が早くてもバトンの受け渡しが下手では
金メダルは取れません。次走者がトップスピードになる時、バトンが的確にスムースに渡るように、前走者は細心の
注意を払わなければなりません。(後工程はお客様)
一般にリードタイム短縮の改善は業務の抜本的な変化を必要とする場合が多く、一つの特定の部署で完結する
改善は皆無といっていいと思われます。
何かやろうとすれば、前後工程に対する働きかけが必要ですし、協力がなければ改善は進みません。
特に、前工程は「後工程はお客様」の考えで、後工程の仕事が 善にできるよう、自分の仕事の枠組みを作る必要
があります。源流管理の考えから言っても、後工程の管理水準を上げるためには、前工程の力が必要です。
後工程は前工程に対するフィードバックで、そのお返しをする事になります。
フィードバックは苦情を言うことで終わるではなく、お互いは協力して、より良い仕事の仕組みとすることです。
この講座では良く「仕事の仕組み」と言う言葉が出てきますが、仕事の仕組みを変えなければ、しばらくは良いとし
ても、必ずいつか同じような問題が発生します。
再発を防止して同じ問題が発生しなければ、管理水準が向上し、企業の体質が強固になったと言うことです。
セクショナリズムによる、出来ない理由の説明をしても何の効果もありません。
一緒になってその理由を見つけ、一緒になって解決することが必要です。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
18
しかしながら、全社一丸となってある目標に対して進んでいくことは口で言うほど簡単なことではありません。
いわゆるセクショナリズムと言われる,お家の事情がついつい出てしまうからです。
各部署が持つ痛みやつらさを部署全体が感情移入できるほど理解し、共にその問題を解決する姿勢が無ければ、
リードタイムは短くなりません。
再度言いますが、これは各部署が「仲良しクラブ」になることではなく、
特に後工程は、協力的ではあるが厳しく、時には前工程の悪いものは絶対受け取らない、あるいは悪さを計数値と
して指摘することが必要です。この姿勢によって、やり直しの再発防止が出来るからです。
同時に、経営者の確固たる信念に裏付けられたリーダーシップが不可欠です。
下は常に上を見ていますから、上が何に関心があるのかには敏感に反応します。
第三は、
成績評価を行う評価指標のあり方を含めた全体のシステム(仕事の仕組み)の改善が重要となってきます。
一般的に効率(出力/入力)の指標、もしくは出力のみの評価指標が多く、リードタイムに関する指標を取っている
企業は少ないと思います。
時間の概念を持つ指標を掲げ、常に自分の過去と比較し、同一水準で比較できる評価指標が必要です。
競争相手は、他社ではなく、過去の自分、現在の自分だからです。
なぜなら、他社との比較によるベンチマークは、必ずしも言葉の定義が同一とは限りませんし、
仮に定義が同じだとしても、その仕事のしくみが詳細に分るわけではなく、
ただ数字を比較して、「負けているから頑張ろう」というモチベーションにはなっても、「どういう方法でやろう」という
やり方を学ぶ事はできません。
その点、自分の評価指標はその定義も明確ですし、過去の自分と比較し、
比較の結果、良し悪しの原因も推定が可能となってきます。悪かった所は、再発防止により過去に犯した過ちを、
二度と起こさないこと、過去に当たり前と思っていた過ちが二度と起こらなければ、必ず、過去の自分に勝つことが
出来ます。
トヨタでは[Beat the TOYOTA]と言う言葉がはやりましたが、正確には[Beat the current TOYOTA]と言うべき
でしょう。
各部署の責任区分を明確にして、その結果が成績指標に現れるようにすべきであり、
例えば、工程原価の仕組みでも、責任部署別費用振替システム等、他人に責任転嫁することなく、自分の責任と
して受け止められる指標とすべきです。
一般的には期間管理されている財務管理も、受注オーダー別、部署別管理等細部管理に転換することによって、
全ての部署が過去の自分と比較、競争できることになり、当然再発防止の活動も具体的にすることができます。
プロセス指標
結果としての指標だけでなく(成果指標)、プロセスの結果を表す、プロセス指標を整備する事が必要です。
プロセス指標に厳密な定義はありませんが、財務のように結果を見せる指標ではなく、ある目的達成のために

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
19
各プロセスが、どのような状態になっているかを示す指標です。厳密ではありませんが、その指標を管理する事に
より、設定した目標項目の結果を、知らず知らずのうちに良くする指標と考えてください。
例えば、
リードタイム短縮で言えば、営業では引き合いから、仕様書作成までの期間や、仕様変更件数等がプロセス指標で
あり、受注件数や受注獲得率はプロセス指標ではありません。
この指標を分析して、改善の方法を見つけ、仕事の仕組みを変えるヒントを見出すことが容易になってくる事に意義
があり、その目標が正しければ、結果としての指標も付いてきます。
四つ目は
個別受注組立型産業において、オーダーデリバリーリードタイムは軽視されがちですが、量産型と同様に、
経営上極めて大きな意味を持ちます。
筆者には、個別受注組立型の産業の場合、
冒頭にも述べたように、毎回製作するものが異なるために、量産型の産業と比較し、学習効果を軽視しがちであり、
評価指標の継続的フォローについても、違うものを同じ土俵で評価できないと言う意識が先に立ってしまうように
思われます。
財務についても、一件の受注が大型で、年間件数の極めて少ない業界以外、
個別プロジェクト管理や、工程別原価管理等を行ない、プロジェクト毎に評価し、次の改善に繋げているでしょうか。
見えるようにすること、そして見えた失敗は二度と起こらないように再発防止すること、評価して、ベンチマークするこ
と、当たり前のことを、当たり前のようにやる仕事の仕組みを構築する必要があります。
リードタイム短縮のために、各部署が連携を持ちながら、進めるべき業務は、数多くありますが、
そのなかで もキーとなるのは
①役割分担では、生産管理部のリーダーシップ、
②業務内容では設計の標準化
ではないかと筆者は考えています。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
20
2.リードタイムと付加価値時間
一般に、オーダーデリバリーのリードタイムは、顧客からの引き合いからスタートし、多くの工程を経て、
顧客への製品の引き渡しをもって終了します。個別受注型の工程の流れを下図に示します。
①先に述べたリレーにたとえると、第一走は営業です。
営業は顧客からの引き合いを、受注に結びつけるのが組織としての重要な任務ですが、
リードタイムの観点からは、顧客の要求機能を具体的に明文化し、設計に仕様書として伝達することが役目となり
ます。
仕様書(スペック)は顧客側が作成し、それに基き、発注するのが普通ですが、
個別受注産業の場合、顧客は要求機能がイメージとしてあっても、製品として設計するにはあいまいであったり、
不十分であったりで、受注側が顧客とのヒアリングの中から、作成することが多い。
設計は仕様書と言う「バトン」を営業からもらって走り出します。
無論、製作途中でも客先からの仕様変更は発生し、時間が経つほどその影響は増加するので、営業部門は、迅
速に情報を把握し、後工程に正確に伝達する事が必要です。
②設計は仕様書に基き、客先の要求機能を満足する製品を設計します。
要求機能を全て満足しない製品は全て廃品となり、売ることが出来ません。
どこまで工程が進んでいようが、やり直しとなりますから、コスト的にも時間的にもロスとなります。
仕様書の記述内容があいまいだったり、不足していたら、徹底的に確認することが重要ですし、
仕事の仕組みとしても、抜けがあったり、誤解の生じない工夫が必要です。
図面出図、部品表発行を持って後工程の調達や製造の内製加工部門に引き継がれます。
前述の営業からの仕様変更、および設計責任(設計ミス等)、後工程要望等(コスト削減等)の設計変更は
仕様決定 図面作成
組付、トライバラシ、梱包、 出荷検査
部品調達
部品加工
営業
顧
客
引き合い
設計
製造
現地調整
製造 検査製造
仕様書発行 図面出図
部品集合組み付け完トライ完
検査合格引渡し完
供給先(自社)
製造
購買
個別生産組立産業型企業の工程とマイルストーン
仕様決定 図面作成
組付、トライバラシ、梱包、 出荷検査
部品調達
部品加工
営業
顧
客
引き合い
設計
製造
現地調整
製造 検査製造
仕様書発行 図面出図
部品集合組み付け完トライ完
検査合格引渡し完
供給先(自社)
製造
購買
個別生産組立産業型企業の工程とマイルストーン

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
21
やり直しとなりロスが生じますから、過去のデータ分析等も通じ、再発防止に努力することが必要です。
③調達、加工
出図された図面、部品表を基に、組み付けるための部品の製作が開始されます。
製品は多くの部品から成り立っており、内製と外注に区分され、組立開始を日程的ターゲットとして一斉にスタートし
ます。生産能力にもよりますが、部品手間隙がかかる部品や、すぐ作れる簡単な部品もあります。
全ての部品が集まってはじめて組立工程が開始できます。
(厳密には、サブアッシー構造をとれば、全てが集まらなくても可能ですが、それは後述します。)
も時間のかかる部品(ボトルネック)は 後に出来上がりますから、組立開始はこの部品の日程で決まります。
従って、この工程のリードタイムはこのネック部品の日程で決定されます。
④組付け、トライ
製品製作の 終の工程です。
全ての部品が集まって組みつけが開始され、トライアウトを行なうことにより、出来上がった製品が全ての要求機能
を満足する事が確認されて終了します。
全体のリードタイムだけでなく、各工程のスタートと終了の定義を行ない、工程毎のリードタイムを評価する体制が
必要です。
その際、後工程は全ての前工程の影響を受けますから、前工程は「後工程はお客様」の気持ちを忘れず、後工程
がどうしたら楽に早くできるかを常に考えることが重要です。
そして、後工程は様々な情報フィードバックすることで、その努力に報いると言う姿勢を持つ事が必要です。
ⅰ)リードタイムの構成要素
①実際に仕事をしている期間(付加価値時間)、
②待ち時間(停滞時間)、
③やり直し時間
④運搬時間
の四つに大別されます。実際に時間を取ってみると分かるのですが、
意外と付加価値時間が少ないのに気が付くと思います。
実際にオーダーデリバリーのリードタイムに対する仕事をしている時間(前後工程責任による待ちを含めない
標準作業での標準作業時間)の比率を付加価値時間比率と名づけ、
この付加価値時間比率の逆数を(そのままだと小数点以下となり、分かりにくいため)リードタイムの絶対値だけで
なく、これをサプライチェーンマネジメントの一つの評価指標として、確認することが重要です。
評価指標
付加価値時間比率の逆数=オーダーデリバリーのリードタイム/実際に仕事をしている時間

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
22
特に生産のリードタイムを考える時は
(製品が完成した時刻― 初の工程に仕掛かった時刻)/実際に仕事をしている時間
として、 優先に考えなければならない指標の一つで、生産工程の組織力を表わす指標となっています。
流れ化の出来ていない工程では、工程間在庫が多く、この指標を大きく(悪く)させる基になっています。
ⅱ)待ち時間
生産だけでなく、情報のロットサイズが大きいために、待ちが増加することがあります。
物の流れにおいて、ロットサイズの大きさがリードタイムに極めて大きな影響を与え、
トヨタ生産方式では「1 個流し」を究極の目標にしていることは皆さんご周知のことと思います。
情報の流れにおいても同様のことが言えます。
全ての情報が整わないと、情報が出されないとすると、前に確定した一部の情報は、そのロットの 後の情報が
出来るまで、発信を待つことになります。
それが次工程の作業開始のために必要な情報だとしたらどうでしょう。
全情報が整わなくても、スタートできる部分もあるはずです。
前工程のある部分の情報が明確となれば、次工程がフライイングしても、「あわてものの間違い」を起こさない
内容を、全ての情報が整う前に先出しすることです。
後工程への情報は小ロットとし、特に次工程がネックとなる部分を明確にし、その情報を優先して作り、提供すべ
きです。
製造の場合、設計が図面を書くのを待ち、調達が外注品を集める時間を待っているのです。
設計が も調達時間が長い図面情報を先出しし、調達が他の部品に先行して発注すれば、部品集合日を
その分だけ先出しできることになります。すなわち組み付け開始を早めることが出来ることになります。
ⅲ)やり直し時間
次にやり直しが、三つの意味で、リードタイムを伸ばす要因となります。
①実際のやり直しのために時間が必要となる。
②やり直しを予測し、仕掛からない、もしくはトップスピードで走らない。
③やり直しを予測し(容認し)、遅れが自己責任とならぬように冗長な日程計画を実行する。
例えば製造を例にとって考えると
①については説明の必要は無いでしょう。
いざ、設計の出図が完了し、自工程がスタートしても、また仕様変更や設計変更があればやり直しをし、
外注品の精度不良があり、またやり直しをする事態が発生します。
そのたびに、進行は中断され、やり直しを行い、再度トップスピード入るには、単に中断された分だけでは
すまない影響があります。
本当にやり直しが無ければ、思いもよらない短期間で、仕事が完了するのに驚かれることでしょう。
一度推測してみてください。現状の日程計画表に示されている製造の工程が、もし何のトラブルも無く,スイスイと
加工が完了し、組み付け、トライが出来たら、何時間、もしくは何分で出来る仕事なのでしょうか。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
23
②、③については、実際の中断時間以上に大きな影響があります。
製造はその遅れを組みつけ遅れとか、製作遅れと全社的に評価されるとしたらどうでしょう。
現象としては確かにそうなのかも知れませんし、事情を良く知らないトップは誤ってそう評価するかもしれません。
製造としては、自分の責任でもないのに、割り切れない思いとなり、再度そのような事態を避けるため、
再発防止対策を立てるに違いありません。
設計変更を容認し、設計変更があっても遅れない製造日程を生産管理に提出するのです。
その間違った対策を生産管理が看破できないとすると、それが標準日程となり、リードタイムは、その状態で全社的
にオーソライズされてしまうのです。
設計にしても調達にしても、製造同様、前工程のやり直しの影響を受けますから、製造と同様の態度をとったらど
うでしょう。全体として、リードタイムはどんどん長くなってしまいます。
このような態度は、セクションが明確に分かれ、組織の区分がはっきりして、且つ評価システムもしっかりして、
一見、管理の行き届いた組織体のように見えますが、本当にそうでしょうか。
大きな病気をする度に、生命保険の額が増えていくのと同じように、大きな仕様変更がある度、標準日程が延び
ていきます。本当にこれで良いのでしょうか。
ⅳ)運搬時間
運搬時間はともすれば輸送時間のみを考えがちですが、単に A 地点から B 地点まで、移動させる時間を意味す
るものではありません。
ここでも待ち時間の所で説明したロットサイズが問題になります。
例 : A 地点から B 地点まで、移動させる時間10分、X 製品が1分に1個完成するとしましょう。
X を運搬ロット1個とする場合と10個とする場合の運搬時間を考えて見ましょう。
運搬ロットが1の場合は 初の製品が完成してすぐ輸送されるわけですから、10分後には B 地点に到達
しているわけですが、運搬ロットが10個の場合は、 初の製品は、後の9個が完成するまでの9分間待っ
てから、10分掛けて輸送され、合計19分かかってやっと B 地点に到達できるわけです。
初の製品は、待ちの9分を運搬の時間と見れば、運搬時間は全く違うと言うことになります。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
24
3.リードタイムとキャッシュフロー
リードタイムとキャッシュフローの話はデルのビジネスモデルの話が有名で、話す必要が無いほどでしょう。
ゲートウエイやコンパックは衰退し、デルのシェアが急進した歴史を見ても明らかです。
リードタイム分だけ借金が溜まっているといったら言い過ぎすぎでしょうか。
企業は、製品を作るための材料、部品を買い、設備を買い、人を雇って給料を払って、製品を作ります。
しかしながら、製品が売れ、お客様に対価を支払ってもらうまではお金は入ってきませんから、
それは借金でまかなうことになります。
一方オーダーデリバリーのリードタイムとは、お客の注文があってから、お客に製品をお届けする(対価をお支払い
頂く)までの期間を意味しますから、それが長いということは、永い期間借金をし続けて、物を作り続けていることに
なります。
言い換えれば、リードタイムが短ければ、短いほど借金が少ないということになります。
無論、実際には受取、払い込みの手形の決済期間が問題となりますが、これが同等だとすれば、サプライチェーン
内の在庫はリードタイムと正の相関があり、
その在庫はすなわち一時的借金ですから、言い過ぎではないことになります。
次ページの図は自動車におけるサプライチェーンの模式図ですが、この楕円の円周がリードタイムであり、
この面積が全体在庫と考える事ができます。リードタイム(円周)が長くなれば,このサプライチェーン内の在庫(面
積)が増加する事になります。
受注
生産計画
部品発注
必要数予測
受 注
生 産
出 荷
部品受入
部品メーカー
納 車
完成車輸送
部品輸送
営業・生産管理部門
一体で輪を縮める(トータルリードタイム・コストetc)
販売店オーダー
生産
出荷
注 文
車両組立工場
お客様
楕円の面積が在庫量 周の長さが時間

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
25
4.リードタイム短縮のための方策の分類
それぞれの業務を下図①~⑤の観点から見直します。
①各個別業務の仕事の仕組み改善による期間短縮
・各工程の業務の実質作業時間を仕事のしくみを改善して短縮する。
②業務間の情報伝達の仕組み改善によるやり直し削減による期間短縮
・情報の共有によってやり直しを削減する。
③業務間の情報伝達の仕組み改善によるフライイング、オーバーラップによる期間短縮
・情報の小出し、確度の高い情報のフライイングによる先行手配をかけ工程間のオーバーラップを行う。
④再発防止の仕組みつくりによるやり直し削減による期間短縮
・やり直しの原因を徹底的に究明し、その原因を再発させない仕事のしくみを作り上げる。
⑤アイドルの明確な区分(工程の 終に1個)による標準時間の設定
・さまざまなタイミングに設けられている、バッフアを 小限とし,各工程の 後に1つだけ設け、
改善の進行と共に、それを限りなく O に近づける。
製造
調達
設計
営業
現状
1
各工程のオーバーラップ
各工程のやり直し削減
やり直しバッファ
2、4
3
5
短縮
各工程の業務改善
各工程のバッファ削除
製造
調達
設計
営業
現状
1
各工程のオーバーラップ
各工程のやり直し削減
やり直しバッファ
2、4
3
5
短縮
各工程の業務改善
各工程のバッファ削除
営業 設計 調達 製造

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
26
5.工程別リードタイム短縮の着眼
リードタイム短縮のアイデア発掘のために参考となる知識を工程別に記述します。
1.製品の開発製作工程の概要
受注個別生産の場合、工程(ステップ)は大きく分けると
1. 引合い
2. 受注
3. 仕様決定
4. 設計
5. 調達
6. 加工
7. 組付
8. 配線、配管
9. 調整、トライ
10. 出荷検査、分解、梱包、発送
11. 再組付現地トライ
の 11 ステップに分けられ、それぞれが問題を抱えながら、相互に情報を出し合い、業務を遂行しています。
2.各工程での改善の目の付け所
1.営業
引き合いから受注、仕様決定までは、業種により業務分担は様々ですが、一般に主役は営業、助演は設計
となっています。
営業の役割は単に受注を獲得、促進するだけではありません。
発注仕様を確定し、正しく早く設計に伝達することにあります。
そして、その仕様は発注者、受注者両者にとってメリットがある仕様で確定されるべきです。
ではどうすれば、両者にとってメリットのある仕様になるのか。
1. 顧客の必要とする能力、サービス力、信頼性があり、
2. 価格が適正で(出来るだけ低コストで)
3. 短期間で手に入る 仕様です。
これは
「過去に作った実績のある設備を基本として、顧客ニーズに対応して、局部的に改善されたもの」
が一つの回答となりえます。
顧客をその方向へ誘導することが両者の利益に繋がることを、営業は理解すべきです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
27
そのためには営業の IT 武装化が必要です。
例えば、本社のコンピューターと接続し、顧客の要望に沿った過去の製品を容易に検索するシステム等
を利用して、顧客と仕様を過去の設備をベースとして確定していけば、その方向へ進むことが可能です。
更に、より具体的に、スピーディに仕様決定がなされ、設計とも直結してきます。
次に営業の重要な役目は
やり直しを発生させ、リードタイムを長くする 仕様変更をいかに減少させるか ですが、
「お客様は神様で、お客様の言う事は聞かなければしょうがない。」と考えていませんか。
仕様変更の中は全く突然のことで、お客様の気まぐれであることは決してありません。
何らかの理由があるはずです。
原因は大別すると
①状況が不確定で、仕様作成時点当初より迷っていたが、必要時期的に期限がきて、やむを得ず仕様確定
したが、状況が確定したら当初とは異なっていた。
②外部状況が急変した。(経済動向、競合他社動向)
③内部調整が不十分だった。
等で、営業は、顧客との打ち合わせの中で、十分仕様変更の可能性を予知できるものもあるはずです。
その情報を的確に設計に繋げる仕事の仕組みになっているでしょうか。
作成された仕様書の問題のある場合もあります。
①仕様書( 終仕様確認書)の記載項目は設計にとって十分か。
②設計が一義的に理解できる内容となっているか。
③仕様変更の可能性の情報が盛り込まれているか。
・仕様変更発生原因を分析するためのデータが取られているでしょうか。
過去に起きた仕様変更を分析し、仕事の仕組みを改善することは、次の仕様変更を減らすことにつながります。
仕様変更に限らず、原因別、現象別、顧客別、項目別、ロス量別等々、様々の角度からデータを分析し、
どうしたら再発が防止できるかの観点から、継続的に改善を進めれば、減少します。
・仕様書項目の確定度分析
仕様書の発行予定日と顧客との仕様確定の日程が合わず、記述項目が全欄記述できない、もしくは 100%確定し
ていない場合があります。顧客の要求納入日を満足するため、それでもフライイングせざるを得ない場合、項目
別に確定度を記録し、設計に伝達します。
データを集積し、確定度と仕様変更の影響の相関を分析します。
項目によっては、確定度が低くても、リードタイムに影響を与えない項目もあれば、仕様が変われば大きなロスと
なる項目もあります。
・仕様書項目の後工程への影響度分析
同じような意味で、後工程でネックとなる部品(調達リードタイムの長い部品等)が関与する仕様は、確定時期を

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
28
早める必要があります。
他の部品より先に図面を確定し、調達を開始して初めて集合日(後述)を同じにできるからです。
・仕様変更責任の明確化と受注金額に対する処置の明確化
再発防止のためには、その費用負担も含めて、その責任の所在を明確にする必要があります。営業の立場では、
顧客との間で揉め事は避けたい気持ちはあると思われますが、責任区分を明確にし、その費用も具体的にして
おく必要があります。
これはお金を顧客から取る、取らないは別として、仕様変更の重要さを認識させ、削減への動機付けの効果があ
ります。(内部だけでなく、顧客にも)
あるメーカーの専用設備調達では㋱、自 と言う記号があります。立会い時に不具合をビラに記入し、いつまでに何をやり、再確認するかを記入する
際に、その不具合の責任区分として、メーカー責任か、顧客責任かを明確にし、記録する。
それによってその不具合対策のお金はどちらが持つのかを決定する方法を取っています。
「営業でのキーワード」
・不確定状況での外段取り
-----不確定状況下での後工程への情報伝達とフライイング可能業務の整理
・情報の小出し
・受注仕様書 ------- 実績のある設備へ導くための検索手段
・仕様変更 ---------- 原因究明と再発防止手段
・営業の設計情報での武装化
2.設計
生産のリードタイムは設計が決める。
主役は設計部門、しかし、設計を助ける助演は製造(生産技術)、調達からのフィードバック。
リードタイムは設計の標準化が決め手
設計は得てして、自分の技術的興味から新機構のもの、自分の新しい設計を目指したがるもので、それ自体
は悪いことではありません。
設計は自分が白紙から線を引くほうが圧倒的に楽で、モチベーションも高いのです。
(塗り絵を描くよりも、白いキャンバスに自由に描くほうが楽しいのです。)
しかし、 も考えなくてはいけないのは顧客の要望です。
「いかにすれば、顧客の要望に合致するもの(Q)を、 も安いコスト(C)で、 も早く(D)作り得るか」です。
顧客は製品を買いたいのではなく、製品の機能を買いたいのだということを忘れてはいけません。
(影の声)独りよがりは開発部門に任せましょう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
29
顧客の要望(機能)は、スペック(仕様)で表されます。
長年同じジャンルの物を作っている組織体であれば、受注生産といえども、似たような仕様の設備を過去に
作っているはずです。
それをベースとして、良いとこ取りして、できるだけまねして設計すれば、学習効果もあり、作り易いはずです。
・なぜ設計の標準化が出来ないのでしょうか。
自由に線を引く従来の設計に勝る従来部品検索システムおよび便利なコピー&チェンジ CAD システムが
出来ていないためです。
①過去のものを検索しようとすれば、部品のコード体系がきわめて重要です。
型式設定、コード設定(製品分類)、品番設定の方法が厳密に体系付けられ、それが検索に便利なように
なっていることが必要です。
②過去のものを使おうとすれば、そのつなぎ部分に検討をする事が増加します。流用する部分、つなぎのため
の新設計部分が分かりやすく表示され、つなぎの部分が設計し易くなっていることが必要です。
③また仕様と標準部品、あるいは標準サブアッシー、標準ユニットとの関連付けが明確となっている必要があり
ますし、
④現在受注したプロジェクトの仕様と近似の過去のプロジェクトの検索システムも必要となってきます。
これらを整備し、システムを作り上げることは、大変な苦労ですが、
標準部品の設定を増やすことは調達を含めた作る側で十分報われますし、設計工数も大幅に削減可能です。
個別受注生産だからといってあきらめてはいけません。
例えば繊維機械を作っている企業が、自動車を受注するわけではないのですから、製品群をカテゴリー別に
いくつかに分類すれば、細部は異なっても、同じような機能を有し、同じような構造をとっていると思います。
全体が流用できなくても、S/A、部品と細分化していけば、標準化できる部分はあるはずです。
・標準化された部品を製作する部署はどうでしょう。
前に製作した事のある部品と、全く新規に加工するものとでは先回の学習効果が存続していれば、それを
有効に使えるでしょうし、ツールが残っていればそれを使用することも可能です。
部品作成の手順、日程も先回の作成で分かっており、納期見積もりも精度の高いものとなるに違いありません。
更にはコスト削減のアイデァも先回の経験から考え易いでしょう。
このように設計の標準化は
設計部門の合理化だけでなく、製作コストの低減、品質向上、納期遵守の観点から、計り知れない効果を持って
います。
・「部品流用率」が設計のプロセス指標となっていますか?
設計の評価指標として、「一人当たりの設計点数」を取っている組織は多いと思いますが、それはそれで効率の
観点からは必要なことでしょうが、もっと大事なのは、図面を書かないことです。
部門目標をそれに定めると、人間はその指標がよくなるように努力します。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
30
「一人当たりの設計点数」の定義を、「流用したものは設計点数に入れない」と定義したらどうでしょう。
流用すればするほどこの指標は悪くなる、すなわち効率が悪いと言うことになってしまいますから、
たぶん流用率は低下することになります。
少なくても、評価指標を「一人当たりの設計点数」で存続するならば、「流用したものは設計点数に入れる」と
しなければなりませんし、
更に、ここでは「部品流用率」を新しく定義し、評価指標として認知しないと、流用設計が進みません。
人は自分の行動が進歩していることを自分で認知し、他人に認知されることによって、更に良くなろうと努力する
生き物なのです。それを知るのは評価指標です。
「設計におけるキーワード」
・流用設計か新規設計か
・部品流用率、S/A 流用率
・コンポーネント、S/A の標準化とはめ込み設計
・図面検索手段、方法
・設計変更原因分析(やり直しの低減)
・設計変更被害を 小化する仕事の仕組み
・承認図設計(仕入先との連携強化と前段取り)
・設計構造(S/A 構造)
・製造設計(作り易さへの考慮)
・設計基準工数
3.調達(購買)
組み立て型産業の場合は量産型、個別生産型を問わず、外注依存度が高く、7割以上に達することもまれで
はありません。一つの部品がなくても、製品は完成しないわけですから、図面が出てから外注部品を如何に迅
速に集めるかが、リードタイムを大きく左右することになります。
調達の仕事は一般的には「調達は事務屋の仕事、仕入先との人間関係こそが調達を成功させる。」と信じてい
る人がいますが、本当でしょうか。
それも必要でしょうが、生産技術屋を配し、設計図面への注文と、納期見積もりをしっかり行う事が重要です。
もっと作りやすい設計(加工必要工程数、必要材料)で、同一もしくはそれ以上の機能を発揮できる構造を提
案できる仕事の仕組みが有効です。
これによりリードタイム、コストを大幅に削減し、品質を向上することが可能です。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
31
仕入先との関係は、リードタイムという狭い観点から考えるのではなく、運命共同体として如何にして共に成長
していくかとの観点から考え、その実行結果として、調達リードタイム短縮が成しえると考えるべきです。
以下に仕入先との関係で考慮すべきことを述べます。
・仕入先の選択とその育成計画
仕入先は組立型産業にとって、共に成長していくとも言える存在であり、経営姿勢、協力度、自社依存率や
技術力を考慮して、慎重に選択し、将来にわたって期待値とあるべき姿を共有することが必要です。
有力な仕入先は、発注区分を下図の右方に進むよう、仕入先の長期的育成計画を立て、実行していく必要が
あります。
工程 → 部品 → サブアッシー → 製品 → 承認図
主要な仕入先には設計段階より参加させるべきです。
それにより、仕入先は事前に多くの情報を得ることが出来、また製造を考慮した図面が描かれ、
その結果、短納期で、コストの安いものを供給可能となります。
育成計画には定期的な仕入先の技術力の把握が必要不可欠です。
どのような人財、設備、工程を保有しているのか。
部品の加工精度は?。
自社の生産能力は、外注を含めると? 等々
・仕入先の教育、仕入先との人事交流
仕入先の教育の中で、 も重視しなければならないのは、発注した部品が全体の製品(システム)の中で、
どのように構成され、どのような機能を期待されているのか、理解させることです。
無論、どこが品質上重要かは図面情報により知ることが出来ますが、自社の製品が全体のシステムの中で、
どのように取り付けられ、どのような働きをするのか、を実際に自分の目で確認するか、しないかでは、大違い
です。
自分で組み付けてみれば、その形状の必然性が理解でき、システムのトライアウトを行なえば、どこを精度保
証すべきか、その機能上、過剰な精度保証箇所はどこか等、知ることが出来ます。
コスト、品質、リードタイム面での多くの知見を自分の体で体得できた人間が育成され、仕入先での取り組みの
できる人材が育成されることは、その完成製品の付加価値を飛躍的に高めることに寄与します。
その逆もあります。
発注先の設計者は図面を書きながら、その実際にその部品の製作過程を見ていません。
自分で物を作ってみれば、その設計の QCD の観点から改善すべきことが実感できます。
・仕入先からの創意工夫提案制度
個別受注生産の組立工業の部品仕入先は一般に汎用部品を供給する大企業、もしくは個別設計部品を
供給する中小零細企業に大別されます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
32
設計は汎用部品に対しては、出来るだけ特注品とならないように十分配慮するので、その結果、個別設計
部品に無理を強いる結果となります。
あるいは作り方を熟知していない設計者は、難しい加工、工数のかかる加工、必要以上の許容加工公差等
言い換えれば、コストのかかる作りにくい加工を必要とする図面を書き上げます。
製品の受注先からクレームがある度に、仕上げ指示をレベルアップしたり、検査項目を増加したりして、対応し
がちです。構造を考え直すより簡単に処理でき、設計責任を回避できるからです。
本来は構造を本質的に見直し、作り安さを保ったまま、クレームの再発防止をすべきなのに、です。
前に述べた人事交流も量的には限りがあり、広範囲に広げるのは難しい状況です。
その結果、何が起きるのでしょう。
注文を受けた中小零細の仕入先は、難しいと分かっていても転注を恐れ、図面どおりの部品を苦労して作り上
げるのです。これではコストを増加させるだけで、調達リードタイムは増加する一方です。
物を実際に作っている仕入先は、どこが一番作りにくいのか、どうすれば安く作れるのか、どうすればお客の
クレームを減らせるのか、知恵を持っています。
しかしながら、立場上、発注先に従って、図面通り作る方が、好印象をもたれ、今後の受注も期待できること
を良く知っています。
砕けた表現をすれば、「小賢しいことを言って睨まれるより、『はいはい』と言っていたほうが良い」となります。
調達は仕入先の知恵を設計にフィードバックすることによって、納期を短縮できる機会を与え、コスト削減や
品質向上を狙える仕組みづくりを講じる必要があります。
内製部品では生産技術や製造が行なっている QCD の観点からの設計変更依頼を、仕入先の創意工夫制度
や原価低減、品質向上などの提案制度を導入することによって、実現させるのです。
無論、その提案により得られた利益は仕入先とある比率で分配することにならないと、その活動は活性化しま
せん。
・仕入先の評価基準と表彰制度
仕入先には年度毎に、Q,C,D,F(突発事象に対する対応性)に関する期待値と、それが達成できたかどうか
を判断する評価基準を計数値で定め、共有する事が必要です。
それを元に、年度末にその結果を反省し、次年度へ向けての取り組み方を協議することが重要です。
それにより、仕入先との人間関係だけでなく、組織的結束力を強める働きをします。
上記を仕入先の自分自身の時系列成長度の見える化とすれば、
表彰制度は仕入先間の競争原理を利用したモチベーションアップに繋がります。仕入先は発注者から
他の仲間の仕入先よりも優れた存在である事の証明書をもらうことは次の行動に影響を与えます。
継続すること、乱発しないことが肝要です。
・仕入先の負荷の把握
仕入先の負荷は、自社への依存度が極端に高い場合を除き、自社の発注量で負荷が見積もれるとは限りま
せん。一般的には多くのパトロンを持ち、他のパトロンの負荷は明らかにせず、より多くの受注を獲得しようとし
ます。自社の発注量に山谷が大きい場合や自社への依存度が低い場合、仕入先は自己防衛上、そのような

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
33
行動に出るのはやむを得ません。
パトロン自体がもともと顧客よりの受注量に山谷があるのですから、必然的に外注への発注量は、増幅されて
変動し、谷の時に、餓死してしまうリスクが存在することがその理由です。
特に工作機械や、装置類は景気の変動を受け、大きくその負荷が変動しますからなおさらです。
したがって発注者は仕入先の負荷を、正確に把握し、調達遅れのリスクを回避しなければなりません。
・発注量予側と負荷予側
有力な仕入先には事前に発注量の予側を提示し、心積もりや前順備をさせることが肝要です。
遠い将来の予測では当りはずれが大きすぎて予測になりません。
中期(半年先くらい)は実需、もしくは引き合いによる需要予測を基に、長期育成計画を参考にして、
発注予測を提示し、それに対し、仕入先は、他社よりの受注予測も含めて、自分達の負荷見積りを返します。
運命共同体には何よりも信頼関係が重要だからです。
・長納期部品の先行手配
リードタイムを決定するボトルネック部品は も重要な管理部品となります。
そのような部品が、顧客の要求するリードタイムに合致しない場合は、先行で手配することが必要です。
しかし、客の確定仕様と合致しない場合は、それが流動性のある部品なら良いのですが、廃品となるリスクを持
っています。
リスクを低減させるためには、仕様決定の一部前出しとか、流動性のある状態で購入し、後加工を内製で行な
う等の処置を行なう必要があります。
・カムアップシステム
外注先の部品の納期管理はどのように行なっているでしょうか。
量産型の産業と異なり、量も少なく、仕入先は中小の企業であり、納期管理にも十分手が回らない企業も多い
はずです。
個別受注型の産業では、部品種類数だけ多く、発注個数も少ないといえども、必要な部品が一部品でも納期
通り納入されなければ、組立できません。
多くの場合、組立現場からの督促で、その未納入が発覚することになり、組立日程の遅れを引き起こします。
その結果を予測して、組立の日程はそれを見越して、冗長な日程を組んだり、いくつかのプロジェクトを並行し
て進め、その非効率を避けようとします。
それが、製造のリードタイムを延ばすことになります。
それを避けるためには、全て揃ったのか、現在何が集まってないのか、事前に、誰もが簡単に分かり(見える
化)、手が打てる仕事の仕組みが必要です。組み付け開始時によくよく調べたら、「何がない、かにがない」で
は手遅れになってしまいます。
しかし、いちいち事前に納入状況をチェックし、未納仕入先に督促していては大変ですが、情報技術の進ん
だ現在、自動的にチェックし、自動的に督促し、自動的に対策を確認することが可能です。
カムアップシステムは、事前に決められた集合日(組立開始の 2,3 日前)に、納入予定の部品をチェックし、
未納入の仕入先に連絡し、その督促をし、予定日通りの納入を約束させるシステムで、情報の検索、情報の授

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
34
受等により、計画遅れの防止を行います。
「調達におけるキーワード」
・負荷予告
・仕入先能力管理
・仕入先育成計画
・内外製区分
・調達区分 工程 → 部品 → サブアッシー → 製品 → 承認図
・工程調達
・部品調達
・サブアッシー調達
・製品調達
・承認図調達
・工数調達
・複社発注(二社発注)
・種類分けのみ内製後加工(工程設定の複合化)
・場内外注
・日程計画、製作とのマッチング(集合管理)、
・スケジュール管理の細分化(仕入先の報告システム)
・カムアップシステム (×:納入日に結果がわかる)
・受け入れ検査 → 出荷基準成績表
・平準化調達(標準部品)
・ネック部品の半加工在庫、先行手配
・特殊工程部品、特殊工程の個別能力管理
・情報ネットワーク
4.加工、組立
加工、組み付け工程は、 初に前工程の悪さが「吹き溜る」工程です。
仕様変更、設計変更、調達遅れ、外注部品品質不良等々数え上げるときりがありません。
そのような前工程の悪さをもらいながら、お客様への納期保証の責任だけ押し付けられては、管理者はたまった
ものではありません。
したがって、それを逃れるために、結局の処、加工、組み付け以降の業務は、ケースに現れるように、前工程の
やり直しやミスを包含した冗長な計画としがちですが、これは百害あって一利無しです。
標準時間に基づいた実働時間で計画すべきで、どうしても後工程に対する納期遅れを心配するならば、
改善されるまで、責任工程の 後にひとつだけ、調整と証するバッファを設けるべきで、そこには実作業を
含んではいけません。あくまでバッファです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
35
標準時間に基づいた実働時間の計画は前工程の悪さを顕在化(見える化)します。
なぜなら、問題があれば、計画通りに進まないからです。前工程の原因でも、計画通り進まなければ自分の管理
責任になるので、前工程に対する是正要求を厳しくすることになります。再発防止を求めます。
一方調整を含んだ冗長な計画ではどうでしょうか。
よほど大きなやり直しや前工程遅れがあっても、「調整の時間」で計画通り進行してしまうのです。
計画通りですから全く問題ありません。
問題の無い所では改善は進みません。
悪いことをした部署に再発防止を要求することなど考えもしません。
製造部門が考えるべき課題
製造部門が他の部門に働きかける重要なポイントをいくつか上げてみましょう。
・図面への注文
製造部門の仕事は図面の書かれたものを忠実に作ることだと信じていませんか。
製造部門は作りやすい構造、品質向上のための構造、コストの安い構造、メンテナンスしやすい構造等々、
多くの顧客満足度を高める構造的知識を持っています。
これらをフィードバックして、リードタイムを短縮するのが、源流管理です。
製造の源流の設計にアクションをとり、自らの仕事をより質の高いものに変化させるのです。
その意識を持ちながら、図面に対する注文を行うことです。その部品に反映できなくても、構造要件書として
部品単位に整理して設計にフィードバックするのは後工程の責務です。
・問題の発見と早いフィードバック、不具合処理
そうは言っても、不具合は皆無という訳にはいかないのが実情です。
不具合の発見後、早急にフィードバックし、不具合処理を迅速に行わなければ、次の作業にかかれないことも
あります。
・定例ミーティングの実施
日に一回は定刻ミーティングを行いましょう。
製造現場に大きなビラを掲示し、組付け担当者はその日に発生した問題を残らず書き込みます。
(問題の見える化)。
それを用いて一日のまとめを短時間で「メリハリをつけて」行うのです。
当然発生した時点ですでに連絡がなされ、アクションがとられている項目もあるでしょう。それについては
再確認の場となるわけですが、同時に関係部署の情報の共有の場となるのです。
不具合内容と対策内容、対策責任部署、対策日程、日程計画変更の有無、再発防止策等を決定し、既に
起きた不具合に対するフォローも行い、消し込みをしていきます。
日程計画変更の有の場合は即座に変更日程を作成し、現日程と差し替え、掲示します。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
36
・進行状況の見える化
進行状況の見える化は加工、組立てだけの問題ではありませんが、特に吹き溜るこの工程は特に重要です。
現状と管理板が常に一致していることが重要で、一度現状と管理板が不一致であることが発見されるとその後
は誰も信用しなくなり、機械的に記入しているだけの「うどの大木」に成り下がってしまいます。
・生産技術の役割
個別受注型産業の場合、量産型より生産技術に関する力の入れ方が少ないような気がします。
工程と言う概念や標準作業、標準時間と言う概念が当てはめにくいのが理由の一つではありますが、
一つ一つの製品が違うと言う意識が強すぎ、工作図を作っても次は違う製品なので、工作図も違うのでムダだ、
と言うことなのでしょうか。
結果、つくり方は現場任せ、日程も現場任せ、不具合処理も、----結果、フィードバック情報による再発防止も
標準化や図面へのフィードバックとして残らず、学習による効果が残りにくいことになります。
集合と配膳(バイキング、SPS)
ここで言う集合とは数学で言う集合とは異なり、組み付けの日程から、この日までに組み付けする部品が集まら
ないと、組みつけが予定通り勧められない限界の日を指します。
組み付けは部品が全て揃わないと、組み付けを始めてから、手順を変更したり、やり直しが発生したりして、
効率を下げる可能性があるからです。
したがって、組み付け開始前に部品が揃っているかどうか、揃っていない場合には探して見つけることが必要
となります。部品の数、種類が多くなると、これが意外と難しいので工夫が必要です。
いわゆる「見える化」を行なうことが重要です。
一般的には「消しこみ」という方法を用います。
組み付けの日程表に基き、部品表に基き作られたリストを張り出し、揃ったものをリストから消しこんでいくやり
方で、皆の目と意識を利用できる点で、コンピューターに入力管理と併用するのが良いと思います。
自動車会社では新車の組み付けのトライ時には良くこの消しこみを使用します。
まず①全ての部品とは何と何、②入荷したものはどれ、入ってないのは、③この品番はどの現物、④これはどこ
に組み付けるの、この部分の組み付け部品は全部揃ってる等々
この過程をしっかりやっておかないと、組付けを開始してから、探し物や、やり直し、果ては欠品手配等で、
組みつけのリードタイムが思いもよらず長くなることがあります。
作業を中断することによってペースが上がりません。
部品表を有効に活用し、物の置き場を、組み付け工程別に箱に入れて揃えることを配膳と言います。
あるいは必要なものだけ一つのトレーに入れて揃えるので、バイキングとも名づけられ、
それをライン大量生産で用いる場合、SPS(セットパーツシステム)と呼ぶ場合もあります。
・順序作業とサブアッシー構造
サブアッシー構造とは一つの基本部品に全ての部品を順序作業によって組み付ける構造ではなく、
ある部品群をあらかじめ組み付け(組みつけられた部品群をサブアッシーと言う)、そのいくつかサブアッシー
を基本部品に取り付けていく構想で設計された構造を言います。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
37
サブアッシー構造では、全部品が揃わなくても、そのサブアッシーに必要な部品が揃えば、組みつけが可能で
すし、あらかじめいくつかのサブアッシーを並行に組み付け、その後一気に基本部品の組みつけが可能とな
り、集合の分散化(平準化)が計れますし、
基本部品への組みつけが順序作業とならないため、組み付けのリードタイム短縮も期待できます。
例えば
基本部品Bに、サブアッシーX(構成部品 X1, X2、-- Xn)、Y(構成部品 Y1, Y2、-- YM)、Z(構成部品 Z1, Z2、---- Zl)
を組み付ける時、
X,Y,Zのサブアッシー組付け日数がそれぞれ XT,YT,ZT、
BへのX,Y,Zの組み付けが A 日(通常短時間)で済むとし、X,Y,Zのサブアッシー組付けを並行して行えば、
サブアッシー構造の時、 組み付けのリードタイム = Max[XT,YT,ZT]+A、
サブアッシー構造でない時、 組み付けのリードタイム = XT+YT+ZT
となり、大幅なリードタイム短縮となる可能性が高い。
一方の「集合」の観点から見れば、X、Y、Zの順にBに組み付けるとすれば、
部品 Y1, Y2、-- YM は 初の集合日より XT 日後を集合日とすればよく、Z1, Z2、---- Zlは XT+YT 日後でよいことに
なり、集合日の分散が図られます。
「加工、組付けのキーワード」
・日程計画から時刻計画へ(計画管理の小ロット化)
・工程分割(長すぎる工程は管理が甘くても何とかなる)
・フレキシブルとルーズの混同
・集合日と組立日のマッチング
・日程情報管理の見える化
・工程待ち実績の記録と再発防止
・標準作業と標準時間
・多能工化と能力の柔軟性
・5Sと見える化
・前段取り、後段取り
・パラレル生産、パラレル加工
・サブアッシー組み付け構造
・S/A 組み立て
・オーバーラップ作業
・標準部品設定
・標準部品在庫

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
38
・ネック部品
・設計変更とやり直し
・配線、配管の外段取り化
5.調整、トライ、工場立会い
調整という言葉は非常に便利な言葉で、全ての悪さを隠し、組織間の良好な人間関係を維持します。
本当ですか?
「全ての悪さを隠し」以外は全くの「うそ」です。
ここでの調整は、本来はあってはならない業務で、出来るだけゼロとすべき業務なのです。加工、組付けと同じ
ように実作業以外は含んではならず、やり直しをここで片付けるなどもってのほかです。
次の現地トライを極小化するための仕事を極大化すべきです。
そのための条件を整えるのに、事務屋は全力を挙げて、損をすることは絶対にありません。
「調整作業のキーワード」
・日程計画から時間計画へ
・標準作業と標準時間
・実作業内容の細分化、確定、標準時間設定
・実作業と余裕代の明確な分離
・ばらつきと再発防止
・時間調整の調整期間となっていないかの確認
・前工程の吹き溜まり ---- 情報のフィードバックと再発防止の仕組みは?
・前工程での成熟度が上がれば、調整作業は極小に出来る。
・顧客要望とのミスマッチ原因究明の仕事の仕組み
6.現地調整、量産トライ、引渡し
この仕事を極小化することは、顧客満足度を上げ、顧客の信頼を勝ち取るだけでなく、コストを下げる大きな
要因となる重要なステップです。
全社を挙げてこのステップの日程を短くする努力をすべきであり、この時点でのやり直しを極小化する事が重要
となります。
そのためには、5.調整作業の中で、いかに自工場の中で、現地を再現し、現地での量産状況を作り上げて、
トライをするかにかかっています。
同時に、ここでのトラブルは絶対再発防止する必要があります。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
39
問題の真の原因を「なぜ、なぜ、なぜ」を繰り返し、究明し、必ず具体的に「何をやるか」を決めなければ
なりません。
「現地調整でのキーワード」
・早急な情報伝達と全社バックアップ体制
・製作地で事前にやれることは無いのか
・トラブルの再発防止の仕事の仕組み
7.検査の役割
検査の役割はリードタイム上重要視されないのが一般的ですが、それは間違いです。
悪いことを指摘するだけが検査ではありません。
検査はともすれば不明確となる部品調達、加工組み付け、調整トライ社内立会い、現地調整量産トライの四ステ
ップの工程移動の達成基準を明確に定め、その責任の所在を明確にする役割を持つ必要があります。
いくらスケジュール通りといっても、規定の達成基準に達していないものは、工程移動を認めてはなりません。
当事者同士でではいい加減になりがちなので、ジャッジする部署が必要となる場合があります。
検査がその役目を担うのが適当です。
しかしながら、検査の役割はくどいようですが、出来たものの悪いことを指摘することではありません。
悪いものが出ないようにするのが仕事で、そのためには原因を追究し、原因となっている部署を特定し、再発を
防止し、その結果やり直しを防止し、良いものを早くお客様に届けることです。
その観点から考えればリードタイム上きわめて重要な役割を担っています。
・受け入れ検査
仕入先より納入された部品を検査するのを受け入れ検査といいます。
これは、出来たものの悪いことを見つける仕事ですが、これを行なわず、組み付け後の機能検査で、トラブルが
発覚したらどうでしょう。再度、部品を製作し、確認し、悪い部品を取り除き、新しい良い部品を組み付け直すと言
う処置をしなければなりません。
コスト的な損失ばかりでなく、時間的にも大きなロスとなり、日程を守るためには大変な苦労を必要とします。
普段は暇でも集合日近くなると極めて高負荷となるからです。
しかしながら必要悪と言えども、後々のリスクを考えるとやらざるを得ません。
これを簡略化し、真の検査の機能を満足するために、納入部品に成績表を添付させる仕事の仕組みがあります。
成績表とは、図面に書かれた情報が全て満足しているか、仕入れ先が部品を作成した時点で自ら確認し、記録
として検査結果を記したいわば仕入先が自分の作成した部品の品質を保証した証書のようなものです。
数多くの部品を層別し、受け入れ検査を行なう部品と、
仕入先のレベルに応じて品質保証活動を信頼し、成績表合格による無検査に分類します。
検査は成績表の検査項目、検査部位、要求公差を、仕入先と共に作りあげるのに協力し、指導します。
受け入れ検査をして、ハネルのと、どちらが仕入先のモチベーションがあがるでしょうか。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
40
8.生産管理(情報システム)
生産管理の目的は
『社会や市場が要求する品質の製品を、要求される時期に要求量をタイミングよく、且つ経済的に生産する』
事です。
したがって、生産管理の命題は
「コストをさげ、顧客に製品を出来るだけ早く届ける方策であるリードタイム短縮する」ことにほかなりません。
しかし、生産管理部や情報システム部は、一般的に、製品開発製作の直接に関与する実業務を行っていません。
この課題を解決するために、何を行うべきなのでしょうか。どんな仕事をすべきなのでしょうか。
戦略的に、プロジェクトのリードタイムをどうすべきか考え、さまざまなトライを行うよう、各工程への意識付けを行っ
ているでしょうか。
各工程への意識付けには、全社的な評価体制、フォローシステムだけでなく、各工程のパフォーマンスを自己管
理する仕組みが必要です。
そのためには、同一指標で継続し、時系列的に、その評価指標が「誰の目にも見える」事が重要となってきます。
継続的に、リードタイムの改善が進んでいることが「見える化」できていますか、
そしてそれはどんな仕事の仕組みが寄与しているのか、あるいはどの工程の改善が効いているのか分かるように
なっていますか。
それはどんな指標のトレンドで分かるのですか。
個別受注型といえども、プラント建設ではありませんから、プロジェクトは次から次にやってきます。
それぞれのプロジェクトにおいて何か新しいことにチャレンジしていますか。
プロジェクトをある観点から同じように評価し、何が良くて何が悪かったのか評価していますか、
そしてその原因は何かを分析していますか。
確かに、それらの仕事の改善はラインの各部の仕事かもしれません。
しかしながら、プロジェクト日程設定、進行のフォロー体制等、新しい仕事の仕組みを開発し、見える化し、その
課題に対し、全社のモチベーションを上げる仕事の仕組みを開発することが生産管理、情報システムの真の仕
事といえると思います。
改善に向かうように、仕事の仕組みを考え、旗を振るのは生産管理の も重要な仕事と言えるでしょう。
情報システム関係部署は、上記の内容をコンピュータシステム上からサポートして、各走者(営業、設計、調達、
製造)が気持ちよく走れるようにする、いわば脇役ですが、各走者の性格、人柄、特徴を十分に理解していなけ
れば、実効を挙げるシステムとはなりません。
それぞれの部署の仕事の仕組みを生管と同レベルで理解し、どうしたら、各部署が楽に走れるか、早く走れるか
を考え、常にどうしたら仕事の仕組みを改善できるか、問題意識を持つ事が必要です。
「言われたスペックのものを作るからスペックをください」と言う姿勢ではなく、「どうしたら仕事がより良くなるか」と
考え、自らが近い将来、その仕事を担当する時、どういうシステムが欲しいか、と考え、そのシステムを使う部署と
共に考えることが重要です。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
41
リードタイムに関する生管の定常業務としては次のようなものがあげられます。
いずれも上記の如く、コーチ、もしくは応援団、旗振り役としての機能が期待されています。
・内外製選定
あるカテゴリーは内製、あるものは外注とおおよそこれまでの経緯から決まっていますが、負荷の状況から、
内外製をバランスよくとることが必要です。
負荷変動時の考え方として、外注には出来るだけ一定の量を振り分けるべきで、変動への対処は内製で取る
べきでしょう。
製造部門は出来るだけ一定の量を確保して、変動部分は外注に調整してもらいたいと考えています。
また製作数の多い部品を加工したがるものです。その方が自分達の仕事が安定し、能率上好都合だからです。
生管計画者もまた、自社の業績を考えると自分達の仕事量は確保し、効率の良い仕事を自社に振り向けようとし
ますが、本当にそれで良いのでしょうか。
しかしながら、外注先の方が企業規模が小さく、変動に対する体力が納入先に比べ、弱いのが一般的です。
さらに大きな景気変動が起きた時に、訓練も無しに対応できるのでしょうか。
技術上の観点からは
①製品の特徴から技術上のコアコンピタンスとなる部品、②新技術を織り込む必要のある部品、③製品が複雑で
技術力がないと製作できない部品、④製作納期(リードタイム)が長く、調達のネックとなる部品、⑤部品の品質が
製品の品質を決定付ける部品、⑥種類が多く内製で打ち分けた方が良い部品
等はできるだけ内製とすべきでしょう。
・日程管理、進行管理(各工程の初めと終わりの定義とその管理)
それぞれの部門内の細部日程は各部門に任せておいても良いのですが、部門間の引渡しとなる期日(バトン
受け渡し時)は生管がコントロールする必要があります。
各部門は定められた引渡し日に、情報や物を後工程に責任を持って引き渡さなくてはいけません。
生管には、その引渡しを行なう期日を設定し、引渡しが予定通り、確実に行なわれたかどうかをチェックし、部門
の評価をする義務があります。予定通りでない部分があれば、責任の所在を明確にし、再日程を組み、更にその
原因の再発防止を行なう仕事の仕組みを作る必要があります。
具体的には仕様書発行管理、出図管理、仕様書発行管理、出図管理、集合日管理、社内検査合格日管理、
顧客検収日管理等がそれに当たります。
また、各部門が自分の工程を実践中に、前工程からの情報変更や、後工程からの変更依頼等その期日遵守の
阻害要因が発生します。仕様変更、設計変更はその代表ともいえるものです。
これらは全て、図面情報からのやり直しとなり、その規模が大きくなれば、時には上記引渡し日の変更を余儀なく
される場合もあります。
これには複数部門の調整が必要で、その調整役は生管であり、際日程の設定が必要な場合はその再日程計画
をオーソライズする必要があります。これらの調整業務を設変調整と呼びます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
42
・推進会議体の組織化と運営
例えば、
自動車のモデルチェンジは同時に数多くのプロジェクトが並行して進行しています。
プロジェクトの推進会議体として新車進行会議が回/月があり、原価管理も含めて、進行管理を行なっています。
生産管理部が主催し、副社長以下各部門の役員、部長が出席します。
夫々のプロジェクとの新車発売日程を遵守するために、その準備段階でのマイルストーンを決め、その時点で、
どのような状態になっているかをフォローし、今後の実行計画を審議する場となっています。
日程の微調整を行なわなければならないか、挽回するために何を行なうかを決定します。
同時に、競合他社の車や自社の他のプロジェクトを含めた徹底的な比較を行い(ベンチマーク)、目標値の変更
や日程の早だしを検討します。
・プロジェクト評価(リードタイム)
プロジェクとの規模により、標準日程が設定されていますが、各部門は常に新しい試みにより、リードタイム短縮の
挑戦をし続けています。
短縮された日程は生管が各部門との入念な打ち合わせと根回しを行なった結果、新車進行会議にてオーソライ
ズされます。
一度日程を切り下げ、何とかやれたとなると、よほどの事情がない限り、同一規模のプロジェクトは、それ以上
長い日程では組まれることは決してありません。
初は挑戦でも、次回からは標準となってしまうのです。
個別受注型の組立産業ではこの新車開発過程が製品製作過程とみなすことができます。
ざっと書きましたが、皆さんの会社の生管は十分な機能を果たしているでしょうか?

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
43
3.製造現場における改善手法
前項では、リードタイム短縮のために全社の各部署における果たすべき役割について記述しましたが、
ここでは主に製造現場におけるリードタイム短縮のために必要ないくつかの手法について
学んで行きたいと思います。必ず自分の職場で自由に使えるようになってください。
3.1.ものと情報の流れ図
3.1.1 ものと情報の流れ図の役目
ものと情報の流れ図は、TPS で用いられる手法の一つですが、
基本は、自工程の改善を行なう時に、自工程だけでなく、自工程の前後工程までを含めた一連のものの流れを、
情報の流れを含めて、一枚のマップに書き上げ、
全体の流れを把握したうえで、この系の全体 適を求める改善を進めるための道具であるといえます。
自分の工程の改善を行なう際に、近視眼的に自分の工程のみを見て改善するだけでなく、
広く前後工程を見て、
・どのようにして、後工程に喜ばれる供給が出来るのか、
・どのように前工程に要求すれば、全体の系(サプライチェーン)がよりよいものになるのか、
その系を考える人たちの共通言語として、必要となってきます。
先にも述べたように、リードタイムの悪化は、情報のロットサイズや、工程間在庫の停滞が大きな要因となっている
場合が多く、加工時間そのものの寄与度は少ない場合が大半であり、
反対に言えばそこにリードタイム短縮のネタが隠れています。
くどくど説明するよりも「ものと情報の流れ図」とはどんなものなのか一度見てみましょう。
3.1.2 具体的作成例と意味(米人の書いたものと情報の流れ図 :次ページ図 1 参照)
次ページ図 1 の例(「トヨタ生産方式にもとづくものと情報の流れ図で、現場の見方を変えよう」より引用)では
物の流れをゼブラ線と二本線(外部への物流)で、
情報の流れを実線で書き(紙ベースは直線、通信ベースは稲妻線)、
三角は工程間在庫、四角を工程で表しています。
四角の中の記述はノートと呼ばれるもので、
一般には、タクト、サイクル、段取り時間、可動率、稼働時間等の情報が書き込まれる。
なお図中バッチサイズとはロットサイズのことである。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
44
この図をどのように描くかは、改善ターゲットをどの範囲にするかで決まります。
ここでは、表皮の裁断から始まって表皮を完成し、自社B工場のシートベースを受け入れて、
製品(椅子)を完成、出荷までの工程の改善を扱っているといえるでしょう。
外注からは、シート表皮の生地が入荷されると思われます。
この記述内容を見て、実際の工程内容を理解できれば、工程改善の方向性が見えてきます。
図 1、ものと情報の流れ図
3.1.3 顧客の要求を満足するには
初は顧客の要望を整理するところから始まります。
ここでは後工程は流通センターであり、流通センターのほしいものを、ほしい時に、ほしい量だけお届けすればよい
のです。それ以上でも、それ以下でもいけません。
自工程の生産スピードの基盤となるものです。しっかり調査しましょう。
流通センターは2種類の椅子 D タイプと T タイプを週に 500 個づつ計 1000 個毎日供給してほしいとしています。
この顧客の要望に対し、自分の工程の能力が、同期させて必要なものを、必要なだけ作る能力があるのか、
もしくは過剰に作れる能力なのか調べなければなりません。
自社 A 工場
自社 B 工場
(3)

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
45
しかし、この記述では、月~金曜日の 5 日なのか、月~日曜日の 7 日なのか良く分かりません。
明確にする必要があります。
また対象工場 A の稼動が月~金曜日なのか、1 シフトなのか 2 シフトなのかも不明確です。
もう少し詳しく調べて書く必要があります。
なぜなら、その状況により、 適なオペレイションに大きな差異を生じる可能性があるからです。
ここでは調べた結果、流通センターの受け入れは月~金の 8 時から 5 時までで、工場 A の稼働時間と同じである
ことや、椅子の置き場は非常に狭く、いつもスペースを確保するために、置き場の移動を頻繁にやっていることも
わかりました。
現状用いているトラックにはこの椅子は 50 脚はいります。
このように物の流れのスピードに関する内容を調査、記述しておきます。
3.1.4 自社 A 工場のものの流れ
初は物の流れから見ていきましょう。
不十分な記述ですが、この記述から自社 A 工場のものの流れを推測してみましょう。
工程は
の 4 工程で、工程のブロックの上部に書かれています。
その工程の枠の中の下方に書かれている はその工程に従事している作業者を表しており、
例えば 縫製工程では 3 人の人間が従事していることが分かります。
工程枠と工程枠の間には、物の流れを示すゼブラ線とともに△一日と書かれています。
裁断工程完了品の在庫量が一日分あるという意味になり、それぞれの工程完了品は大量の工程間在庫を持って
運営されている様子が分かります。
その下のブロックは各工程のノートと呼ばれるもので、物の流れに対する重要な情報に関する調査結果が書かれて
いますが、この記述ではまったく不足しています。
更に書いてある内容を見てみましょう。
裁断工程は布地を切る裁断機の段取り時間が長く掛かるため、60 反のバッジ生産を行なっています。
ここでは、この 60 反が D タイプ、T タイプ何脚分に相当するのかこの記述では分かりませんが、
本来は、明確に記述されなければなりません。
また、段取り時間が 20分とかかれているだけで、60反が何脚分に相当するのか、段取り完了後どの程度のスピード
で物が流れてくるのか、まったく調べられていません。
裁断 縫製 布張り 終組付

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
46
次に縫製工程を見てみましょう。
この記述からは、ラインで縫製部位を分担して流しているのか、セルで独自に全縫製を完結するセル方式で
行なっているのか、不明確です。更にトータルサイクルタイムという聞きなれない言葉を使っており、
何秒で一個出来上がってくるのか、よく分からない表現となっています。
これでは改善の方向が見えてきません。
なぜでしょうか。
明白です。顧客のほしいものをほしいスピードで作ることが重要なのに、現状各工程は、どのようなスピードで
作っているか、この記述では見えてこないのですから、どこをどう改善すればいいのか分かるはずはありません。
3.1.5 工場の椅子を作るスピード(タクトタイム)
この顧客は、どのようなスピードでものを供給してもらいたいのでしょうか。
それにこたえるために生産サイドは、どのようなスピードで、物を作ればよいのでしょうか。
くどいようですがあくまでも顧客である流通センターの「ほしいものを、ほしい時に、ほしい量だけ」の観点から
考えます。
顧客である流通センターの要望にこたえるためには
タクトタイム = 稼働時間×(可動率)/必要個数 = 8H×5/1000 = 144 sec (可動率 100%として)
で供給すればよいことになります。
出来た製品が 100%良品で、スムースに生産が進めば、その同一スピードで物を作ればよいことになります。
現実的には、可動率を加味しておおよそ 150 sec に一個作るすなわち「二分半で一個作れば良い」ということに
なります。
それに対して能力が余っている工程はリソーセスを削減したり、不足している工程は機械や人の能力を上げる努力
をする必要があります。
3.1.6 各工程の分析
必要タクトに対して A 工場の各工程の生産はどのようになっているのでしょう。
工程は全部で 4 工程あり、ノート(ブルー線で囲まれたゾーン)に観測結果が書かれていますが、
記述内容が不足しており、全工程間に中間在庫が存在し、物の流れが停滞している状況がわかりますが、
このままでは何をどう改善すればよいのか、良く分かりません。
一度そのような眼で、各工程の能力を調べて見ましょう。
そのために調べるべき項目は何でしょう。
供給するスピードと作るスピードが、同一であることが、必要な要件であることがわかりました。
一個作るのにどれだけの時間がかかるのか、それを「タクトタイム」といいます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
47
タクトタイムに余裕率を掛けたものをサイクルタイムとして設定して、生産のスピードとして工程の設定をします。
その工程の実力により余裕率は異なりますが、安定した工程なら 95%程度に設定してよいでしょう。
ちなみにトヨタの車体溶接工場での可動率は 95%、余裕率は 1 として工程の設計を行い、生産計画も管理水準も
この数字で行っています。
同様に考えると、ここでのサイクルタイムはいくつに設定すべきでしょうか。ただし、可動率は 90%とします。
タクトタイム = 純稼働時間 / 必要個数
純稼働時間=稼働時間×可動率-段取り時間
サイクルタイム = タクトタイム / 余裕率
このように、サイクルタイムを出すためには、必要個数だけでなく、稼働時間、可動率、段取り時間、等の情報が
不可欠ですが、ここでは調べられていません。
縫製のノートには、「トータルサイクルタイム=150 秒、段取り時間 2 分」だけしかなく、
これでは必要サイクルタイムを算出することは出来ません。
サイクルタイムを正しく、明確にしなければ、今後の改善はいい加減なものになってしまいます。
ラインのサイクルタイムが算出されたら、
各工程のサイクルタイム、可動率、段取り時間、段取り頻度、部品の収容状況、部品の工程間移動のタイミング、
工程間在庫、生産指示方法、基準工数等、可動に影響する要素を観測し、記録しておくことが重要です。
3.1.4 で前述されていた『ノート』の作成が改善のヒントを与えてくれます。
ただし注意しなければならないのは、この例では一種類ですが、ラインでは一般に多くの種類の部品が混在され
て流すことが一般的です。
したがって、部品によってこの数字が一部異なる場合が多く、カテゴリー分類し、生産量が極端に少ないものを
除いて、全てのカテゴリーについて調査する必要があります。
3.1.7 例題前半
ここまでやってきたことを例題でやって見ましょう。自分で出来なければ意味がありません。
演習に用いる例題はこの章の末尾にあります。
3.1.8 自社他工程からの部品供給
前項までで、自工程の確認は終わりました
ここでは自社 B 工場から椅子のベースとなるフレームとフォームの組みつけられた、いわゆる椅子の躯体が
組みつけられた状態で、送られてきます。
それをこの図では分かりませんが、何処かに 4 日分の中間在庫をもって A 工場に供給されています。
それが自分の工程と同期して送られてくることが必要です。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
48
同期とは、自分の工程で、椅子のカバーが作られる順序とスピードが一致していることで、
その間に予期せぬ交通渋滞や生産ストップによる欠品に起因する供給停止に対する 小限の安全在庫を確保し
ておくことです。
天災や交通事故などの大きなラインストップを恐れて、大量の在庫を持つ必要はありません。
それによる損失は、きっぱりとあきらめることが肝心で、起きたら 善の努力をしてリカバリーし、
常日頃の工程間在庫を低減することを優先します。
種類が少ない場合は、在庫補充のかんばんでも良いのですが、この送られてくる躯体の種類が多い時は
それぞれの種類毎に在庫を持つ必要があり、各種類ごとに 低限の在庫を持つとしても、全体として大量の在庫に
なってしまいます。
また、同期して送られてこないと、種類ごとに余分な在庫が必要となってきます。
同期してとなると、「A 工場と B 工場間の情報をどのように行なうか」が重要になってきますが、
ここでは何も記述されていません。
この情報のやりとりは、生産管理などのコントロールセンターから双方に向かって発信されるべきではなく、
相互間でリアルタイムに交わされるもので無ければなりません。
なぜなら生産現場は生き物で、刻々事態が変化するからで、中央管制では刻々変化する状況をフォローして、
瞬時に行なう計画変更や、双方向のやり取りに仲介する必要は無く、相互に自立的に行なえる仕事の仕組みが
重要になってきます。
中央管制は各オペレイションの状況が的確に把握できれば良いのであり、その情報を基に
次の行動計画を適切に作ることであり、現在の仕事をどうするかは、関係するオペレイションユニットが自律的に
必要な情報を取り合い、対処する仕組みのほうが、より変動に対応しやすいといえます。
3.1.9 他社からの購入部品や自工程の原材料の供給
これも他工場からの部品の供給と同様で、できるだけ小刻みに供給されることが重要です。
大物で種類の多い時には、外注からは
『順立て(部品を自分のラインで組み付ける順番に整列された状態にすること、たとえば車におけるシートなど)』で
納入させることもあります。
粗形材の材料(鋼材や、鋳物、鍛造品など)はどうしてもロット単位が大きくなりがちなので、注意を要します。
3.1.10 部品の種類とその並びの一致
A 工場の躯体の生産スピードと縫製された表皮の生産スピードが一致する必要は良く分かりました。
どちらかが早く作られれば、布張りの工程でただ待つことになり、結局遅いほうのスピードでしか
布張りした椅子は出来上がらないことになります。
しかし、ここで考慮しなければならない重要なことがもうひとつあります。
スピードが同じだけでは不十分なのです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
49
2 つの工程から作り出されてくる部品が、その製品が必要とするものでなければ、
いくら作るスピードが同じであってもまったく意味のないことになってしまいます。
つまり、出来上がってくる部品の順番が大きな意味を持つことになります。
たとえば布張りの工程で、本当は背もたれの大きな躯体が供給された時に、本来、緑の縫製されたカバーが
取り付けられなければならないのに、黄色のカバーが順番で送られて来たらどうでしょう。
この椅子は布張りできません。誤った種類の椅子を作ってしまいます。
このように部品の種類が、いくつもあり、その組み合わせで、製品が成り立っている場合が大半ですから
いくつかの部品を組みつけて行く複雑な製品の場合、組み立てることは出来ないことになるからです。
3.1.11 生産指示情報の伝達
物の流れの調査に続いて情報の流れを整理、記述する必要があります。
この例では実線の矢印で書かれています。電送の場合は稲妻線になっています。
欠かれるべき情報は以下の 3 項目です。
ⅰ)顧客からの納品指示
顧客から、何をいつ、どれだけ、どういう順序で、どこに製品を届ければよいのか
その情報はいつ、どのような頻度で、どういう方法(情報媒体)で、
ⅱ)仕掛指示
各工程がいつ、何を、どれだけ、作り始めるかを、
その情報はいつ発信されるのか、どういう方法(情報媒体)で、
ⅲ)原材料、部品の発注
仕入先に対する、何をいつ、どれだけ、どういう順序で、どこに原材料や部品を届ければよいのか
3.1.12 店からの情報による後補充
生産順序として「一個流し」が基本ですが、
前工程がロット生産を余儀なくされる時や、距離的に離れている場合、
仕掛け指示の方法として用いられるのが「かんばん」です。
図 2 の改善結果と図 1 の現状を比較してみてください。
図 1 では生産管理部から各工程にパラレルにダイレクトオーダーがなされています。
これだと前工程は何を作ればよいのか 初から分かっているので、後工程の進捗とは無関係に生産を続けること
になり、同期の取れた生産が出来ません。結果、後工程の前には膨大な工程間在庫が溜まることになります。
改善結果では、生産管理部より生産指示されるのはペースメーカーの裁断工程だけで、後は全て、店を持ち
種類ごとに並べ、売れたものから「かんばん」をはずし、前工程に生産指示を行なっています。
この方法によって、自動的に前工程の進捗が後工程の進捗に同期化された状態を作り出します。
生産管理部は、顧客からの製品の納入順序どおりの並びで裁断工程に生産指示するだけで、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
50
裁断工程と出荷状況を把握していれば、顧客に納入保証可能となります。
また、材料メーカへの発注や納入指示も、材料につけられたかんばんを発注伝票の代替として使用すれば、
常にある一定の在庫量にコントロール可能となり、在庫を確認する必要はなくなります。
3.1.13 例題後半
ここまでやってきたことを例題で前半に続けてやって見ましょう。
ここでは①現状の追加分に加えて、②改善後のものと情報の流れ図を仕上げてください。
自分で出来なければ意味がありません。
3.1.14 改善後のものと情報の流れ図
改善後の「ものと情報の流れ図」の一例を図 2 に示します
ノートは全て書いてありませんが工程設計が大きく変わっているのが分かると思います。
もっとも重要なポイントは工程が大きく減り、また各工程の同期化が重要視されていることです。
必要量にあわせてペースメーカー工程のタクトが設定され、
それに集まってくる前工程が、同期化されることによって工程間在庫が大幅に減って、リードタイムが短縮されてい
る様子が分かると思います。
図 2 改善後のものと情報の流れ図

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
51
3.1.15 改善の評価指標
後に
ものと情報の流れ図を用いて改善した時、改善の評価をどう見るかについて評価指標を考えて見ましょう。
改善後に何人削減できたとか、工程間在庫が何日減ったというのは改善の結果の評価であり、
リードタイムに対する評価ではありません。
では、リードタイムの評価としてみるときはどうすればよいのか、というと
オーダーデリバリーのリードタイムはお客からオーダーを受けてから届くまでの時間ですが
製造現場から見ると、生産管理部が「作りなさい」と指示されてからどれだけの時間たたら製品が出てくるかが
その力を現すことになります。
物が出来てくるまでの時間はその加工法が複雑で多岐にまたがる場合もあれば、
簡単にワンショットで出来る場合もあり、絶対値での比較がその改善の大きさを表すのが難しい場合があります。
ここでは、各工程で 1 個作るために必要な時間を ti とした時 その総和Σti と、
ある一個の製品がしかかり始めてから完成品として出てくるまでのもっとも長い時間 Lmax の比で表すことにします。
Lmax はその加工ロットサイズ、工程間在庫によって左右され、実加工時間はきわめて短いものであると同時に
実加工時間の削減には大きなコストがかかるものである割には、オーダーデリバリーのリードタイムの短縮に大きく
寄与しない場合が多いものです。
製造現場の作り方の工夫によってリードタイムの短縮には Σti /Lmax をとるのが良いのですが、
これでは 0.0003 とか、小数点以下となって見にくいので、その逆数を取って評価する方法をとっています。
図 3 における階段上の線の下段が実加工時間 Lmax、上段がΣti となっています。
加工時間比率=23.6x8x3600/188=3615
図 3 リードタイム改善の評価尺度

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
52
3.1.14 ものと情報の流れ図 演習例題
アクメスタンピング(株)調査結果
1.前提条件
アクメスタンピングは自動車組み立て工場向けに複数の部品を作っているが、その納入実績(納期)の改善を、
顧客のステートストリート組立工場から要求されているだけでなく、原価の引き下げをも要求され、窮地に立って
いる。
工程調査を行い、「物と情報の流れ図」を道具に使って、改善し、この会社の窮地を救ってください。
2.調査結果
①生産品目
アクメでは自動車のインストルメントを補強し、様々な
樹脂部品を取り付けるためのブラケットを製作している。
ブラケット完成品は右ハンドル用と左ハンドル用の 2 種類
があり、中央のベースとなる部品は内製であり、
2000t トランスファプレスにより 加工される。
ベースとなる部品は前後2部品で構成されており、断面
が半円状をしており、小物部品を取り付けるベースとなっ
ている。この 2 部品とも右ハンドル用と左ハンドル用があ
る。
小物部品は、スポット溶接で、ベース部品に接合されている。
下図の溶接ガンを組み付けた、マルチ
スポット溶接機によって、挟み込んで、
高電流を流す事によって接合するため、
断面が閉じていては溶接ができない。
従って、ベース部品に小物部品を組み
つけてから、二つをあわせて、溶接する
順序作業となっている。
小物部品は外注となっており、
月度生産計画に基づき、前週に本今週
の生産分を
発注し、月曜に5日分納入される。
小物部品をスポット溶接された半完成品は、その後
組み付け工程でボルト締めの小物部品を取り付けたり、
前後の結合の組立工程を経て、製品完成品となる。
インパネブラケット
プレス機械

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
53
②顧客
ⅰ)立地
顧客のステートストリート組立工場は隣県に立地し、40km 離れている。
渋滞は殆ど無く、トラックは平均時速40km で走る。アクメでの荷積み、顧客での荷卸には夫々20 分かかる。
ⅱ)勤務形態
昼夜 2 シフト,8:00~5:00,21:00~6:00(内昼休み時間 1 時間、シフトに 1 回 10 分のホットタイム)
20 日/月
ⅲ)要求製品数量
18,400 個/月 右ハンドル用(RH)12,000 個/月 左ハンドル用(LH)6,400 個/月
ⅳ)製品収容状態
鉄製通い箱 右、左ハンドル用共用、収容数 10 個/箱 寸法 L:1200 ㎜ X D:800 ㎜ X H:1400 ㎜
ⅴ)納入トラック
・納入トラックの荷台は 2400X7000X2200、積載率は 大 80%
・製品積載状況は容積勝ちで、重すぎて、積めないということは無い。
ⅵ)その他受け入れ制約
・受け入れターミナルは余裕あり、何時納入しても可。
・納入トラックサイズも制限なし
ⅶ)アクメへの生産情報供与
・前月 20 日に、当月 1 日からの 30/60/90 日の生産計画フォーキャストを電送。
③材料供給メーカー
・ベース部品を含めて、アクメスタンピングのプレスに使用するコイルは 200km 離れたミシガン鉄鋼より
毎週火、木曜納入される。
④アクメ稼動状況
ⅰ)稼働時間
・20 日/月
・全ての生産部門が昼夜 2 シフト
・8 時間/シフトで、必要に応じて残業
⑤アクメの生産工程
ⅰ)アクメのこの製品ファミリーの生産工程は金属部品のプレス(スタンピング)、溶接(ウエルディング)、
組立(アッセンブリ)の順で、完成品は日次でステートストリート組立工場へ積載、運搬される。
ⅱ)スタンピング
・ インパネブラケットだけでなく、アクメの他の製品に多くの部品を供給する。
・ 2000 トン(t)トランスファプレス、コイルは自動投入
・ サイクルタイム:一秒(60 個/分)

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
54
・ 段取時間 1 時間/回
・ 可動率:85%
・ 在庫状況 材料在庫:コイル 5 日分、 工程完了在庫:フロント、リアとも、RH 4600 個、LH 2400 個
ⅲ)溶接第一
・ インパネブラケット専用工程
・ 人―機械工程 作業者 1 名
・ サイクルタイム:39 秒
・ 段取時間:10 分 治具部の交換
・ 可動率 100%
・ 在庫状況 工程完了在庫 RH 1,100 個、LH 600 個
ⅳ)溶接第二
・ インパネブラケット専用工程
・ 人―機械工程 作業者 1 名
・ サイクルタイム:46 秒
・ 段取時間:10 分 治具部の交換
・ 可動率 80%
・ 在庫状況 工程完了在庫 RH 1,600 個、LH 850 個
ⅴ)組立第一
・ インパネブラケット専用工程
・ 人―機械工程 作業者 1 名
・ サイクルタイム:46 秒
・ 段取時間:10 分 治具部の交換
・ 可動率 80%
・ 在庫状況 工程完了在庫 RH 1,600 個、LH 850 個
ⅵ)組立第二
・ インパネブラケット専用工程
・ 人―機械工程 作業者 1 名
・ サイクルタイム:46 秒
・ 段取時間:10 分 治具部の交換
・ 可動率 80%
・ 在庫状況 完成品在庫 RH 2,700 個、LH 1,440 個
ⅶ)出荷
・ 完成品倉庫から製品を出し、顧客への出荷のため積載する

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
55
⑥アクメの生産管理と情報伝達
ⅰ) ステートストリートからのフォーキャストを MRP に入力
ⅱ) MRP を使ってミシガン鉄鋼に対し、6 週間のフォーキャストを出す。
ⅲ) FAX にて翌週の注文を出し、ミシガン鉄鋼に納入させる。
ⅳ) ステートストリートから日次の確定オーダーを一週前に受け取る。
ⅴ) 顧客オーダー/仕掛け数量/完成品在庫/予定直行率に基づいて MRP ベースの部品ごとの週次所要を
算出する。
ⅵ)スタンピング、溶接(#1,#2)、組立(#1,#2)の各工程に対して週次計画を発行する。
ⅶ)出荷部門に対して、日次の出荷計画を発行し、それに従い出荷する。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
56
3.1.15 ものと情報の流れ図 演習例題 宿題
次の調査結果を基に、課題に答えなさい。
TWI 工業
概況
TWI 工業は、いくつかのトラクター用部品をつくっている.
本ケースでは 1 つの製品フアミリーを対象とする。対象商品フアミリーはステアリングアームで、
部品構成多様である.
TWI のこの製品フアミリーの顧客は特定仕様のトラクターメーカー(いわゆる特機メーカー)と修理ビジネス
の両方である.
製品構成が多様であり、顧客からの構成要求がオーダー毎に異なるため、
ステアリングアームは「受注生産」事業になっている.
現在顧客のオーダーは 27 日かかって、TWI のすべての生産工程を通過する。
この永いリードタイムと大量の受注残の影響で、TWI は顧客に対して 60 日の長いリードタイムを
提示している。
しかしながら、TWI の顧客は 2 週間以上先の所要量は正確には予測できないので、
出荷の 2 週間前に注文を調整する。
この注文の調整が結果として TWI の「混乱」につながっている。
TWI の生産管理課が顧客オーダーを受注した順序に、ほぼ忠実に製造現場にリリースしている
にもかかわらず、製造現場ではオーダーを製品構成毎にバッジにし、
時間のかかる段取り替えの回数を減らしている。
これもまた「混乱」のもとになる。
製品
・ ステアリングアームはその両端に鍛造部品が溶接された金属の棒
・ TWI のステアリングアームには長さで 20 種類、直径で 2 種類、溶接される部品が 3 種類ある。
(両端には別々の部品を溶接することが出来る。)
つまり TWI が供給するステアリングアームの型番は 240 種類ある。(20x2x3!)

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
57
顧客の要求
・一ヶ月 24,000 個
・注文数の範囲は 25 個~200 個で、平均 50 個
・段ボール箱で納入 5 個/箱
・さまざまな顧客に対する出荷が何便かある。
・おのおのの顧客が要求する製品の構成はオーダー毎にまったく異なる。
・TWI は出荷の 60 日前にオーダーが届くよう求めている。
・顧客はしばしば出荷日の 2 週間前に所要量を調整する。
稼働時間
・月 20 日稼動
・全工程 2 シフト
・8 時間/シフト 必要に応じて残業
・休憩 15 分 x 2 回 /シフト
・人手作業は休憩時間中は止まる。
・昼食時は無給
TWI 生産管理課
・顧客オーダーを 60 日前に受け取り、MRP に入力する。
・顧客オーダー毎に「ショップ・オーダー」を生成する。
・ショップ・オーダーを出荷の 6 週間前に製造へリリースし、棒材と鍛造部品の MRP 調達を開始。
・毎日優先順位リストを製造の主任達に対して発行する。主任たちは自部門を通るショップ・オーダーを、
このリスト に従ってソートする。
・顧客のサイズ変更を 2 週間前に受け取り、主任たちに対して当該オーダーに合わせるように
アドバイスする。
・出荷部門に日時の出荷計画を発行する。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
58
生産工程(右下図参照)
・ステアリングアームの製品ファミリーに対する TWI の工程には金属棒材の切断、 両端への部品の溶接、
仕上げ(余分な溶接くずの除去)、協力工場での塗装、先端部組立がある。
両端につける鍛造部品の接合部も TWI で、機械加工される。
完成したステアリングアームは積載され、日時ベースで顧客に出荷される。
・棒の長さの変更には切断、溶接、仕上げの各工程で 15 分の段取り時間を要する。
・棒の直径の変更には、切断、溶接、仕上げの各工程
で、1 時間の段取り時間を要する。
直径の変更に必要な段取り時間のほうが長いのは、
主として品質管理部からの検査要求の増加のため。
・3 種の溶接部品の変更には加工工程で
2 時間の段取り 時間を要する。
・金属棒材はミシガン鉄鋼から供給される。
棒材の調達リードタイムは 16 週、月 2 回納入。
・両端につける鍛造部品はインディアナ工業から供給
される。
鍛造部品の調達リードタイムは 12 週、月 2 回納入。
製造工程情報
1.切断(非専用:多くの TWI の製品向けに鋸で棒材を切る)
・人手作業 一人
・サイクルタイム 15 秒
・段取り時間 長さの変更 15 分 、直径の変更 1 時間
・可動率 100%
・観察されるたな卸し
切断前の棒材 20 日分
切断した棒 5 日分

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
59
2.溶接#1(本製品ファミリー専用)
・加工された鍛造部品の 1 個目を棒の一端に溶接
・自動化工程 マシンサイクル外に人手による着脱
・サイクルタイム:人手の部分 10 秒、機械加工 30 秒
・段取り時間 長さの変更 15 分、 直径の変更 1 時間
・可動率 90%
・観測されるたな卸し:溶接済みアーム 3 日分
3.溶接#2(本製品ファミリー専用)
・加工された鍛造部品の 2 個目を棒のもう一方の端に溶接
・自動化工程 マシンサイクル外に人手による着脱
・サイクルタイム:人手の部分 10 秒、機械加工 30 秒
・段取り時間 長さの変更 15 分、 直径の変更 1 時間
・可動率 80%
・観測されるたな卸し:溶接済みアーム 3 日分
4.仕上げ(本製品ファミリー専用)
・自動化工程 マシンサイクル外に人手による着脱
・サイクルタイム:人手の部分 10 秒、機械加工 30 秒
・段取り時間 長さの変更 15 分、 直径の変更 1 時間
・可動率 100%
・観測されるたな卸し:仕上げ済みアーム 5 日分
5.塗装(外注)
・塗装リードタイム=2 日
・トラック 1 日 1 便 塗装完了品を納入し、塗装前部品を持っていく。
・観測されるたな卸し:塗装工場に 2 日分、 塗装済みのアーム TWI に 6 日分
6.先端部組み付け(本製品ファミリー専用)
・人手作業 6 人
・総作業時間/個 : 195 秒
・段取り時間 : フィクスチャー交換に 10 分
・可動率 100%
・観測されるたな卸し(倉庫にある完成品) 4 日分

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
60
7.鍛造部品の加工(本製品ファミリー専用)
・自動機 1 台 マシン担当 1 人
・サイクルタイム:30 秒
・段取り時間 : 2 時間
・可動率 100%
・観測されるたな卸し
サプライヤーから納品された鍛造部品 20 日分
加工済み鍛造部品 4 日分
8.出荷部門
・製造倉庫から完成品を出し、顧客へ出荷するトラックへ載せる。
課題
以上の情報を基に
(1)現状と改善後のものと情報の流れ図を書き、
(2)評価尺度を設定し、
(3)改善案を整理し、
(4)改善前後の評価尺度を比較せよ。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
61
3.2 製品ファミリーの分析
3-2-1 分析の必要性
先ほどの例でお分かりのように、同期生産を行なうためにはサイクルタイムが一致しているだけでは不十分で、
そのものの種類と順番が一致していることが必要なことが理解できました。
いくらスピードが一致していても、その種類の並びが一致していなければ、まったく意味が無いことがお分かりに
なりましたか。
多様化の時代になり、皆さんの改善しようとする職場にはさまざまな部品が流れてきます。
中種中量のライン生産工程では、ある工程は共通で通り、他の工程はその部品単独での加工が必要な場合も
あります。
同じ工程を通る場合でも、MC(マシニングセンター)では加工物の種類により、
・加工のサイクルタイムが大幅に違う場合もあり、
・更には、部品は原材料である粗形材の形状や材質も異なれば、表面処理、熱処理が異なる場合もあれば、
・標準のものとは若干違うものや追加工のあるものもあるかもしれません。
スタンダローンのセル方式とは異なり、中種中量のライン生産を行なう、それら全ての製品に対し、どう加工するかを
全体 適の考えから意思決定しなければ、システム全体の改善は出来ないと考えられます。
そのために、その工程で加工する製品ファミリーの分析が必要になってきます。
その工程を経て完成される製品、もしくは部品にはどんなものがあり、どのような属性を持ち、
どんな状況になっているのか、熟知していなければ、改善は出来ません。
ひとつの製品だけ改善しても、全体のバランスが悪く、改悪になってしまうこともあります。
では何がどう分かればよいのかを少し考えて見ましょう。
3-2-2 物の名前と品番、型式
製品や部品には必ず名前がついていますが、情報として取り扱うために、名前とは別に品番がついています。
名前では細かいところまで、分類できなくても、品番であれば、容易に特定できます
品番の付与方法は各組織体によってまちまちですが、それぞれの桁の具体的な数字は全て意味を持っています。
言い換えれば、製品の製作工程との関係で、「ある一定の決まり」に基づいて設定されているということになります。
まずは、その付与方法の「決まりごと」を理解するところから始まります。
決まりごとが理解されると、まるっきり始めての製品でも、おおよそのことが分かります。
具体的に言うと、
カローラのプレス品の車の屋根の部分は 63111-12020 と付与され、その補強部材のレインホースは 63115-12030
ビッツの屋根は 63111-12050 というようになっています。
6 は板金部品のアッパー、3 はその中でも屋根に近い所、11 は もメインになる部品、120 は小型車、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
62
後の 20 はカローラの号口となります。(現在は変わっているかもしれません。)
完成された時は一般に「型式+オプション」となり、カタログに載せられますが、その前の自社の製作工程や、
部品メーカーでは品番がその部品のデータ上の名前となります。
3-2-3 製品品番、部品品番、工程品番
(ⅰ)製品品番とはその製品が商品として、顧客に届けられる時の品番であり、その組織体において異なる品番が
付与される場合があり情報の伝達時に考慮する必要があります。
たとえばAという組織体が自分の製品の一部の部品としてXをBという組織体から購入する場合、
XをAではX1と呼び、BではX2と呼ぶ場合があります。
なかなか統一することが出来ず、問題となることが多いのですが、部品を商品とする企業体では統一することが
必要と考えられます。
(ⅱ)部品品番は同一組織体で製品の一部として使用する部品の名前として用いられます。
購買部品の場合はサブアッセンブリー名として品番が付与されますが、内製で組みつけられる場合は
層別に分類された部品表に工程符号がかかれ、どのような工程を経てその部品がくみ上げられていくのか
分かるような表現で表されています。
(ⅲ)工程品番
ライン形態で物が作られる場合や熱処理や表面処理等形状が殆ど変わらない場合、工程品番を付与する場合が
あります。
たとえば 5 工程で加工完了する場合、各工程(たとえば 3 工程、4 工程)完了品に品番を付与する場合です。
あるいは機械加工の原材料である鋳物や鍛造品などの素形材等に部品品番ではなく、工程品番として
設定する場合もあります。 図 4 カテゴリー分類
3-2-4 工程分析をする場合の部品分類の観点
ひとつの工程で数多くの品番を加工組付けする場合、ひとつだけの
部品の調査結果に基づいて、改善したのでは全体としてアンバランス
な工程となってしまいます。
かといって全部品を観測、調査するのではいくら時間があっても
足りません。先に述べたように、ひとつの工程でさまざまな部品を加工
しているラインを工程改善する場合、下記に述べるような観点から、
まとめて考えることにしましょう。
整理して似たようなものはひとつとしてくくって考え、いくつかのグループ
として考えるのです。
たとえば、右図の 1 から 20 までの 20 ある品番を整理すると
A から E の 5 つに分類され、代表品番 5 つの品番について調査、分析
品番 タイプ
1 A
2 B
3 B
4 C
5 A
6 D
7 B
8 E
9 A
10 C
11 B
12 D
13 C
14 D
15 A
16 B
17 A
18 B
19 E
20 A
タイプ 品番
1
5
9
15
17
20
2
3
7
11
16
18
4
10
13
6
12
14
8
19
D
E
A
B
C

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
63
することになります。
その時、どのようにグループ化するかは次の観点から考えます。
(ⅰ)品番別生産量
生産量の極端に少ないもの、過去あったが 近は殆ど無いものは抹消します。
少ないもので、(3)(4)(5)が他の量の多いものと近似の場合は親子関係として、親が代表します。
また、よく使われるものに PQ 線図と呼ばれるものがあります。
これは生産品日(Product)と生産量(Quantity)の関係をヒストグラムのような柱状図にまとめ,
各頂点を結んだ曲線により特性を把握す
る手法である。
また、カテゴリー分類する場合や、
ロットサイズやロット数を決める場合、
前述の親子決めなどにも有効です。
横軸に生産品目 縦軸に数量をとり,生産
量の も多い生産品目から順に記入して
行きます。
プロセス,材料 形状などが違う場合は,
すべて異なる品目として記入します。
図 5 PQ 線図の例
(ⅱ)品番による加工工程の違い
ある部品だけ、他の部品に無い工程を経て完成されるとか、工程をスキップして完成されるもの、
あるいはある工程だけ他の品番には無い特殊なものが追加組みつけられるもの。
(ⅲ)品番による加工工数、サイクルタイムの違い
加工工数が大きく異なり、基準時間が大きく異なったり、人員の増減が必要なものは分類して考える必要が
あります。
工程改善にはこの分類が特に重要です。
分類の際にはあまり細分化せず、少々の違いは無視し、同じカテゴリーにくくってよいと考えましょう。
少々とはサイクルタイムによりますが、一分以下のサイクルで無ければ 5%程度は問題無いと考えます。
工数については 0.2 人工程度は無視しても良いと思います。
(ⅳ)品番によるロットサイズの違い
ロット生産をしている場合、ある期間中のロット数を同じにして生産するのか、
a b c d e f g h i j
製品の種類
製品の量

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
64
ロットサイズを同じにして生産するのか、ロット数やロットサイズの大きさで分類する場合もあります。
この場合も(ⅲ)と同じように少々の違いは無視し、同一グループとしましょう。
(ⅴ)段取り替えが必要か、必要ないか
たとえば、製品 A から B に加工が移る場合は段取り替えが必要だが、
製品 A から C に移る場合は段取り替えが必要ない場合は、A と C は同一グループ、B は別グループとして
分類する場合もあります。
1~5 を整理して、目的に照らし合わせて、品番のカテゴライズ(グループ分け)を行ないます。
3-2-5 製品の分類 演習
それでは、テーマ実習の品番の整理をトライしてみてください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
65
3.3 ライン改善に良く使われる改善手法
3-3-1 ラインバランスとネック工程
ライン生産等の流れ生産を行なう場合、
重要な要素となるのがラインバランスであり、ボトルネック工程の解消が効率化の決め手になる場合が多いもので
す。
ラインバランスが取れていないと、仕掛品の停滞する工程や、加工すべきワークが欠品し、手待ちの工程が発生し、
ラインとして流れ化を目指している生産の理想が追及できなくなってしまいます。
流れ生産で、バランスさえ整っており、工程間搬送が一個流しの原則に従っていれば、
工程間に在庫ゼロ、もしくは1(作業の順番で異なる)となります。
完璧にバランスがとることは不可能かも知れませんが、常に も長い時間を必要としている、ネック工程を改善し、
山を低くしていく活動を続けていけば、徐々にその山谷が平滑になって行きます。
3-3-2 サイクルタイム測定
当然のことながら、工程毎にサイクルタイムを測定することが必要です。
地味な仕事ですが、この観測、測定、記録がなければ、その先の改善はありえません。
測定する場合、同じ製品ばかりを加工、組立を行なうとは限らず、前に述べた製品ファミリーの分析をしっかり
やっておかないととんでもないミスを犯すことになります。
同一製品だけを加工するのならば、測定ミスの可能性を含めても、2,3度行なえば作業のばらつきを踏まえても、
信頼に足るデータが得られるのですが、同一ラインを流れる製品ファミリーは細分化すると、とてつもない数となり、
測定に膨大な労力がかかるだけでなく、どのように整理して改善案に結びつけるのかさえ、
迷ってしまうことになりかねません。
前項で述べた製品ファミリーの分析を前もって必要なことが、お分かりいただけると思います。
観測値のバラツキは必ず発生しますが、特に加工工程では、今述べた製品による加工内容のばらつき、
組立工程では作業スピードや付帯作業の有り無しに気をつけましょう。
また作業習熟により時間が大きく異なるのも組立工程の特徴ですが、習熟者の時間を基本にして考えるのが
普通です。
またバラツキが多い工程は、何かしらバラツキが発生する原因が潜んでいます。
たとえば、“時々切子が引っかかっており、標準作業には無いけれどもその処理に時間がかかっている”とか
“ボルトを締め付ける時、前に仮止め時に部品の位置決めが悪く、後で締めるボルトがねじ穴がずれていて、
もう一度締めなおすことがある“とかいった作業では、
まずばらつきが発生しないように原因を解明し、バラツキをとめることが先決となります。
もうひとつ、測定前に、今の計画生産量から計算し、サイクルタイムがいくら必要か、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
66
必要サイクルタイムを計算により求めておきます。
必要サイクルタイム=稼働時間 x 可動率/必要数で一般には可動率を 95%くらいにとります。
この時間を目安として測定したサイクルタイムと比較しながら、どの工程が問題か、
どの工程に余裕があるのかを考えながら、観測することが重要です。
3-3-3 測定結果の整理と問題工程の把握
測定したサイクルタイムを基にピッチダイヤグラムを作成してみましょう。
形式は厳密に規定することは必要ありません。
各工程のサイクルタイムの測定値(実線)を
折れ線で結べばよいのです。
更に生産計画から求められる必要サイクルタ
イムに余裕率 0.95を掛けた必要サイクルタイ
ムの線(図中破線)を引き、全体を眺めてみ
ます。
実測値の線が必要サイクルタイムを越してい
る工程はありませんか。
右図では 123 工程が必要サイクルタイム
60SEC を越えた 65SEC となっています。
図 6 ピッチダイヤグラム 記入例
この図を見ると、まず第一に 124 工程を、60SEC 以下のサイクルタイムにする必要があります。
このままでは需要に供給が追いつかず、残業等の時間外労働が必要となります。
いかに他の工程が早く完了しても 65 秒以下のスピードで物を供給することは出来ません。
124 工程はいくつかの要素作業を行なっているので、124 工程の要素作業の改善だけでなく、他工程との要素作業
の組み合わせの変更によってもサイクルタイムを短縮できる可能性があります。
たとえば、サイクルタイムの短い 127 工程に、124 工程の作業を移して、バランスを取ることです。
そのときに先行作業条件があるかどうかに注意する必要があります。
仮に要素作業④が 8SEC かかっているとしましょう。
この要素作業④を 127 工程に移すことを考えた時、124 工程は 57SEC、127 工程は 53SEC となり、
現状より改善され、かつ必要サイクルタイムの 60SEC がクリアできるのですが、
もし⑧~⑭間での要素作業の中に④をやってから出ないと出来ない要素作業があったらどうでしょう。
たとえば、車で言うと、シートを組み付ける前にフロアカーペットを敷いてしまうことは出来ません。
また 124 工程ではなく、123 工程や 124 工程がボトルネック工程となっていたらどうでしょうか。
機械が作業を支配している工程では、機械それぞれの役目が異なるために、作業の組み換えは人間の行なう
sec 6560
5550 55 55
5040 45 46
必要サイクルタイムx0.9530
20 実測工程別サイクルタイム
10
121 122 123 124 125 126 127
1 0 0 1 1 1 1
①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭ ⑮⑯⑰⑱
55 45 50 65 55 55 46
工程名
人数
要素作業
サイクルタイム

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
67
要素作業のように感嘆には組み替えが難しいのが普通です。
簡単に言えば、人間は練習さえ普段やっていればなんでもできるのですが、機械はロボット等の汎用機を除いて
決まったことしか出来ないのです。
したがって機械を増やすとか、工程を増設する等の設備投資に走りたがりますが、できるだけ避ける努力が
必要です。
設備の動作を詳しく観察して、機械のシーケンスや、個別動作の改善、個々の動作のスピードアップ等が必要に
なってきます。
特に重要なのは、個々の動作を早くするスピードアップではなく、
ⅰ)動作をなくすることが出来ないか
ⅱ)動作をオーバーラップさせることが出来ないか
の二つの観点から、改善の方法が無いかを、考えます。
スピードアップは機械に無理を与えがちですし、設備故障の原因にもなりかねません。
ちびちび稼いでも、大きな設備故障があれば、その効果も吹っ飛んでしまいます。
3-3-4 機械のサイクルタイムとシーケンス変更
前の項で機械のサイクルタイムアップの方法
について述べましたが、もう少し詳しく話したいと
思います。
右の絵は専用機械とロボットからなる工程で、
機械で加工完了したワークをロボットが機械内に
進入し、取り出し、箱に運び、収納し、次の素材
置き場から素材をつかみ、機械にセットし、機械
から出たところで、機械のふたが閉まり、加工が
開始されます。
レイアウトの関係から、ロボットと機械は離れて
おり、ロボットの回転とアームの伸縮で、
長時間かかってゆっくりとセット、取り出しを行な
っています。
図中の番号はロボットの動作順序を表していま
す。
動作順序
ロボットの動き 0.加工機械の扉開く(開き端)
①ロボット原位置から加工完了品を取りに行く
②取り出し、加工完了品の箱に入れる
③加工前素材を取りに行く
④素材を加工機械に運ぶ
⑤ロボット原位置に戻る 図 7 改善前後のロボットのシーケンス
①④ ②
⑤
③
加 工 機 械
加 工 前 素 材
加 工 完 了 品
ロ ボ ッ ト
⑤④ ②
①素 材 ③ 完 成 品 ⑥仮 置 台 仮 置 台
ロ ボ ット原 位 置
⑦
⑧加 工 完 了 品
加 工 前 素 材
加 工 機 械
ロ ボ ッ ト

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
68
⑦加工機械の扉閉じる
0.機械加工開始
以上がロボットの動作であるが、システムのサイクルをロボットと機械のシステムとして表すと、
「問題点と何をすべきか」が分かりやすくなります。
3-3-5 連合作業分析による改善
連合作業分析は、そのシステムに含まれるユニットの動作をオーバーラップすることにより、サイクルタイムの短縮
を行なうのが狙いです。
つまり、ユニット A が動いている間、ユニット B が停止しているのではなく、別の仕事をしている比率を高めることに
よって、サイクルタイムを縮めるとするものです。
1 サイクルの間に、それぞれが相手の動作が足かせとなって自分が動けない時間を減らすのです。
これを応用して、前項のシステムを改善してみましょう。
問題はロボットが動いている(仕事をしている)間、機械
が仕事が出来ないのを工夫しなければなりません。
ロボットが完成品を取り出したり、素材を供給するため
に機械が動けない時間を 小限にする工夫をします。
この例では、素材と完成品の仮置き台を作り、ロボット
の原位置を機械に近づけることによって、
サイクルタイムを短縮する工夫をしています。
3-3-6 改善前後の連合作業分析表
改善前後のロボットと機械の動作のオーバーラップ
の差に気が付かれたことと思います。
改善前はロボットが加工完良品を機械から取り出し、
完成品を完了品箱に入れて、 図 8 連合作業分析表
それから素材を機械に投入するまで 42sec もの長時間機械は動くことが出来ませんが、
完了品と、素材の仮置台を機械から出たすぐ側に設置し、そこに仮置きすることで、機械を動かし、
ロボットは機械が動いている間にそこから、完良品を完了品箱に入れたり、素材を素材パレットから仮置台に
置いたりする仕事を平行して行なえば、機械の始動タイミングを 27sec も早くすることが出来、
サイクルタイムもその分だけ早くすることが出来ます。
このように、ロボットや機械の動作速度を早くすることなく、ロボットと機械の動作をオーバーラップさせ、
サイクルタイムを短縮するする方法がきわめて重要になってきます。
ロボット 機械(機)扉開く
(ロ)原位置より機械に移動 10
(ロ)加工完了品を取り、パレットに入れる 12
(ロ)素材をとり行き、機械に入れる 13
(ロ)ロボット原位置に戻る 7
(機)扉閉じる(機)ワーククランプ(機)加工油 吐出(機)加工開始、第一ドリル前進(機)加工 80(機)扉開く
(機)扉開く(ロ)原位置より機械に移動(ロ)加工完了品を取り、パレットに入れる

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
69
3-3-7 見込み発車と緊急停止
2 つ以上のシステムが協力して仕事をする場合など、インターロックの取り合いがサイクルタイムを長引かせる基と
なります。出来ればそれぞれ相手がどこにいても、自分は自由に動けるのが一番ですが、どうしてもそうできない
場合があります。
その場合のインターロックのとり方によって、サイクルタイムが大きく変わってくる場合があります。
ひとつは相手方の条件が整うまで他方は動き始めないインターロックのとり方です。
今回の例で言えば、機械の扉が開いて、後退端の信号を受けてから初めてロボットが動き出すケースです。
信号を受けない限り動き出さないのですから、干渉によるユニットの破損やトラブルについては安全ですが、
サイクルタイムが長くなる可能性を持っています。
もうひとつの方法として、動きだしは別の信号でもらって、リアルタイムで、必要情報をチェックしていく方法です。
たとえば「機械扉開く」の信号をもらって、ロボットが動き出し、ロボットがある位置まで来た時に、扉後退端の信号が
入らなかったらロボットが緊急停止する方法です。
いつ起きるのか分からない頻度の少ないトラブルに対し、毎回サイクルタイムを長くする制御方法を取らず、
緊急停止で対応する制御方法はサイクルタイムが短く、その達成が難しい場合よくとられる方法です。
緊急停止後の原位置復帰は少し厄介ですが、トラブルの少なく、サイクルタイムが厳しいラインはこの方法が良いと
思われます。
3-3-8 カタログエンジニアと改善テクニシャン
今まで述べてきた改善方法は自分たちが使用する機械について熟知していないとなかなか出来ないものです。
カタログを見て、機械を買うだけのエンジニアには出来ません。
常日頃、自分たちの工程のシステムに接し、その内容を完全に把握できている技術者にのみ、このような変化する
時代のシステムが改善できることを心得る必要があります。
誰よりもその工程やそのシステムを知っている人のみが改善を進められることを考慮する必要があります。
更に、出来れば、エンジニアと一緒になって動くテクニシャンがいるとその力は倍増します。
エンジニアのイメージしたちょっとしたものは、作れるテクニシャンです。
機械の仕入先や製缶業者にその都度、物を作ってもらっていては思ったように改善は進みません。
考えたことを時間をおかずに、すぐに作って、試してみる、外注メーカーに頼んだのではこうはいきません。
3-3-9 個別工程の改善の必要性
今までボトルネック工程の改善の話ばかりしてきましたが、ネックでない工程は何も考えなくても良いのでしょうか。
ここでは、124 工程を除く他の工程は改善の必要が無いのかというと、そうではありません。
たとえば 121 工程は 45SEC であり、このラインの中で も早く作業が完了します。
改善のリソーセスが限られている場合には、後回しにすることもやむをえないと思いますが、簡単に見つかり、
簡単にやれることはすぐに実行すべきです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
70
少し改善すれば、他の工程と結合して、工程短縮が可能になる可能性が増大します。
他のネック工程からの要素作業の受け皿も大きくすることが出来ます。各平均に負荷を均すことも平準化の観点か
ら、必要なことですが、その時には工程削減の夢は捨てなければなりません。
時には工程削減を狙って、ある工程に要素作業を寄せて、ひとつの工程を殆ど仕事が割り当てられない状況に
持っていくことが重要です。
誰が見てもおかしな工程設定ですから、この状態を続けて良いとは考えません。
実際に仕事をしている人は、自分だけ楽をしているというのは耐え切れません。
次なる改善によって、この工程をなくするという機運が強くなり、改善に拍車がかかることになります。
このようにして工程やラインを削減していく方法を「寄せ止め」といって、よく使われる手法です。
3-3-10 いくつかの実例
次の章では、連合作業分析のいくつかの改善の考え方を用いた、実例を見てみましょう。
要は人間であれ、機械であれ、連合作業の相手が動いて働きをしている間、自分が何もしないで、
その相手を監視しているのではなく、同時に自分も働きをして、無駄な時間(アイドル時間)を減らす工夫をすること
なのです。ですから個々の働きをするスピードはまったく同じであり、変わることはありません。
前に示したロボットと機械の例も同様な問題でした。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
71
3.4 連合作業分析
前節で説明した連合作業分析は良く使われる手法ですのでぜひともマスターしたい手法です。
トヨタ生産方式で、用いられる「まわり作業」はその代表的なもので人間一人と機械 10 台のシステムで
連合作業分析を行なっているといっても良いでしょう。
ここで、連合作業分析を用いた、いくつかの実例を見てみましょう。
要は人間であれ、機械であれ、連合作業の相手が動いて働きをしている間、自分が何もしないで、
その相手を監視しているのではなく、システムの中の他の要員と同時に自分も働きをして
無駄な時間(アイドル時間)を減らす工夫をすることなのです。
ですから個々の働きをするスピードはまったく同じであり、変わることはありません。
前に示したロボットと機械の例も同様な問題でした。
3-4-1 測定と連合作業分析表(現状)の記入
初に、ストップウォッチで現状作業を測定し、測定用紙に記入するところを説明します。
イメージする作業はエアコンに冷媒を充填する作業です。
前工程で組み付け完了したエアコンに冷媒を充填しなければ、エアコンは機能を発揮しません。
レイアウトは右図をイメージしてください。
作業者の動きと時間の観測結果は以下のようです。
①まず前工程の完成品置き場からエアコンを取り出し,
作業台に 10DM(1/100min)で持ってきます。
②次に作業台のエアコンにガスボンベから接続されている
ホースを仮接続します。10 DM かかりました。
③エアコンのねじにボースを締め付けていきます。(5 DM)
④エアコンのバルブをゆっくり開きます(7 DM)
⑤充填装置を操作します。(8 DM)
しばらくの間、充填されていくのを確認します。
ガスが充填完了されるまで 100 DM かかりました。
⑥充填が完了したのでエアコンのバルブを閉めます。
(7 DM) 図 9 冷媒ガス充填作業
⑦エアコンから充填用のホースをはずします。(10 DM)
⑧次工程へ移動します。(次の組み立て完了品を取りに向かいます。) (10 DM)
バルブ
ガスボンベ
完了品置き場
前工程完了品
充填作業台

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
72
以上の動作を連合作業分析表に書くと右下図のようになります。
分析表は大きく 2 つのブロックに分かれており、上段には数値が、
下段には図が書かれています。
サイクルタイムは説明する必要は無いでしょう。
「正味」は作業者と機械が 1 サイクルの間に実際に働いて
いる時間が記録されています。
充填機がガスを充填している時間 100 DM,
作業者がさまざまな仕事をしている時間が 1 サイクルの間に
トータルで 64 DM ということを示しています。
次の「アイドルタイム」の欄には、
1 サイクルの間に仕事をしていない時間を示しています。
1 サイクル 164 DM の間に 100 DM しか仕事をしていないので、
アイドル率は 100/164=61%と記述されています。
同様に充填装置も 64/164=39% となります。
これでは、人も機械も、仕事をしているとはいえません。
一般にアイドル率は 5%程度が目標とされています。
3-4-2 何が問題なのでしょうか。
もっとも重要なところは機械がガスを充填している間、
作業者はただ見ているだけになっていることです。
もし作業台が複数あれば、機械が充填している間
次の準備をしたり、あるいは前の製品の後処理が
出来るはずです。
そうすることによって、人と機械が一方が働いている間に、
他方も監視しているだけではなく、
付加価値をつける仕事が可能になります。
その結果、サイクルタイムを短縮することが可能となって
きます。
右図には、その考え方を基にした改善結果を示しています。 図 10 改善前後の連合作業分析表
よく検証してみましょう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
73
3-4-3 演習課題 「人を機械の監視役にするな!」
次は皆さんが改善する番です。
がんばって、この成形ラインの改善を行ないましょう。
ⅰ)成形機によるプラスチック成形作業
・観測概況
現在プラスチック成形機が 6 台あり並列に並び、各機械にはオペレーターが一人づつ付いており、
成形機に材料を計量し、充填したり、出来上がった製品を取り出し、
型に残ったカスをエアで吹き飛ばしたり、のんびりと行なっている。
需要の状況は、比較的安定しており、将来的にも大きな変化は
なさそうであるが、コスト競争は今後厳しくなると予測されている。
・測定結果
各人の作業内容と時間を測定してみると
No.1~No.6 までほぼ同様で、次のようであった。
製品が成形完了すると
・作業者は
1)金型を取り出す(6 DM)
2)機械と金型をエアで掃除する(15 DM)
3)金型から成形品を取り出す(10 DM)
4) 金型に原料を入れる(12 DM)
5)金型を機械に入れ、機械をスタートさせる(12 DM) 図 11 成形機レイアウト
6)原料を計量する。(機械が動いている間にやっている)(25DM)
と時間測定された。
同様に成形機の時間を測定してみる。
・成形機
1)成形マシンサイクル(143 DM)
レイアウトは右上図のようであり、
作業者は成形機が製品を作っている間は、暇そうにしており、手持ち無沙汰のようである。
以上の情報を基に、改善後の連合作業分析表を書き、
この工程の問題を把握し、改善目標を定め、生産システムを改善しなさい。
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
成形機作業者
レイアウト
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
成形機作業者
レイアウト

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
74
3-4-4 「特定の人しか出来ないと,こうなる。」「順序が決まっているとこうなる」
「“多能工化”が効率化の手段である」という言葉を皆さんは聞いたことがあると思います。
そのため多くの製造現場では、教育訓練計画を作って、一人の人が多くの工程を担当できるように
日夜がんばっています。
実際に多くの人が関わってあるひとつのまとまった仕事をする時に、
その仕事の中に特定の人しか出来ない仕事があるのと無いのでは大きく効率が変わってくるのが
連合作業分析をしてみると実感できます。
もうひとつ、「この仕事が終わらないと、次の仕事にかかれない」といったように
作業の順番に規制がある場合(順序作業)、効率化が妨げられる場合があります。
この二つの例を次の例題で見てみましょう。
この現場は、右図のような巨大な洗濯機をイメージしてください。
この籠がぐるぐる回って、大量の衣料を
一度に洗う装置なのですが、
あまりに大きいので、
回転軸を支えるベアリングを
比較的頻繁に交換する必要があります。
しかしながら交換時間は洗濯できない
ため、できるだけ早く、しかも少ない工数
でベアリング交換をしたいと
経営者は思っています。
ラインストップ時間を短く、工数も少なく
ベアリング交換をするためには
どうすればよいだろうか。
という問題です。
図 12 大型遠心分離洗濯槽の点検修理
(1)現状の事前調査結果(ヒアリングによる)
・ここでは、クレーンを用い、モノを移動させるには玉掛けの免許が必要で、段取り工 C しか免許を持っていない。
・また、洗濯槽の真上にある掻取装置は関節型ロボットを用いており、回転することにより、籠を吊り上げる際、
その干渉領域からはずすことが可能なのだが、現状では気が付いている者は居なかった。
・このベアリングのグリス交換時に、掻取装置のロボットも同時に分解点検をすることにしている。
どうせ、グリス交換の時、このシステムは止まるので、同時に掻取装置の分解点検を行なったほうが、
別途掻取装置の分解点検を行なうより、システムを止める時間が減るという考え方をとっている。
掻取装置掻取装置
カゴカゴ
クレーンクレーン
籠
ベアリング
分解修理部位

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
75
・製造部は、籠をはずさなくてもベアリング点検やグリス交換を可能な構造に洗濯浴槽を変えるよう主張したが、
構造上不可能と分かり、仕上げ工 D でしか出来ないこの作業を講習会を行い、誰でも出来るように主張している。
(2)現状の観測結果
今回の洗濯槽の点検修理作業の連合作業分析結果を右図に示す。
結果は惨憺たるものである。
この作業に関わる人間は
・部品組立工 A,
・組立工 B
・段取工 C
・仕上工 D の 4 名。
・サイクルタイム 345 min
であり、
各人のアイドル率は
・部品組立工 A 42.0 %
・組立工 B 60.3 %
・段取工 C 81.2 %
・仕上工 D 79.7 %
と、ほぼ半分以上仕事をしていない。
早急にこの仕事の仕組みを改善する
必要がある。
(4) 初に決めるのは改善の方向性です。 図 13 大型遠心分離洗濯槽の現状連合作業分析表
345min のトータルサイクルタイムを短くする方向性か、4 人かかって仕事をしている人数を減らす方向性か、
どちらに重点をおくかにより、その改善計画の立案内容が大きく変わってきます。
ⅰ)まず 初は、トータルサイクルタイムを短くする方向性で考えて見ましょう。
ここでは「順序作業をなくせ」(この仕事が終わらないと、次の仕事にかかれない)を用います。
右上図の矢印のところが順序作業になっています。
たとえば「掻取装置取り外し」をしないと本当に「籠締め付けボルトを緩める」ができないのでしょうか。
上の図を見てもそのようには見えません。
現状のままでも籠を吊り上げるためにはクレーンと干渉するかもしれませんが、ボルトは緩められそうです。
掻取装置取り外し中に落下する危険があるので、下でもし「籠締め付けボルトを緩める」作業の安全が心配なら、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
76
固定物に落下防止のワイヤーを取り付けるなどの対策が出来るはずです。
同様に、グリースを詰め替え後、籠の締め付けボルトを締めないと「掻取装置を取り付け」られないのでしょうか。
これも順序作業ではなく、工夫をすれば同時に出来そうですね。
少し考えただけで、順序作業をなくし、各作業要素をオーバーラップすることにより、345min かかっていた仕事を
345-(53+45)=247 min に短縮できました。
ⅱ)次に、作業人員削減の方向で考えて見ましょう。
アイドル率から見ても、4 人が必要とは考えられません。
現状の連合作業分析表から見ても、3 人、もしくは 2 人でも十分なように見受けられます。
ここでは「特定の人しか出来ない仕事を減らせ」で考えて見ましょう。
このケースで「特定の人しか出来ない仕事」は何でしょう。
冒頭にあったように段取り工 C の玉掛け作業、仕上げ工 D のベアリング点検、グリース詰替え作業です。
この作業が A,B,C,D 誰でもが出来るよう教育され、資格を取ることが出来た暁にはどうなるでしょう。
ざっと見ただけでも、仕上工 D の仕事 70 min は C,D に置き換えてもその時間は C,D とも手待ちの状態なので
まったく問題ないと考えられます。
それでも一方はまだ多くの手待ちの時間があります。
玉掛け作業でも同様です。誰もが出来るということは、自由にその作業の組み換えが可能になり、
アイドル時間を減らす可能性が高まります。
3-4-5 演習
ここからは、皆さんが考えて、改善後の連合作業分析表を完成させましょう。
アイドル率を減らし、サイクルタイムを短縮し、考えられるもっとも良い仕事の仕組みを作ってください。
3-4-6 「共同作業をなくせ」
人-人型の連合作業分析では「共同作業をなくせ」ということが改善のポイントになります。
たとえば二人の人が別々の仕事を行い、
そのサイクルの中である時だけ二人が共同でやる仕事が含まれていたとします。
各人は個人でやっている時は自分のペースでやっているので、共同の作業にかかる前の仕事が完了する瞬間が
同時とは限りません。いや、いかにタイミングを合わせようとしても微視的に見ると同時であるはずがありません。
必ず待ちが生じたり、遅れを挽回しようとして、標準とは異なった無理な動きが生じます。
そこに必ず余裕が必要となります。
その前の独自で行なっている作業要素の中に余裕を持っておかないと、相手との共同作業に遅れが出て、
相手を待たせてしまう可能性があるからです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
77
このような場合、連動作業分析表には見えないかもしれないが、
各作業要素の標準時間に必要以上の余裕が含まれる危険性やアイドル率を高く設定する仕事配分や、
余分な人をつける危険性を孕んでいます。
かくして監督者の目には「だらだらした仕事をしている」と見えてきます。
3-4-7 製材作業
次の例を見てみましょう。
製材所での作業です。
長尺の製材原木を定尺に切断する作業は、押し手、引き手、取り手の 3 名と丸鋸機械のシステムで行なわれる。
押し手は床積みの製材原木を引き手と協力して(共同作業)のこぎり台に上げ、引き手は直角に切断し、
取り手は切断木をのこぎり台より取り所定の場所に積み上
げることになっています。
ここでの共同作業は、押し手と引き手の製材原木を床から
取り上げ、のこぎりへ移動させることである。
この共同作業をなくして、一人でも可能な作業要素とするこ
とによって、作業を柔軟に組み合わせることが出来、
効率が飛躍的に向上します。
現状の連合作業分析表を書いてみよう。
のところが共同作業になっています。 図 14 製材作業レイアウト
そのため押し手は自分の仕事が終わっても 246 DM の
ところで終わっても引き手の仕事の完了する 306 DM
まで、待ってはじめて次のサイクルに入ることができる。
また、
切断にはいっても 4 者(押し手、引き手、取り手、機械)が
互いに順序作業になっているために、
小刻みにアイドル時間が発生しています。
これらを発生させないためには、
前述の「人を機械の監視役にしない」だけでなく、
「人を人の監視役にもしない」ことが重要である。
しかしながら、さまざまな改善の考え方の視点を
成就させるためにはちょっとした小道具を考え出し、
作り出し、現状の仕事の仕組みを変革するリーダーシップ
が大変重要となってきます。
無論、それらの改革を進めることを良しとする企業風土、
職場風土も重要なポイントだ。
皆さんの職場ではこのような小改善を気軽に行なえる 図 15 製材作業現状の連合作業分析表
企業風土があるだろうか。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
78
3-4-7 演習
さて、この製材所の製材原木を短尺にする作業を改善するために、どのような小道具を作って、
結果、改善後どのような連合作業分析表を目指すのか、河どのような結果を目指すのか
書きなさい。
ⅰ)改善後の連合作業分析表
ⅱ)このシステムに追加すべき小道具、設備(製缶作業にて簡単に作ることが可能なもの)
3-4-8 ライン化(流れ化) 温水器の梱包作業
温水器の梱包作業は包装工 A,B,C の 3 名と 近入れた自動結束機 1 台で構成されている。
現状のサイクルタイム 81DM は定時で、ほぼ需要を
満たしている。
自動結束機は完全自動ではなく、包装工 B と 1 セットで
ケースにバンド 3 本掛けて居る。
3 人の作業分担は一応決まってはいるものの、
合理的に決められたものでなく、遅れたものの応援を
少し暇な人が行なうなど完全に決まっていない。
また、他人の進行状況とは関係なく、自分のペースのみ
で、仕事を進めている結果。少し、自分の工程完了品が
出来ると適当にサボっている。
そのため各人の前には多くの工程間在庫であふれて
おり、どれが前に完了したものかさえ分からない状態で、
管理された状態とは言えない職場である。
工場長は「作業の見える化」のために、ライン生産に
移行するための青写真を書くようあなたに命じた。
さてあなたはラインをどのように設計するので
あろうか。
図 16 梱包作業 現状の連合作業分析表
現状の連合作業分析表は右図のようである。
まず要素作業を作業の順番に並べて、その要素作業の作業時間を列記してみる。
①商品にシールを貼る 12 DM
②ケースを折る 7
③底板を入れる 15
④品物を入れる 33

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
79
⑤あて物を入れる 14
⑥ホッチキスでふたを止める 8
⑦ケースにバンドを掛ける 43
⑧製品置き場に運ぶ 26
流れ化するためには各人の作業時間を合わせ、サイクルタイムを設定する必要がある。
その設定されたサイクルタイムが、需要量が確保できる必要十分なサイクルタイムになっているか検証。
要素作業を合計しても 158 DM であり、現在必要サイクルタイムが 81DM なので厳しいが二人でも何とかやれる
状況と推察。後は作業組み合わせが成り立つかどうかを調べる。
①~⑤までがトータル 81、⑥から⑧までがトータル 77DMなので、あてものを全て Aが入れるのではなく、半分入れる
ことにすれば、現状の需要なら一工程 A①~⑤、二工程 B⑥~⑧で、タクト 81DM で流れ化可能、
ただし A の仕事がアイドル率 0%で厳しすぎるので、ものの置き方を工夫して要素作業時間①~⑤トータルで
5DM 程度の短縮するアイデアを出す必要があり、早速現場と相談しよう。
3-4-8 演習
改善後の連合作業分析表を書きなさい。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
80
3.5 工程分析
「工程分析とは仕事の過程を図式モデルとして記述し、その論理的、総合的検討を通して 適のプロセスを
求めるための手法である。」とあるように数多くの方法があるので、方法をひとつひとつ説明することは避けて、
具体的な問題を解きながら、何をどう考えればよいのかを中心に進めて行きたいと思います。
3-5-1 例題
推進器基幹部品
・問題の背景
調査を指示された部品は推進器の組立に使用される基幹部品で、 近組立ラインの生産タクトが 90 秒に
能力増強された結果、欠品が頻発し、組立部より、機械部に対し、早急に改善を要求されている部品である。
機械部に転属 1 年目のあなたは自分の実力をアピールするためにも、工程分析を行い、問題解決を図りたい。
3-5-2 前提条件
予備調査の結果、次の前提条件で分析することにした。
ⅰ)加工部品
・調査した一連の工程ではこの部品専用の加工を行っている。
ⅱ)組織体系
・この工場は、検査部に属する検査工を除いて、機械部21組に属している。
ⅲ)勤務体系
・勤務は 8:00~5:10,休憩は昼休み 50 分、午前、午後に各 10 分の休憩があり、実働 8 時間である。
ⅳ)設備の調達
・設備の調達には、旋盤は 3 ヵ月、リーマは 2 週間のリードタイムが必要であり、
・それぞれの機械類の価格は旋盤 600 万、スロッターマシン 300 万、4 年償却、とし、
・また、現在遊休となった旋盤一台、フライス盤一台は現在倉庫にあり、20 万ほどで、整備可能である。
ⅴ)作業習得
・人は旋盤には 2 週間、リーマは一ヶ月の訓練を必要とする。
ⅵ)アワーレイト
・人件費はアワーレイト 2000 円/時間となっている。
ⅶ)部品収納状態
・この部品の重量は約1kg、容器の収容数は素材から工程完成品全て 10 個で、工程間を通い箱として
使用している。
・箱の大きさは 360x420x280、で、工程間を運搬台車の許容重量は 200kg である。
ⅷ)レイアウト
・鋳物工場、組立工場は別棟となっているが、加工工程と隣接している。
・距離は図中にある縮尺に従い、計測、記述するが、おおよその数値となっている。
・添付の工場レイアウトは、現状の工場レイアウトである。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
81
図17 3-5-1 例題の工場レイアウト
工場レイアウト
機械工場
・鋳物置き場⇒第一旋盤 500m
・第一旋盤⇒リーマ作業台 150m
・リーマ作業台⇒一時置き場 50m
・スロッター⇒第二旋盤 600m
・第二旋盤⇒洗浄場 800m
・洗浄場⇒組立組付品置場 400m
第1旋盤 4台
第2旋盤 2台
リーマ
作業台4台
スロッター1台
仕掛待ち置場
洗浄場
鋳物置場
組付置場
仕掛待ち置場
検査場
完成品置場
鋳物工場

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
82
3-5-3 調査結果
工程の調査結果は以下のとおりであった。
まず旋盤加工の 1 時間前、2 時間毎に鋳物倉庫から素材を機械工場へ運搬し,
第一旋盤より 50m 離れた素材置き場に一時置きされる。
計画時間になると、第 1 旋盤へ運び、吸引面の切削、外径削りを行う。計測すると 35 秒かかっている。
次に同じ旋盤で、刃具交換を 20 秒掛けて行い、直径 23mm の穴ぐりを 70 秒で行う。
更に、リーミング作業のための削り代を残して,刃具交換を 30 秒掛けて行い、直径 25mm の仕上孔あけを行う。 後
に、また同じ保持状態で,突起部の内側を 50 秒で、仕上切削する。
一連の作業は設備、作業者は 4 台、4 人で、パラレルに行われている。個人の作業時間は殆ど変わらない。
完成品の安全在庫を 1 時間分保持している。
旋盤加工を終わった品物を,仕上作業場の作業台に 2 時間毎に運搬工が運んでいる。
工程間を運搬する作業者は、各工程を順々に回って、身の入った箱を台車に積んで次の工程へ行き、
次の工程で降ろし、また実を積んでは次の工程へ行き、 後の工程の空のパレットを鋳物工場へ運んでいく。
この工程では直径 25mmの穴をリーマを使って仕上げる.
この作業はいわゆる人海戦術で、設備は殆ど無く、作業者がバイスに半製品を固定し、もくもくとリーマをかけている。
時間を計ってみると 1 個仕上げるのに 120 秒かかっている。
人手の作業で、設備故障も無いので、安全在庫は 30 分と全工程中 も少ない。
作業台は比較的容易に、フォークリフトで動かせそうな物であり、移動は簡単にできそうだ。
次にスロッターへ移動し,キー溝を掘る.この場合,機械は 1 台しかないため,半日位,加工待ちが
発生することが多い。能力が足りない分は残業でカバーしているため、工程完成品も山のように積まれている。
日々の残業時間の設定はどのようにやっているのか、職長に聞いてみた。
「今は定時を終わってから毎日 4 時間残業だよ、この工程は、作業者が一人なんで、
そいつに毎日残業させるわけにいかないんで困ってるよ。しかたないから、俺も時々やってるよ。」
運搬が二時間毎にリーマ工程完成品を運んで来るが、置き場が乱雑な上、溢れかえって、困っている。
スロッターで,キー溝を切削した後,品物を第 2 旋盤へ運び,シャフト穴とキー溝を基準にして
位置決めをし,もう一方の側の面削りと突起部の切削を行い,さらにその突起部のまわりに細い溝を切り込む。
ワークを取りにいって、機械にセットし始めるまで 15 秒、セットし始めてから工程完成品を取りはずすまで 70 秒、
箱に入れるまで 10 秒かかっている。
ここでの安全在庫は 2 時間の設定なのだが、能力不足分と、通常の能力不足分と混在し、遅れているのか進んで
いるのか全くわからない。
その後,品物を洗浄場まで運び,そこで吸引面の洗浄を行う。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
83
箱から取り出し、ハンガーに掛けてから、洗浄ブースから出てくるまで、20 分かかる。
ハンガースピードは可変であり、ピッチは固定で 1m である。
洗浄性能はハンガースピードと洗剤塗出圧で制御可能であるが、現在ともに 大設定値の半分位で稼動している。
現在のスピードは 0.5m/分となっている。
この工程での問題は、洗浄ブースがひとたび故障すると、長時間の停止となってしまうことである。
2 時間程度は一般的で、先回火災発生時には 2 日の操業停止に追い込まれた。
しかし、安全在庫は検査後で持つため、設定していない。
洗浄後,再び箱に入れられ、検査係の検査をうける。
検査は、全数検査ではなく、1個/箱の抜き取り検査で切子の付着や、バリの有無など、目視検査が主力である、
特に大掛かりな検査装置は使われていない。
検査完了後に、完成品として組立ライン側に運ばれるまで、完成品置き場に保管される。
完成品置き場は、現在内製加工品として、2 日を標準としている。
組立現場からの引き取りは、かんばんにより 2 時間ピッチで引き取られるが、
そのかんばんは機械現場の仕掛け指示には用いられていない。
機械現場はあくまで計画生産による仕掛け指示に基いて生産を開始している。
以上の結果を観測とタイムスタディにより把握したあなたは分析にはいった。
3-5-4 工程分析
ⅰ)各工程の生産能力の確認
現場を調査して、フロープロセスチャートを書いてみると、 初に目に付くのはスロッターの能力です。
このようにいくつかの工程を経て完成する製品の工程分析で、第一に考えるのは工程の生産能力のバランス
です。
言い換えれば、各工程のサイクルタイムがバラバラであれば、
その製品の生産能力は も遅い工程(ネック工程、もしくはボトルネックと呼びます)によって決定されるという事
で、その工程の能力が後工程の必要量と対応していなければなりません。
また能力の余っている工程は、リソーセス(人、機械)を削減して、コストを下げなければいけません。
後工程のサイクルタイムが 90 秒なので、この部品も 90 秒に一個作る能力があればよいのです。
少なすぎても、多すぎてもいけません。
一般的にちょっと多い処を狙います。後工程の組立の要求 90 秒に一個の供給ですから、
85 秒くらいを目安とします。
ⅱ)フロープロセスチャートから工程の順序とサイクルタイムを計算してみよう。
工程は次の通りですね。
第一旋盤 → リーマ削り → キー加工 → 第二旋盤 → 洗浄 → 検査 → 組立

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
84
夫々の工程の生産能力は記述から分るものもあれば分らないものもあります。
一般的に工程調査は 1 回で完結する事はなく、整理、考察して、解決策を検討すると、
「これが足りない、あれも調べなければ」と、再調査をするのが一般的です。
労力を惜しまず、疑問に思ったらすぐに現場に戻り確認し、追加測定しましょう。
「分からなかったら現場に戻れ」です。
①第一旋盤
記述より、35+20+70+30+50=205sec/4 = 0.85min
能力が余っている。 必要台数は 205/90=2.28 台、
現在 4 台構成だが、3 台あれば、余力がある。まず一台、一人を削減しよう。
次に旋盤の刃具交換に時間がかかっていることに着目しよう。
並列に仕事をするのではなく、工程別に専用化することによって、この刃具交換時間を無くす事が出来る。
このように、工程を専用化してしまえば、(流れ化)刃具交換等の人でのかかる段取り替えがなくなる一方、
一台の機械が止まれば、全ての生産が止まる,また、段取り替えの時間を下げようとするモチベーションが
下がるので、一台で全てを加工するセル方式とどちらを選択するかは、そのラインの管理者のポリシーによる
ところが大きい。
ここでは流れ化を取り、右表のように設定する。
②リーマ仕上げ
記述より 120 秒と書かれているが、何人でやっているかわからない。(再度見に行こう)
しかし、安全在庫も少ないと書かれているので、能力はありそうだ。
作業台 4 台なので、4 人で仕事をしていると設定しよう。
120/4=30sec=0.5min の能力を持っているが、必要能力は 90 秒
120/90=1.5 人、とりあえず、二人は減らそう。
ここでは。第二旋盤の仕事とリーマ仕上げの多能工化が出来れば、さらに一人減らせる。
③キー溝加工
スロッターマシンの能力不足で、残業も多く(4 時間残業)、他の工程が定時とすれば、2/3 の能力しかない。
ここでは、サイクル測定がされていないが、大幅な能力不足は記述から明白である。
機械を一台増設しよう。人は加工部品のセットと完成品の取り外しだから、多台持ち可能であろう。
④第二旋盤
機械二台、人間二人であり、15+70+10=95sec=1.58min, 1.58/2=0.79 分
現状では余裕があるが、一台ではわずかに能力不足。組立の能力に対し十分だが、一台ではわずかに能力が
足りない。さらに動作分析を行い、なんとか一人にできると思われるが、今回は二人で継続しよう。
第一工程 → 第二工程 → 第三工程
切削外形 35 穴繰り 70 仕上げ 50
工程変更 50 55 50

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
85
⑤洗浄
現在、1m ピッチで 0.5m/分で動かしているので、加工物は 2 分に 1 個できてくる。
したがって、この工程も 2 時間以上の残業をしているはずである。
作業者は箱からワークを取り出し,ハンガーに掛け、洗浄されたワークを取り外し、箱に入れるだけの仕事で、
20 秒程度で終わってしまう仕事である。
設備能力を見てみよう。
現在[ 大設定値の半分位で稼動]と記述されているので、1 分までの能力を確保できる。
設定値を変えて,85 秒まで能力を上げよう。
但し、この工程は突発故障が発生すると長時間停止になることが分かっており、これを阻止する対策を打つ
必要がある。保全を一名増員し、予防保全を行なおう。
⑥検査
洗浄が残業となっているので、検査も共連れで、残業となるはず。
検査時間は記述されていないが、箱一個の抜き取りで、箱の収容数は 10 個であり、
その上、仕事の内容は「切子の付着や、バリの有無など、目視検査が主力』とあり、10 秒あれば十分と思われる。
洗浄工程の人がやればよい。
これを工程内チェックと呼び、『品質は工程内で作りこむ』考えの一つになっています。
(ⅲ)まとめ
以上から、 初のイメージ通り、キー溝加工の工程の生産能力のみが組立の要求しているサイクルを満足してい
ない事が分り、この工程の能力を上げる事が、全体の効率を上げられると推測される。
ここは、300 万出して、スロッターマシーンを購入し、二台持ちで、能力を倍増する方向で行こう。
2000 円/h*4h*25 日=20 万円、従って 300/20=15 ヶ月で元が取れることになる。
もし金が無いなら、旋盤を売って、スロッターを買おう。
そして、85 秒サイクルで,全工程生産しよう。
その時の 終的な設備と人員は別表2設備数と人員数の通りとする。
現状設備 12 台、人員 13 名、改善後設備10台、人員6名と生産性は現状の約 2 倍になる。
(ⅳ)工程間在庫
(1)全体に工程間在庫の多いのに気が付きましたか。
在庫が必要な原因は
①各工程の能力がアンバランスで、そのためのバッファとして必要なもの、
②安全在庫として設定したもの、
③運搬ロットが大きいため、待ちが生じるもの
に分けられます。
①としては、特にキー加工の能力不足により、大きな工程間在庫が発生しています。
他の工程でも、生産能力のばらつきにより、安全在庫と称して、(厳密にはいえない)5 時間の在庫を持っています。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
86
更には、組立工程への供給保証のため、洗浄工程の長時間の設備故障に備えて、完成品在庫として、
莫大な在庫を抱えています。
これらの問題を一つ一つ、対策を立てて、改善する必要があります。
工程間の状況を整理して、記入すると
鋳物倉庫 → 素材置き場 → 第一旋盤 → リーマ仕上 → キー加工 →
50M
準備 1 時間 安全在庫 1 時間 安全在庫 30 分 完成品在庫 MAX
ロット 2 時間 運搬ロット 2 時間 仕掛在庫 MAX 4 時間
4 時間
第二旋盤 → 洗浄 → 検査 → 完成品置場 → 組立
安全在庫 2 時間 安全在庫 0 在庫 2 日 ロット 2 時間
図 18 工程間在庫
(2)運搬の巡回サイクルを考えてみよう。
計算表シート1の計算より運搬人員 1 名で 1 時間サイクル、二名に増員すれば、
30 分サイクルで各工程を「みずすまし*1」できる。
ここでは工程で改善され、余剰となった人員を回し、2人で運搬することにする。
生産サイクルが 90sec なので、運搬ロットは、20個、すなわち2箱となる。
*1:みずすましとは、一人の人が工程間を渡り歩いて、部品を運搬する運搬方法を言う。
(3)各工程の在庫削減
各工程の在庫は運搬時刻のばらつきや各生産工程のばらつきを考慮し、安全在庫を 30 分と設定する。
運搬ロット+安全在庫=1 時間となる。
また、鋳物置き場から第一旋盤までの素材在庫は中間の機械工場素材置き場は取り除いたので、中間在庫も減少
している。
工程は、検査工程を洗浄工程に統合したので、第一旋盤、リーマ仕上げ、キー加工、第二旋盤、洗浄の 5 工程で、
在庫は各工程各 1 時間、計 5 時間分となる。
(4)レイアウト
運搬は付加価値を生まないので、工程順に近づけて、並べ、運搬距離を短縮するレイアウトにすべきである。
ここでは、
そして、できる限り、必要の無い置き場を減らすよう、考えなければなりません。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
87
しかしながら、今回の改善は洗浄のブースは、移設には莫大な費用がかかるので(一般には億)割愛し、
改善1のレイアウトの如く、作業台だけで固定設備のないリーマ仕上の工程、及び大規模な基礎工事の無い
スロッターマシーンを移設することにして動線を短くした。
終的には、レイアウト 2 の如く、第一、第二旋盤も移動して、工程間の運搬は手押し台車とし、必要な工程の人
が必要な時に取りに行く方法に変更する。鋳物工場からの素材運搬のみ 2 時間ロットとし、フォークリフトで運搬
する方法にして変更する。運搬時間が短くなることによって工程間在庫は減少します。
図 19 改善後のレイアウト例
・鋳物置き場⇒第一旋盤 500m
・第一旋盤リーマ作業台 150m
・リーマ作業台⇒一時置き場 50m
スロッター⇒第二旋盤 600m
第二旋盤⇒洗浄場 800m
洗浄場⇒組立組付品置場 400m
第1旋盤 4台
第2旋盤 2台
洗浄場
鋳物置場
組付品置場
検査場
完成品置場
鋳物工場
スロッター2台
リーマ
作業台2台
機械工場

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
88
ⅳ)見える化による管理方法の改善
①前工程完成品置き場、本工程完成品置場在庫の明示
床にペンキ書きで箱の置場を明記し、
定められた位置以外は絶対に箱を置かない。
他に箱があれば異常が起きていることが分かる。
4Sの徹底を図ることが管理をしやすくすることに
つながる。
同時に箱の流れがスムースになる流し方にする
図 20 箱の置き場の分離
②生産管理板
右図のような生産計画と生産実績を、あるピッチで記入していく生産管理板を用いることが有効である。
ここには時間毎の生産実績や問題発生時の処理、
原因等が記入されているだけでなく、
過去の 高値や、目標値も記入されており、
モチベーション上も有効となる。
(ⅴ)多能工化教育
生産能力で各工程に半端工数(小数点以下の工数)
が発生する場合、工程を大括りにし、半端工数を
減らすよう改善しなればならない。
そのためには、工程間が距離的に近いだけでなく、
各作業者が多くの工程を担当できるように、
多能工(複数の工程を担当できる人)教育が必要
となる。第一ステップの改善案ではいくつかの半端工数が 図 21 生産管理板の例
発生しているので、レイアウト変更(レイアウト2)とともに多能工教育により、更に工数削減は可能である。
3-5-5 改善案の評価
(1)生産効率
効率はどれだけのインプットで、どれだけアウトプットしたかの比(アウトプット/インプット)で表わされる。
生産効率は生産高(生産量)/Σ(人員 x 時間)で計算される。
工程設備
仕掛中 空箱
運搬待ち 先行運搬
仕掛中
完成品
2箱以上積まない

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
89
アウトプットは 8 時間稼動、可動率 100%として、320 個、インプットは現状 113 時間・人、改善後 88 時間・人
と計算される。(計算表シート 2)
したがって、効率は現状 2.8 個/人・時間、改善後 3.6 個/人・時間となり約 3 割の効率アップとなった。
(2)リードタイム、加工時間比率
リードタイムは要求が生じてから、供給されるまでの時間で定義されます。
したがって、ここでは、材料供給の時点から計算することにします。
また、リードタイムを分類すると、加工に要する時間+運搬に要する時間+停滞している時間で表わされる。
加工に要する時間はその作業標準書に定められている時間を言い、能力とは異なります。
も注目しなければならないのは停滞している時間です。
停滞は在庫の所でも述べたように、①~③の原因で起こります。ですからこの逆を目指せばよいのです。
すなわち各工程の能力のバランスを取り、安全在庫を減らし、運搬ロットを小さくする、です。
計算表より
リードタイム 加工時間 加工時間比率
現状 2368.5 29.91 79.19
レイアウト1 606.8 20.83 29.13
レイアウト2 575.7 20.83 27.64
図 22 評価結果
(4)管理状態
生産能力が全工程 90sec とほぼ同一となり、スムースに流れるようになった。
機械工場内の多くの中間在庫、完成品在庫の山が無くなり、工程間在庫も床面に書かれた枠内のみとなり、
多くのスペースが削減された。洗浄工程の保全強化により完成品在庫も大幅な削減が実現した。
工程も集約され、一箇所に集結し、更に目で見る管理が可能となり、管理監督者だけでなく、その生産現場に
働く全員が、自工程だけで無く前後工程の進捗状況がわかるようになった。
以上が一連の検討結果であり、必ずしもフロープロセスチャートやオペレイションプロセスチャートを
フォーマットに基づいて書かなくても良いが
①需要と各工程の能力、投入リソースとの関係
②工程間在庫、工程内在庫、ロットの大きさ
③運搬の仕方
④管理の「見える化」状況
⑤改善前後の評価指標による比較
⑥多能工化の進展状況
については必ず検討することが必要です

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
90
3-5-6 工程分析
もうひとつ工程分析を演習してみましょう
今度はフロープロセスチャートも書いてみましょう。
(ⅰ)調査結果
観察した結果を忠実に記録していく。特に時間、距離、を明確にすること
機械職場からの出庫票に基づき、素材置き場に来た作業者 2 人は、素材置き場から 3m の位置に台車を止め、
素材を運搬台車に一本一本載せ始めた。一本載せるのに約 30 分掛かっている。
一回に運搬台車で運ぶのは重さから安全のため、素材 20 本と決められている。
乗せ終わると#301 の機械の脇まで、約 70m 運び、機械の脇の素材置き場に素材を下ろした。
こちらも台車は 3m よりは近づけないため 2 人がかりだ。
降ろし終えたが、一向にその素材を使う気配が無い。
運んでいた作業者に聞いてみると、材料運搬は機械加工開始の 4 時間前に行うというのである。
『なぜそんなことするのだろう、材料の顔を早く見ておかないと心配なのかなあ』と思いながら、
加工開始まで、物の流れるスピードを確認するために、工務部に行き、生産計画を確認した。
担当者に確認した所、年間生産量は 100,000 個、一日 8 時間、250 日稼動で計画しているとのことであった。
機械加工は穴あけ、孔ぐり、タッビング、更には座ぐり、やすりかけと一連の作業後、切断し、完成する。
一本の素材より 50 個のバルブ本体が作られる。
作業が始まって、一台の機械からは 3 分後に初品が出、3 分に一個づつ完成品が出てくる。
機械と作業者は3台、3人で、同じ仕事を並列に行っている。
工程完成品 240Ⅹ360Ⅹ160 の箱に 10 個収容され、30 箱単位でバリ取り工程へ送られる。
ところが完成品置き場には既に 4 時間分の在庫が置いてある。
聞くと、不慮の事態に備えて常時 4 時間分の完成品在庫をおいて、後工程に迷惑をかけないようにしているのだ
と言う。
次のバリ取り工程の職場は同じ機械工場にあり、100m ほど離れた所にある。
この作業をしている作業者は、組織的には同じ機械課なのだが、仕上げ組と言って、機械加工とは組が異なって
いる。行ってみると、こちらにも前工程の完成品(機械加工完了品)が置いてある。
どうしてここにあるのか聞いて見ると、仕事の遅れ進みがあるから、ここに 1.5 時間の在庫を置かないとスムース
に仕事できないと組長が説明してくれた。
一個バリ取りするのに約 30 秒、そしてまたここにも仕事を完了したこの工程の完成品が 2 時間分置いてあった。
再び質問したが、予想通り、先ほどの機械置き場の答えと同じだった。
次の工程はどこかと、完成品を取りに来た運搬について行くと、また#301 の方へ逆戻りしていく。
運搬のロットサイズは同じく 300 個である。着いた所は先ほどの#301 の隣のドリル・プレスであり、距離はバリ取り場
から 105m である。比較的小さい機械で#301 よりは機械も人も少ないようだ。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
91
ここにもバリ取り完成品が 2 箱積んであった。
箱から取り出されたバリ取り完成品は 3 分後にはドリルプレス工程完成品となって出てくる。機械は一台である。
他の工程と同じように工程完成品が 4 時間分積まれている。
ここを過ぎると検査場に運搬される。検査は外観特にバリが無いかと、ノギスによる寸法チェックで 1 分に 2 個でき
る簡単なものだ。これらの運搬も 300 個単位で行われる。検査場はドリル・プレスのすぐそばにあり、距離にして 30m
くらいである。
検査後、この半完成品はバルブの命ともいえるバルブシートのラッピング工程の前に、一旦倉庫に保管され、
需要に応じてラッピングに回されるが、平均すると 2 日位倉庫で眠っていると言われている。
この倉庫は機械工場が手狭になり、敷地の端に新しく建設されたため、機械工場からほぼ 1 キロ、ラッピング機械か
ら 850m もあり、運搬からいつも何とかならないかと言われている。
ラッピング作業者はバリ取りと同じく、仕上げ組である。
需要が確定すると 、300 個単位で倉庫より戻され、いよいよシート・ラッピングに入るが、あたり面の摺り合わせと
テストで、1 個づつ流している。一個当たり 10 分もかかる。8 台の機械が並び、並列に作業が進行している様子は、
壮観である。
ここも他と同じで工程の前には前工程完成品が 1.5時間分置かれており、本工程完了品が 2時間分置かれてい
る。
ラッピング後、外部を塗装するのであるが、塗装は 100 個単位で運搬され、塗装ブースが故障すると、復帰に長
時間必要な事もあって、前工程品を 4 時間分自工程に置き、完成品は 40m 離れた包装場へ 100 個単位で持って
行っている。一個当たり塗装では 2.1 分かかる。塗装ブースへはチェーンに固定された部品用ハンガーに、
部品の内側をマスキングして一個づつ吊るされる。
塗装された半製品は、簡易包装のため、包装場に運ばれる。包装場には 3 時間分の塗装完了品が在庫として置
かれ、作業者が簡易包装をする。包装は 0.6 分の工数がかかる。
包装が完了するとコンベアで組立部門倉庫へ運ばれる。倉庫では平均 2.5 日在庫された後、組立ラインに送ら
れるものと、補給品としてお客へと発送されるに分けられる。
組立は部が異なり、組立部となっている。
バルブに必要な購入品や、機械部で作られた部品を、この組立工場にあるこの倉庫に保管している。
バルブ組立ラインの要求にしたがって、かんばんシステムで供給されている。
後に、工務部に行き、現状の需要及び今後の見通し、稼動計画と稼動方針を確認したが、
工務部長より下記の説明を受けた。
・現在は年間 10 万台のベースで需要は安定している。
・季節商品でもないので、月割りで計画している。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
92
・稼働日は 250 日とし、日当たり 8 時間稼動で、工程により若干のばらつきはあるかもしれないので、
細かい話は製造部長に任せるが、できるだけ、定時の 8 時間稼動で作って欲しい。
・そのための改善に必要な 低限の出費は認めるが,大幅な設備投資は認めない。
(ⅱ)以下の内容は、一度自分で、フロープロセスチャートを描き、改善の検討を行い、改善計画を立案してから
確認の参考としてから読んでください。
1)改善の方向性と目標の設定
観察を行い、FPCに書き上げてから、この例題ではやたらと停滞や貯蔵が多いと気がつきましたか。
なぜなのでしょう。「流れ化」が出来ていない事によります。
まずここに気がつくことが、IE エンジニアとして実践力が付いた人(出来る人)と言えます。
ここでは主に
㋑組織の問題、
㋺生産量と設備能力の整合性の検討不足、
㋩レイアウト上の問題、
㋥検査方法、
が流れ化の実現を妨害していると、観察記録より推測されます。
改善の方向性(テーマ)をリードタイム短縮、工程間在庫の低減に置いたら、
次に今回の改善の目標(評価指標)を設定しなければなりません。
目標を設定するには、その指標の現在の値(現状)を知らなければなりません。
そのために現状を調査し、フロープロセスチャートに記述するのです。
ここでは、この課題の
仕事の掛かりから組立工程倉庫に収まるまでの時間(リードタイム)と
加工時間比率を評価指標として、
現状と改善目標、および改善後の値を評価するのが良いと思います。
2)改善方法の具体性
皆さんの改善方法は総じて具体的になっている人は少ないと思います。
キーは、どうやって(HOW)目標を達成できるかの手段が明確になっているかと、
なぜ今までそれが出来なかった(現状)のに、今回出来るのかの記述が無いからです。
(殆どの人がそうだと思います。)
例えば「貯蔵をなくす」とだけ書いたとしても、それは方法ではなく単なる希望です。
今仕事をしている人も馬鹿ではありません。
今まで必要だからあったのです、何か改善しなければ、不必要にはならないはずです。
どうすれば、無くせるのか考えて計画することです。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
93
ここまで言及していなければ、改善は実現しません。
3)改善のための検討内容
今回の調査結果での検討のプロセスの一例を示します。
①必要能力と設備(工程)能力の検証、設備能力と在庫
第一にやらなければならないのは必要能力(需要)に比べて、
各工程の設備(工程)能力がぎりぎりなのか、余裕があるのか、足りないのか、今後それがどうなるのかを
検討する事です。
必要能力は、100,000/(250*8)=50/h、一時間に 50 個、つまり 1.2 分(0.02h/個)のタクトで作れば良いのです。
各工程の能力との関係はどうでしょうか。(表1)
工程の能力はタクト内で、バランスが取れていなければなりません。
能力のある工程なら、多くの工程完了品を在庫とする必要が無い、のは想像できますよね。
能力の無い工程の前後には多くの在庫を持ち、稼働時間を長くして挽回するか、設備投資や人員追加等の処置を
して生産能力を上げる必要があります。
これを解決しない限り在庫は減らせません。
必要能力 機械加工 バリ取り ドリルプレス 検査 シートラッピング 塗装 包装
1.2 分 1.0 0.5 3.0 0.5 1.3 2.1 0.6
表1.必要能力と現状の各工程能力
必要能力を確保するために次の方策を採ります。(仮定)
ⅰ)ドリルプレスを2台購入し、能力を 1.0 分に上げる。
ⅱ)塗装のハンガーを改造し、従来1個掛けを2個掛けにし、能力を 1.05 分にする。
ⅲ)シートラッピングは機械が高価なので、とりあえず残業で対処する。
以上を行うと、能力は表2の如くなる。
必要能力 機械加工 バリ取り ドリルプレス 検査 シートラッピング 塗装 包装
1.2 分 1.0 0.5 1.0 0.5 1.3 1.1 0.6
表2.必要能力と設備能力変更後の各工程能力
ここでは、能力の無いシートラッピングの前後には能力差調整用の在庫が必要となります。
しかしそれは5分(1/12h)で、数としては5個程度で良い。
②組織と在庫
次に組織の話に気がついてほしいのです。
①で設備能力をあわせても、
加工組、仕上げ組、と組織が異なるために、他組織に迷惑をかけるわけにはいかないので、
勢い工程完成品在庫や仕掛前在庫を保険として多く持つことになります。
ここでは組織の統合が必要です。加工組と仕上組を一つの組にしてしまう必要があります。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
94
検査と作業組の間でも組織の壁があります。しかし『品質は工程で』と考えると、
簡単な検査は作業組で行い、品質保証すれば良いのです。
③ロットサイズと在庫
ここでは加工する補助バルブが一種類なので、関係ありませんが、何種類かあったらどうでしょうか。A、B、C と種類
があり、ロットサイズが大きいとリードタイムが長くなります。
段取り替えや材料交換などのラインストップも夫々の工程で異なるので、そのための工程間在庫も
必要となります。
④順序作業の制約
次の工程の設定に入る前に、順序作業の制約を確認する必要があります。
夫々の作業の先行関係がどうなっているかの確認です。
例えばXの作業を行う前には、Yの作業を行うことが出来ないとか、(ここでは機械加工する前に
バリ取りは出来ないし、ドリルプレスも出来ないが、ドリルプレスと仕上げ作業は先行関係が無い)
作業内容の順序の制約があるのか無いのか、これは若干の固有技術知識が要ります。
⑤工程の確定と記述
④が完了したら工程の確定に入ります。
ここでは機械加工→ドリルプレス→仕上げ、検査→在庫→シートラッピング→在庫→塗装→包装
とすることになります。
シートラッピングの機械を一台設備投資すれば、更に前後の在庫を止めることが出来ます。
後に包装の仕事が半端工数なので今後の改善検討項目とします。
⑥レイアウト変更
次にレイアウト変更です。工程間在庫を 小限にし、工程順序の改善をした上で、動線を短くする
レイアウトを作成し、現状と比較します。
レイアウト変更はまず、設備が大きく、移動に投資が必要で、今回見送るものを固定します。
ここでは塗装ブースとシートラッピングがその対象でしょうか。
それに対し、出来るだけ離れ小島を作らず、人のいる作業場を固めて配置することです。
今回は現状のレイアウトは、提示されていませんが、記述を見れば、
推定で現状と改善後のレイアウトがかけるのではないかと思います。
⑥改善後のFPCの作成
出来上がった改善報告書の基に、改善後のFPCを仕上げ、前後の比較をします。
⑦目標に対する達成度
出来上がった改善FPCより改善案の目標に対する達成度を評価します。
達成していなければ更なる改善を計画し、目標を達成するめどが立つまで検討します。
しかし、実施が遅れれば、その間の利益がなくなってしまうので、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
95
一次計画として実行に移すことも考えられます。
以上の手順を踏み、工程改善が行われます。
無論、目標が異なれば、また異なった手順を踏むことになります。
くどいようですが
FPCに限らず、IE の解析に使う手法やチャートは作るのが目的ではなく、より良い改善を行うための”道具”で
あることを忘れないようにしてください。
ここまで行った演習結果を提出してください。
後に
現状では、ここでできた製品は組立ラインへコンベアで送るのであるが、
これは組みつけられるラインへ送られるのではなく、倉庫に保管され、60 時間も寝ているのである。
(設備が壊れて組み立てラインを止めるのを恐れて、2日の以上の在庫を持っている。)
倉庫に眠らせるために、コンベアで急いで運ぶのであり、且つ押し込むのであるから、全くのムダであり、コンベアで
直結する必要性も無い。是が非でも改善すべきである。
まず機械工場内に補助バルブの店を持ち、4 時間程度(一応とりあえず、
従来の信頼性データを基に設定)の在庫を持つ。
組立のライン側と店との間は定期便を走らせ、かんばん(別途講義した方法)で引取りを行う。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
96
4.テーマ実習の進め方
ものづくり知識創造学テーマ実習の概要
(Ⅰ)工場見学、問題発見シートの記述
(Ⅱ)問題発見シートの整理
(Ⅲ)問題発見内容の発表
(Ⅳ)テーマ課題Ⅰ(クランクシャフトライン改善)説明
(Ⅴ)クランクシャフトライン現状調査
(1)フローチャート作成
(2)各要素作業タイム測定、サイクルタイム測定
(3)各工程サイクル線図作成
(4)ラインバランスとボトルネックの把握
(5)工程間在庫、完成品在庫、原材料在庫,測定
(6)生産指示方法、仕掛かり指示、加工品種指示方法の調査、記述
(7)物と情報の流れ図作成
(Ⅵ)改善目標の設定と改善具体的方法立案のための調査
(1)ライン改善目標の作成(リードタイム、サイクルタイム、工程間在庫、完成品在庫、原材料在庫)
(2)ネック工程の詳細観測と測定
(3)ネック工程のサイクルタイム短縮のためのシーケンス調査、連合作業分析
(4)ネック工程のサイクルタイム短縮のための具体的改善計画の作成
(5)生産指示方法、仕掛かり指示、加工品種指示の提案作成
(Ⅶ)テーマ課題Ⅱ(織機組み立てライン工作図の作成と利用)説明
(Ⅷ)現状の需要とサイクルタイムの検証
(Ⅸ)工程別要素作業の観測、測定
(Ⅹ)工作図の作成
(Ⅺ)現状の山積み表の作成
(Ⅻ)サイクルタイム変更時の工程変更実践

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
97

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
98
(第8回)実習第一週
(テーマ)改善対象工程のフローチャートの作成
実習の課題は、クランクシャフト加工および組付工程を組立ラインに同期した生産方式にするための改善策を
提案することです。
・当日の活動内容
1限目の活動内容
実習テーマの内容把握、行動目標との関係理解
講師の説明を聞き、テーマ実習の内容を理解し、取り組む問題を把握します。
製品構成、対象部品等についての説明を行います。
2、3限目の活動内容
1.工程の概要説明
クランクシャフト工程の概要について講師が説明します。
・2.現場の確認と状況把握
現場で工程を確認し内容および問題点の把握を行います。
講師の工程概要説明を現場で確認し、工程の理解を深めて下さい。
4限目の活動内容
講師の説明および現場確認に基づき、クランクシャフト工程のフローチャートを作成します。
第8回でのアウトプット
クランクシャフト工程フローチャート

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
99
(第9回)実習第二週
(テーマ)ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図の作成①
改善を行うためには、まず現状を把握し問題点を見つけることが重要です。
現状とあるべき姿のギャップが問題点ですので、現状調査・分析が改善の出発点となります。
事前学習
クランクシャフト工程の理解を踏まえて、ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図を作成しますが、調
査の担当、内容等を決めておいて下さい。
各図表の担当およびグループのリーダも決めて下さい。
第4~6回で学習した、ものと情報の流れ図、ラインバランスについて復習しておいて下さい。
・当日の活動内容
1限目の活動内容
生産指示方法について講師が説明します。
ものと情報の流れ図を作成する際の、情報の流れに必要のものとなります。
受注から出荷までの業務および情報の流れ、および工程への生産指示方法の概要を理解して下さい。
2~3限目の活動内容
ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図を作成するための調査を行なっていただきます。
事前に決めた担当、調査内容に従って効率良く調査して下さい。
(注意!!)質問を受けるのは、指定した者に限定させていただきます。
現場作業者に直接インタビューするのは避けて下さい。必要な場合は、講師に許可を得て下さい。
1. ものと情報の流れ図
生産指示方法の講義内容の現場での確認、仕掛品量の調査等を行ないます。サイクルタイムについては、
ラインバランス表、サイクル線図を書くための担当者と情報交換して下さい。
2. ラインバランス表、サイクル線図
各工程の加工サイクルタイムについては、事前にビデオ撮影してありますので、これを活用して下さい。
これ以外の調査が必要な場合は、講師と相談し現場での測定を行なって下さい。
4限目の活動内容
本日の調査内容の中間まとめを行なって下さい。次回も調査の時間がありますが、今回の調査を踏まえて
次回の調査の計画を確認・調整して下さい。
第9回でのアウトプット
ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
100
次回に各図を完成していただきますので、次回の追加調査等が効率的に実施できるよう、書ける部分まででかまい
ませんので書いてみて下さい。
(第 10 回)実習第三週
(テーマ))ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図の作成②
今回で、ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図を完成させていただきます。
事前学習
前回に引き続いて調査および各図表の作成を行なっていただきますが、前回の活動を踏まえて効率的な活動と
なるようリーダを中心として計画を調整・見直しして下さい。
現場で測定できないデータがありましたら、事前に講師に連絡・相談下さい。
・当日の活動内容
1~4限目の活動内容
各工程の調査の続きを行ないます。
5限目の活動内容
調査が完了し次第、図表の作成に取り掛かってください。
次回以降の改善案作成につながるよう、問題点の把握が出来るように留意して下さい。
・ラインバランス表、サイクル線図のフォーマットは準備してありますので、これを利用し作成して下さい。
第10回でのアウトプット
ものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図
今回は、完成したものを提出して下さい。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
101
(第11回)実習第四週
(テーマ)改善項目・目標の作成、ネック工程詳細調査①
現状調査に基づき、何があるべき姿に対する障害になっているかを考え、改善項目とその目標値を設定します。
事前学習
前回作成したものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図に基づき、クランクシャフト工程の改善目標を
考えてみて下さい。
・当日の活動内容
1~2限目の活動内容
クランクシャフト工程の改善目標(リードタイム、工程間在庫、完成品在庫等)を作成し、発表していただきます。
改善目標とものと情報の流れ図、ラインバランス表、サイクル線図の関連を講師と共に確認し、必要であれば見直し
を行います。
3~4限目の活動内容
1. ネック工程の確認
目標が決定されたら、これを達成するために障害となっている工程(ネック工程)を確認し、ネック工程を
詳細に調査・分析する計画を立てます。リーダ、担当等についても決めておいて下さい。
具体的改善案につながる調査・分析が必要となりますので、調査内容を十分検討して下さい。
改善案作成のためには、ネック工程以外の工程の調査も必要となるかもしれません。
人-機械、人-複数機械等の連合作業分析やサイクルタイム短縮のためのシーケンス調査等が必要になります。
2. ネック工程の調査
計画に基づいてネック工程の詳細調査を実施します。
今回の調査を終えた後に、調査内容の振り返りを行なってください。
改善のために適当な工程の調査ができているかを確認し、必要な場合は調査計画の変更・調整を行ないます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
102
(第12回)実習第五週
(テーマ)改善項目・目標の作成、ネック工程詳細調査・分析②
改善に対する障害を除去するための改善案を検討するための分析を行います。
・当日の活動内容
1~3限目の活動内容
引き続きネック工程を主とした詳細調査を実施します。
前回の調査を踏まえて、効率的かつ効果的な調査を行なって下さい。
4限目の活動内容
1. ネック工程の分析①
前回および今回の調査に基づき、現状のシーケンス図、連合作業分析表を作成します。
調査完了分から随時、図表の作成を行なって下さい。
2. ネック工程の分析②
現状のシーケンス図、連合作業分析表により現状の問題点の把握と改善点の検討を行なって下さい。
次に、改善後のシーケンス図、連合作業分析表を作成し、改善効果を見積もります。
第12回でのアウトプット
現状および改善後のシーケンス図、連合作業分析表および改善効果の算出。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
103
(第 13 回)実習第六週
(テーマ)改善計画の作成および予想効果の算出、提案資料の作成
事前学習
前回までの調査・分析に基づく改善案についてネック工程の改善以外にもクランク工程全体の改善について
討議し、アイデアを数多く出しておいて下さい。
改善目標達成のための方策として、ネック工程の改善のみならず、レイアウト、工程への情報の出し方等などを
検討する必要があります。
・当日の活動内容
1~2限目の活動内容
改善案の作成および予想効果の算出。
これまでの調査・分析内容を再確認し、改善計画を作成します。
出来るだけ大きな投資に頼る改善ではなく、作業の内容やもの・情報の流れを変えることによる改善を
主眼にしてください。
すなわち、短期間に実行可能な計画が望ましいことになります。
リードタイムを短縮する改善を大別すると、以下のようなものがあります。
・ 個々の仕事時間を短くするための改善
・ 仕事のオーバーラップを増やすための改善
・ 情報の伝達を早く、正確に行い、コントロールを的確に行なう改善
・ 管理を的確に行なう改善
改善計画の中には、工程の評価指標(改善のみえる化)も検討して下さい。
また、ものと情報の流れ図の改善後の姿も描いて下さい。
製造部門、生産技術部門、生産計画部門の者を同席させますので、
インタビューが必要な場合は、活用下さい。
3~4限目の活動内容
改善計画をプレゼンテーションするための資料を作成します。
プレゼンテーションの内容は、 低下記のものを含む必要があります。
ⅰ.メンバーの紹介
ⅱ.リードタイム短縮の意義、必要性
今、全社的プロジェクトとして、なぜリードタイム短縮に取組まなければならないか。
ⅲ.リードタイム短縮が会社に与える影響、効果の予測
会社全体に対してマクロな観点から説明、必ずしも定量性を必要としない。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
104
ⅳ.モデル工程のリードタイム分析
改善前、後を視覚的にわかりやすく説明
ⅴ.現状の問題点
・ リードタイムに対し、何が、どの程度悪さをしているか
・ なぜ問題か
を明確にする。
ⅵ.このプロジェクトが目指す目標
ⅶ.目標を達成するための改善実行計画
ⅷ.計画実行に対するフォロー体制および改善効果を測る指標
ⅸ.オーソライズ(模擬)
第13回でのアウトプット
提案書、プレゼンテーション資料

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
105
(第14回)実習第七週
(テーマ)中間発表およびプレゼンテーション資料の見直し
事前学習
前回作成した改善計画およびプレゼンテーション資料を十分に再検討、見直しを行なって下さい。
・当日の活動内容
1~2限目の活動内容
中間発表を行なっていただき、講師が内容のチェックを行ないます。
これまで学んだことが生かされているか、計画の実行可能性等について評価します。
3~4限目の活動内容
中間発表のチェックに基づき発表資料の見直しを行ないます。
第14回でのアウトプット
提案書、プレゼンテーション資料

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
106
5.ケーススタディの進め方
(Ⅰ)ケーススタディ学習に当たって
ケーススタディは講義と実習を繋ぐ疑似体験の場です。
講義で習ったことの理解を深め、実習での改善実践の助けになるものです。
自らが、ケースの主人公になったつもりで、このケースに現れた現場を改善する意気込みで、ケースを読み、
重要な部分を拾い出し、その後、課題に答えて、何を考えて、行動すべきか考えてください。
一般的にはケーススタディは、事実のみを記述して、グループでディスカッションをすることが目的で、
その中で、考える力が養われるとされていますし、それが目的だとされています。
しかし、『ものづくり知識創造学」ではそれぞれのケースには、テーマがいくつか混在しており、
そのテーマについては、「このように考えるのが成功の確率が高いですよ、ここを確認してくださいね」
と言っています。
それに気付くことによって、他の場での行動に差がつくと考えています。
ケースの中で、結果ではなく、主人公や関係者が、プランをどう作成するかの意思決定を行う際、
あるいは行動する際、何を考慮し、何をトリガーとして決めているのか、
そのプロセスをよく読み取ってください。
プロセスにある要件が、必ず、今後の自分の行動や意思決定に参考になるはずです。
講座を有意義に行うために、自学自習がキーポイントになります。
厳しいスケジュールですが、学習指導書にしたがってやるべきことを必ずやる決意で臨んでください。
(Ⅱ)使用するケース文
講座の時間内では以下の 4 ケースを用います。
①C1:『ケース 14:津田工業』
実習企業の製造現場を改善しようとしている二人の技術者の体を借りて、問題意識と、彼らの行動、および
思考プロセスを、表現しています。たぶん受講者の皆さんも、同じような立場で、同じような問題意識で、
日々悪戦苦闘して、製造現場のオペレイションの改善を目指していることと思います。
今回の実習のために、何が問題で、彼らはどう行動すべきと考えているのか、その思考過程と行動の変化を
しっかりと読み取ってほしいと思います。
あわせて、実習企業の様子や、雰囲気もつかみとり『実習テーマの問題解決にも参考になれば』、と考えて
います。
②C2:『ケース 15:大川製作所』
大量生産を伴わない個別受注型産業(装置産業等)や、中種中量生産の製品の加工、組み付け型産業

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
107
において、生産性やリードタイムの観点からどのようなオペレイションが必要なのであろうか。
そして、量産型と比較し、脆弱とされる仕入先は零細企業が多く、存続すら危ぶまれる状況の中で
その管理は今後どのような観点から考えるべきなのであろうか。
そしてその手法として昨今用いられているひとつの方法についてスポットライトを当ててみた。
このケースを通じて、リードタイムの重要性や、組立集約型産業とそこに部品を提供する中小企業のあり方
について考えていただきたいと思い、取り上げました。
③C3:『ケース 10:競争の激化と商品種類』
顧客の価値観の多様化と、買い手市場の現実は企業間の熾烈な競争を生み、その競争に勝たなくては
存続出来ない時代となり、その結果、商品の種類が増加の一途をたどっています。
一方、部品や製品種類の増加はその量産効果を消滅させ、コストを圧迫し、企業業績を落としかねない
事態を生んでいます
製造現場は段取替増加を嫌い、ロット生産に走りがちで、工程内、および工程間在庫の増大を生み、
運転資金の増大を生もうとしています。
組立型産業では、誤組付に悩まされ、作業者の精神的ストレスが増大しています。
このケースでは商品種類の適正化を『プロジェクトとしてどう展開していくか』に焦点を当て、
プロジェクトの進め方について考えてもらおうと思っています。
実習では、プロジェクトを進めるという観点での模擬実践は難しいので、このケースで、
テーマ実習の「プロジェクト進め方」を学んで欲しいと思っています。
③C4: 『ケース 9:販売と生産のコンフリクト』
受講生の皆さんは生産関係の方が多いと思います。
このケースでは、販売と生産のコンフリクト(紛争)を取り扱っています。
生産と販売はいわば富を作り出している車の両輪のようなものですが、その立場の違いがあり考え方や
重視する点が大きく異なり、その結果、いろいろな場面で、意見の衝突が生まれます。
これをコンフリクトと呼んでいます。
このケースではこのコンフリクトが生まれる過程を書くことによって、その立場の違いを明白にし、
それぞれの立場を理解し、自分の立場を理解してもらうことやシステムの機能によってそのコンフリクトを和らげ
る状況を描いています。生産サイドの受講生の皆さんには両者の立場を理解してもらうことを期待して
このケースを取り上げました。
なお、このケースは講義では行なわず、レポートとし、提出することにより、ケーススタディ終了とし、
成績査定の対象とします。
(Ⅲ)提出物の再配布
皆さんからいただいた提出物(C○S2、R:記号は後記参照)は、事務局で整理して、全員に再配布いたします。
他のメンバーがどう考えているか、よく読み、
自分の気付きの参考にして、自分のレベルアップに活用してください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
108
(Ⅳ)各週の進め方
ケーススタディは第2回から第4回まで4週にわたって、次のステップで進めます。
細部は各週の進め方を参考にしてください。
(ⅰ)事前学習
与えられたケース文を三回程度読み(多いほうが良い)、重要な部分と感じた部分を、なぜ重要と感じたかを含め
て、抜き出します。C○S1、S2、R を仕上げてきます。
(ⅱ)講座 1 時間目(C○S1T、S2T の作成)
C○S1、S2 のグループ討議:事前学習にて持ち寄った C○S1、S2 をもとにグループ内で討議し、
発表用にまとめます。
(ⅲ)講座 2 時間目(C○S1T、S2T の班別発表および議論)
1 時間目のまとめを基に、各班が交互にその内容を元に討議を行います。
主に、重要と感じた部分の内容や経験の違いを議論します。
(ⅳ)講座 3 時間目(C○RT の作成)
C○R のグループ討議:事前学習にて持ち寄った C○R、をもとにグループ内で討議し、
発表用にまとめます。
(ⅴ)講座 4 時間目(C○RT、の班別発表および議論)
3 時間目のまとめを基に、各班が交互にその内容を元に発表し、討議を行います。
(ⅵ)講座 5 時間目(講師よりの解説の聴講)
後に講師より、受講者に何を築いてもらいたくて書かれたケースなのか、何を理解してもらいたいのか、
何を今後応用してもらいたいのか党の解説を行なう
(Ⅴ)その他
様々の立場でのケース文や、学生の作成したケース文等、今回使用以外のケーススタディ文(筆者もしくは学生
創作)が沢山あります。
課題に対する意見を自分なりにまとめることを前提に提供しますので、やる気のある受講者は申し出てください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
109
第2回、第3回 (ケーススタディ一、二週 )
ここではケーススタディ第一週目の進め方細部を示します。
第三週は S1、S2 の討議、議論は行なわずに RT のみ行ないますが、進め方は同様です。
以下説明は右の凡例の記号を用います。
凡例
2 回
講義前提出物 : C1S1、C1S2、C1R、 ケース1の S1 フォーマットのチームレポート(無しは個人)
講義後提出物 : C1S2T、C1RT ( S1,S2,R ) :R は課題レポート
3 回
講義前提出物 : C2S1、C2S2、C2R、
講義後提出物 : C2S2T、C2RT
全員必ず実施して受講してください。未実施では班内の他のメンバーにも迷惑がかかります。
課題は大きく分けて 2 種類あります
S1,S2 と呼ぶ「重要な部分の抜き出し」 と R と呼ばれる「課題』です。
それぞれ、フォーマットを決めておきますので、
・それにしたがってプリントアウトしたものと
・データとして USB に格納したもの を持参してください。
①ケースの文中、自分が重要だと思ったことを抜き出し、その理由を明記する。(受講前提出物*S1)
本講座では、リードタイム短縮上重要と思ったところを抜き出してください。
・ケース原文の重要ポイントを網掛けし、斜体に変更します。
・その後ろに□で囲ってその理由(なぜ重要と思うのか、何に気付いたか、自分の職場ではどうか)
を明記します。
②抜き出し部の一覧表を作成します。(受講前提出物*S2)
記入内容は、下記をエクセルの表形式に表す。(後出S2の具体例参照)
ⅰ.ページ行、ナンバー
ⅱ.文の内容(長い場合は書き出しと書き終わり)
ⅲ.重要と思った理由
ⅳ.自分の職場との比較
講座開始前に講義用パソコンに入力するので、データはUSBに入れて持参してください。
また、各自パソコン持参のこと。
③課題に対する自分の考えの整理
C1 S1 T

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
110
*S1の具体的事例
下記にS1 の記入例(安全に対する重要ポイント)を示します。
10 どうも日曜日にはトラブルが有って設置できなかったらしい。前川がなにやらス
ーツをビシッと決めた営業風の男と話している。えらい好対照だ、前川の方はグ
リスで右半分汚れた作業服に帽子である、どうも何で日曜に来なかったのかと怒
っている。しばらく話していたが、スーツは何度か頭を下げて帰って行った。沼
田は前川に恐る恐る近づいた。金曜日初めて前川に有った時こんな優しい人がい
15 るのかと思ったほどであったからである。「前川さんどうしたんですか。」「このコ
ンベア、日曜日の朝、ラインに入れようと吊ったら溶接部が折れて落ちかかったん
だ、落ちたら怪我するかも知れない、良く見ると溶接が完全に出来てない上にペン
キ塗ってごまかしているんだ、すぐ来いって言ったんだけど、神戸からだと遅く
なるとか、技術の人間が出張中だとか言って、今日になって営業が来て、謝ったっ
20 てどうしようもないよ、製造なり、技術なりが来て、現物をしっかり見て、原因を推 測して、製造現場にフィードバックして、再発防止せんかったらまた同じ事にな っちゃう、安全の事なんで昨日はラインに入れずに朝メーカーに見せてから溶接し
直して入れるつもりだったけど、結局営業が見ただけで大丈夫かなあ、沼田君
このように、原文に加筆、追加修正しながら、自分の思う所を加えながら、説明していきます。 *S2の具体的事例
下記にS2の記入例を書いておきました。あくまで例です。
ページ no. 文の内容 重要と思った理由 自分の職場との比較
P10L20~22 製造なり技術
~ なっちゃう
安全は製造現場にとって第一
再発防止が出来なければなら
ない
事故報告書を自分が書くだけ
仕入先にきちっと再発防止策を説明
させるべき。
以下続く
・S1,S2 を各人が自学学習で作ってこないと、このケーススタディは無駄な時間となってしまいます。 各自、ケースを熟読して充実した S1,S2 を作ってきてください。
安全が製造現場にとって
も重要なのに問題を再
発させない保証はどこに
も無い。全体の性能は再
発防止が出来るかどうか
にかかっている。
自分達の職場では事故
報告書は書くが、メーカー
にはそれほど厳しくない。
仕入先にも再発防止をど
のようにするかきちっと説
明させるべきだ

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
111
2.当日の進め方
①C1S1、2のグループ討議と整理 45 (分:概略の時間配分)
②C1S1T のプレゼン、全体討議 45
③C1Rのグルプ討議と整理 45
④C1RT のプレゼン、全体討議 45
⑤C1の解説、および C2課題の説明 45
1限目
Ⅰ)グループ別討議①
各班の打ち合わせを行います。
・1限で打ち切りますので、開始より少し前に集まり、班別に討論を行うことを勧めます。
・発表、質疑、質疑回答、書記の分担等、役割分担をリーダーの采配で決めます。
リーダーは全員が均等に機会を得るように配慮します。
ケーススタディの も重要な部分はこのディスカッションの部分だと筆者は考えています。
グループ討議を通じて、自分の物の見方や考え方を説明し、他人のそれを聞く事によって、相互に啓発しあい、
自分の物の見方や考え方をレベルアップすることを期待しています。
・C1 について、各人の持ち寄った C1S1、C1S2 を突合せ、議論をしながら、
全員の意見を集約し、全体を C1S1T、C1S2T として、仕上げます(*C2S1T)
2限目
Ⅱ)C1S1,2T の発表と討議②
複数の班が存在するとして、発表は2つの班とし、5 ページをめどに、交互に S1 を説明し、
自班と違う部分については討議します。
発表(プレゼン)班
①C1(C2)を S1T、S2T に基づき、発表します。
順次くくりながら、プロジェクターで映し出された画面を見ながらプレゼンを行います。
プロジェクターを二台用い、S1,S2 を併行して写し出しながら、プレゼンするのがわかり易いと思います。
ⅰ.なぜ重要と思うのか、
ⅱ.何に気付いたか、
ⅲ.自分達の職場ではどうか の三点を中心に行います。
②全体を一気にプレゼンするのではなく、4~5 ページで段落を置き、他班と発表、聴講を交代します。
班のメンバーとの議論に入ります。
議論はまず、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
112
ⅰ。班により重要として抜き出した部分の相違している部分を議論します。
発表班で取り上げたが、聴講班では取り上げなかった内容、もしくはその逆の内容についてです。
聴講班から問題提起を行い、討論を経て、この部分は受講者として決着をつけます。
ⅱ。自分の会社での状況比較について意見を述べます。
・ 同じようなことがおきたら自分の組織体ではどうするだろうか
自分としては(もし異なるなら)どうすべきかの意見を言う。
・ 類似事例の紹介:自分の組織で類似の話があったが、どう対処された。自分はどう思った。
③書記(聴講班も同じ)
書記の役目は重要です。
発表の内容は書く必要ありません。
聴講班からの質門、それに対する発表班からの受け答えを記入していきます。
特に受講者の類似事例については詳細に記録します。
結論が出た場合には結論を、時間の関係で、中断した所を明記します。
④リーダーは、司会をとり、討議が完了したら次の 4,5 ページに移ります。
全員が均等に、スムースにプレゼンできるように采配を奮います。
時間を配慮し、質疑の進行をスムースに行います。(時には中断し、まとめを述べます)
終まで同様に進め、完了したら、司会は終了を宣言します。
聴講班
①プレゼンを聴いている人は、自分のパソコンに自班の S1T,S2T を映し出し、プレゼンターの発表と比較
しながら聞きます。自班と異なるところを、質門表に、説明に対する質門もしくは意見を書いていきます。
パソコンに同時入力できればベターです。
低でも、一人一枚は書きましょう。
②一区切り付いた所で、賛成意見、反対意見を述べ、討論に入ります。(発表班②に同じ)
討論は
・ⅰ自分達が重要として抜き出してないにも拘らず、発表された所、
・ⅱ自分達が重要として抜き出したにもかかわらず、発表者が飛ばした所
・ⅲ自分達と重要と考えた理由が異なっている所
・ⅳ自分の職場で類似のケースで、異なった展開となった所
が論点です。
発表班の司会の進行に従い、スムースに議論を進めます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
113
Ⅲ)班別まとめの討議と「S2T」の提出
これは課外で行い、レポートとして次回提出します。
まとめは自分たちの S2 をベースにして、全体討議終了後、各班の書記のメモを参考に、
チームで C1、C2 の 終版「S2T」として仕上げます。
フォーマットは各班 S2T と同様です。
次週の開始前に講座パソコンに入力した物を、事務局にてプリントアウトして、各人に配布します。
3限目
Ⅳ)グループ別 C1R 討義 ③
C1R について、各班の打ち合わせを行います。
各設問について、ひとつづつ班員の持ち寄った設問について自分の解答の要点を説明し、討議を行ないます。
1 限で打ち切りますので、S1、S2 同様様子を見て、次回事前討議を行なうかどうか協議して決めてください。
・発表、質疑、質疑回答、書記の分担等、役割分担をリーダーの采配で決めます。
リーダーは全員が均等に機会を得るように配慮します。
ケーススタディの も重要な部分はこのディスカッションの部分だと筆者は考えています。
グループ討議を通じて、自分の物の見方や考え方を説明し、他人のそれを聞く事によって、相互に啓発しあい、
自分の物の見方や考え方をレベルアップすることを期待しています。
・R について、各人の持ち寄った C1R を突合せ、議論をしながら、
全員の意見を集約し、全体を C1RT として、仕上げます(*C1RT)
4限目
Ⅴ)C1RT の発表と討議④
3 限にて行なった討議の結果まとめた C1RT を班毎に発表します。
発表は一課題ずつ、発表、聴講を交互に行います。
他班と表現や内容の違う部分を議論します。
特に内容が大きく違うところは、極端に言えば一方の意見に集約するほどの議論を重ねてください。
Ⅵ)班別まとめの討議と「C1RT」の提出
これは課外で行い、レポートとして次回提出します。
まとめは自分たちの C1RT をベースにして、全体討議終了後、各班の書記のメモを参考に、

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
114
チームで C1、C2 の 終版「C1RT」として仕上げます。
5 限目
(Ⅶ)今回のケースの解説(40)
講師より今回のケースの解説をします。
・講師はこのケースで受講者になにを気づいてほしくて書かれているのだろうか
・何をどう学んでほしいか
・今後の自分の仕事にどう生かしてほしいのだろうか
・重要な考え方、プロセスのポイントは?
等について解説します。解説書は当日配布します。
質疑の時間も含みます。
(Ⅷ)次回課題の説明と質疑④ (5)
みなさんの議論していただいたケースに対し、数項目の課題(R)を当日与えられています。
ケース文がしっかり理解されていれば、難しい課題ではありません。
重要なのは自分が遭遇している同じような問題がないか、考え、整理してみることです。
これは講師には出来ません。皆さん自身の問題なのですから。
「問題の所有者が もよく問題解決できるポテンシャルを持っている」
課外学習 R
この課題に対して、各自、一つの設問に対し、
①この設問は何を答えてもらいたくて、聞いているのだろうか
②このケースで何を学んで欲しいか、
③ケース文のどの部分が、この設問の回答を示唆しているところだろうか
④設問と同様なことを考えなければならないことが自分の職場でもあっただろうか、
その時どんなプロセスで、結論になったんだっけ? 本当はどう処置すべきなのだろうか。
⑤自分の職場で同様のことが起きていないか、
これに近い問題が将来おきそうな気がするがどうするか、どうやって決めようか
⑥自分は本当にTPSを理解できただろうか。理解している人はどう行動するだろうか。
等を考えて、答えてください。
事前にワード一問 A4 一枚(12ページ参考フォーマット参照)、もしくは ppt一枚程度に仕上げてください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
115
・課題例
課題の例を示します。
課題 ケース 10
夫々の設問に例題の内容について答え、
夫々の設問に対し自社で起きている状況と問題を説明しなさい.
1. 急増する商品種類そしてそれから引き起こされる部品種類の増加の影響で、
製造現場では何が起きているのか、箇条書きにして、説明を加えよ。
2. 例題では、適度以上の商品種類は、販売側についても必ずしも有利ではないと
言っているが、それはどのような意味か、具体的に例をあげて説明せよ。
5. 宮本の行ったベンチマークとは何か、
そして、ベンチマークを行う際、気をつけねばならない事を列記せよ。
6. 宮本は商品、部品種類の適正化の会議を招集したが、
会議の進め方で、学ぶべき点を述べよ。
9. 小林は、情報システムの観点からこの問題をどう捕らえているかを説明し、
この問題に対する情報システムをどう構築すべきと考えたのか、説明せよ。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
116
課題の記入フォーマットの一例を示します。
C○R記入フォーマット(個人事前学習用)
疑 問 に 思 っ た こ と
自 由 意 見
課 題 番 号 課 題 内 容
課 題 に 対 す る 記 述
班 氏 名 所 属
ケ ー ス 課 題 討 議 事 前 学 習 レ ポ ー ト

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
117
第4回(ケーススタディ第三週)
講義前提出物 : C3R、
講義後提出物 : C3RT (次回開始前)
2.当日の進め方
1,2 週とは少し異なり、S1 、S2 を行なわず、R から始めます。進め方はまったく同様です。
1 限目
①C3R のグループ討議と整理 45
2限目
②C3R の全体討議 45
3限目
③C3の解説,質疑応答 45
宿題
課外③C1RT 作成
課外ケース学習
C4 について、C1、C2、C3 同様に C4S1、C4S2、C4R を作成し、個人レポートとして C4S2、C4R のデータでの
提出を求めます。
このレポートを持ってケーススタディ終了とします。
提出は6週の講座開始前に講座パソコンに入力してください。
作成の要領はC1,C2、C3の時と同じ要領ですが、規定のフォーマットの表紙(別紙)をつけてください。
後に全員のレポートを事務局で印刷し、配布します。
班別討議は義務付けませんが、時間と熱意があれば、課外で班別討議を勧めます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
118
6.横展テーマの進め方
受講者はリードタイムに関する自社、あるいは自らが遭遇している問題に対し、
会場会社で行っているメインテーマの検討過程を応用して、自らが中心となって、問題解決を推進していきます。
院生は社会人とペアになって、社会人が取り上げたテーマを協力して解決していきます。
その中で、実際の問題に対する取り組み方を勉強していくことになります。
進め方は下記1~10 の如くですが、表紙に 初にお渡しするフォーマットの部分に相当するものを記入して、
その後ろに独自のデータや説明資料を加えて、個別面談に臨んでください。
個別面談の要領については、4.実習の進め方2ページを参照してください。
1.横展テーマの決定と登録
受講者はまず上司と相談し、横展テーマにどのような問題をテーマとして進めるか、決定します。
決定内容を規定のフォーマットに整理して、横展テーマの登録を行います。
第二週に横展テーマ登録書1、2、3、4,5,項を記入し、提出。
上司は受講者のテーマ内容を確認し、登録書にサインし、受講者の問題解決遂行をバックアップします。
2.現状分析
第三週講座前に、現状分析計画もしくは分析結果を提出します。
横展テーマ登録書6,7項記入し、業務フロー、問題の説明、重要性、緊急性について説明し、問題の定量評価
の出来た分を説明。今後の調査方針、分析項目を説明する。
可能な限り、データとし、図、表で作成してください。
3.横展テーマ登録書(全項目記入)提出
第四週講座前に、規定のフォーマットもしくはそれを参考にして、独自の登録書をデータで提出します。
(フォーマットは規定のものにこだわる必要はなく、独創的なものを歓迎しますが、記述項目は 低限
フォーマットにあるものを含んでください)
4.改善計画書の作成
第四週講座前に、規定のフォーマットもしくはそれを参考にして改善計画書を提出します。
登録書同様、独自のフォーマットでもかまいません。
5.実践と講義でのフォロー(実践上の指導、質疑)
講座期間中は、実習時間中に、個人別時間割を決め、その時間グループ討議から抜け出し、個人面談の形で、
講師と10分程度、改善計画書テーマの進行状況の報告や、進め方に対する質疑、アドバイス等を
テーマ登録書、改善計画書を基に行ないます。
①講座パソコンに前週分進行状況を入力します。
②講師との面談を行ないます。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
119
③面談内容を記録します。
6.横展テーマ(自己テーマ)発表会
第 11 週に中間発表会を行ないます。
これは発表の練習をする場ではなく、今までの横展テーマの進捗状況を他の受講者に聞いてもらい、
自分の気の付かなかったところを指摘してもらったり、参考意見を聞く場です。
自分の問題意識、達成すべきゴールをそれぞれの評価指標を明確にし述べること、現状分析結果を論理的に
述べることです。出来れば改善の方策や実施計画等も述べてください。
発表は ppt で行なってください。
また第 15 週に横展テーマ(自己テーマ)の 終成果発表会を、テーマ発表に引き続いて行ないます。
成果発表ですから、基本的には完了報告発表ですが、大きなテーマでは講座期間中に間に合わない場合も
ありますが、 低でも改善計画まではやり遂げて発表することが必要です。
発表時間は発表6分、質疑2分 /人 程度とします。
7.横展テーマの講座内での整理
全員の横展テーマの①テーマ登録書(別添)、②改善計画書(別添)、③中間発表会発表資料の三点を
事務局にて整理し、16 週目、反省会時に配布します。
8.講座終了後のフォロー
講座の期間の関係で、改善実施まで進めないと考えられますが、講座終了後に実践の進行に伴い、新たな質疑
があれば、メール等の手段で継続的に行います。
9.結果報告
プロジェクト完了後(中間発表での完了予定)、「横展テーマ結果報告会」を受講生の所属する組織体の中で、
実施してください。
発表内容は 終16週目に行なった発表に加えて、
「その後の実施状況」と「改善実施後のフォロー」、「改善の評価」、「今後の展開計画」とします。
講師も出来る限り参加しますので、メール等で連絡ください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
120
7.なぜ今重要でやるべきと思うか 付表:改善の効果の定量化
8.具体的な目標と評価尺度, 実施スケジュール
9.目標達成に必要な関連部署
10.目標達成のためにクリアしなければならない問題
3.テーマ名
4.テーマ概要
5.会社方針、部門方針との関係
6.従来のしくみの概要とその問題点
ものづくり知識創造学 横展テーマ登録書日付
1.氏名 上司認印
2.所属・タイトル

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
121
9.スケジュールと協力要請部署、要請内容
3.テーマ名
5.現状のリードタイム分析 付表:ガントチャート等リードタイムの内訳のわかる資料
8.具体的な改善実施項目と投資額および効果予測
ものづくり知識創造学 横展テーマ改善計画書日付
1.氏名 上司認印
2.所属・タイトル

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
122
7. 自己ケース文の作成
後のステップは、この実習の成果を知的財産として残す過程です。
あなた自身が、職場に帰って、何か困った時、あるいは後輩に『気付き』を与える時、
読み直せば、発表資料のpptからは得られない効果があります。
ガイダンスの記述と少し重複しますが、作成上の留意点を説明します。
受講者は2種類のケース文を書きます。
一つは講座でのグループ討議(含むインタビュー)に関するもの(ケース文 A)、
もう一つは横展テーマに関するもの(ケース文 B)です。
AとBではその目的が少し異なります。
Aはグループ活動によって、自分に新たな「気付き」が生まれた時、あるいは自分が他の班員に与えられた時の
様子と心の変化を具体的に表わすのが目的です。
受講者の知識、経験、性格等によって、その考え方や意思決定パターンも異なりますので、それを知る意味でも
有益です。
Bは受講者の次のプロジェクトを進める時の参考にするための資料であり、自分が次のプロジェクトを進める時の
参考や、受講者に続く後輩に対する指導書的な意味を持っています。
Ⅰ)グループ討議ケース文(A)
1.文の記述
文の内容は、グループでのテーマ実習(含むケーススタディ討議)での内容に限定します。
1週、 低でも A4 一ページ位は書きましょう。思ったことを単純に書けば良いのです。
後に全てを思い出してまとめて書こうとするとなかなか出来ないものです。
一日A4 1 ページ以上の実習での
①グループ討議での様子、
②印象に残ったグループ員の発言、
③ 終決定した記述に至るプロセス、
④自分の発言内容とその根拠、
⑤理解した内容等に限定して、
実習中はメモを取りましょう。
それを整理しながら、結果だけでなく、具体的などのようなプロセスでどのように意思決定したのかを
日記を書くつもりで、少し物語風に書いて見ましょう。
データを USB 等のメディアで持参して、講義前に講座用パソコンに入力してください。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
123
2.文の校正、追加
書かれた物を毎週講師とともに確認し、質疑をしながら、更なる気付きを書き加えていきます。
横展テーマの講座でのフォローと同時に、個人別に行ないます。
3.同一班員文の確認
第3週に一度班員全員のデータをまとめて、配布します。
4.自己ケース文 A の製本、配布
反省会時に、全員のコピーし、製本します。
Ⅱ)横展テーマケース文(B)
1.文の記述
文の内容は、横展テーマでの内容に限定します。
後に全てを思い出して、まとめて書こうとするとなかなか出来ないものです。
1週、1週、起こった出来事を中心に書いて行き、10週前に横展発表の資料と共に読み直して修正します。
データを USB 等のメディアで持参して、講義前に講座用パソコンに入力してください。
自分の組織体で、横展テーマがどのような経過で進んで行っているのか、
①自分の行動とその拠り所、
②周囲の関係者の思惑、言動とそれが自分の行動に与えた影響、
③テーマ推進のための打ち合わせや会議の様子、
④進展のターニングポイントとなった出来事や発言、行動、
⑤自分に新たな気付きが生まれた場面、タイミングとその時の背景、プロセス等
教材のケース文を参考にして作成する。(ケーススタディで、自分のケース文を作るつもりで)
それを整理しながら、結果だけでなく、何を考えたのか、関係者はどう思っていたのか、周囲の状況は
どうだったのか、等を中心に、具体的にどのようなプロセスで、自分はどのように意思決定したのかを
物語風に書いて見ましょう。
後輩を指導するには、理屈や説教では難しくても、先輩の経験した(中には失敗した)ケースを小説のように
読ませるほうがより深く理解してくれると私は思います。
2.文の校正、追加
書かれた物を毎週講師とともに確認し、質疑をしながら、更なる気付きを書き加えていきます。
横展テーマの講座でのフォローと同時に、個人別に行ないます。
3.ケース文 B の発表
第11週の反省会時に物語風にアレンジした自己ケース文を、説明を加えて話します。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
124
ワードで書いた文章に、重要ポイントに網掛けをするケーススタディS1 スタイルを推奨します。
プレゼント言うほど大げさなものでなく、紹介程度でかまいません。
事前に受講生および講師全員にコピーを準備し、配布してください。
10.横展テーマのケース文(ケース文 B)のサンプル
参考に、大学生が書いた(少し修正しておりますが)「段取り短縮」のケースを添付します。
少し自己陶酔型ですが、この程度の遊びがあったほうが、後輩の教育には受けるかもしれません。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
125
横展テーマケース文(B)サンプル
例12.徳山印刷
原作 山口真矢 金沢工業大学 経営情報工学科 4年
監修 池田 寛 金沢工業大学 経営情報工学科 教授
1.徳山印刷
川口がこの印刷工場を訪れるのはこれが二回目である。5月になって就職先も決まり、いよいよ卒論を本格的に
始める体制が出来、徳山印刷を再訪問したのだ。
一回目は沼田教授や研究室の全員と 3 月の終わりに、この印刷会社だけでなく、バスを作っている会社や、
ベアリング、ルームパーテーション、湯沸かし器のコントロールパネル等ものづくりを行っている北陸の特色ある、
ニッチトップ企業の工場見学巡りをした時に訪れている。
このあたりは大きな出版社が無いのに、中堅の印刷会社が多く、夫々の特色を持ち、住み分けをしながら、
しのぎを削っている。これは昔の加賀百万石時代に培った鎧製作の伝統が、活版印刷の活字作りや植字の技術に
活きて、今日にきていると聞いた事がある。川口の今訪れている徳山印刷も名証2部に上場しており、売り上げ50
億ほどの中堅で、地元では人気があり、川口の大学の卒業生も多い。
初はインクの強烈な臭いに、「こんな場所での研究はとてもやってられないな」と思ったが、二回目の今回は、
香水とは行かないまでも、そんなに悪い臭いではないと感じるようになったのには自分ながら驚いている。
それに先回印刷と言われても、コピー機で教科書などを印刷するぐらいのことしか思い浮かばなかった川口に
とって、輪転機がフロア一面に 20 ライン以上も並び、見えないぐらいのとてつもないスピードで印刷しているのは
圧巻で、興味を引かれ、卒業研究をこの印刷会社でやろうと決心したのだった。
2.沼田研究室
川口は今大学 4 年、3 年間まじめに勉強した甲斐があって、単位の習得を3年で完全に済ませ、
4 年では就職活動と卒業研究に没頭できる環境を作り出していた。
彼の所属する沼田研究室はトヨタ生産方式を主に勉強し、それらをこの地の他の製造業で実際にやってみると
いう一風変わった研究室である。
他の研究室では学生がゼミ室に来て、パソコンと向かい合っているのに、内の教授ときたら「ゼミ室に来るのは
発表の時だけで良い、何か分からんことがあったら、研究している現場で質問を受けるからいつでも言って来い」と、
自分の責務を放棄するようなとんでもない発言を言い出す変わり者だ。
そのくせ、週に二度もゼミを開催するから全員集合せよとは、全く言動不一致もいいところだ。
この川口の指導教官である沼田はトヨタ自動車で四十年近くキャリアを積んできたらしい。川口が見る所、かなり
大雑把な人間で、余り細かな所にはこだわらない性格のようで、単純明快なところが良いと川口は思っている。
頭の回転が速いのか、変人なのか、突然なるほどと思わせるような「たとえ」で学生をからかうのを趣味にしている、
悪趣味な人間であるが、時には厳しく、時には優しくという言葉がまさに似合う人間である。
この研究室はまず、リーン生産方式を徹底的に理解することから始まる。
この学科では、3年の11月には研究室に配属になるのだが、驚いた事には、3年のコアゼミで、リーン生産方式を
10章に別け、膨大なパワーポイントを用いての講義を毎週聴かされる。当たり前の事をもっともらしく説明されるのに
はうんざりだが、そのあと 15 分ほど 4 年生が卒論を発表して、我々3 年生に聞かせてくれる。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
126
まだ途中経過の説明だが、教室から飛び出して、企業の製造現場での研究は臨場感があり、教授の講義より
はるかに面白い。更に自分が聞いても分るほど発表内容に差があり、この差はどこから出るのだろう、どうも頭の
良し悪しではないような気がするが、要因はなんだろう。
それに、これは3年生に聞かせるためなのか、4年生の発表練習なのか良く分らない。
発表の終わりの教授のコメントは「おい、馬場、お前今月何回現場見に行った、このままだと卒業できんぞ、今週
から週2で、現場見て来い」とか、「高村、一度納入部品の一時置きのストア、確認せんと論旨が証明できんぞ」とか
訳の分らん事ばかり言って、「構成がこうなきゃとか、文脈を整えるにはこうでなきゃいかん」といったアドバイスが全
くないのだ。これじゃあ、3年の教育にも、4年生の教育にもならないんじゃないのだろうか。
川口は「窓を開けてみよ、外は広いぞ」とか「明るく、仲良く、元気良く」の言葉につられて、この研究室を選んだの
だが、大丈夫なのだろうかと不安に駆られた。
3.ケーススタディ学習
川口の心配もよそに4年生は全員無事卒業していった。追い出しコンパでは4年生は盛んに「山田君」の話をして
いる。この研究室には山田という人間は居ないはずだが。川口は不思議に思って4年の馬場に尋ねた。
「山田君って誰のことですか、内の研究室には、山田って人はいないはずですが。」
「お前、山田君も知らんのか、ヌマタケンで、山田君を知らん奴はモグリだ、山田君は成長するんだ、山田君と共に、
不肖、馬場君も成長したわけよ。」酔った馬場が隣から大声で説明した。
ポカンとしている川口にしらふの吉田が馬場をなだめて再度説明した。
「山田君というのは“成長する山田君”という名前のケーススタディ集で、内の先生が企業にいた時にかかわった、
サプライチェーンの上流から下流までの各流域での、実態と改善プロジェクトを小説風にアレンジしたもので、
春からこれを使って、しこたま絞られるから、覚悟していたほうはいいぞ。」
「えっ、何ですか、それ、そんなに厳しいんですか。」
「とにかく長いし、読むのが大変なんだ、一般のケーススタデイの教材と異なり、A4 びっしり、そうだな、一ページ
1000 字位かな、 低でも 20 ページ、長いのは 40 ページを 10 ケースやるんだぜ、その上、その中に、どんな企業
でも、例えば量産型のライン生産形態でも、個別受注の一品料理の企業でも、使われるべき物の考え方を隠してあ
るから、それを見つけ出して説明しないといけない、うまく見つけて、次に課題に対して答えられないとやり直しで、
何時までたっても終われない、そしてそれを応用して卒論を仕上げないといけないんだ、これで終わったと思うなよ、
そのうえだよ、自分たちがやった卒論を基にして、ケースを作るまでが卒論合格の条件だって言うんだぜ、
内の先生は。お前ら、分ってこの研究室へ来たんだろ。」
「えっ、そんなこと聞いていたら、ヌマタケン、選んでませんよ、何で事前に教えてくれなかったんですか。」
川口はコアゼミ時の一抹の不安が現実のものとなったことを理解し、酔いが一気に醒めるのを覚えた。
何も知らない他の連中は、景気が上がっているのがうらやましく感じた。更に吉田はにんまりしながら続けた。
「でも、先生は結構厳しいふりしてるけど甘いから大丈夫だよ。俺らの学年でケース、まともに書けたの、誰も居ない
けど、卒業できてるから。」
4.現場観察といくつかの問題の発見
受付で記帳をして、面倒を見てくれ、困った時に相談に乗ってくれる高田さんを呼び出してもらう。
『川口君、よう来たな、今日はテーマの選定か。それじゃあ忘れてるだろうから、前工程からおさらいしようか」と言っ
た高田に対し、「サッパンの所は良いです。前の工場見学の時、サッパンは企業秘密が多くてと、おっしゃってたじ

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
127
ゃないですか。すぐ調べたいという時、自由に出入り出来なかったり、データは出せないと言うことになると、研究も
一旦停止しなければならなかったり、論文に論理性が欠如することになって、後になって困りますので。」
「よし、それじゃあ、原材料の所から行くか、」印刷の原材料は紙とインクである。
ここへ来るのは二度目なのだが、今回は先回来た時と比べてどういうわけか、周りが良く見えるような気がする。
先回来た時には何気なく通り過ぎていた通路でも、やたらとたくさん、しかも乱雑に、印刷済みの商品が置いてある
ことに気が付いたし、それが、さまざまな形のパレットに載っているものや、パレットも無く、直接通路に置かれている
ものさまざまであることも確認できた。そのため、通路の使用できる領域が半分ほどに減っており、通路が通りにくい
ことや、紙くずが散乱していることにも気付いた。川口は前を歩いている研究の手助けをしてくれる大学の先輩でも
あり、今回の職場先輩?でもある高田に尋ねた。「高田さん、この通路は完成品置き場なんですか、えらいたくさん
製品が並んでいますが。」「いや、単なる通路だよ、でも今は決算前で、注文された帳票をお客さんに引き取っても
らえなくて、置くところが無いからここに置いてあるんだ。もっとも決算前でなくても、定常的にここは完成品が置かれ
ていて、実態は出荷前の倉庫といったほうがいいかなあ。」「それじゃあ、今ここに置かれているのは、異常じゃない
と判断されていると言うことなのですか。」川口の質問に少しむっとしたように高田は言った。「正確に言うと異常なん
だろうけど、これで仕事に支障があるわけじゃないんだから、特に問題とも思ってない。今あるスペースは有効に使
わんとな。」川口はこれ以上聞くと今後に差し支えると思って、それ以上質問するのをやめたが、いくら直接仕事に
支障が無いからといって、ゼミでやったケースの4Sや「見える化」の観点からこれは問題ではないのかと心の中でつ
ぶやいた。
川口はケースの発表の時に、馬鹿の一つ覚えのように怒鳴る沼田の言葉を思い出していた。
「必要なのは問題意識だ、問題意識の無い人間に改善は生まれない、幸運の女神も絶対にほほえまない。」
5.常識の罠
資材置き場に行く途中で川本常務と出会った。
川本常務は何でも沼田教授の友達の友達らしく、沼田のこの現場教育のやり方に強い関心を持っており、研究室
が開設された当初から、隣の水屋研の連中ともども自分の職場を提供している。今年も川口の他に、水屋研の3人
もこの現場を借りて研究している。先回の工場見学の時にも挨拶をし、川口も顔を覚えていた。
高田となにやら話しこんでいる。その後でニコニコしながら川口にも話しかけてきた。
「川口君、頑張れよ、俺ら企業人は長いことこの会社でやってきてるから、見えるものも見えなくなっている、
こんなもんで当たり前、常識と言うベールで、問題も問題として見えなくなってしまっている。君達の新鮮な目で、
何者にも汚染されていない目で、研究して意見を言ってくれ、皆期待してるし、それによって君達の実力も上がり、
社会に貢献出来る力が付き、当社も改善できれば一石二鳥と言うもんだ、高田、良く面倒見てやってくれよ、そして
良い意見があれば、嫌がらずにどんどん実行に移してやってみてくれよ、やってみると今まで俺達には垢で見えな
くなっている所が分るようになるかもしれんしな。川口君、じゃあまた少しまとまったら話を聞かせてくれよな。」
資材置き場は紙ロールの山である。種類を分けているのは大きく、ロール幅、紙厚、紙質であるが、すごい量で
ある。「高田さん、この紙は何か月分あるのですか、」「うーん、俺にもわからん、製紙会社にとって、我々印刷会社
はお客のはずで、俺らのほうが神様なのだが、実態は製紙会社のほうが強くて、我々のうれしいように紙を供給して
くれないんだよ。向こうの生産計画に左右されることが多くて、内に印刷物の実需があってから、紙を手配していた
のでは、お客が要求する納期になんか間に合わないし、勢い見込みで発注するしかないんだよ。ところが内で多く
扱っている帳票類のように、比較的定期的に受注されるので、需要予測を立てやすいものでも、必ずしも思惑通り
受注できないので、それが狂うとロールがあふれたり、ロールが無かったりで、てんやわんやになってしまう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
128
何せ種類が多いからなあ。掛け算で効いてくるからこんなにたまってしまうんだ。これでも今日は少ないほうだ。
「印刷物の実需があってからでは間に合わないのですか。」『成長する山田君』のケースで、生産と販売のケースを
勉強した川口には、実需という言葉も十分理解できた。
「使って余ったものか、それとも今から使うものかどこを見れば分るんですか、それに今から使うとすれば、いつ
使うロールかどこを見ればわかるのか教えてください」
この質問には高田も困ってしまい、
「どっかに帳票でも張ってあるだろう、ちょっと探してみよ。」
とロールのあちこちに乱雑に張ってある紙切れを見始めた。
「うーん、分らん、コンピューターにでも入力されてんのかなあ。」ロールの大きさがばらばらででかいものから、こじ
んまりしたものまでさまざまである。置いてある所に、区画線が引いてあるわけでもないし、ましてや所番地も付いて
いない。単に来たものを勝手に置いてあるようにしか思えない。これではコンピューターに入力しようもないし、
そもそも使いたい時に、大捜索隊を出動させなければ、必要なものが取り出せないのではないか、と川口は思った
が、口にしなかった。これ以上高田の心証を悪くしては卒論が危ないと思ったからだ。
ロール置き場のそばには大掛かりな自動倉庫が屹立していた。
川口は話題をロールからそらし、この巨大な自動倉庫に変えた。
「高田さん、こちらの立派な自動倉庫は何を置いてあるんですか。」
「これはお客さんの伝票や帳票類を預かっているんだ。」
「印刷できたらすぐお客さんに配送するんじゃないんですか。」
「いや一回にたくさん印刷して、お客さんが必要な時に言ってくるから、その時配送するんだ。」
「一回に大きなロットで印刷して、作っておいて今すぐ必要のないものをここで保管していると言うことですか、
それじゃあ保管する費用だけ損じゃないんですか。」
「いや、ちゃんとお客さんが保管料払ってくれるから、内は儲かるんだよ。」
「へぇ、良いお得意さんですねぇ。昔からそうなのですか。」
「いや昔は、全量配送していたらしいが、お客さんところが手狭になったのかなあ、内に置いてくれっていうことにな
って。」
「なんで今必要な分だけ小ロットで生産しないんですかね。」
「今から現場を見ればすぐ分かるよ。」
次に向かった先は実際に印刷が行われている所だ。フロア一面輪転機が並んで、すごい勢い回転し、どんどん
印刷物が刷り上って行く。それにしてもすごい速さだ。一秒に紙を何メーター位送るんだろう。あっという間に印刷物
の山が出来ていく。
しかし良く見ると、実際に刷っているラインは全体の半分以下のようだ。後のラインは動いていない。どうしてなん
だろう、仕事が無いのかなあ、常務は今忙しくてみな気が荒くなっているから、安全にはよく気をつけるように、と
アドバイスしてくれたが、あれは常務の思い違いかなあ。20 ライン以上もある輪転機が数えてみると 8 本しか動いて
いない。
「高田さん、動いているラインが少ないんですが、景気が悪くて、仕事が無いんですか。」
「馬鹿言っちゃいかん、今はめちゃくちゃ忙しくて、残業2時間位やっているラインもあるんだ。」
「でもラインの半分以上仕事が無くて止まっているじゃないですか。それとも故障ですか。」

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
129
「いや、あれは仕事が無くて止まっているんでもないし、故障でもないよ。多分、段取り替えをしているんじゃないか
な。」
「この稼動状態で普通なんですか。」
「そうだな、大体いつもこんなもんかなあ。」
川口とは平然と答える高田に唖然としてしまった。確か内の先生はラインを設計する時の可動率の前提は 95%だと
言っていたが、今ここの可働率は 40%いっていないということになる。いくら業種の違いとはいえ、ひどすぎるのでは
ないか。しかも故障はあんまり無くて、仕事も残業やるほどあるとなると、段取り替えでどれだけ時間を使っていると
いうんだ。川口とは頭を金槌で打たれたような気がした。
6.ものと情報の流れ図
強いショックを受けたまま、次の工程に向かった。印刷物を 終の商品にする所だ。ここは昨年も研究室の先輩
が研究を行った所で、研究熱心な川口は事前にその卒論を読んでいた。流れ化に関するテーマなのだが、データ
も無く、授業で受けた流れ化の実施ステップにある、ものと情報の流れ図が書かれていないので、何が言いたいの
か、なぜそういえるのか、さっぱりわからなかった。実際行ってみると、人と印刷物を載せた台車で、何がどうなって
いるのかさっぱり分からない。仕事が今予定通りに進んでいて、問題ないのか、それとも遅れていて、異常なのか、
すら分からないし、中間在庫を載せた台車がやたらと多く、『ものの流れ』がどうなっているかも把握できない。
「高田さん、このフロアの印刷物はどういう工程を経て完成するんでしょうか。」
「いろんな種類があって一概には言えないけど、印刷されたものがさっき見た輪転機の所から持って来られて、第一
はバスター、これはかかるものとかからんものがある、次が切断、この工程は殆ど全部通る、その次が中間と呼ばれ
るもので、これがいろんな工程があって、その商品によって通る工程が千差万別、簡単には説明できん、 後が製
本梱包、大半の商品が通る工程だ。去年の小西君がまとめてあるので参考になると思うよ。」
「それが良く分からなくて、」
「そうかも知れんな、小西君は現場をあまり見に来なかったからなあ。」
後は発送場だ。
発送場に置かれた印刷物に張られている帳票を見ると必ずしも今日今から発送予定のものばかりではないことに
気がついた。どうも前工程で完成されたものが自動的にここに送られてくるらしい。
昼から来たのにもう4時になる。今日は高田さんの時間をえらく使ってしまった。でもテーマをある程度絞れたから、
俺にとっては大収穫だ。高田さんに別れを告げ、帰路に着いた。「ここからだと我が家は近い、今日はテーマを決め
るぞ」
7.テーマの選定
テーマは4つに絞られた。夕飯後、部屋に戻って考え始めた。さあて、テーマはどれにするかなあ。
川本が興味を持って、テーマ候補に挙げたのは次の4項目であった。
1.紙ロールの調達及び管理方法
2.ロットサイズの改善と自動倉庫の撤去
3.枚葉課の流れ化
4.輪転機の段取り短縮
まず消去法で1と2が落ちた。1は高田さんが製紙会社との関係を話していた、問題解決には製紙会社との折衝が

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
130
必要となってくる、これは研究とはいえないし、何か分っても、仕入先との折衝事では俺の手には負えない、
面白そうだがまず落とそう、
次に自動倉庫はムダで、小ロット化の話だが、顧客との関係上、徳山では全く問題意識が無い、保管料をもらっ
ているから経費上負担にならないと考えているようだ。次の販売戦略や意識改革という観点からは面白そうだが、
これはコンサルタントの仕事で、学生の研究ではないだろう。それに高田さんの「今に分かるよ」という言葉も気がか
りだ。それに小ロットにするには段取り短縮が条件だから、4をやれば必然的に2は出来るポテンシャルを持つことに
なる。
残りは3と4どちらにしようか。
4もおもしろそうだ。PQ 線図を書いて、層別すれば面白いものができそうだ、ひょっとすると大半の印刷物は流れ化
ができるかもしれない。先輩には悪いが、あれよりは良いものが書けそうだ。
でもあの可動率40%は衝撃だなあ、動かしたいのに、何かの原因で、半分以上ラインが止まっていると言う事な
んだよなあ、もし自動車と同じレベルに持っていけたら、あの半分の設備と人で、今の量印刷可能ということだから、
驚くよなあ。現場の人は何も感じてないようだけど、どう思っているのだろう。問題だと思ってないのだろうか。
それとも今までいろんなことをやってきたけどうまく行かず、仕方ないと思っているのだろうか。
この間、設備増強の話が新聞に載っていたけど、年間利益の倍ぐらいの設備投資が、もし可動率が上がれば
いらなくなってしまうほどの影響力だ。徳山印刷にとってはこちらの方が優先順位が高いのではないだろうか。それ
にケーススタディでプレスの段取改善の内容がかなり詳しく書かれていたから、参考になるかもしれんし、
よしっ、決めた,これで行こう。川口はいろいろ悩んだ挙句、輪転機の段取替えの研究を行う事にした。
いよいよ卒論の研究テーマを発表する時が来た。
先生は「自分で決めろ」と言うだけなので後報告だけで良い。徳山印刷の人たちに共感してもらえば良いのだ。み
んなの前でテーマを発表した後で、何も出ませんでは格好がつかない、何か今までの殻を破る発見をして 後の
結論を出さなければと考えると緊張した。
受付で手続きを済ませ、会議室へと案内された。そこには高田と、常務、製造部長がすでにいた。今後のことを
考えて、まずは深々と頭を下げ大きな声で挨拶をし、席につき研究テーマについて話をした。川口は先日の工場見
学で感じたことを話し、4つの候補を説明し 終的になぜこのテーマに絞られたかの自分自身の思考プロセスを
説明した。
後に研究テーマを説明すると、製造部長もその問題には興味があるらしく、すんなりと話が通った。
いよいよ本格的に卒論の開始である。
8.可動率と稼動率
まず川口は自分が 終的にこのテーマを選択したきっかけとなった可動率の実態を調べることから手を付け始め
ようと考えた。
「高田さん、可動率のデーターってありますか。」
「ああ。稼動の記録表を計算すればすぐ分ると思うし、たぶん計算した結果もプロットしてあると思うよ。俺の記憶だと
80%弱だったような気がするけど。」
「えっ、80 ですか。」どうも自分の『ざっと見』とかけ離れている。ワークサンプリングをするまでも無く、50 は行って
いないように思われる。
「こちらの可動率の定義はどういう風ですか。」

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
131
「こら、川口、人を馬鹿にするなよ、可動率は稼働率と違って、製造するために動かしたい時に動く割合のことだろ、
稼動率は 120 位だと思うよ。」
「いや、そんなつもりでは、ただ私のイメージと合わないので。というのはこの間テーマ選定の時に 8 ラインしか動い
ていなかったんですよ。ざっと見に、20 ライン位ありますので、40 位かなと思ったんですが。」
「この前来た時はたまたま止まっているラインが多かったんでないか、内の機長(徳山印刷ではラインマンのことを
こう呼ぶ)はまじめな人が多いからでたらめは書いていないと思うよ。それじゃあ、後で記録表を見てごらんよ。」
高田と別れて、稼動記録を見ながら、川口は考えていた。どうもデータと稼働状況の現実のイメージと一致しない。
記録表には○時○○分印刷完了、ライン停止、△時△△分段取り開始×時××分段取り完了としか書いてない。
これは可動率をどうやって計算しているのだろう。これだけでは可動率は計算できないはずだが。
混乱して分けが分らなくなった川口は、ふっと沼田の口癖を思い出した。
『分らんかったら、ぐじぐじ考えても無駄なこった、お前ら頭が悪いんだから、何も思いつくはずない。頭の悪いやつ
は足と目を使え、汗流せ』稼動記録を返してラインに行ってみる。やっぱりこの間と同じだ。9 ラインしか動いていな
い。どうしてなんだろう。ここはまた『○書いて立ってろ!』で行くしかないか。
9.段取り時間とは?
川口は止まっているラインをじっと見ていた。前ロットが完了し、次の印刷をすべく、段取替えに入ったところらし
い。ローラー等機構部分の交換を完了すると、職長は段取替え完了○時○○分と記入している。
不審に思った私は「こちらで研究させていただいてる川口です。まだ初品も出ず、順調に印刷物が出てこないのに
どうして段取完了なのですか。」と人のよさそうなその機長に尋ねた。
機長は「段取り完了して、今からは調整です。」と答えたが、その後一向に印刷物が出て来ない、時々試し刷りをし
ては止まり、ロール紙を引きちぎってはまた刷り、なかなか順調に輪転機が回らない。しばらくして、順調に流れ出し
たが、機長はその時刻を気にしている風も無い。
ますます疑問が募った川口は「段取時間をパフォーマンスメジャーとして取っていますか、今回はどうでしたか。」
と聞くと、機長はそんな当たり前の事をなぜ聞くのかと言いたそうに、
「もちろん、段取時間は重要ですから毎回記録して、短縮のために分析していますよ、ほら今回は前の奴が終わっ
たのが、△時△△分、段取り完了時刻が○時○○分だから差っぴいて□時間□□分ですよ、昔はこの倍くらいか
かっていましたが、早くなりました。」と言って自慢げにしている。
「その後、順調に流れるまで、いろいろやっておられましたが、その時間は取ってありますか。」と川口。
「ああ、調整ですか、あれはロス紙のデータを取っています。どれだけ印刷調整で紙をムダにしたかです、これも減
りましたよ。」と済ましている。
「可動率は取っておられますよね。」
「俺は取ってないけど、生産管理の連中が稼動記録にデータ打ち込んで、可動率を出して、職長にラインごとの
グラフ作って提出するもんだから、可動率がほかのラインより低かったり、前月より低いと、職長から『人を入れてるの
に、どうして低いんだとか、どうして下がったんだ』とかうるさくてしょうがない。人を入れたって言ったって、段取り手
伝う奴がフリーターで、来てもちっとも役に立たんし、ほんとに必要な時にはいないし、何の役にも立たないんだもん、
しゃーないよ。」
と 後は愚痴をこぼしている。
「すいません、 後にもう一つ、このラインの安定時のラインの送りスピードと、今回の印刷物のロールの総長はいく
らか教えていただけませんか。」

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
132
「えっ、送りスピードは分かるけど、何、その後のやつ」
「あの例えば一枚の印刷物がこのラインの送り方向で 5O センチとするじゃないですか、そして印刷量が一万枚と
すれば、印刷物のロールの総長は 50 万センチということですけど。」
「いやそんなんは、俺ら機長には分るわけないし、知ってなんの役に立つの。」
「どうもありがとうございました。今後もいろいろ教えてください。」
「段取り中はかまってやれないけど、安定して回りだしたら相談に乗ってやれるからいつでもおいでよ。」
年配の職長さんにお礼を言って分かれると、川口の頭の中は疑問だらけになった。
川口は以前やったプレスのケーススタディでは、段取り時間の定義は、『前ロットの 終品が加工完了してから、
今ロットの初良品が加工し、更に初品以降も定められたサイクルタイムで連続して良品加工完了する時を、今ロット
初品加工開始時刻とし、(今ロット初品加工開始時刻)―(前ロット 終品加工完了時刻)で表される。』だったはず
だ。だから装置の全てのユニットを今回加工品用に設定されても、良品が安定的に連続的に流れ始めるまでは、
段取り時間の範囲内であるはずだが、どうも稼動記録のデータからは『全てのユニットを今回加工品用に設定完了
する』までが段取り時間とされており、機長もそれで、パフォーマンスを管理されているようだ。
これでは真の段取時間は短くならない。
それに可動率の計算もどうやっているのか、[総稼働時間-段取り時間(調整含まず)]/総稼動時間で計算して
いるようだ。これではチョコテイ(微小停止)は表面に現れず、可動率とはいえない。可動率と稼動率が混同してしま
っている。
可動率は理論的に加工プロセスが 100%その能力を発揮した時に、その製品の加工に必要する時間を総稼働時間
から計画停止時間を差し引いた時間で除したものが定義のはずだ。機長の話では、『理論的に加工プロセスが
100%その能力を発揮した時にその製品の加工に必要する時間』が計算されているとは思えない。製品の数(ここで
は製品の送り方向の長さの総量)も、輪転機の加工能力(ここでは送りスピード)にも、機長は無関心だ。
それに、生産管理が誤った計算で評価指標を算出し、それで職長がその数字だけで、管理しようとしていることも
気になる。結局真因の追究も出来ず、機長のモチベーションも上がらず、改善が進むわけがない。生産現場を正し
く評価するためには可動率の定義に従った評価尺度を用いなければ、結局、他責として他を非難するだけで、自ら
評価尺度を上げようとする行動に結びつかない。
川口は自分のイメージする可動率と高田の言っていた可動率の数字の大幅な相違がおぼろげながら、掴めたこ
とに、少し安心感を覚えた。 初からイメージが合わないでは研究が進められない。川口は自分の頭を整理するた
めに、図を描いてみると、次のように頭の整理が付いた。
定時割れの場合は下図のようになり、可動率=B/A であらわされる。
インク
不良 機械故障 材料
入替
定時
総稼動時間 A
生産高を能力 100%で加工する時間B
予知し得る L/S 予知し得ない L/S
段取り
計画停止

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
133
家に帰り、その日の出来事を日記風に書いてみることにした。こうすることで、自分が過去にどんなことをやってい
たかや、自分の意思決定までのプロセスを確認できるので、研究につまずいたときに役立つからだ。
10.段取り替えの現状調査
1 週間後、再び工場を訪れた。
まずは現状調査の開始だ。現状把握しないことには何も始まらない。この日は色んな人とのヒアリングを中心に調査
した。するとある事が分かった。この工場での段取り換えは外段取り・内段取りに関しては支援スタッフと呼ばれる人
達が担当し、調整作業を機長が担当していることが分かった。
段取り作業といっても詳しくは以下のように 3 つに分ける事が出来る。
①内段取り…機械を停止させないとできない段取り作業
②外段取り…機械を停止させなくても出来る作業(前段取りと後片付けがある。)
③調整作業‥・内段取り後、品質の精度確保のため、機械を停止して行う作業
先回のヒアリングでは調整作業は段取り時間とは思ってないようだ。そこで両者のことを詳しく調査するべく、現場
を取り仕切る、前畑マネージャーに話を伺うことにした。今は支援スタッフがやっている外段取りや内段取りは、以前
は手の空いた機長がやっていたが、それでは機長の仕事が増え、負担が大きいことから支援スタッフを設けたこと
を知った。
即ち、内段取り作業で出来るものは外段取りにし、支援スタッフにやらせる、内段取りは機長と支援スタッフが共同
で行い、時間を短くする、特に機械的に片付く仕事は支援スタッフが行う、と言うものだった。『内段取りより外段取り
に移行せよ、次に内段取りを短縮せよ』は段取り短縮の王道で、一気に段取り時間が減るはずだったが、思惑通り
に行かない。
前畑は続けて、支援スタッフがうまく機能していないことを川口にぼやいた。なぜなのだろうか。川口は疑問に
思った。同時に、高田が前に自動倉庫の前で「今に分かるよ」と言った理由を理解した。
実は後で悔やむのであるが、素直な川口は前畑のこのぼやきで、これを研究テーマの主体に持ってこようと考え
た。
11.テーマの決定と研究の方向性の決定
テーマは『支援スタッフの有効活用による段取り替えの改善』である。
しかし、なぜ人を投入しても時間がかかるのだろうか。川口はこの疑問を探るべく、しばらく支援スタッフの動きを
観察し、ヒアリングを続けることにした。
3 週間のヒアリングと現場観察の結果、川口の考察は下記のようなものだった。 支援スタッフの有効活用が出来
ていない原因は、内段取り時に支援スタッフの入るタイミングが悪かったり、適正な必要人数を把握してないことで
ある。
内段取り支援に入るメンバーは、工場内をブロックに分割し、そのブロック毎に人を配置しているため、自分の
ブロックでの段取り換えは把握しているが、それ以外はあまり把握していないし、他の人が何をやっているのかも
あまり把握していない。
また段取りの作業内容によっては支援が 1 人でいい場合もあるが 2 人、3 人と作業内容によって変動する。
そのため内段取りの作業時に人が足りない時は、他のブロック担当のメンバーを呼びに行くために、探しにいかなく
てはならず、そのために段取り作業が中断されたり、段取り開始のジャストタイミングに人が入れない。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
134
しかし実際に内段取り作業を見ていると、あきらかに人数が足りない場面があった。普段は工場内に散らばってい
ても、段取り換え時に、適正な人数がさっと揃えば内段取りにかかる時間は縮小するはずである。
まずは支援の要請を機長が前日に作業予告版を見て、紙に記入し申請するという往来の方法から、支援者自ら
が 1 日の行動を決められるようにすれば良いと思う。機長が決めると、次の日に支援スタッフが休んでしまった場合
には人数が足りず、内段取り作業が遅れてしまう。しかし支援者自らが行動を決めれば、前日に翌日の何時何分に
何号機でどういった作業の段取りがあるか把握できるので、人が足りないのをカバーできる対策も出来るし、機長の
指示を仰ぐ必要がなくなり、作業にスムーズに入れる。
どういった作業があるかが分かれば、後は何人投入するかがポイントとなる。やる作業はパターンが決まっている
ので、全パターンで何人が適正かを見つけることで人の投入もうまくいく。これら 2 つが完成すれば支援スタッフは
うまく機能する。
これら 2 つを完成するためには、まず計画通りに作業ができることや、印刷にかかる時間をしっかり把握できるように
なること、誰でも作業が出来るように多能工化を推進する必要がある。また、内段取り作業を全てパターン化し、
各パターンで、人の投入の数を変えてみて比較するなど、データ分析を行うことも必要になってくる。
その他にも段取り換えを短縮できそうな方法としては、必要作業は機械の種類ごとで変わってくるので、標準作業
票を機械の種類ごとに作る。標準作業票をもう一度見直して、もしかしたらオーバーラップで出来る作業もあるかも
しれないし、外段取りの方にもっていける作業があるかもしれない。
川口は自分ながら良くやったと考えていた。何せ週に3回のペースで工場を訪れ、3週間でここまで考え出していた。
それもそうである。川口は週3回も現場に通い、持ち前の明るさで作業員ともすでに打ち解け、何でも話せるように
なっていた。作業員と打ち解けて話せることは非常に大事なことである。恥ずかしがったり、躊跨していたりでは聞き
たいことも聞けないし、友達にならなければ改善など出来ない。
12.予期しない発表会
川口は頭の中を文章にし、高田に報告した。すると高田は
「この内容を会社で発表してくれないか」と思いがけない言葉を口にした。
びっくりした川口も「1 人ですか?」と聞き返す。
「1 人じゃ大変だろうから、沼田教授の講義のついでにやるのはどう?」高田は答える。
実は前々から徳山印刷は沼田教授の講義が聞きたく、この時すでにアポを取っていた。川口も「勝手にするなよ」
と心で思いながらも、OK を出した。発表までは後 1 カ月ある。更に研究を進め、作業員や教授を驚かしてやると
心に誓った。
発表まで後 1 週間となった。川口のこの 3 週間の進捗を見てみよう。
縦軸を時間、横軸を作業内容とした表に、作業者名と、何号機での内段取りかをプロットする体制が出来上がって
いた。前日に作業予告版で翌日の作業内容を確認し、翌朝に機長からの配膳リスト(支援要請内容)を見て確認し、
プロットしている。 まだ立ち上がったばかりで、すぐにうまくいくとは思わないが、これでデータを取って比較すれば
少しは良くなるかなと思ったが、更なる問題点があった。支援スタッフは内段取りの支援以外にも、外段取りの仕事
を抱えているため、内段取りの支援ばっかりに入っていると、本来の外段取りの作業が遅れてしまう。そのため 1 日
のスケジュールを決める際に、名前をプロットする点でネックになっているようだ。また、一度プロットして決定しても、
スタッフは工場のあちこちにちらばっており、印刷も予定通りにいかない時もあるので、内段取りの時間になっても
いないということもしばしばである。そうなった場合に、いない人の分を他の人に頼むのだが、自分が担当じゃないと
言いだし、結局作業が遅れるのである。臨機応変に対応できていない。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
135
また、内段取りの支援に行っている人の外段取りの分の仕事が多ければ、早く終わりそうな人が手伝うということも
していない。そのため、誰かが遅くなってしまう。この辺の見える化も今後進めていかなくてはならないだろう。
ちなみに、携帯電話を持たせて、内段取りの時間になったら呼び出すのはどうかと提案したが、コストの点で却下さ
れた。
その他の問題点として、支援スタッフの仕事の量を軽減し、内段取りにどんどん入ってもらうために派遣社員を
導入したのだが、仕事の割り当て、1 日のスケジュールを作っていないのだ。派遣社員の動きをちらちら見てみると、
手待ちでボーつと立っている姿ばかりが見受けられた。何もしないほうがよっぽどつらいだろう。せっかく派遣社員を
入れたのだから、定時まで、このスケジュールを見たら動けるようなものを作らないといけない。
これも見える化である。
また作業の切り離しの点でも問題を感じた。支援スタッフの作業の一部を切り離して、その作業を外部社員に渡し
ているのだが、その切り離しの内容は 2 種類に分かれている。印刷業務からの切り離しと、毎日の業務からの切り離
しである。派遣社員にも 2 種類あり、徳山印刷で正社員になりたい人とそうでない人である。正社員になりたい人に
は印刷業務からの切り離しの部分をさせて、正社員になりたくない人には毎日の業務からの切り離しの部分をさせ
るのであるが、これが逆になってしまっている。まあいろんな問題点が出てきたが、中間発表でぶちまけてみんなに
問題意識を持ってもらおう。そしてみんなに動いてもらおう。自分ひとりの力では無理である。川口は新たな問題も
含め発表資料(パワーポイント)を作った。
12.沼田教授の講評
発表の時がやってきた。既に沼田教授が到着しており、さっそく会場に向かった。
今日の川口は気合に満ちていた。今日の発表会は川口の発表、沼田教授の講義で計 2時間である。その後、昼食
を取り、沼田教授を工場に案内する予定だ。
午前 9時、発表を始めた。聴講者は沼田教授をはじめ、作業員、専務、常務、部長、更には社長も出席していた。
しかし、川口は人前に出るのが大好きで、緊張はするものの始まってしまえば余裕である。発表で大事なのは内容
のみならず、下を見ないで聴講者の目を見て話すことや、大きな声ではっきりと話すことも大事である。
それらを忠実に守り、発表を終えた。その結果、問題点を素直に受け止め、今後一緒に取り組むと言ってもらい、
川口もホッとしていたが、沼田教授だけは違った。
『よく頑張ったのは認めるが、内容はまだまだまだだ。』言われてしまった。
なぜなのだろう。川口も理由が分からないまま、沼田の講義が始まった。内容は段取り替えについてである。 初
は段取り替え、段取り時間の重要性と定義を、なぜそうでなければならないのかを中心にくどくど説明している。
その後改善事例などを紹介して、約 1 時間講義し、午前の予定を終了した。
昼食後、沼田教授を常務や高田、前畑が案内した。すると、あれも駄目これも駄目などダメだしのオンパレードで
あった。
工場視察を終えた沼田教授は、徳山印刷に対しこう述べた。
「段取りも大事だが、まずは 5S を徹底してください。この工場は私が見た中でもかなり悪いほうです。」と。
この言葉にみんな納得したようだった。川口が家路につこうとすると、沼田教授が川口に一言
「お前が今日提案した内容は何ぼのもんか定量的に説明し、その論拠を述べよ、もし出来なければもう 1 度
ケーススタディの 2 をしっかり読め」とだけ言い、帰っていった。
川口は家に帰り、教授の言葉を理解しようとしていた。『何ぼのもん』とは?何のことだろう。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
136
どれほど効果があるのかと聞いているのか、先生はいつも思いついたらすぐやってみよ、ぐじぐじ考えるよりやって
みるほうが早いと言っているじゃないか。今日徳山の連中が納得してやるといっているんでいいんじゃないのか。
待てよ、そう言えば現状分析して、その後目標設定もしていないし、無論目標の必然性も立証していない。無論
目標も無いのだから、自分の提案で、目標を達成できるかどうかの目安や計画もあるわけない。お前は単なる思い
つきの意見を述べたに過ぎないと言っているのかもしれない。
テーマの設定の方も前畑さんの言葉があまりに印象的で、可動率や段取り時間の分析をそこそこにして、
支援スタッフの有効活用に飛びついてしまったけど、有効活用したらどれだけ段取り時間によるラインストップが
減って、可動率がどれだけ上がるかも、ちっとも推定できないじゃないか、無論そんな状態で、目標の設定も、達成
の見通しも立つわけがない。要は目的達成のために、何を行えば寄与度が高いのかを分析する処から始めないと
いかん、という事を先生は俺に気付かせたかったのではなかろうか。そもそも俺には段取り時間の現状分析が不足
していたのではなかろうか。
よしっ、もう一度プレスの段取り短縮のケースを読んでみよう。
じっくり3時間かけてケーススタディを3度も繰り返し読み直した。川口は沼田教授の言葉の意味をようやく理解する
事が出来た。段取替時間は調整と内段取りを合わせたものなのに、内段取りの問題ばかりに注目し、調整のことを
気にもかけていなかった。しかもケースでは、調整作業が段取り改善のキーだと言っている。仮に内段取りよりも
調整の方が段取り替え時間の多くを占めていたならば、川口の改善は小さな部分の改善で効果があまり見られな
い、ということにもなる。
この事を思い出した川口はもう 1 度、ケーススタディを参考に研究手順を組み直し、新たな気持ちでスタートする
ことを決めた。
13.再度の現状調査
7 月中旬、川口はビデオカメラを持って工場に向かった。段取り替え時間短縮のためにやらなければならないの
は、まずモデルラインを選定し、段取り替え時間の現状調査をすることだ。
なぜモデルを作るかというと、始めから全ラインでやっていては時間と労力がかかり、改善に失敗したときに
ダメージが大きい。モデルを作れば、少人数でも改善に取り組め、業務に差し支えることも少ない。モデルで改善が
成功すれば、同じような輪転機だから、別のラインにも展開可能であるし、何かやっていると、何やってるんだろうと
隣の人たちも興味津々、うまく行くと俺んとこもという雰囲気が生まれるから、モデルを作るのだ。
これも山田君にでていた。
モデルラインを 3 台選定し、いよいよ調査開始である。ここで登場するのがビデオカメラである。段取り替え時間の
把握は IE のタイムスタディという手法を使い調査するのだが、ビデオカメラがあればその場でストップウオッチを
使って計測しなくても、撮影した映像を家へ帰ってからでも見ることが可能なので何回でも計測可能である。時代の
進歩のお陰で楽に現状調査が出来るのだ。
さっそくカメラを段取り替えのあるモデルラインに設置し、撮影を開始する。やはりカメラが気になるのか
機長や支援スタッフも少し不機嫌そうな顔をしながら作業をしていた。しかし、先月に友好な関係が出来つつあった
ので、意地悪はされずに「今日はカメラマンかい」の言葉だけで、いつもの行動どおりに段取り替えを進めている。
段取り替えが終了し、カメラを家へ持ち帰り、映像を見てタイムスタディをしてみた。ノートを開き、各作業に何分
かかっているかを記入していく。初めての作業で実際の段取り替え時間よりも時間がかかってしまったが、まずは
成功だ。沼田教授の言ったとおり、調整作業のほうが長く、全体の時間も 1 時間を超え思ったよりも長かった。
しかし、1 回だけでは何ともいえないので、しばらくタイムスタディを繰り返し、現状をもっと把握していくことにした。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
137
14.中間発表
いよいよ中間発表会となった。
モデルラインのタイムスタディも終わり、作業内容と所要時間の程度やばらつきも把握できてきた。
発表内容は前回徳山印刷で発表した内容をベースに、段取り替えの定義や、改善の手順、タイムスタディの
結果の 1 部などを加えて発表した。目標の設定は本来 初にあると教授には言われたが、現状分析が終わるまで
は、自分にとってあまりその数値の必然性が説明できなかったので、今回はパスした。
もちろんここでも誰よりも大きくはっきりとした声を心がけた。発表が終わり、沼田教授の第 1 声が
「なかなかいいんじゃない、工場をしっかり見てきている」と初めてお褒めの言葉をいただいた。
水屋教授にも同じことを言われ、川口にとってこのうえない評価をいただいた。自分のやっていたことは間違えでは
なかった。今後もこのまま続けていこう。
翌日、川口は休む間もなく工場に向かい、ビデオ撮影を続けていた。中間発表で自分が 1 番進んでいることに
気付いた川口は、このままぶっちぎって卒論を誰よりも早く終わらせると新たな目標をつくっていた。
目標を持つことで常に自分を追い込めるからだ。改善でも、ベンチプレスの競技でも、目標を持つことが
モチベーションアップに貢献することを強く感じていた。
川口はビデオ撮影による現状分析を夏休みいっぱい続けたのであった。
15.段取り替えのキー、調整時間
9月、川口も 7月から続けていた、段取り替え時間の現状調査がほとんど終わり、現状調査の結果をまとめ始めた。
無論段取り替えのタイムスタディと同時に可動率の調査も平行して進めている。
可動率の実態と可動率を落としている段取り替えの寄与度、内段取り、調整作業の仕事の内容と時間的ばらつき、
ほぼ調べるべきデータはここ3ヶ月で取れてきた。
この時点で『山田君』の内容がなるほどなあと思われるようになって来た。今までは「分ったつもり」だったのだ。
多くの産業が高度成長から安定成長期に入ってきた今、顧客のニーズは多様化し、多種少量生産になってきた。
そのため、一台の機械を有効に働かせようとすると、段取り替えをうまく短時間でやるか無段取りでやれるように汎用
ラインとするかである。汎用ラインとすると複雑で冗長な設備が出来上がる危険性もある。何でも出来るということは、
何でも備えていなければならないということだからである。やはり段取り替えをいかに短時間でやるかが
コアコンピタンスとなってくる。
可動率もデータを取ることが出来た。3ヶ月間のデータだけでなく、モデルラインの可動率を過去 1 年分調査した。
印刷スピードと印刷量から逆算すると今回のデータと大幅な違いは無く、 初の直感が正解で、40%程度である。
当初徳山で取っていたデータが8割弱であるから、大変な違いである。八割動いているならあまり問題としないだろ
うが、半分以上動いていない、となれば大問題と思うんじゃなかろうか。
言い換えれば、能力の半分以上生産していないのである。先生の言う 95%は無理としても 80%になれば半分の
機械は不必要になるのだから、とんでもないことである。しかもたまに突発故障があったとしても非常にまれなケース
で、調整作業が完全に完了してからは、ほぼフル回転で輪転機は回り続けている。少々金を掛け、人手を割いても
段取り短縮をやらねばならないことが実感される。俺の研究も日本の多くの印刷業に対して、大変な貢献をする、
悪くない。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
138
現状調査として、タイムスタディのデータも含め、段取り替えに関する項目を全て過去 1 年分調査した。
段取り時間も大事だがそれだけでなく、段取り替えの 1 日の回数や、1 回にかかる時間なども大事である。その調査
の結果、おもしろいことが分かった。
段取り替え時間は内段取り時間と調整時間にわけられるが、その割合をヒストグラムで見てみると、
どのモデルラインも内段取りが全体の 2 割、調整作業が全体の 8 割と、段取り替え時間のほとんどが調整作業が
占めていることが分かった。また標準偏差でバラつき具合を見ても、内段取りよりも調整作業の方がばらついていた。
この結果は、まさにケーススタディと同じパターンである。そこで、ケーススタディを更に参考にし、改善のターゲット
を調整作業に紋ることに決めた。
16.改善案の創出・再現性
大学祭も終わり、川口も、久し振りに工場へと足を運び高田・前畑にここまでの現状を報告し、今後の取り組みに
ついて話をする。
現状調査が終わると次は、改善案の考案である。調整作業に改善の的を絞ったものはいいものの、改善案は夢
物語ばかり、なかなかこれだという現実味のあるものが思い浮かばない。家へ帰り、いつものように改善日記に今日
の出来事を整理する。
すると 1 つのことから、改善案を思いついた。
今日の前畑の会話の中で、ここでは主にどんな製品を作っているのかを話していた時に、ここで製造している
製品は常に新しいものではなく、8割がリピートだよと言っていたのを思い出した。川口はこのことから「じゃあ段取り
も8割は作業が一緒だから、再現がきっちりできれば、調整はやり直しなく一回で済むはず。時間が短縮できる。
それにこの様な話は確か沼田教授の改善事例で出てきたはずだ。これでやってみよう!」と、仮説を立てた。
整理すると、『徳山印刷の印刷は 8 割がリピート、したがって一回過去に調整でき、フル回転で印刷できたのなら、
その条件を再現できたら、8 割は問題なく印刷できるはずだ。』という仮説だ。
学科内での合同発表を終えて、これまでの研究過程に自信を持った川口は、さっそく次の段階に取り組み始めた。
仮説の立証といよいよ改善のスタートである。
改善の手法は印刷物に関わるデータを履歴として残し、次に同じ印刷物を印刷する時に、履歴を使うというやり方
だ。しかし、履歴を使うといってもどのデータを履歴として残すかが重要となってくる。そこで調整作業の作業項目を
見直した。調整作業はこの工場では大きく分けて 4 種類ある。その中でも、難しい作業と、簡単な作業がある。簡単
な作業は 1 度コツを掴めばすぐに出来るようになるが、難しい作業は、コツを掴んだとしても周りの環境(印刷なので
紙質や室温・湿度)に左右されやすく、個人の習熟度によって時間にバラつきが生じる。履歴を残す項目としては、
後者の作業に関するものの方がいいだろう。
調整作業を難しい作業と簡単な作業にヒアリングを基に分けると、難しいとされる部類に入るものが 1 つあった。
その作業はインクと水のバランスを調整する作業であった。実は、印刷というのはインキと水のバランスの一言に
つきる、と言われるぐらい印刷における大事な作業なのだ。作業者もこの作業にいつも苦しんでいる。特に色数が
多い印刷物に関しては 1 つの色を調整すると、他の色のバランスがくずれたりもするので、やっかいな作業である。
しかし、この作業時に調整する印刷機の調整箇所にはラッキーなことに、調整ハンドルがついているので、
値を残していく事が可能なのだ。値で残していく事が出来れば、作業者もミスしにくい。こういった点から、履歴を残
す項目をこの作業を基に選定した。ここまで決まれば後は簡単である。項目を記入していくフォーマットを作り
準備段階は終了だ。
11 月下旬。いよいよデータ取りの開始だ。作業者の負担も考えて、朝一にある仕事は自分でデータを取り、それ

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
139
以降は作業者に取ってもらうことにした。そのため 2 日に 1 回朝 8 時に工場に行くことになった。データ取りは 1 人
で行わねばならないなと思っていたが、同じような研究をしている、水屋研究室の四坊さんと共同でデータを交互に
取りにいくことになった。それでも 2005 年いっぱい続けるとあってかなりきついが、ここさえしっかりすれば研究も
ほとんど終わりである。川口は気合を入れた。
データ取りはまず、履歴を全く使わずに調整作業を行った場合で、かかった時間、そして履歴を残していく項目の
データをフォーマットに記入していく。リピートの周期は 1~3 ケ月だが、どのぐらいの量リピートがくるかは予測しにく
いので、とりあえずは全ての印刷物のデータを取っていった。時間がたつと同じ印刷物が必ずデータ調査期間内に
何点か来る。来た時に、前回の履歴データが記入されているフォーマットを持ってきて、そのデータを使い
調整作業を行う。作業終了後にかかった時間を前回の結果と比較する。ここまでやって、1 点の印刷物の調査終了
とした。これをひたすら続けた。
12 月は 20 年ぶりの大雪とあって、工場に向かうのに苦労することもあったが、目標があるからこそ何とか頑張れ、
データ取りを無事終了した。そして、新しい年を迎えた。
肝心の改善データもなかなか良い結果が出ていた。
データには良いデータも悪いデータも無いのだが、ついつい自分の仮説を正当化するデータが出るとにんまりして
しまう。川口の悪い癖だ。
先生からはいつも『データを色眼鏡で見るな。会社をつぶすのはお前みたいな奴が企画を通すからだ、お前が
悪いデータだと思うデータを大事にしろ、企業のデータは自分の言いたい事を通すために作るからいつでも疑問の
目で見ろ、データを見るのではなく、データを持って、現場を見ろ』と言われ続けてきた。
まとめ方としては、まずモデルライン別に、得られたデータを振り分けていく。その数は3台合わせて、25 点で
あった。この改善プロジェクトを 1 年続けるとなれば点数もかなり増えてくるだろうが今はこれだけだ。
ライン別に振り分けたら、次は、履歴データを使用する前と、使用した後で結果を比較していく。棒グラフで表して
いく。すると結果が一目瞭然で分かる。結果は、約 7 割履歴データを使用した後の方が調整時間が短縮された。
残り3割に関しては調整時間が逆に延びてしまった。そこで、この結果が果たして本当に履歴データの効果が
あった、と言えるかどうかを検証するべく、2 年生の時に使った統計のテキストを引っ張ってきて、t 検定という手法を
用いて結果の検証をしてみた。この手法は簡単に説明すると、結果を前後で比較し、その結果が本当に変化が
あったかどうかを見極める方法である。(Excel の分析ツール参照)
この手法で検証を行ってみると、履歴の効果が認められるという結果になり、仮説を証明する事が出来た。
17.残った疑問・機種による効果のばらつきの原因は?
結果が出たが、川口は悩んでいた。モデルライン全体で見てみると、履歴の効果が確認できたものの、ライン別に
見てみると、効果が確認出来るものと出来ないものに分かれてしまったのだ。なぜだろう。
川口は残り限られた時間をこの結果の原因追求に当てることにした。この原因を探るべく、まず、モデルラインで
条件の違うものは何かないかということを考えた。
すると条件の違う点が 1 つ見つかった。それはその機械に投入した印刷物の色数である。色数は多ければ多い
ほど調整作業時間が長く、色数が少ないほど調整時間は短いとされる。こういったことから、もしかしたら、履歴を
使っても、調整時間が短縮されなかったものに関しては、この色数が関係しているのではと思い、縦軸に調整時間
削減率(色数の多いものは短縮される箇所も多いから削減率は大きいのでは?)横軸に色数を取り散布図で関係
を表してみた。しかし、結果はばらついており、相関係数を出してみても 0.05 と相関が全くないという結果に

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
140
なった。
ん~、色数ではないのか。じやあ何なのだろうか。
川口はこの疑問を解決すべく工場へと向かった。分らなくなったら「現場」である。
川口は改善結果をプリントし、このような結果になったことを前畑や高田に報告し、同時に作業者に調整作業が
長くなってしまう要因は他にないか聞いて回った。
すると、どの作業者も 初に口にするのが、メンテナンス作業の不備ということであった。どうもこの工場では、
機械のメンテナンスは作業者に一任してあり、機長が自分の担当する機械を点検するだけで、それ以外の人間は
全く関与していない。
メンテナンスは点検する箇所が多く、時間もかかるため面倒くさがる機長が多い。その結果、メンテナンス不備を
隠すためにその場しのぎを繰り返し、異常が起こってからメンテナンス作業となっていた。
それによく考えてみると、メンテナンスが出来ていないという事は、5Sの1つ「清掃」が出来ていないことになる。
清掃をしながら、機械を点検するのが清掃の基本である。これは沼田教授がこの工場に訪れた時の感想につなが
ってくる。いらないものがあったり、ものが乱雑に置かれてあり何があるか分からない状態になっている。
つまりこの工場は5Sが全く出来ていない工場である。川口はこの話とメンテナンスの問題の 2 点セットを、改善結果
の原因に結びつけることにした。
18.論拠の乏しい原因分析・メンテナンスの影響
さっそく内容をまとめて、沼田教授に見せた。
すると一言「これは単なるヒアリング結果を書いているもんじゃないのか、メンテナンスの不良が調整を長くするという
証拠を見せろ、そしてどうしてそれが言えるのか、説明しろ、so what はwhy so とセットで無ければ駄目だ、警察だ
って自白だけで検挙したら、後でえらい目に会うから物的証拠を揃えない内は検挙しないんだ、自白は変わるかも
しれんからな。データを見せろ」と、いつものへたくそな『たとえ』で大声で怒鳴られた。ヒアリングデータしかないと
川口が言うと、沼田は「何か証明するデータがないと難しいな」と言ってきた。
「それもそうだな。俺がいくら言ったってデータがなければ説得力無いよな。でもデータがあるのかな」川口はだめも
とでもう一度工場に向かった。この頃には『困ったら現場へ』が完全に身に染み付いていた。
さっそく前畑に相談すると、「メンテナンス記録ならあるぞ」と言われた。メンテナンス記録とはメンテナンスをいつ
やったかをライン別に記録していってあるものである。これを見てみると、結果の出たラインはメンテナンスがしっかり
と行われているのに対して、結果の出なかったラインはメンテナンスがしっかりと行われていないことが分かった。
「このデータも十分に使えるが、もっとメンテナンスの不備と調整の関係が分かるデータはあるか」と聞くと、
「もう無い」と返事が来た。
「今からではメンテナンスに関してはこれ以上の結果は出ないな。でも、しっかりと履歴の効果は確認できたんだか
ら、メンテナンスは今後の重要課題にして、卒論をしめよう」川口は家に帰り、卒論にこのことを付け加えた。
数日後、このことを卒論と共に沼田教授に見せて、説明した。
「そうか、残念だが時間的に仕方ない。これは次の 3 年生の課題だな。」と沼田教授は残念そうに合格点を出した。
川口はダントツで卒論を終える事が出来た。沼田研のメンバーはその頃必死になって卒論に取り組んでいた。
『早目に何でも取り掛かれば後から必ず楽になる。 そして行き詰ったら現場へ行け』
これが後から来る4年生へ送る言葉だ。川口はつぶやいた。
完 23,000 字
これには日付がありませんが日付が合ったほうが後で思い出すのに便利かもしれません。

金沢工業大学情報マネジメント研究所
ものづくり知識創造学
141
参考文献
・トヨタ生産方式にもとづく「もの」と「情報」の流れ図で現場の見方を変えよう!!
・新版 IE の基礎