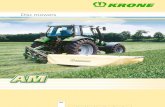第1章 PISA2003調査-数学的リテラシー-...- 2 - 4 オラン ダ 538 リヒテ ンシュ...
Transcript of 第1章 PISA2003調査-数学的リテラシー-...- 2 - 4 オラン ダ 538 リヒテ ンシュ...

第1章
PISA2003調査-数学的リテラシー-

目 次
Ⅰ 調査結果の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 数学的リテラシー問題の結果 ・・・・・・・・・・・・・1
(1)各国の数学的リテラシーの得点の変化 ・・・・・・・・1
(2)我が国の得点の変化 ・・・・・・・・・・・・・・・・1
(3)数学的リテラシーの得点 ・・・・・・・・・・・・・・1
(4)習熟度レベル別の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・2
(5)国際比較及び経年比較 ・・・・・・・・・・・・・・・5
(6)正答率の分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
Ⅱ 出題された問題について ・・・・・・・・・・・・・・・・10
(1)調査問題の枠組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(2)公表問題の考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
① 為替レート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
② スケートボード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
③ トッピング選び ・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
④ 花壇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
⑤ 歩行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
⑥ 身長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
⑦ 輸出に関する問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・39
⑧ 盗難事件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
⑨ 地震 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
Ⅲ 指導の改善に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
(1)基本的な概念の理解(意味理解)及び数学的に解釈し
表現する指導を重視すること ・・・・・・・・・・・・・48
(2)実生活と関連させた指導を重視すること ・・・・・・・48
(3)他教科や総合的な学習の時間で扱われる内容との関連を
図ること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
(4)小・中学校,中・高等学校の連携を一層進めること ・・・50

- 1 -
Ⅰ 調査結果の概要
2003 年調査では数学的リテラシーが調査の中心分野であった。同時に,読解
力,科学的リテラシーを含む主要 3 分野に加え,問題解決能力についても調査
された。 この調査では,義務教育修了段階の 15 歳児が持っている知識や技能を,実生
活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかどうかが評価された。
また,思考プロセスの習得,概念の理解,及び様々な状況でそれらを生かす力
が身に付いているかどうかを評価することも重視されている。 1 数学的リテラシー問題の結果 (1)各国の数学的リテラシーの得点の変化
PISA2003 PISA2000 香港 550 1 位 - フィンランド 544 2 位 536 4 位 韓国 542 3 位 547 2 位 オランダ 538 4 位 - リヒテンシュタイン 536 5 位 514 14 位 日本 534 6 位 557 1 位 (注)「-」はデータなしを示す。
(2)我が国の得点の変化 「PISA2000:557」 → 「PISA2003:534」 (1 位グループ(1 位)) (1 位グループ(6 位))
(3)数学的リテラシーの得点
調査結果は,OECD 加盟国の平均が 500 点,標準偏差が 100 点になるよう換算され
ている。次の表は,換算された得点をもとに平均得点を算出し,数学的リテラシー全
体及び 4 つの領域についてその結果を示したものである。 (注)数学的リテラシー及び 4つの領域については,Ⅱ 出題された問題について を参照のこと
数学的リテラ
シー 量 空間と形 変化と関係 不確実性
国・地域 得
点 国・地域 得点 国・地域 得点 国・地域 得点 国・地域 得点
1 香港 550 フ ィ ン
ラ ン ド 549 香港 558 オ ラ ン
ダ 551 香港 558
2 フ ィ ン
ラ ン ド 544 香港 545 日本 553 韓国 548 オ ラ ン
ダ 549
3 韓国 542 韓国 537 韓国 552 フ ィ ン
ラ ン ド
543 フ ィ ン
ラ ン ド 545

- 2 -
4 オ ラ ン
ダ 538 リ ヒ テ
ン シ ュ
タ イ ン
534 スイス 540 香港 540 カナダ 542
5 リ ヒ テ
ン シ ュ
タ イ ン
536 マカオ 533 フ ィ ン
ラ ン ド
539 リ ヒ テ
ン シ ュ
タ イ ン
540 韓国 538
6 日本 534 スイス 533 リ ヒ テ
ン シ ュ
タ イ ン
538 カナダ 537 ニ ュ ー
ジ ー ラ
ンド
532
7 カナダ 532 ベ ル ギ
ー 530 ベ ル ギ
ー 530 日本 536 マカオ 532
8 ベ ル ギ
ー 529 オ ラ ン
ダ 528 マカオ 528 ベ ル ギ
ー 535 オ ー ス
ト ラ リ
ア
531
9 マカオ 527 カナダ 528 チェコ 527 ニ ュ ー
ジ ー ラ
ンド
526 日本 528
10 スイス 527 チェコ 528 オ ラ ン
ダ 526 オ ー ス
ト ラ リ
ア
525 ア イ ス
ランド 528
11 オ ー ス
ト ラ リ
ア
524 日本 527 ニ ュ ー
ジ ー ラ
ンド
525 スイス 523 ベ ル ギ
ー 526
上の表から分かるように,我が国の得点は,いずれも OECD 平均を上回っているが,
量及び不確実性の領域は,空間と形及び変化と関係の領域より得点や順位が低くなっ
ている。
(4)習熟度レベル別の結果
換算された生徒の得点を次の 7 つの習熟度別レベルに分けている。なお,右側の欄
は,各レベルにいる生徒の特徴の一例を示したものである。
レベル 6 669 点以上 複雑な問題場面において探究やモデル化を
基に,情報を概念化し,一般化し,利用でき
る
レベル 5 607 点以上 669 点未
満 複雑な場面でモデルを発展させ使うことが
できる
レベル 4 545 点以上 607 点未
満 複雑だが具体的な場面で,明示されたモデル
を効果的に使うことができる
レベル 3 483 点以上 545 点未
満 連続的な計算など,明確に述べられた手順を
実行できる
レベル 2 421 点以上 483 点未
満 直接的な推論を行う文脈において,場面を解
釈し認識できる

- 3 -
レベル 1 358 点以上 421 点未
満 情報がすべて与えられ,問いも明確な見慣れ
た場面で,問いに答えることができる レベル 1 未
満 358 未満 ―
次の表は,我が国と平均得点で我が国より上位にある 5 カ国について,習熟度レベ
ル別に生徒の割合を示したものである。 (注)参加国全体の結果については,報告書を参照のこと
習熟度レベル 1 未満 1 2 3 4 5 6 日本 4.7 8.6 16.3 22.4 23.6 16.1 8.2 OECD 平
均 8.2 13.2 21.1 23.7 19.1 10.6 4.0
香港 3.9 6.5 13.9 20.0 25.0 20.2 10.5 フィンラ
ンド 1.5 5.3 16.0 27.7 26.1 16.7 6.7
韓国 2.5 7.1 16.6 24.1 25.0 16.7 8.1 オランダ 2.6 8.4 18.0 23.0 22.6 18.2 7.3
数学的リテラ
シー
リヒテン
シュタイ
ン 4.8 7.5 17.3 21.6 23.2 18.3 7.3
日本 5.7 9.2 16.6 23.1 23.6 15.1 6.7 OECD 平
均 8.8 12.5 20.1 23.7 19.9 11.0 4.0
香港 4.1 7.0 13.7 21.5 25.8 18.7 9.2 フィンラ
ンド 1.4 5.0 14.6 26.9 27.3 17.9 7.0
韓国 2.6 7.2 17.0 25.2 26.0 15.6 6.4 オランダ 4.1 10.1 18.3 23.0 21.9 15.9 6.7
量
リヒテン
シュタイ
ン 4.0 7.6 16.5 24.1 24.8 17.1 6.0
日本 4.2 7.4 13.9 20.0 21.9 18.2 14.3 OECD 平
均 10.6 14.2 20.4 21.5 17.2 10.4 5.8
香港 4.1 7.0 13.2 18.7 21.5 19.9 15.6 フィンラ
ンド 2.5 7.3 17.0 25.5 24.6 15.2 7.9
韓国 4.8 8.4 14.7 19.7 19.9 16.5 16.0 オランダ 3.7 10.1 18.6 24.9 21.9 14.6 6.2
空間と形
リヒテン
シュタイ
ン 5.7 8.1 14.9 21.5 23.2 16.5 10.1

- 4 -
日本 6.4 8.5 15.7 20.6 21.1 16.4 11.3 OECD 平
均 10.2 13.0 19.8 22.0 18.5 11.1 5.3
香港 5.6 8.0 14.5 20.6 23.0 18.6 9.8 フィンラ
ンド 2.7 7.0 16.1 24.5 24.1 16.7 8.9
韓国 3.0 7.0 15.7 22.3 23.6 17.5 10.9 オランダ 1.4 7.2 16.4 22.7 21.8 19.2 11.3
変化と関係
リヒテン
シュタイ
ン 4.6 10.0 15.1 20.7 20.5 18.6 10.5
日本 4.9 9.1 17.5 23.7 23.5 14.8 6.6 OECD 平
均 7.4 13.3 21.5 23.8 19.2 10.6 4.2
香港 3.3 6.3 12.5 19.3 24.8 21.1 12.7 フィンラ
ンド 1.6 5.5 15.4 27.2 27.0 16.4 6.8
韓国 2.2 7.2 17.3 25.0 25.7 15.7 6.7 オランダ 1.0 6.7 17.0 23.4 23.2 19.1 9.5
不確実性
リヒテン
シュタイ
ン 5.2 9.5 18.4 23.0 23.8 14.9 5.1
我が国の特徴として次のことがいえる。
・ 数学的リテラシー全体についてみると,レベル 6 の生徒の割合が 8%で 3 番目に
多く,レベル 5 以上の生徒の割合が 24%で 6 番目に多い。また,レベル 2 以上の
生徒の割合は 86%で 8 番目に多い。日本より平均得点が上位の国と比較すると,
特にフィンランドとの比較で,我が国はレベル 1 未満の生徒の割合が多い。 ・ 量については,レベル 2 以上の生徒の割合は 85%で 12 番目に多く,レベル 5 以
上の生徒の割合は 22%で 9 番目に多い。 ・ 空間と形については,レベル 2 以上の生徒の割合は 88%で 8 番目に多く,レベル
5 以上の生徒の割合は 32%で 2 番目に多い。我が国は,空間と形の領域について
全般的に高いレベルにある。 ・ 変化と関係については,レベル 2 以上の生徒の割合は 85%で 8 番目に多く,レベ
ル 5 以上の生徒の割合は 27%で 6 番目に多い。 ・ 不確実性については,レベル 2 以上の生徒の割合は 87%で 11 番目に多く,レベ
ル 5 以上の生徒の割合は 22%で 9 番目に多い。

- 5 -
(5)国際比較及び経年比較
(注)以下の数学的リテラシーの 3 つの側面及び問題形式については,Ⅱ 出題された問題について を参照のこ
と
①包括的アイディア
包括的アイディア 合計
量 空間と形 変化と関係 不確実性 全体問題数 84* 22 20 22 20 OECD 平均より正答
率が低い問題 11 3 0 2 6
%(当該問題数/全体問題数) 13.1 13.6 0 9.1 30.0 OECD 平均を5ポイ
ント以上,下回る問題
数 7 2 0 1 4
%(当該問題数/全体問題数) 8.3 9.1 0 4.5 20.0 同一問題 全問題数 19 - 9 9 1 前回と比較して正答
率が下がった問題数 9 - 4 5 0
%(当該問題数/全体問題数) 39.8 - 44.4 55.6 0 前回の正答率を5ポ
イント以上,下回る問
題数 2 - 1 1 0
%(当該問題数/全体問題数) 10.5 - 11.1 11.1 0 * 数学的リテラシーの問題は,全部で 85 題あったが,分析から 1 題はずされたため,ここでは全体問題
数を 84 題としている。以下,問題数を示す場合は分析対象からはずされた問題を除外して示す。
・ 包括的アイディアの国際比較から,量及び不確実性の領域に課題があると考えら
れる。
・ 包括的アイディアの同一問題による経年比較からは,空間と形,変化と関係の領
域の 2 つの領域でともに約半数の問題で平均正答率が下がり,約半数の問題で平
均正答率が上がっていた。
(注)2000 年には,空間と形,変化と関係の 2 つの領域の調査を行っている。次の表は,この 2 つの領域につい
て平均得点の経年比較をしたものである。
2003 年調査 2000 年調査 2003 年-2000 年
空間と形 553 565 -12
変化と関係 536 536 0
空間と形,変化と関係の全問題について平均得点を比較すると,空間と形については 2000 年調査から 2003
年調査へ 12 点下がり,変化と関係については 2000 年調査,2003 年調査ともほぼ同じ結果である。ただし,空
間と形についても統計的に有意な差は認められない。

- 6 -
②数学が用いられる状況
数学が用いられる状況 合
計 私的 教育的 職業的 公共的 科学的 全体問題数 84 18 15 5 28 18 OECD 平均より正
答率が低い問題 11 2 1 0 4 4
%(当該問題数/全体問題数) 13.1 11.1 6.7 0 14.3 22.2 OECD 平均を5ポ
イント以上,下回る
問題数 7 2 0 0 2 3
%(当該問題数/全体問題数) 8.3 11.1 0 0 7.1 16.7 同一問題 全問題
数 19 3 8 1 1 6
前回と比較して正
答率が下がった問
題数 9 2 4 0 0 3
%(当該問題数/全体問題数) 39.8 66.7 50.0 0 0 50.0 前回の正答率を5
ポイント以上,下回
る問題数 2 1 1 0 0 0
%(当該問題数/全体問題数) 10.5 33.3 12.5 0 0 0
・ 数学が用いられる状況の国際比較から,科学的場面での扱いが課題と考えられる。
・ 数学が用いられる状況の同一問題の経年比較から,私的場面での扱いが課題と考
えられる。
③数学的プロセス
数学的プロセス 合計
再現 関連付け 熟考 全体問題数 84 26 39 19 OECD 平均より正答
率が低い問題 11 3 6 2
%(当該問題数/全体問題数) 13.1 11.5 15.4 10.5 OECD 平均を5ポイ
ント以上,下回る問題
数 7 2 4 1
%(当該問題数/全体問題数) 8.3 7.7 10.3 5.3 同一問題 全問題数 19 6 12 1 前回と比較して正答
率が下がった問題数 9 3 6 0
%(当該問題数/全体問題数) 39.8 50.0 50.0 0

- 7 -
前回の正答率を5ポ
イント以上,下回る問
題数 2 2 0 0
%(当該問題数/全体問題数) 10.5 33.3 0 0
・ 数学的プロセスの国際比較から,関連付けの問題への対応が課題と考えられる。 ・ 数学的プロセスの同一問題の経年比較から,再現の問題への対応が課題と考えら
れる。 ④問題形式
問題形式 合
計 選択肢 複合選択
肢 求答 短答 自由記述
全体問題数 84 17 11 13 22 21 OECD 平均より正答
率が低い問題 11 0 3 1 4 3
%(当該問題数/全体問題数) 13.1 0 27.3 7.7 18.2 14.3 OECD 平均を5ポイ
ント以上,下回る問
題数 7 0 2 1 3 1
%(当該問題数/全体問題数) 8.3 0 18.2 7.7 13.6 4.8 同一問題 全問題
数 19 2 4 7 - 6
前回と比較して正
答率が下がった問
題数 9 1 2 2 - 4
%(当該問題数/全体問題数) 39.8 50.0 50.0 28.6 - 66.7 前回の正答率を5
ポイント以上,下回
る問題数 2 0 0 1 - 1
%(当該問題数/全体問題数) 10.5 0 0 14.3 - 16.7 ・ 問題形式の国際比較から,複合的選択形式の問題への対応が課題と考えられる。
・ 問題形式の同一問題の経年比較から,自由記述の問題への対応が課題と考えられ
る。
(注) 同一問題で 5ポイント以上正答率が下がった問題は「歩行」「立方体の面」の 2題で,「歩行」
については後ページに掲載しているのでそちらを参照されたい。

- 8 -
⑤数学的プロセスと問題形式のクロス集計 下の 2 つの表は,全 84 問について,平均正答率が OECD 平均を下回る問題を数学
的プロセスと問題形式をクロスして取り出したものである。ただし,選択肢形式と複
合選択肢形式は選択肢として,短答形式と求答形式は短答・求答としてまとめている。
全体再 現 関連付け 熟 考 合 計 再 現 関連付け 熟 考 合 計
選択肢 0(7題)
1(14題)
2(7題)
3(28題)
選択肢 0 7.1 28.6 10.7
自由記述 0(4題)
3(9題)
0(8題)
3(21題)
自由記述 0 33.3 0 14.3
短答・求答
3(16題)
2(16題)
0(3題)
5(35題)
短答・求答 18.8 12.5 0 14.3
合計 3(27題)
6(39題)
2(18題)
11(84題)
合計 11.1 15.4 11.1 13.1
この表から,関連付けかつ自由記述の問題,熟考かつ選択肢の問題に課題があるこ
とが考えられる。
また,以下の表は,我が国が 2位グループであった量及び不確実性の領域について,
平均正答率が OECD 平均を下回る問題を数学的プロセスと問題形式をクロスして取
り出したものである。
量再 現 関連付け 熟 考 合 計 再 現 関連付け 熟 考 合 計
選択肢 0(3題)
0(2題)
0(1題)
0(6題)
選択肢 0 0 0 0
自由記述 0(0題)
0(0題)
0(1題)
0(1題)
自由記述― ― 0 0
短答・求答
2(6題)
1(8題)
0(1題)
3(15題)
短答・求答 33.3 12.5 0 20.0
合計 2(9題)
1(10題)
0(3題)
3(22題)
合計 22.2 10.0 0 13.6
不確実性再 現 関連付け 熟 考 合 計 再 現 関連付け 熟 考 合 計
選択肢 0(2題)
1(4題)
2(5題)
3(11題)
選択肢 0 25.0 40.0 27.3
自由記述 0(1題)
1(3題)
0(1題)
1(5題)
自由記述 0 33.3 0 20.0
短答・求答
1(2題)
1(2題)
0(0題)
2(4題)
短答・求答 50.0 50.0 ― 50.0
合計 1(5題)
3(9題)
2(6題)
6(20題)
合計 20.0 33.3 33.3 30.0
これらの表から,量では短答・求答の問題に,不確実性では関連付けの問題に課題
があることが考えられる。
(題)
(題)
(題)
(%)
(%)
(%)

- 9 -
(6)正答率の分布
次の表は,全 84 題の正答率の分布である。 平均正
答率 10% 未満
10%台
20%台
30%台
40%台
50%台
60%台
70%台
80%台
90%台
日本 57.7% 1 3 4 9 12 15 14 13 10 3 OECD 平均
48.9% 1 5 10 11 18 8 16 12 1 2
正答率が 50%台以上の問題について,我が国は 84 題中 55 題(65.5%)を占めるが,
OECD 平均では 39 題(46.4%)である。

- 10 -
Ⅱ 出題された問題について
(1)調査問題の枠組み
数学的リテラシーの定義
数学が世界で果たす役割を見付け,理解し,現在及び将来の個人の生活,職業生活,友
人や家族や親族との社会生活,建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活におい
て確実な数学的根拠にもとづき判断を行い,数学に携わる能力
数学的リテラシーの 3つの側面
数学的な領域(包括的アイディア)
包括的アイデ
ィア 説 明 問題数
量
数量的な関係,数量的なパターン,数量的な現象。相対的な大
きさの理解,数のパターンを見付けること,量及び(数えるこ
とや測定のように)量としてとらえることが可能な実世界の対
象の特性を数を用いて表すこと。数を理解し処理すること。ま
た,重要なのは「量的推論」であり,「量的推論」は数感覚,数
を表現すること,演算の意味の理解,暗算や見積もりに関わっ
ている。
22
空間と形
空間的,幾何的な現象や関係。ものの形の構成を分析するとき,
対象の性質や相対的な位置を理解するとともにそれらの形が異
なる表現や異なる次元で表されても認識でき,類似点や相違点
を探すこと。
20
変化と関係
変数間の関数的な関係と依存関係とともに変化の数学的関係を
明らかにすること。数学的関係は方程式や不等式の形をとるこ
とが多いが,等しい,割り切れる,含む,などのより一般的な
関係も含む。関係は記号,代数,グラフ,表,幾何的表現など
様々の異なる表現によって表される。いろいろな目的や性質の
ために様々な表現が役立つので,ある表現から別の表現に翻訳
することは,状況や問題を扱う際に非常に重要である。
22
不確実性 確率的・統計的な現象や関係であり,これらは今日の情報化社
会においてますます身近になっている。 20
(注)各問題を数学カリキュラムの領域で分類すると次のようになる。
数学カリ
キュラム
の領域
数 代数 幾何 関数 確率 統計 離散数学
問題数 26 3 18 9 5 18 5

- 11 -
数学が用いられる状況
私的 生徒の日々の活動に直接関係する文脈 18 教育的 生徒の学校生活に現れるような文脈 15 職業的 職業の場面に現れるような文脈 5 公共的 生徒が生活する地域社会における文脈 28
科学的
より抽象的な文脈で,技術的な過程,理論的な場面,明らかに数学
的な問題についての理解に関連する。ここには,数学の教室でよく
直面するような数学そのものである「数学内的」文脈も含まれる。
17 数学内的 1
数学的プロセス(能力クラスター)
再現クラスター
比較的よく見慣れた,練習された知識の再現を主に
要する問題を解く能力。
具体的には,数学的事実についての知識やありふれ
た問題の表現に関する知識を有していること,等しい
ものを認識すること,身近な数学的対象や性質を思い
出すこと,決まりきった手順を行うこと,アルゴリズ
ムや技術的な技能をそのまま適用すること,見慣れた
標準形式の記号や公式を使うこと,簡単な計算を行う
ことである。
26
関連付けクラスター
再現クラスターの上に位置付くもので,やや見慣れ
た場面,又は見慣れた場面から拡張され発展された場
面において,手順がそれほど決まりきっていない問題
を解く能力。
典型的な問題は,解釈を大いに要求し,異なる表現
を結び付け,解を求めるために問題場面の異なる面を
結び付けるものである。
39
熟考クラスター
関連付けクラスターのさらに上に位置付くもので,
洞察,反省的思考,関連する数学を見付け出す創造性,
解を生み出すために関連する知識を結び付ける能力。
典型的な問題は,より多くの要素を含んでおり,結
果の一般化や説明,正当化を要求するものである。
19
問題形式
選択肢形式 与えられた選択肢から 1つの答えを選択する問題。 17 複合的選択肢形
式
与えられた選択肢の中から選択する問いが連続している
問題。 11
求答形式 答えが問題のある部分に含まれており,短い語句又は数値
で答える問題。正答は 1つしかない。 13
短答形式
(論述)
短い語句又は数値で答える問題。正答は複数ある。 22
自由記述形式
(論述)
答えを導いた考え方や求め方,理由を説明するなど,長め
の語句で答える問題。 21

- 12 -
(2) 公表問題の考察
次ページ以降では,公表された調査問題(本調査問題)22 ユニットのうち,9 ユニッ
トを取り上げている。問題を取り上げるに当たっては,数学的リテラシーの 3 つの側面
及び問題形式に配慮し,さらに正答率が OECD 平均を下回っている,経年比較の結果
正答率が下がっている,正答率があまり高くないなどの点を考慮した。 取り上げたのは次の 9 ユニット,計 17 問である。
日本 OECD 差 日本 OECD為替レート 問1 量 公共的 再現 短答形式 79.1 79.7 -0.6 7.6 6.6為替レート 問2 量 公共的 再現 短答形式 74.0 73.9 0.1 9.4 8.8為替レート 問3 量 公共的 熟考 自由記述形式 42.9 40.3 2.6 21.5 17.4トッピング選び 問1 量 職業的 関連付け 短答形式 66.1 48.8 17.3 2.5 5.1スケートボード 問1 量 私的 再現 短答形式 58.5 72.0 -13.5 10.6 4.7スケートボード 問2 量 私的 再現 選択肢形式 67.0 45.5 21.5 3.3 4.5スケートボード 問3 量 私的 関連付け 短答形式 53.6 49.8 3.8 9.4 5.5花壇 問1 空間と形 教育的 関連付け 複合的選択肢形式 37.8 20.0 17.8 1.3 2.5歩行 問1 変化と関係 私的 再現 自由記述形式 40.9 36.3 4.6 18.3 21.0歩行 問2 変化と関係 私的 関連付け 自由記述形式 33.9 20.6 13.3 30.7 38.7身長(背が伸びる) 問1 変化と関係 科学的 再現 求答形式 78.3 67.0 11.3 8.6 8.3身長(背が伸びる) 問2 変化と関係 科学的 関連付け 自由記述形式 43.3 44.8 -1.5 29.3 21.1身長(背が伸びる) 問3 変化と関係 科学的 再現 求答形式 74.5 68.8 5.7 8.1 7.5輸出 問1 不確実性 公共的 再現 求答形式 64.6 78.7 -14.1 6.5 7.5輸出 問2 不確実性 公共的 関連付け 選択肢形式 54.9 48.3 6.6 4.0 6.9盗難事件 問1 不確実性 公共的 関連付け 自由記述形式 29.1 29.5 -0.4 14.4 15.0地震 問1 不確実性 科学的 熟考 選択肢形式 68.0 46.5 21.5 4.7 9.3
ユニット問題の分析 全体の割合(%)
番号 包括的アイディア 状況・文脈 能力 問題の形式正答率 無答率
(注)以下の「ア.結果についての考察」における国際比較などで述べている 13 カ国とは次の国や地域のことで
ある。
日本,オーストラリア,カナダ,フィンランド,フランス,ドイツ,アイルランド,
イタリア,韓国,ニュージーランド,アメリカ,オランダ,香港

- 13 -
① 為替レート <量の問題で,数学的プロセスは再現であり平易な計算で解決できるが,
正答率が OECD 平均をやや下回っている>
シンガポール在住のメイリンさんは,交換留学生として 3 ヶ月間,南アフリカに留学する準備
を進めています。彼女は,いくらかのシンガポールドル(SGD)を南アフリカ・ランド(ZAR)
に両替する必要があります。
為替レートに関する問 1
メイリンさんが調べたところ,シンガポールドルと南アフリカ・ランドの為替レートは次のとお
りでした。
1 SGD = 4.2 ZAR
メイリンさんは,この為替レートで,3000 シンガポールドルを南アフリカ・ランドに両替しま
した。
メイリンさんは南アフリカ・ランドをいくら受け取りましたか。
答え:........................................................
為替レートに関する問 2
3 ヵ月後にシンガポールに戻る時点で,メイリンさんの手持ちのお金は 3,900ZAR でした。彼女
は,これをシンガポールドルに両替しましたが,為替レートは次のように変わっていました。
1 SGD = 4.0 ZAR
メイリンさんはシンガポールドルをいくら受け取りましたか。
答え:........................................................
為替レートに関する問 3
この 3 ヶ月の間に,為替レートは,1 SGD につき 4.2 ZAR から 4.0 ZAR に変わりました。
現在,為替レートが 4.2 ZAR ではなく 4.0 ZAR になったことは,メイリンさんが南アフリカ・ランド
をシンガポールドルに両替するとき,彼女にとって好都合でしたか。答えの理由も記入してください。

- 14 -
問 1 状況:公共的 能力:再現 問題形式:短答形式 学習指導要領との関連:中学校 1 年 C 数量関係 (1)エ 比例,反比例の見方
や考え方を活用できること 為替レートに関する問 1の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 12,600 ZAR (単位不要)
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
正答 誤答 無答 日本 79.1 13.4 7.6 OECD 平均 79.7 13.8 6.6
問 2 状況:公共的 能力:再現 問題形式:短答形式
学習指導要領との関連:中学校 1 年 C 数量関係 (1)エ 比例,反比例の見方
や考え方を活用できること 為替レートに関する問 2の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 975 SGD (単位不要)
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
正答 誤答 無答 日本 74.0 16.6 9.4 OECD 平均 73.9 17.3 8.8
問 3 状況:公共的 能力:熟考 問題形式:自由記述形式
学習指導要領との関連:中学校 1 年 C 数量関係 (1)エ 比例,反比例の見方
や考え方を活用できること

- 15 -
為替レートに関する問 3の採点基準
コード 回答
正答(1点)
11
「はい」で,正しい説明がなされている。 • はい。(1SGD の)為替レートが下がったことにより,メイリンは手持ちの
南アフリカ・ランドに対して,より多くのシンガポールドルを受け取った。
• はい。1 ドルが 4.2ZAR であれば,929ZAR になる。(注:生徒が,SGD で
はなく ZAR で回答したが,計算と比較が明らかに正しい場合,このミスは無
視してよい。)
• はい。メイリンは,1SGD あたり 4.2ZAR を受け取っていたが,現在は 1SGD
を手に入れるために 4.0ZAR を支払えばよいから。
• はい。1SGD あたり 0.2ZAR 安いから。
• はい。4.2 で割ると,4で割ったときより値が小さくなるから。
• はい。為替レートが下がらなければ,受け取る額が約 50 ドル少なくなったの
で,メイリンには好都合である。
誤答/無答(0点)
01
「はい」だが,説明が記入されていない。または説明が不適切である。 • はい。為替レートが安いほうがよい。
• はい。ZAR が下がると SGD に両替したとき受け取る金額が増えるので,メイ
リンには好都合である。
• はい。メイリンには好都合である。
02 その他の答え
99 無答
正答 誤答 無答 日本 42.9 35.6 21.5 OECD 平均 40.3 42.3 17.4
ア.結果についての考察
問 1,問 2 ともに,正答,誤答,無答の生徒の割合は OECD 平均とほぼ同じである。
これらの問題は,比例関係について理解できていれば,簡単に解決できる問題である。
誤答や無答となった生徒の中には,1SGD=4.2ZAR などの表記が理解できない生徒もい
たものと思われる。 問 3 は,問 1,問 2 に比べ,正答率が 30 ポイントあまり下がり,誤答は 20 ポイント,
無答は 10 ポイントあまり上がっている。この問題については,問題の意図がとらえら
れなかった生徒もいたと思われるが,この問題だけでなく「身長」に関する問 2 や「盗
難事件」に関する問題のように,自分の考えを整理し自分の考えを数学的な表現(記述)
を用いて説明する問題では,正答率があまり高くないので,そのような力が育っていな
いことも理由として考えられる。

- 16 -
イ.指導上の留意点
比例関係は,実生活の中でもいろいろな場面でみられる基本的な数量関係である。指
導に当たっては,日常生活や他教科の内容などから生徒が興味や関心をもつと考えられ
るものを扱うよう工夫したい。特に,この問題のように,経済のグローバル化や国際化
に対応した問題を工夫することも積極的に考えたい。
また,自分の考えを自分の言葉で表現し,確かめたり他の生徒と意見を交換したりす
るような場面を充実させる工夫も必要であろう。その際,他の生徒と意見を交換する中
で次第によりよい考えや,よりよい表現ができるようにしたい。

- 17 -
② スケートボード<量の問題で,数学的プロセスは再現であり平易な計算で解決できる
が,正答率が OECD 平均を 10 ポイント以上下回っている>
浩二さんはスケートボードが大好きです。彼はスケボーファンという店に値段を調べにやって
きました。
この店では,既製品のボードを買うこともできますが,デッキ 1 個,車輪 4 個のセット,トラ
ックの 2 個セット,金具のセットを別々に買って,オリジナルのボードを組み立てることもでき
ます。
店の商品の価格は次の通りです。
商品 価格
(ゼット)
既製品のスケートボード 82, 84
デッキ 40, 60, 65
車輪 4 個のセット 14, 36
トラック 2 個のセット 16
金具のセット(ベアリング,
ゴムパッド,ボルトとナット)10, 20
スケートボードに関する問 1
浩二さんは,自分のスケートボードを組み立てたいと思っています。この店で部品を買ってスケ
ートボードを組み立てる場合の最低価格と最高価格はいくらですか。
(a) 最低価格: .........................................ゼット
(b) 最高価格: ゼット

- 18 -
スケートボードに関する問 2
この店にはデッキ 3 種類,車輪セット 2 種類,金具セット 2 種類があります。トラックのセット
は 1 種類しかありません。
浩二さんが組み立てられるスケートボードは何種類ですか。
A 6 B 8 C 10 D 12
スケートボードに関する問 3
浩二さんの予算は 120 ゼットです。彼はこの予算で一番高いスケートボードを買いたいと思って
います。
浩二さんが 4 つの部品にかけることができる金額はそれぞれいくらですか。下の表に記入してく
ださい。
部品名 金額(ゼット)
デッキ
車輪のセット
トラックのセット
金具のセット

- 19 -
問 1 状況:私的 能力:再現 問題形式:短答形式 学習指導要領との関係:中学校 2 年 C 数量関係 (2)ア 起り得る場合を順序
よく整理することができること スケートボードに関する問 1の採点基準
コード 回答
完全正答(2点)
21 最低価格 80 ゼット,最高価格 137 ゼット,ともに正しい答え
部分正答(1点)
11 最低価格 80 ゼットのみ正しい答え
12 最高価格 137 ゼットのみ正しい答え
誤答/無答(0点)
00 その他の答え
99 無答
完全正答 部分正答 誤答 無答 日本 54.5 8.0 26.9 10.6 OECD 平均 66.7 10.6 18.0 4.7
問 2 状況:私的 能力:再現 問題形式:選択肢形式
学習指導要領との関係:中学校 2 年 C 数量関係 (2)ア 起り得る場合を順序
よく整理することができること スケートボードに関する問 2の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 D 12
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
A B C D 無答 日本 11.8 12.2 5.7 67.0 3.3 OECD 平均 25.4 18.3 6.3 45.5 4.5
問 3 状況:私的 能力:関連付け 問題形式:短答形式
学習指導要領との関連:中学校 2 年 C 数量関係 (2)ア 起り得る場合を順序
よく整理することができること

- 20 -
スケートボードに関する問 3の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 デッキ 65 ゼット,車輪のセット 14 ゼット,トラックのセット 16 ゼット,
金具のセット 20 ゼット 誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
4 つ正答 3 つ正答 2 つ正答 1 つ正答 誤答 無答 日本 53.6 10.8 15.9 5.8 4.6 9.4 OECD 平均 49.8 16.7 17.3 5.6 5.0 5.5
ア.結果についての考察
問 1 の部分正答は,採点基準から分かるように,最低価格又は最高価格の一方が正答
であったものである。したがって,部分正答となった生徒は,表をよみ間違えたり,単
純に計算間違いをしたりした可能性が考えられる。誤答についてはその原因は明確では
ないが,問題の意図や表から必要な情報がよみ取れなかったことなどが考えられる。 問 2 の正答率は 67.0%である。この問題と同じような解法をとる「トッピング選び」
に関する問題の正答率は 66.1%(OECD 平均:48.8%)で,この問題の正答率とほぼ同
じである。 また,この問題の反応率をみると,我が国の生徒は,正答の次に B の 8 と答えた生
徒の割合が高くなっている。これは,場合の数を求める場合に,積の法則と和の法則を
取り違えたものである。平成 14 年度高等学校教育課程実施状況調査では,次ページの
ような問題が出題されている。教育課程実施状況調査問題の正答率は,アが約 54%,
イが約 40%であった。教育課程実施状況調査問題も,「スケートボード」に関する問題
2 と同様,積の法則を用いて場合の数を求める問題である。しかし,正答率が「スケー
トボード」に関する問題 2 よりも低くなっている。その原因として,「スケートボード」
に関する問題の場合,教育課程実施状況調査問題より,問題場面や状況が理解されやす
く考えが進めやすいということが考えられる。 問 3 の正答率は,53.6 で,問 1 の正答率とほぼ同じである。しかし,この問題は,価
格の表から組合せを作って実際に価格を計算し,120 ゼットに最も近いものを見付け出
さなければならない。例えば,車輪のセットと金具のセットの 4 つの組合せを計算すれ
ばデッキの価格は必然的に決まってしまうので,そのような方略を見いだせば 4 通りの
計算(実際は 3 通りの計算)ですむが,そうでなければ問 2 で求めた 12 通りの計算を
しなければならない。自分で適切な解決のための方略を見いださなければならないので,
問 3 は問 1 より難しい。部分正答になった生徒は,ねらいを定めて計算し他の場合の確
認をしていないか,確認することを忘れたものと思われる。

- 21 -
右の図のように 4 本の縦線 a,b,c,d
とそれらに交わる 5 本の横線でできた図
形の中に点 A があります。このとき,点
A を含む四角形の個数は,次のようにし
て求めることができます。 ① 点 A を含む四角形は,点 A をはさむ縦線 2 本と横線 2 本で決まる。 ② 点 A をはさむ縦線 2 本の組合せは,縦線 a に着目すると,縦線 a と縦線
c,縦線 a と縦線 d の 2 通りがあり,縦線 b に着目した場合も同様に 2通りある。したがって,全部で 4 通りある。
③ 同様に考えて,点 A をはさむ横線の組合せは,全部で ア 通りある。 ④ したがって,点 A を含む四角形の個数は,全部で イ 個である。
上の ア , イ にあてはまる数値を求め, の中に書きなさい。
イ.指導上の留意点
場合の数を求めるとき,基本になるのは和の法則と積の法則を理解し,適切に使い
分けることである。その際,生徒に分かりやすい例を取り上げることが大切であり,解
答についての考察で述べたように,実生活の中にその例を求めるのは有用である。「ス
ケートボード」や「トッピング選び」に関する問題は,日常経験するものであり,特に,
「スケートボード」に関する問 3 は,生活の中で合理的な判断をする方法を考えさせる
ものである。このような生徒が興味や関心をもちやすく,有用な例を普段から準備して
おくことが必要であろう。
a b c d
・A

- 22 -
③ トッピング選び<量の問題であり,②スケートボードの問題の類似問題である>
ベースとしてチーズとトマトの 2 つをトッピングしたピザを出しているピザ屋があります。これ
にトッピングを追加することもできます。追加トッピングとして選べるのはオリーブ,ハム,マ
ッシュルーム,サラミの 4 種類となっています。
学さんは,2 種類のトッピングを追加したピザを注文しようと思っています。
学さんは何通りの組み合わせを選ぶことができますか。
答:.........................................................通り
状況:職業的 能力:関連付け 問題形式:短答形式 学習指導要領との関係:中学校 2 年 C 数量関係 (2)ア 起り得る場合を順序よく
整理することができること
トッピング選びに関する問の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 6
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
正答 誤答 無答
日本 66.1 31.4 2.5 OECD 平均 48.8 46.1 5.1
ア.結果についての考察 この問題は, 234 ÷× という簡単な計算で答えを求めることができるが,大切なのは
問題の状況を適切にとらえることである。この問題では,追加トッピングとして選ぶこ
とができるのは 4 種類で,この中から 2 種類を選んでトッピングすることが述べられて
いる。選ぶ 2 種類のものの順序を考慮する必要はないので組合せの総数を求めればよい
と正しく判断することが必要である。 正答率は 66.1%で,OECD 平均より約 20 ポイント上回っており,また,国際比較を
すると,我が国の正答率は 13 ヵ国中では最も高い。誤答としては, 44× 又は 34× , 44 +と計算したものなどが考えられる。
平成 14 年度高等学校教育課程実施状況調査で「6 枚のトランプのカードから 2 枚の
カードを選ぶとき,選び方の総数を求めなさい」という問題を出しているが,この問題

- 23 -
の正答率は約 55%であった。教育課程実施状況調査の問題の方が,この問題より求め
る場合の数は大きくなっているが,問題の状況は分かりやすい。この問題の正答率の方
が実施状況調査の正答率より高くなっていることから,生徒にとっては,「トッピング
選び」のような問題設定の方がより興味をもちやすいとも考えられる。 イ.指導上の留意点
問題の状況を適切に解釈することをまず大切にしたい。状況が十分にとらえられな
い生徒に対しては,具体的な場合を書き出してみるよう指導したい。例えば,この問
題では(オリーブ,ハム),(オリーブ,マッシュルーム),・・・などと書き出すか,樹
形図を用いてかき出すことで,どのように考えを進めていけばよいかをとらえること
ができよう。

- 24 -
④ 花壇<経年比較で,正答率が下がっている>
ある人が,長さが 32 m の木材を使って,花壇の外わくを作りたいと考えています。この人は次
のようなデザインを考えています。
長さが 32 m の木材で,A~D それぞれのデザインの花壇を,作ることができますか。「できる」
または「できない」のどちらかを○で囲んでください。
デザインの種類 32 メートルの木材で,できるかできないか
デザイン A できる / できない デザイン B できる / できない デザイン C できる / できない デザイン D できる / できない
A B
C
10 m
6 m
10 m
10 m 10 m
6 m
6 m 6 m
D

- 25 -
状況:教育的 能力:関連付け 問題形式:複合選択肢形式 学習指導要領との関連:中学校 2 年 B 図形 (2)イ 三角形の合同条件を理解し,そ
れに基づいて三角形や平行四辺形の性質を論理的に確かめるこ
とができる
花壇に関する問の採点基準
コード 回答
完全正答(2点)
2
デザイン A~D のすべてについて正しい答え デザインA:できる
デザインB:できない
デザインC:できる
デザインD:できる
部分正答(1点)
1 4 つのうち 3 つについて正しい答え
誤答/無答(0点)
0 4 つのうち 2 つ以下について正しい答え
9 無答
4つ正答 3つ正答 2つ正答 1つ正答 誤答 無答 日本 37.8 32.4 13.0 14.1 1.4 1.3
OECD平均 20.0 30.8 19.4 25.8 1.6 2.5
日本 OECD 平均
2003 年 37.8 20.0
2000 年 42.6 19.9 2003 年-
2000 年-4.8 0.1

- 26 -
ア.結果についての考察 この問題は,実生活にも関係しているが,どちらかと言えば教室の中で見られる擬似
現実的な問題といえる。A と C の図形については辺を移動することによって縦 6m,横
10m の長方形に変形できる。したがって,A,C,D の花壇の外枠は長さ 32m の木材で
作ることができる。B の図形は,2 つの辺の長さが高さの 6m より長くなり,B の花壇
の外枠は長さ 32m の木材で作ることはできない。 結果については,前ページの表のような表記がなされているので,1 つ正答,2 つ正
答,3 つ正答について A,B,C,D のいずれに正答しいずれに誤答したのか,判断が
できない。したがって,2000 年調査から約 5 ポイント正答率が下がった原因について
も明確なことは述べられない。 イ.指導上の留意点
A,C の図形を縦 6m,横 10m の長方形に変形するときにもとになるのは,向かい合
う長方形の 2 辺の長さが等しいということであり,B の図形(平行四辺形)の 2 つの辺
の長さが高さより長いというのは,直角三角形の斜辺の長さは他の 2 辺の長さより長い
ということである。したがって,まず,このような基本的な知識を確実に定着させるこ
とが大切である。 また,1 つの知識をいろいろな場面で活用し多面的な見方をしておくことも必要であ
る。ここでいえば,2 つの辺の長さが等しいときには,一方の辺をもう一方に移動して
考えることができるということである。なお,ある問題を解決するとき,生徒からいろ
いろな解法を引き出し,表現させることもこのような力を育てる上で有効である。

- 27 -
⑤ 歩行<経年比較の結果,正答率が下がっている>
上の写真は,ある人が歩いた足跡を示しています。歩幅 P は「左右の足跡のカカトからカカト
まで」の距離とします。
男性の場合,n と P のおよその関係は,公式 140=Pn
で表わせます。
ただし,
n = 1 分間の歩数
P = 歩幅(m)
歩行に関する問 1
晴夫さんの歩数は 1 分間に 70 歩です。この公式を晴夫さんの歩行に当てはめると,晴夫さんの歩幅は
どれくらいですか。 どのように考えたのかも示してください。 歩行に関する問 2
博さんは自分の歩幅が 0.80 m であることを知っています。公式を博さんの歩行に当てはめます。
博さんの歩く速度は 1 分当たり何 m か,また 1 時間当たり何 km かも求めてください。どのよう
に考えたのかも示してください。

- 28 -
問 1 状況:私的 能力:再現 問題形式:自由記述形式 学習指導要領との関連:中学校 1 年 C 数量関係 (1)エ 比例,反比例の見方
や考え方を活用できること 歩行に関する問 1の採点基準
コード 回答
完全正答(2点)
2
0.5m または 50cm または 21
(単位は,なくても可)
•
5.014070
14070
==
=
pp
p
• 14070
部分正答(1点)
1
公式に数値を正しく代入しているが,答えが誤り,または答えを出してい
ない。
• 14070=
p [公式に数値を代入したのみ]
• 14070=
p
p14070 =
2=p [代入は正しいが,計算結果が誤り]
または,
公式を正しく変形して,140
np = にしたが,その後の作業が正しくない。
誤答/無答(0点)
0 その他の答え • 70cm
9 無答
完全正答 部分正答 誤答 無答 日本 40.9 27.9 12.9 18.3 OECD 平均 36.3 21.8 20.9 21.0

- 29 -
日本 OECD 平均 2003 年 40.9 36.3
2000 年 46.1 34.3 2003 年-
2000 年-5.2 2.0
(注) 問 1 は完全正答の生徒の割合だけを正答率としている。
問 2 状況:私的 能力:関連付け 問題形式:自由記述形式
学習指導要領との関連:中学校 1 年 C 数量関係 (1)エ 比例,反比例の見方
や考え方を活用できること 歩行に関する問 2の採点基準
コード 回答
完全正答(3点)
31
分速何メートル,時速何キロメートルがともに正解(単位は不要) • n = 140 x .80 = 112 • 博さんは 1 分当たり 112 x .80 m = 89.6 m 歩く。 • 速度は 1 分当たり 89.6 m。 • したがって,時速 5.38 km または 5.4 km。
分速・時速とも正解であれば計算経過の有無を問わない。概数による誤差
は,可(例 分速 90 m,時速 5.3 km (89 X 60) )。 • 89.6,5.4
• 90,5.376 km/時
• 89.8,5.376 m/時[注記:時速について単位を付してない答えは,コード 22
とすること]【注 km/時なら単位不要(問に書いてあるので)m/時で単位を付
けていないとコード 22】
部分正答(2点)
21
コード 31 と同様だが,歩数を分速(メートル)に換算するための 0.80 を
掛けていない。例 毎分 112 m,時速 6.72 km。 • 112,6.72km/時
22
分速 (89.6 m)は正しいが,時速(キロメートル)への換算が誤っている,
または抜けている。 • 89.6,時速 8,960 km
• 89.6,5376
• 89.6,53.76
• 89.6,0.087km/時
• 89.6,1.49km/時

- 30 -
23
方法は正しい(明記されている)が,小さな計算間違いがあり,コード 21 または コード 22 に該当しないもの。答えは 2 つとも誤り。 • n=140 x0 .8 = 1120; 1120 x 0.8 = 896. よって分速 896 m,時速 53.76km。
• n=140 x0 .8 = 116; 116 x 0.8 =92.8. 分速 92.8 m,時速 5.57km。
24
時速 5.4 km のみ答えて,分速 89.6 m を答えていない(途中の計算も示し
ていない)。 • 5.4 • 5.376 km/時
• 5.376 m/時
部分正答(1点)
11
n=140×0.80=112 とし,その後がない,またはこの観点で誤ったやり方
を示している。 • 112 • n=112, 0.112km/時
• n=112,1120km/時
• 分速 112 m,時速 504 km
誤答/無答(0点)
00 その他の答え
99 無答
完全正答 部分正答
(2点)
部分正答
(1 点)誤答 無答
日本 18.2 20.2 6.9 24.1 30.7 OECD 平均 8.0 9.0 19.9 24.4 38.7
日本 OECD 平均
2003 年 33.9 20.6
2000 年 37.2 18.9 2003 年-
2000 年-3.3 1.7
(注) 問 2は,完全正答の生徒の割合に,2つの部分正答の生徒の割合を 0.5
倍して加えたものを正答率としている。
ア.結果についての考察
問 1 の正答率は 40.9%で,完全正答のみが正答とされている。この問題には,1 分間
の歩数と歩幅の関係式が示されており,この関係式は興味深いものであるが,ここでは
その式を利用するだけである。部分正答の割合が 27.9%である。採点基準から分かるよ

- 31 -
うに,この部分正答には,関係式に数値は正しく代入されているが,代入したままで終
わっていたり,答えが誤ったりしたものが含まれる。この誤りは,関係式に数値を代入
すると未知数が分母に来るので,その後の処理が適切にできなかったものと考えられる。
正答率が 2000 年調査から 5.2%下がった理由は,前ページの表からだけでは判然としな
いが,部分正答の生徒の割合が増えた可能性は考えられる。 問 2 は,与えられた関係式から 1 分間の歩数を求め,さらに分速と時速を求めなけれ
ばならない。採点基準から分かるように,部分正答(2 点)には,分速か時速のどちら
か一方を間違っているものや解法は正しいが小さな計算間違いがあるものなどが含ま
れる。また,部分正答(1 点)には,関係式から 1 分間の歩数を求めたが,その後の処
理ができなかったものも含まれる。 完全正答及び 2 つの部分正答の生徒の割合を単純に加えると 45.3%であるので,問 1
の完全正答の生徒の割合と比して未知数が分子にある問 2 の場合には,関係式に数値を
代入した後,計算をした生徒の割合が少し増えていることが分かる。「簡単な関係式に
ついて,未知数が分子にあれば計算できるが,未知数が分母にある場合には計算するこ
とができない」生徒が少し増えてきているといえるかもしれない。 国際比較をすると,我が国の正答率は 13 ヵ国中では香港に次いでよく,完全正答の
生徒の割合は香港とほぼ同じである。香港と大きく異なるのは,部分正答(1点)の生
徒の割合と無答の生徒の割合である。問 1 で誤答になった生徒の割合と無答であった生
徒の割合を加えるとほぼ問 2 の無答の生徒の割合に等しくなる。したがって,問 1 がき
ちんと答えられなかったので,問 2 を答えるのをやめてしまった生徒もいると考えられ
る。 イ.指導上の留意点
分数方程式は現在の教育課程では扱われていないが,例えば 140=Pn
という式は,
Pn 140= という式に簡単に変形できるので,扱いの難しい式ではない。中学校 1 年の反
比例の指導では,xay = という式と axy = という式は同じ式であるということを学習し,
必要に応じて使いやすい方を使うよう指導されている。その際,関連して本問のような
内容も発展的に扱えばよい。 実生活の中から生徒が興味や関心をもちやすいものを集め,日ごろから準備をしてお
くことや,単に代入して計算するのではなく計算するための工夫が必要であることを学
ぶことが大切であろう。

- 32 -
⑥ 身長<自由記述形式で,正答率が OECD 平均をやや下回っており,また経年比較でも
正答率が下がっている>
オランダの 1998 年の若い男女の平均身長が,下のグラフに示されています。
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
190
180
170
160
150
130
140
身長
(cm)
1998 年の若い男子の平均身長
1998 年の若い女子の平均身長
年齢(歳)

- 33 -
身長に関する問 1
1980 年からみると,20 歳の女子の平均身長は 2.3 cm 伸びて,現在 170.6 cm です。1980 年の
20 歳の女子の平均身長はどのくらいでしたか。
答え:........................................................cm
身長に関する問 2
女子の平均身長について,12 歳以降はその増加の割合が低下しています。このことがグラフでど
のように示されているか,説明してください。
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
身長に関する問 3
このグラフによると,女子の平均身長が同じ年齢の男子の平均身長を上回っているのはいつです
か。
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

- 34 -
問 1 状況:科学的 能力:再現 問題形式:求答形式 学習指導要領との関連:小学校 4 年 A 数と計算 (4)小数の意味とその表し方
について理解するとともに,小数の加法及び減法の意味に
ついて理解し,それらを用いることができるようにする 身長に関する問 1の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 168.3 cm (単位 cm は設問中にあり)
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
正答 誤答 無答 日本 78.3 13.1 8.6
OECD 平均 67.0 24.7 8.3
日本 OECD 平均
2003 年 78.3 67.0
2000 年 76.6 61.6 2003 年-
2000 年 1.7 5.4
問 2 状況:科学的 能力:関連付け 問題形式:自由記述形式
学習指導要領との関連:小学校 4 年 D 数量関係 (3)ウ 資料を折れ線グラフ
に表したり,グラフから特徴や傾向を調べたりすること 身長に関する問 2の採点基準
コード 回答
正答(1点)
重要なのは女子のグラフの傾きの「変化」を述べることにある。明示的
でも暗示的でもよい。コード 11 と 12 はグラフの傾きについて明示し
たもので,コード 13 は増加量そのものについて 12 歳前と後を暗示的
に比較したもの。

- 35 -
11
12 歳以降の傾きの鈍化を述べている。数学用語でなく日常用語を用いて
いる。 • 以降はまっすぐ伸びていない。まっすぐより外れている。
• カーブが下がっている。
• 12 歳以降は前よりなだらかになる。
• 女子の線は平らになるが,男子の線は上がって行く。
• まっすぐより外れる。男子のグラフは上がり続ける。
12
数学用語を用いて,12 歳以降の傾きの鈍化を述べている。 • 傾きが小さくなっている。
• 12 歳以降はグラフの変化率が減少している。
• [生徒が,12 歳前と後の曲線のx軸に対する角度を実際に測っているもの]
一般に「傾き」「勾配」「変化率」等の語があれば,数学用語を用いて
いるとみなすこと。
13
増加量そのものを比べている(比較は暗示的でも可)。 • 10 歳から 12 歳までの増加は約 15cm だが, 12 歳から 20 までの増加は
わずかに約 17 cm である。
• 10 歳から 12 歳までの増加率は年平均約 7.5cm だが,12 歳から 20 歳ま
では年平均 2cm である。
誤答/無答(0点)
01
「女子の身長が男子より下る」ことを述べているが,女子のグラフの傾
きや,女子の 12 歳前と後の成長率の差異を述べていない。 • 女子の線が男子より下がっている。
解答が「女子のグラフの傾きが前よりゆるくなっている」ことと「男子
より下がっている」ことを同時に述べている場合は,完全正答 (コード 11, 12 or 13) とすること。題意は男子と女子の比較を求めていないの
で,男子と女子の比較の答えについては無視し,それ以外の部分で判定
すること。
02
その他の誤った答え。例えば,設問が明白にグラフについて質問してい
るのに,グラフの特徴を述べていない答え。 • 女子は成熟が早い。
• 女子は男子より早く思春期に入るので,身長が伸びはじめるのも早いから。
• 女子は 12 歳以後,身長があまり伸びない。[12 歳以後伸びが減るとは言っ
ているが,グラフについて述べていない。]
99 無答

- 36 -
正答 誤答 無答 日本 43.3 27.4 29.3
OECD 平均 44.8 34.1 21.1
日本 OECD 平均
2003 年 43.3 44.8
2000 年 45.0 45.8 2003 年-
2000 年-1.7 -1.0
問 3 状況:科学的 能力:再現 問題形式:求答形式
学習指導要領との関連:小学校 4 年 D 数量関係 (3)ウ 資料を折れ線グラフ
に表したり,グラフから特徴や傾向を調べたりすること 身長に関する問 3の採点基準
コード 回答
完全正答(2点)
21
正しい年齢幅 11-13 歳 • 11 歳と 13 歳の間
• 11 歳から 13 歳まで,女子は男子より平均身長が高い。
• 11 歳~13 歳
22
11,12 歳になると,身長は女子が男子を上回る,と述べている。(日常用
語でこのように言うことは,年齢幅 11~13 歳を意味するので,正解) • 11,12 歳になると,身長は女子が男子を上回る。
• 11~12 歳
部分正答(1点)
11
完全正答の欄に示した以外で 11,12,13 歳にわたる答え • 12 ~13 歳
• 12 歳
• 13 歳
• 11 歳
• 11.2~12 .8 歳
誤答/無答(0点)

- 37 -
00
その他の答え • 1998 年
• 13 歳以降は女子が男子より身長が高い。
• 10 歳から 11 歳までは女子が男子より身長が高い。
99 無答
完全正答 部分正答 誤答 無答 日本 62.5 23.9 5.5 8.1 OECD 平均 54.7 28.1 9.7 7.5
日本 OECD 平均
2003 年 74.5 68.8
2000 年 77.5 69.4 2003 年-
2000 年-3.0 -0.6
ア.結果についての考察
問 1 は,単純な引き算で解決できるものであり,国際比較をすると,我が国の正答率
は 13 ヵ国中では韓国,フランスに次いで高いものであった。 問 2 の正答率は,43.3%で OECD 平均(44.8%)を 1.5 ポイント下回っている。国際
比較をすると,我が国の正答率は 13 ヵ国中では香港,イタリアに次いで低いものであ
った。また,無答率が OECD 平均より 8 ポイントあまり上回っている。関数の変化の
様子を数学的に表現することについては,小学校,中学校,高等学校と繰り返し指導さ
れているが,そのような力は十分には育っていないと考えられる。 問 3 の部分正答は,採点基準から分かるように,グラフはよみ取っているが完全には
解答できていないものである。問いが「平均身長を上回っているのはいつですか。」と
なっているのでどのように答えればよいか迷ったことも考えられる。 イ.指導上の留意点
数学では,変化の様子を的確にとらえるためにグラフを利用するが,生活していく上
ではグラフをかきそのグラフからどのようなことをよみ取るかが大切になってくる。こ
の問題では,「グラフの傾きが 12 歳以降,それまでよりゆるやかになっているので,女
子の平均身長の増加の割合が低下している」ことをよみ取ることができるかどうかをみ
ようとしている。グラフを利用して変化の様子をとらえるには,グラフの傾きの変化に
目を向けることが必要であり,このことは数学科では繰り返し指導されている。 グラフの傾きを考える意味を理解させるため,変化の様子が一定でないグラフについ
て,その様子を自分の言葉で表現させ表現をより適切で説得力のあるものにしていく過
程で,「グラフの傾き」に気付かせるなどの工夫をしたい。

- 38 -
当然のことであるが,このように繰り返し指導されている内容や,ある内容に関連し
た内容については,異なる学校種間で「どのような指導がなされているか」を互いに把
握しておくことが大切である。導入場面などで適宜取り上げることにより,生徒の理解
を容易にしたり,興味や関心を高めたりすることにつながると考えられる。

- 39 -
⑦ 輸出に関する問題<問題のグラフは生活の中でよく目にするグラフであるが,グラフ
をよむ問題で,OECD 平均を 10 ポイント以上下回っている> 下のグラフは,通貨としてゼットを用いるゼットランド国の輸出に関する情報を表しています。
輸出に関する問 1
1998 年のゼットランド国の総輸出額はいくらでしたか(単位:百万ゼット)。
答え:
輸出に関する問 2
2000 年にゼットランド国が輸出したフルーツジュースの金額はいくらでしたか。
A 1.8 百万ゼット B 2.3 百万ゼット C 2.4 百万ゼット D 3.4 百万ゼット E 3.8 百万ゼット
ゼット国の輸出品の分布
(2000 年)
1996-2000 年のゼット国の年間輸出額
(単位:百万ゼット)
年
タバコ
7%
羊毛
5%
綿織物
26%
フルーツジュース
9% 米
13%
茶
5%
肉類
14%
その他
21%
20.4
25.4 27.1
37.9
42.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1996 1997 1998 1999 2000

- 40 -
問 1 状況:公共的 能力:再現 問題形式:求答形式 学習指導要領との関連: 小学校 3 年 D 数量関係 (1)イ 棒グラフのよみ方及びかき方について知る
こと 小学校 4 年 A 数と計算 (4) ア 端数の大きさを表すのに小数を用いるこ
と。また,小数の表し方及び 1/10 の位について知ること 輸出に関する問 1の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 27.1 百万ゼットまたは 2,710 万ゼットまたは二千七百十万ゼットまたは
27,100,000 ゼットまたは 27.1(単位不要)。切り上げた 27 でも可。
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
正答 誤答 無答 日本 64.6 28.8 6.5
OECD 平均 78.7 13.8 7.5 問 2 状況:公共的 能力:関連付け 問題形式:選択肢形式
学習指導要領との関連: 小学校 5 年 D 数量関係 (2)百分率について理解し,それを用いることがで
きるようにする 輸出に関する問 2の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 E 3.8 百万ゼット
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
A B C D E 無答 日本 10.2 8.9 13.8 8.2 54.9 4.0
OECD 平均 10.5 10.2 16.2 7.8 48.3 6.9

- 41 -
ア.結果についての考察 問 1 は,棒グラフから 1998 年の年間輸出額を答えればよい。そのまま答えれば 27.1
百万ゼットであるが,これでも正答となっている。グラフを正しくよむことができれば,
容易に正答になる問題である。 正答率は 64.6%で,OECD 平均を約 14 ポイント下回っている。また,国際比較をす
ると,我が国の正答率は 13 ヵ国中では韓国と並んでアメリカの次に低い。誤答が 28.8%あることから,このような状況に至った主な原因として,単位となっている百万ゼット
の取り扱いを誤ったことが考えられる。 問 2 は,2 つのグラフから 42.6 百万ゼットと 9%を見いだし,42.6×0.09 を計算すれ
ばよい。解答は選択肢となっているので,概数で計算し最も近いものを答えればよい。 正答率は,54.9%で OECD 平均を約 6 ポイント上回っている。5 つの選択肢は,それ
ぞれ 1996 年から 2000 年までの年間輸出額に 0.09 を乗じたものである。誤答では,13カ国のいずれの国でも C を選んだ生徒の割合が高いが,これは 1998 年の年間輸出額に
0.09 を乗じたものである。問 1 で 1998 年の輸出額を取り上げているのでそれに影響さ
れたことが考えられる。 イ.指導上の留意点
ここで取り上げられるグラフは,社会科(地理分野)などで扱われることが多い。特
に算数や数学では,27.1 百万ゼットのような数値の扱いをあまりしないので,このよう
な表記に不慣れな生徒が多いと考えられる。算数,数学でも他教科との関連を踏まえ,
授業の導入部などで他教科の題材についても積極的に取り上げるようにしたい。

- 42 -
⑧ 盗難事件<正答率は前回調査の結果を上回っているが,OECD 平均をやや下回っており,
正答率もあまり高くない>
ある TV レポーターがこのグラフを示して,「1999 年は 1998 年に比べて,盗難事件が激増して
います」と言いました。
このレポーターの発言は,このグラフの説明として適切ですか。適切である,または適切でない
理由を説明してください。
年間の
盗難事件数
1999 年
1998 年
505
510
515
520

43
状況:公共的 能力:関連付け 問題形式:自由記述形式 学習指導要領との関連: 小学校 3 年 D 数量関係 (1)イ 棒グラフのよみ方及びかき方について知ること 小学校 5 年 D 数量関係 (3)百分率の意味について理解し,それを用いることが
できるようにする
盗難事件に関する問の採点基準
コード 回答
完全正答(2点)
21
[注:以下のコードにおける「適切ではない」という答えは,「レポーター
のグラフ解釈が適切でない」ことをあらわしたあらゆる文章をさす。「適
切である」も同様。評価する際,単に語句上の「適切である/適切ではな
い」でコード化することなく,生徒の解答がこのレポーターのグラフ解釈
を適切だと表明しているか否かで評価すること。]
適切ではない。グラフのごく一部が示されているにすぎないという事実に
着目している。 • 適切ではない。グラフの全体が表示されるべきである。
• グラフ全体が示されれば,盗難事件の増加はわずかな増加にすぎないことが
わかるため,グラフの適切な解釈だとは思えない。
• 適切でない。このレポーターはグラフの先端だけ見たが,0~ 520 件までの
全体を見れば,それほど増加していない。
• 適切でない。グラフを見ると大きく増加しているように見えるが,数値を見
ればそれほど増加していない。
22
適切ではない。割合またはパーセントの増加に関する正しい説明をしてい
る。 • 適切ではない。全体の 500 件に対して 10 件の増加は急激な増加ではない。
• 適切ではない。パーセントにすれば,その増加はおよそ 2%にすぎない。
• 適切ではない。8 件の増加は 1.5% であり,多いとは言えないと思う。
• 適切ではない。 今年の増加は 8~ 9 件にすぎず, 507 件に比べると大きく
ない。
23
判断するには時系列データが必要だとする答え • 激増かどうかは言いきれない。1997 年の盗難の数が 1998 年と同様なら,
1999 年に大きく増加したと言えるかもしれない。
• 「激増」とは何か,わからない。増加が大きいか小さいかは,少なくとも変
化が 2 つ以上ないと,考えられない。
部分正答(1点)

44
11
適切ではない。しかし説明が詳細でない。 盗難件数の実数の増加にのみ着目し,全体の件数と比較していない。 • 適切ではない。10 件の盗難事件が増えたにすぎない。「激増」という言葉は
盗難件数の増加の実状を説明していない。増加はおよそ 10 件にすぎず,これ
を「激増」とは言わない。
• 508 件から 515 件への増加は大きな増加ではない。
• 適切でない。8~9 件は大きな量ではない。
• 多少は増えた。 507 件から 515 件へは,増加であるが激増ではない。
[注:グラフの目盛が明瞭でないことから,増加の実数の読み方は 5 件
から 15 件まで認める。]
12 適切ではない。方法は正しく,細かな計算ミスがある答え • 方法,結論とも正しいが,増加率を 0.03%とした答え
誤答/無答(0点)
01
適切ではない。不充分または誤った説明。 • 賛成できない。
• このレポーターは「激増」と言うべきでなかった。
• 適切でない。TVレポーターは大げさに言う傾向がある。
02
適切である。グラフの見かけに重点を置いて,盗難件数が 2 倍になったと
指摘している。 • 適切。グラフの高さが 2 倍になっている。
• 適切。盗難件数がほぼ 2 倍になっている。
03 適切。説明なし,またはコード 02 以外の説明
04 その他の答え
99 無答
完全正答 部分正答 誤答 無答 日本 11.4 35.4 38.8 14.4 OECD 平均 15.4 28.1 41.5 15.0
日本 OECD 平均
2003 年 29.1 29.5
2000 年 24.9 26.5 2003 年-
2000 年 4.2 3.0

45
ア.結果についての考察 我が国の結果は,完全正答と比較して部分正答の割合が多く,部分正答の割合は完
全正答の 3 倍以上である。採点基準から分かるように,部分正答には,盗難件数の実
数の増加のみに着目し,全体の件数と比較せずに「この程度の増加は激増ではない」
などの説明をしているものが含まれる。「為替レート」に関する問題でも述べたが,自
分の考えを整理し自分の考えを数学的な表現(記述)を用いて説明する問題では,正
答率があまり高くない。特に,この問題の正答率が高くないのは,「適切か,適切でな
いか」の判断をし,その上でその理由を説明するものであったからだと思われる。
イ.指導上の留意点
自分の考えを自分の言葉で表現しながら,他の生徒を納得させるような指導を大切
にしたい。そのような指導の中で,数学的な表現のよさ(的確性,簡潔性など)を理
解させ,数学的な表現に習熟させたい。 また,この問題は,数学が使われる状況として公共的に分類されているが,社会の
中でものごとを批判的に理解することは大切なことである。他の人が述べた意見に対
して「なぜ?本当か?」と確認しながら理解する力は,算数や数学の授業を通して身
に付けさせるようにしたい。

46
⑨ 地震<正答率は OECD 平均を上回っているが,今回課題と考えられる不確実性,熟考,
選択肢の問題である>
地震と地震の頻度についてのドキュメンタリー番組が放送されました。番組では地震を予知でき
るかどうかについても議論が交わされました。
ある地質学者は次のように言いました。「今後 20 年以内にゼットランド市で地震が起きる確率
は 3 分の 2 だ」
この地質学者の言葉の意味を一番よく反映しているのは次のどれですか。
A 13.32032
=× 。だから,いまから 13 年から 14 年の間にゼットランド市では地震が起きる。
B 32 は
21より大きい。だから,今後20年の間にゼットランド市ではいつか必ず地震が起きる。
C 今後 20 年の間にゼットランド市で地震が起きる確率は,地震が起きない確率より大きい。 D 地震がいつ起きるかはだれも確信できないので,何が起きるかを予言することはできない。
状況:科学的 能力:熟考 問題形式:選択肢形式 学習指導要領との関連:中学校 2 年 C 数量関係 (2)イ 不確定な事象が起こり得
る程度を表す確率の意味を理解し,簡単な場合について確率を
求めることができる
地震に関する問の採点基準
コード 回答
正答(1点)
1 C
誤答/無答(0点)
0 その他の答え
9 無答
A B C D 無答 日本 8.1 11.4 68.0 7.9 4.7 OECD 平均 9.8 12.3 46.5 22.0 9.3

47
ア.結果についての考察 この問題の正答率は 68.0%で,国際比較をすると,我が国の正答率は 13 カ国中では
最も高い。前ページの表で,日本の結果と OECD 平均を比較すると分かるように,日
本の誤答で最も割合の高いのは B であるが,OECD 平均では D である。A,B で述べ
られていることは誤りであるが,D で述べられていることは誤りとは言えない。しか
し,「地質学者の言葉の意味を一番反映している」には当たらない。 平成 13 年度小中学校教育課程実施状況調査では,次のように,この問題と類似した
問題が中学校 3 年で出題されている。
1の目が出る確率が61であるさいころがあります。このさいころを投げるとき,
どのようなことがいえますか。下のア~オの中から最も適切なものを 1 つ選んで,
その記号を の中に書きなさい。 ア 5 回投げて,1 の目が 1 回も出なかったとすれば,次に投げると必ず 1 の
目が出る。 イ 6 回投げるとき,そのうち 1 回は必ず 1 の目が出る。 ウ 6 回投げると,1から 6 までの目が必ず 1 回ずつ出る。 エ 30 回投げるとき,そのうち 1 の目は必ず 5 回出る。 オ 3000 回投げると,1 の目はおよそ 500 回出る。
この問題の正答率は 54.4%であったが,誤答として多かったのはイ(25.6%)であ
った。前述のように「地震」に関する問題でも多かった誤答は B であり,同様の間違
いと考えられる。この主な原因として,確率についての意味理解が不十分なことが考
えられる。
イ.指導上の留意点 この問題は,正答率を国際比較すれば悪くはないが,さらに正答率を改善するため
には確率の意味理解をより重視する必要がある。平成 13 年度小中学校教育課程実施状
況調査報告書には「実験を通して体験的に確率の意味を理解する活動を重視する必要
がある」と述べられている。生徒の実態に応じた適切な体験を通して,確率の意味の
理解と数学的確率のよさの感得が図られると思われる。

48
Ⅲ 学習指導の改善に向けて
IEA(国際教育到達度評価学会)が行っている TIMSS は,それぞれの国で生徒が学校
カリキュラムの内容をどの程度習得しているかを調査・分析するものである。一方,
OECD(経済協力開発機構)が行っている PISA は,それぞれの国の子どもたちが将来生
活していく上で必要とされる知識や技能を活用する力が義務教育修了段階においてど
の程度身に付けているかを調査・分析するものである。したがって,PISA 調査では,学
校の教科で扱われる一定範囲の知識の習得を超えた部分まで評価しようとしており,生
徒がそれぞれ持っている知識や経験をもとにして,自らの将来の生活に関係する課題を
積極的に考え,課題解決に知識や技能を十分活用する能力があるかどうかをみるものと
なっている。それゆえ,数学的リテラシーに関する指導の改善においても,教育課程全
体で改善を考えていく視点が大切である。 算数・数学科では,次の四点を述べておく。
(1)基本的な概念の理解(意味理解)及び数学的に解釈し表現する指導を重視するこ
と 「身長」に関する問題の問 2 では,「女子の平均身長の増加の割合が低下している
ことがグラフでどのように示されているか」が問われている。この問いの正答率は
43.3%で OECD 平均の 44.8%を下回っており,無答率も 29.3%でイタリアの 30.9%についで高くなっている。 数学では,基本的な概念の理解(意味理解)が十分でなければ,状況(問題の文
脈)が変わったとき,身に付けた知識や技能を活用できなくなる可能性があり,い
ろいろな状況で問題の解決に数学的リテラシーを活用する力を育てるには,算数・
数学科で基本的な概念の理解(意味理解)を一層重視すべきである。 また,前述のように「身長」に関する問題で無答率が 30%程度であったが,その原
因として,自分の考えを自分の言葉で表現したり,他の生徒に分かりやすく説明した
りする経験が十分でないことが考えられる。「為替レート」に関する問題の問 3 や「盗
難事件」に関する問題など,状況やデータを解釈し,それに基づいて自分の考えを整
理し自分の考えを数学的な表現を用いて説明(記述)する問題でも,正答率があまり
高くない状況がみられた。
自分の考えを数学的な表現を用いて説明する力は,今後いろいろな場面で必要にな
ると考えられる。数学的な表現を解釈し,同時に適切な数学的な表現で自分の考えを
説明する指導を今後,一層重視する必要がある。具体的には,生徒の考えを発表させ,
発表された考えを生かしながらよりよい考えに高めていく,いわゆる練り上げの授業
を重視すべきであろう。なお,基本的な概念の理解(意味理解)は自分の考えを表現
し確認しながら深められると考えられるので,基本的概念の理解(意味理解)の指導
と併せて,数学的に解釈し表現する指導を大切にしたい。 (2)実生活と関連させた指導を重視すること
PISA の問題は,生徒が現在,あるいは将来遭遇すると考えられる私的,教育的,職

49
業的な生活場面などを想定し作成されている。 例えば,「スケートボード」や「トッピング選び」に関する問題は,それぞれの店を
実際に訪れたとき,多くの人が自然に考えるような問題である。 「スケートボード」に関する問題の問 2 の正答率は 67.0%,「トッピング選び」に関
する問題の正答率は 66.1%であった。一方,これら 2 つの問題と同様の解法が使える
平成 14 年度高等学校教育課程実施状況調査問題の場合,正答率はこれら 2 つの問題よ
り低かった。この原因として,「トッピング選び」や「スケートボード」に関する問題
の場合,教育課程実施状況調査問題より,問題場面や状況が理解されやすいというこ
とが考えられる。また,実生活に関することであるので,興味や関心が増し,問題解
決への意欲が増したということも考えられよう。
算数・数学科での学習内容を実生活と関連させ考えさせることは,数学的な概念を
理解しやすくすることや,それまでさほど意識していなかった生活における課題を,
数学を用いて解決できる課題として意識することにつながる。さらに,生活の中の課
題を数学的に解決することは,生活を合理化すると同時に,生徒が数学の有用性や実
用性を認識し,算数・数学に対する好感度や有用性の意識を変えることにつながると
考えられる。例えば,授業の導入に学習内容と関連した生活の中の話題を取り入れた
り,生活の中の課題を既習の内容を活用して解決させたりすることなどが考えられる。 今回公表された PISA2003 の問題も参考にし,算数・数学科での学習内容を実生活
と関連付けた指導を重視すべきである。
(3)他教科や総合的な学習の時間で扱われる内容との関連を図ること (2)で述べたことと関連するが,算数・数学科の内容と理科や社会科,技術・家
庭科などの各教科,総合的な学習の時間の内容と関連を図り,適宜算数や数学の授業
に指導内容として取り入れることは,算数・数学科での学習内容をより豊かにし,い
ろいろな場面で生徒が知識や技能を有効に活用することにつながる。 例えば,「為替レート」の問題や「輸出」の問題は社会科の地理的分野で扱われる可
能性があるが,中学校の数量関係の指導の導入場面などで取り入れることは可能であ
ろう。また,総合的な学習の時間にアンケート調査などの調査を行ったとき,統計と
関連した内容を扱うことは可能である。PISA では,統計的な問題が出題されることが
少なくないが,これはリアルデータに基づいて自分の考えをまとめ上げることが生活
の中で重視されると考えているからであろう。実際,新聞やテレビなどには様々な統
計データがあふれている。実生活において大切なことは,「盗難事件」に関する問題で
示唆されるように,新聞やテレビなどで扱われる統計データから結論されていること
がらを鵜呑みにするのではなく,統計データの表し方の特徴を理解しデータから導き
出されることがらを批判的に理解することである。したがって,総合的な学習の時間
で統計的なデータから自分たちの考えをまとめ上げるときも,小グループなどで活発
に議論をし,お互いの意見に耳を傾けながらもそれぞれの意見を批判的に理解する姿
勢を育てることを大切にしたい。そのような姿勢は,(1)で述べた基本的な概念の理
解など算数や数学を学ぶ態度を形成することにもつながると考えられる。 なお,中学校では,生徒の実態に応じて,統計的な内容を課題学習や選択教科とし

50
ての「数学」で指導することを考えてもよい。 (4)小・中学校,中・高等学校の連携を一層進めること
「身長」に関する問題の問 2 のグラフの傾きのように,小学校,中学校,高等学校
で繰り返し指導されている内容やある内容に関連した内容については,異なる学校種
間でどのような指導がなされているかを互いに把握し,導入場面や発展場面などで適
宜取り上げ,生徒の理解を容易にしたり,興味や関心を高めたりすることが大切であ
る。特にここでは,指導内容,指導方法に関する連携を積極的に行うよう強調してお
きたい。最近,小・中連携,中・高連携は以前より盛んになってきているが,まだ児
童生徒に関する情報交換が大半で,指導内容,指導方法に関する連携は十分には行わ
れていない。また,小・中・高の連携はあまり耳にしない。小・中間,中・高間,小・
中・高間で算数・数学科での内容の扱い方,指導方法などについて意見を交換し合い,
子どもの現状についての理解を進めるとともに,各学校種間での指導のギャップを小
さくし,よりよい指導となる工夫を積極的に行いたい。