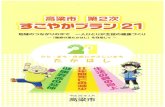Arterial 15 懇話会ABI<1.10、1.10㱡ABI㱡1.50は90%となっている。こ...
Transcript of Arterial 15 懇話会ABI<1.10、1.10㱡ABI㱡1.50は90%となっている。こ...

2
第9回 宮崎血管治療懇話会
PADの予後は大腸がんや乳がんよりも悪い 末梢動脈疾患(peripheral arterial disease;PAD)とは、四肢の末梢動脈が動脈硬化によって狭窄、閉塞することで血流が悪くなる病態をいう。間欠性跛行などが代表的な症状だが、患者の多くは無症状であったり、診断がつかず腰や足に痛みがあるにもかかわらず放置されていたりするケースもある。 PADと同様の動脈硬化性疾患には脳血管障害や急性冠症候群などがあるが、これらは症状が明確で、知名度も高い。そのため発症後はすぐに救急車で搬送されるなどして医療機関で治療を受けるのが一般的な流れである。これに対して、PADは疾患への認知度が低いため「歳のせいだろう」と受診に至らない潜在的な患者が非常に多いと推測される。認知度については患者だけでなく医師への普及も不十分であり、診断および専門病院への紹介に至らない例が多いと思われる。 だが、PADは悪性疾患ではないが、それ以上に予後は悪い。2009年に報告されたPADの5年後の予後を示した
報告1)では、イベント無再発生存率はPADと診断されていない群では9割近いのに対し、無症候性でもPADがあると7割、症候性では6割ときわめて低く、大腸がんや乳がんの予後よりも悪い。だが、PADで足の動脈が閉塞した患者に「大腸がんよりも予後が悪い」と説明しても、なかなか理解を得られないのが実情である。 なぜ予後が悪いか考察すると、PADの背景にpolyvascular diseaseが潜んでいるからである。図 1に2009年のEuropean Heart Journalでの報告2)を示すが、心血管疾患による死亡はPADが2.9%で冠動脈疾患、脳血管障害よりも高くなっていることが分かる。PADは認知度の低さや無症候、非典型的な症例が多いことから、診断に至らない例が多い。一般に冠動脈疾患や脳血管障害では、薬物療法や非薬物療法を取り混ぜたOMT(optimal medical theraphy)が行われているが、PADは診断がつかないため治療にも結びつく機会が少ないと考えられる。また、診断がついていても軽くみられOMTがなされないことが予後の悪さにつながっている。無症候性でも動脈硬化が進行しており、われわれはPADの早期発見と早期のOMTを行う必要性があることを、まずは医療者に広く知って
山科 章(東京医科大学循環器内科学主任教授)
四肢血圧脈波検査による心血管疾患管理
(%)3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
心血管疾患発生率
心血管死亡
2.1
2.9 2.82.9
1.91.9
0.90.91.21.2
2.8
1.6
1.2
イベントの発生率心筋梗塞 脳卒中 (/年)
冠動脈疾患 脳血管疾患 末梢動脈疾患
図1 ● 心血管疾患の発症率(文献2より引用)

3
懇話会
もらうことが目下の使命であると考えている。
動脈硬化性疾患の診断には下肢の血圧測定が重要 2010年に米国心臓病学会(Americal College of Cardiology Foundation;ACCF)と米国心臓協会(American Heart Association;AHA)が、無症候性の成人に対する心血管リスクを評価するためのガイドラインを公表した。それによると、足関節上腕血圧比(ankle brachial index;ABI)はClassⅡa、エビデンスレベルBとなっている。ACCFとAHAによる2011年改訂のPADの管理ガイドラインでも、「50歳未満で糖尿病と他のリスク因子が1つ以上」「50~65歳で喫煙歴あるいは糖尿病」「65歳以上」「運動時に下肢症状(例:跛行)あるいは安静時疼痛」「下肢脈拍の異常」「動脈硬化性の冠動脈疾患、頸動脈疾患、あるいは腎動脈疾患」といったリスクをもつ人では、ABIの測定によりPADの有無を確認する必要があると記載している。 ABIの測定法については、AHAのscientific statementではドプラ計測(Doppler法)が強く推奨されている。ドプラ計測は図23)のごとく駆血帯を後脛骨動脈や足背動脈、および両側の上腕動脈に巻き測定するもので、AHAでは2回ずつ測定することになっている。しかしながら、この計測法ではどんなに手慣れた看護師でも計測に30分はかかってしまうため、少なくともスクリーニングをこの計測法で実施するのは臨床現場においては現実的ではない。 われわれが臨床現場で実施しているのは、オシロメトリック法(Oscillometric法)を用いたABIである。2000年ごろに計測機械が登場している。ドプラ法は測定者によるエラー、6点を計測する間の血圧変動によるエラーなど
があるが、オシロメトリック法ではそういうエラーが回避でき、四肢を同時に測定できるといった利点がある。通常のオシロメトリック法の駆血帯、つまり外来血圧や家庭血圧で測定する上腕に丸めて測る駆血帯は血圧値がドプラ法に比べ高く出る傾向があるが、圧迫カフとセンターカフを別に設けることで、一体型カフよりも正確に計測できる。 そしてオシロメトリック法の最大の利点は、ABIの値だけでなく波形も確認できる点である。これについては後述する。
四肢の脈波波形からみるPAD患者の特徴 われわれのグループは2000年から約1年間にわたり、オシロメトリック法を用いて健診等の受診者約13,000人のデータを収集した。このうち心血管リスクや心血管疾患の既往のまったくない健常者約5,000人から、健常者の測定時の収縮期血圧別に年齢と上腕̶足首間脈波伝播速度(brachial-ankle pulse wave velocity;baPWV)の関連をノモグラムとして作成した(図3)4)。 baPWVとは心臓からの脈波が伝わる速度から血管の硬さを推定する検査で、上腕と足首の脈波から伝わる速度を測る方法である。脈波は心臓から末梢に移動するが、同じ速度で伝わるとすると上腕のほうが下肢より心臓に近いため、当然ながら脈は速く伝わる。心臓から上腕と足関節までの距離の差、上腕と足関節の脈波の立ち上がりの時間差から速度を推定することができる。われわれの調査では、年齢の高い人や測定時に血圧が高い人では脈波速度が速くなり、60歳の健常男性では、baPWVが
右側ABI
DP/PT DP/PT
高いほうの右側足関節収縮期血圧(後脛骨動脈または足背動脈)高いほうの上腕収縮期血圧(左側または右側)
=
左側ABI
高いほうの左側足関節収縮期血圧(後脛骨動脈または足背動脈)
ABI:足関節血圧 /上腕血圧比
高いほうの上腕収縮期血圧(左側または右側)
=
図2 ● ABIの測定(文献3より引用)

4
1,200~1,400cm/secが正常域であると考えられた。 ところで、動脈硬化性疾患を有する患者(図4)では、baPWVや波形、ABIにどのような特徴が生じるのだろうか。まずオシロメトリック法で得られた波形をみると、PADの症状を呈する患者では左足首の波形だけが特化して小さく、なだらかになっている。いわゆる遅脈、小脈である。血圧も低く、ABIも低値である。また左足首の脈の立ち上がりが右足首と比べて遅くなっており、左のbaPWVは低値となっているが、閉塞のため左足の脈の伝達が遅延しているためである。baPWVも左のほうが遅くなり、ABIも低値となる。一方、右足首の脈の立ち上がりをみると、上腕の脈の立ち上がりとの差がほとんどなく、
baPWVは2,275cm/secと著しく高値である。図3をみるとわかるように、50歳の男性としてはきわめて異常高値であり、全身の動脈壁硬化があると考えられる。 2009年に報告されたEvent-free survival by ABI category1)では、ABIの値を5群に分け、5年間のイベント無再発生存率を調べている。これによるとABI<0.50のイベント無再発生存率はほぼ約50%、0.50≦ABI<0.70では約60%、0.70≦ABI<0 .90では約80%、0.90≦ABI<1.10、1.10≦ABI≦1.50は90%となっている。このように0.90より下で予後が悪く、低値になるほど生存率は下がっている。AHAの改正ガイドラインではABIが1.40より上は下腿動脈の石灰化を伴い、正確な計測がで
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
(cm/ 秒)
baPWV
80年齢
50 60 704030
男性
160~150~160140~150130~140120~130 ~120
80(歳)年齢
50 60 704030
女性
図3 ● 健康な健診受診者における測定時収縮期血圧別にみた年齢とbaPWV(文献4より引用)
図4 ● 動脈硬化疾患を有する患者のPAD波形(健診受診者、50歳代、男性)
尋ねると間欠性跛行あり、50m歩くと左下肢痛
動脈触診 大腿 膝窩 足背 後脛骨右 2 2 2 2左 0 0 0 0

5
懇話会
きていない可能性があるため、ドプラ法以外の測定法を用いることを推奨している。1.40未満については、1.01~1.40が正常、0.91~1.00が境界的異常、0.90以下が異常としている。この境界的異常という概念は以前にはなく、近年になり作られた。われわれは、0.90以下は症状が出始めるライン、0.91~1.00は症状はなくても動脈硬化による狭窄があるので異常値であるという認識である。
なぜ“ABI≦0.90”が独り歩きしているのか ガイドラインがABI 0 .91~1.00を境界的異常とする根拠は、2008年のJAMAで報告されたメタ解析(図5)5)
にある。ABIが1.11~1.20に発生する心血管イベントを1とすると、ABIが1.10より低値になるほど男女ともイベント発生ハザード比が高くなり、0.91~1.00では約2倍となるからである。しかし、2014年に報告された別の研究6)では、0.90以下で明らかに心血管イベントの累積発生率が高くなっている。 何が問題かというと「見落とし」の危険性である。九州大学のグループが実施した4,000人あまりの糖尿病患者を7年間フォローアップした調査では、糖尿病患者の場合は、ABIが0.91~1.00でも0.90以下と同じくらい予後が悪いことが示されている。 次に、同じ図5でABI値ごとにみた総患者数と総死亡数を紹介する5)。棒グラフの塗りが男性、斜線が女性、薄い色が母集団の数で濃い色が総死亡数を示している。総死亡の相対的ハザード比はABIが低くなるにつれて高いが、総死亡の絶対数は母集団の数の多いABI 0 .91~1.00になるにつれて多いことがわかる。つまり0.90という数値
だけにこだわると、境界的異常や正常の群で心血管イベントを見逃す可能性が高くなる。PADの診断のためには、運動負荷実施後にABIを測ることも1つの方法だが、多忙な臨床現場において医療者の負担を強いることにもなりかねない。そこで、PADの診断に何が有用かというと足首の脈波の波形である。これを確認することで見逃しを回避することができるが、その方法は次頁に紹介する。 上肢にも動脈狭窄があることは知られているが、見逃されていることが多い。事例を紹介する。60歳代の男性患者で、測定すると両足には問題がなかったが、左上腕の血圧は右と比べて低く、遅脈が認められた。血圧は右上腕135/75mmHg、左上腕112/71mmHgで収縮期血圧に20mmHgあまりの左右差がみられた。CTアンギオで確認をすると左鎖骨下動脈が完全閉塞していた。無症状であり内科的に経過観察していたところ、間欠性跛行などの症状を呈するようになり、右足のABIが1.15から0.90と低下したことから、経皮的に右腸骨動脈の血管形成術を施行した。これはあくまでも一例ではあるが、上腕に注目したスタディもあり、2012年のLancetには上腕血圧の左右差のある症例での相対リスクをみたメタ解析の結果が報告されている7)。それによると上肢の収縮期血圧が15mmHg以上だと心血管イベントの発症が2.4倍、総死亡率が1.5倍、心血管死亡も1.6倍高まっている。 なお、上肢のPADは左側に生じやすい。一般的に外来での血圧測定は右腕で、家庭血圧は利き腕(通常は右)と反対の上腕(左)で測るが、左右差を考慮しないで同一側だけで測定を続けるとPADや高血圧を見落とす可能性がある。少なくとも臨床現場においては初診、あるいは年に1回は両側の血圧計側が必要である。
(人)
(95%CI)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
6.0
4.0
2.0
1.0
0.0
総死亡数
ハザード比
≦0.60 0.61-0.70 0.71-0.80 0.81-0.90 0.91-1.000.91-1.00 1.01-1.101.01-1.10 1.11-1.20(標準)
ABI
1.21-1.30 1.31-1.40 ≧1.40
男性
1.11~1.20を1としたときの死亡のハザード比
女性
男性(本文参照)
女性
図5 ● ABI値ごとにみた総死亡のハザード比と母集団の数と総死亡者数(文献5より引用)

6
“ABI≧0.90”の見落とし回避にUT、%MAPを重視 見落としを防ぐもう1つの手段がオシロメトリック法による波形をみる方法である。事例を紹介する。不安定狭心症で入院となった70歳代の女性患者。回診で足の脈はよく触れるが、腹部に聴診器で当てると血管雑音(ブリューイ)が激しく聞こえる。formでABIを測定すると、右は0.96、左は0.91であった。ガイドラインでは境界的異常であるが、大動脈造影を施行すると複数の狭窄病変が見つかった。 波形をみる際、注目したいものがUT(upstroke time)と%MAP(mean arterial pressure)である。通常、大動脈の波形は大動脈弁が開放され急激な立ち上がりをみせる。UTはその部分の脈波の立ち上がりからピークまでの時間を示すもので、異常か正常を判断する1つの目安となる。奈良県立医科大学の吉川らは足首の脈波では180msec未満を正常としている。%MAPは、波形の面積の平均がどこにあるかを示すもので、波形にメリハリがないと%MAPは高い値を示し、鋭い波形だと低い値を示す(図6)8)。狭窄・閉塞があると%MAPの数値は大きくなり、45%未満を正常とする。 再び症例を紹介する。2型糖尿病の60歳代、女性。100m歩くと両足の間欠性跛行あり。血圧は右上腕が96 /56mmHg、 左 上 腕 が100 /57mmHg、 右 足 首 が85/52mmHg、左足首が79/47mmHg。ABIは左0.85、右0.79。波形は右足首で凹凸があまりなく、UTは163msecと182msecと比較的短い。大腿動脈のPCIを施
行することとなったが、UT、%MAPの状態から血管雑音を確認。そのうえで腹部大動脈の造影を実施すると、大動脈に複数の高度狭窄がみられた。結果的にPCIは施行したが、このように足の治療を目的としても冠動脈の評価は必要であり、その目安としてUTや%MAPが有用であると考えられる。
ABI、baPWVを駆使した動脈硬化性疾患のリスク層別化 われわれは15年ほど前から血圧脈波検査装置を用い、延べ数で5万件以上に検査を実施した。すると全身疾患とbaPWVの関係性がみえてきた。例えばC型肝炎ウイルス陽性例や、CRPが連続的に高い例、多量飲酒者、肺活量が悪い例、メタボリックシンドローム、血圧や血糖が高い例、閉経後の女性、BNP高値、軽度肥満者が体重増加した例、心拍数が高い例、CKD、喫煙者などでbaPWVが早く高くなることが明らかになった。通常、脈波速度は年に12~13cm/secずつ速くなるが、今挙げた因子をもつような人は速くなるレートが早い。メタボリックシンドロームの人は3倍、血圧と血糖値が高い例では5倍早まると考えられる。 ギリシャのVlachopoulosが日本のデータをメタ解析しているが、その論文ではbaPWVが1m/sec上昇すると心血管疾患の発症リスクは1.12倍高くなると報告している9)。わが国の大規模な疫学研究で知られる久山町研究では40歳以上の約3,000人を抽出して分析したところ、baPWVレベル別にみた心血管疾患発症の相対危険度は、多因子で補正してもなお、baPWVが速くなるにつれ高く
正常波形
面積平均値
狭窄波形
UT(upstroke time)
UT
UT延長170msec170msec
200msec
38%
正常:180msec 未満UT延長
正常波形
狭窄波形
%MAP(mean arterial pressure)
%MAP正常:45%未満
100%
0%
50%100%
0%
振幅
図6 ● 脈波解析の重要性(UTと%MAP)(文献8より引用)

7
懇話会
なることが明らかになった10)。 われわれが用いている血圧脈波検査装置は血管狭窄度(ABI)と動脈壁硬化度(baPWV)が同時に測定できるメリットがある。この装置を有効に活用する方法として、まずABIをみて0.90以下ならPADと診断し、それ以上(0.91~1.00)では%MAPやUTを検討しPADの見落としを回避する。さらにそれらをクリアすればbaPWVをみて、1,800cm/secあれば動脈壁硬化が進んでいるので、存在するリスク因子に対して何らかの対応をする。1,400cm/sec以上ではCKDや高血圧のリスクが高まるため、生活習慣の改善などの指導をすべきであろう(図7)。それ以下であれば経過観察をする。
ABIを測り、PADを認識する PADは決してまれな疾患ではなく、糖尿病患者の17~18%は罹患している可能性がある。下肢だけでなく上肢
にもPADがあることを認識すべきである。心不全や冠動脈疾患などリスクのある対象では、病歴や診察に加えてbaPWV、ABIなどを計測することを強く勧める。ABIが0.91~1.00であっても予後が悪い集団だと捉え、血管雑音の確認や波形をよく観察することが重要である。脈波の観察は大動脈炎や大動脈弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症などの発見にも有用である。 冒頭でも記したが、PADは血管疾患管理において重要な病態であり、医療者はもとより一般の人にもその存在を広く知らしめることが、われわれに課された使命であると考えている。最近では整形外科の医師も間欠性跛行などを訴える患者にはABIを測り、PADではないことをルールアウトしてから治療をされるケースが多いと聞く。血管は全身を巡る器官ととらえると、1つの部位だけに病変が生じることはありえない。多科が一緒になって患者を診ていくことが望ましい。
1) Diehm C, et al. Mortality and vascular morbidity in older adults with asymptomatic versus symptomatic peripheral artery disease. Circulation 2009 ; 120 : 2053 -61 .
2) Alberts MJ, et al. Three-year follow-up and event rates in the international REduction of Atherothrombosis for Continued Health Registry. Eur Heart J 2009 ; 30 : 2318 -26 .
3) 日本脈管学会(編). 下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指針Ⅱ(TASC Ⅱ). メディカルトリビューン, 2007 .
4) Yamashina A, et al. Nomogram of the relation of brachial-ankle pulse wave velocity with blood pressure. Hyperten Res 2003 ; 26 : 801 -6 .
5) Ankle Brachial Index Collaboration, Fowkes FG, et al. Ankle brachial index combined with Framingham Risk Score to predict cardiovascular events and mortality: a meta-analysis. JAMA 2008 ; 300 : 197 -208 .
6) Natsuaki C, et al. Association of borderline ankle-brachial index with
mortality and the incidence of peripheral artery disease in diabetic patients. Atherosclerosis 2014 ; 234 : 360 -5 .
7) Clark CE, et al. Association of a diff erence in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2012 ; 379 : 905 -14 .
8) 吉川公彦. 閉塞性動脈硬化症診断におけるABI測定と脈波形の重要性. Arterial stiff ness No.14 . メジカルビュー社, 2008 : p58 -60 .
9) Vlachopoulos C, et al. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with brachial-ankle elasticity index: a systematic review and meta-analysis. Hypertension 2012 ; 60 : 556 -62 .
10) Ninomiya T, et al. Brachial-ankle pulse wave velocity predicts the development of cardiovascular disease in a general Japanese population: the Hisayama Study. J Hypertens 2013 ; 31 : 477 -83 .
文献
ABI≦0.90
baPWV≧1,800cm/sec
PAD;ハイリスク;二次予防YES
足首パルス波形の評価%MAP≧45% or UT≧180msec
YES
ハイリスクアプローチ;リスクファクターの修正YES
NO
baPWV≧1,400cm/sec 生活習慣の改善+αYES
NO
フォローアップ
NO
NO
図7 ● 四肢血圧脈波検査によるSteno-Stiff ness(狭窄̶硬化度)に基づくリスク分類と対応法